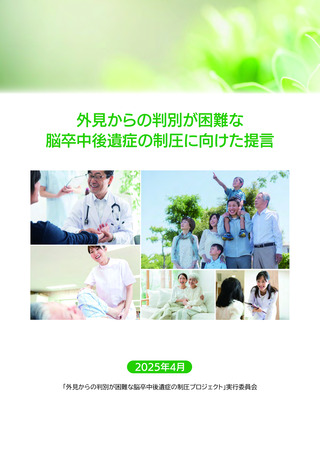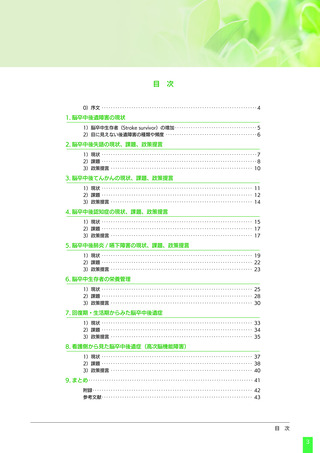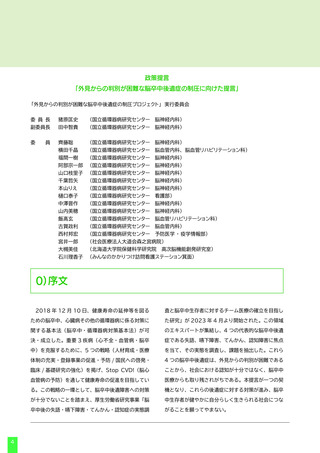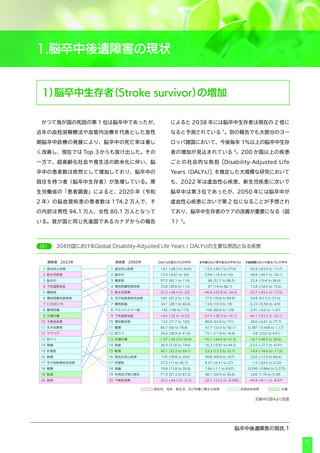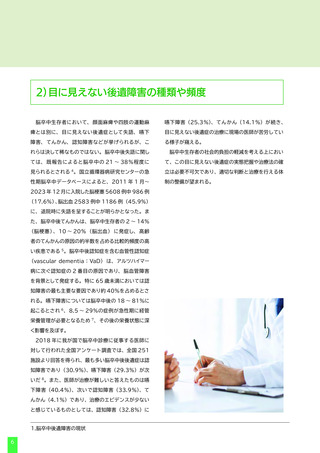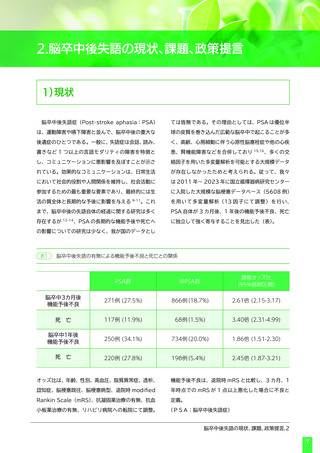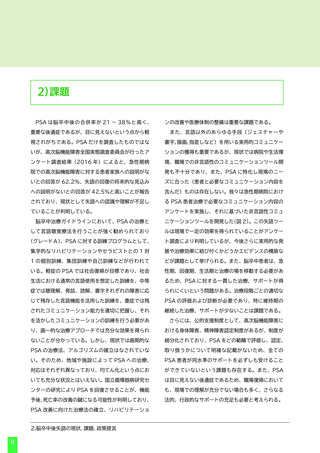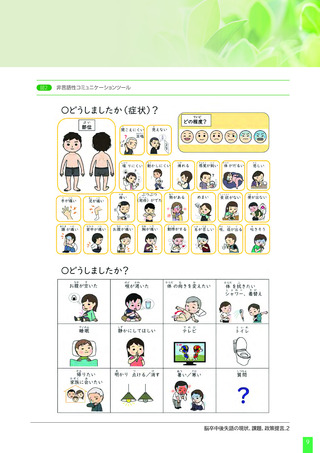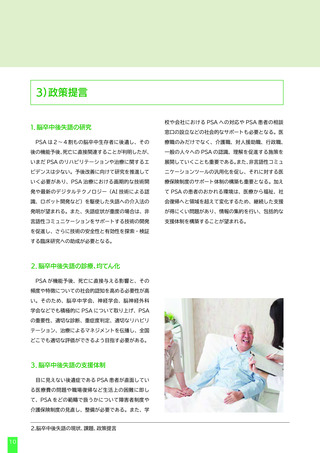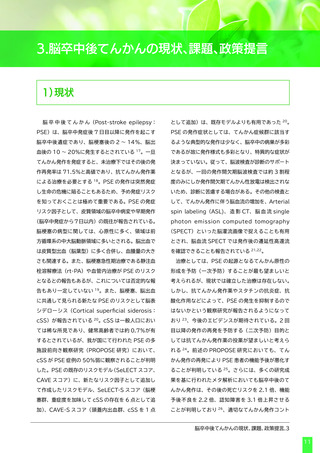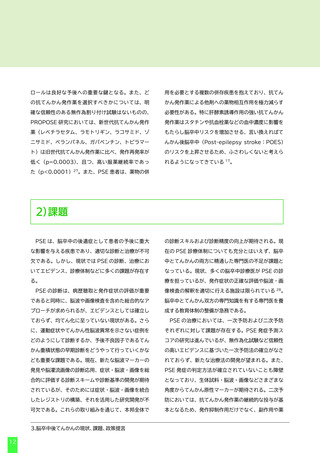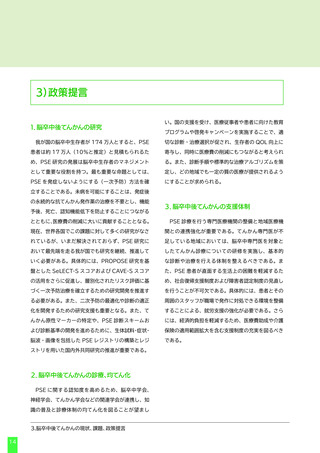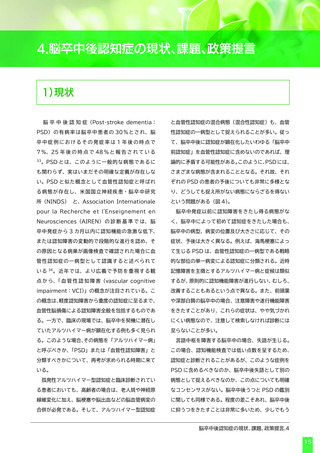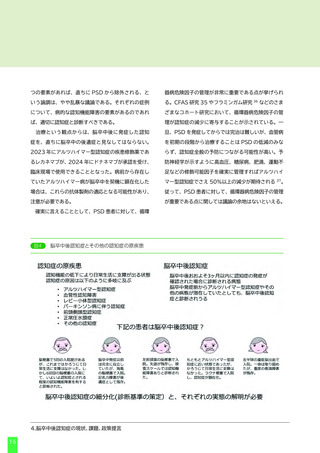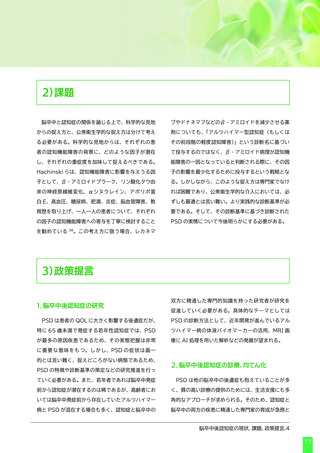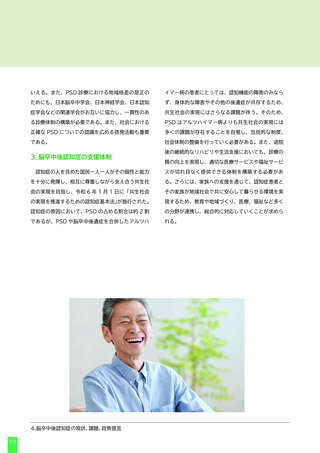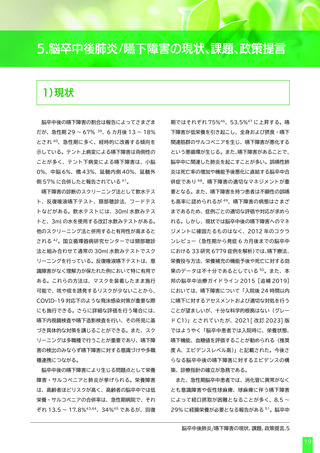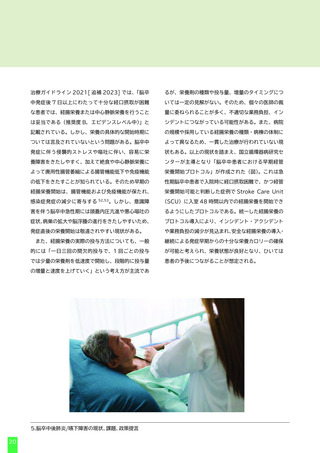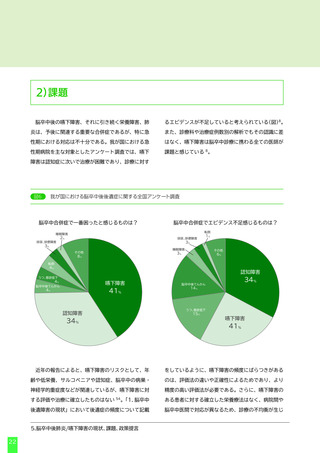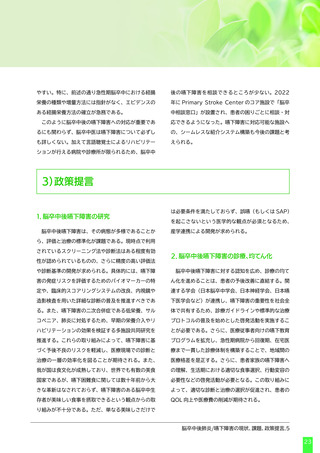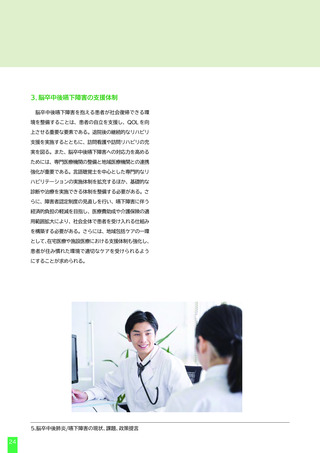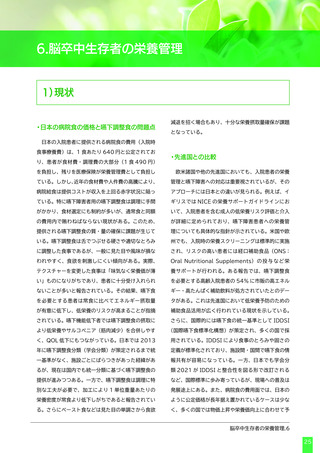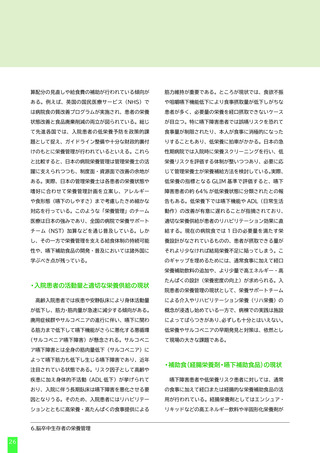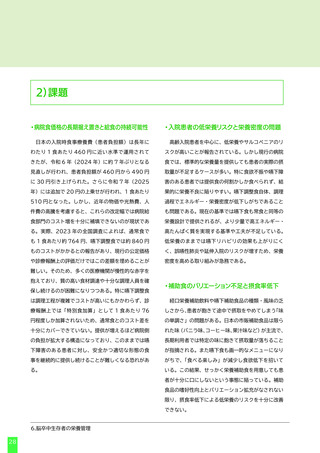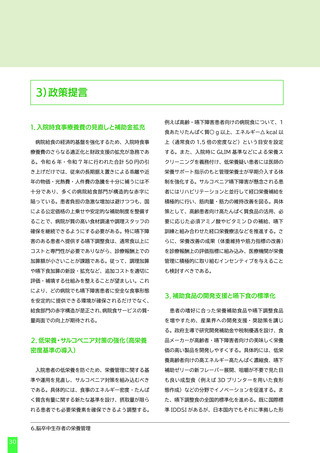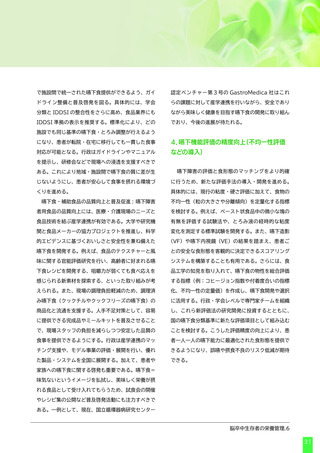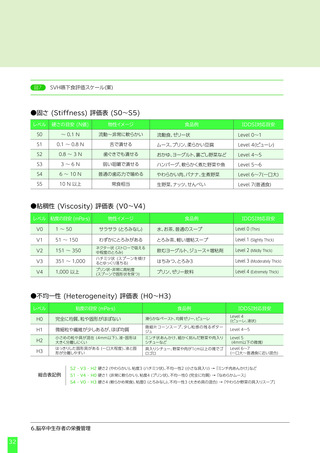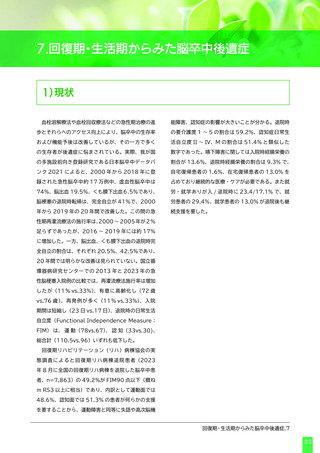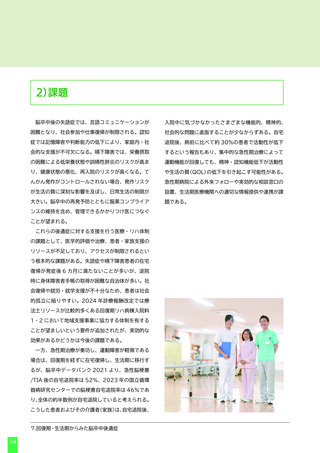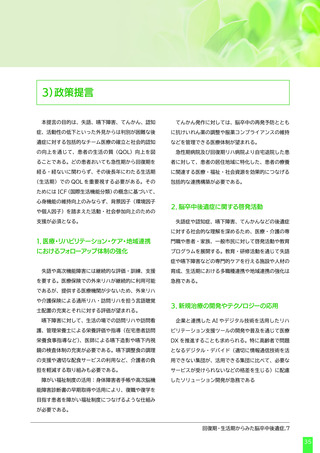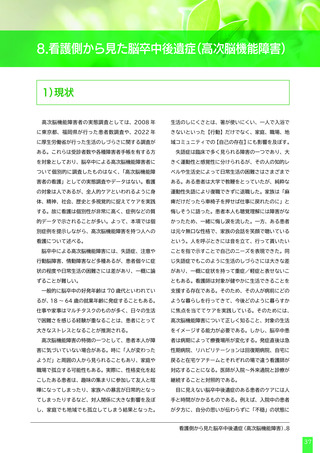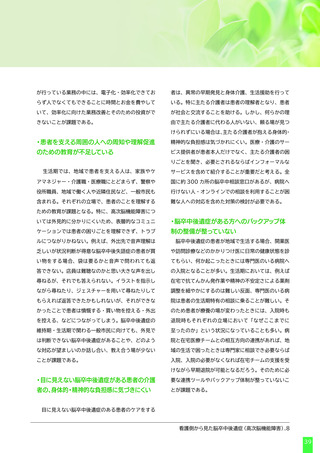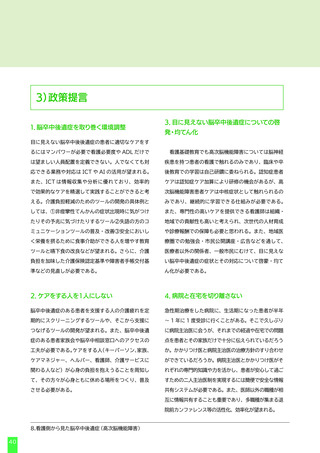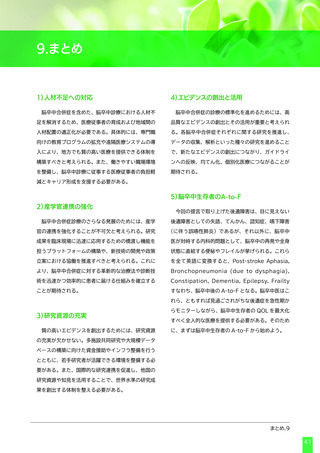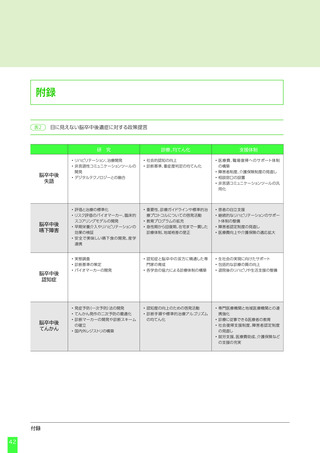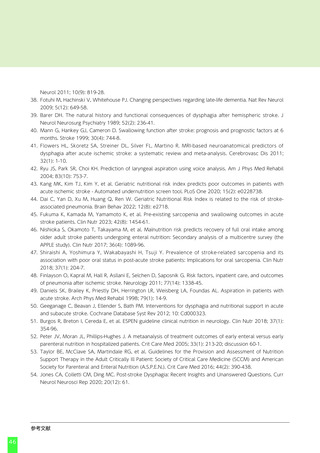よむ、つかう、まなぶ。
外見からの判別が困難な脳卒中後遺症の制圧に向けた提言 (30 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.ncvc.go.jp/hospital/wp-content/uploads/sites/2/20250707_neurology_seisakuteigen.pdf |
| 出典情報 | 「外見からの判別が困難な脳卒中後遺症の制圧に向けた提言」発表(7/7)《国立循環器病研究センター》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
3)政策提言
1.
入院時食事療養費の見直しと補助金拡充
例えば高齢・嚥下障害患者向けの病院食について、1
食あたりたんぱく質○ g 以上、エネルギー△ kcal 以
病院給食の経済的基盤を強化するため、入院時食事
上(通常食の 1.5 倍の密度など)という目安を設定
療養費のさらなる適正化と財政支援の拡充が急務であ
する。また、入院時に GLIM 基準などによる栄養ス
る。令和 6 年・令和 7 年に行われた合計 50 円の引
クリーニングを義務付け、低栄養疑い患者には医師の
き上げだけでは、従来の長期据え置きによる乖離や近
栄養サポート指示のもと管理栄養士が早期介入する体
年の物価・光熱費・人件費の急騰を十分に補うには不
制を強化する。サルコペニア嚥下障害が懸念される患
十分であり、多くの病院給食部門が構造的な赤字に
者にはリハビリテーションと並行して経口栄養補給を
陥っている。患者負担の急激な増加は避けつつも、国
積極的に行い、筋肉量・筋力の維持改善を図る。具体
による公定価格の上乗せや安定的な補助制度を整備す
策として、高齢患者向け高たんぱく質食品の活用、必
ることで、病院が質の高い食材調達や調理スタッフの
要に応じた必須アミノ酸やビタミン D の補給、嚥下
確保を継続できるようにする必要がある。特に嚥下障
訓練と組み合わせた経口栄養療法などを推進する。さ
害のある患者へ提供する嚥下調整食は、通常食以上に
らに、栄養改善の成果(体重維持や筋力指標の改善)
コストと専門性が必要でありながら、診療報酬上での
を診療報酬上の評価指標に組み込み、医療機関が栄養
加算額が小さいことが課題である。従って、調理加算
管理に積極的に取り組むインセンティブを与えること
や嚥下食加算の新設・拡充など、追加コストを適切に
も検討すべきである。
評価・補填する仕組みを整えることが望ましい。これ
により、どの病院でも嚥下障害患者に安全な食事形態
を安定的に提供できる環境が確保されるだけでなく、
給食部門の赤字構造が是正され、
病院食サービスの質・
量両面での向上が期待される。
3.
補助食品の開発支援と嚥下食の標準化
患者の嗜好に合った栄養補助食品や嚥下調整食品
を増やすため、産業界への開発支援・奨励策を講じ
る。政府主導で研究開発補助金や税制優遇を設け、食
2.
低栄養・サルコペニア対策の強化(高栄養
密度基準の導入)
品メーカーが高齢者・嚥下障害者向けの美味しく栄養
価の高い製品を開発しやすくする。具体的には、低栄
養高齢者向けの高エネルギー高たんぱく濃縮食、嚥下
入院患者の低栄養を防ぐため、栄養管理に関する基
補助ゼリーの新フレーバー展開、咀嚼が不要で見た目
準や運用を見直し、サルコペニア対策を組み込むべき
も良い成型食(例えば 3D プリンターを用いた食形
である。具体的には、食事のエネルギー密度・たんぱ
態作成)などの分野でイノベーションを促進する。ま
く質含有量に関する新たな基準を設け、摂取量が限ら
た、嚥下調整食の全国的標準化を進める。既に国際標
れる患者でも必要栄養素を確保できるよう調整する。
準 IDDSI があるが、日本国内でもそれに準拠した形
6.脳卒中生存者の栄養管理
30
1.
入院時食事療養費の見直しと補助金拡充
例えば高齢・嚥下障害患者向けの病院食について、1
食あたりたんぱく質○ g 以上、エネルギー△ kcal 以
病院給食の経済的基盤を強化するため、入院時食事
上(通常食の 1.5 倍の密度など)という目安を設定
療養費のさらなる適正化と財政支援の拡充が急務であ
する。また、入院時に GLIM 基準などによる栄養ス
る。令和 6 年・令和 7 年に行われた合計 50 円の引
クリーニングを義務付け、低栄養疑い患者には医師の
き上げだけでは、従来の長期据え置きによる乖離や近
栄養サポート指示のもと管理栄養士が早期介入する体
年の物価・光熱費・人件費の急騰を十分に補うには不
制を強化する。サルコペニア嚥下障害が懸念される患
十分であり、多くの病院給食部門が構造的な赤字に
者にはリハビリテーションと並行して経口栄養補給を
陥っている。患者負担の急激な増加は避けつつも、国
積極的に行い、筋肉量・筋力の維持改善を図る。具体
による公定価格の上乗せや安定的な補助制度を整備す
策として、高齢患者向け高たんぱく質食品の活用、必
ることで、病院が質の高い食材調達や調理スタッフの
要に応じた必須アミノ酸やビタミン D の補給、嚥下
確保を継続できるようにする必要がある。特に嚥下障
訓練と組み合わせた経口栄養療法などを推進する。さ
害のある患者へ提供する嚥下調整食は、通常食以上に
らに、栄養改善の成果(体重維持や筋力指標の改善)
コストと専門性が必要でありながら、診療報酬上での
を診療報酬上の評価指標に組み込み、医療機関が栄養
加算額が小さいことが課題である。従って、調理加算
管理に積極的に取り組むインセンティブを与えること
や嚥下食加算の新設・拡充など、追加コストを適切に
も検討すべきである。
評価・補填する仕組みを整えることが望ましい。これ
により、どの病院でも嚥下障害患者に安全な食事形態
を安定的に提供できる環境が確保されるだけでなく、
給食部門の赤字構造が是正され、
病院食サービスの質・
量両面での向上が期待される。
3.
補助食品の開発支援と嚥下食の標準化
患者の嗜好に合った栄養補助食品や嚥下調整食品
を増やすため、産業界への開発支援・奨励策を講じ
る。政府主導で研究開発補助金や税制優遇を設け、食
2.
低栄養・サルコペニア対策の強化(高栄養
密度基準の導入)
品メーカーが高齢者・嚥下障害者向けの美味しく栄養
価の高い製品を開発しやすくする。具体的には、低栄
養高齢者向けの高エネルギー高たんぱく濃縮食、嚥下
入院患者の低栄養を防ぐため、栄養管理に関する基
補助ゼリーの新フレーバー展開、咀嚼が不要で見た目
準や運用を見直し、サルコペニア対策を組み込むべき
も良い成型食(例えば 3D プリンターを用いた食形
である。具体的には、食事のエネルギー密度・たんぱ
態作成)などの分野でイノベーションを促進する。ま
く質含有量に関する新たな基準を設け、摂取量が限ら
た、嚥下調整食の全国的標準化を進める。既に国際標
れる患者でも必要栄養素を確保できるよう調整する。
準 IDDSI があるが、日本国内でもそれに準拠した形
6.脳卒中生存者の栄養管理
30