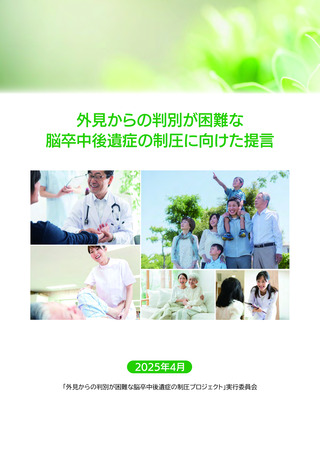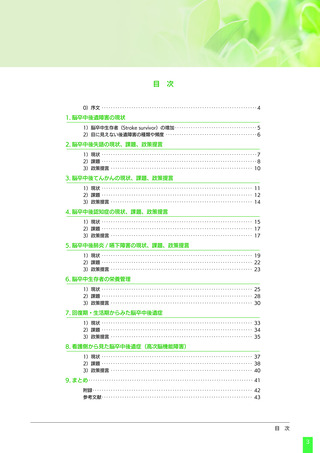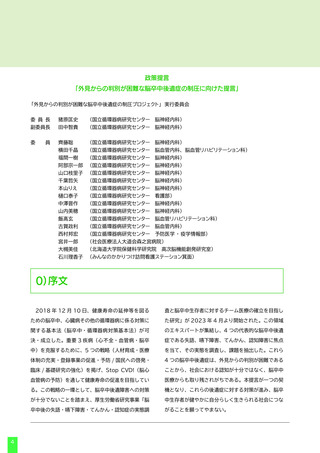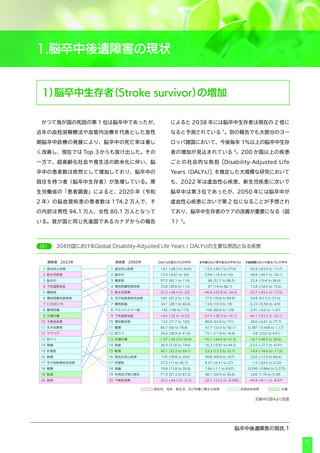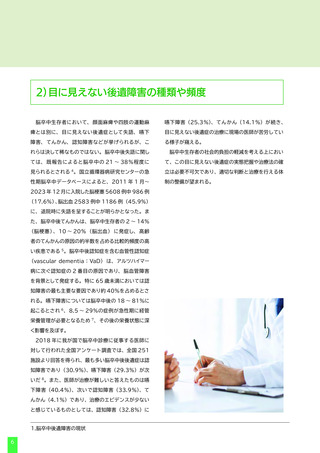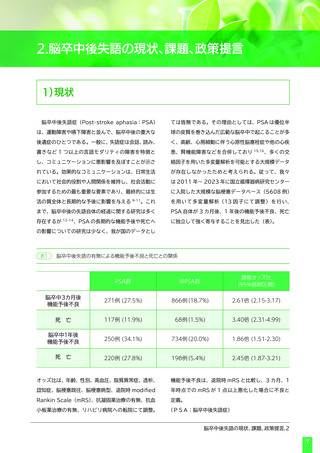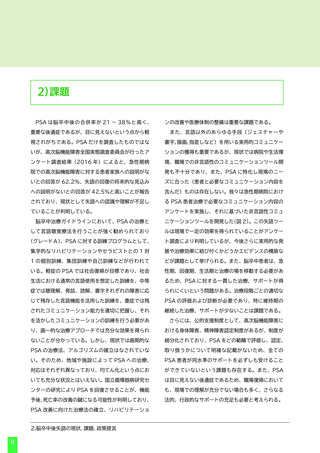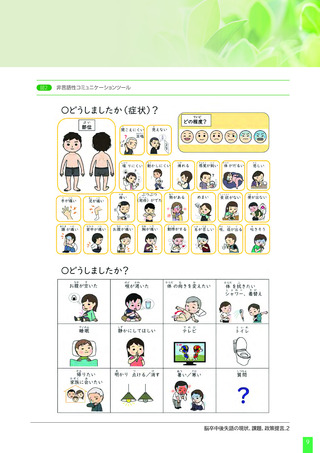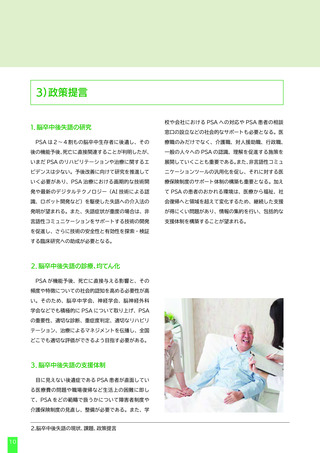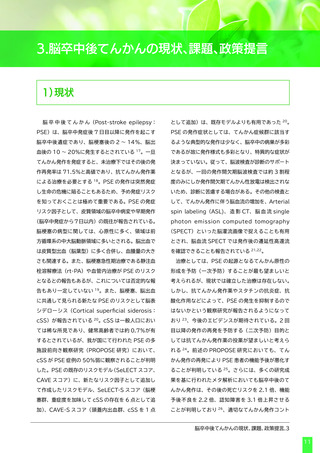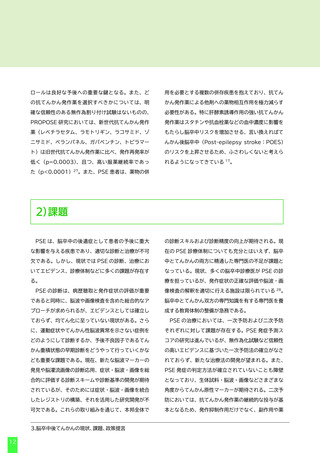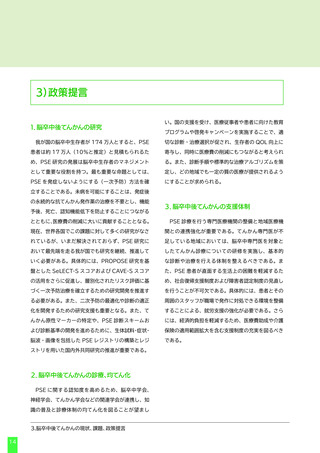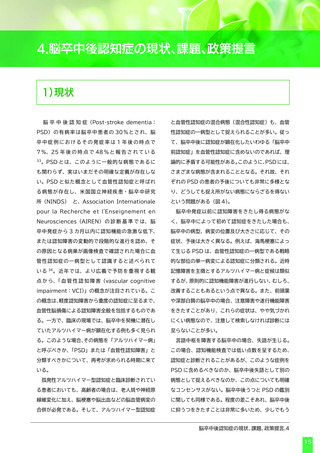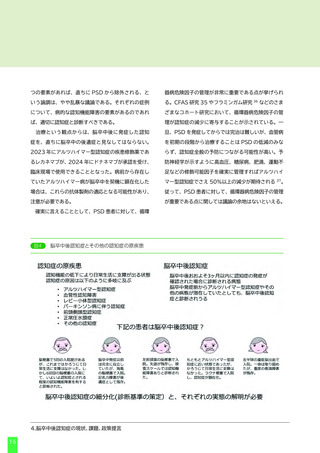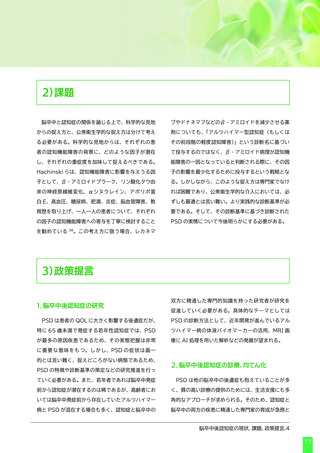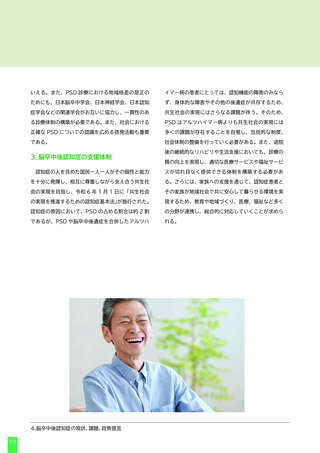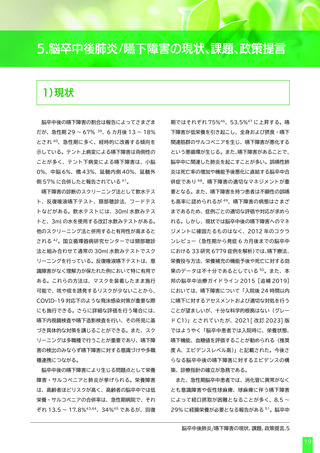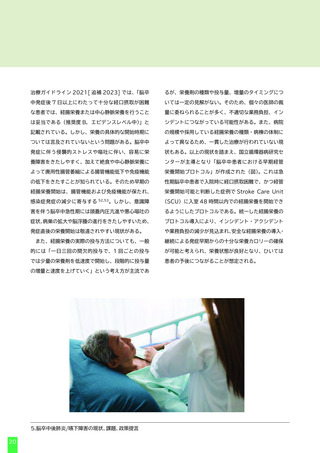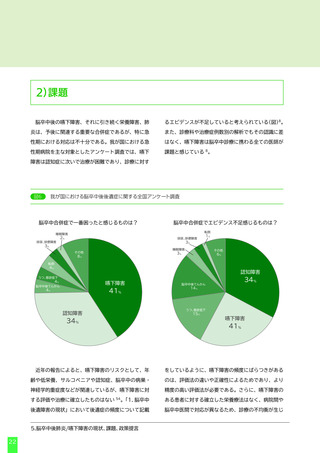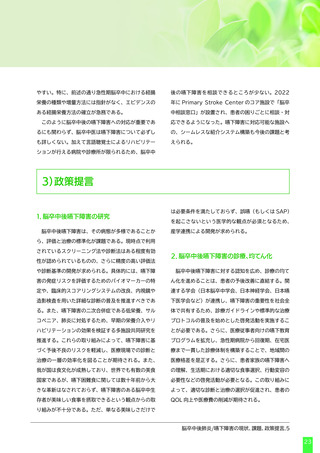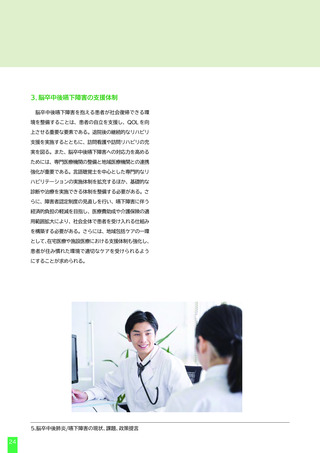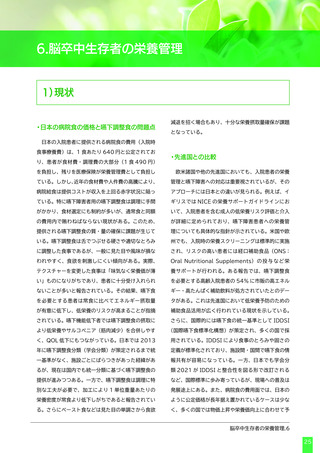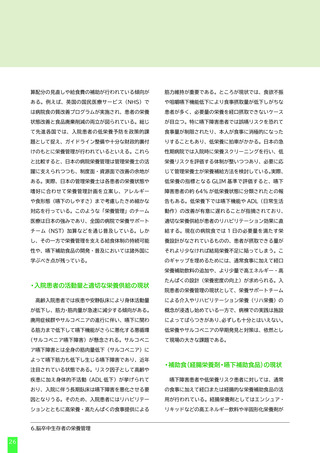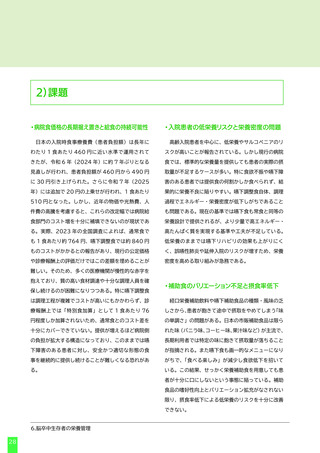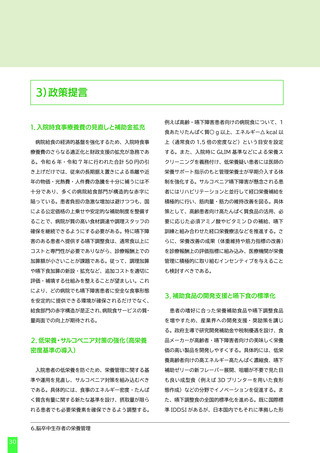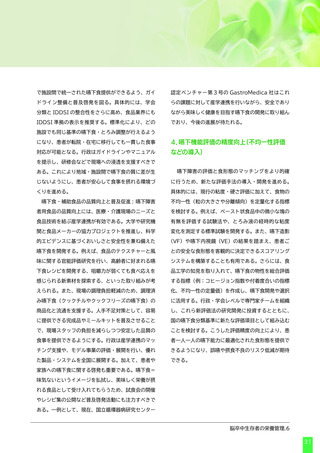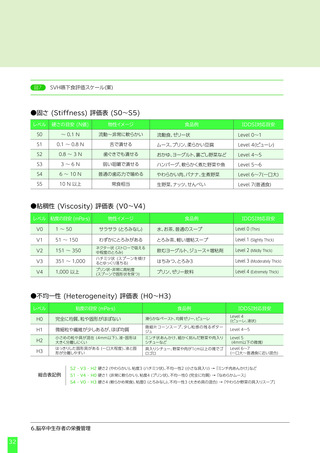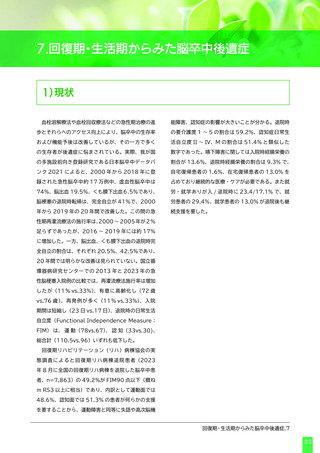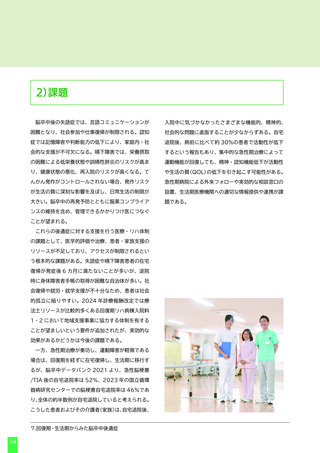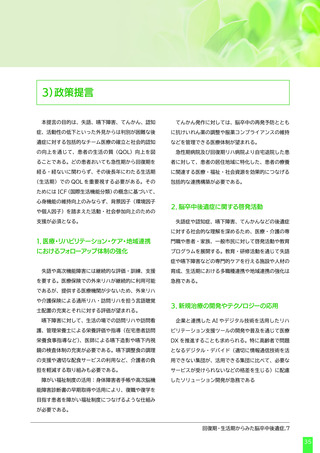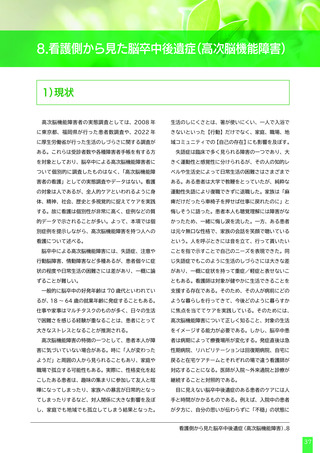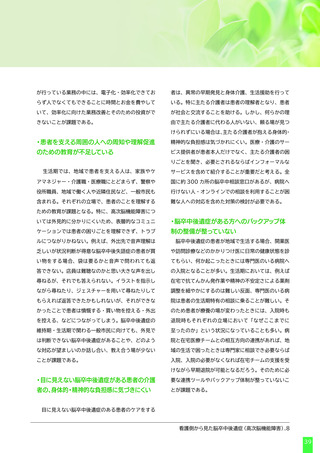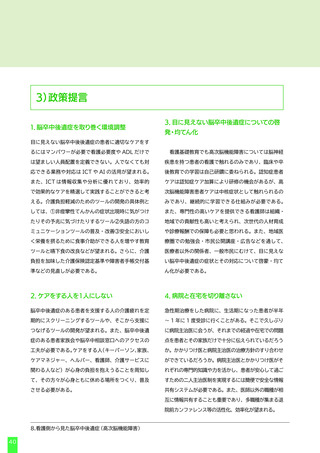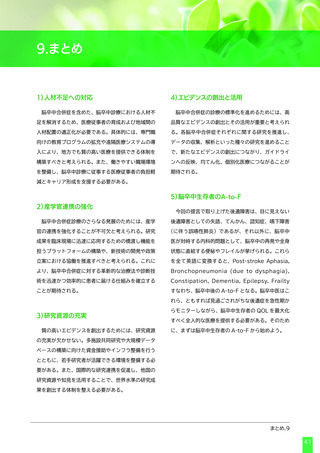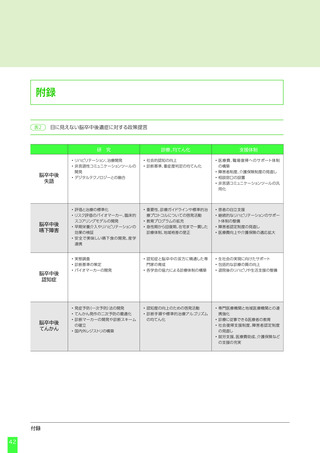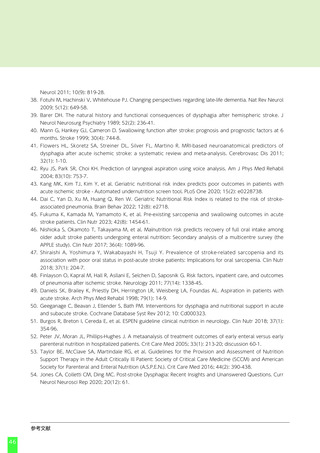よむ、つかう、まなぶ。
外見からの判別が困難な脳卒中後遺症の制圧に向けた提言 (26 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.ncvc.go.jp/hospital/wp-content/uploads/sites/2/20250707_neurology_seisakuteigen.pdf |
| 出典情報 | 「外見からの判別が困難な脳卒中後遺症の制圧に向けた提言」発表(7/7)《国立循環器病研究センター》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
算配分の見直しや給食費の補助が行われている傾向が
筋力維持が重要である。ところが現状では、食欲不振
ある。例えば、英国の国民医療サービス(NHS)で
や咀嚼嚥下機能低下により食事摂取量が低下しがちな
は病院食の質改善プログラムが実施され、患者の栄養
患者が多く、必要量の栄養を経口摂取できないケース
状態改善と食品廃棄削減の両立が図られている。総じ
が目立つ。特に嚥下障害患者では誤嚥リスクを恐れて
て先進各国では、入院患者の低栄養予防を政策的課
食事量が制限されたり、本人が食事に消極的になった
題として捉え、ガイドライン整備や十分な財政的裏付
りすることもあり、低栄養に拍車がかかる。日本の急
けのもとに栄養管理が行われているといえる。これら
性期病院では入院時に栄養スクリーニングを行い、低
と比較すると、日本の病院栄養管理は管理栄養士の活
栄養リスクを評価する体制が整いつつあり、必要に応
躍に支えられつつも、制度面・資源面で改善の余地が
じて管理栄養士が栄養補給方法を検討している。実際、
ある。実際、日本の管理栄養士は各患者の栄養状態や
低栄養の指標となる GLIM 基準で評価すると、嚥下
嗜好に合わせて栄養管理計画を立案し、アレルギー
障害患者の約 64% が低栄養状態に分類されたとの報
や食形態(嚥下のしやすさ)まで考慮したきめ細かな
告もある。低栄養下では嚥下機能や ADL(日常生活
対応を行っている。このような「栄養管理」のチーム
動作)の改善が有意に遅れることが指摘されており、
医療は日本の強みであり、全国の病院で栄養サポート
適切な栄養供給が患者のリハビリテーション効果に直
チーム(NST)加算などを通じ普及している。しか
結する。現在の病院食では 1 日の必要量を満たす栄
し、その一方で栄養管理を支える給食体制の持続可能
養設計がなされているものの、患者が摂取できる量が
性や、嚥下補助食品の開発・普及においては諸外国に
それより少なければ結局栄養不足に陥ってしまう。こ
学ぶべき点が残っている。
のギャップを埋めるためには、通常食事に加えて経口
栄養補助飲料の追加や、より少量で高エネルギー・高
・入院患者の活動量と適切な栄養供給の現状
たんぱくの設計(栄養密度の向上)が求められる。入
院患者の栄養管理の現状として、栄養サポートチーム
高齢入院患者では疾患や安静臥床により身体活動量
による介入やリハビリテーション栄養(リハ栄養)の
が低下し、筋力・筋肉量が急速に減少する傾向がある。
概念が浸透し始めている一方で、病棟での実践は施設
廃用症候群やサルコペニアの進行に伴い、嚥下に関わ
によってばらつきがあり、必ずしも十分とはいえない。
る筋力まで低下して嚥下機能がさらに悪化する悪循環
低栄養やサルコペニアの早期発見と対策は、依然とし
(サルコペニア嚥下障害)が懸念される。サルコペニ
て現場の大きな課題である。
ア嚥下障害とは全身の筋肉量低下(サルコペニア)に
よって嚥下筋力も低下し生じる嚥下障害であり、近年
注目されている状態である。リスク因子として高齢や
疾患に加え身体的不活動(ADL 低下)が挙げられて
嚥下障害患者や低栄養リスク患者に対しては、通常
おり、入院に伴う長期臥床は嚥下障害を悪化させる要
の食事に加えて経口または経腸的な栄養補助食品の活
因となりうる。そのため、入院患者にはリハビリテー
用が行われている。経腸栄養剤としてはエンシュア・
ションとともに高栄養・高たんぱくの食事提供による
リキッドなどの高エネルギー飲料や半固形化栄養剤が
6.脳卒中生存者の栄養管理
26
・補助食(経腸栄養剤・嚥下補助食品)の現状
筋力維持が重要である。ところが現状では、食欲不振
ある。例えば、英国の国民医療サービス(NHS)で
や咀嚼嚥下機能低下により食事摂取量が低下しがちな
は病院食の質改善プログラムが実施され、患者の栄養
患者が多く、必要量の栄養を経口摂取できないケース
状態改善と食品廃棄削減の両立が図られている。総じ
が目立つ。特に嚥下障害患者では誤嚥リスクを恐れて
て先進各国では、入院患者の低栄養予防を政策的課
食事量が制限されたり、本人が食事に消極的になった
題として捉え、ガイドライン整備や十分な財政的裏付
りすることもあり、低栄養に拍車がかかる。日本の急
けのもとに栄養管理が行われているといえる。これら
性期病院では入院時に栄養スクリーニングを行い、低
と比較すると、日本の病院栄養管理は管理栄養士の活
栄養リスクを評価する体制が整いつつあり、必要に応
躍に支えられつつも、制度面・資源面で改善の余地が
じて管理栄養士が栄養補給方法を検討している。実際、
ある。実際、日本の管理栄養士は各患者の栄養状態や
低栄養の指標となる GLIM 基準で評価すると、嚥下
嗜好に合わせて栄養管理計画を立案し、アレルギー
障害患者の約 64% が低栄養状態に分類されたとの報
や食形態(嚥下のしやすさ)まで考慮したきめ細かな
告もある。低栄養下では嚥下機能や ADL(日常生活
対応を行っている。このような「栄養管理」のチーム
動作)の改善が有意に遅れることが指摘されており、
医療は日本の強みであり、全国の病院で栄養サポート
適切な栄養供給が患者のリハビリテーション効果に直
チーム(NST)加算などを通じ普及している。しか
結する。現在の病院食では 1 日の必要量を満たす栄
し、その一方で栄養管理を支える給食体制の持続可能
養設計がなされているものの、患者が摂取できる量が
性や、嚥下補助食品の開発・普及においては諸外国に
それより少なければ結局栄養不足に陥ってしまう。こ
学ぶべき点が残っている。
のギャップを埋めるためには、通常食事に加えて経口
栄養補助飲料の追加や、より少量で高エネルギー・高
・入院患者の活動量と適切な栄養供給の現状
たんぱくの設計(栄養密度の向上)が求められる。入
院患者の栄養管理の現状として、栄養サポートチーム
高齢入院患者では疾患や安静臥床により身体活動量
による介入やリハビリテーション栄養(リハ栄養)の
が低下し、筋力・筋肉量が急速に減少する傾向がある。
概念が浸透し始めている一方で、病棟での実践は施設
廃用症候群やサルコペニアの進行に伴い、嚥下に関わ
によってばらつきがあり、必ずしも十分とはいえない。
る筋力まで低下して嚥下機能がさらに悪化する悪循環
低栄養やサルコペニアの早期発見と対策は、依然とし
(サルコペニア嚥下障害)が懸念される。サルコペニ
て現場の大きな課題である。
ア嚥下障害とは全身の筋肉量低下(サルコペニア)に
よって嚥下筋力も低下し生じる嚥下障害であり、近年
注目されている状態である。リスク因子として高齢や
疾患に加え身体的不活動(ADL 低下)が挙げられて
嚥下障害患者や低栄養リスク患者に対しては、通常
おり、入院に伴う長期臥床は嚥下障害を悪化させる要
の食事に加えて経口または経腸的な栄養補助食品の活
因となりうる。そのため、入院患者にはリハビリテー
用が行われている。経腸栄養剤としてはエンシュア・
ションとともに高栄養・高たんぱくの食事提供による
リキッドなどの高エネルギー飲料や半固形化栄養剤が
6.脳卒中生存者の栄養管理
26
・補助食(経腸栄養剤・嚥下補助食品)の現状