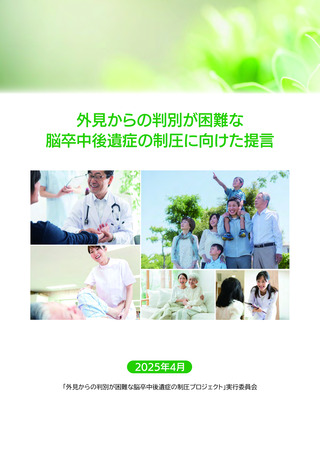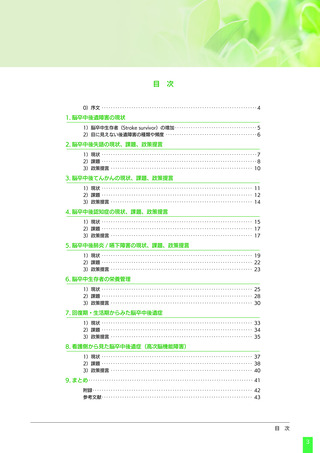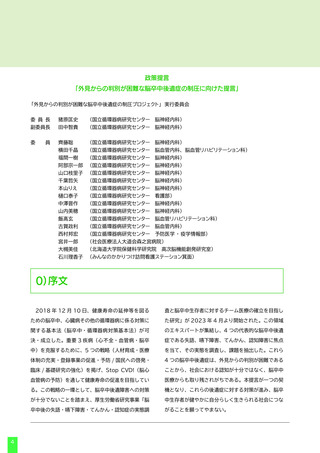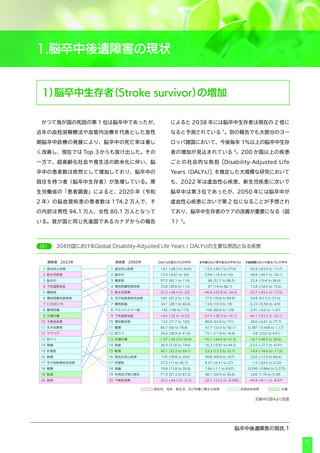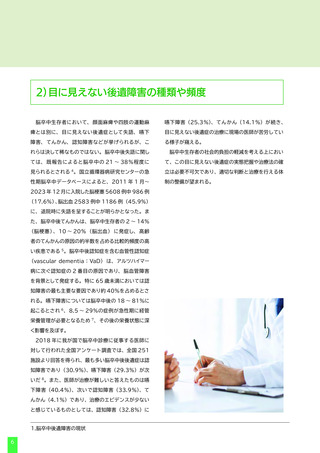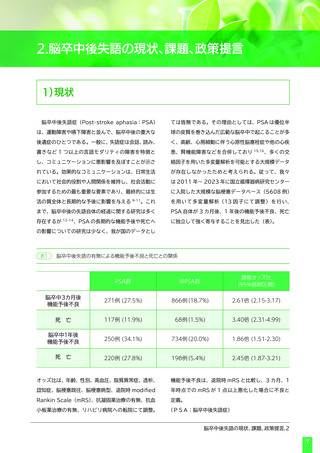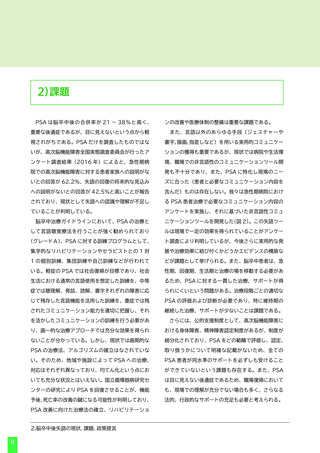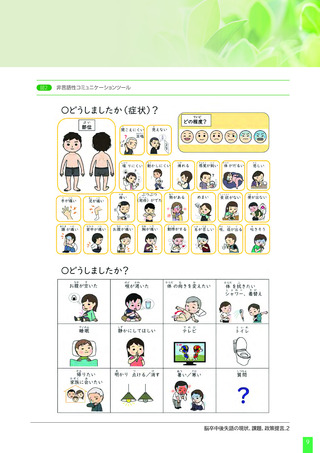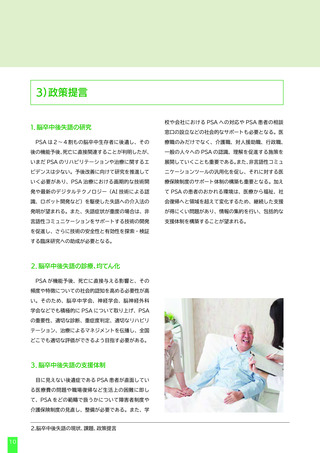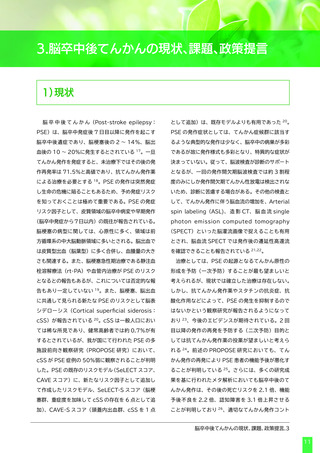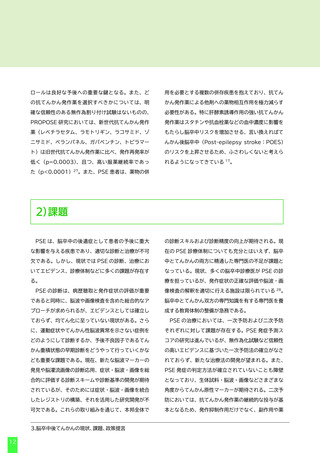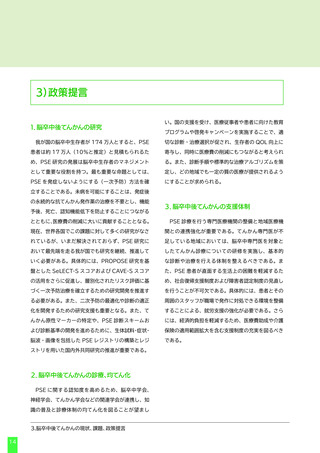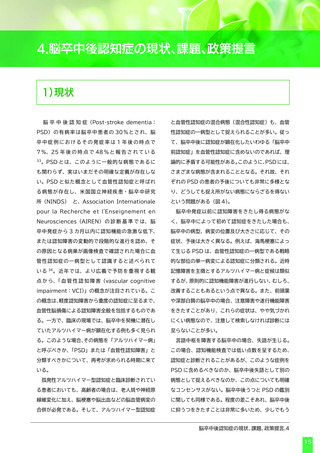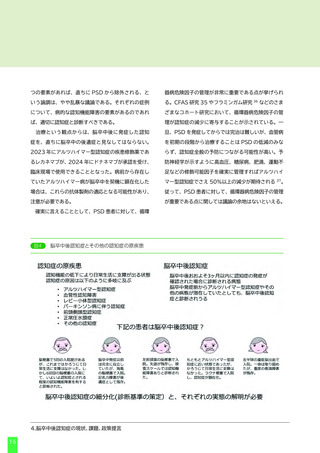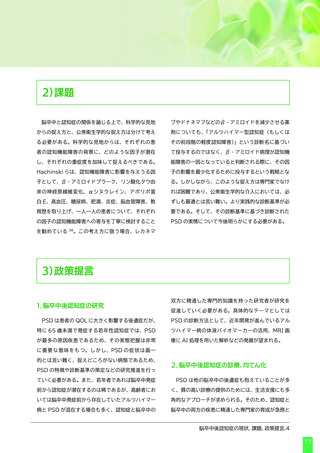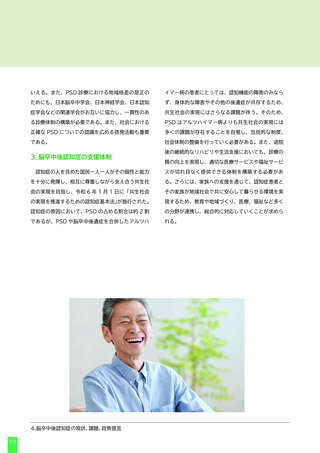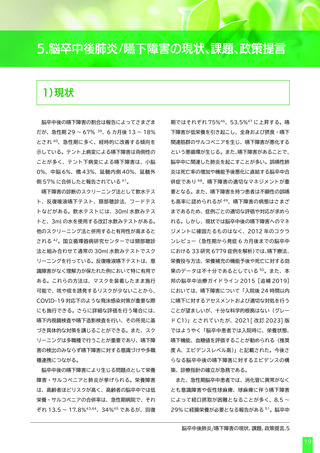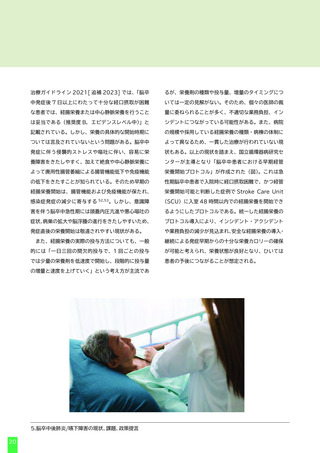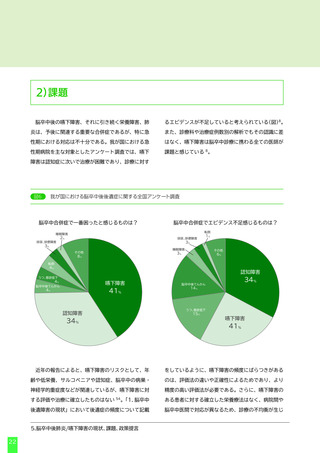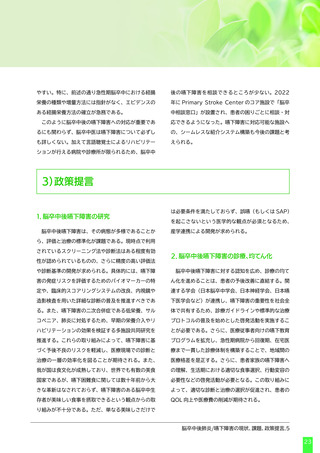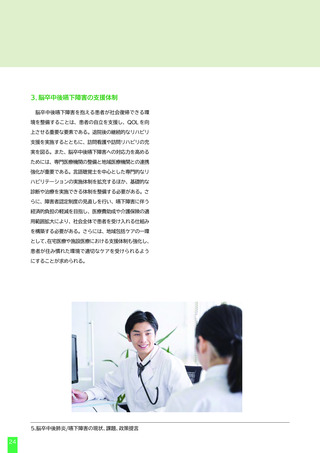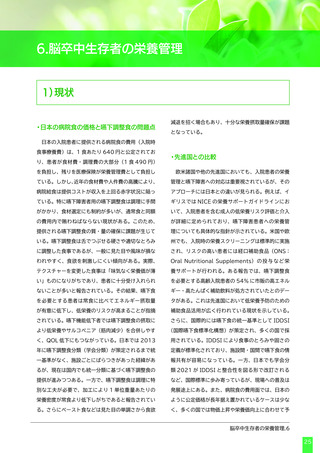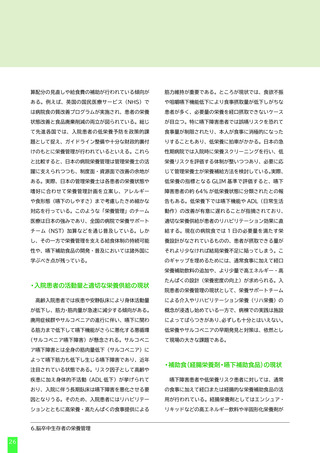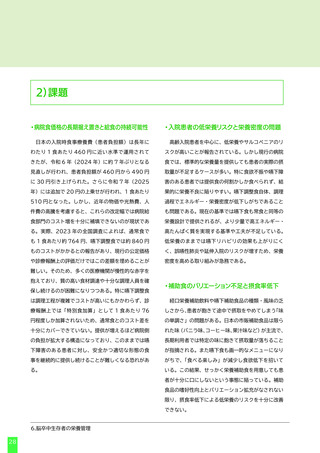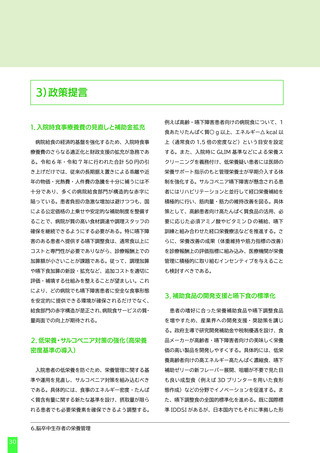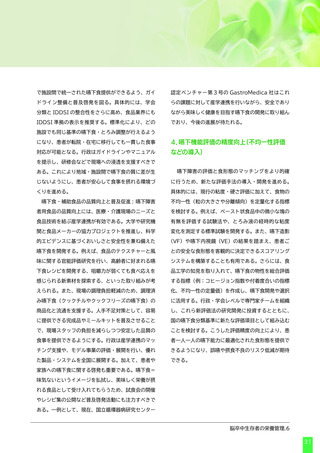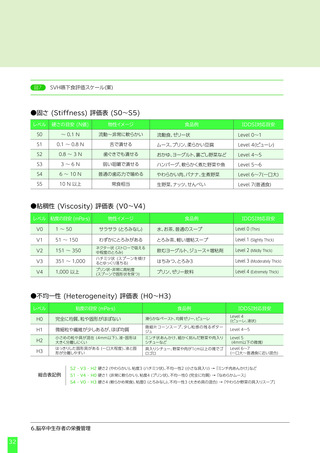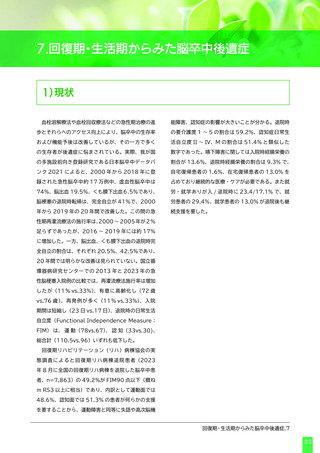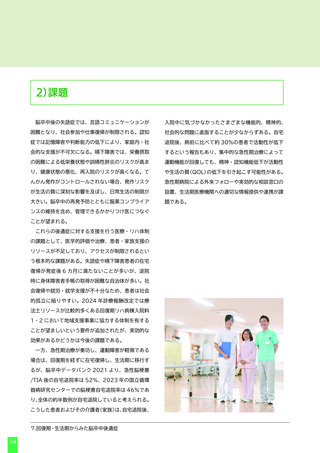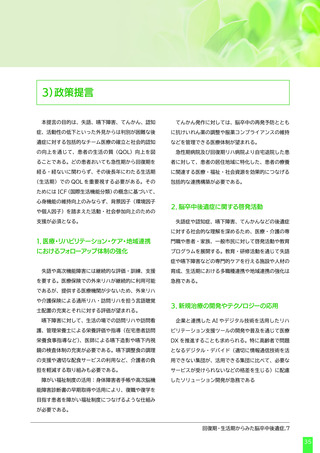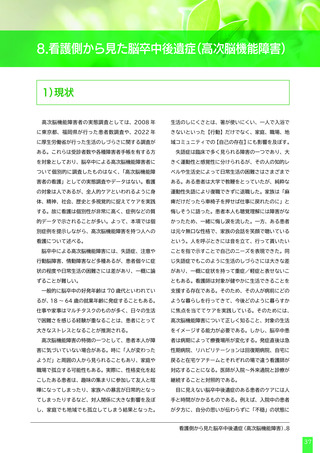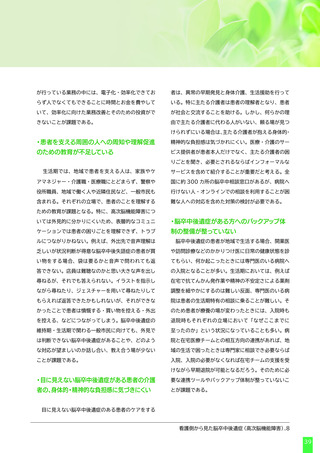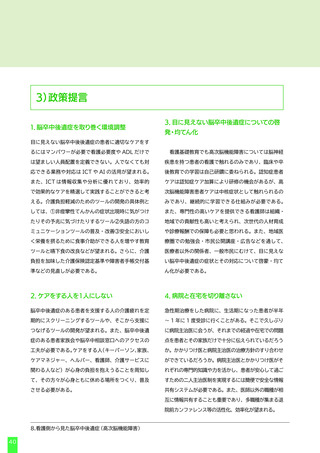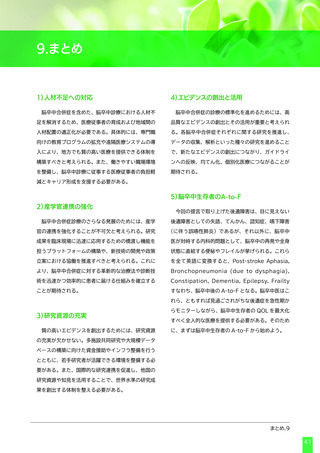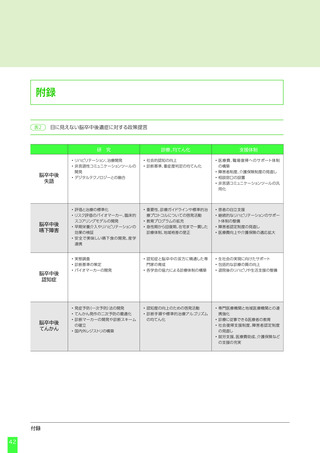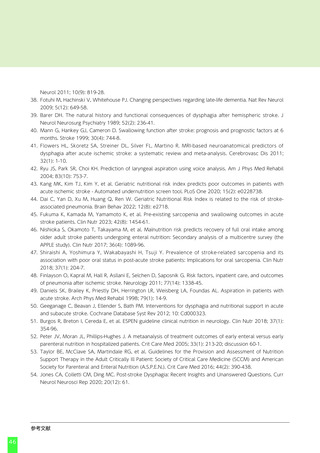よむ、つかう、まなぶ。
外見からの判別が困難な脳卒中後遺症の制圧に向けた提言 (27 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.ncvc.go.jp/hospital/wp-content/uploads/sites/2/20250707_neurology_seisakuteigen.pdf |
| 出典情報 | 「外見からの判別が困難な脳卒中後遺症の制圧に向けた提言」発表(7/7)《国立循環器病研究センター》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
広く用いられ、経口摂取困難な場合には経鼻・経胃
備され、市販製品も増えてはいるが、欧米に比べ種類
チューブでの投与が実施される。一方、経口摂取を維
や味の多様性は発展途上である。例えばイギリスの
持できる嚥下障害患者には、とろみ調整食品(飲み物
BAPEN は「味の飽きがこないよう複数のフレーバー
に混ぜてとろみを付与する粉末・液体)や、市販の嚥
を用意すべき」と提言しており、各種のジュースタイ
下補助食品(ゼリー状食品や濃厚流動食)が補助的に
プ・ミルクタイプ・デザートタイプの ONS が処方現
提供されている。これら補助食品は嚥下しやすい物性
場で使い分けられている。日本でも主要メーカーから
に調整されており、誤嚥予防や栄養補給に役立つ。例
栄養剤や嚥下補助食が販売されているものの、患者の
えば、とろみ剤を使用することで水分の嚥下安全性が
嗜好に合う選択肢を増やす余地がある。第三に、エビ
向上し、誤嚥性肺炎のリスク低減に寄与する。しかし
デンスと評価の不足も現状として挙げられる。補助食
現状では、補助食品に頼った栄養補給にはいくつかの
品が摂取量や転帰に与える効果について、現場では有
問題が指摘されている。第一に嗜好性の問題である。
用との実感がある一方、どの種類の補助食品をいつど
市販の栄養補助飲料や嚥下食は味の選択肢が限られ、
のくらい用いるのが最適かといった科学的根拠は十分
長期使用する患者では味飽き(taste fatigue)に
確立されていない。例えば、日本では嚥下調整食加算
より摂取量が低下しやすい。実際、ある研究では高齢
などはなく、補助食品の使用も各施設の裁量に委ねら
患者にミルク風味と果汁風味の高栄養サプリメントを
れているため、その使用実態や有効性データの収集が
提供したところ、大半の患者がミルク風味を選好し続
不十分である。総じて、補助食は嚥下障害患者の栄養
け、果汁系の製品は酸味への嗜好の低さから敬遠され
管理を支える重要なツールとなっているが、その味や
る傾向があった。このことは、複数のフレーバーやタ
種類の限界、エビデンス不足といった現状の課題が認
イプの製品を提供し、味のマンネリ化を防ぐ工夫が摂
識されている。今後、患者の嗜好に配慮した製品開発
取継続に重要であることを示唆している。第二に、製
や、補助食品を含めた栄養管理の効果検証が求められ
品バリエーションの少なさである。日本では近年「ス
る。
マイルケア食」制度により介護食品の分類・表示が整
脳卒中生存者の栄養管理.6
27
備され、市販製品も増えてはいるが、欧米に比べ種類
チューブでの投与が実施される。一方、経口摂取を維
や味の多様性は発展途上である。例えばイギリスの
持できる嚥下障害患者には、とろみ調整食品(飲み物
BAPEN は「味の飽きがこないよう複数のフレーバー
に混ぜてとろみを付与する粉末・液体)や、市販の嚥
を用意すべき」と提言しており、各種のジュースタイ
下補助食品(ゼリー状食品や濃厚流動食)が補助的に
プ・ミルクタイプ・デザートタイプの ONS が処方現
提供されている。これら補助食品は嚥下しやすい物性
場で使い分けられている。日本でも主要メーカーから
に調整されており、誤嚥予防や栄養補給に役立つ。例
栄養剤や嚥下補助食が販売されているものの、患者の
えば、とろみ剤を使用することで水分の嚥下安全性が
嗜好に合う選択肢を増やす余地がある。第三に、エビ
向上し、誤嚥性肺炎のリスク低減に寄与する。しかし
デンスと評価の不足も現状として挙げられる。補助食
現状では、補助食品に頼った栄養補給にはいくつかの
品が摂取量や転帰に与える効果について、現場では有
問題が指摘されている。第一に嗜好性の問題である。
用との実感がある一方、どの種類の補助食品をいつど
市販の栄養補助飲料や嚥下食は味の選択肢が限られ、
のくらい用いるのが最適かといった科学的根拠は十分
長期使用する患者では味飽き(taste fatigue)に
確立されていない。例えば、日本では嚥下調整食加算
より摂取量が低下しやすい。実際、ある研究では高齢
などはなく、補助食品の使用も各施設の裁量に委ねら
患者にミルク風味と果汁風味の高栄養サプリメントを
れているため、その使用実態や有効性データの収集が
提供したところ、大半の患者がミルク風味を選好し続
不十分である。総じて、補助食は嚥下障害患者の栄養
け、果汁系の製品は酸味への嗜好の低さから敬遠され
管理を支える重要なツールとなっているが、その味や
る傾向があった。このことは、複数のフレーバーやタ
種類の限界、エビデンス不足といった現状の課題が認
イプの製品を提供し、味のマンネリ化を防ぐ工夫が摂
識されている。今後、患者の嗜好に配慮した製品開発
取継続に重要であることを示唆している。第二に、製
や、補助食品を含めた栄養管理の効果検証が求められ
品バリエーションの少なさである。日本では近年「ス
る。
マイルケア食」制度により介護食品の分類・表示が整
脳卒中生存者の栄養管理.6
27