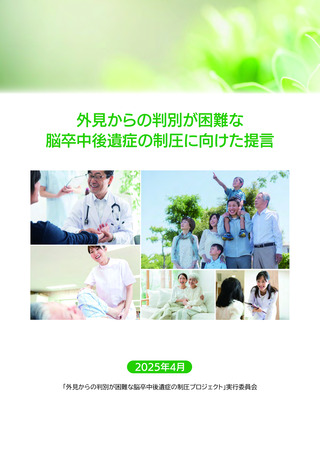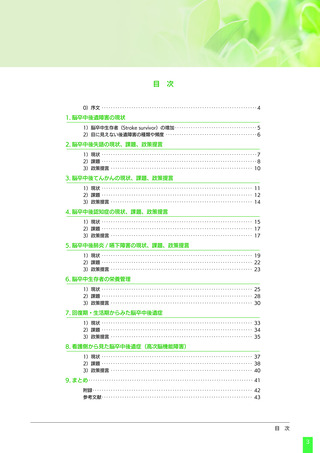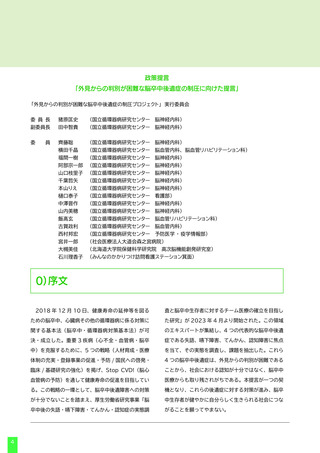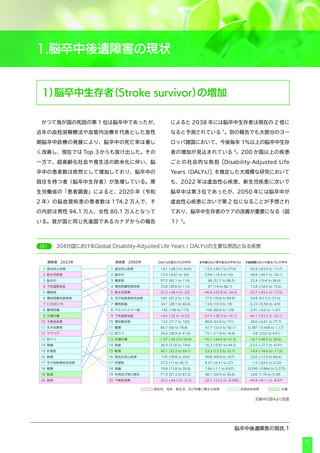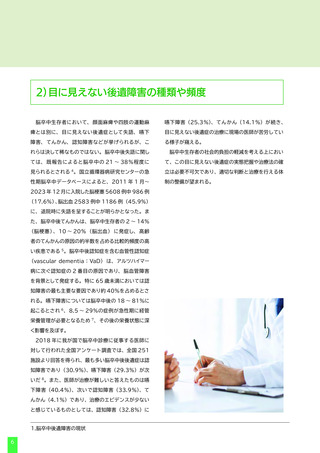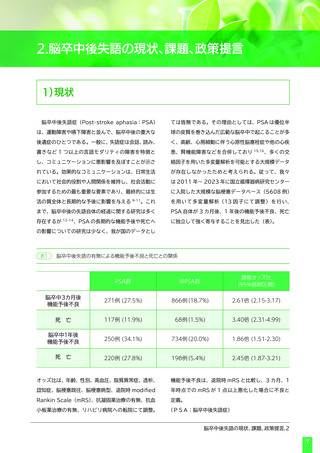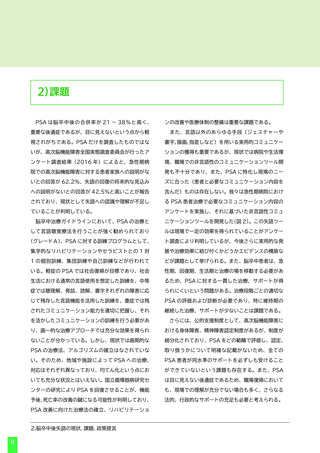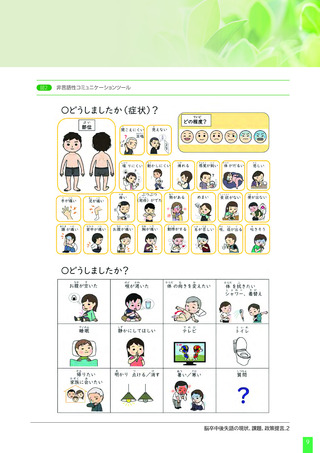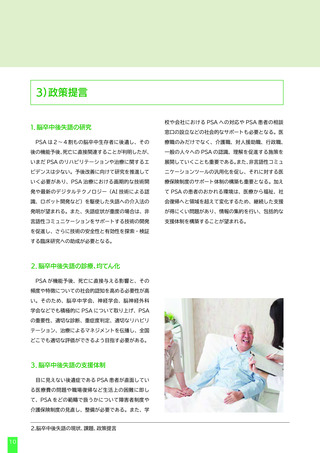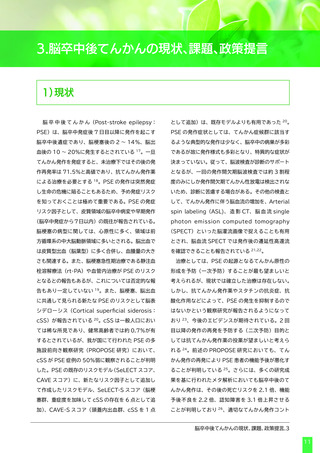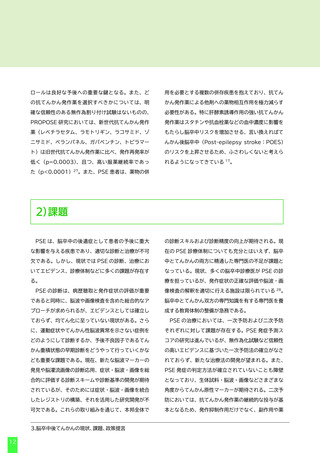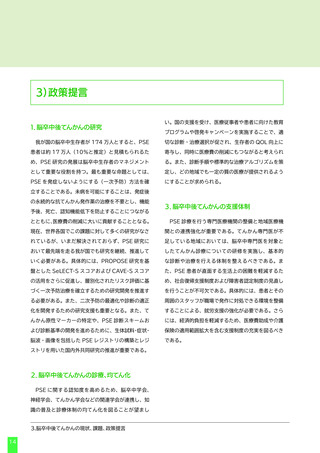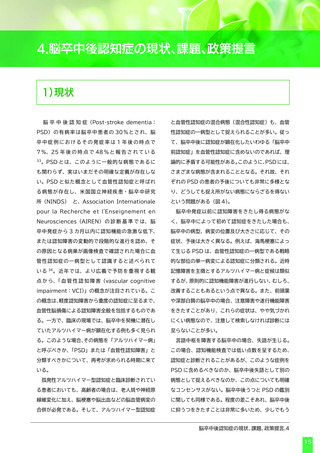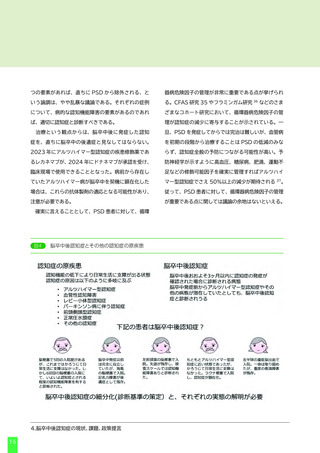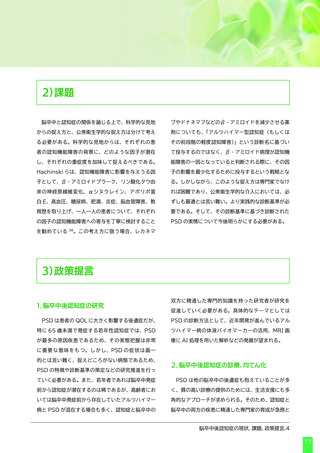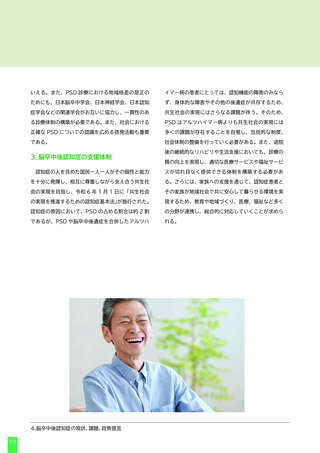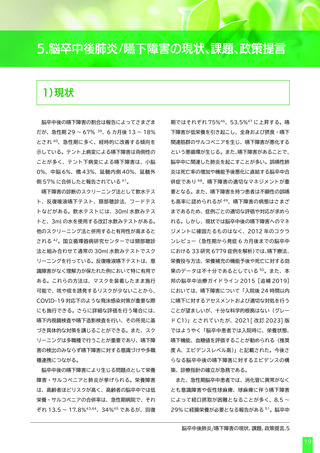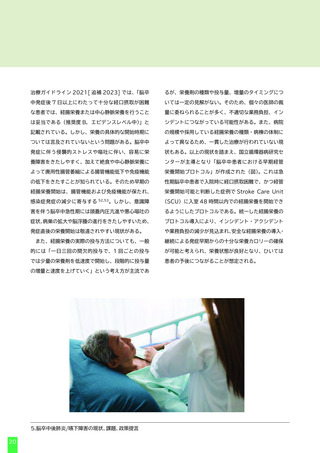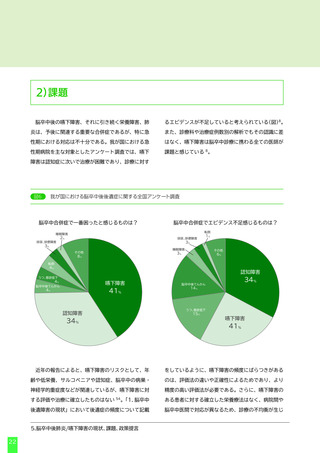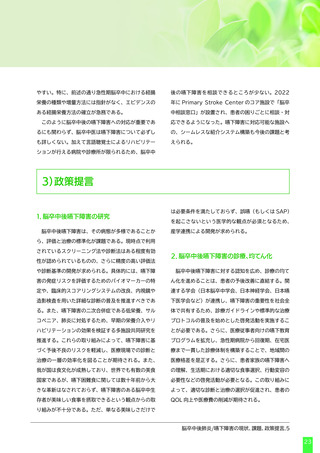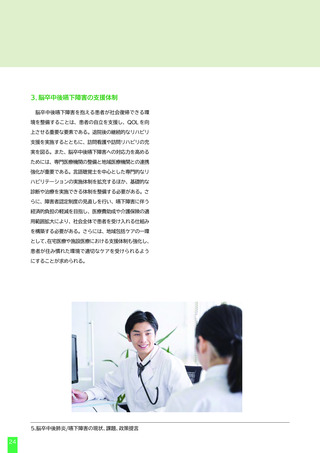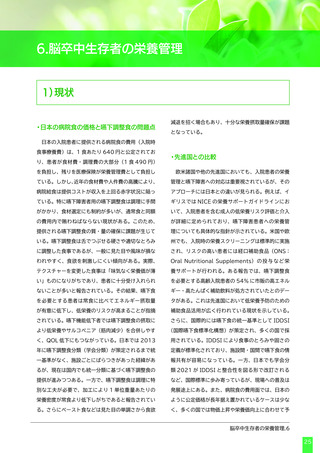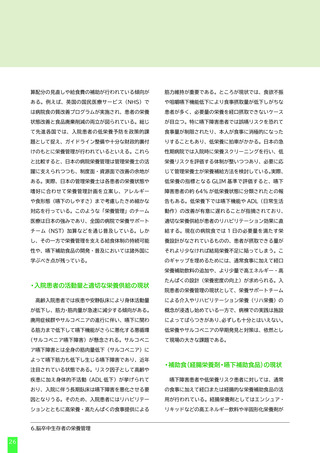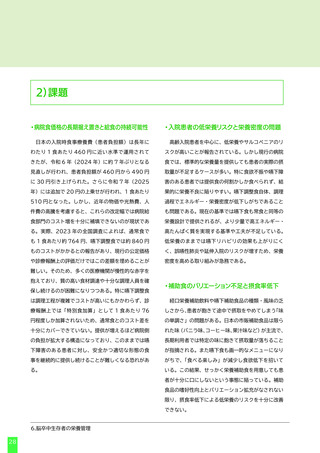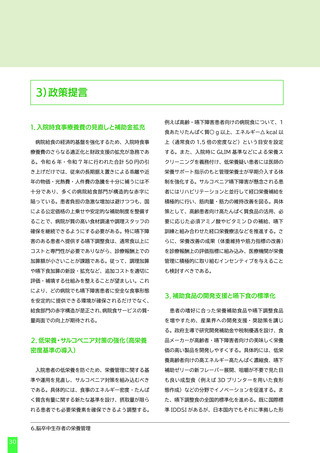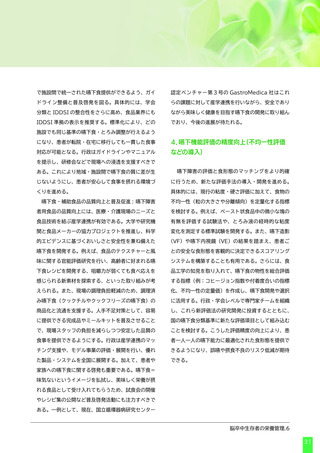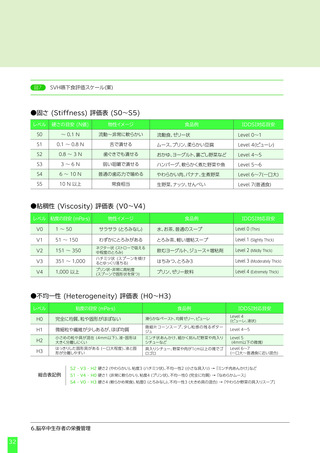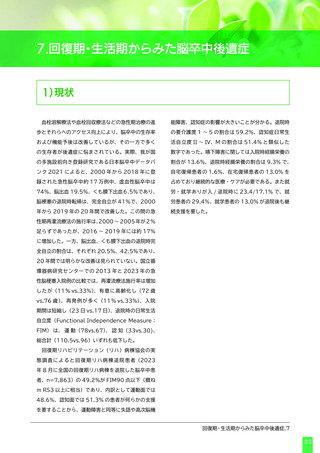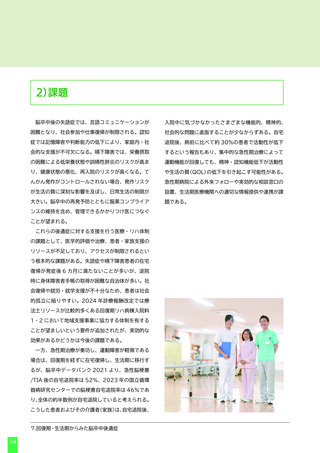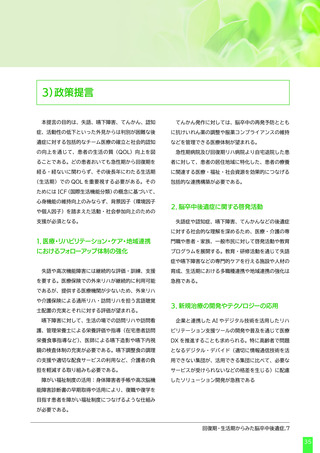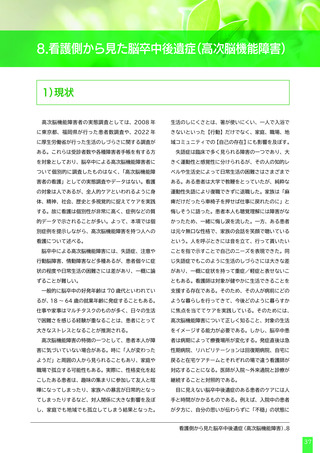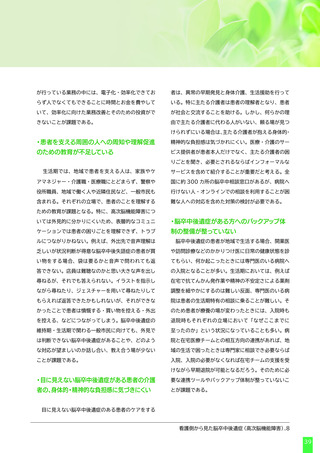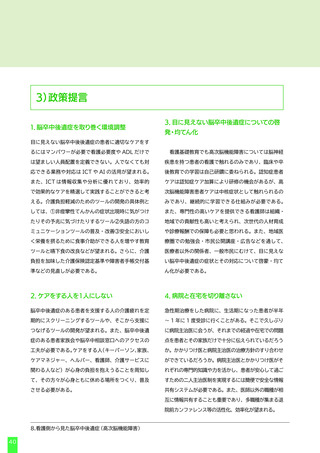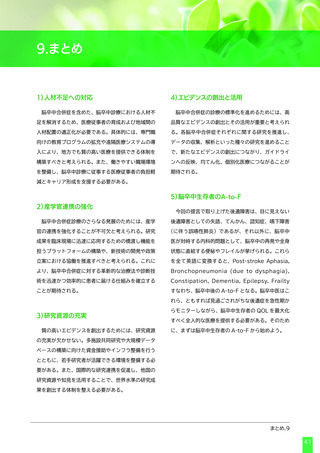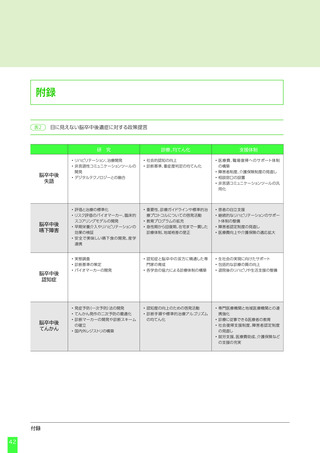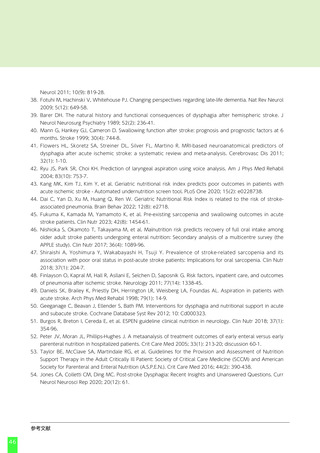よむ、つかう、まなぶ。
外見からの判別が困難な脳卒中後遺症の制圧に向けた提言 (11 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.ncvc.go.jp/hospital/wp-content/uploads/sites/2/20250707_neurology_seisakuteigen.pdf |
| 出典情報 | 「外見からの判別が困難な脳卒中後遺症の制圧に向けた提言」発表(7/7)《国立循環器病研究センター》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
3.脳卒中後てんかんの現状、課題、政策提言
1)現状
脳 卒 中 後 て ん か ん(Post-stroke epilepsy:
として追加)は、既存モデルよりも有用であった 20。
PSE)は、脳卒中発症後 7 日目以降に発作を起こす
PSE の発作症状としては、てんかん症候群に該当す
脳卒中後遺症であり、脳梗塞後の 2 ~ 14%、脳出
るような典型的な発作は少なく、脳卒中の病巣が多彩
血後の 10 ~ 20%に発生するとされている 17。一旦
であるが故に発作様式も多彩となり、特異的な症状が
てんかん発作を発症すると、未治療下ではその後の発
決まっていない。従って、脳波検査が診断のサポート
作再発率は 71.5%と高値であり、抗てんかん発作薬
となるが、一回の発作間欠期脳波検査では約 3 割程
による治療を必要とする 18。PSE の発作は突然発症
度のみにしか発作間欠期てんかん性放電は検出されな
し生命の危機に陥ることもあるため、予め発症リスク
いため、診断に苦慮する場合がある。その他の検査と
を知っておくことは極めて重要である。PSE の発症
して、てんかん発作に伴う脳血流の増加を、Arterial
リスク因子として、皮質領域の脳卒中病変や早期発作
spin labeling(ASL)、 造 影 CT、 脳 血 流 single
(脳卒中発症から7日以内)の既往が報告されている。
photon emission computed tomography
脳梗塞の病型に関しては、心原性に多く、領域は前
(SPECT)といった脳灌流画像で捉えることも有用
方循環系の中大脳動脈領域に多いとされる。脳出血で
とされ、脳血流 SPECT では発作後の遷延性高還流
は皮質型出血(脳葉型)に多く合併し、血腫量の大き
を確認できることも報告されている 21,22。
さも関連する。また、脳梗塞急性期治療である静注血
治療としては、PSE の起源となるてんかん原性の
栓溶解療法(rt-PA)や血管内治療が PSE のリスク
形成を予防(一次予防)することが最も望ましいと
となるとの報告もあるが、これについては否定的な報
考えられるが、現状では確立した治療は存在しない。
告もあり一定していない 19。また、脳梗塞、脳出血
しかし、抗てんかん発作薬やスタチンの抗炎症、抗
に共通して見られる新たな PSE のリスクとして脳表
酸化作用などによって、PSE の発生を抑制するので
シデローシス(Cortical superficial siderosis:
はないかという観察研究が報告されるようになって
20
。cSS は一般人口におい
おり 23、今後のエビデンスが期待されている。2 回
ては稀な所見であり、健常高齢者では約 0.7%が有
目以降の発作の再発を予防する(二次予防)目的と
するとされているが、我が国にて行われた PSE の多
しては抗てんかん発作薬の投薬が望ましいと考えら
施設前向き観察研究(PROPOSE 研究)において、
れる 24。前述の PROPOSE 研究においても、てん
cSS が PSE 症例の 50%弱に観察されることが判明
かん発作の再発により PSE 患者の機能予後が悪化す
した。PSE の既存のリスクモデル(SeLECT スコア、
ることが判明している 25。さらには、多くの研究成
CAVE スコア)に、新たなリスク因子として追加し
果を基に行われたメタ解析においても脳卒中後のて
て作成したリスクモデル、SeLECT-S スコア(脳梗
んかん発作は、その後の死亡リスクを 2.1 倍、機能
塞群、重症度を加味して cSS の存在を 6 点として追
予後不良を 2.2 倍、認知障害を 3.1 倍上昇させる
加)
、CAVE-S スコア(頭蓋内出血群、cSS を 1 点
ことが判明しており 26、適切なてんかん発作コント
cSS)が報告されている
脳卒中後てんかんの現状、課題、政策提言.3
11
1)現状
脳 卒 中 後 て ん か ん(Post-stroke epilepsy:
として追加)は、既存モデルよりも有用であった 20。
PSE)は、脳卒中発症後 7 日目以降に発作を起こす
PSE の発作症状としては、てんかん症候群に該当す
脳卒中後遺症であり、脳梗塞後の 2 ~ 14%、脳出
るような典型的な発作は少なく、脳卒中の病巣が多彩
血後の 10 ~ 20%に発生するとされている 17。一旦
であるが故に発作様式も多彩となり、特異的な症状が
てんかん発作を発症すると、未治療下ではその後の発
決まっていない。従って、脳波検査が診断のサポート
作再発率は 71.5%と高値であり、抗てんかん発作薬
となるが、一回の発作間欠期脳波検査では約 3 割程
による治療を必要とする 18。PSE の発作は突然発症
度のみにしか発作間欠期てんかん性放電は検出されな
し生命の危機に陥ることもあるため、予め発症リスク
いため、診断に苦慮する場合がある。その他の検査と
を知っておくことは極めて重要である。PSE の発症
して、てんかん発作に伴う脳血流の増加を、Arterial
リスク因子として、皮質領域の脳卒中病変や早期発作
spin labeling(ASL)、 造 影 CT、 脳 血 流 single
(脳卒中発症から7日以内)の既往が報告されている。
photon emission computed tomography
脳梗塞の病型に関しては、心原性に多く、領域は前
(SPECT)といった脳灌流画像で捉えることも有用
方循環系の中大脳動脈領域に多いとされる。脳出血で
とされ、脳血流 SPECT では発作後の遷延性高還流
は皮質型出血(脳葉型)に多く合併し、血腫量の大き
を確認できることも報告されている 21,22。
さも関連する。また、脳梗塞急性期治療である静注血
治療としては、PSE の起源となるてんかん原性の
栓溶解療法(rt-PA)や血管内治療が PSE のリスク
形成を予防(一次予防)することが最も望ましいと
となるとの報告もあるが、これについては否定的な報
考えられるが、現状では確立した治療は存在しない。
告もあり一定していない 19。また、脳梗塞、脳出血
しかし、抗てんかん発作薬やスタチンの抗炎症、抗
に共通して見られる新たな PSE のリスクとして脳表
酸化作用などによって、PSE の発生を抑制するので
シデローシス(Cortical superficial siderosis:
はないかという観察研究が報告されるようになって
20
。cSS は一般人口におい
おり 23、今後のエビデンスが期待されている。2 回
ては稀な所見であり、健常高齢者では約 0.7%が有
目以降の発作の再発を予防する(二次予防)目的と
するとされているが、我が国にて行われた PSE の多
しては抗てんかん発作薬の投薬が望ましいと考えら
施設前向き観察研究(PROPOSE 研究)において、
れる 24。前述の PROPOSE 研究においても、てん
cSS が PSE 症例の 50%弱に観察されることが判明
かん発作の再発により PSE 患者の機能予後が悪化す
した。PSE の既存のリスクモデル(SeLECT スコア、
ることが判明している 25。さらには、多くの研究成
CAVE スコア)に、新たなリスク因子として追加し
果を基に行われたメタ解析においても脳卒中後のて
て作成したリスクモデル、SeLECT-S スコア(脳梗
んかん発作は、その後の死亡リスクを 2.1 倍、機能
塞群、重症度を加味して cSS の存在を 6 点として追
予後不良を 2.2 倍、認知障害を 3.1 倍上昇させる
加)
、CAVE-S スコア(頭蓋内出血群、cSS を 1 点
ことが判明しており 26、適切なてんかん発作コント
cSS)が報告されている
脳卒中後てんかんの現状、課題、政策提言.3
11