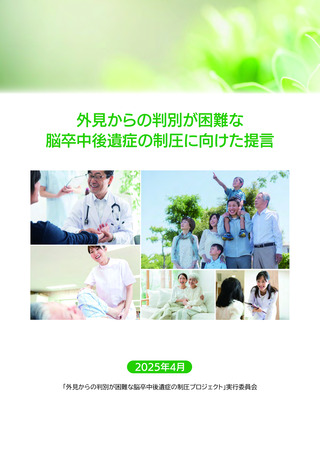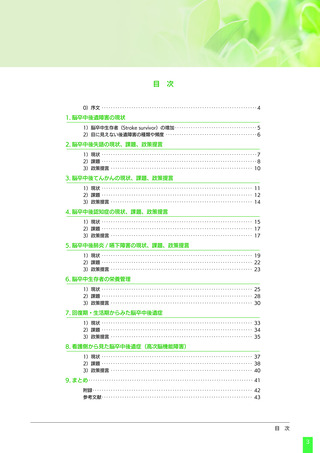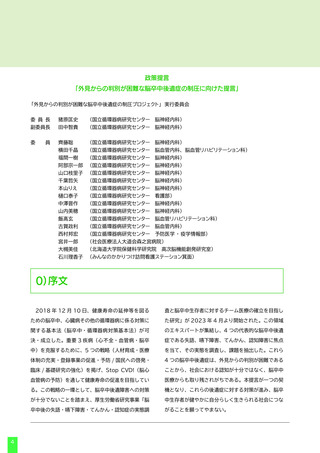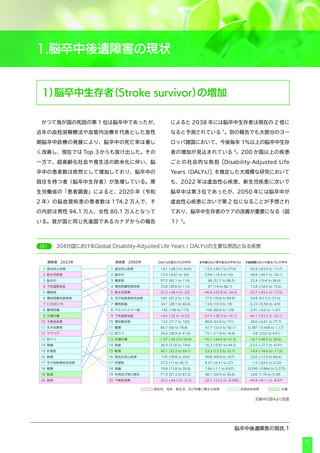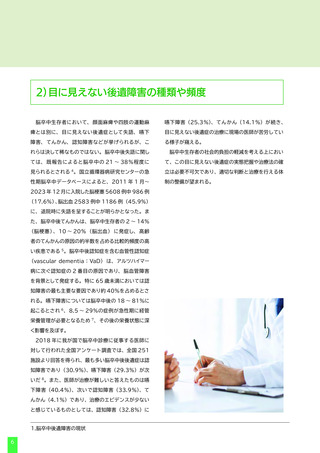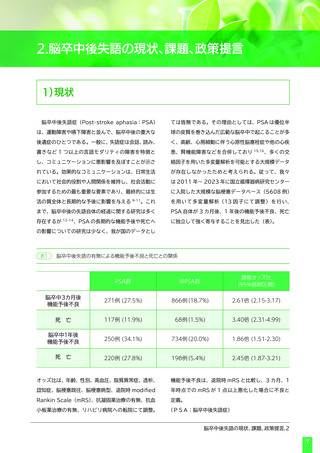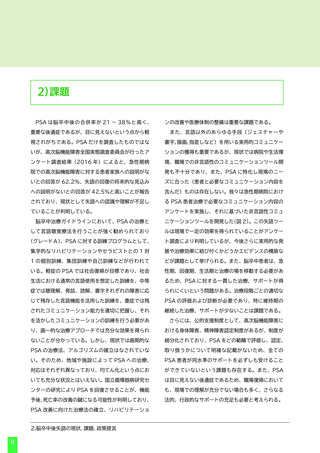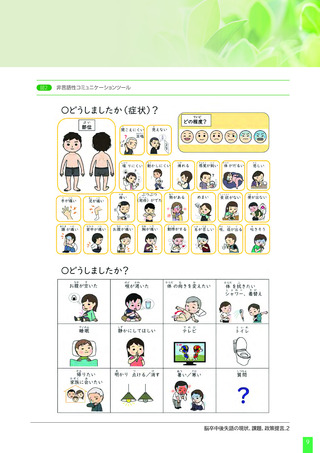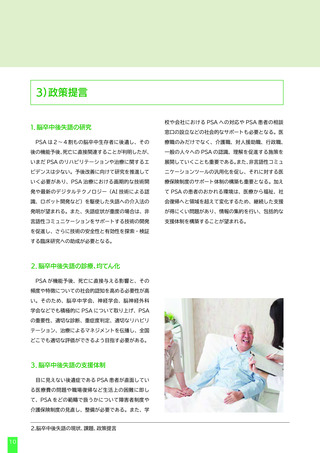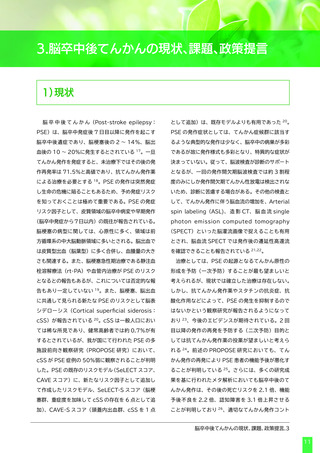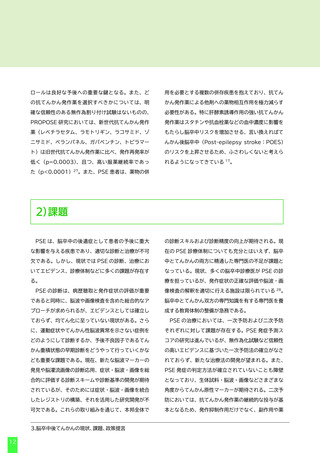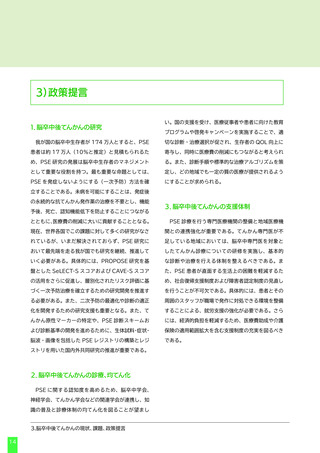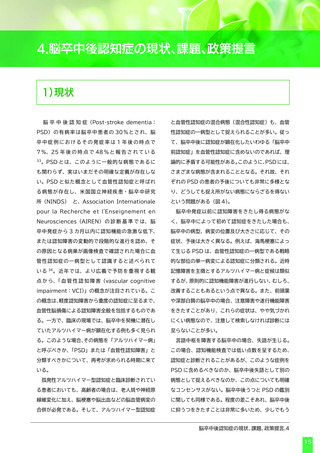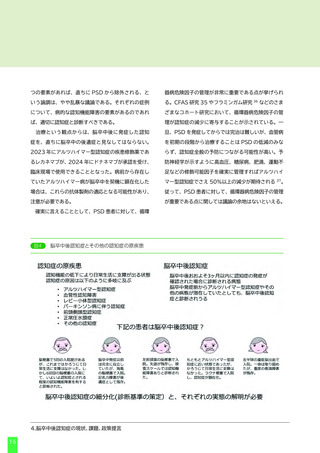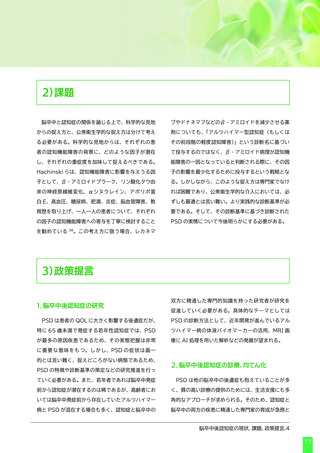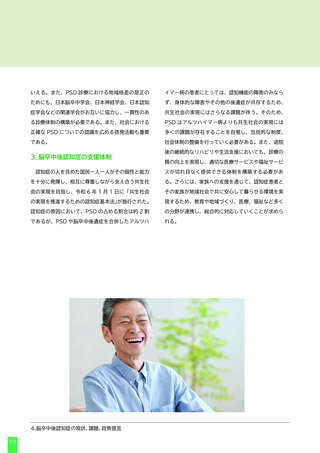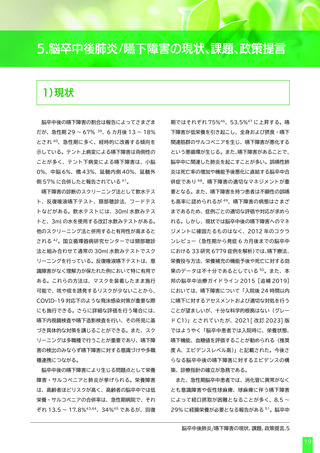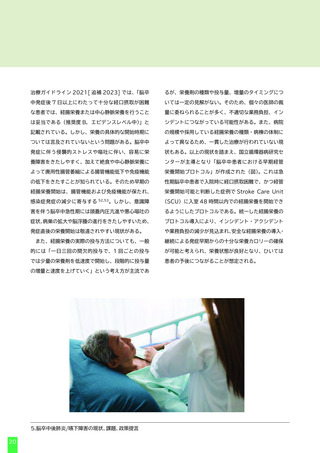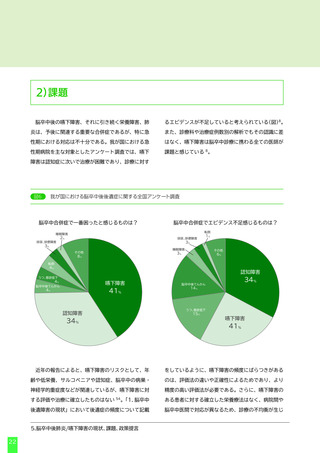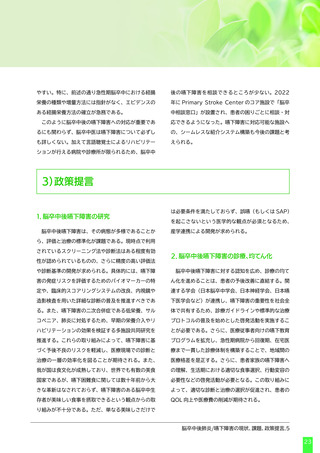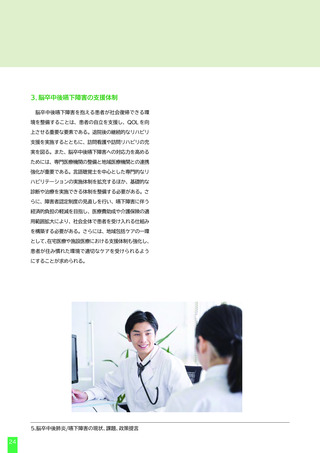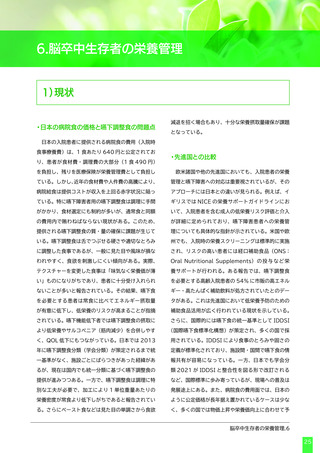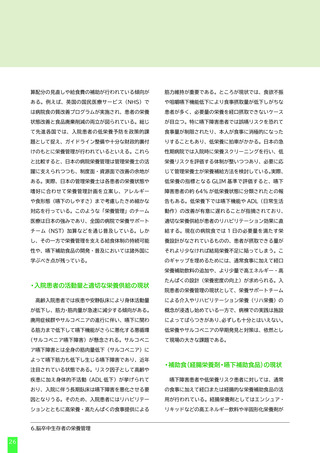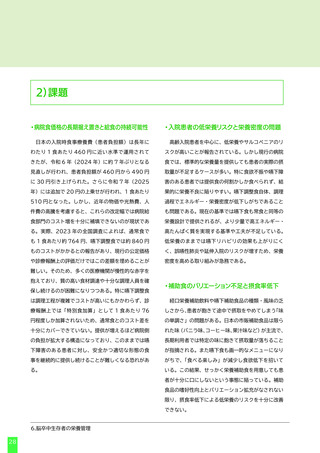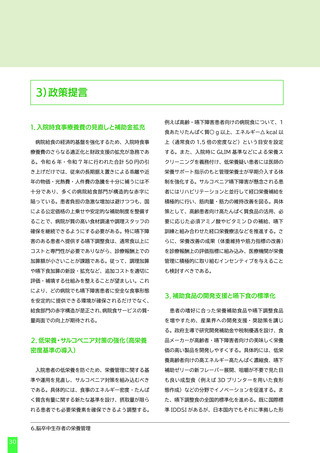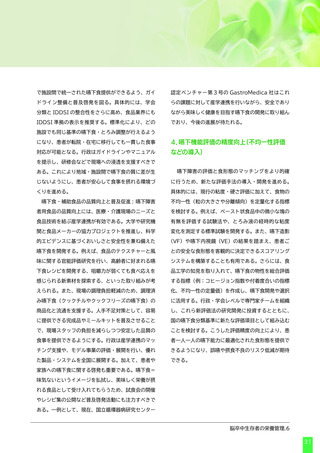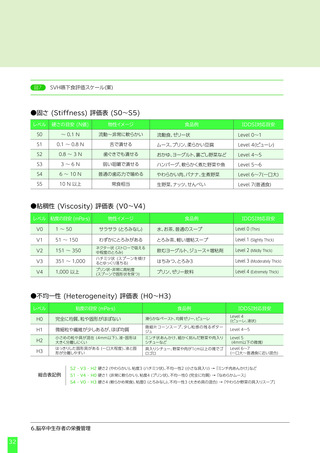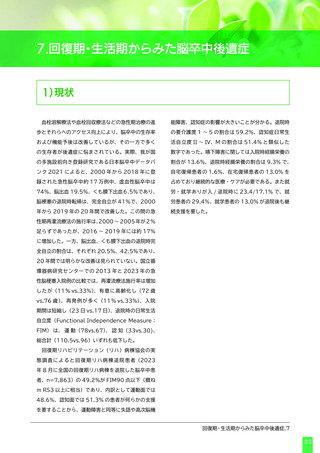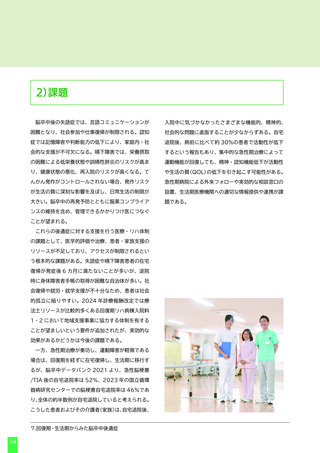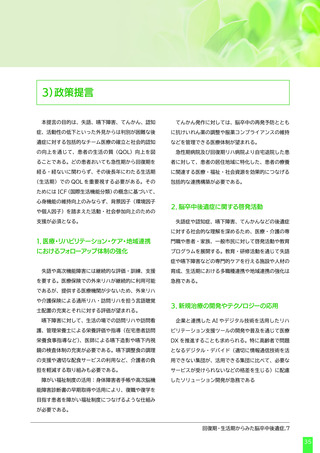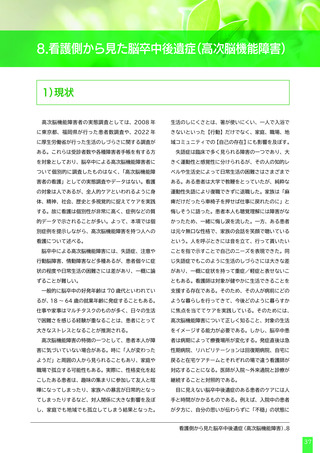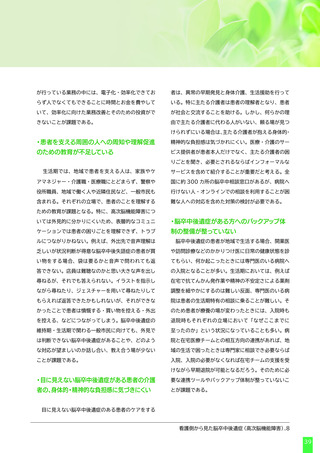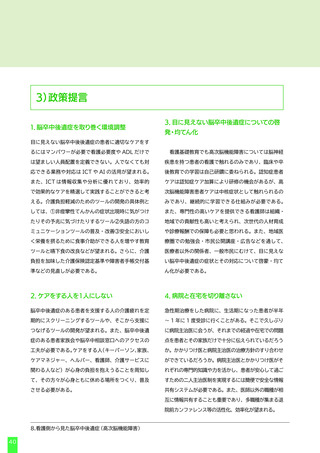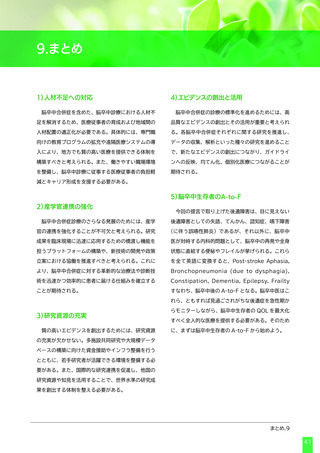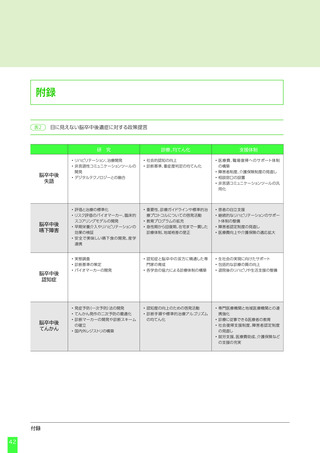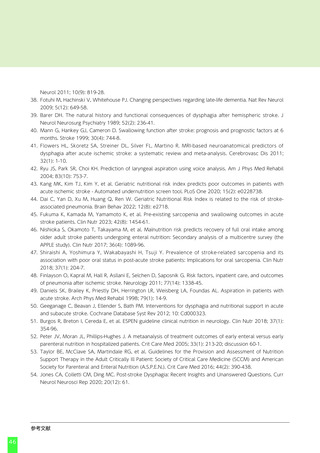よむ、つかう、まなぶ。
外見からの判別が困難な脳卒中後遺症の制圧に向けた提言 (37 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.ncvc.go.jp/hospital/wp-content/uploads/sites/2/20250707_neurology_seisakuteigen.pdf |
| 出典情報 | 「外見からの判別が困難な脳卒中後遺症の制圧に向けた提言」発表(7/7)《国立循環器病研究センター》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
8.看護側から見た脳卒中後遺症(高次脳機能障害)
1)現状
高次脳機能障害者の実態調査としては、2008 年
生活のしにくさとは、箸が使いにくい、一人で入浴で
に東京都、福岡県が行った患者数調査や、2022 年
きないといった【行動】だけでなく、家庭、職場、地
に厚生労働省が行った生活のしづらさに関する調査が
域コミュニティでの【自己の存在】にも影響を及ぼす。
ある。これらは受診者数や各種障害者手帳を有する方
失語症は臨床で多く見られる障害の一つであり、大
を対象としており、脳卒中による高次脳機能障害者に
きく運動性と感覚性に分けられるが、その人の知的レ
ついて個別的に調査したものはなく、
「高次脳機能障
ベルや生活史によって日常生活の困難さはさまざまで
害者の看護」としての実態調査やデータはない。看護
ある。ある患者は大学で教鞭をとっていたが、純粋な
の対象は人であるが、全人的ケアといわれるように身
運動性失語により復職できずに退職した。家族は「麻
体、精神、社会、歴史と多視覚的に捉えてケアを実践
痺だけだったら車椅子を押せば仕事に戻れたのに」と
する。故に看護は個別性が非常に高く、症例などの質
悔しそうに語った。患者本人も聴覚理解には障害がな
的データで示されることが多い。よって、本項では個
かったため、一緒に悔し涙を流した。一方、ある患者
別症例を提示しながら、高次脳機能障害を持つ人への
は元々無口な性格で、家族の会話を笑顔で聴いている
看護について述べる。
という。人を呼ぶときには音を立て、行って貰いたい
脳卒中による高次脳機能障害には、失語症、注意や
ことを指で示すことで自己のニーズを表現できた。同
行動脳障害、情動障害など多種あるが、患者個々に症
じ失語症でもこのように生活のしづらさには大きな差
状の程度や日常生活の困難さには差があり、一概に論
があり、一概に症状を持って重症/軽症と表せないこ
ずることが難しい。
ともある。看護師は対象が健やかに生活できることを
一般的に脳卒中の好発年齢は 70 歳代といわれてい
支援する存在である。そのため、その人が病前にどの
るが、18 〜 64 歳の就業年齢に発症することもある。
ような暮らしを行ってきて、今後どのように暮らすか
仕事や家事はマルチタスクのものが多く、日々の生活
に焦点を当ててケアを実践している。そのためには、
で困難さを感じる経験が重なることは、患者にとって
高次脳機能障害について正しく知ること、対象の生活
大きなストレスとなることが推測される。
をイメージする能力が必要である。しかし、脳卒中患
高次脳機能障害の特徴の一つとして、患者本人が障
者は病期によって療養場所が変化する。発症直後は急
害に気づいていない場合がある。時に「人が変わった
性期病院、リハビリテーションは回復期病院、自宅に
ようだ」と周囲の人から見られることもあり、家庭や
戻ると在宅ケアチームとそれぞれの場で違う看護師が
職場で孤立する可能性もある。実際に、性格変化を起
対応することになる。医師が入院〜外来通院と診療が
こしたある患者は、趣味の集まりに参加して友人と喧
継続することと対照的である。
嘩になってしまったり、家族への暴言が日常的となっ
目に見えない脳卒中後遺症のある患者のケアには人
てしまったりするなど、対人関係に大きな影響を及ぼ
手と時間がかかるものである。例えば、入院中の患者
し、家庭でも地域でも孤立してしまう結果となった。
が夕方に、自分の思いが伝わらずに「不穏」の状態に
看護側から見た脳卒中後遺症(高次脳機能障害).8
37
1)現状
高次脳機能障害者の実態調査としては、2008 年
生活のしにくさとは、箸が使いにくい、一人で入浴で
に東京都、福岡県が行った患者数調査や、2022 年
きないといった【行動】だけでなく、家庭、職場、地
に厚生労働省が行った生活のしづらさに関する調査が
域コミュニティでの【自己の存在】にも影響を及ぼす。
ある。これらは受診者数や各種障害者手帳を有する方
失語症は臨床で多く見られる障害の一つであり、大
を対象としており、脳卒中による高次脳機能障害者に
きく運動性と感覚性に分けられるが、その人の知的レ
ついて個別的に調査したものはなく、
「高次脳機能障
ベルや生活史によって日常生活の困難さはさまざまで
害者の看護」としての実態調査やデータはない。看護
ある。ある患者は大学で教鞭をとっていたが、純粋な
の対象は人であるが、全人的ケアといわれるように身
運動性失語により復職できずに退職した。家族は「麻
体、精神、社会、歴史と多視覚的に捉えてケアを実践
痺だけだったら車椅子を押せば仕事に戻れたのに」と
する。故に看護は個別性が非常に高く、症例などの質
悔しそうに語った。患者本人も聴覚理解には障害がな
的データで示されることが多い。よって、本項では個
かったため、一緒に悔し涙を流した。一方、ある患者
別症例を提示しながら、高次脳機能障害を持つ人への
は元々無口な性格で、家族の会話を笑顔で聴いている
看護について述べる。
という。人を呼ぶときには音を立て、行って貰いたい
脳卒中による高次脳機能障害には、失語症、注意や
ことを指で示すことで自己のニーズを表現できた。同
行動脳障害、情動障害など多種あるが、患者個々に症
じ失語症でもこのように生活のしづらさには大きな差
状の程度や日常生活の困難さには差があり、一概に論
があり、一概に症状を持って重症/軽症と表せないこ
ずることが難しい。
ともある。看護師は対象が健やかに生活できることを
一般的に脳卒中の好発年齢は 70 歳代といわれてい
支援する存在である。そのため、その人が病前にどの
るが、18 〜 64 歳の就業年齢に発症することもある。
ような暮らしを行ってきて、今後どのように暮らすか
仕事や家事はマルチタスクのものが多く、日々の生活
に焦点を当ててケアを実践している。そのためには、
で困難さを感じる経験が重なることは、患者にとって
高次脳機能障害について正しく知ること、対象の生活
大きなストレスとなることが推測される。
をイメージする能力が必要である。しかし、脳卒中患
高次脳機能障害の特徴の一つとして、患者本人が障
者は病期によって療養場所が変化する。発症直後は急
害に気づいていない場合がある。時に「人が変わった
性期病院、リハビリテーションは回復期病院、自宅に
ようだ」と周囲の人から見られることもあり、家庭や
戻ると在宅ケアチームとそれぞれの場で違う看護師が
職場で孤立する可能性もある。実際に、性格変化を起
対応することになる。医師が入院〜外来通院と診療が
こしたある患者は、趣味の集まりに参加して友人と喧
継続することと対照的である。
嘩になってしまったり、家族への暴言が日常的となっ
目に見えない脳卒中後遺症のある患者のケアには人
てしまったりするなど、対人関係に大きな影響を及ぼ
手と時間がかかるものである。例えば、入院中の患者
し、家庭でも地域でも孤立してしまう結果となった。
が夕方に、自分の思いが伝わらずに「不穏」の状態に
看護側から見た脳卒中後遺症(高次脳機能障害).8
37