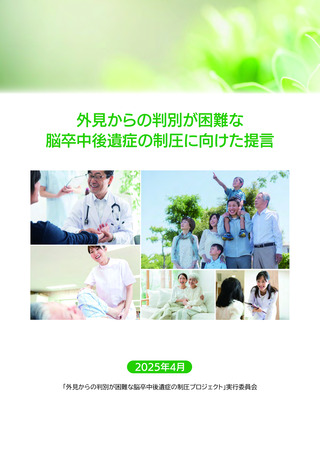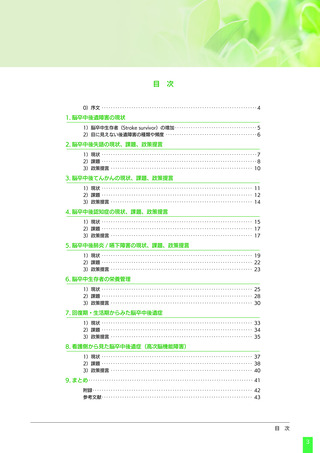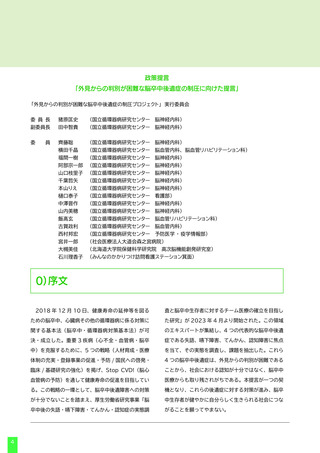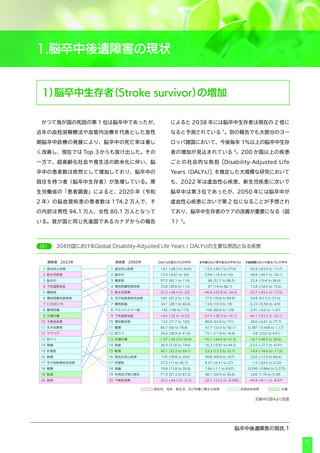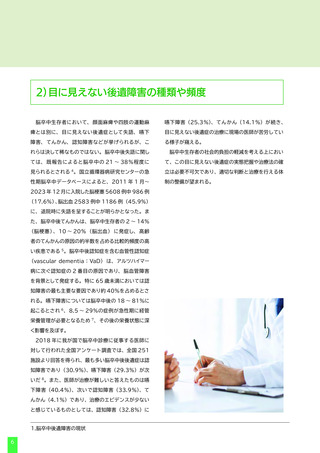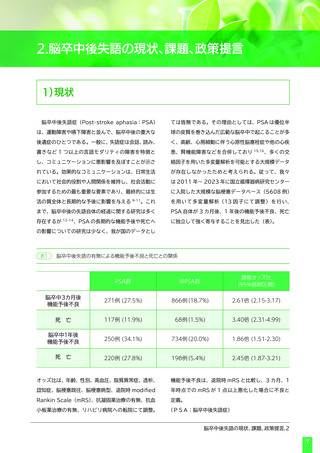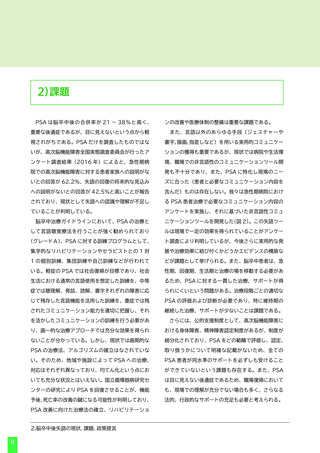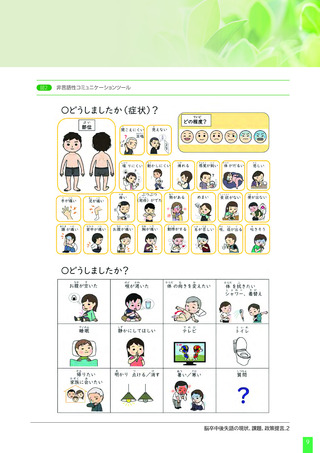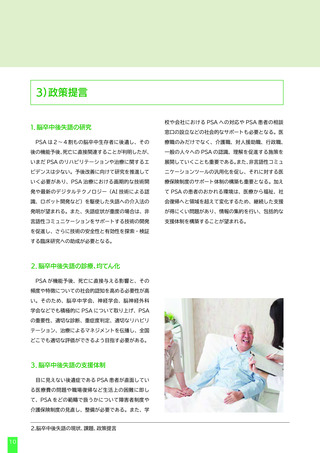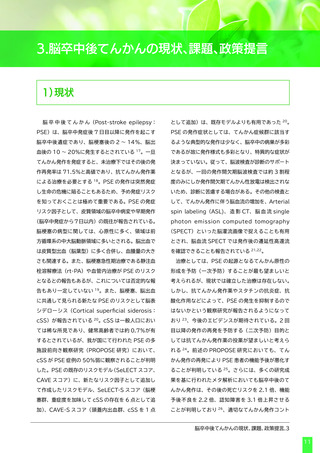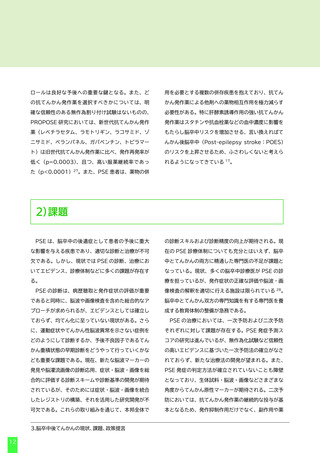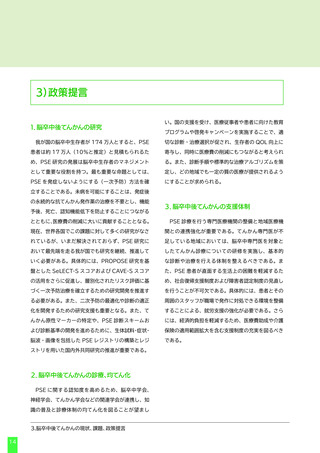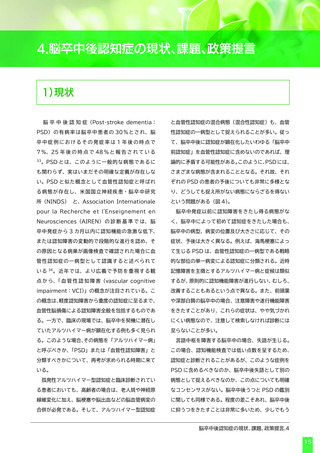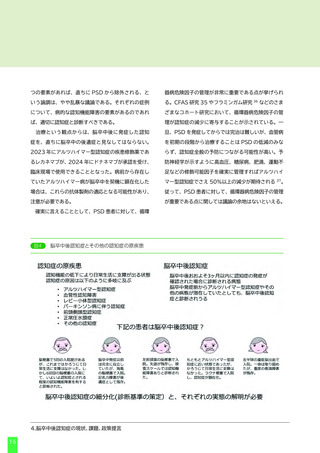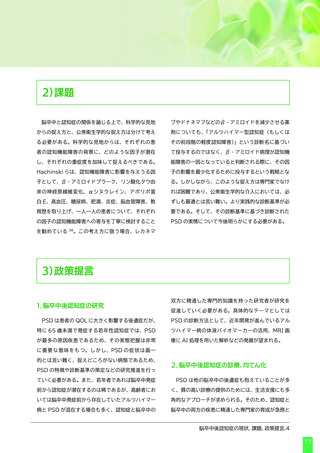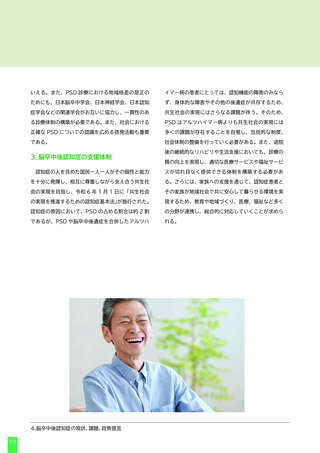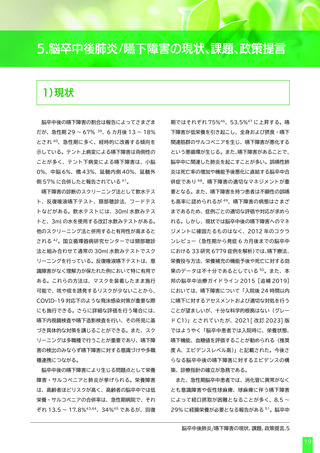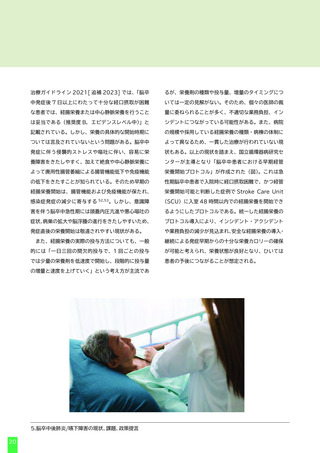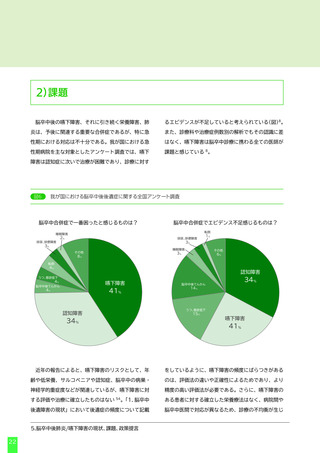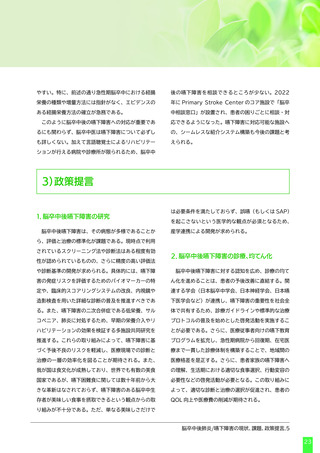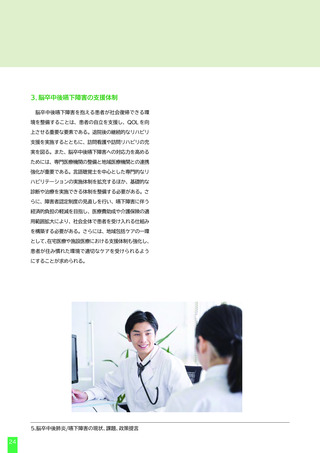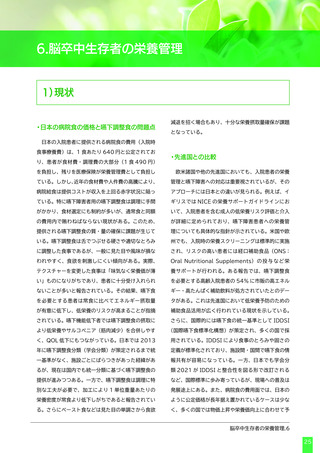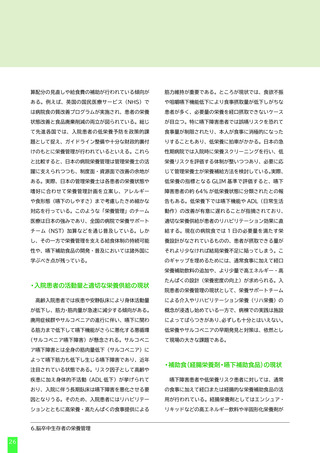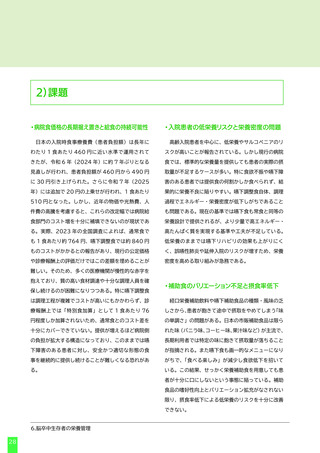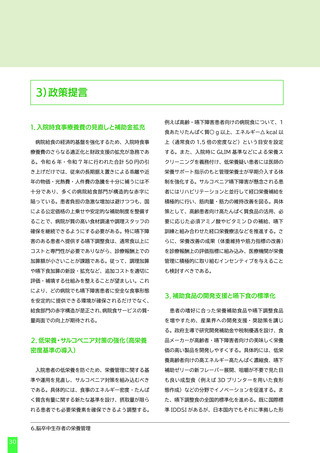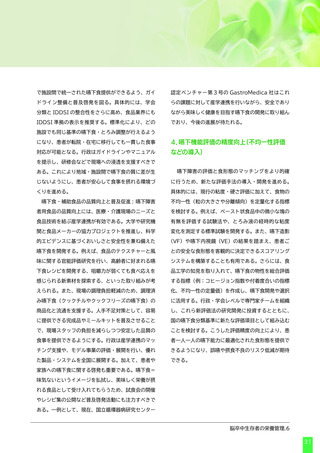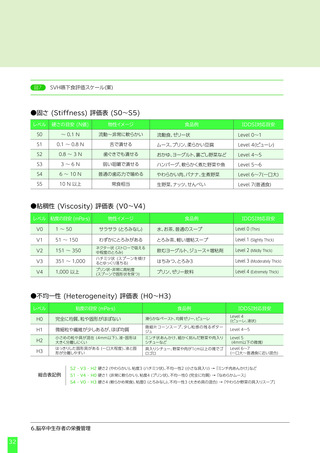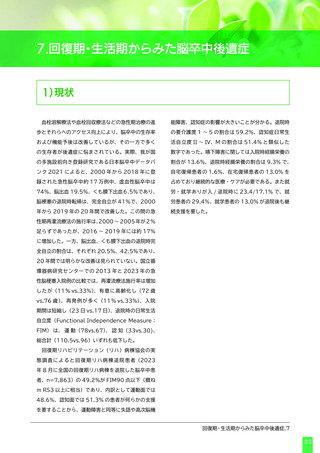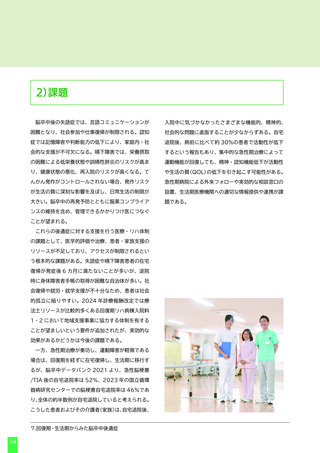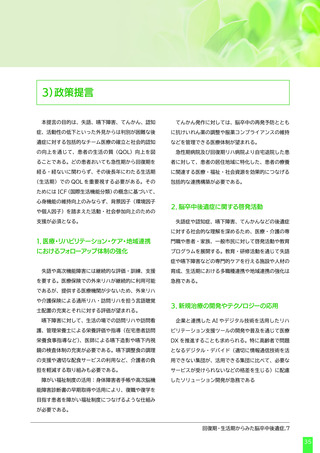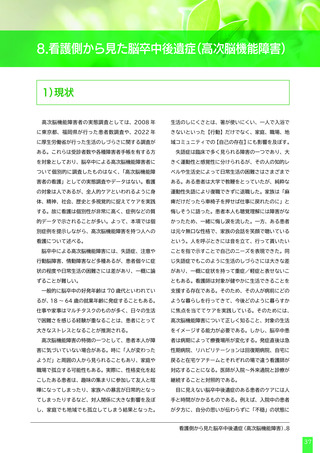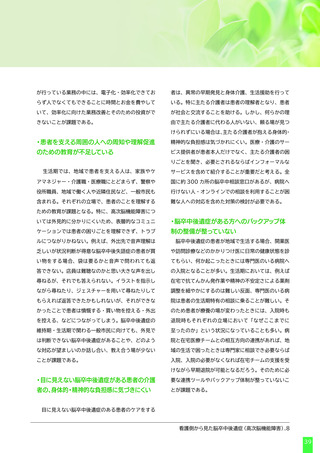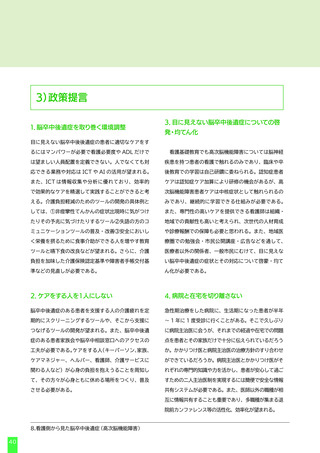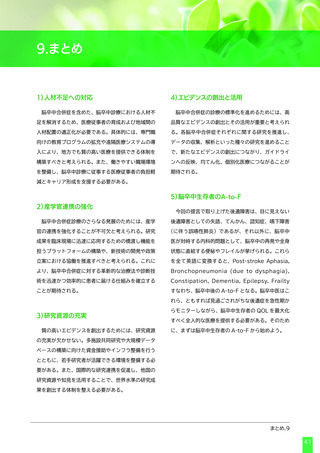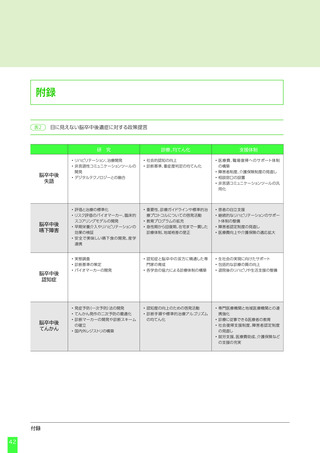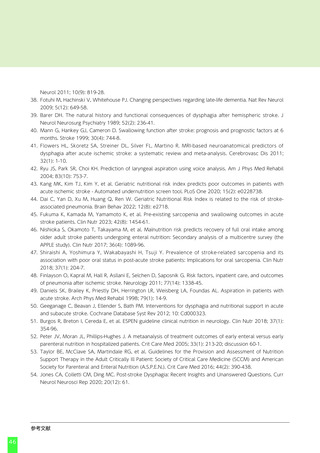よむ、つかう、まなぶ。
外見からの判別が困難な脳卒中後遺症の制圧に向けた提言 (23 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.ncvc.go.jp/hospital/wp-content/uploads/sites/2/20250707_neurology_seisakuteigen.pdf |
| 出典情報 | 「外見からの判別が困難な脳卒中後遺症の制圧に向けた提言」発表(7/7)《国立循環器病研究センター》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
やすい。特に、前述の通り急性期脳卒中における経腸
後の嚥下障害を相談できるところが少ない。2022
栄養の種類や増量方法には指針がなく、エビデンスの
年に Primary Stroke Center のコア施設で「脳卒
ある経腸栄養方法の確立が急務である。
中相談窓口」が設置され、患者の困りごとに相談・対
このように脳卒中後の嚥下障害への対応が重要であ
応できるようになった。嚥下障害に対応可能な施設へ
るにも関わらず、脳卒中医は嚥下障害について必ずし
の、シームレスな紹介システム構築も今後の課題と考
も詳しくない。加えて言語聴覚士によるリハビリテー
えられる。
ションが行える病院や診療所が限られるため、脳卒中
3)政策提言
1.
脳卒中後嚥下障害の研究
脳卒中後嚥下障害は、その病態が多様であることか
は必要条件を満たしておらず、誤嚥(もしくは SAP)
を起こさないという医学的な観点が必須となるため、
産学連携による開発が求められる。
ら、評価と治療の標準化が課題である。現時点で利用
されているスクリーニング法や診断法はある程度有効
性が認められているものの、さらに精度の高い評価法
2.
脳卒中後嚥下障害の診療、
均てん化
や診断基準の開発が求められる。具体的には、嚥下障
脳卒中後嚥下障害に対する認知を広め、診療の均て
害の発症リスクを評価するためのバイオマーカーの特
ん化を進めることは、患者の予後改善に直結する。関
定や、臨床的スコアリングシステムの改良、内視鏡や
連する学会(日本脳卒中学会、日本神経学会、日本嚥
造影検査を用いた詳細な診断の普及を推進すべきであ
下医学会など)が連携し、嚥下障害の重要性を社会全
る。また、嚥下障害の二次合併症である低栄養、サル
体で共有するため、診療ガイドラインや標準的な治療
コペニア、肺炎に対処するため、早期の栄養介入やリ
プロトコルの普及を始めとした啓発活動を実施するこ
ハビリテーションの効果を検証する多施設共同研究を
とが必要である。さらに、医療従事者向けの嚥下教育
推進する。これらの取り組みによって、嚥下障害に基
プログラムを拡充し、急性期病院から回復期、在宅医
づく予後不良のリスクを軽減し、医療現場での診断と
療まで一貫した診療体制を構築することで、地域間の
治療の一層の効率化を図ることが期待される。また、
医療格差を是正する。さらに、患者家族の嚥下障害へ
我が国は食文化が成熟しており、世界でも有数の美食
の理解、生活期における適切な食事選択、行動変容の
国家であるが、嚥下困難食に関しては数十年前から大
必要性などの啓発活動が必要となる。この取り組みに
きな革新はなされておらず、嚥下障害のある脳卒中生
よって、適切な診断と治療の選択が促進され、患者の
存者が美味しい食事を摂取できるという観点からの取
QOL 向上や医療費の削減が期待される。
り組みが不十分である。ただ、単なる美味しさだけで
脳卒中後肺炎/嚥下障害の現状、課題、政策提言.5
23
後の嚥下障害を相談できるところが少ない。2022
栄養の種類や増量方法には指針がなく、エビデンスの
年に Primary Stroke Center のコア施設で「脳卒
ある経腸栄養方法の確立が急務である。
中相談窓口」が設置され、患者の困りごとに相談・対
このように脳卒中後の嚥下障害への対応が重要であ
応できるようになった。嚥下障害に対応可能な施設へ
るにも関わらず、脳卒中医は嚥下障害について必ずし
の、シームレスな紹介システム構築も今後の課題と考
も詳しくない。加えて言語聴覚士によるリハビリテー
えられる。
ションが行える病院や診療所が限られるため、脳卒中
3)政策提言
1.
脳卒中後嚥下障害の研究
脳卒中後嚥下障害は、その病態が多様であることか
は必要条件を満たしておらず、誤嚥(もしくは SAP)
を起こさないという医学的な観点が必須となるため、
産学連携による開発が求められる。
ら、評価と治療の標準化が課題である。現時点で利用
されているスクリーニング法や診断法はある程度有効
性が認められているものの、さらに精度の高い評価法
2.
脳卒中後嚥下障害の診療、
均てん化
や診断基準の開発が求められる。具体的には、嚥下障
脳卒中後嚥下障害に対する認知を広め、診療の均て
害の発症リスクを評価するためのバイオマーカーの特
ん化を進めることは、患者の予後改善に直結する。関
定や、臨床的スコアリングシステムの改良、内視鏡や
連する学会(日本脳卒中学会、日本神経学会、日本嚥
造影検査を用いた詳細な診断の普及を推進すべきであ
下医学会など)が連携し、嚥下障害の重要性を社会全
る。また、嚥下障害の二次合併症である低栄養、サル
体で共有するため、診療ガイドラインや標準的な治療
コペニア、肺炎に対処するため、早期の栄養介入やリ
プロトコルの普及を始めとした啓発活動を実施するこ
ハビリテーションの効果を検証する多施設共同研究を
とが必要である。さらに、医療従事者向けの嚥下教育
推進する。これらの取り組みによって、嚥下障害に基
プログラムを拡充し、急性期病院から回復期、在宅医
づく予後不良のリスクを軽減し、医療現場での診断と
療まで一貫した診療体制を構築することで、地域間の
治療の一層の効率化を図ることが期待される。また、
医療格差を是正する。さらに、患者家族の嚥下障害へ
我が国は食文化が成熟しており、世界でも有数の美食
の理解、生活期における適切な食事選択、行動変容の
国家であるが、嚥下困難食に関しては数十年前から大
必要性などの啓発活動が必要となる。この取り組みに
きな革新はなされておらず、嚥下障害のある脳卒中生
よって、適切な診断と治療の選択が促進され、患者の
存者が美味しい食事を摂取できるという観点からの取
QOL 向上や医療費の削減が期待される。
り組みが不十分である。ただ、単なる美味しさだけで
脳卒中後肺炎/嚥下障害の現状、課題、政策提言.5
23