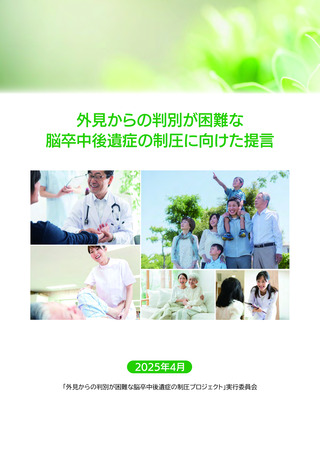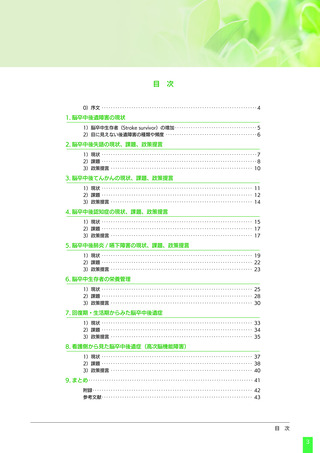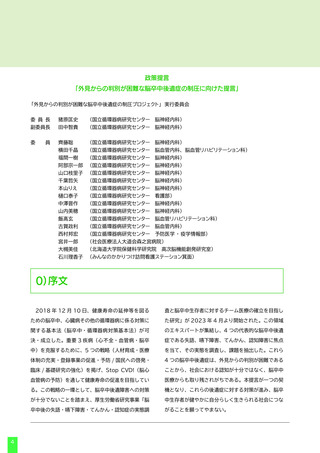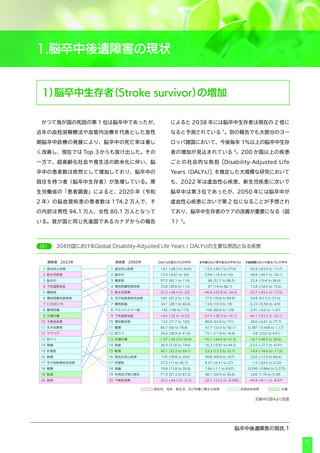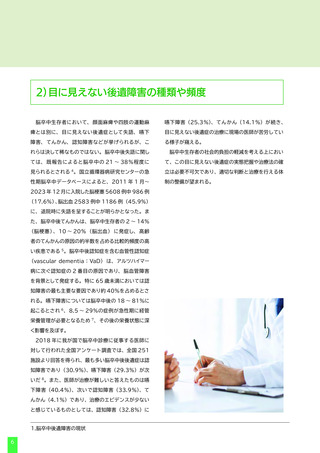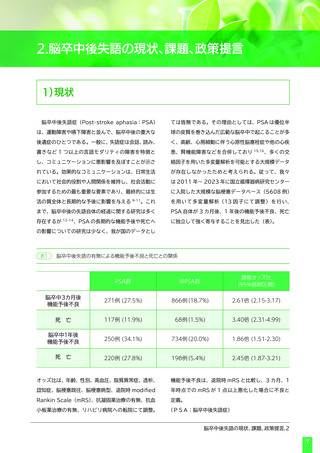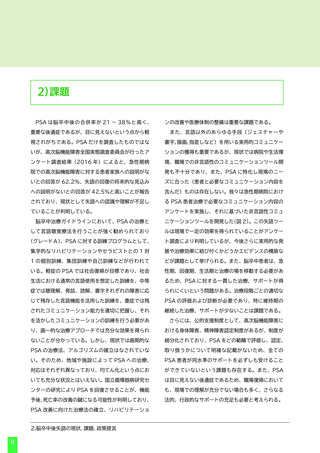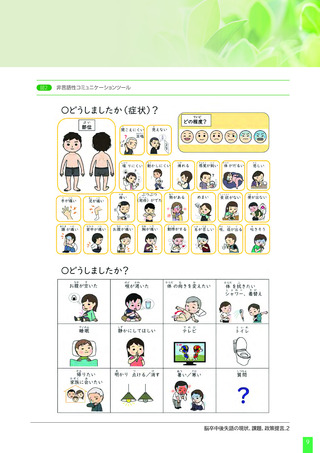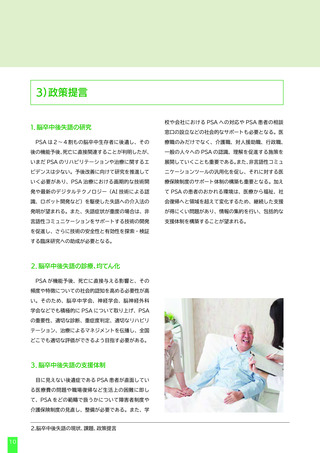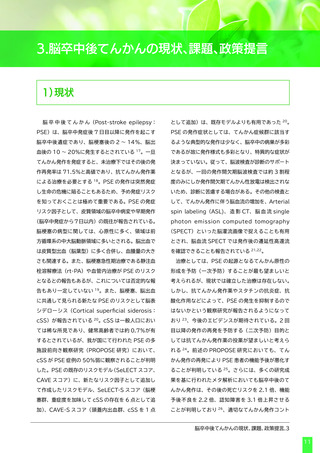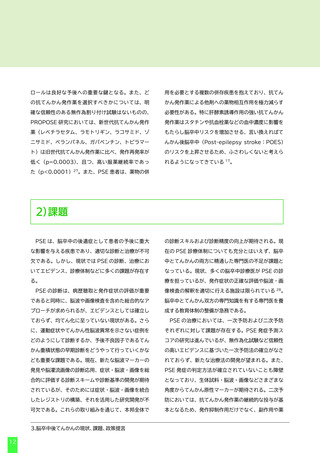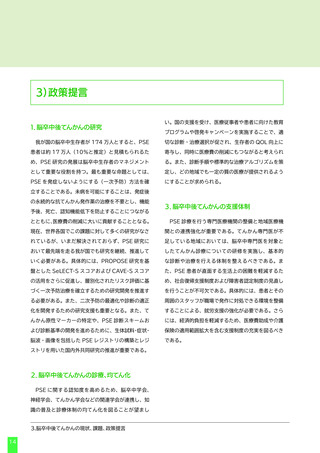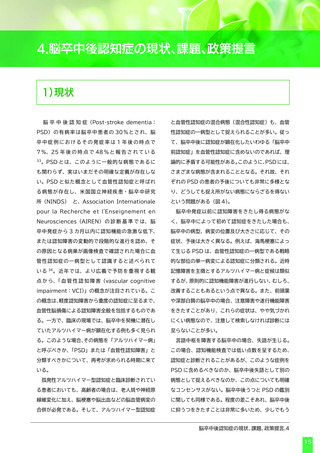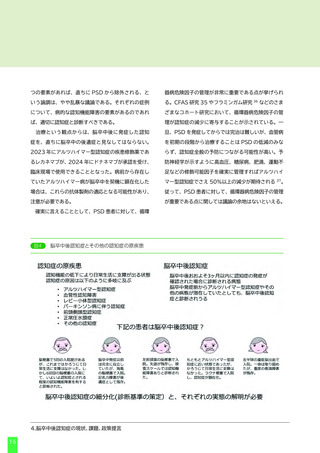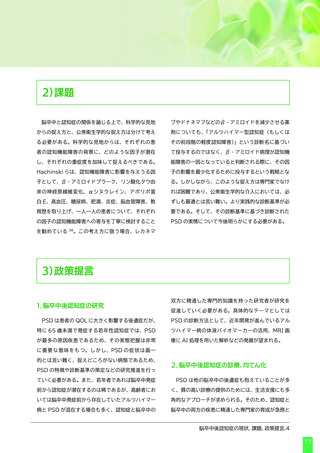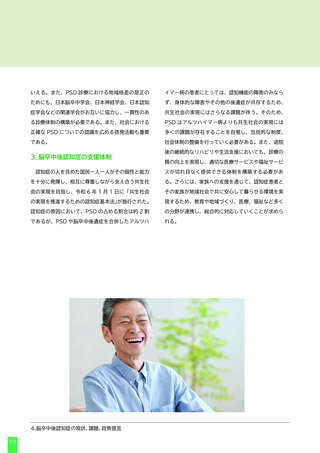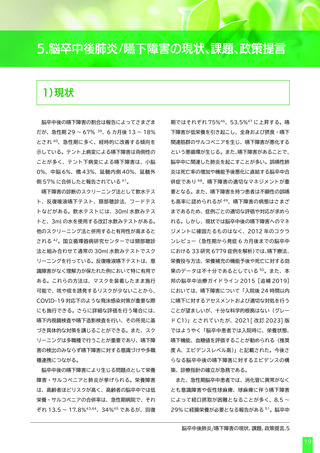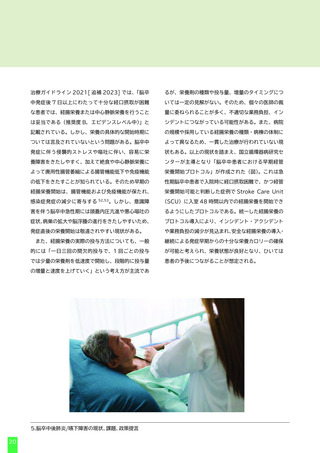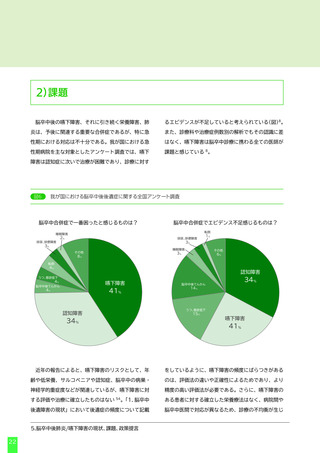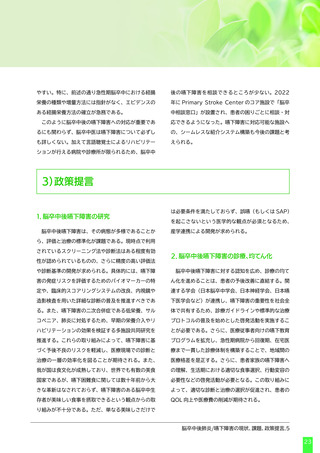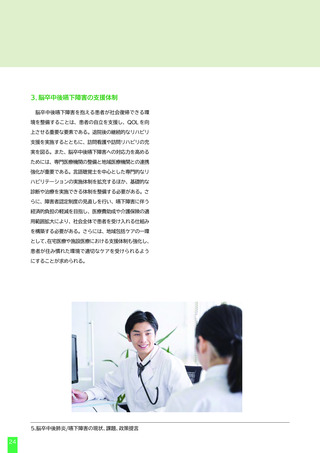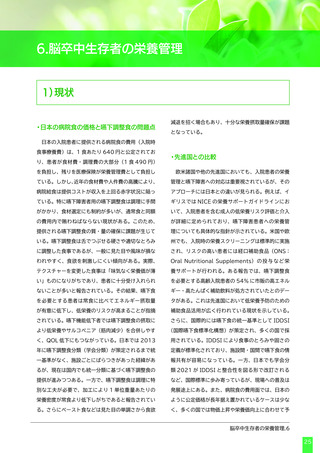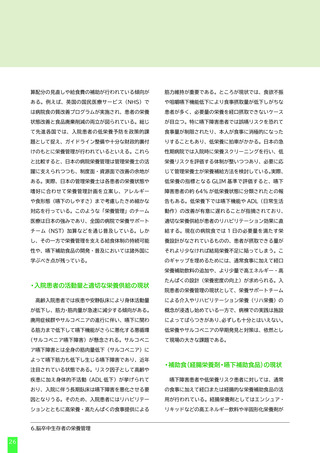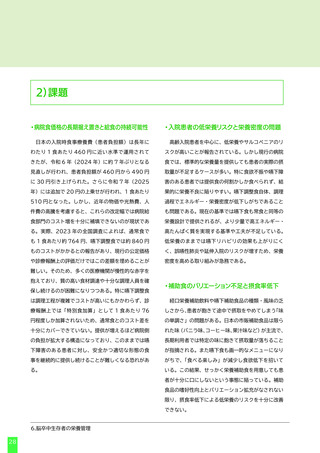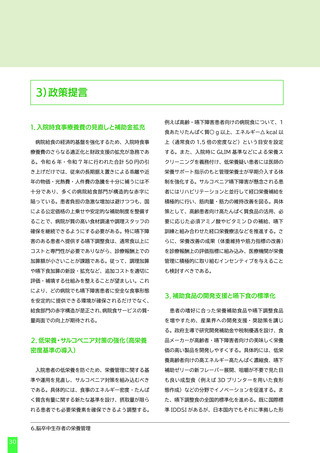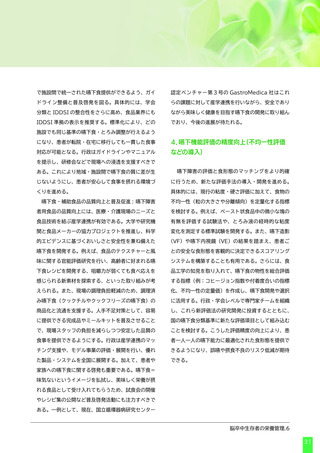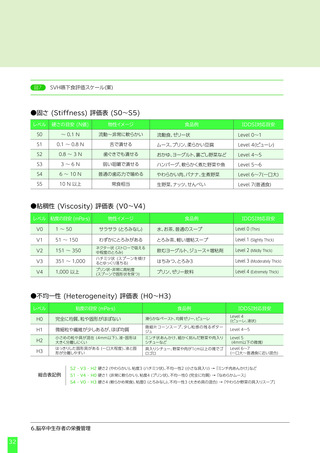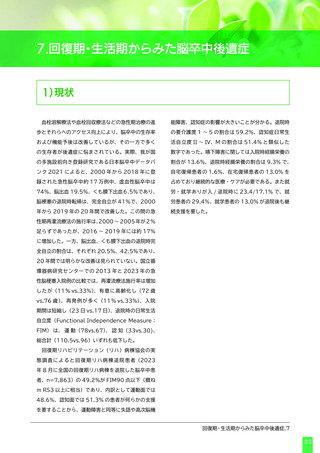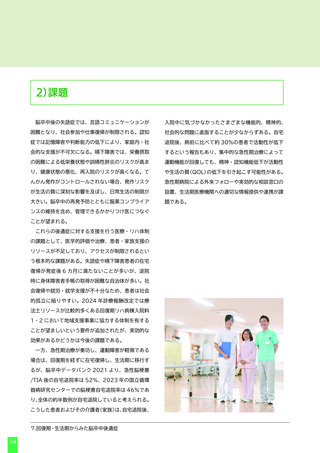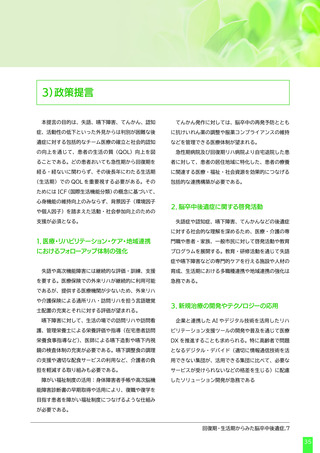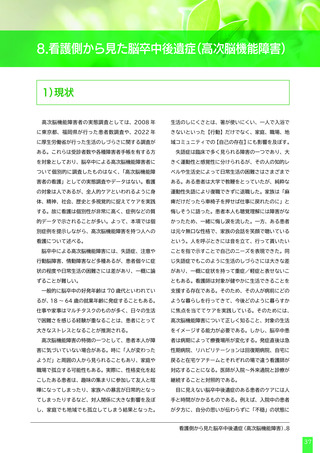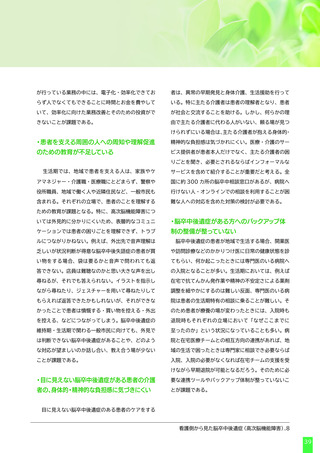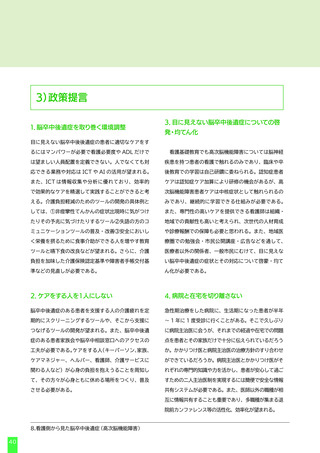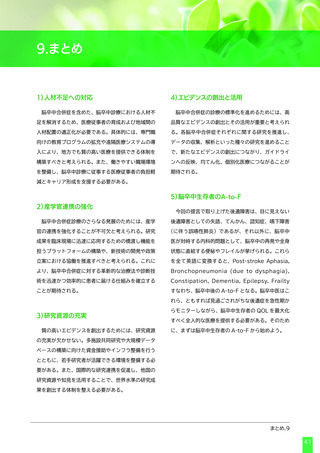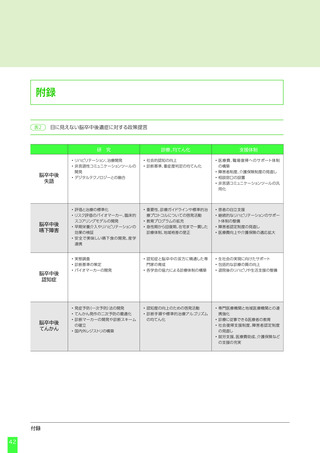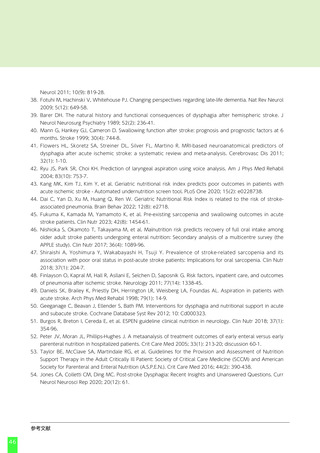よむ、つかう、まなぶ。
外見からの判別が困難な脳卒中後遺症の制圧に向けた提言 (14 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.ncvc.go.jp/hospital/wp-content/uploads/sites/2/20250707_neurology_seisakuteigen.pdf |
| 出典情報 | 「外見からの判別が困難な脳卒中後遺症の制圧に向けた提言」発表(7/7)《国立循環器病研究センター》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
3)政策提言
1.
脳卒中後てんかんの研究
い。国の支援を受け、医療従事者や患者に向けた教育
プログラムや啓発キャンペーンを実施することで、適
我が国の脳卒中生存者が 174 万人とすると、PSE
切な診断・治療選択が促され、生存者の QOL 向上に
患者は約 17 万人(10%と推定)と見積もられるた
寄与し、同時に医療費の削減にもつながると考えられ
め、PSE 研究の発展は脳卒中生存者のマネジメント
る。また、診断手順や標準的な治療アルゴリズムを策
として重要な役割を持つ。最も重要な命題としては、
定し、どの地域でも一定の質の医療が提供されるよう
PSE を発症しないようにする(一次予防)方法を確
にすることが求められる。
立することである。未病を可能にすることは、発症後
の永続的な抗てんかん発作薬の治療を不要とし、機能
予後、死亡、認知機能低下を防止することにつながる
とともに、
医療費の削減に大いに貢献することとなる。
PSE 診療を行う専門医療機関の整備と地域医療機
現在、世界各国でこの課題に対して多くの研究がなさ
関との連携強化が重要である。てんかん専門医が不
れているが、いまだ解決されておらず、PSE 研究に
足している地域においては、脳卒中専門医を対象と
おいて最先端を走る我が国でも研究を継続、推進して
したてんかん診療についての研修を実施し、基本的
いく必要がある。具体的には、PROPOSE 研究を基
な診断や治療を行える体制を整えるべきである。ま
盤とした SeLECT-S スコアおよび CAVE-S スコア
た、PSE 患者が直面する生活上の困難を軽減するた
の活用をさらに促進し、層別化されたリスク評価に基
め、社会復帰支援制度および障害者認定制度の見直し
づく一次予防治療を確立するための研究開発を推進す
を行うことが不可欠である。具体的には、患者とその
る必要がある。また、二次予防の最適化や診断の適正
周囲のスタッフが職場で発作に対処できる環境を整備
化を開発するための研究支援も重要となる。また、て
することによる、就労支援の強化が必要である。さら
んかん原性マーカーの特定や、PSE 診断スキームお
には、経済的負担を軽減するため、医療費助成や介護
よび診断基準の開発を進めるために、生体試料・症状・
保険の適用範囲拡大を含む支援制度の充実を図るべき
脳波・画像を包括した PSE レジストリの構築とレジ
である。
ストリを用いた国内外共同研究の推進が重要である。
2.
脳卒中後てんかんの診療、均てん化
PSE に関する認知度を高めるため、脳卒中学会、
神経学会、てんかん学会などの関連学会が連携し、知
識の普及と診療体制の均てん化を図ることが望まし
3.脳卒中後てんかんの現状、課題、政策提言
14
3.
脳卒中後てんかんの支援体制
1.
脳卒中後てんかんの研究
い。国の支援を受け、医療従事者や患者に向けた教育
プログラムや啓発キャンペーンを実施することで、適
我が国の脳卒中生存者が 174 万人とすると、PSE
切な診断・治療選択が促され、生存者の QOL 向上に
患者は約 17 万人(10%と推定)と見積もられるた
寄与し、同時に医療費の削減にもつながると考えられ
め、PSE 研究の発展は脳卒中生存者のマネジメント
る。また、診断手順や標準的な治療アルゴリズムを策
として重要な役割を持つ。最も重要な命題としては、
定し、どの地域でも一定の質の医療が提供されるよう
PSE を発症しないようにする(一次予防)方法を確
にすることが求められる。
立することである。未病を可能にすることは、発症後
の永続的な抗てんかん発作薬の治療を不要とし、機能
予後、死亡、認知機能低下を防止することにつながる
とともに、
医療費の削減に大いに貢献することとなる。
PSE 診療を行う専門医療機関の整備と地域医療機
現在、世界各国でこの課題に対して多くの研究がなさ
関との連携強化が重要である。てんかん専門医が不
れているが、いまだ解決されておらず、PSE 研究に
足している地域においては、脳卒中専門医を対象と
おいて最先端を走る我が国でも研究を継続、推進して
したてんかん診療についての研修を実施し、基本的
いく必要がある。具体的には、PROPOSE 研究を基
な診断や治療を行える体制を整えるべきである。ま
盤とした SeLECT-S スコアおよび CAVE-S スコア
た、PSE 患者が直面する生活上の困難を軽減するた
の活用をさらに促進し、層別化されたリスク評価に基
め、社会復帰支援制度および障害者認定制度の見直し
づく一次予防治療を確立するための研究開発を推進す
を行うことが不可欠である。具体的には、患者とその
る必要がある。また、二次予防の最適化や診断の適正
周囲のスタッフが職場で発作に対処できる環境を整備
化を開発するための研究支援も重要となる。また、て
することによる、就労支援の強化が必要である。さら
んかん原性マーカーの特定や、PSE 診断スキームお
には、経済的負担を軽減するため、医療費助成や介護
よび診断基準の開発を進めるために、生体試料・症状・
保険の適用範囲拡大を含む支援制度の充実を図るべき
脳波・画像を包括した PSE レジストリの構築とレジ
である。
ストリを用いた国内外共同研究の推進が重要である。
2.
脳卒中後てんかんの診療、均てん化
PSE に関する認知度を高めるため、脳卒中学会、
神経学会、てんかん学会などの関連学会が連携し、知
識の普及と診療体制の均てん化を図ることが望まし
3.脳卒中後てんかんの現状、課題、政策提言
14
3.
脳卒中後てんかんの支援体制