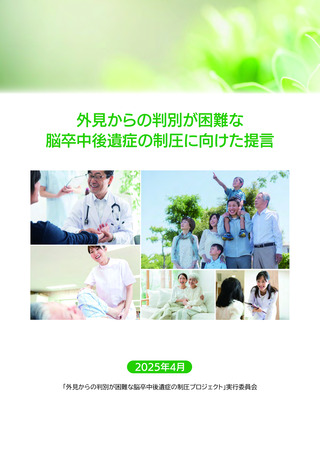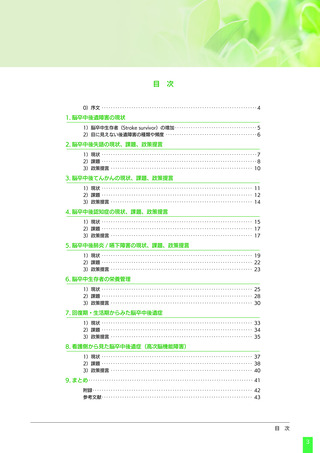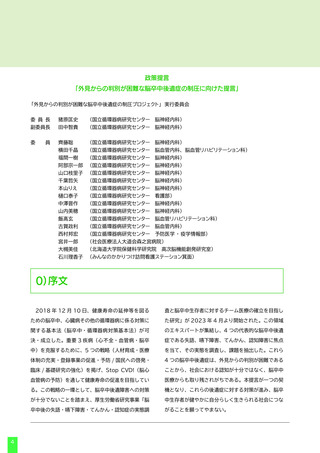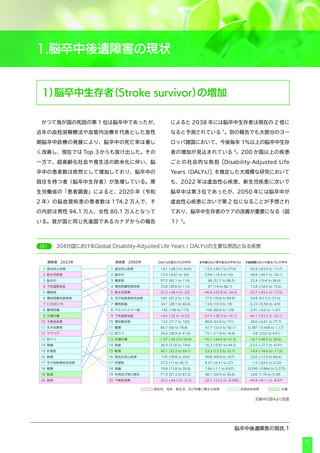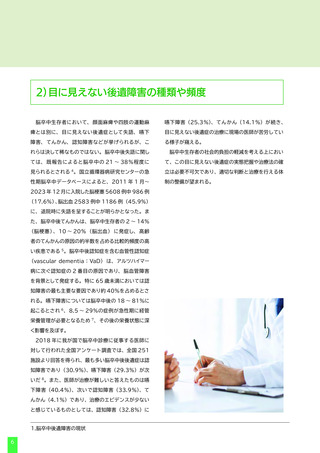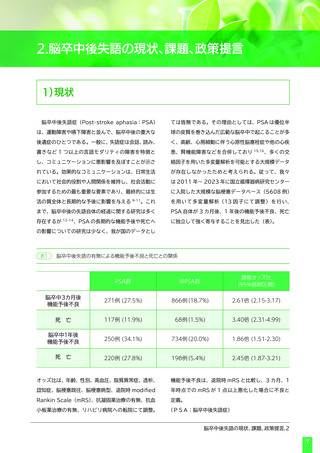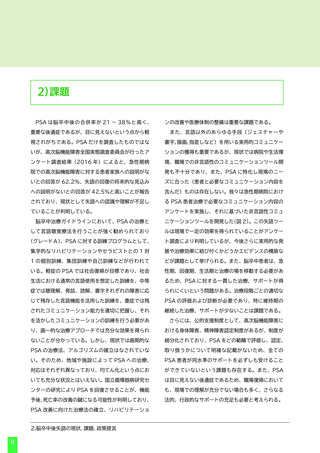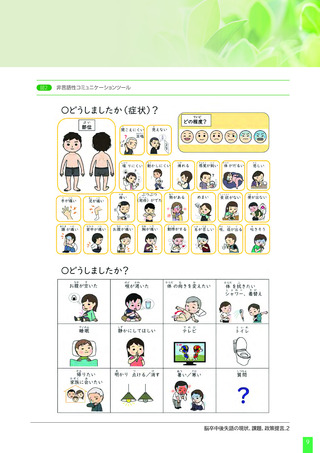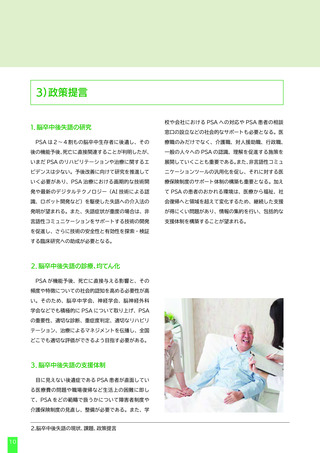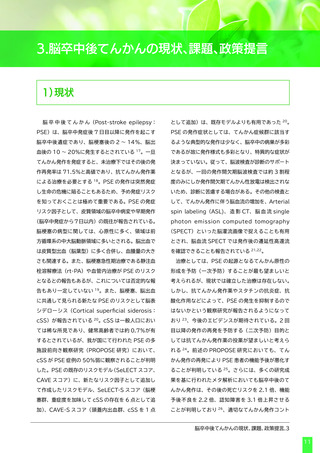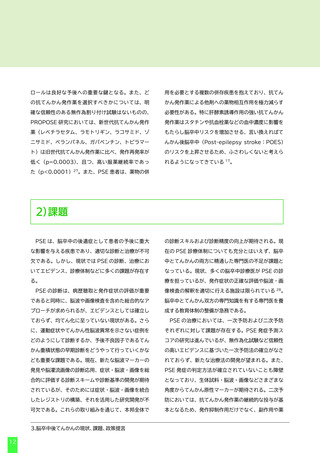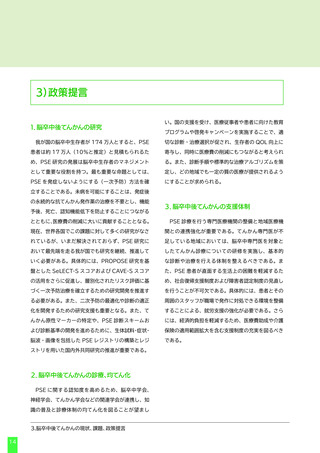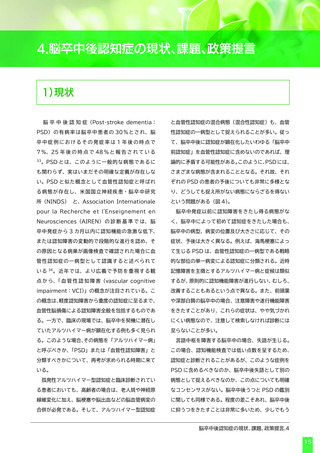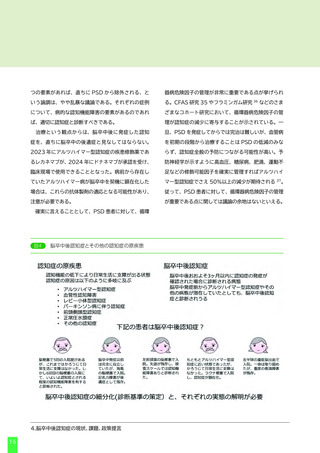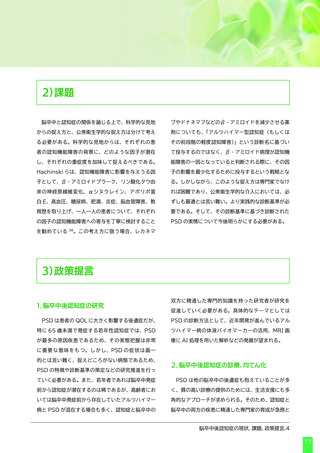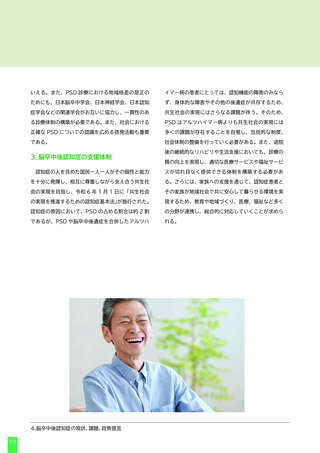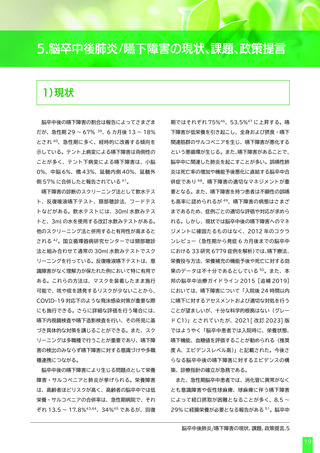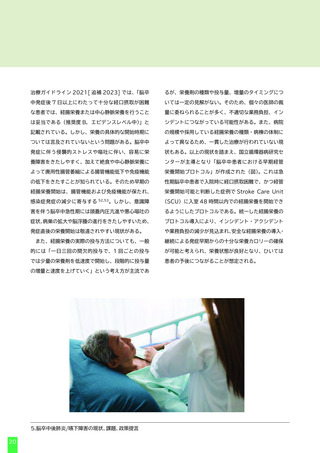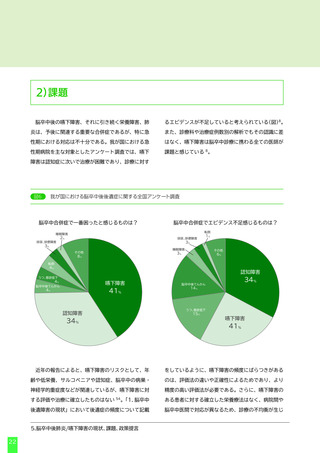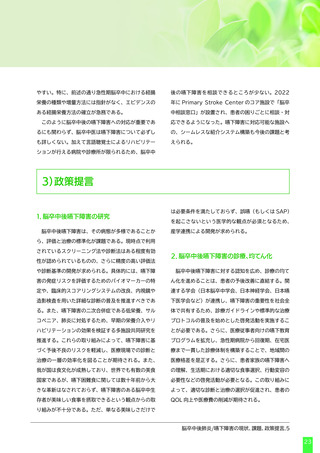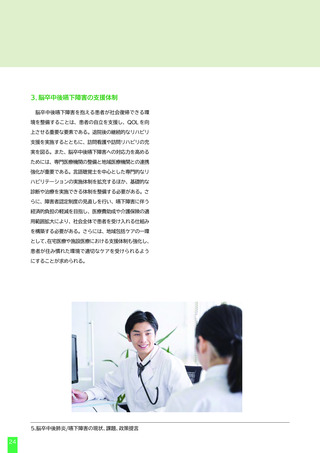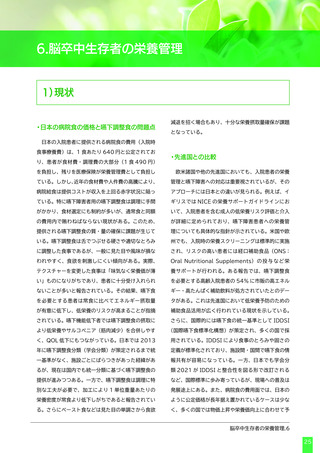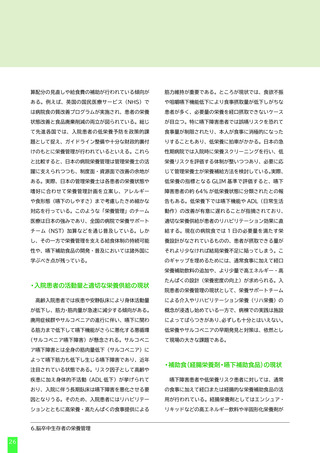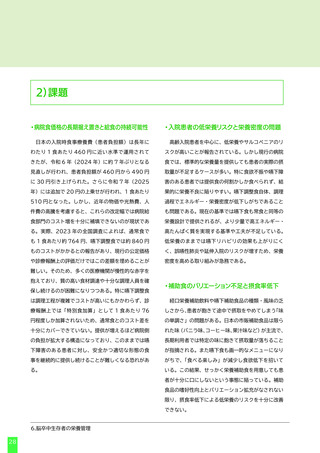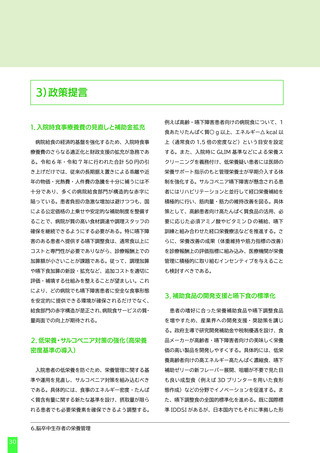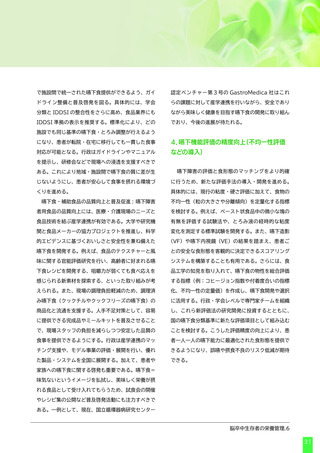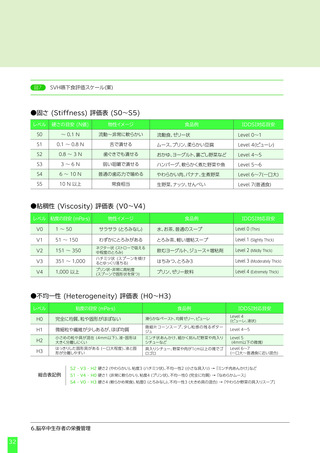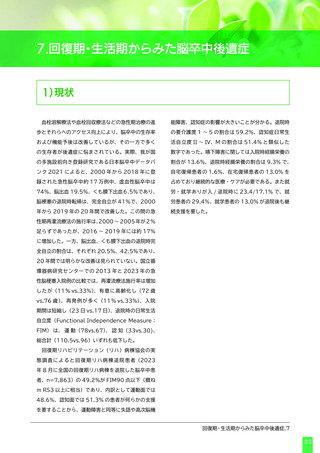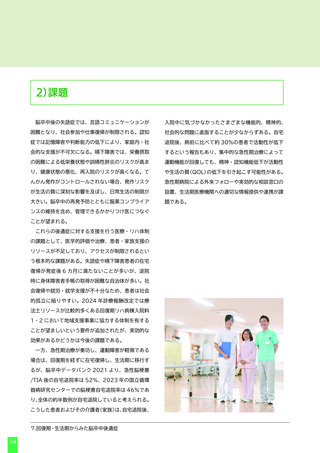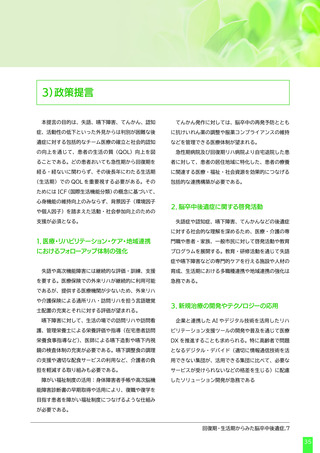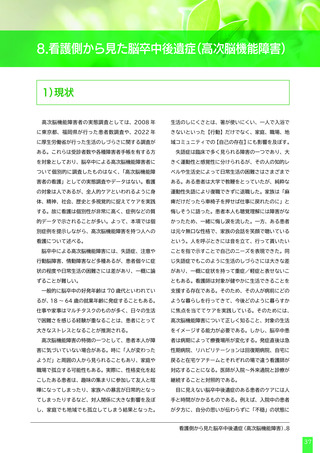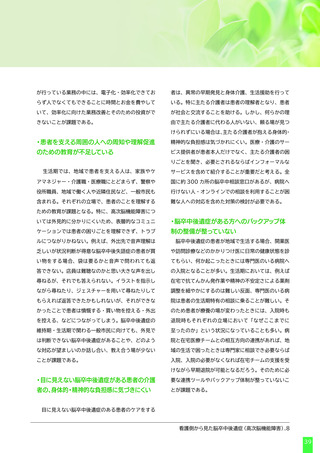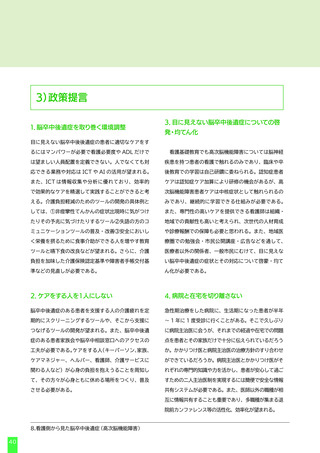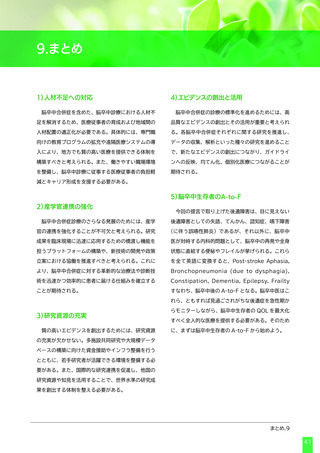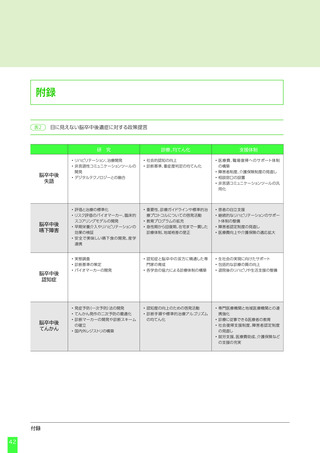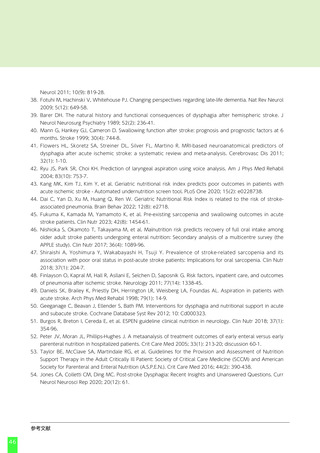よむ、つかう、まなぶ。
外見からの判別が困難な脳卒中後遺症の制圧に向けた提言 (17 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.ncvc.go.jp/hospital/wp-content/uploads/sites/2/20250707_neurology_seisakuteigen.pdf |
| 出典情報 | 「外見からの判別が困難な脳卒中後遺症の制圧に向けた提言」発表(7/7)《国立循環器病研究センター》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
2)課題
脳卒中と認知症の関係を論じる上で、科学的な見地
ブやドナネマブなどのβ - アミロイドを減少させる薬
からの捉え方と、公衆衛生学的な捉え方は分けて考え
剤についても、
「アルツハイマー型認知症(もしくは
る必要がある。科学的な見地からは、それぞれの患
その前段階の軽度認知障害)
」という診断名に基づい
者の認知機能障害の背景に、どのような因子が潜在
て投与するのではなく、β - アミロイド病理が認知機
し、それぞれの重症度を加味して捉えるべきである。
能障害の一因となっていると判断される際に、その因
Hachinski らは、認知機能障害に影響を与えうる因
子の影響を最少化するために投与するという戦略とな
子として、β - アミロイドプラーク、リン酸化タウ由
る。しかしながら、このような捉え方は専門家でなけ
来の神経原線維変化、αシヌクレイン、アポリポ蛋
れば困難であり、公衆衛生学的な介入においては、必
白 E、高血圧、糖尿病、肥満、炎症、脳血管障害、教
ずしも最適とは言い難い。より実践的な診断基準が必
育歴を取り上げ、一人一人の患者について、それぞれ
要である。そして、その診断基準に基づき診断された
の因子の認知機能障害への寄与を丁寧に検討すること
PSD の実情について今後明らかにする必要がある。
を勧めている 38。この考え方に倣う場合、レカネマ
3)政策提言
1.
脳卒中後認知症の研究
双方に精通した専門的知識を持った研究者が研究を
促進していく必要がある。具体的なテーマとしては
PSD は患者の QOL に大きく影響する後遺症だが、
PSD の診断方法として、近年開発が進んでいるアル
特に 65 歳未満で発症する若年性認知症では、PSD
ツハイマー病の体液バイオマーカーの活用、MRI 画
が最多の原因疾患であるため、その実態把握は非常
像に AI 処理を用いた解析などの発展が望まれる。
に重要な意味をもつ。しかし、PSD の症状は画一
的とは言い難く、捉えどころがない病態であるため、
PSD の特徴や診断基準の策定などの研究推進を行っ
2.
脳卒中後認知症の診療、
均てん化
ていく必要がある。また、若年者であれば脳卒中発症
PSD は他の脳卒中の後遺症も抱えていることが多
前から認知症が潜在するのは稀であるが、高齢者にお
く、質の高い診療の提供のためには、生活支援にも多
いては脳卒中発症前から存在していたアルツハイマー
角的なアプローチが求められる。そのため、認知症と
病と PSD が混在する場合も多く、認知症と脳卒中の
脳卒中の両方の疾患に精通した専門家の育成が急務と
脳卒中後認知症の現状、課題、政策提言.4
17
脳卒中と認知症の関係を論じる上で、科学的な見地
ブやドナネマブなどのβ - アミロイドを減少させる薬
からの捉え方と、公衆衛生学的な捉え方は分けて考え
剤についても、
「アルツハイマー型認知症(もしくは
る必要がある。科学的な見地からは、それぞれの患
その前段階の軽度認知障害)
」という診断名に基づい
者の認知機能障害の背景に、どのような因子が潜在
て投与するのではなく、β - アミロイド病理が認知機
し、それぞれの重症度を加味して捉えるべきである。
能障害の一因となっていると判断される際に、その因
Hachinski らは、認知機能障害に影響を与えうる因
子の影響を最少化するために投与するという戦略とな
子として、β - アミロイドプラーク、リン酸化タウ由
る。しかしながら、このような捉え方は専門家でなけ
来の神経原線維変化、αシヌクレイン、アポリポ蛋
れば困難であり、公衆衛生学的な介入においては、必
白 E、高血圧、糖尿病、肥満、炎症、脳血管障害、教
ずしも最適とは言い難い。より実践的な診断基準が必
育歴を取り上げ、一人一人の患者について、それぞれ
要である。そして、その診断基準に基づき診断された
の因子の認知機能障害への寄与を丁寧に検討すること
PSD の実情について今後明らかにする必要がある。
を勧めている 38。この考え方に倣う場合、レカネマ
3)政策提言
1.
脳卒中後認知症の研究
双方に精通した専門的知識を持った研究者が研究を
促進していく必要がある。具体的なテーマとしては
PSD は患者の QOL に大きく影響する後遺症だが、
PSD の診断方法として、近年開発が進んでいるアル
特に 65 歳未満で発症する若年性認知症では、PSD
ツハイマー病の体液バイオマーカーの活用、MRI 画
が最多の原因疾患であるため、その実態把握は非常
像に AI 処理を用いた解析などの発展が望まれる。
に重要な意味をもつ。しかし、PSD の症状は画一
的とは言い難く、捉えどころがない病態であるため、
PSD の特徴や診断基準の策定などの研究推進を行っ
2.
脳卒中後認知症の診療、
均てん化
ていく必要がある。また、若年者であれば脳卒中発症
PSD は他の脳卒中の後遺症も抱えていることが多
前から認知症が潜在するのは稀であるが、高齢者にお
く、質の高い診療の提供のためには、生活支援にも多
いては脳卒中発症前から存在していたアルツハイマー
角的なアプローチが求められる。そのため、認知症と
病と PSD が混在する場合も多く、認知症と脳卒中の
脳卒中の両方の疾患に精通した専門家の育成が急務と
脳卒中後認知症の現状、課題、政策提言.4
17