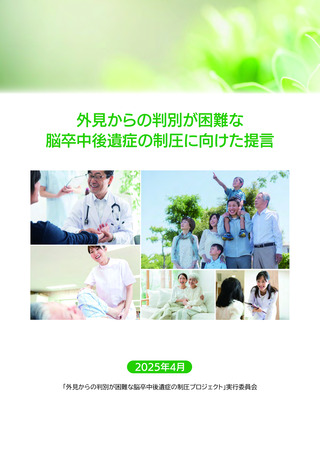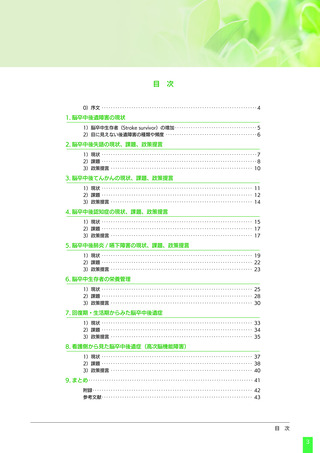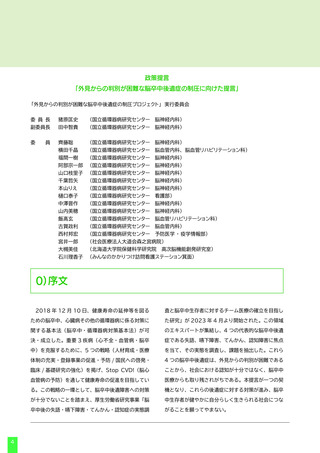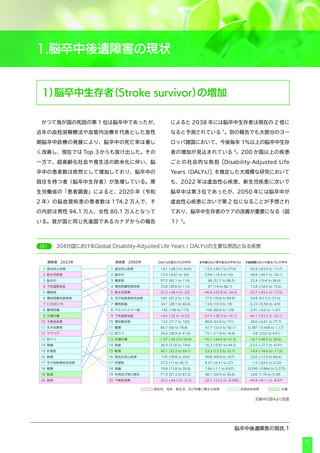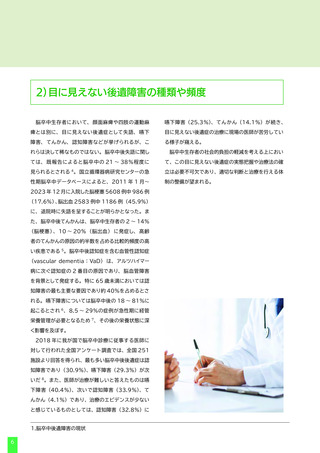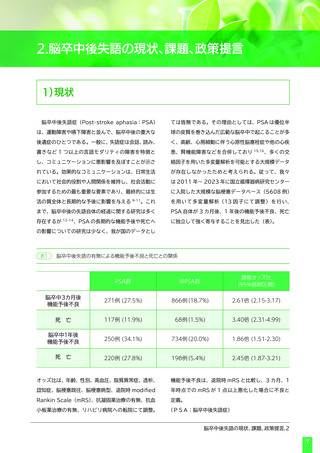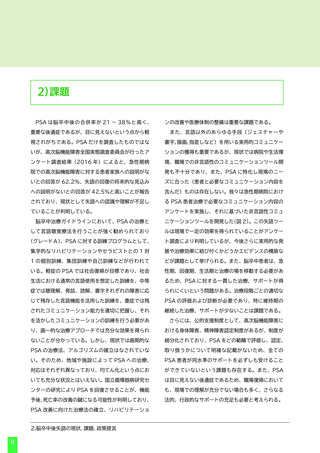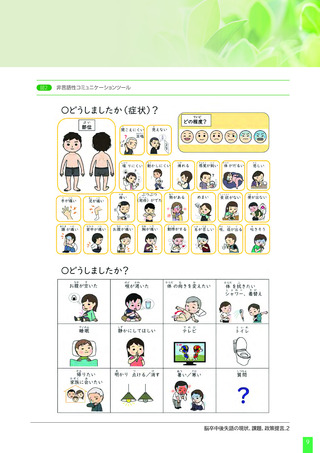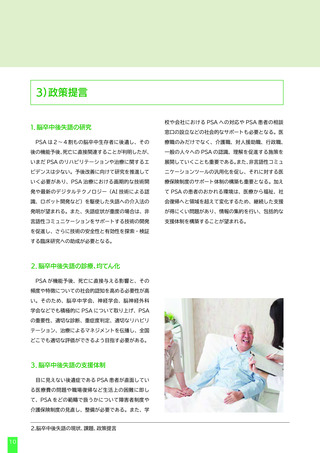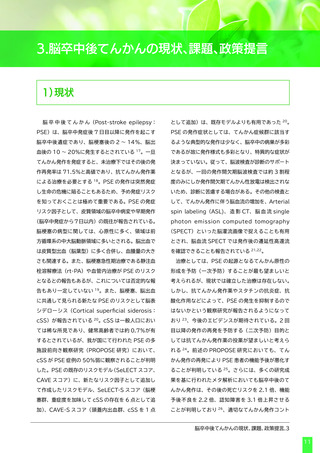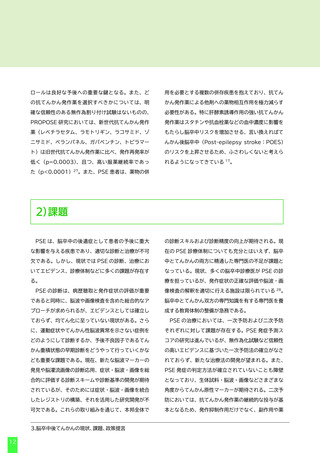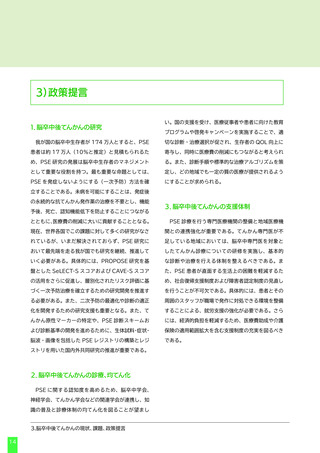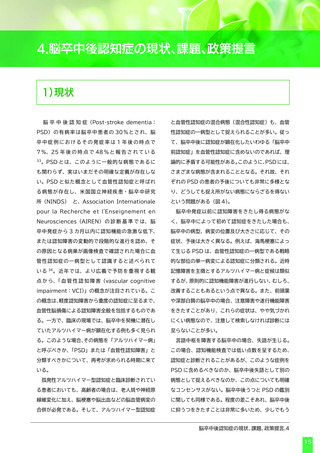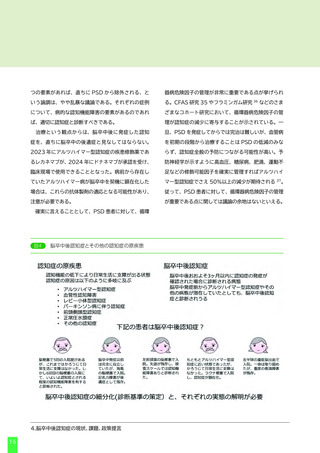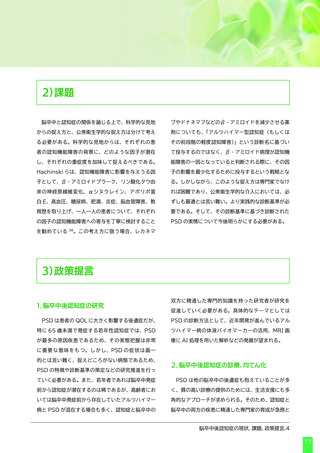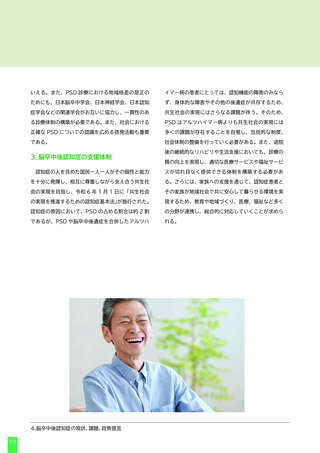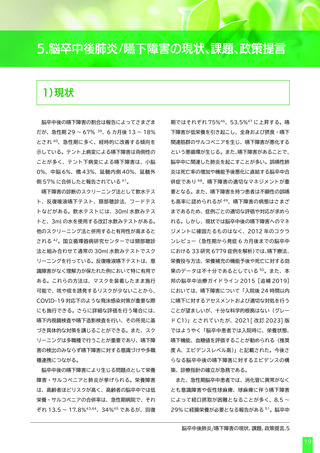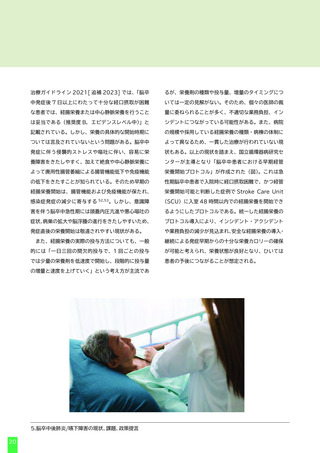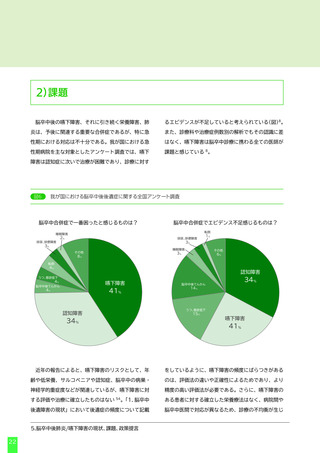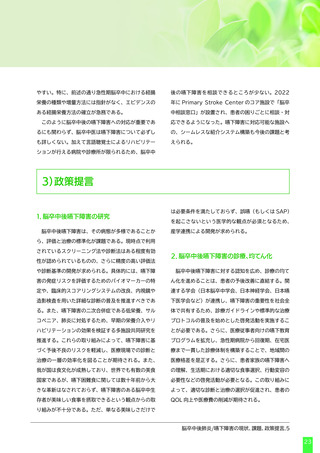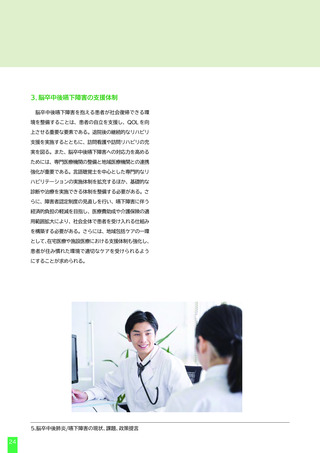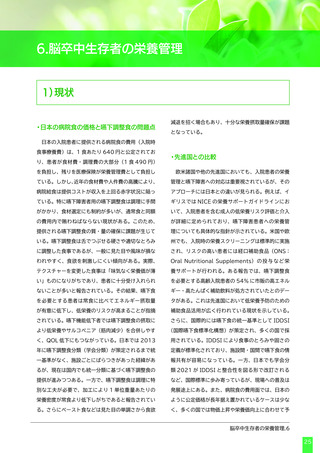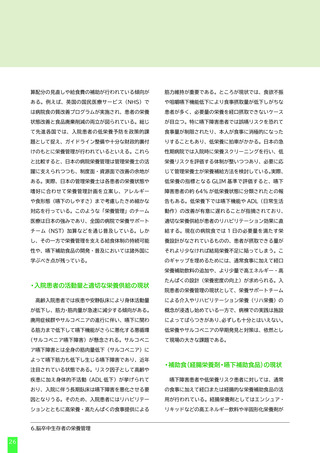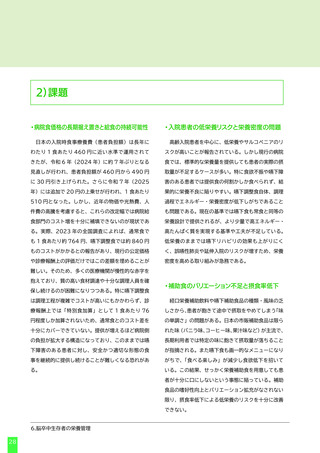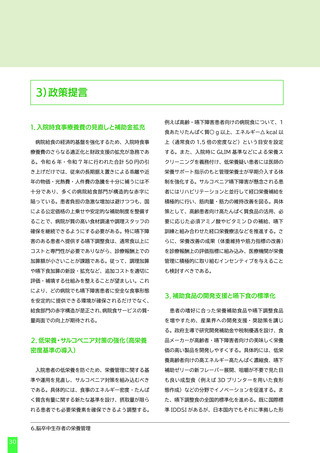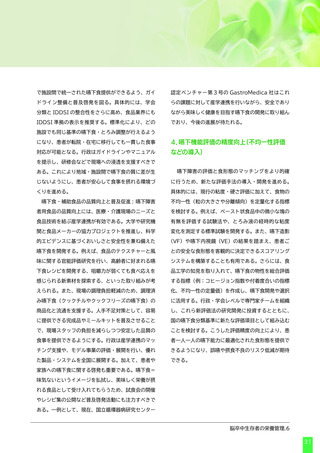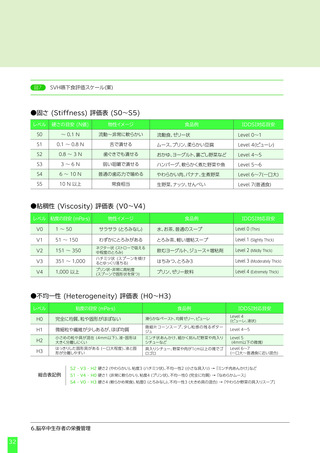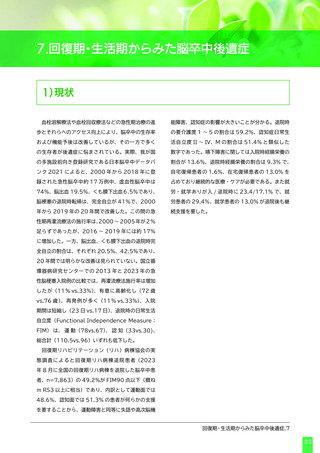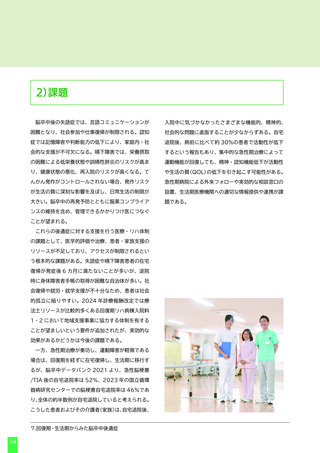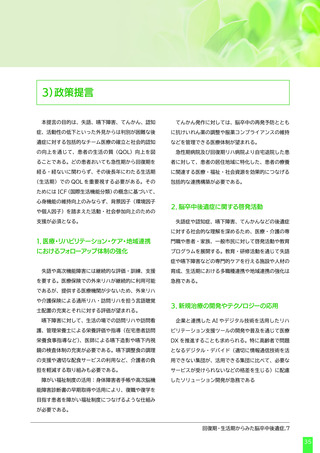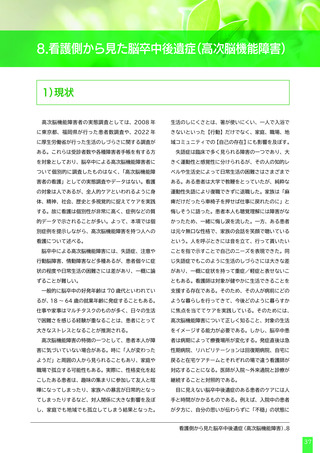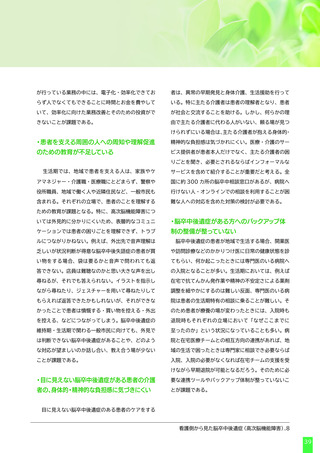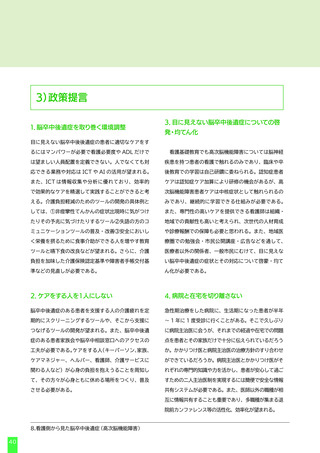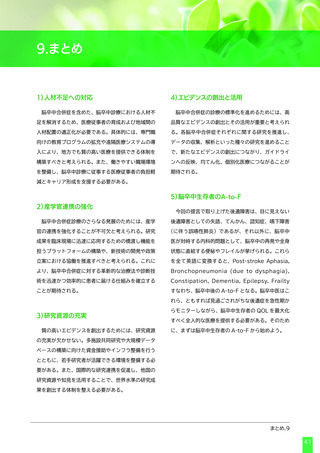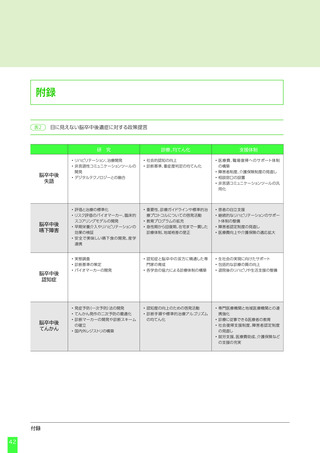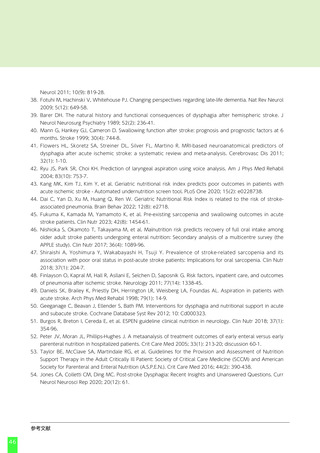よむ、つかう、まなぶ。
外見からの判別が困難な脳卒中後遺症の制圧に向けた提言 (12 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.ncvc.go.jp/hospital/wp-content/uploads/sites/2/20250707_neurology_seisakuteigen.pdf |
| 出典情報 | 「外見からの判別が困難な脳卒中後遺症の制圧に向けた提言」発表(7/7)《国立循環器病研究センター》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
ロールは良好な予後への重要な鍵となる。また、ど
用を必要とする複数の併存疾患を抱えており、抗てん
の抗てんかん発作薬を選択すべきかについては、明
かん発作薬による他剤への薬物相互作用を極力減らす
確な信頼性のある無作為割り付け試験はないものの、
必要性がある。特に肝酵素誘導作用の強い抗てんかん
PROPOSE 研究においては、新世代抗てんかん発作
発作薬はスタチンや抗血栓薬などの血中濃度に影響を
薬(レベチラセタム、ラモトリギン、ラコサミド、ゾ
もたらし脳卒中リスクを増加させる、言い換えればて
ニサミド、ペランパネル、ガバペンチン、トピラマー
んかん後脳卒中(Post-epilepsy stroke:POES)
ト)は旧世代抗てんかん発作薬に比べ、発作再発率が
のリスクを上昇させるため、ふさわしくないと考えら
低く(p=0.0003)
、且つ、高い服薬継続率であっ
れるようになってきている 17。
た(p<0.0001)27。また、PSE 患者は、薬物の併
2)課題
PSE は、脳卒中の後遺症として患者の予後に重大
の診断スキルおよび診断精度の向上が期待される。現
な影響を与える疾患であり、適切な診断と治療が不可
在の PSE 診療体制についても充分とはいえず、脳卒
欠である。しかし、現状では PSE の診断、治療にお
中とてんかんの両方に精通した専門医の不足が課題と
いてエビデンス、診療体制などに多くの課題が存在す
なっている。現状、多くの脳卒中診療医が PSE の診
る。
療を担っているが、発作症状の正確な評価や脳波・画
PSE の診断は、病歴聴取と発作症状の評価が重要
像検査の解釈を適切に行える施設は限られている 28。
であると同時に、脳波や画像検査を含めた総合的なア
脳卒中とてんかん双方の専門知識を有する専門医を養
プローチが求められるが、エビデンスとしては確立し
成する教育体制の整備が急務である。
ておらず、均てん化に至っていない現状がある。さら
PSE の治療においては、一次予防および二次予防
に、運動症状やてんかん性脳波異常を示さない症例を
それぞれに対して課題が存在する。PSE 発症予測ス
どのようにして診断するか、予後不良因子であるてん
コアの研究は進んでいるが、無作為化試験など信頼性
かん重積状態の早期診断をどうやって行っていくかな
の高いエビデンスに基づいた一次予防法の確立がなさ
ども重要な課題である。現在、新たな脳波マーカーの
れておらず、新たな治療法の開発が望まれる。また、
発見や脳灌流画像の診断応用、症状・脳波・画像を総
PSE 発症の判定方法が確立されていないことも障壁
合的に評価する診断スキームや診断基準の開発が期待
となっており、生体試料・脳波・画像などさまざまな
されているが、そのためには症状・脳波・画像を統合
角度からてんかん原性マーカーが期待される。二次予
したレジストリの構築、それを活用した研究開発が不
防においては、抗てんかん発作薬の継続的な投与が基
可欠である。これらの取り組みを通じて、本邦全体で
本となるため、発作抑制作用だけでなく、副作用や薬
3.脳卒中後てんかんの現状、課題、政策提言
12
用を必要とする複数の併存疾患を抱えており、抗てん
の抗てんかん発作薬を選択すべきかについては、明
かん発作薬による他剤への薬物相互作用を極力減らす
確な信頼性のある無作為割り付け試験はないものの、
必要性がある。特に肝酵素誘導作用の強い抗てんかん
PROPOSE 研究においては、新世代抗てんかん発作
発作薬はスタチンや抗血栓薬などの血中濃度に影響を
薬(レベチラセタム、ラモトリギン、ラコサミド、ゾ
もたらし脳卒中リスクを増加させる、言い換えればて
ニサミド、ペランパネル、ガバペンチン、トピラマー
んかん後脳卒中(Post-epilepsy stroke:POES)
ト)は旧世代抗てんかん発作薬に比べ、発作再発率が
のリスクを上昇させるため、ふさわしくないと考えら
低く(p=0.0003)
、且つ、高い服薬継続率であっ
れるようになってきている 17。
た(p<0.0001)27。また、PSE 患者は、薬物の併
2)課題
PSE は、脳卒中の後遺症として患者の予後に重大
の診断スキルおよび診断精度の向上が期待される。現
な影響を与える疾患であり、適切な診断と治療が不可
在の PSE 診療体制についても充分とはいえず、脳卒
欠である。しかし、現状では PSE の診断、治療にお
中とてんかんの両方に精通した専門医の不足が課題と
いてエビデンス、診療体制などに多くの課題が存在す
なっている。現状、多くの脳卒中診療医が PSE の診
る。
療を担っているが、発作症状の正確な評価や脳波・画
PSE の診断は、病歴聴取と発作症状の評価が重要
像検査の解釈を適切に行える施設は限られている 28。
であると同時に、脳波や画像検査を含めた総合的なア
脳卒中とてんかん双方の専門知識を有する専門医を養
プローチが求められるが、エビデンスとしては確立し
成する教育体制の整備が急務である。
ておらず、均てん化に至っていない現状がある。さら
PSE の治療においては、一次予防および二次予防
に、運動症状やてんかん性脳波異常を示さない症例を
それぞれに対して課題が存在する。PSE 発症予測ス
どのようにして診断するか、予後不良因子であるてん
コアの研究は進んでいるが、無作為化試験など信頼性
かん重積状態の早期診断をどうやって行っていくかな
の高いエビデンスに基づいた一次予防法の確立がなさ
ども重要な課題である。現在、新たな脳波マーカーの
れておらず、新たな治療法の開発が望まれる。また、
発見や脳灌流画像の診断応用、症状・脳波・画像を総
PSE 発症の判定方法が確立されていないことも障壁
合的に評価する診断スキームや診断基準の開発が期待
となっており、生体試料・脳波・画像などさまざまな
されているが、そのためには症状・脳波・画像を統合
角度からてんかん原性マーカーが期待される。二次予
したレジストリの構築、それを活用した研究開発が不
防においては、抗てんかん発作薬の継続的な投与が基
可欠である。これらの取り組みを通じて、本邦全体で
本となるため、発作抑制作用だけでなく、副作用や薬
3.脳卒中後てんかんの現状、課題、政策提言
12