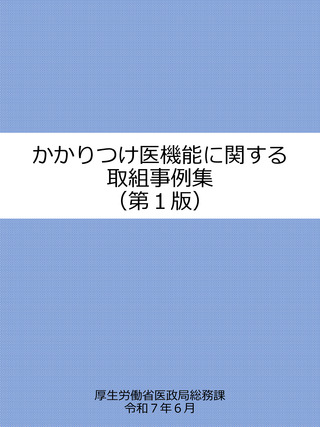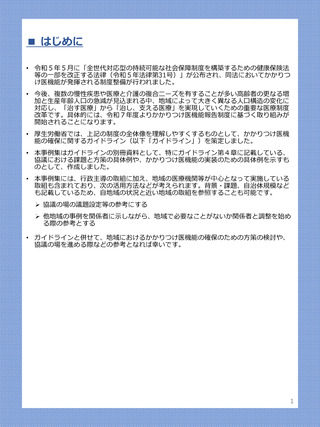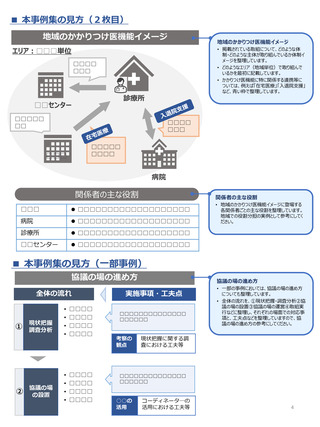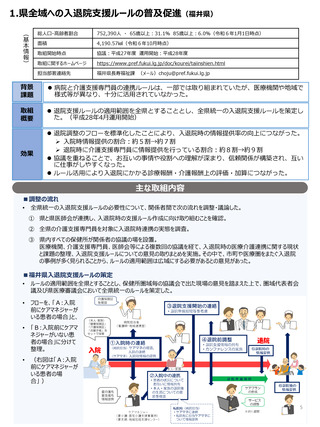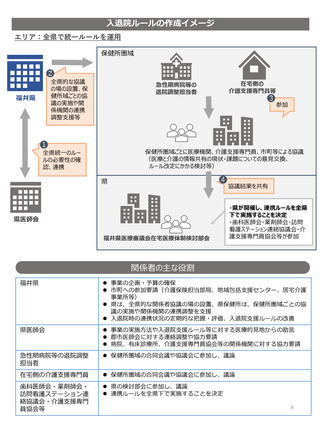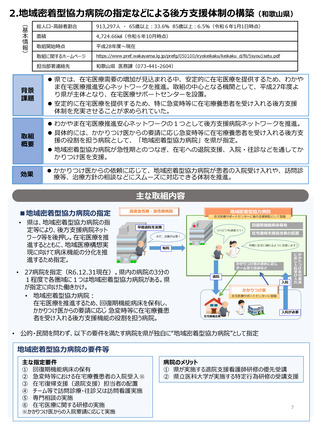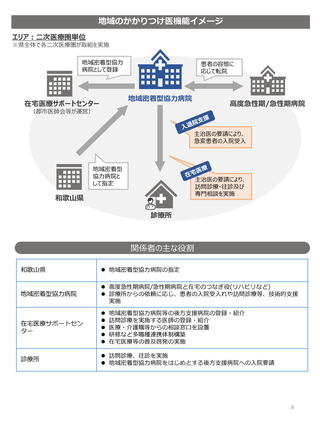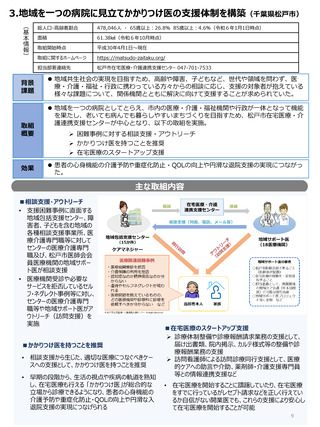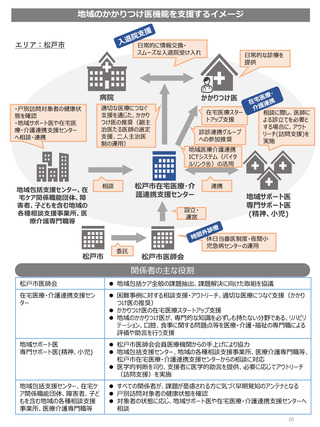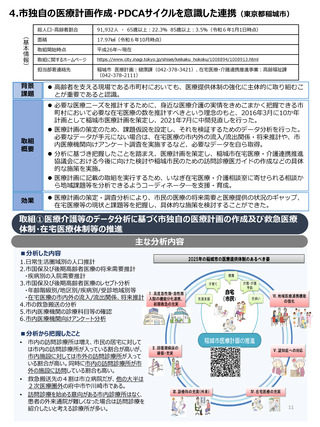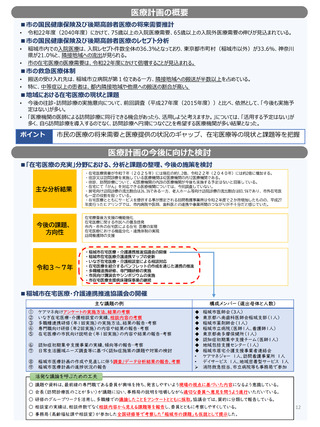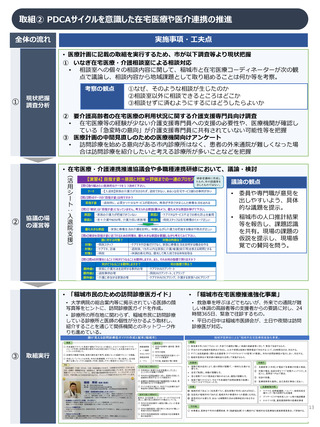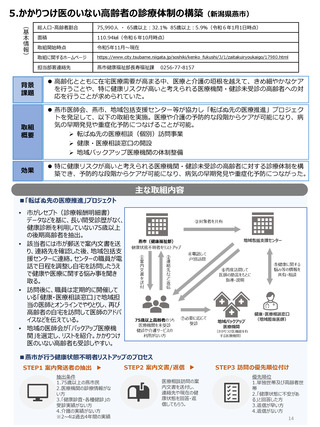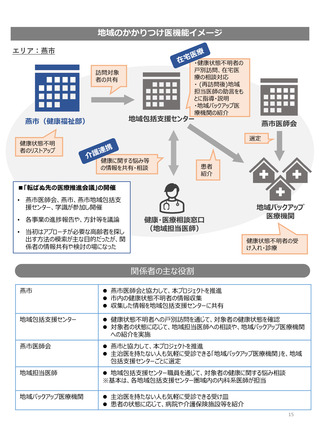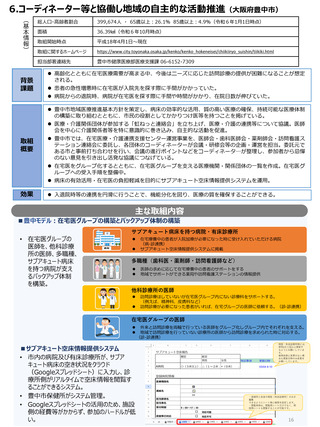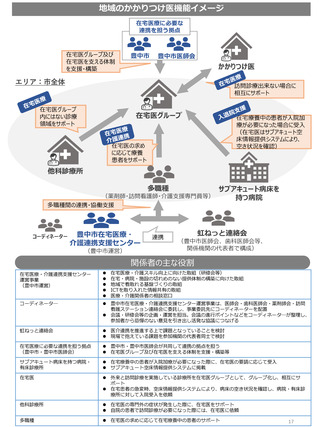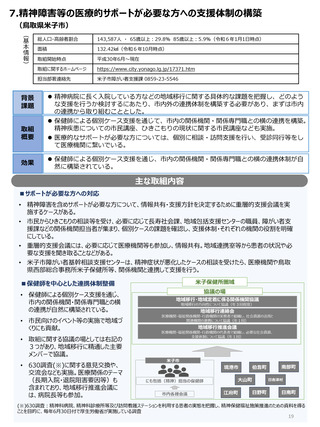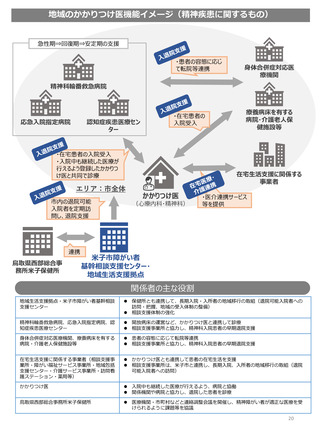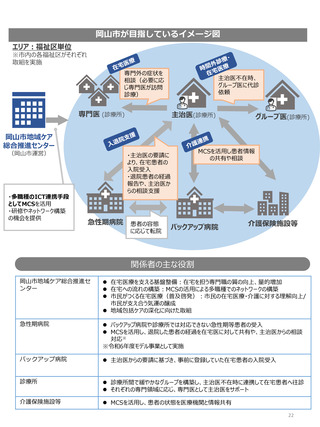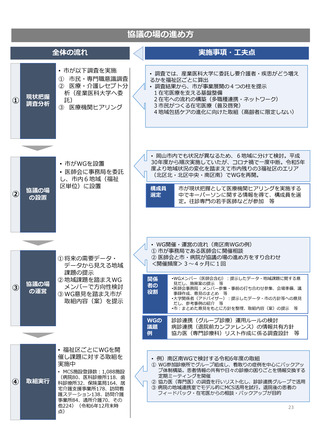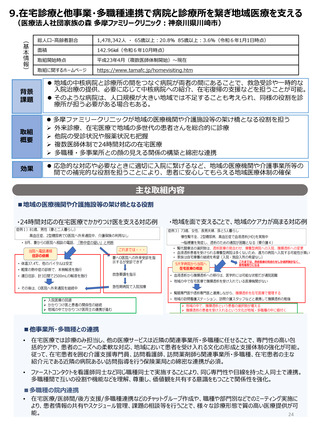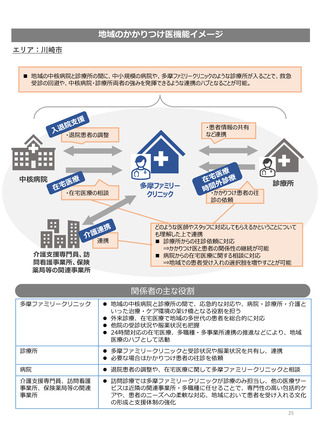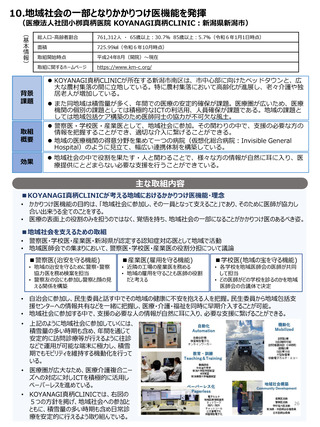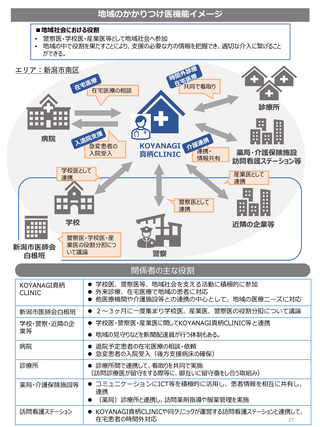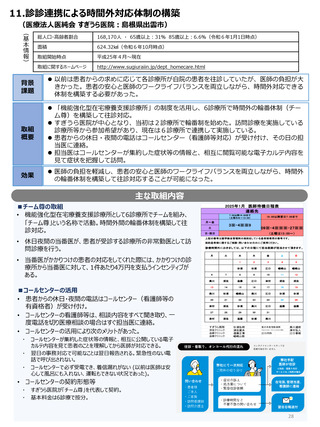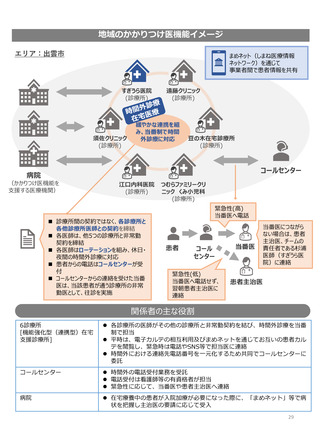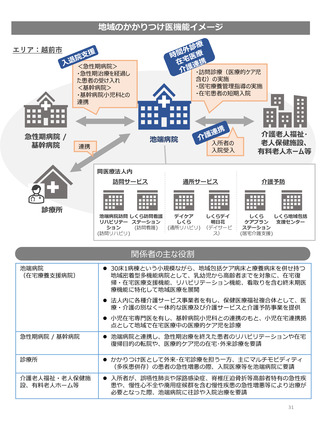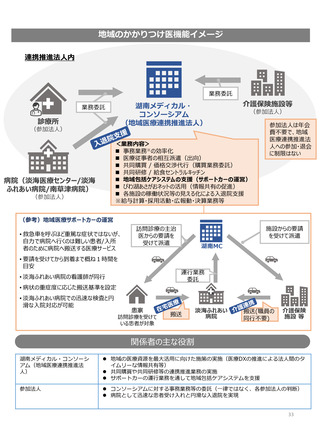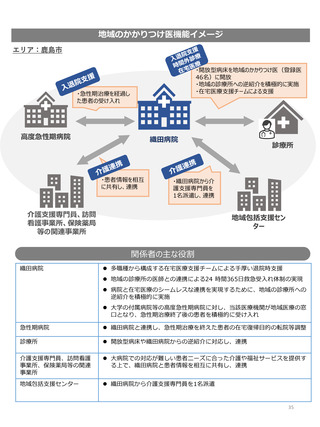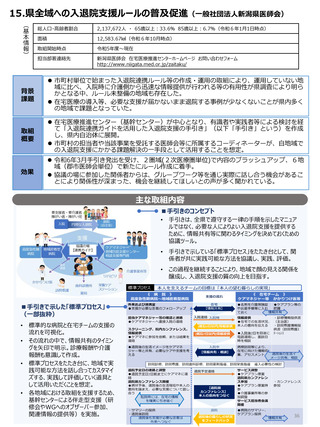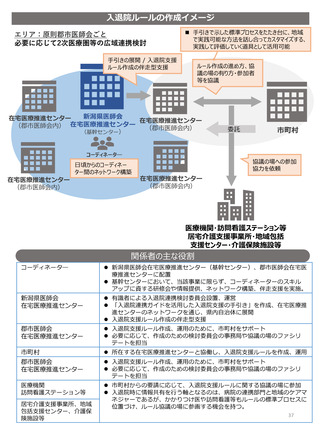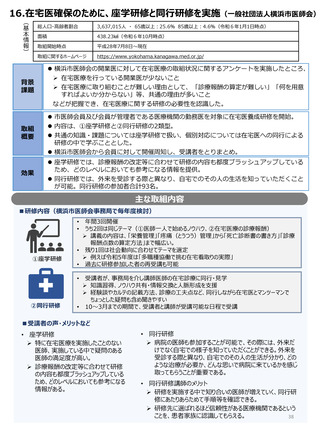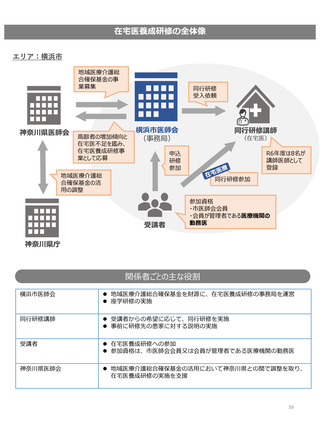よむ、つかう、まなぶ。
かかりつけ医機能に関する取組事例集(第1版)(令和7年6月) (24 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00007.html |
| 出典情報 | かかりつけ医機能の確保に関するガイドラインについて (6/27)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
協議の場の進め方
全体の流れ
現状把握
① 調査分析
②
③
協議の場
の設置
協議の場
の運営
• 市が以下調査を実施
① 市民・専門職意識調査
② 医療・介護レセプト分
析(産業医科大学へ委
託)
③ 医療機関ヒアリング
• 市がWGを設置
• 医師会に事務局を委託
し、市内6地域(福祉
区単位)に設置
① 将来の需要データ・
データから見える地域
課題の提示
② 地域課題を踏まえWG
メンバーで方向性検討
③ WG意見を踏まえ市が
取組内容(案)を提示
• 福祉区ごとにWGを開
催し課題に対する取組を
実施中
④
取組実行
• MCS施設登録数:1,088施設
(病院80、医科診療所118、歯
科診療所32、保険薬局164、居
宅介護支援事業所178、訪問看
護ステーション138、訪問介護
事業所84、通所介護70、その
他224)(令和6年12月末時
点)
実施事項・工夫点
• 調査では、産業医科大学に委託し要介護者・疾患がどう増え
るかを福祉区ごとに算出
• 調査結果から、市が事業展開の4つの柱を提示
1在宅医療を支える基盤整備
2在宅への流れの構築(多職種連携・ネットワーク)
3市民がつくる在宅医療(普及啓発)
4地域包括ケアの進化に向けた取組(高齢者に限定しない)
• 岡山市内でも状況が異なるため、6地域に分けて検討。平成
30年度から順次実施していたが、コロナ禍で一度中断。令和5年
度より地域状況の変化を踏まえて市内残りの3福祉区のエリア
(北区北・北区中央・南区南)でWGを再開。
構成員
選定
市が現状把握として医療機関ヒアリングを実施する
中でキーパーソンに関する情報を得て、構成員を選
定。往診専門の若手医師などが参加 等
• WG開催・運営の流れ(南区南WGの例)
① 市が事務局である医師会に開催相談
② 医師会と市・病院が協議の場の進め方をすり合わせ
<開催頻度>3~4ヶ月に1回
関係
者の
役割
•WGメンバー(医師会含む):提示したデータ・地域課題に関する意
見だし、施策案の提示 等
•医師会事務局:メンバー参集・事前の打ち合わせ参集、会場準備、議
事録作成、意見のまとめ 等
•大学関係者(アドバイザー):提示したデータ・市の方針等への意見
だし、参考事例の紹介 等
•市:まとめた意見をもとに方針を整理、取組内容(案)の提示 等
WGの
議題
例
診診連携(グループ診療)運用ルールの検討
病診連携(退院前カンファレンス)の情報共有方針
協力医(専門診療科)リスト作成に係る調査設計 等
• 例)南区南WGで検討する令和6年度の取組
① WG参加診療所でグループ組成し、看取りの症例を中心にバックアッ
プ体制構築。患者情報の共有や日々の診療の困りごとを情報交換する
定期ミーティングを開催
② 協力医(専門医)の調査を行いリスト化し、診診連携グループで活用
③ 病院の地域連携室でモデル的にMCS活用を試行。退院後の患者の
フィードバック・在宅医からの相談・バックアップが目的
23
全体の流れ
現状把握
① 調査分析
②
③
協議の場
の設置
協議の場
の運営
• 市が以下調査を実施
① 市民・専門職意識調査
② 医療・介護レセプト分
析(産業医科大学へ委
託)
③ 医療機関ヒアリング
• 市がWGを設置
• 医師会に事務局を委託
し、市内6地域(福祉
区単位)に設置
① 将来の需要データ・
データから見える地域
課題の提示
② 地域課題を踏まえWG
メンバーで方向性検討
③ WG意見を踏まえ市が
取組内容(案)を提示
• 福祉区ごとにWGを開
催し課題に対する取組を
実施中
④
取組実行
• MCS施設登録数:1,088施設
(病院80、医科診療所118、歯
科診療所32、保険薬局164、居
宅介護支援事業所178、訪問看
護ステーション138、訪問介護
事業所84、通所介護70、その
他224)(令和6年12月末時
点)
実施事項・工夫点
• 調査では、産業医科大学に委託し要介護者・疾患がどう増え
るかを福祉区ごとに算出
• 調査結果から、市が事業展開の4つの柱を提示
1在宅医療を支える基盤整備
2在宅への流れの構築(多職種連携・ネットワーク)
3市民がつくる在宅医療(普及啓発)
4地域包括ケアの進化に向けた取組(高齢者に限定しない)
• 岡山市内でも状況が異なるため、6地域に分けて検討。平成
30年度から順次実施していたが、コロナ禍で一度中断。令和5年
度より地域状況の変化を踏まえて市内残りの3福祉区のエリア
(北区北・北区中央・南区南)でWGを再開。
構成員
選定
市が現状把握として医療機関ヒアリングを実施する
中でキーパーソンに関する情報を得て、構成員を選
定。往診専門の若手医師などが参加 等
• WG開催・運営の流れ(南区南WGの例)
① 市が事務局である医師会に開催相談
② 医師会と市・病院が協議の場の進め方をすり合わせ
<開催頻度>3~4ヶ月に1回
関係
者の
役割
•WGメンバー(医師会含む):提示したデータ・地域課題に関する意
見だし、施策案の提示 等
•医師会事務局:メンバー参集・事前の打ち合わせ参集、会場準備、議
事録作成、意見のまとめ 等
•大学関係者(アドバイザー):提示したデータ・市の方針等への意見
だし、参考事例の紹介 等
•市:まとめた意見をもとに方針を整理、取組内容(案)の提示 等
WGの
議題
例
診診連携(グループ診療)運用ルールの検討
病診連携(退院前カンファレンス)の情報共有方針
協力医(専門診療科)リスト作成に係る調査設計 等
• 例)南区南WGで検討する令和6年度の取組
① WG参加診療所でグループ組成し、看取りの症例を中心にバックアッ
プ体制構築。患者情報の共有や日々の診療の困りごとを情報交換する
定期ミーティングを開催
② 協力医(専門医)の調査を行いリスト化し、診診連携グループで活用
③ 病院の地域連携室でモデル的にMCS活用を試行。退院後の患者の
フィードバック・在宅医からの相談・バックアップが目的
23