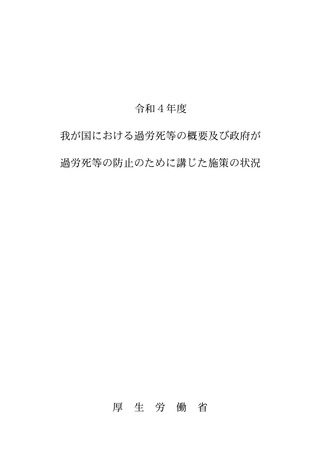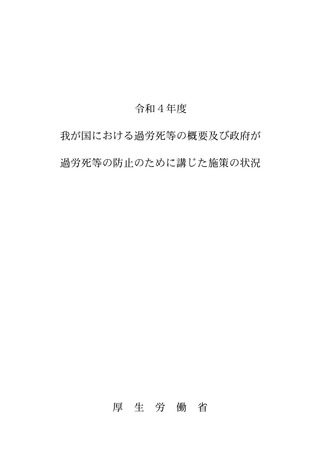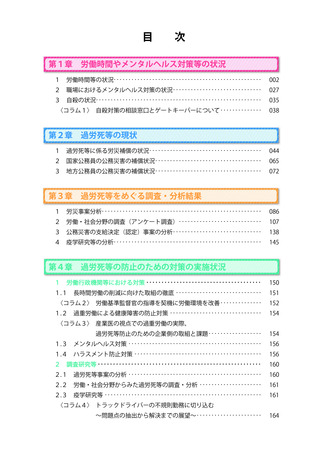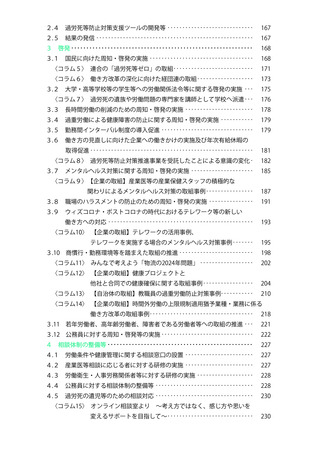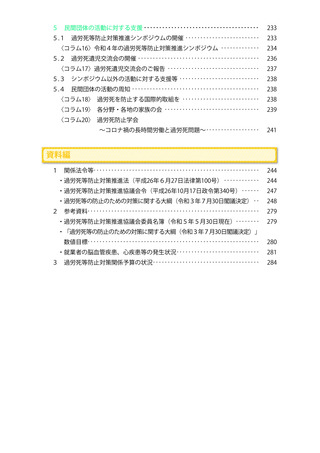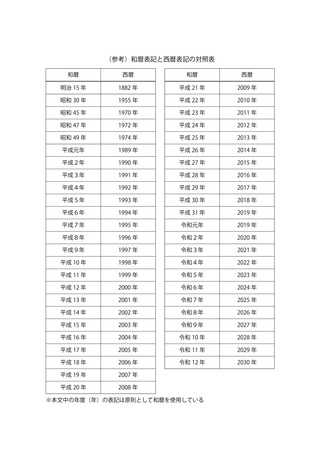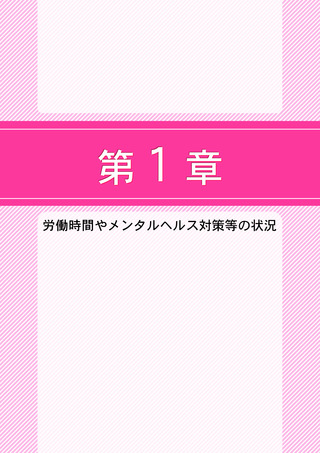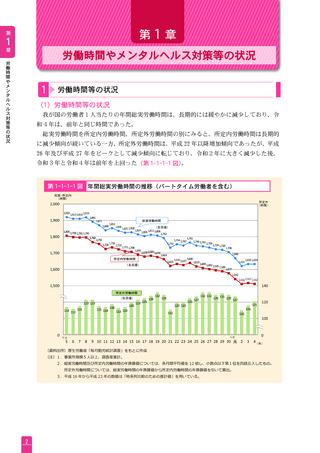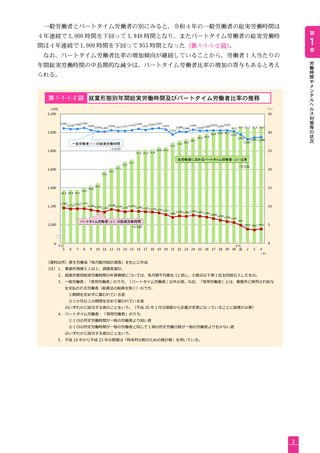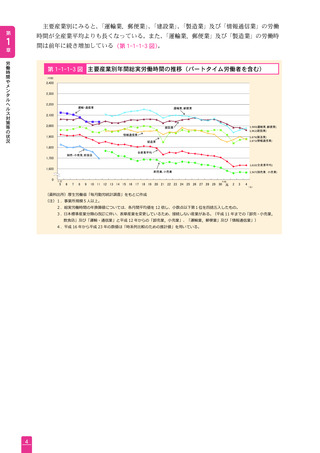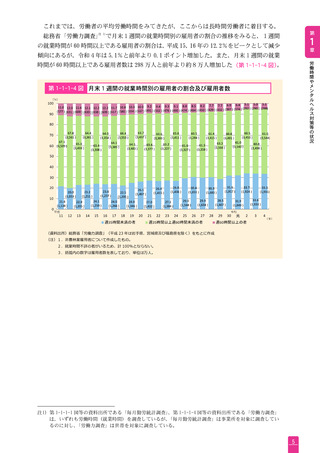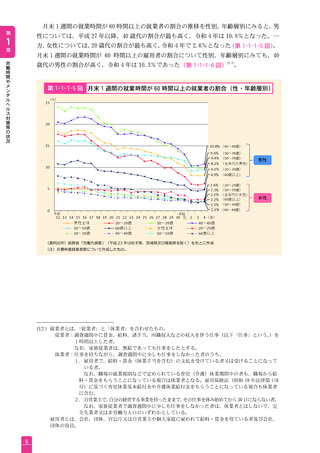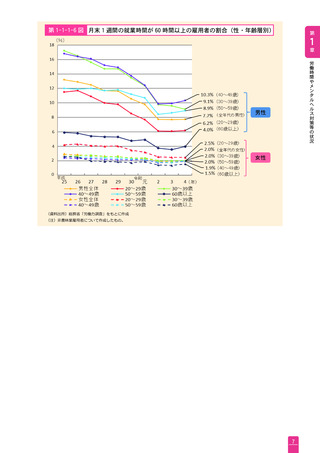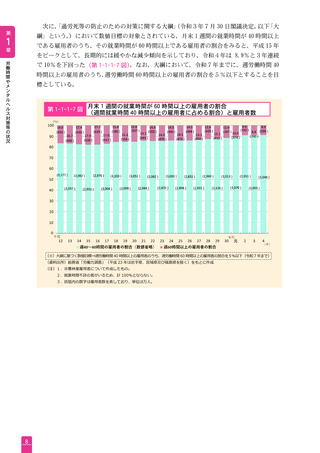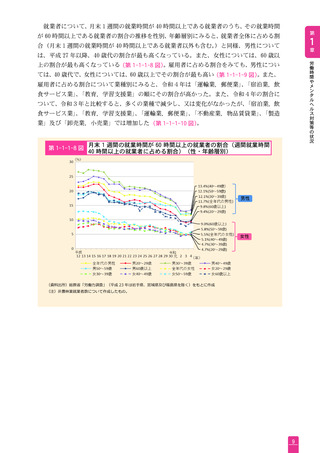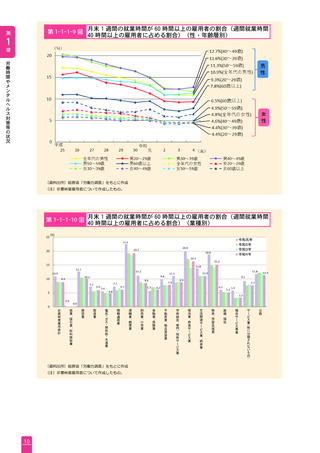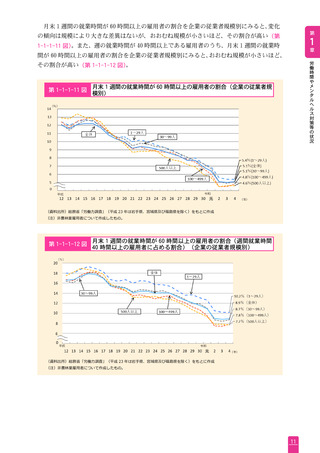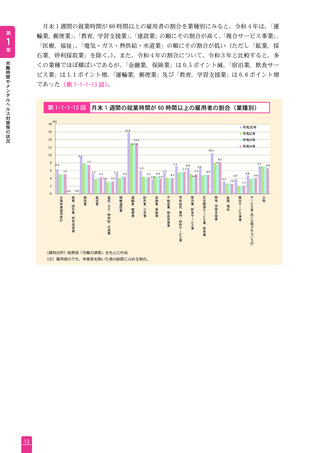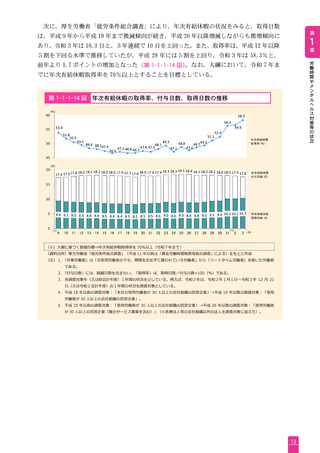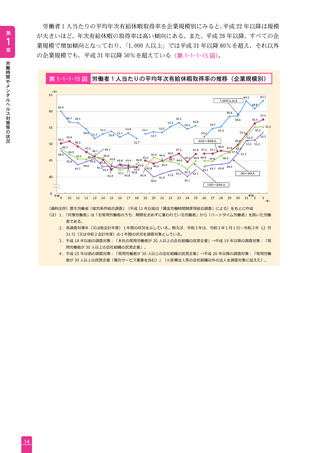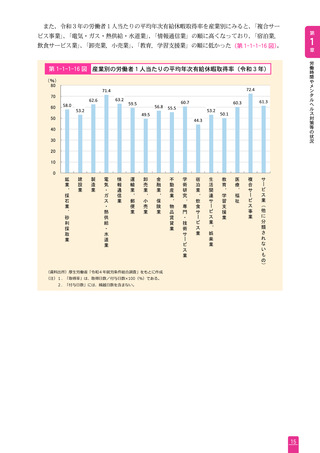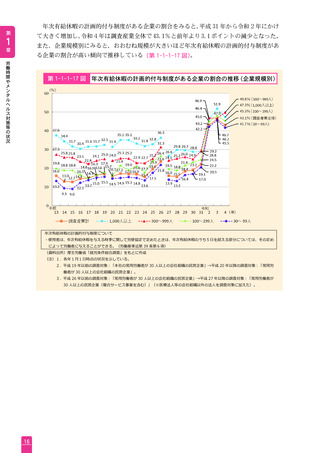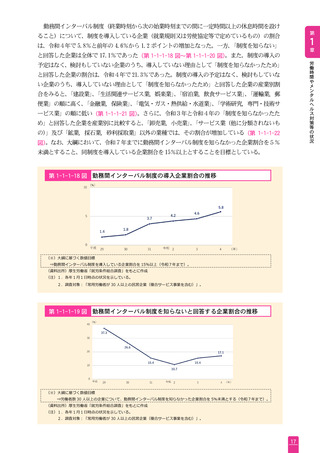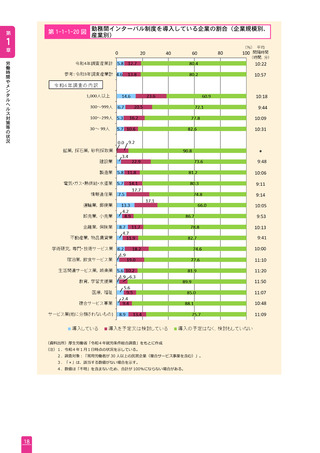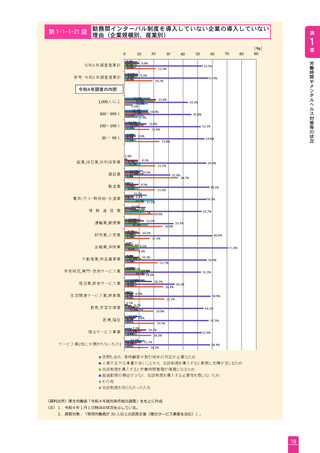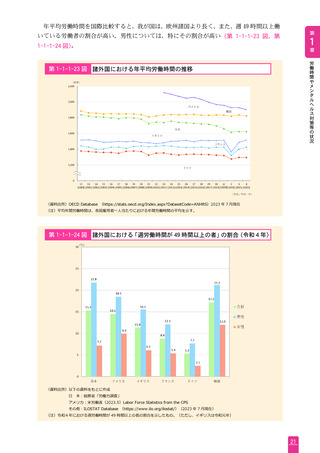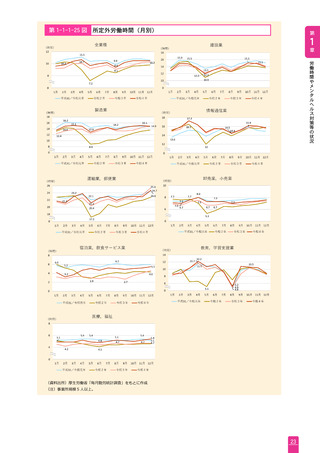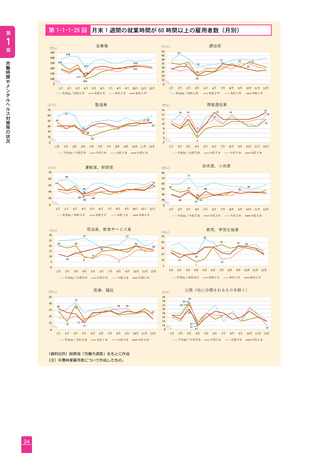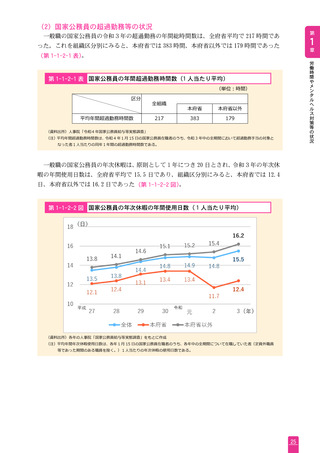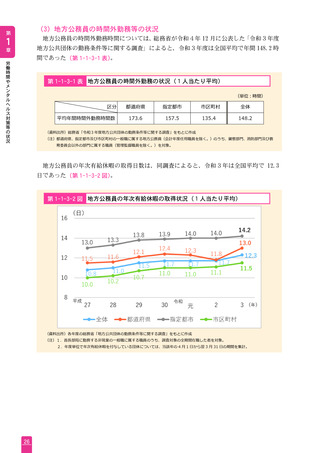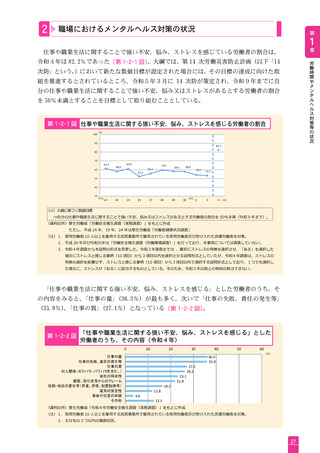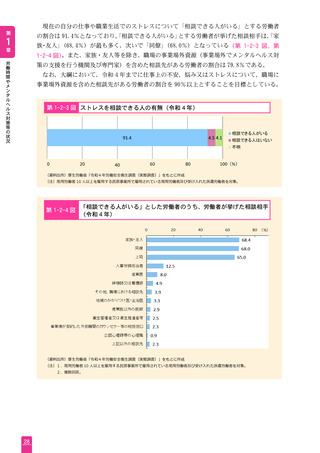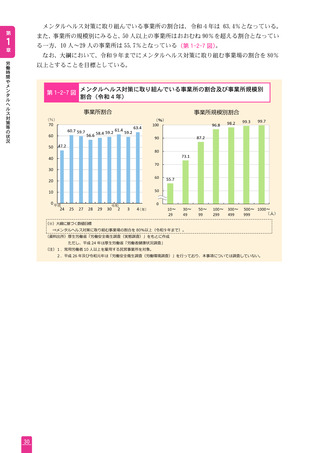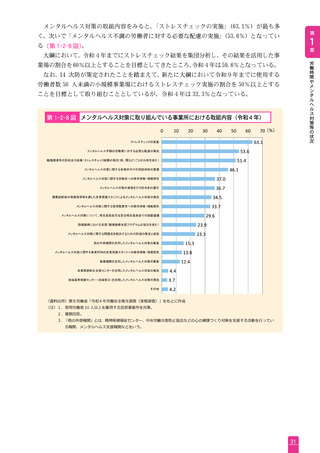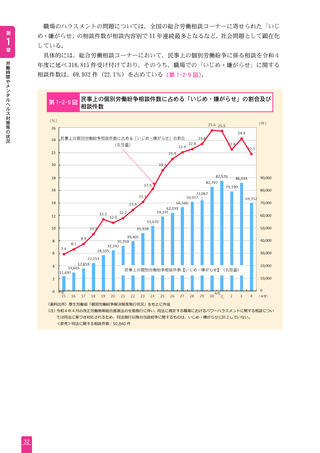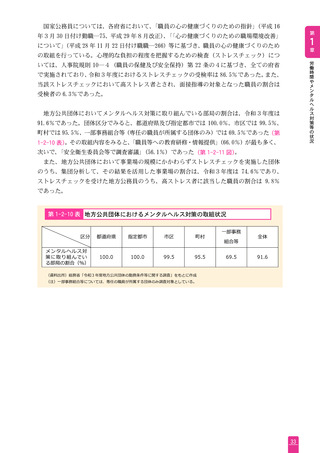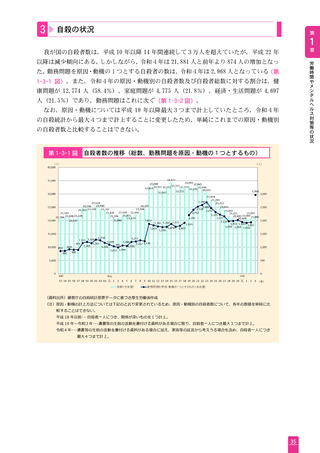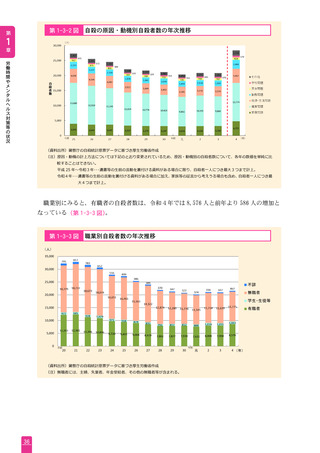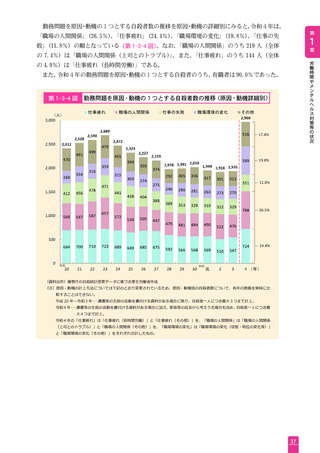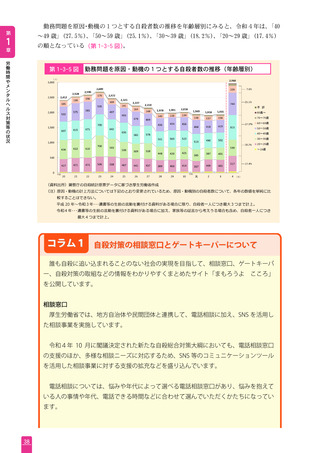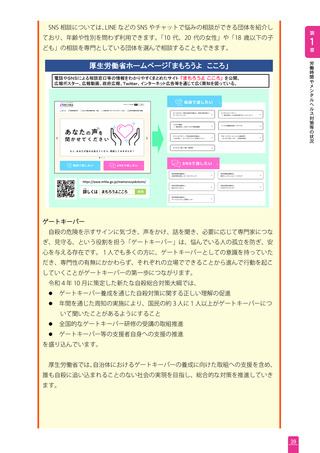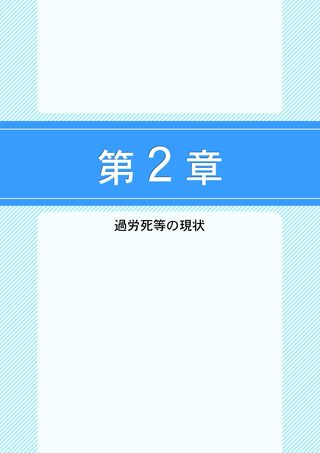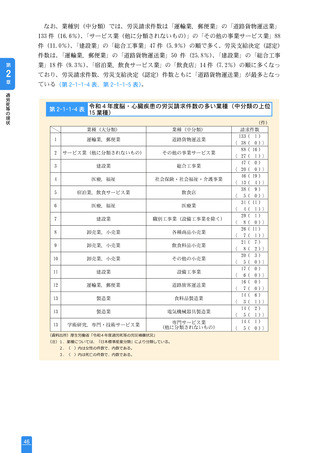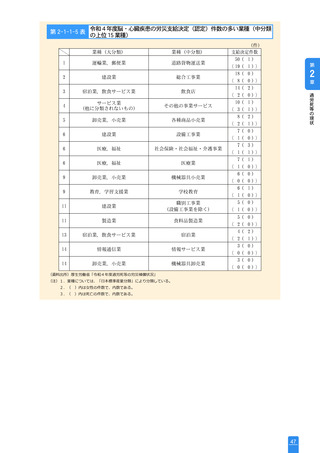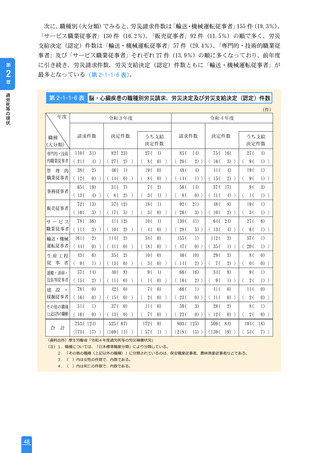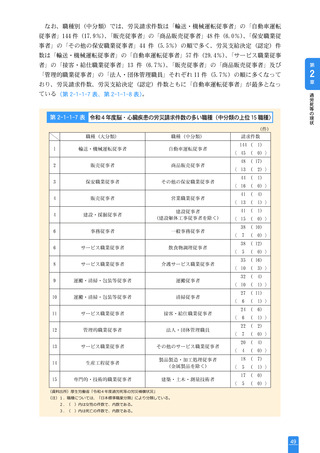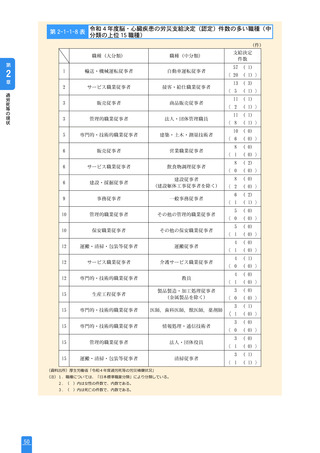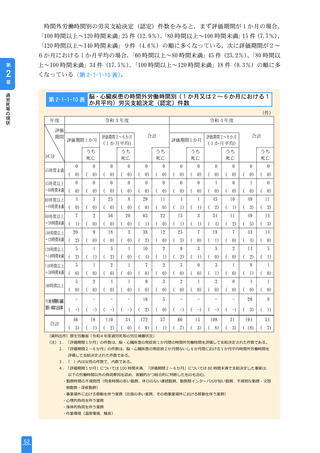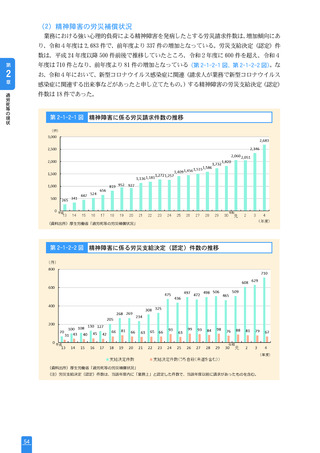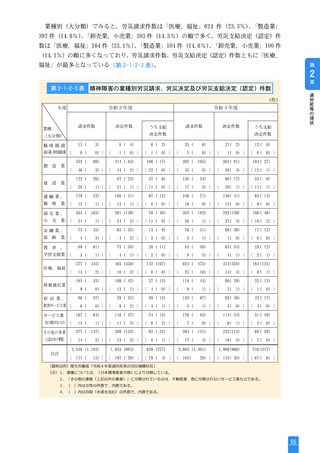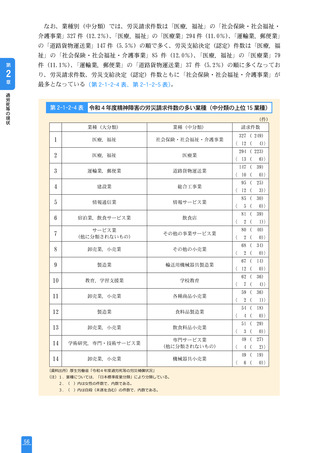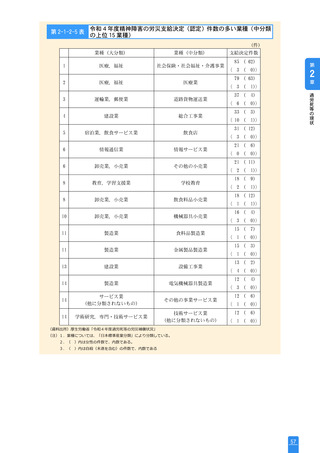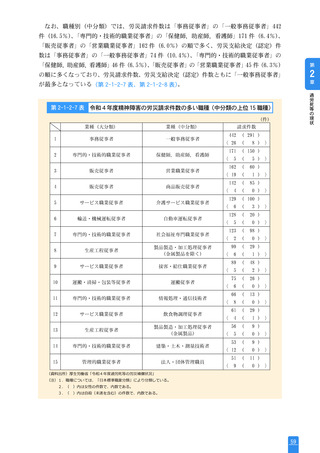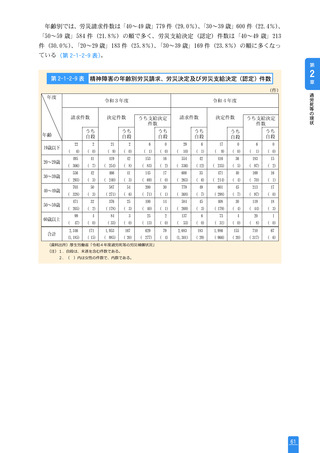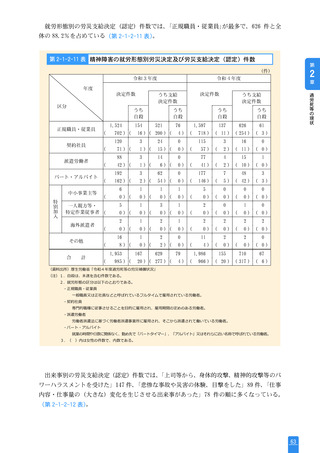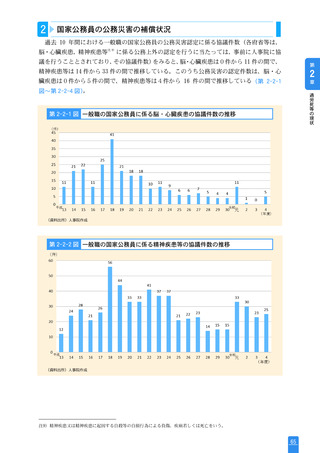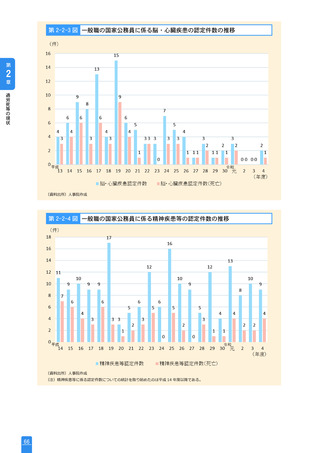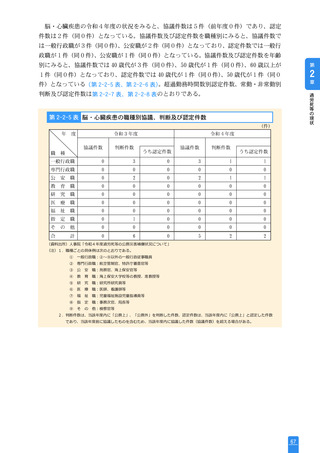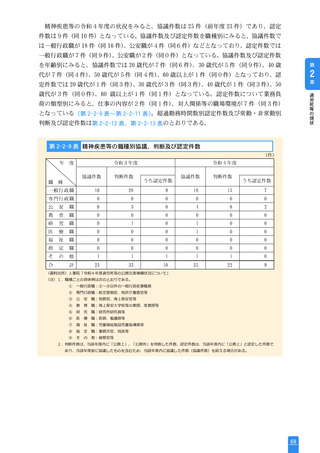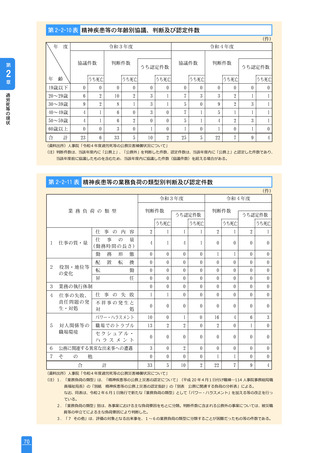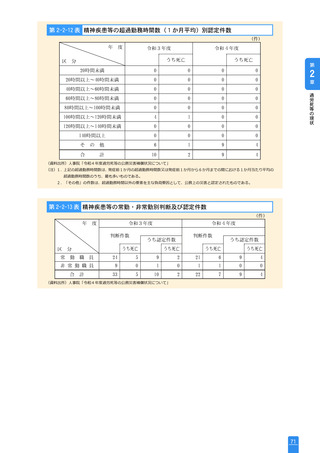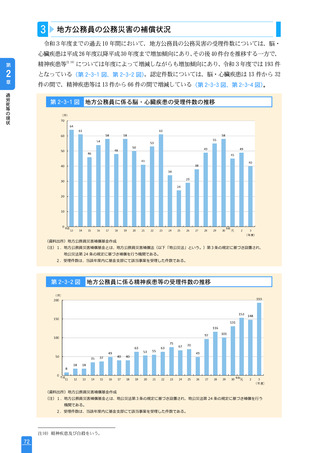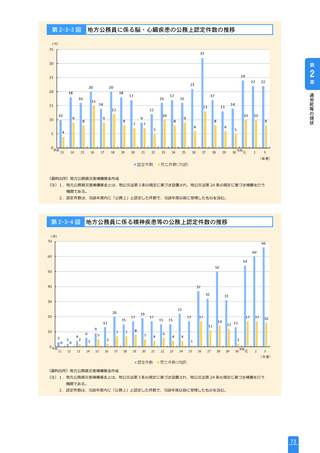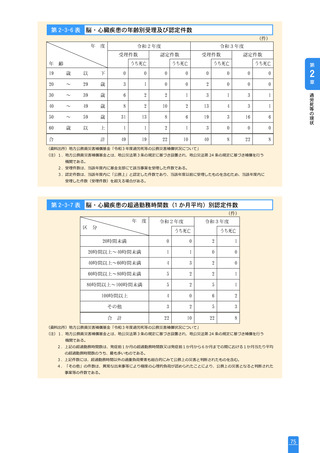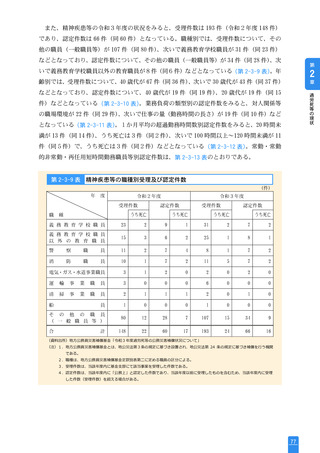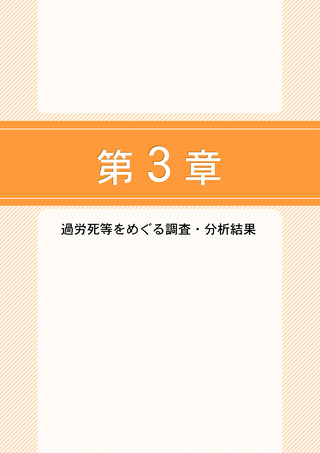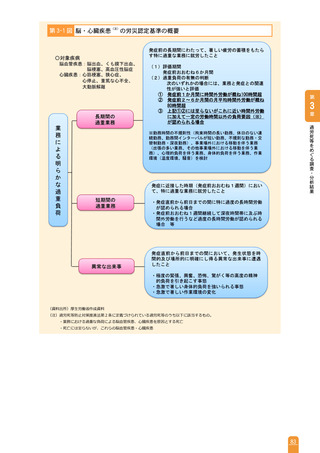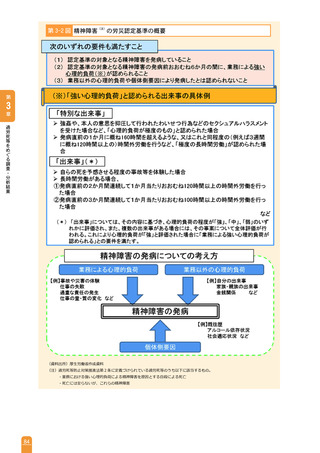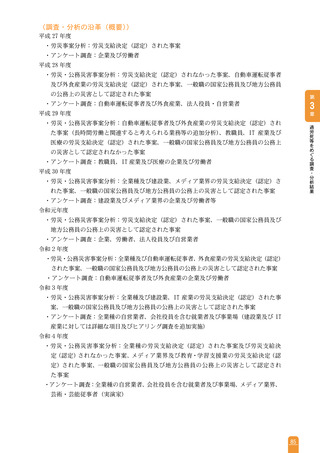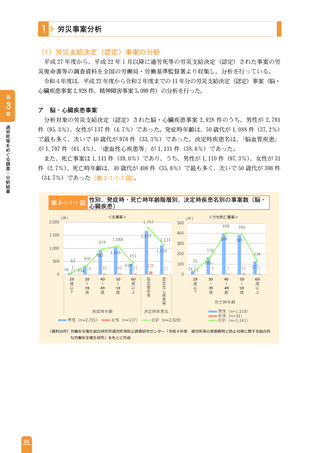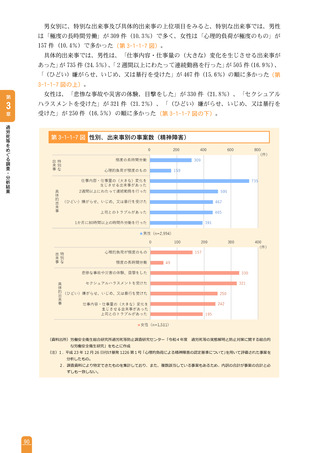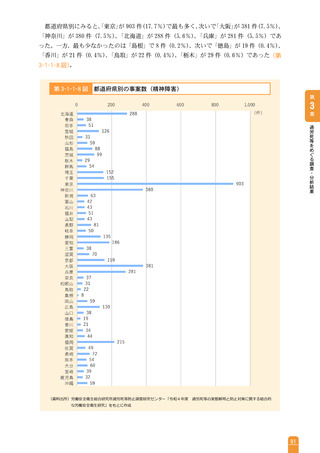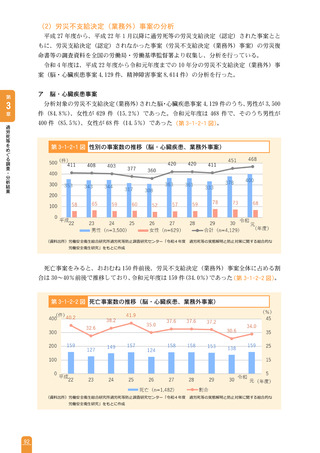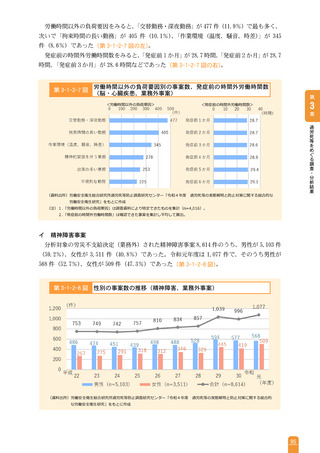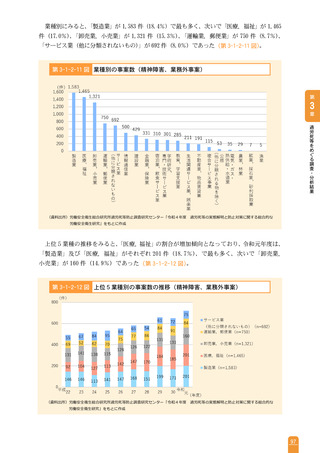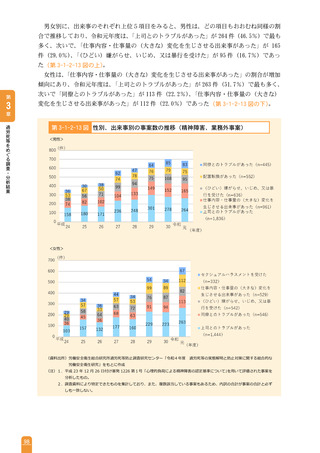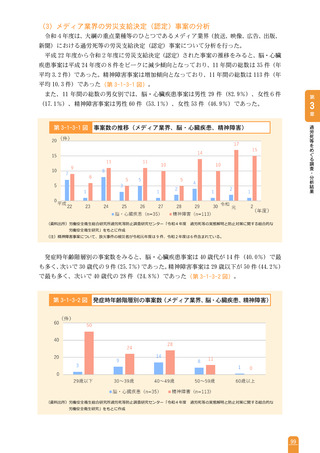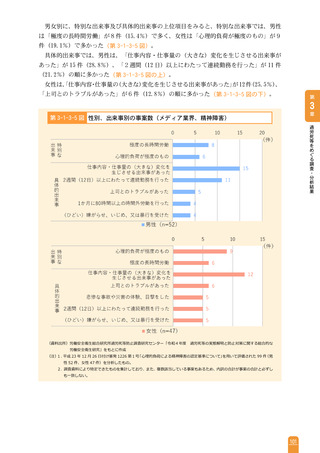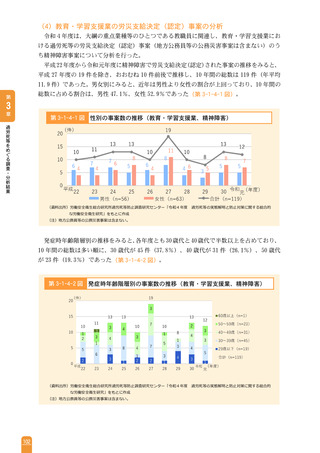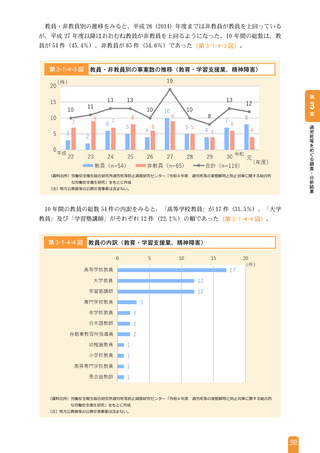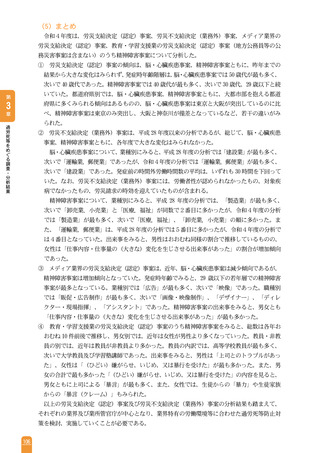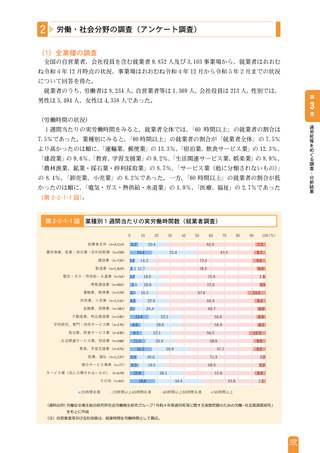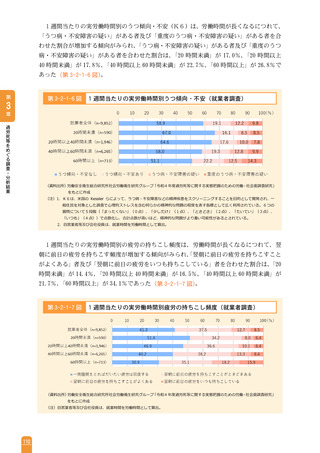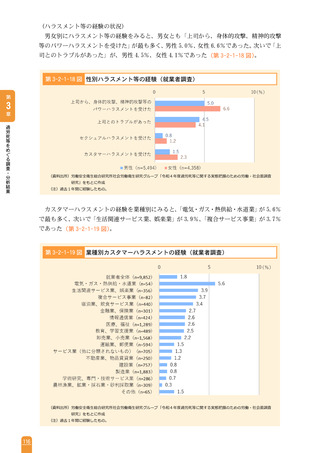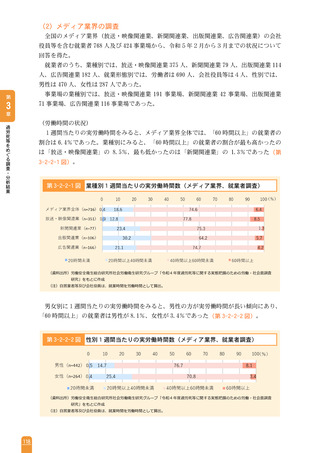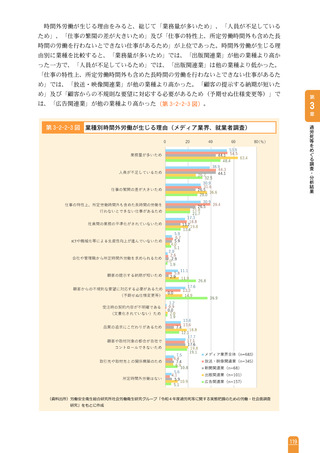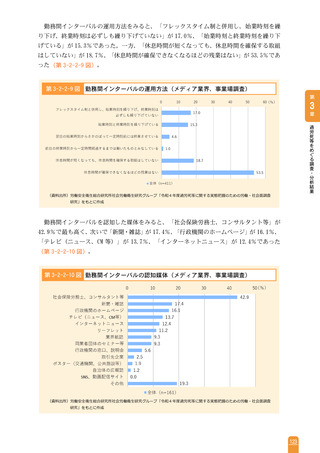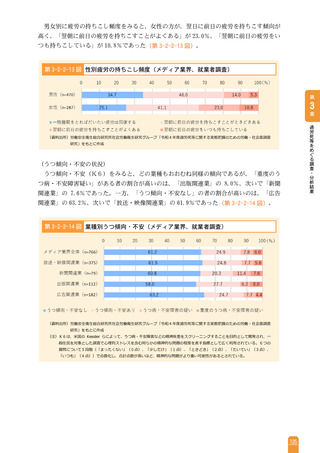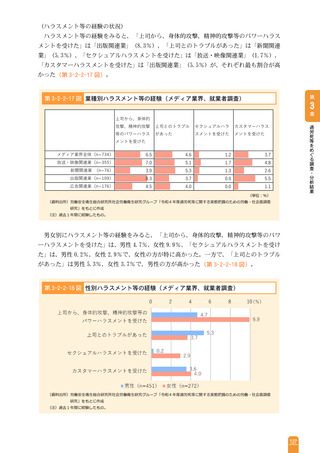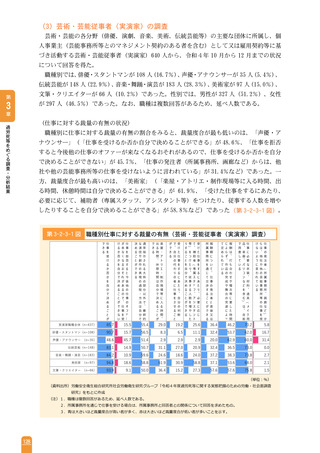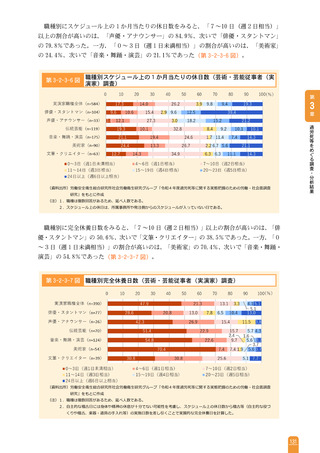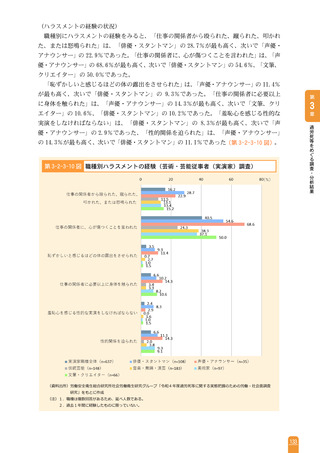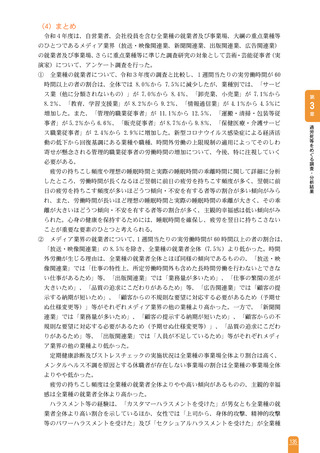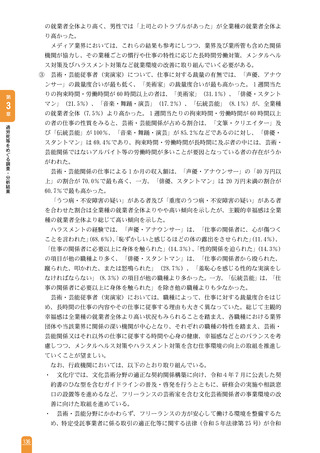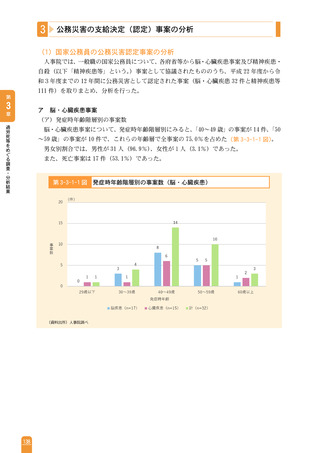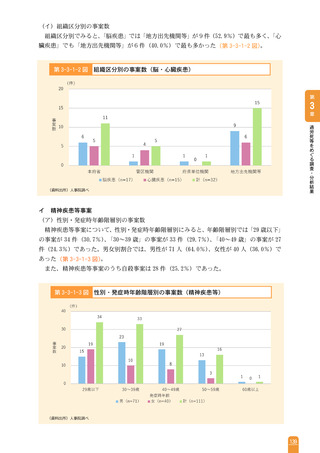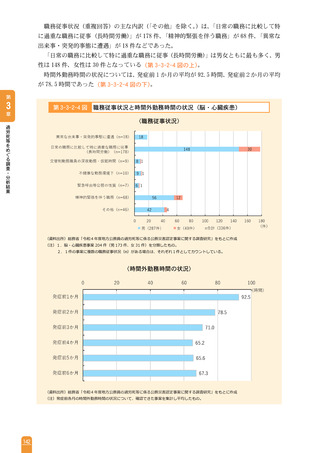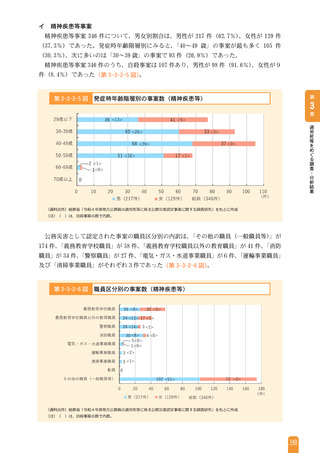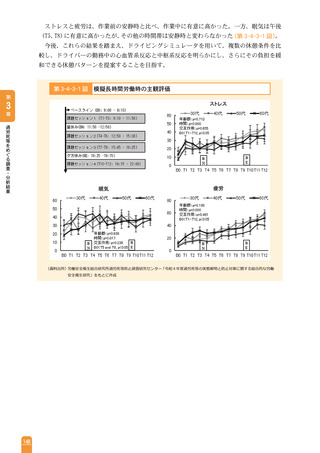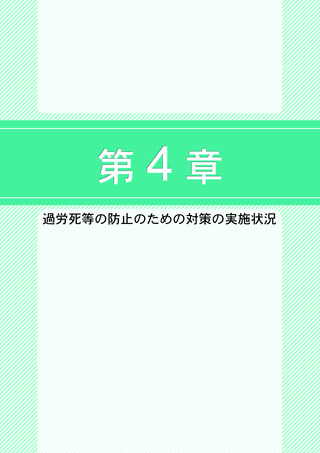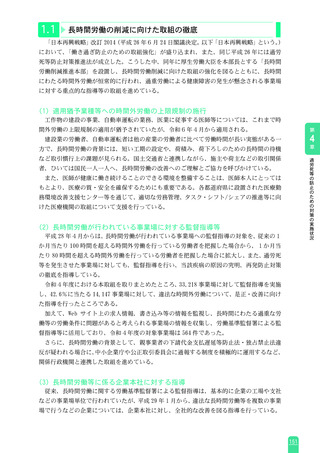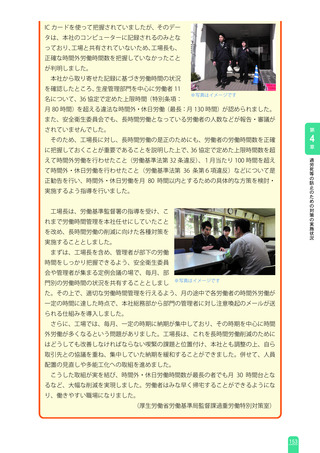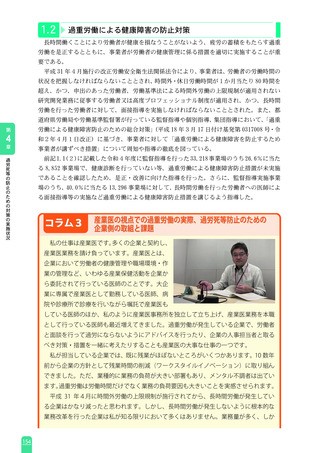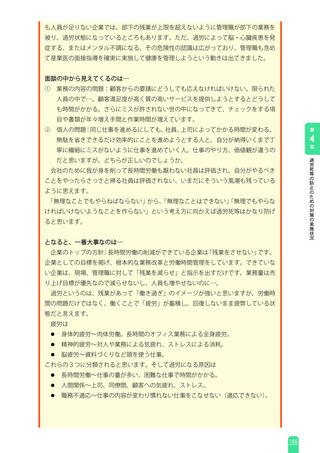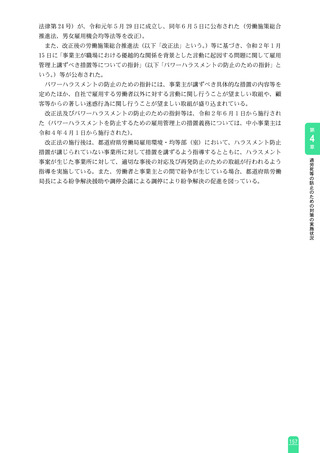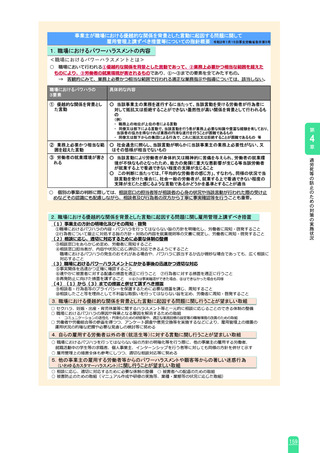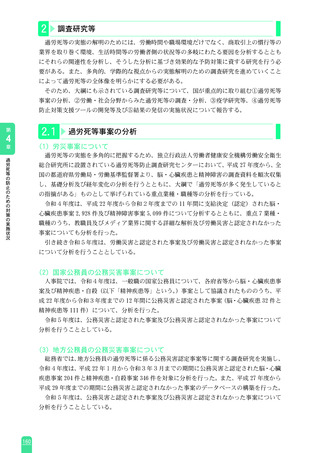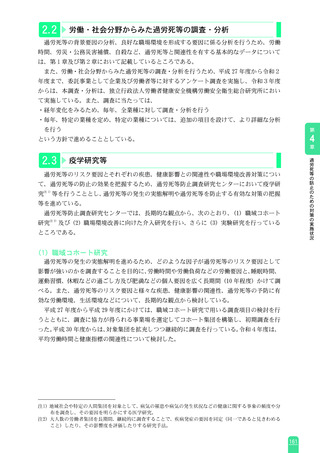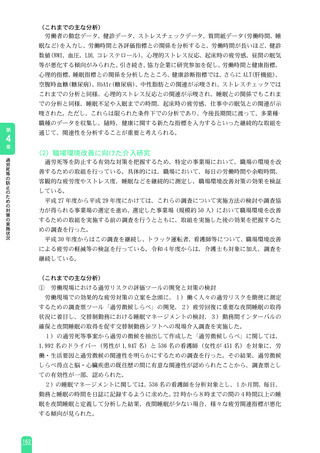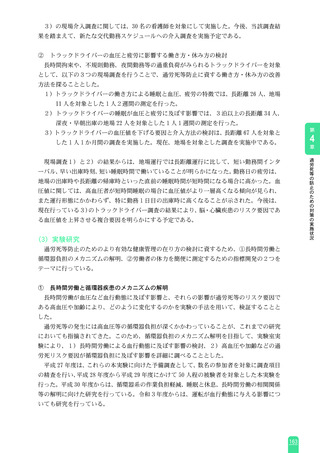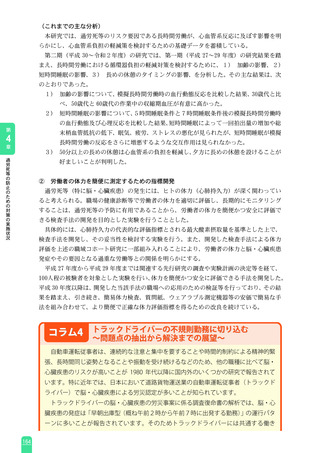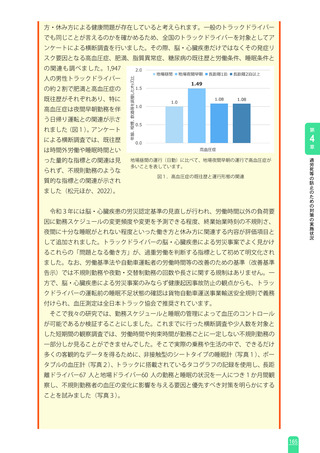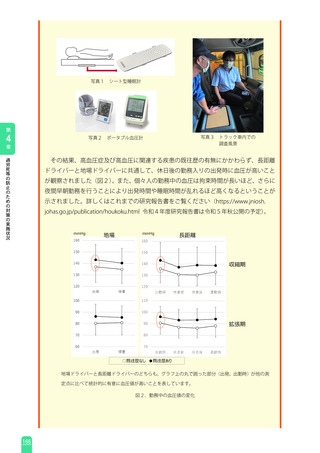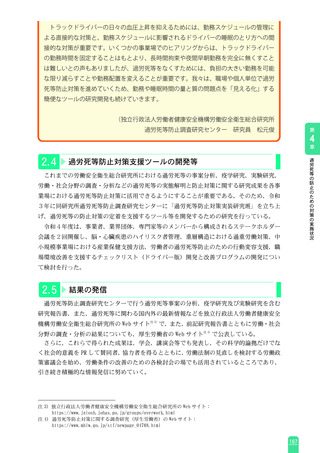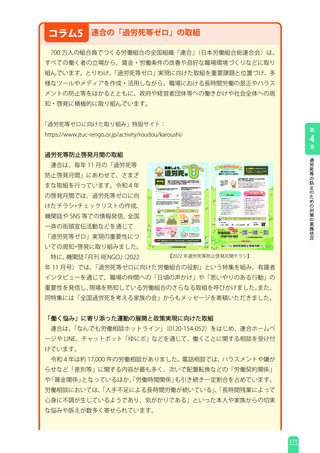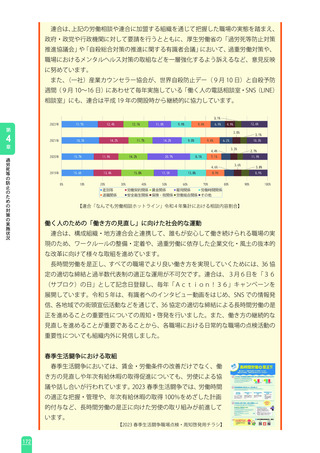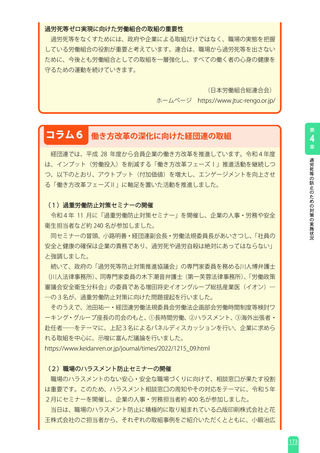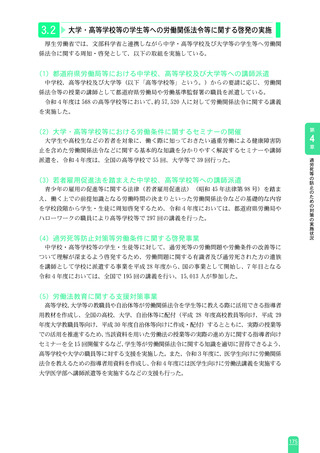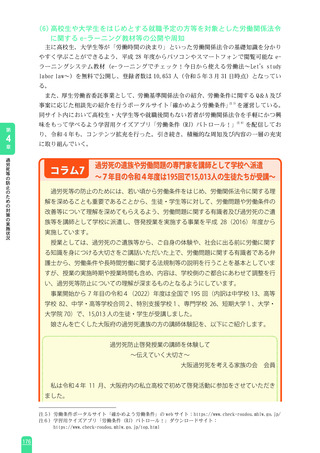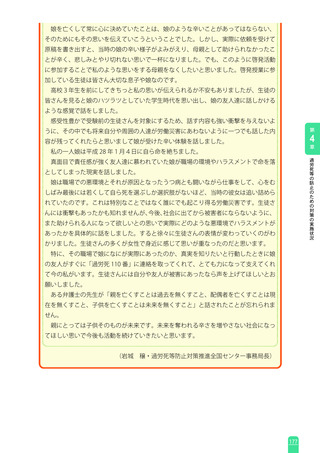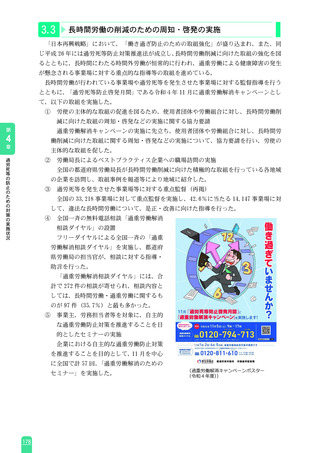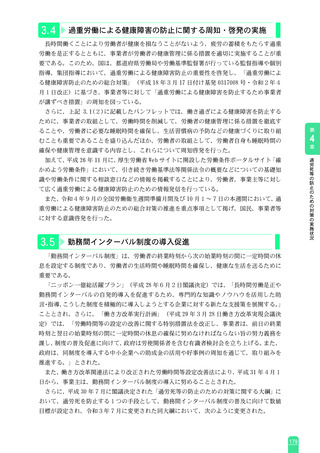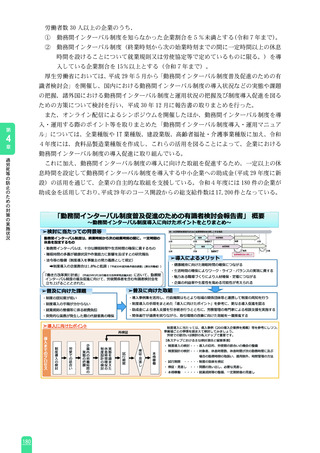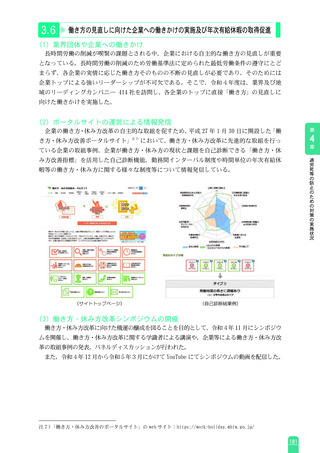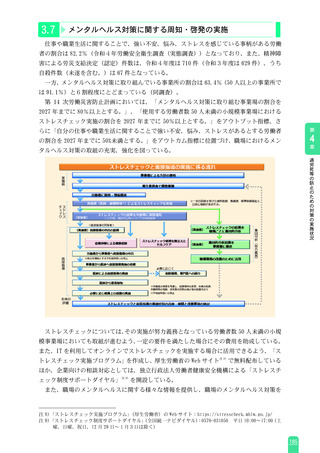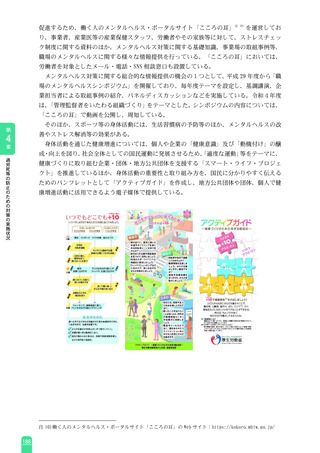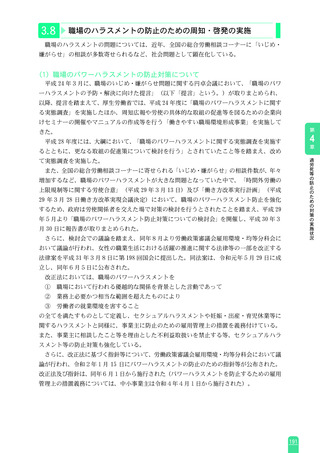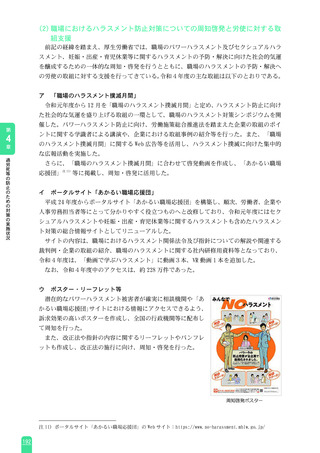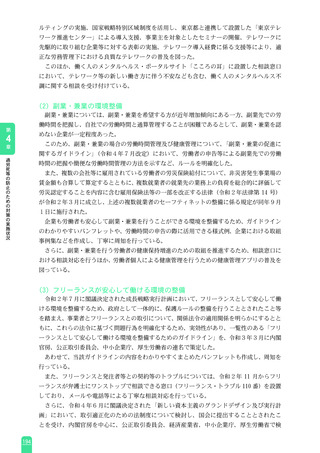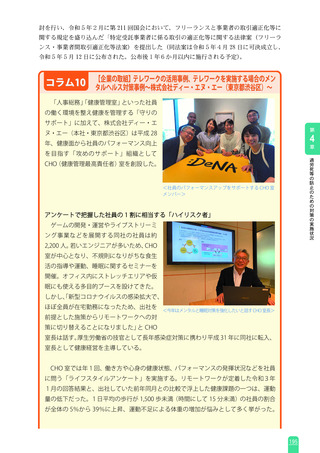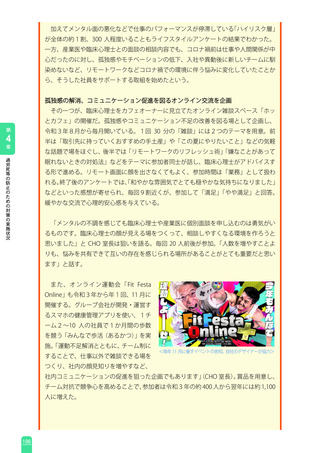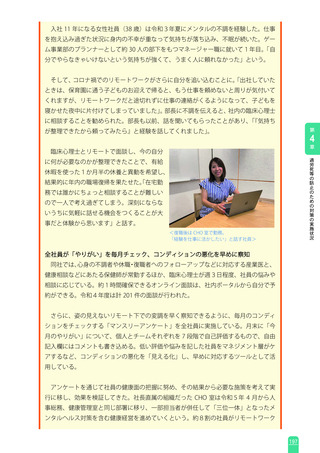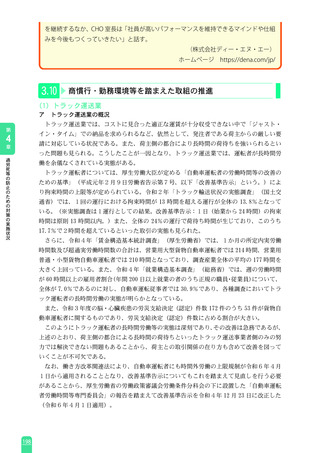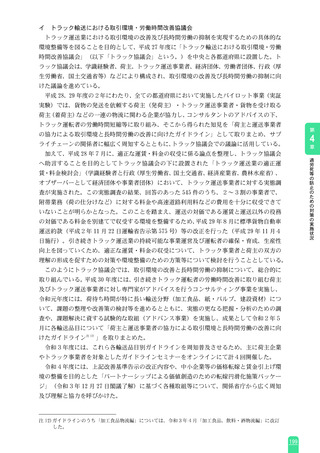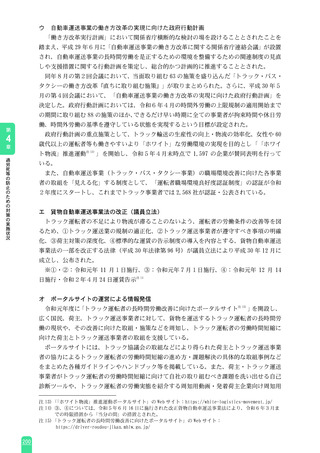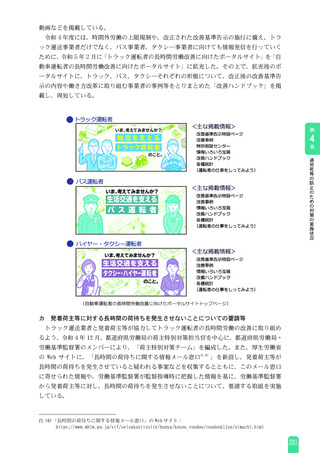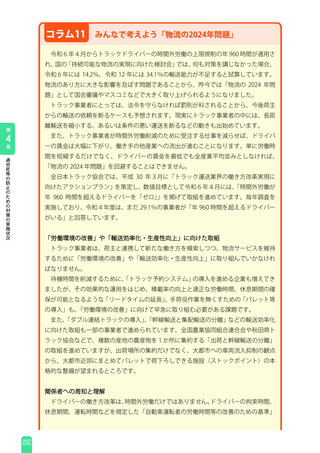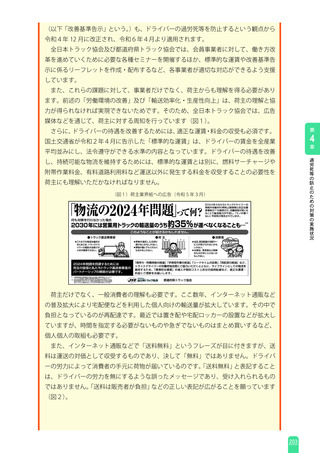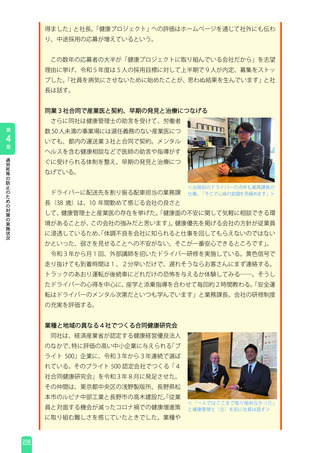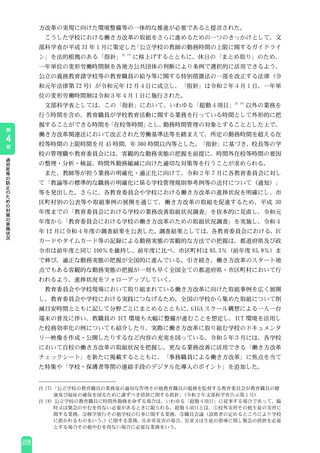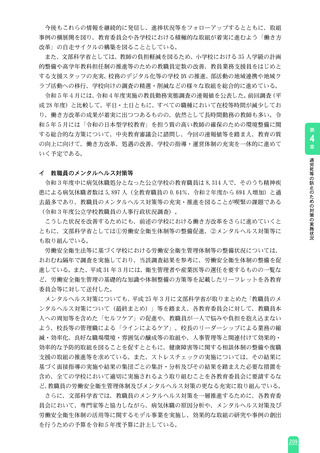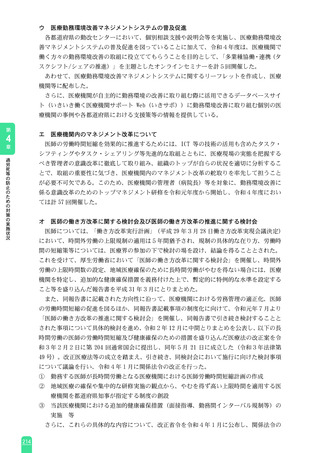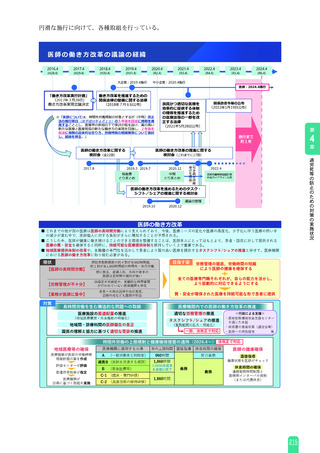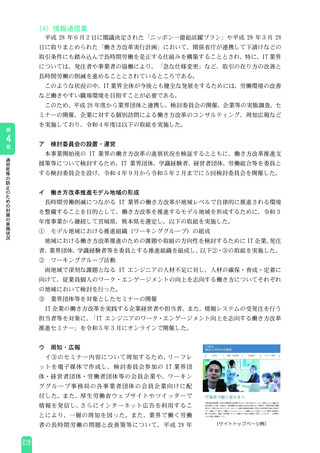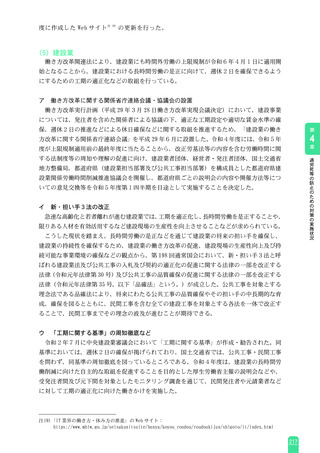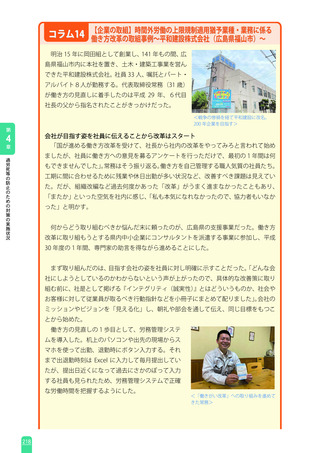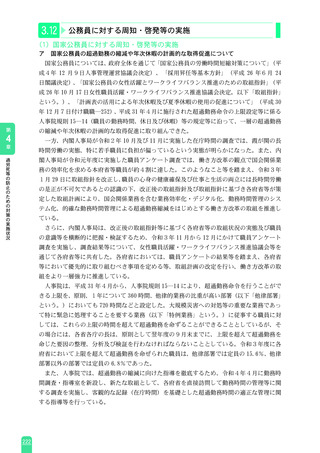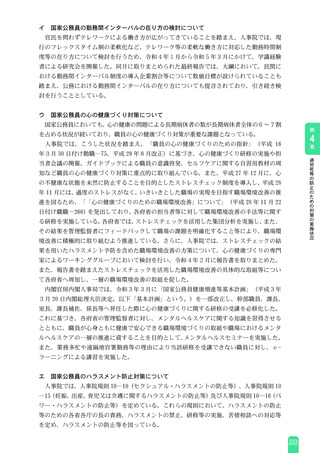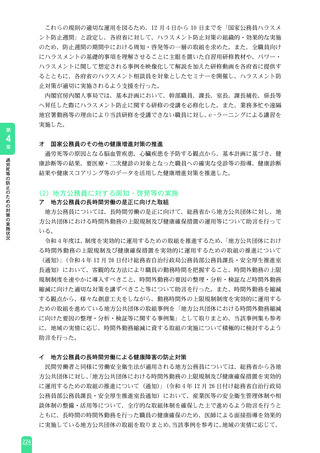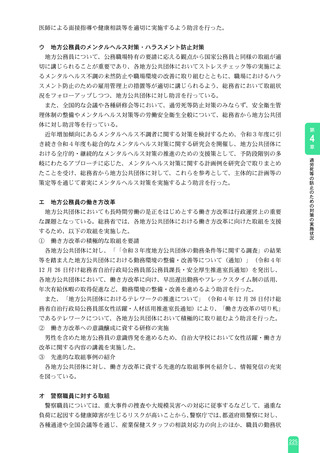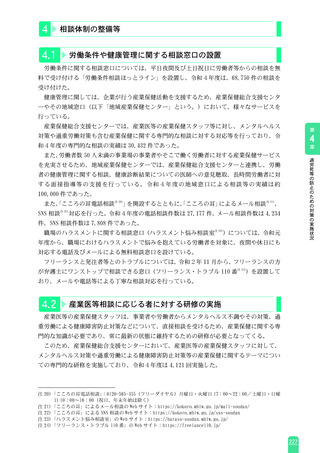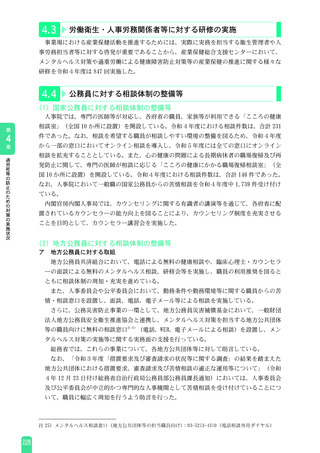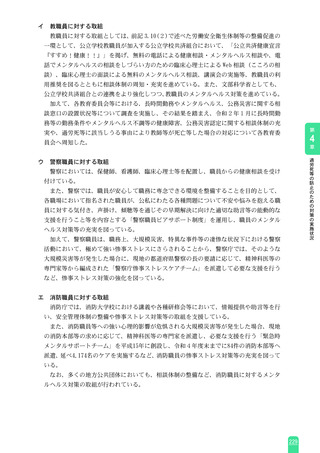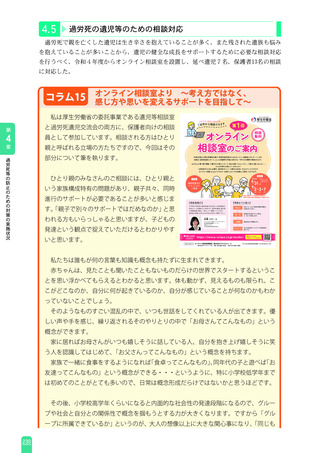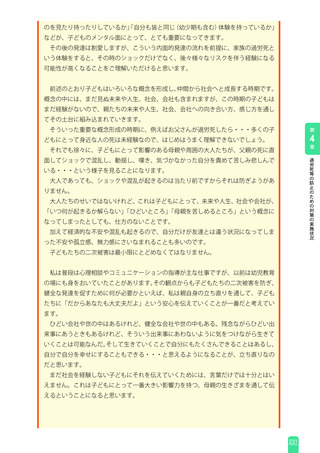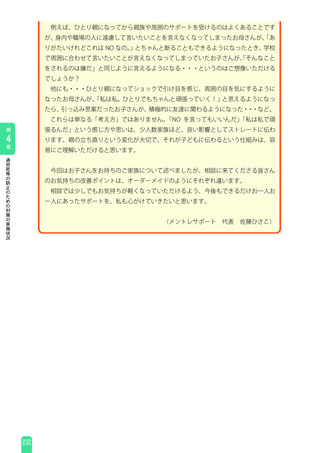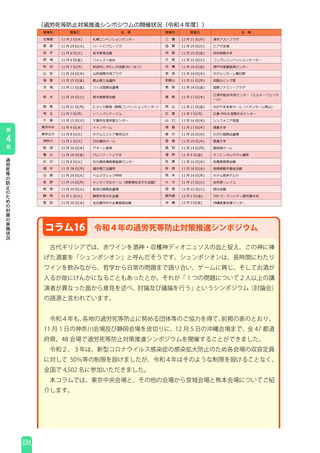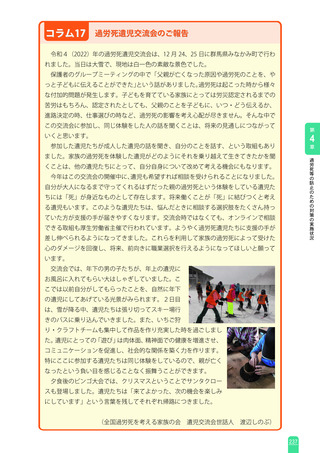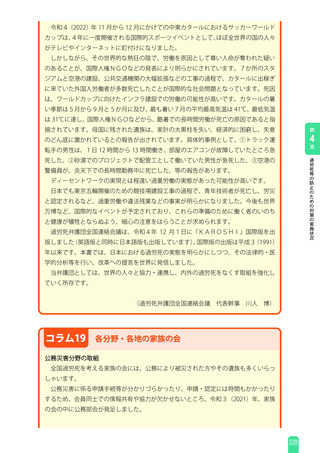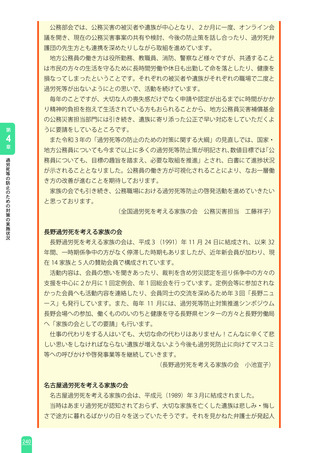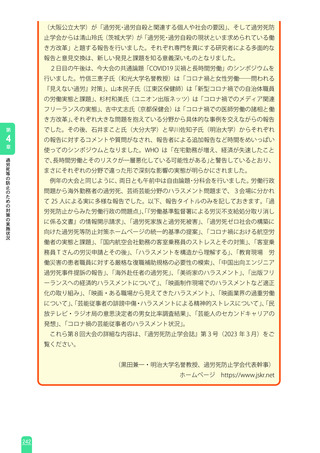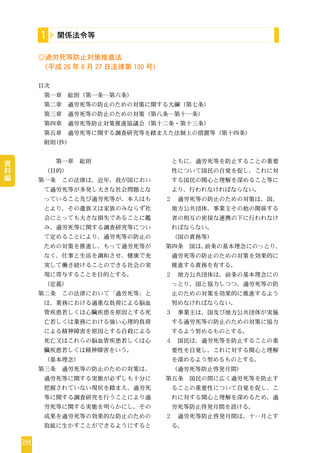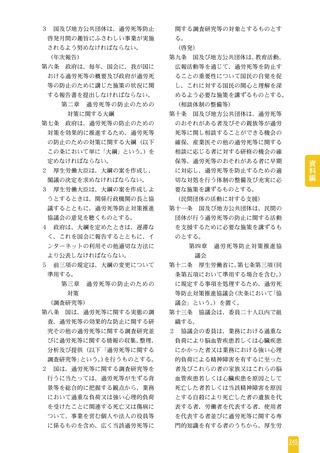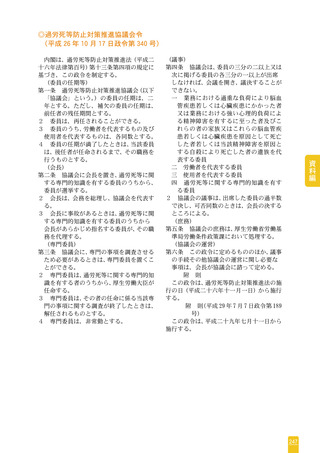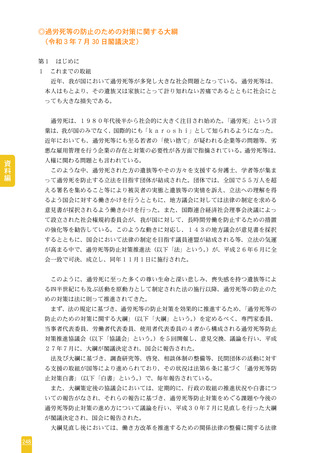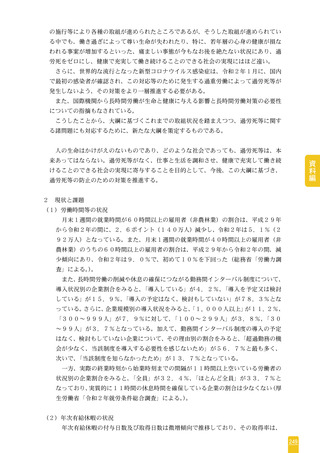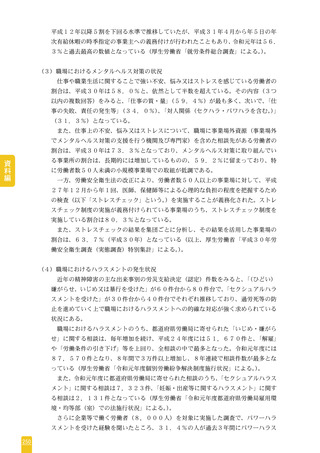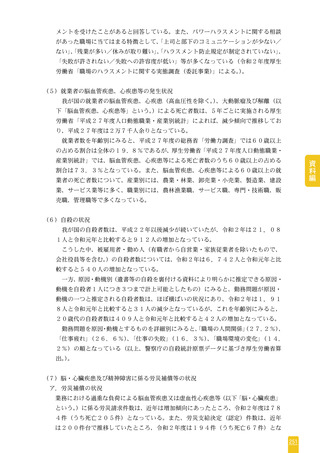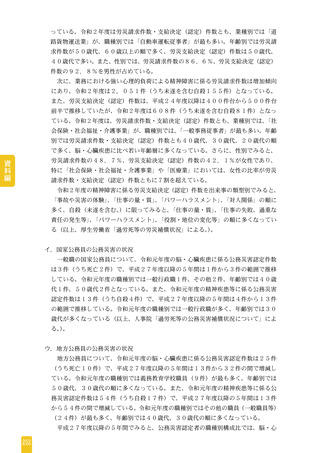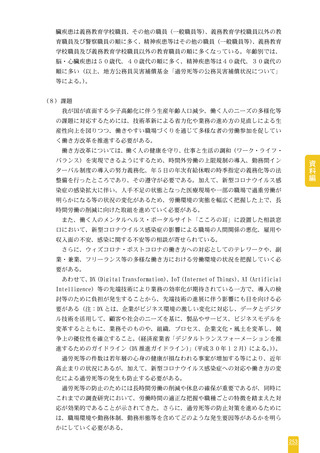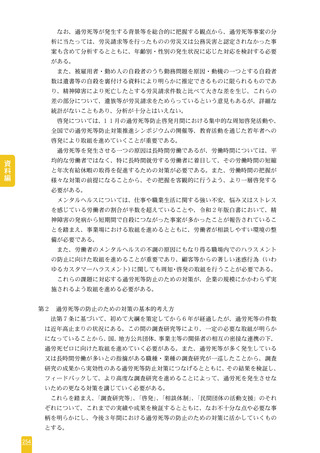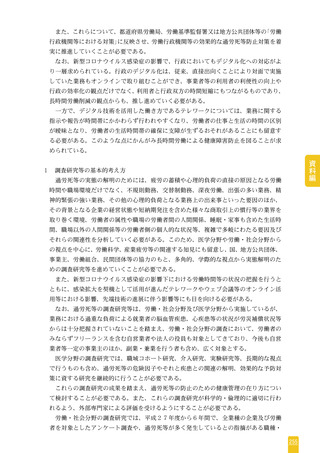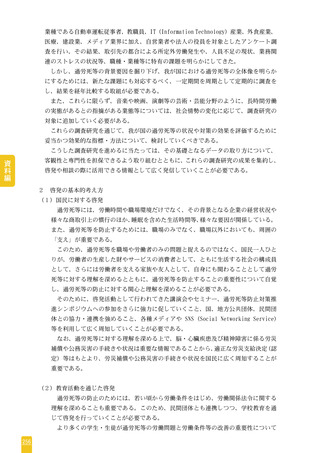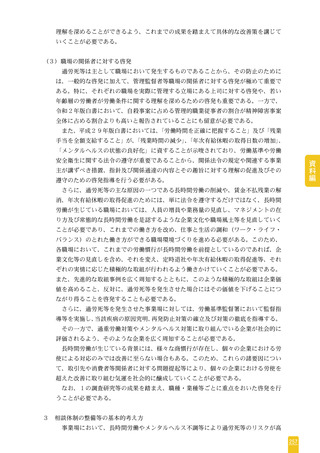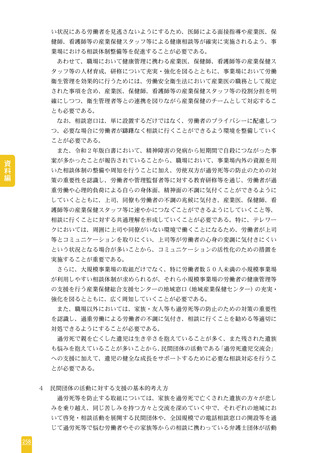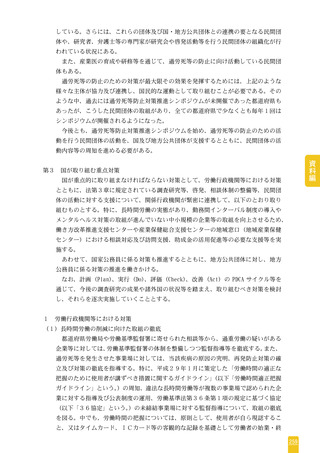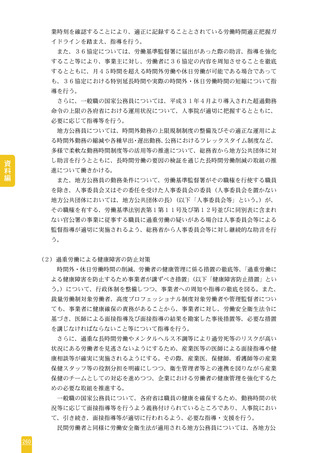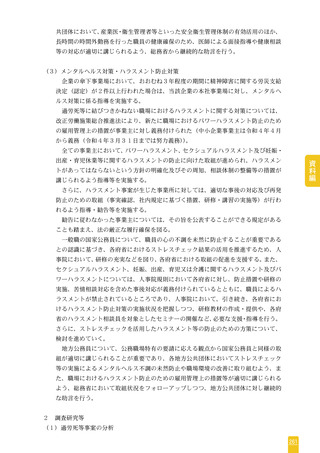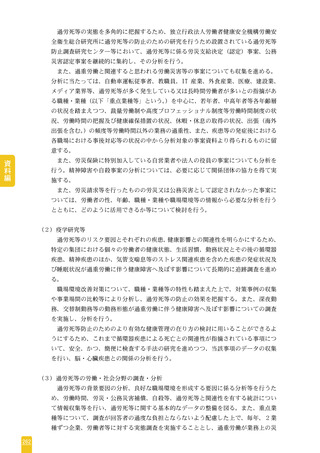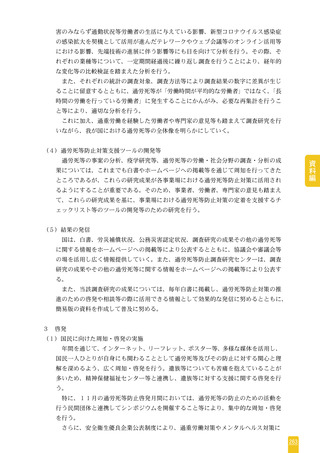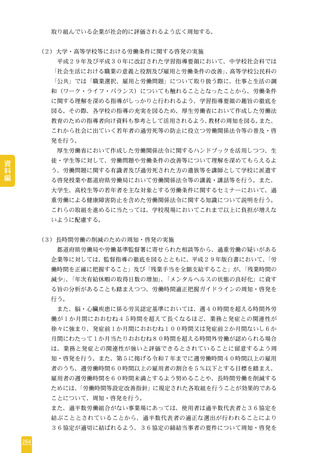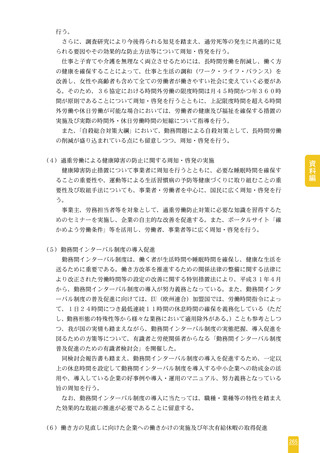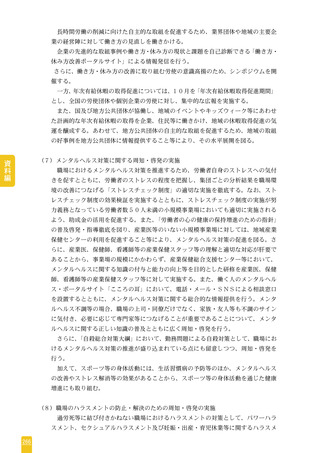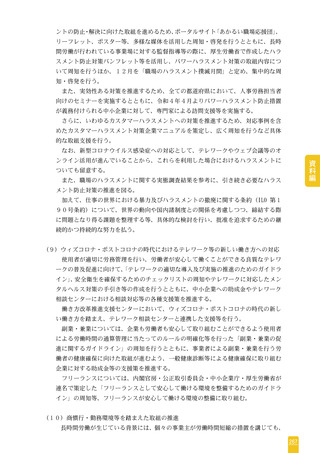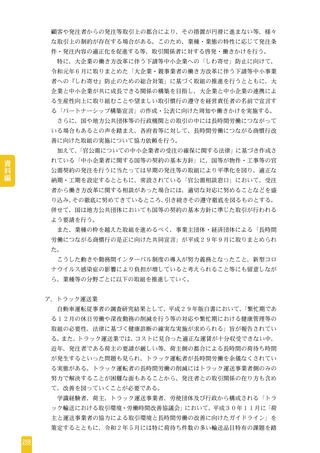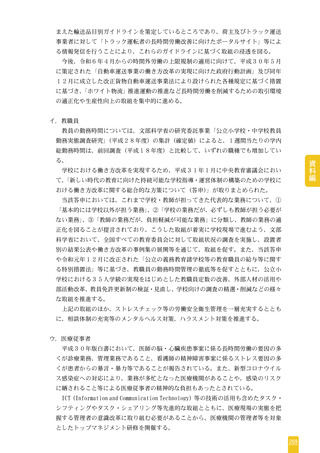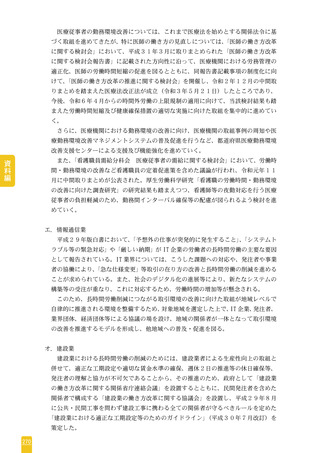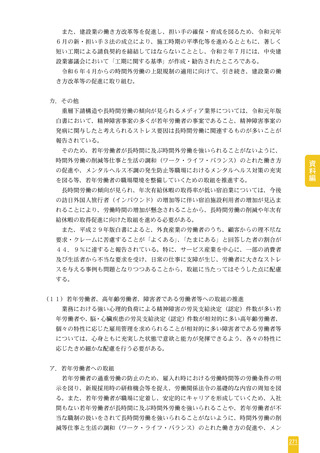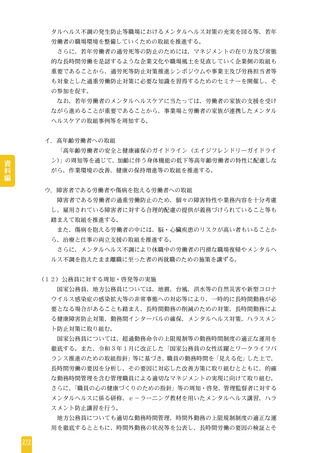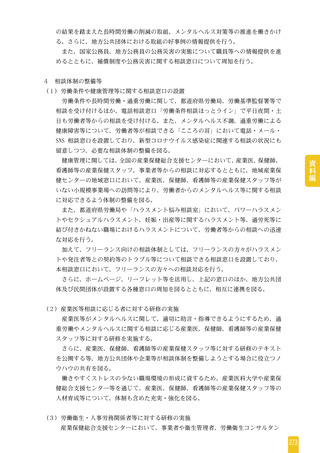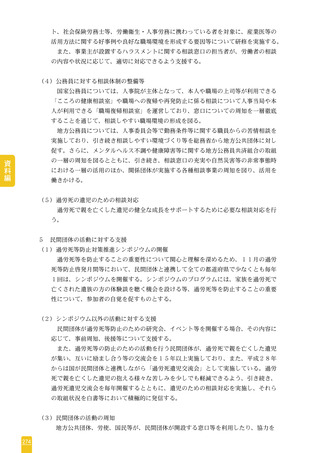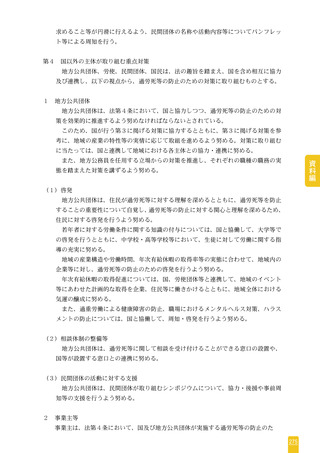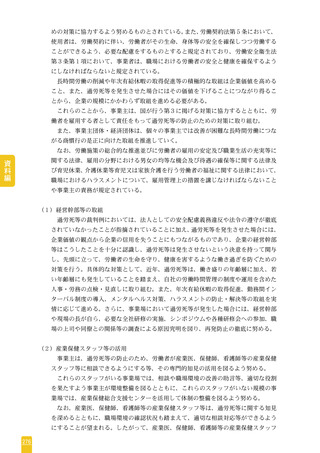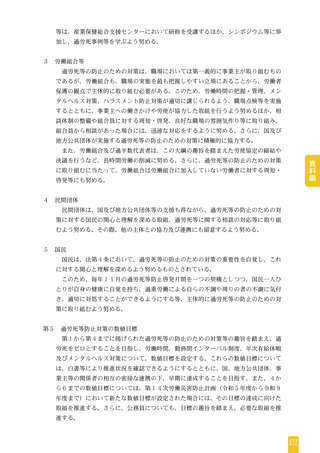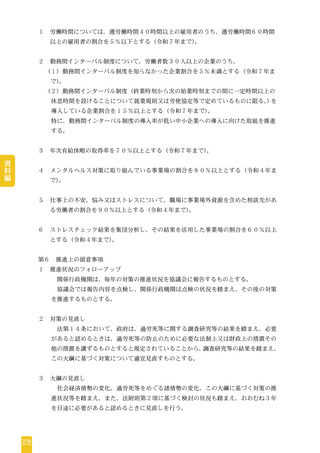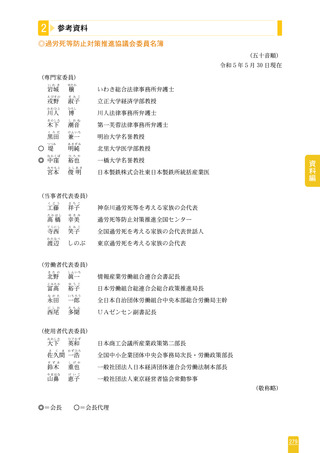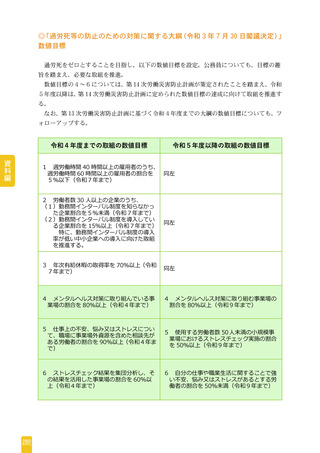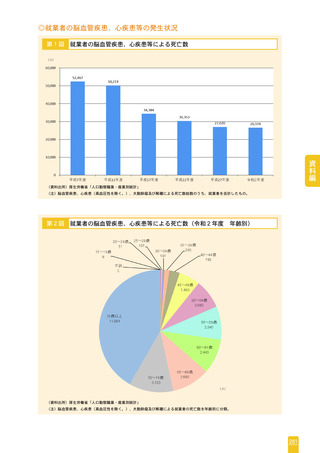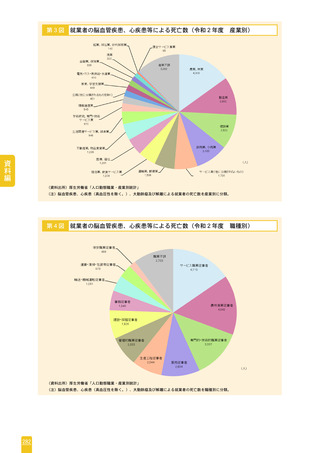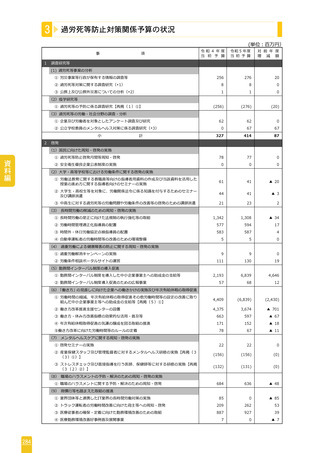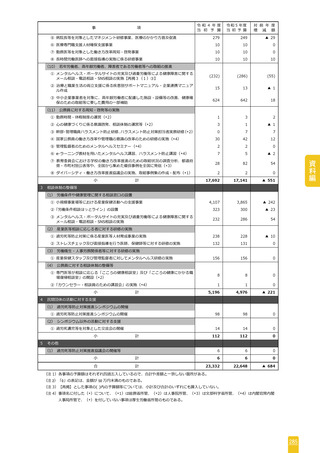令和4年度 我が国における過労死等の概要及び政府が過労死等の防止のために講じた施策の状況(令和5年版 過労死等防止対策白書) (250 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156170.pdf |
| 出典情報 | 令和5年版 過労死等防止対策白書(10/13)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
止学会からは清山玲氏(茨城大学)が「過労死・過労自殺の現状といま求められている働
き方改革」と題する報告を行いました。それぞれ専門を異にする研究者による多面的な
報告と意見交換は、新しい発見と課題を知る意義深いものとなりました。
2日目の午後は、今大会の共通論題「COVID19 災禍と長時間労働」のシンポジウムを
行いました。竹信三恵子氏(和光大学名誉教授)は「コロナ禍と女性労働――問われる
『見えない過労』対策」
、山本民子氏(江東区保健師)は「新型コロナ禍での自治体職員
の労働実態と課題」
、杉村和美氏(ユニオン出版ネッツ)は「コロナ禍でのメディア関連
フリーランスの実態」
、吉中丈志氏(京都保健会)は「コロナ禍での医師労働の諸相と働
第
き方改革」
、
それぞれ大きな問題を抱えている分野から具体的な事例を交えながらの報告
でした。その後、石井まこと氏(大分大学)と早川佐知子氏(明治大学)からそれぞれ
4
章
の報告に対するコメントや質問がなされ、報告者による追加報告など時間をめいっぱい
過労死等の防止のための対策の実施状況
使ってのシンポジウムとなりました。WHO は「在宅勤務が増え、経済が失速したこと
で、長時間労働とそのリスクが一層悪化している可能性がある」と警告しているとおり、
第
4
まさにそれぞれの分野で違った形で深刻な影響の実態が明らかにされました。
章
例年の大会と同じように、両日とも午前中は自由論題・分科会を行いました。労働行政
過
労
死
等
の
防
止
の
た
め
の
対
策
の
実
施
状
況
問題から海外勤務者の過労死、芸術芸能分野のハラスメント問題まで、3会場に分かれ
て 25 人による実に多様な報告でした。以下、報告タイトルのみを記しておきます。
「過
労死防止からみた労働行政の問題点」、
「『労働基準監督署による労災不支給処分取り消し
に係る文書』の情報開示請求」
、
「過労死家族と過労死被害」
、「過労死ゼロ社会の構築に
向けた過労死等防止対策ホームページの統一的基準の提案」
、「コロナ禍における航空労
働者の実態と課題」
、
「国内航空会社勤務の客室乗務員のストレスとその対策」、「客室乗
務員 T さんの労災申請とその後」
、
「ハラスメントを構造から理解する」、
「教育現場 労
働災害の患者職員に対する厳格な復職補助規格の必要性の模索」、
「中国出向エンジニア
過労死事件提訴の報告」
、
「海外赴任者の過労死」、
「美術家のハラスメント」、「出版フリ
ーランスへの経済的ハラスメントについて」、「映画制作現場でのハラスメントなど適正
化の取り組み」
、
「映画・ある職場から見えてきたハラスメント」、
「映画業界の過重労働
について」
、
「芸能従事者の誹謗中傷・ハラスメントによる精神的ストレスについて」
、
「民
放テレビ・ラジオ局の意思決定者の男女比率調査結果」、「芸能人のセカンドキャリアの
発想」、「コロナ禍の芸能従事者のハラスメント状況」。
これら第8回大会の詳細な内容は、
『過労死防止学会誌』第3号(2023 年3月)をご
覧ください。
(黒田兼一・明治大学名誉教授、過労死防止学会代表幹事)
ホームページ https://www.jskr.net
242
242
242