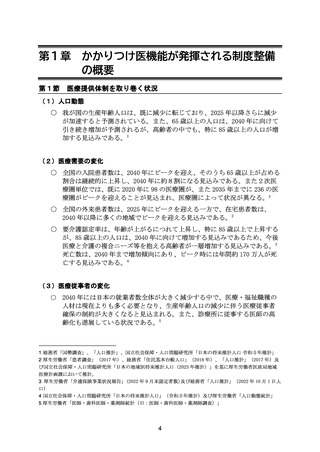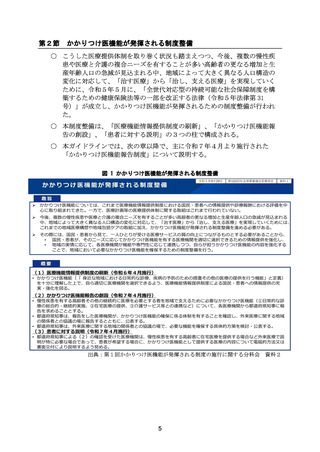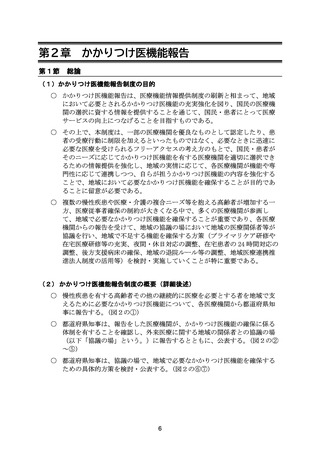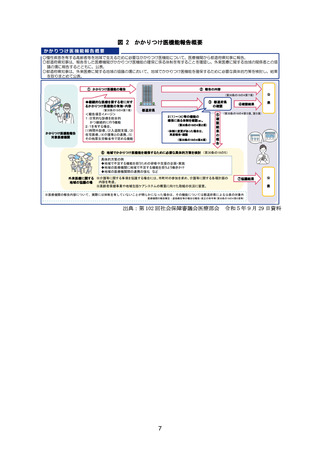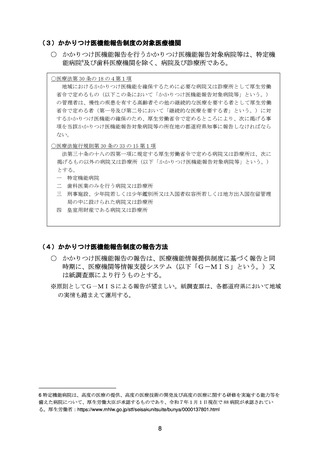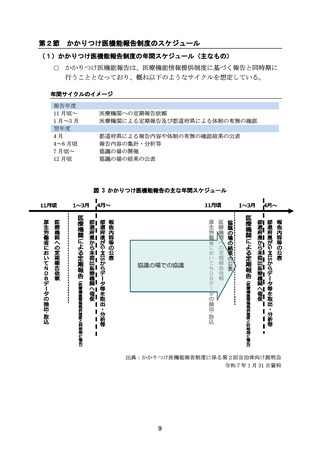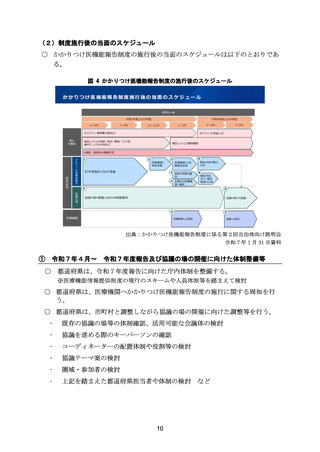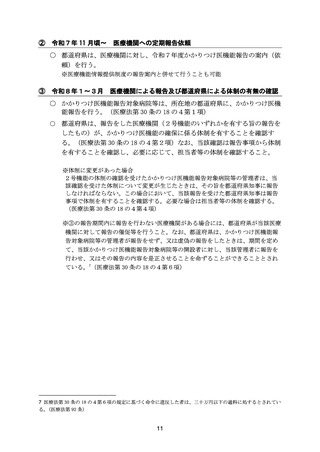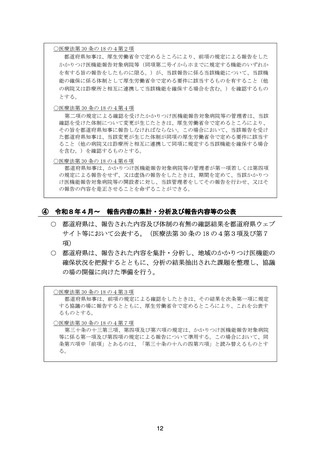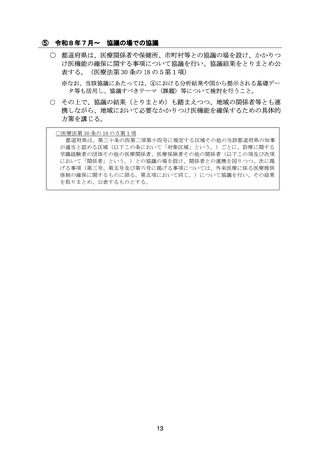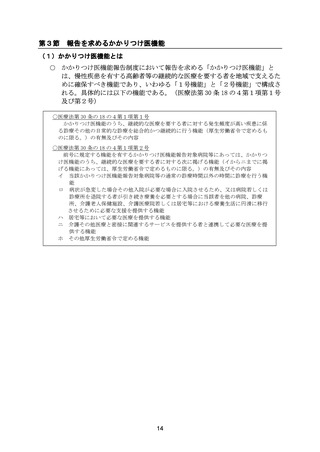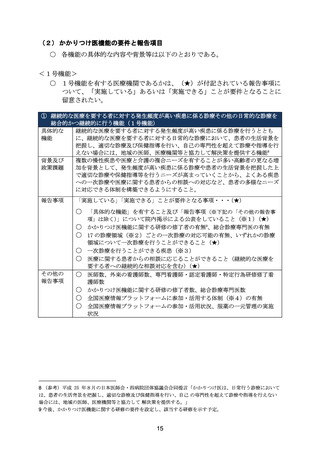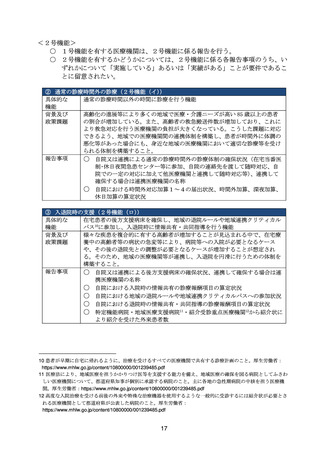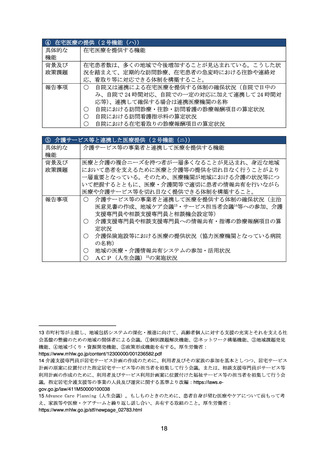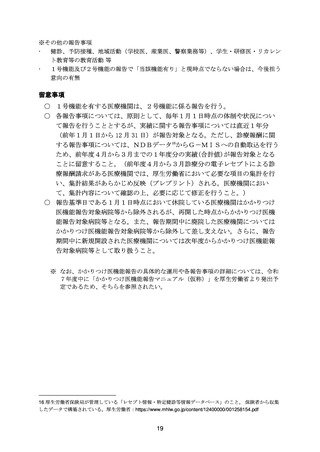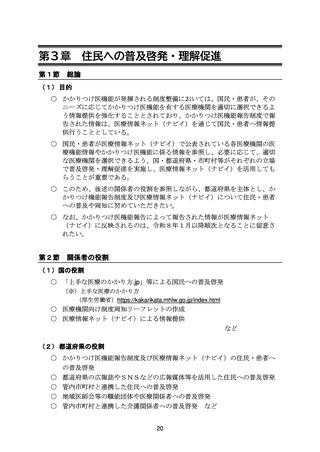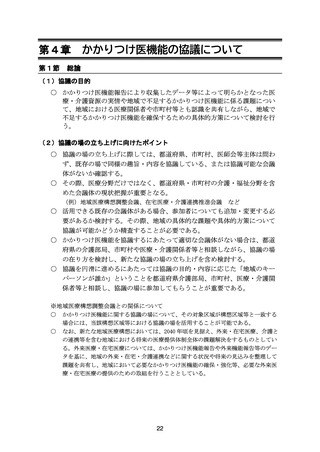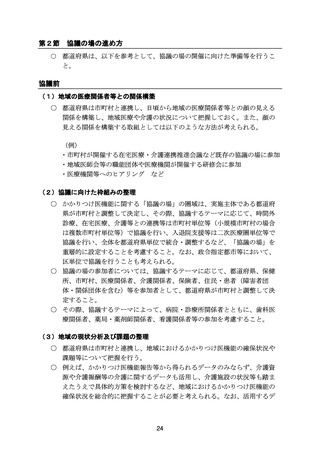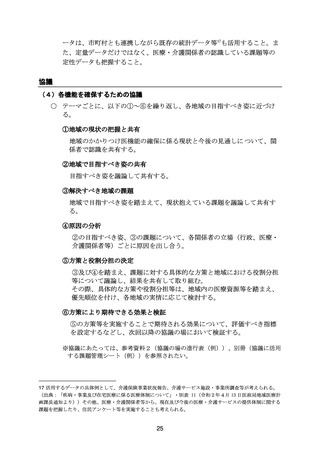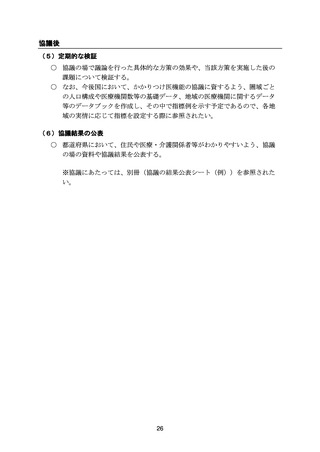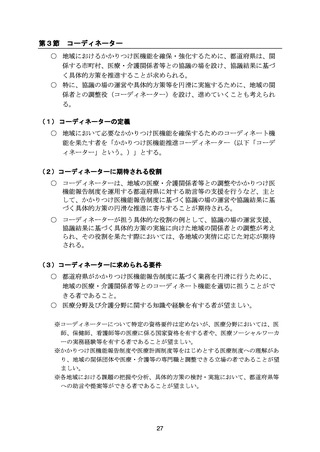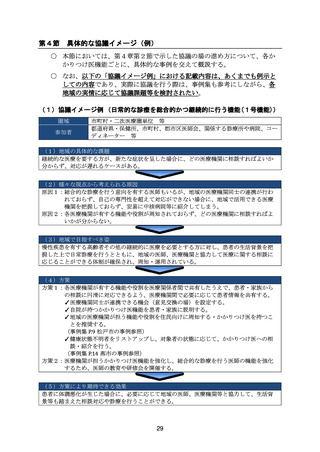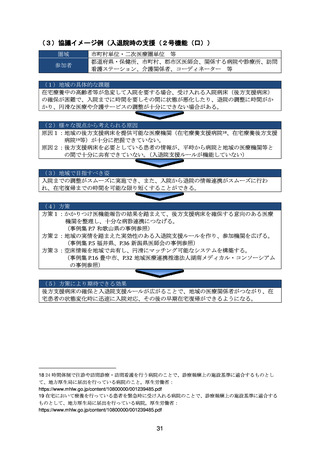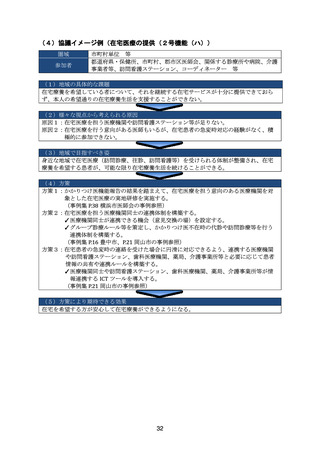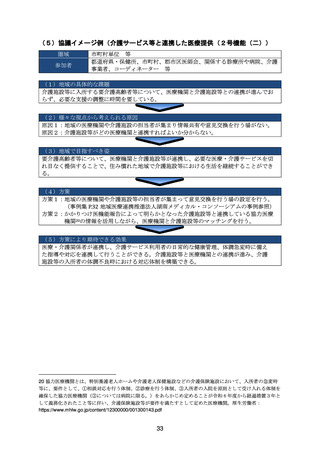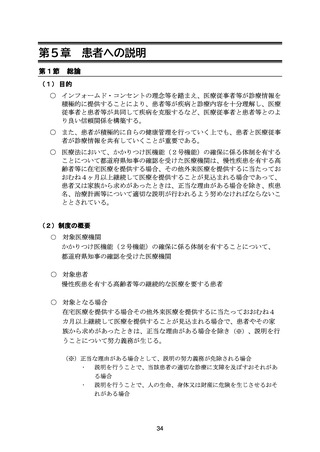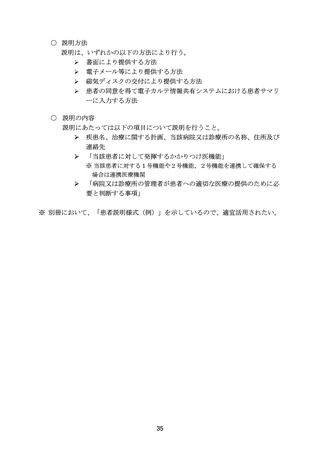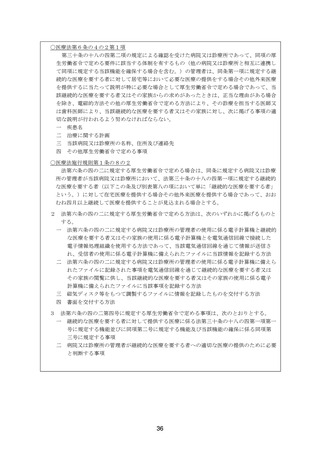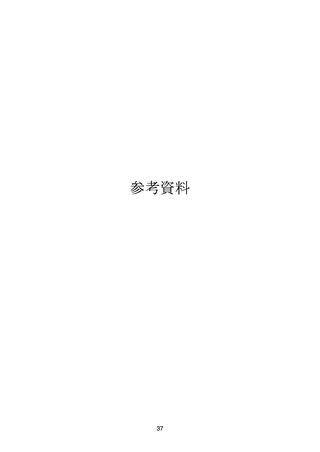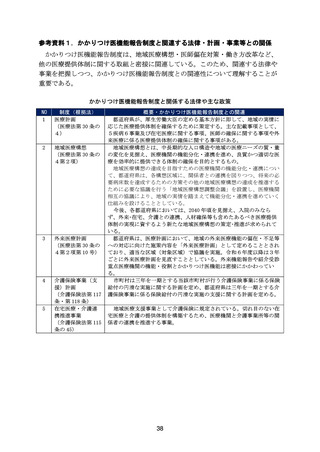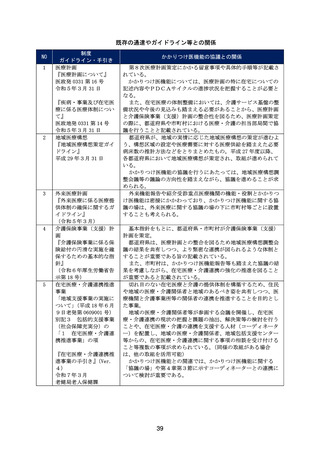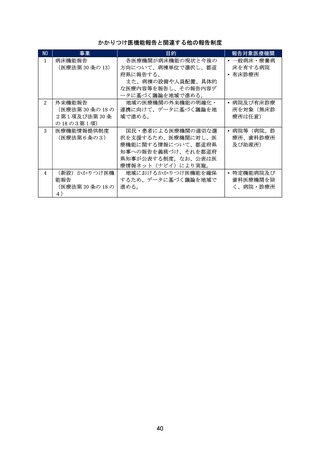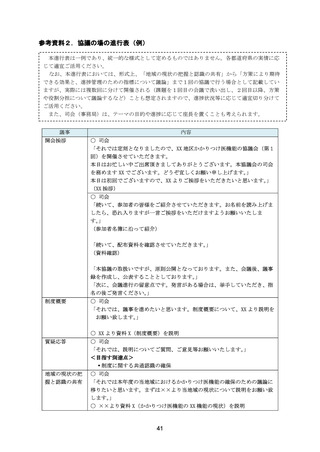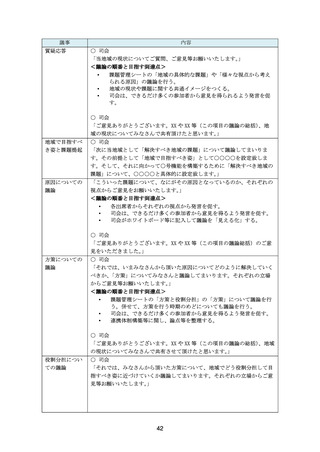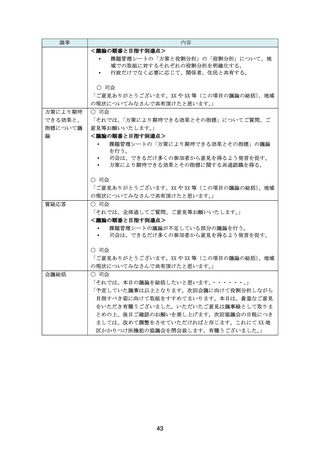よむ、つかう、まなぶ。
かかりつけ医機能の確保に関するガイドライン(第1版)(令和7年6月) (34 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00007.html |
| 出典情報 | かかりつけ医機能の確保に関するガイドラインについて (6/27)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
第5章 患者への説明
第1節
総論
(1) 目的
○ インフォームド・コンセントの理念等を踏まえ、医療従事者等が診療情報を
積極的に提供することにより、患者等が疾病と診療内容を十分理解し、医療
従事者と患者等が共同して疾病を克服するなど、医療従事者と患者等とのよ
り良い信頼関係を構築する。
○ また、患者が積極的に自らの健康管理を行っていく上でも、患者と医療従事
者が診療情報を共有していくことが重要である。
○ 医療法において、かかりつけ医機能(2号機能)の確保に係る体制を有する
ことについて都道府県知事の確認を受けた医療機関は、慢性疾患を有する高
齢者等に在宅医療を提供する場合、その他外来医療を提供するに当たってお
おむね4ヶ月以上継続して医療を提供することが見込まれる場合であって、
患者又は家族から求めがあったときは、正当な理由がある場合を除き、疾患
名、治療計画等について適切な説明が行われるよう努めなければならないこ
ととされている。
(2)制度の概要
○ 対象医療機関
かかりつけ医機能(2号機能)の確保に係る体制を有することについて、
都道府県知事の確認を受けた医療機関
○ 対象患者
慢性疾患を有する高齢者等の継続的な医療を要する患者
○ 対象となる場合
在宅医療を提供する場合その他外来医療を提供するに当たっておおむね4
カ月以上継続して医療を提供することが見込まれる場合で、患者やその家
族から求めがあったときは、正当な理由がある場合を除き(※)、説明を行
うことについて努力義務が生じる。
(※)正当な理由がある場合として、説明の努力義務が免除される場合
説明を行うことで、当該患者の適切な診療に支障を及ぼすおそれがあ
る場合
説明を行うことで、人の生命、身体又は財産に危険を生じさせるおそ
れがある場合
34
第1節
総論
(1) 目的
○ インフォームド・コンセントの理念等を踏まえ、医療従事者等が診療情報を
積極的に提供することにより、患者等が疾病と診療内容を十分理解し、医療
従事者と患者等が共同して疾病を克服するなど、医療従事者と患者等とのよ
り良い信頼関係を構築する。
○ また、患者が積極的に自らの健康管理を行っていく上でも、患者と医療従事
者が診療情報を共有していくことが重要である。
○ 医療法において、かかりつけ医機能(2号機能)の確保に係る体制を有する
ことについて都道府県知事の確認を受けた医療機関は、慢性疾患を有する高
齢者等に在宅医療を提供する場合、その他外来医療を提供するに当たってお
おむね4ヶ月以上継続して医療を提供することが見込まれる場合であって、
患者又は家族から求めがあったときは、正当な理由がある場合を除き、疾患
名、治療計画等について適切な説明が行われるよう努めなければならないこ
ととされている。
(2)制度の概要
○ 対象医療機関
かかりつけ医機能(2号機能)の確保に係る体制を有することについて、
都道府県知事の確認を受けた医療機関
○ 対象患者
慢性疾患を有する高齢者等の継続的な医療を要する患者
○ 対象となる場合
在宅医療を提供する場合その他外来医療を提供するに当たっておおむね4
カ月以上継続して医療を提供することが見込まれる場合で、患者やその家
族から求めがあったときは、正当な理由がある場合を除き(※)、説明を行
うことについて努力義務が生じる。
(※)正当な理由がある場合として、説明の努力義務が免除される場合
説明を行うことで、当該患者の適切な診療に支障を及ぼすおそれがあ
る場合
説明を行うことで、人の生命、身体又は財産に危険を生じさせるおそ
れがある場合
34