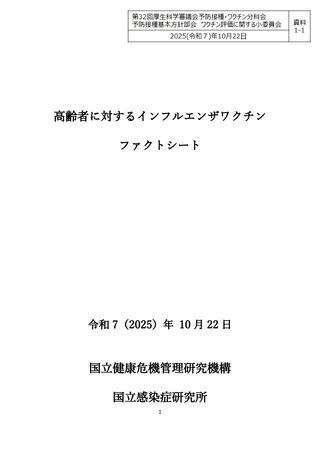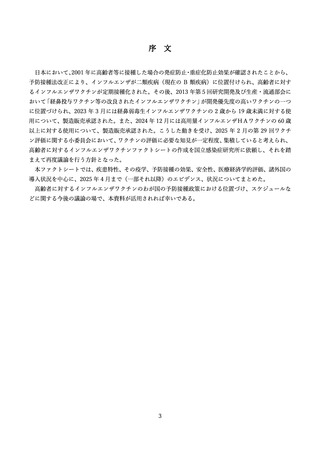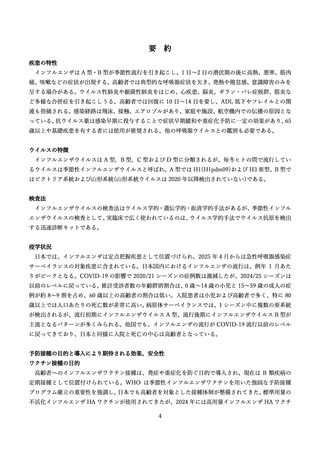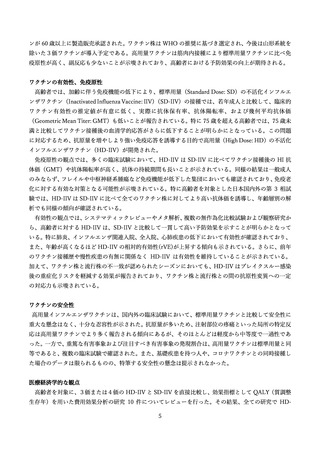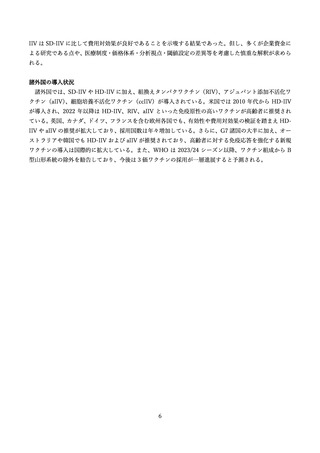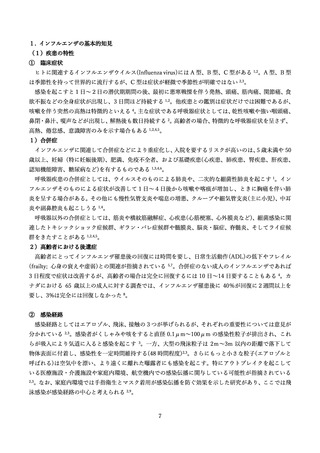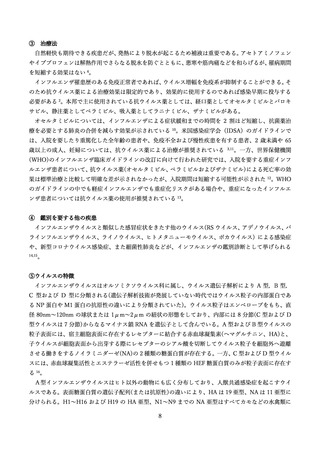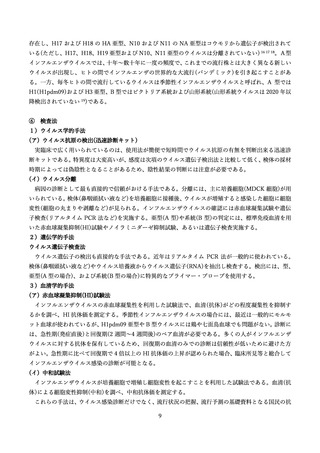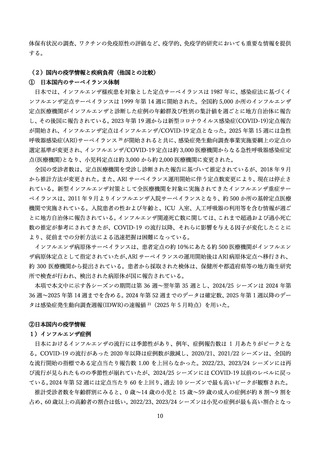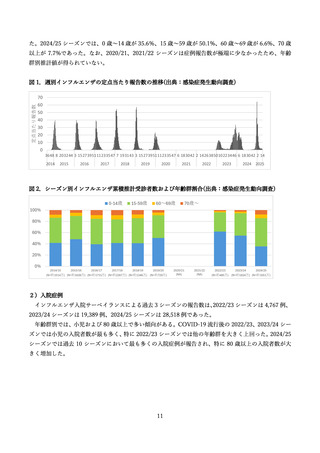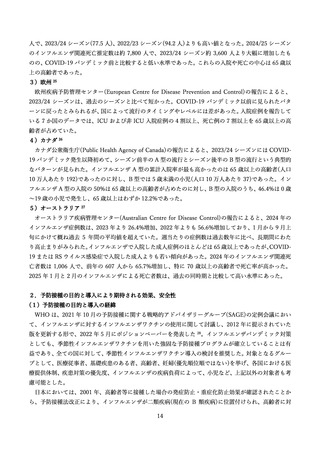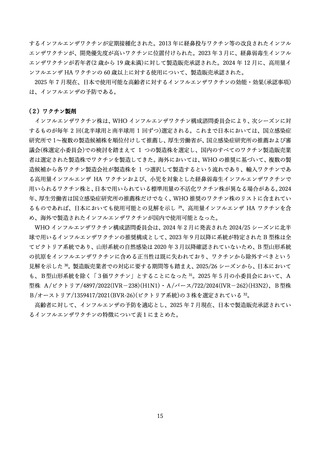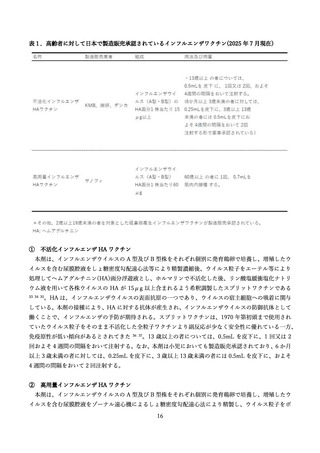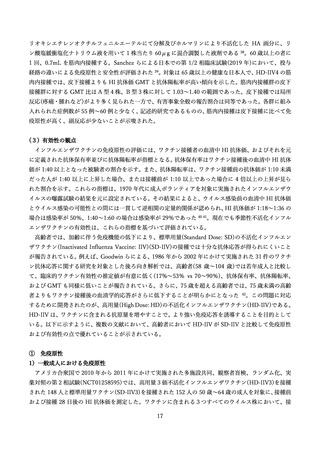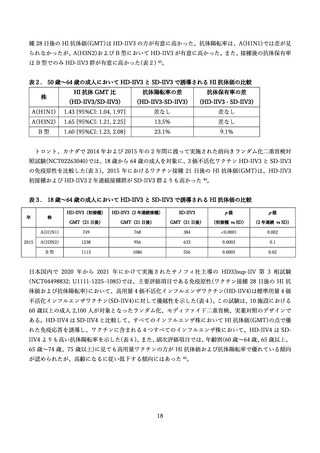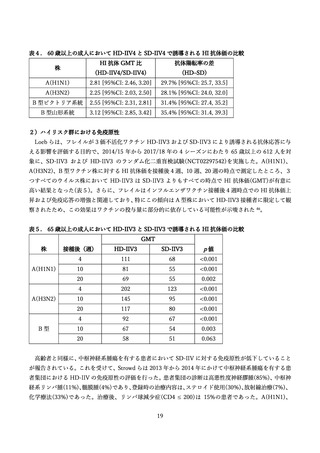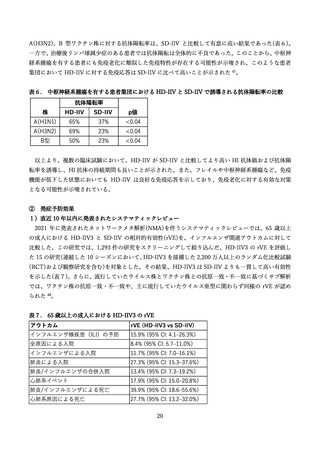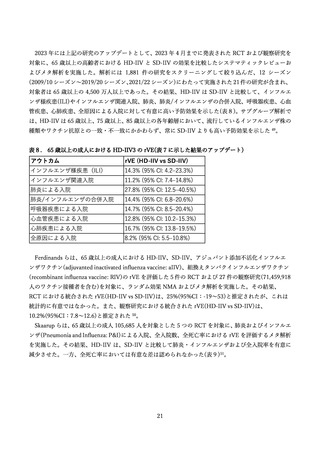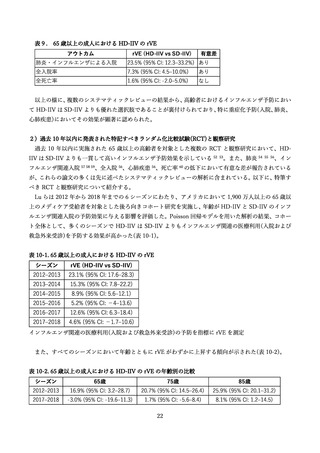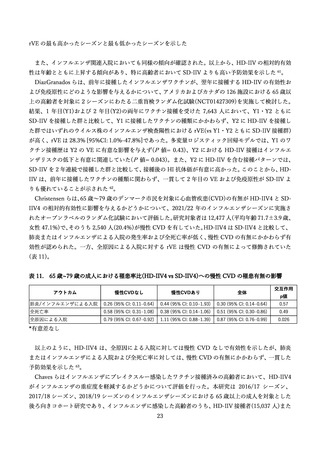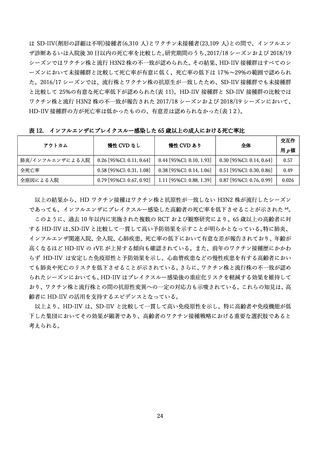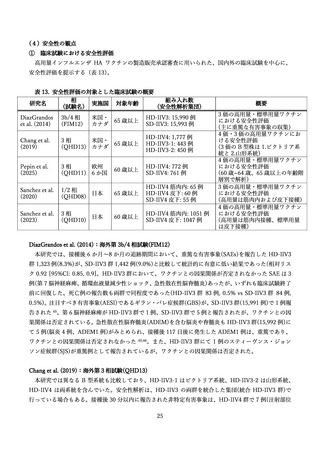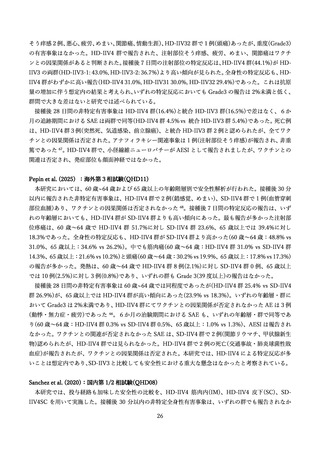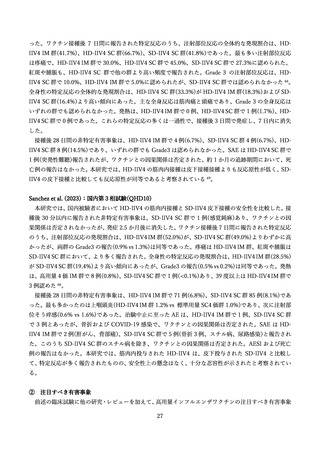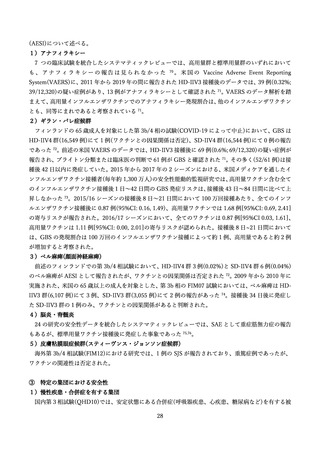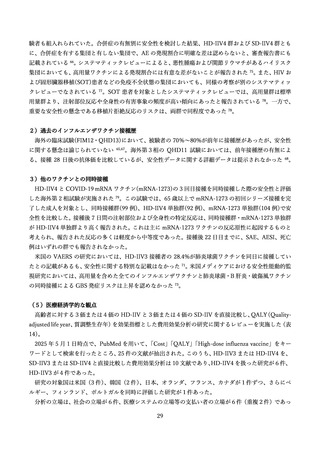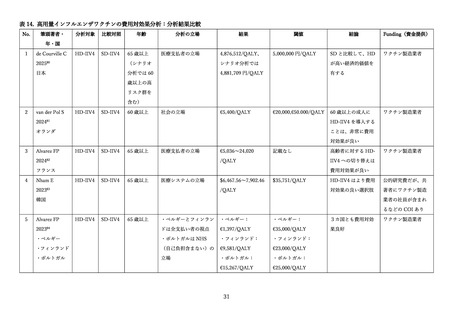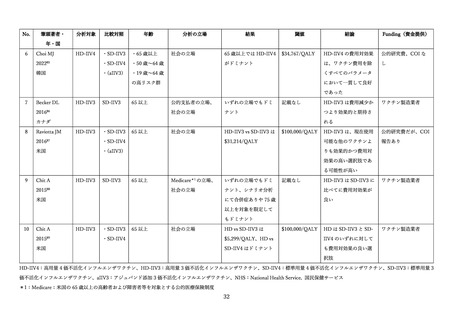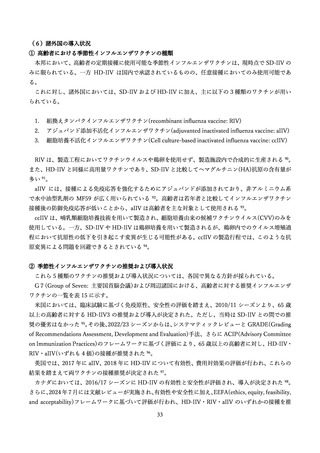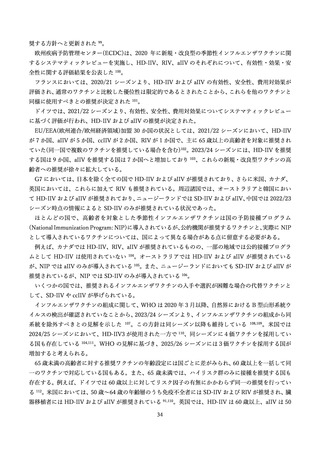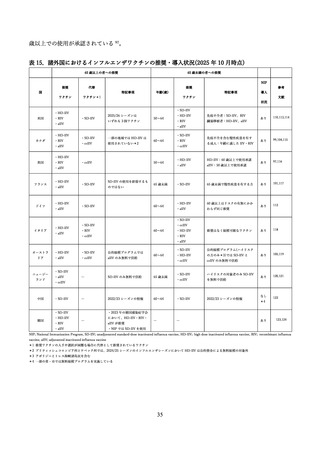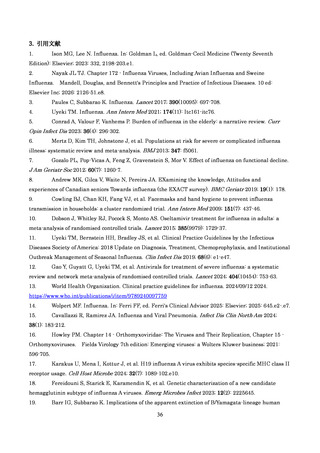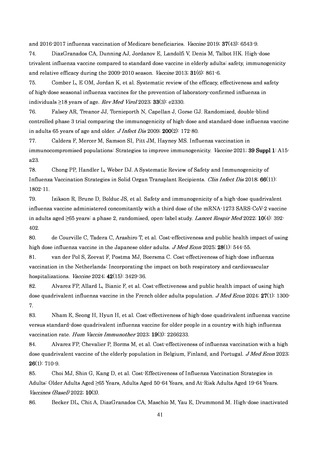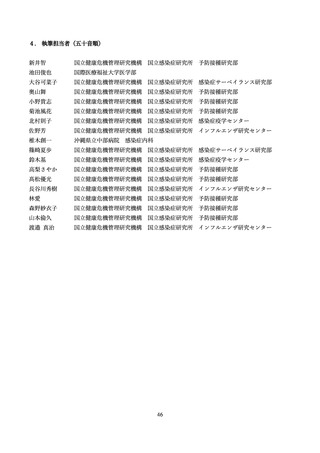よむ、つかう、まなぶ。
03資料1-1森野委員提出資料(高齢者に対するインフルエンザワクチンファクトシート) (9 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64997.html |
| 出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会 ワクチン評価に関する小委員会(第32回 10/22)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
存在し、H17 および H18 の HA 亜型、N10 および N11 の NA 亜型はコウモリから遺伝子が検出されて
いる(ただし、H17、H18、H19 亜型および N10、N11 亜型のウイルスは分離されていない) 16 17 18。A型
インフルエンザウイルスでは、十年〜数十年に一度の頻度で、これまでの流行株とは大きく異なる新しい
ウイルスが出現し、ヒトの間でインフルエンザの世界的な大流行(パンデミック)を引き起こすことがあ
る。一方、毎冬ヒトの間で流行しているウイルスは季節性インフルエンザウイルスと呼ばれ、A 型では
H1(H1pdm09)および H3 亜型、B 型ではビクトリア系統および山形系統(山形系統ウイルスは 2020 年以
降検出されていない 19)である。
⑥
検査法
1)ウイルス学的手法
(ア) ウイルス抗原の検出(迅速診断キット)
実臨床で広く用いられているのは、使用法が簡便で短時間でウイルス抗原の有無を判断出来る迅速診
断キットである。特異度は大変高いが、感度は次項のウイルス遺伝子検出法と比較して低く、検体の採材
時期によっては偽陰性となることがあるため、陰性結果の判断には注意が必要である。
(イ) ウイルス分離
病因の診断として最も直接的で信頼がおける手法である。分離には、主に培養細胞(MDCK 細胞)が用
いられている。検体(鼻咽頭拭い液など)を培養細胞に接種後、ウイルスが増殖すると感染した細胞に細胞
変性(細胞の丸まりや剥離など)が見られる。インフルエンザウイルスの確認には赤血球凝集試験や遺伝
子検査(リアルタイム PCR 法など)を実施する。亜型(A 型)や系統(B 型)の判定には、標準免疫血清を用
いた赤血球凝集抑制(HI)試験やノイラミニダーゼ抑制試験、あるいは遺伝子検査実施する。
2)遺伝学的手法
ウイルス遺伝子検査法
ウイルス遺伝子の検出も直接的な手法である。近年はリアルタイム PCR 法が一般的に使われている。
検体(鼻咽頭拭い液など)やウイルス培養液からウイルス遺伝子(RNA)を抽出し検査する。検出には、型、
亜型(A 型の場合)、および系統(B 型の場合)に特異的なプライマー・プローブを使用する。
3)血清学的手法
(ア) 赤血球凝集抑制(HI)試験法
インフルエンザウイルスの赤血球凝集性を利用した試験法で、血清(抗体)がどの程度凝集性を抑制す
るかを調べ、HI 抗体価を測定する。季節性インフルエンザウイルスの場合には、最近は一般的にモルモ
ット血球が使われているが、H1pdm09 亜型や B 型ウイルスには鶏や七面鳥血球でも問題がない。診断に
は、急性期(発症直後)と回復期(2 週間〜4 週間後)のペア血清が必要である。多くの人がインフルエンザ
ウイルスに対する抗体を保有しているため、回復期の血清のみでの診断は信頼性が低いために避けた方
がよい。急性期に比べて回復期で 4 倍以上の HI 抗体価の上昇が認められた場合、臨床所見等と総合して
インフルエンザウイルス感染の診断が可能となる。
(イ) 中和試験法
インフルエンザウイルスが培養細胞で増殖し細胞変性を起こすことを利用した試験法である。血清(抗
体)による細胞変性抑制(中和)を調べ、中和抗体価を測定する。
これらの手法は、ウイルス感染診断だけでなく、流行状況の把握、流行予測の基礎資料となる国民の抗
9
いる(ただし、H17、H18、H19 亜型および N10、N11 亜型のウイルスは分離されていない) 16 17 18。A型
インフルエンザウイルスでは、十年〜数十年に一度の頻度で、これまでの流行株とは大きく異なる新しい
ウイルスが出現し、ヒトの間でインフルエンザの世界的な大流行(パンデミック)を引き起こすことがあ
る。一方、毎冬ヒトの間で流行しているウイルスは季節性インフルエンザウイルスと呼ばれ、A 型では
H1(H1pdm09)および H3 亜型、B 型ではビクトリア系統および山形系統(山形系統ウイルスは 2020 年以
降検出されていない 19)である。
⑥
検査法
1)ウイルス学的手法
(ア) ウイルス抗原の検出(迅速診断キット)
実臨床で広く用いられているのは、使用法が簡便で短時間でウイルス抗原の有無を判断出来る迅速診
断キットである。特異度は大変高いが、感度は次項のウイルス遺伝子検出法と比較して低く、検体の採材
時期によっては偽陰性となることがあるため、陰性結果の判断には注意が必要である。
(イ) ウイルス分離
病因の診断として最も直接的で信頼がおける手法である。分離には、主に培養細胞(MDCK 細胞)が用
いられている。検体(鼻咽頭拭い液など)を培養細胞に接種後、ウイルスが増殖すると感染した細胞に細胞
変性(細胞の丸まりや剥離など)が見られる。インフルエンザウイルスの確認には赤血球凝集試験や遺伝
子検査(リアルタイム PCR 法など)を実施する。亜型(A 型)や系統(B 型)の判定には、標準免疫血清を用
いた赤血球凝集抑制(HI)試験やノイラミニダーゼ抑制試験、あるいは遺伝子検査実施する。
2)遺伝学的手法
ウイルス遺伝子検査法
ウイルス遺伝子の検出も直接的な手法である。近年はリアルタイム PCR 法が一般的に使われている。
検体(鼻咽頭拭い液など)やウイルス培養液からウイルス遺伝子(RNA)を抽出し検査する。検出には、型、
亜型(A 型の場合)、および系統(B 型の場合)に特異的なプライマー・プローブを使用する。
3)血清学的手法
(ア) 赤血球凝集抑制(HI)試験法
インフルエンザウイルスの赤血球凝集性を利用した試験法で、血清(抗体)がどの程度凝集性を抑制す
るかを調べ、HI 抗体価を測定する。季節性インフルエンザウイルスの場合には、最近は一般的にモルモ
ット血球が使われているが、H1pdm09 亜型や B 型ウイルスには鶏や七面鳥血球でも問題がない。診断に
は、急性期(発症直後)と回復期(2 週間〜4 週間後)のペア血清が必要である。多くの人がインフルエンザ
ウイルスに対する抗体を保有しているため、回復期の血清のみでの診断は信頼性が低いために避けた方
がよい。急性期に比べて回復期で 4 倍以上の HI 抗体価の上昇が認められた場合、臨床所見等と総合して
インフルエンザウイルス感染の診断が可能となる。
(イ) 中和試験法
インフルエンザウイルスが培養細胞で増殖し細胞変性を起こすことを利用した試験法である。血清(抗
体)による細胞変性抑制(中和)を調べ、中和抗体価を測定する。
これらの手法は、ウイルス感染診断だけでなく、流行状況の把握、流行予測の基礎資料となる国民の抗
9