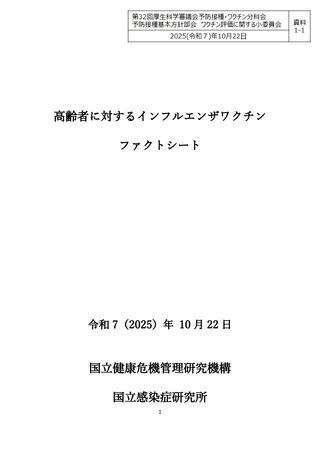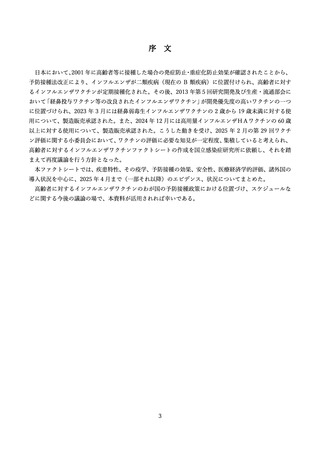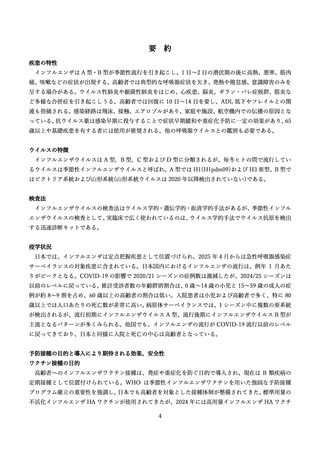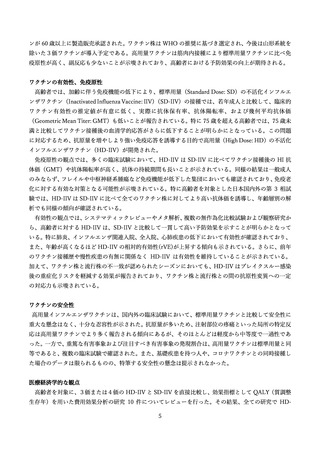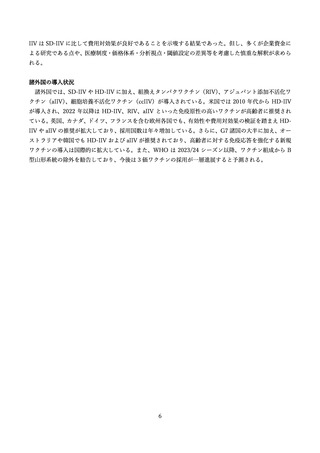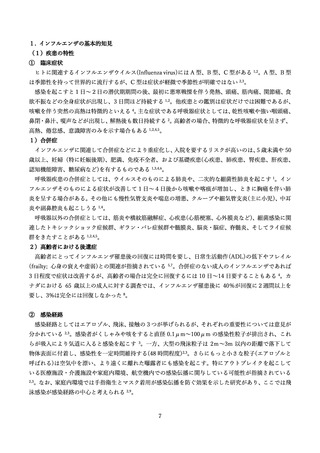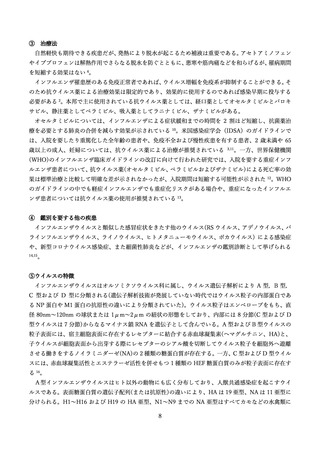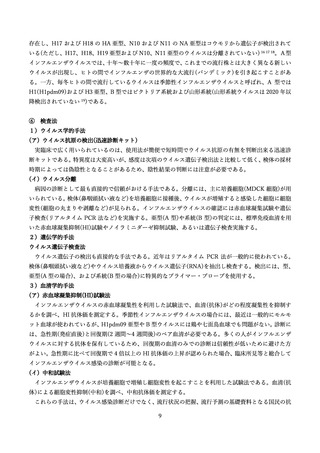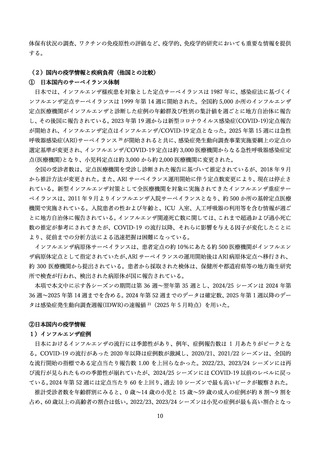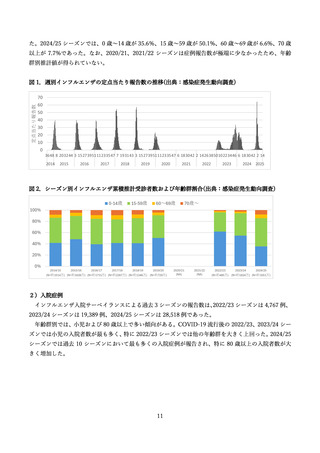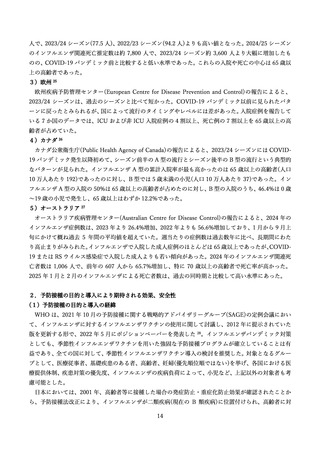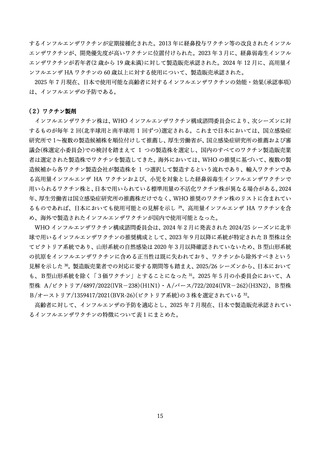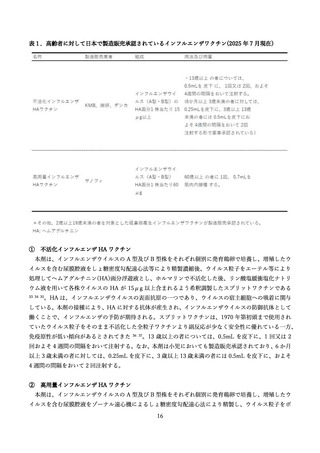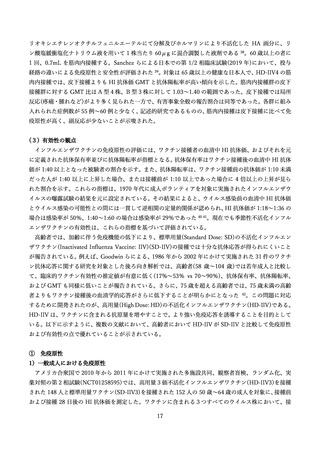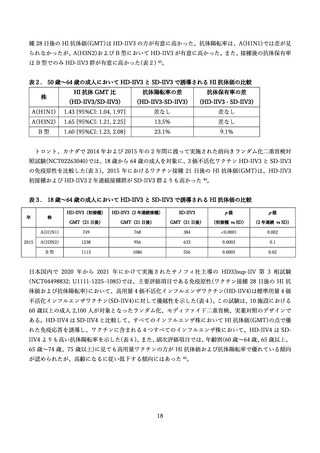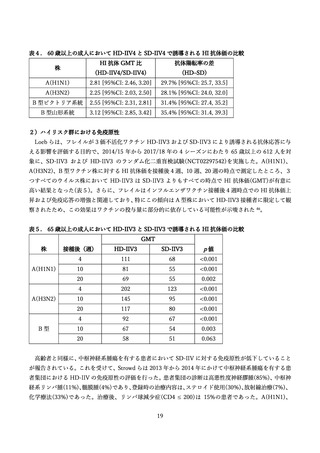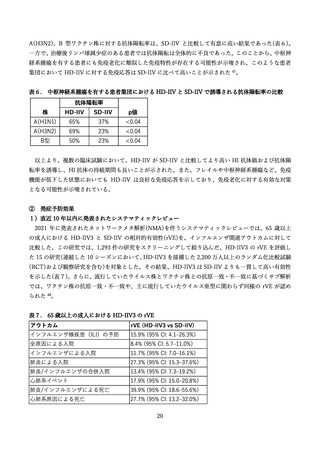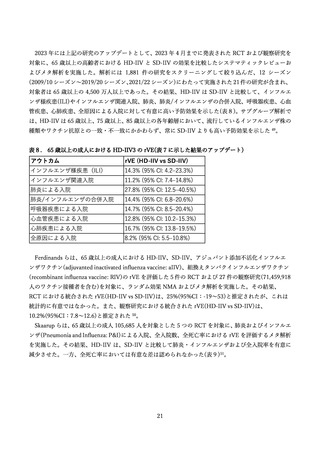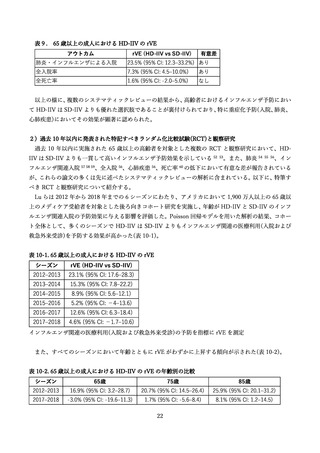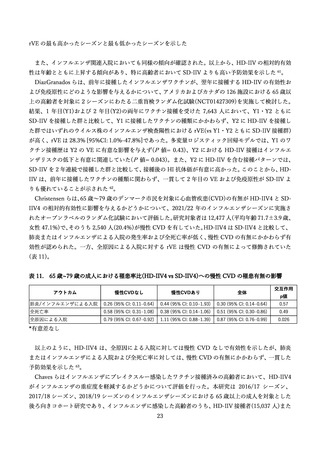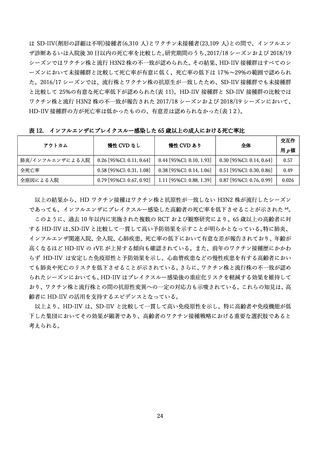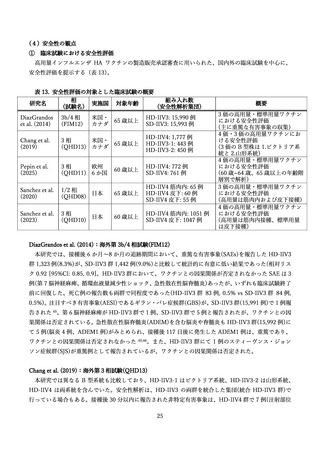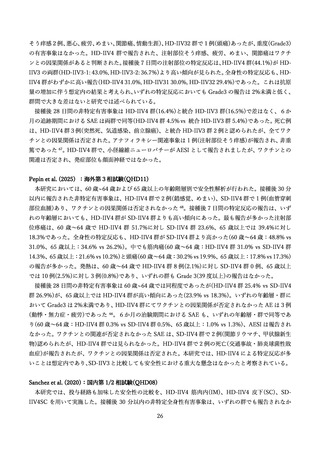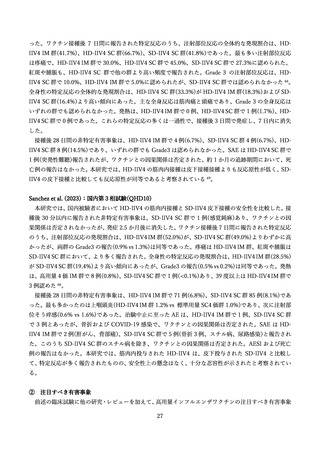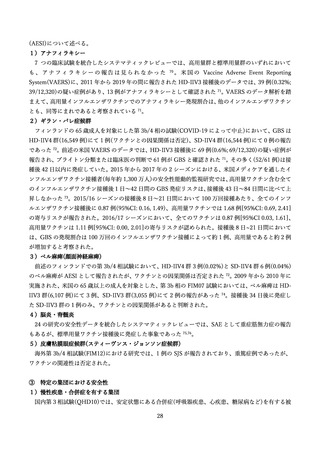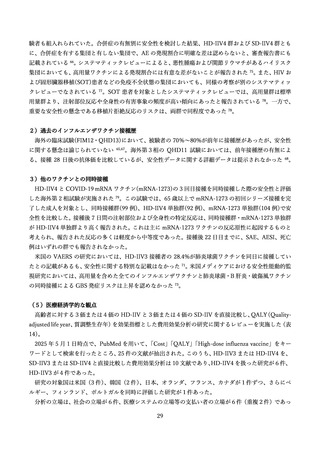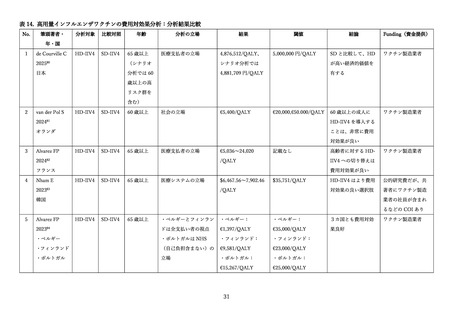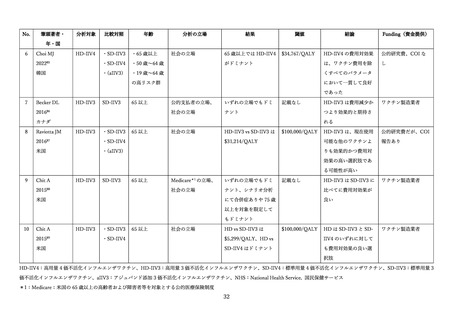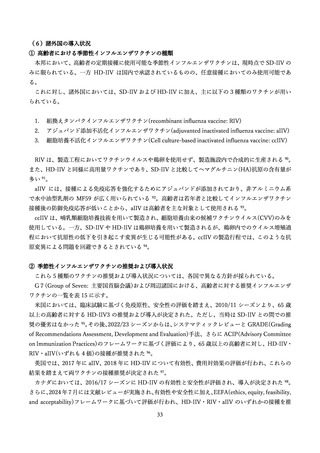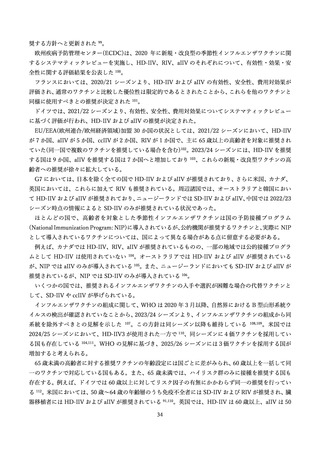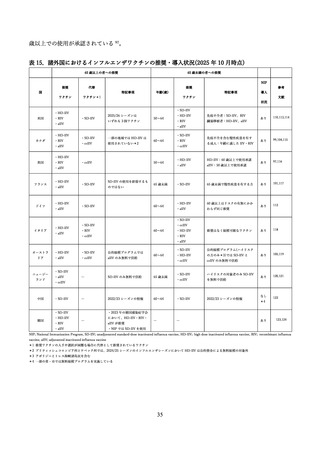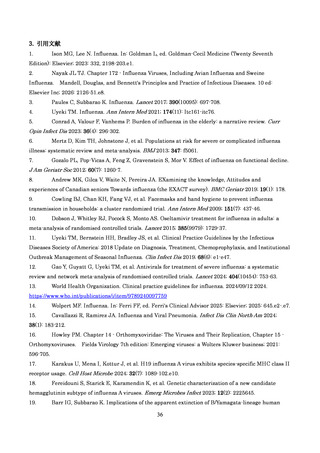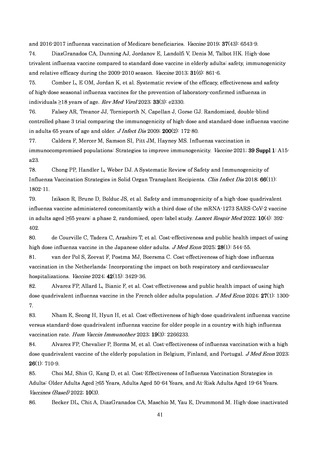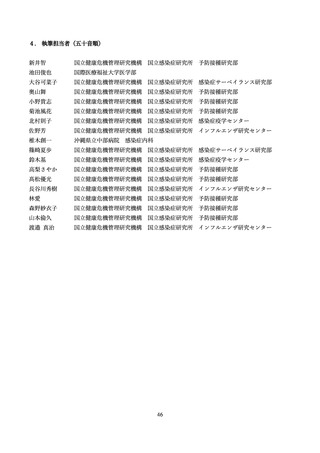よむ、つかう、まなぶ。
03資料1-1森野委員提出資料(高齢者に対するインフルエンザワクチンファクトシート) (8 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64997.html |
| 出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会 ワクチン評価に関する小委員会(第32回 10/22)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
③
治療法
自然軽快も期待できる疾患だが、発熱により脱水が起こるため補液は重要である。アセトアミノフェン
やイブプロフェンは解熱作用でさらなる脱水を防ぐとともに、悪寒や筋肉痛などを和らげるが、罹病期間
を短縮する効果はない 4。
インフルエンザ罹患歴のある免疫正常者であれば、ウイルス増幅を免疫系が抑制することができる。そ
のため抗ウイルス薬による治療効果は限定的であり、効果的に使用するのであれば感染早期に投与する
必要がある 2。本邦で主に使用されている抗ウイルス薬としては、経口薬としてオセルタミビルとバロキ
サビル、静注薬としてペラミビル、吸入薬としてラニナミビル、ザナミビルがある。
オセルタミビルについては、インフルエンザによる症状緩和までの時間を 2 割ほど短縮し、抗菌薬治
療を必要とする肺炎の合併を減らす効果が示されている 10。米国感染症学会(IDSA)のガイドラインで
は、入院を要したり重篤化した全年齢の患者や、免疫不全および慢性疾患を有する患者、2 歳未満や 65
歳以上の成人、妊婦については、抗ウイルス薬による治療が推奨されている 3,11。一方、世界保健機関
(WHO)のインフルエンザ臨床ガイドラインの改訂に向けて行われた研究では、入院を要する重症インフ
ルエンザ患者について、抗ウイルス薬(オセルタミビル、ペラミビルおよびザナミビル)による死亡率の効
果は標準治療と比較して明確な差が示されなかったが、入院期間は短縮する可能性が示された 12。WHO
のガイドラインの中でも軽症インフルエンザでも重症化リスクがある場合や、重症になったインフルエ
ンザ患者については抗ウイルス薬の使用が推奨されている 13。
④
鑑別を要する他の疾患
インフルエンザウイルスと類似した感冒症状をきたす他のウイルス(RS ウイルス、アデノウイルス、パ
ラインフルエンザウイルス、ライノウイルス、ヒトメタニューモウイルス、ボカウイルス)による感染症
や、新型コロナウイルス感染症、また細菌性肺炎などが、インフルエンザの鑑別診断として挙げられる
。
14,15
⑤ウイルスの特徴
インフルエンザウイルスはオルソミクソウイルス科に属し、ウイルス遺伝子解析により A 型,B 型,
C 型および D 型に分類される(遺伝子解析技術が発展していない時代ではウイルス粒子の内部蛋白であ
る NP 蛋白や M1 蛋白の抗原性の違いにより分類されていた)。ウイルス粒子はエンベロープをもち、直
径 80nm〜120nm の球状または 1μm〜2μm の紐状の形態をしており、内部には 8 分節(C 型および D
型ウイルスは 7 分節)からなるマイナス鎖 RNA を遺伝子として含んでいる。A 型および B 型ウイルスの
粒子表面には、宿主細胞表面に存在するレセプターに結合する赤血球凝集素(ヘマグルチニン、HA)と、
子ウイルスが細胞表面から出芽する際にレセプターのシアル酸を切断してウイルス粒子を細胞外へ遊離
させる働きをするノイラミニダーゼ(NA)の 2 種類の糖蛋白質が存在する。一方、C 型および D 型ウイル
スには、赤血球凝集活性とエステラーゼ活性を併せもつ 1 種類の HEF 糖蛋白質のみが粒子表面に存在す
る 16。
A型インフルエンザウイルスはヒト以外の動物にも広く分布しており、人獣共通感染症を起こすウイ
ルスである。表面糖蛋白質の遺伝子配列(または抗原性)の違いにより、HA は 19 亜型、NA は 11 亜型に
分けられる。H1〜H16 および H19 の HA 亜型、N1〜N9 までの NA 亜型はすべてカモなどの水禽類に
8
治療法
自然軽快も期待できる疾患だが、発熱により脱水が起こるため補液は重要である。アセトアミノフェン
やイブプロフェンは解熱作用でさらなる脱水を防ぐとともに、悪寒や筋肉痛などを和らげるが、罹病期間
を短縮する効果はない 4。
インフルエンザ罹患歴のある免疫正常者であれば、ウイルス増幅を免疫系が抑制することができる。そ
のため抗ウイルス薬による治療効果は限定的であり、効果的に使用するのであれば感染早期に投与する
必要がある 2。本邦で主に使用されている抗ウイルス薬としては、経口薬としてオセルタミビルとバロキ
サビル、静注薬としてペラミビル、吸入薬としてラニナミビル、ザナミビルがある。
オセルタミビルについては、インフルエンザによる症状緩和までの時間を 2 割ほど短縮し、抗菌薬治
療を必要とする肺炎の合併を減らす効果が示されている 10。米国感染症学会(IDSA)のガイドラインで
は、入院を要したり重篤化した全年齢の患者や、免疫不全および慢性疾患を有する患者、2 歳未満や 65
歳以上の成人、妊婦については、抗ウイルス薬による治療が推奨されている 3,11。一方、世界保健機関
(WHO)のインフルエンザ臨床ガイドラインの改訂に向けて行われた研究では、入院を要する重症インフ
ルエンザ患者について、抗ウイルス薬(オセルタミビル、ペラミビルおよびザナミビル)による死亡率の効
果は標準治療と比較して明確な差が示されなかったが、入院期間は短縮する可能性が示された 12。WHO
のガイドラインの中でも軽症インフルエンザでも重症化リスクがある場合や、重症になったインフルエ
ンザ患者については抗ウイルス薬の使用が推奨されている 13。
④
鑑別を要する他の疾患
インフルエンザウイルスと類似した感冒症状をきたす他のウイルス(RS ウイルス、アデノウイルス、パ
ラインフルエンザウイルス、ライノウイルス、ヒトメタニューモウイルス、ボカウイルス)による感染症
や、新型コロナウイルス感染症、また細菌性肺炎などが、インフルエンザの鑑別診断として挙げられる
。
14,15
⑤ウイルスの特徴
インフルエンザウイルスはオルソミクソウイルス科に属し、ウイルス遺伝子解析により A 型,B 型,
C 型および D 型に分類される(遺伝子解析技術が発展していない時代ではウイルス粒子の内部蛋白であ
る NP 蛋白や M1 蛋白の抗原性の違いにより分類されていた)。ウイルス粒子はエンベロープをもち、直
径 80nm〜120nm の球状または 1μm〜2μm の紐状の形態をしており、内部には 8 分節(C 型および D
型ウイルスは 7 分節)からなるマイナス鎖 RNA を遺伝子として含んでいる。A 型および B 型ウイルスの
粒子表面には、宿主細胞表面に存在するレセプターに結合する赤血球凝集素(ヘマグルチニン、HA)と、
子ウイルスが細胞表面から出芽する際にレセプターのシアル酸を切断してウイルス粒子を細胞外へ遊離
させる働きをするノイラミニダーゼ(NA)の 2 種類の糖蛋白質が存在する。一方、C 型および D 型ウイル
スには、赤血球凝集活性とエステラーゼ活性を併せもつ 1 種類の HEF 糖蛋白質のみが粒子表面に存在す
る 16。
A型インフルエンザウイルスはヒト以外の動物にも広く分布しており、人獣共通感染症を起こすウイ
ルスである。表面糖蛋白質の遺伝子配列(または抗原性)の違いにより、HA は 19 亜型、NA は 11 亜型に
分けられる。H1〜H16 および H19 の HA 亜型、N1〜N9 までの NA 亜型はすべてカモなどの水禽類に
8