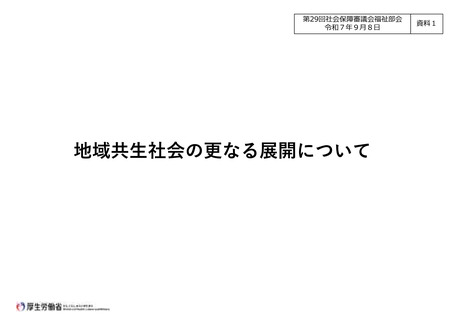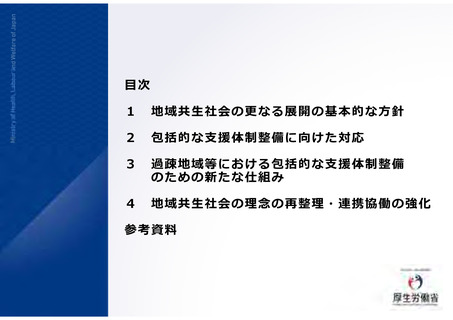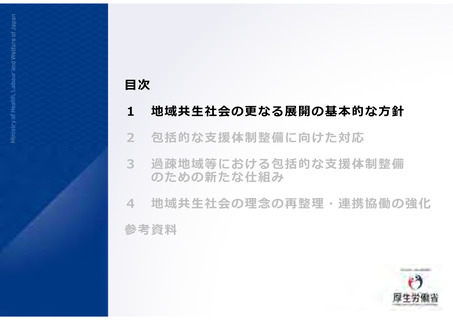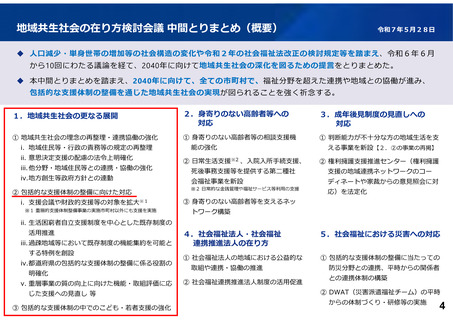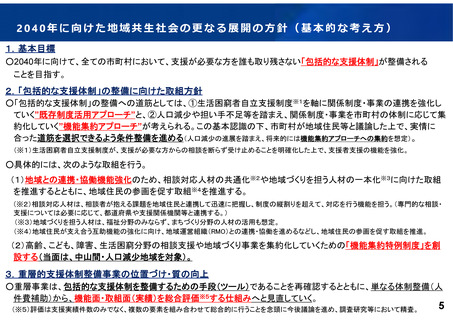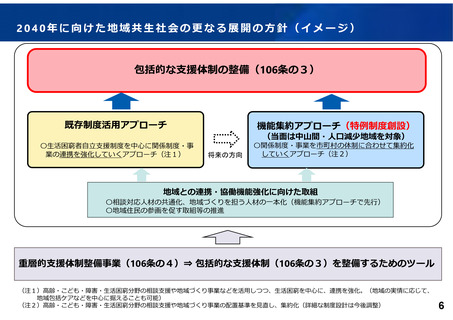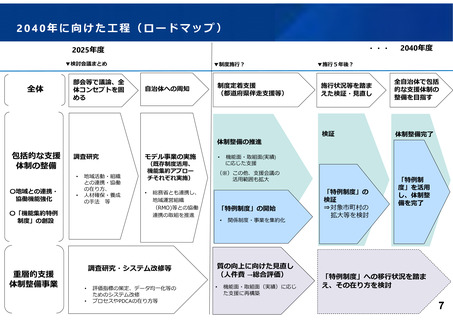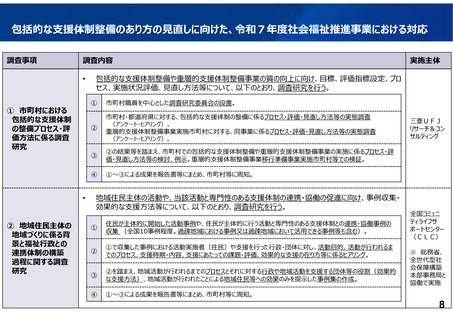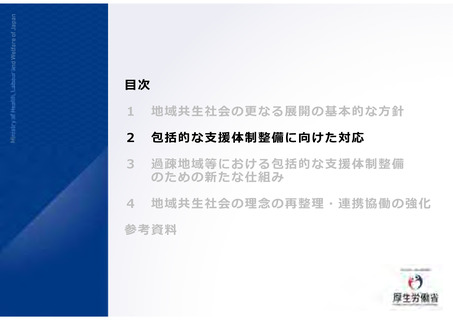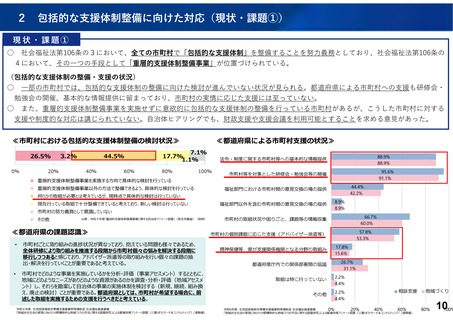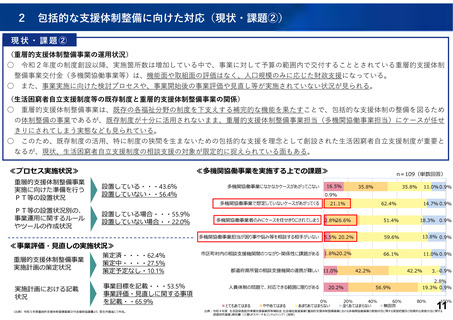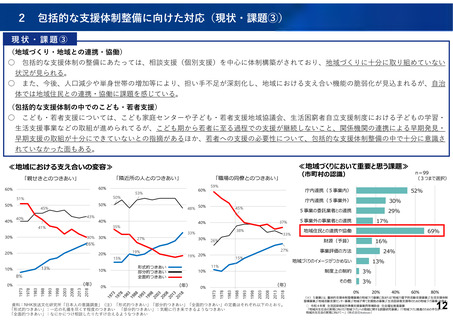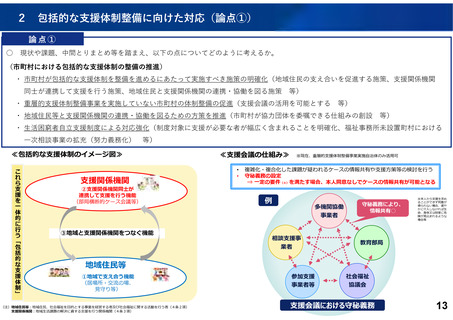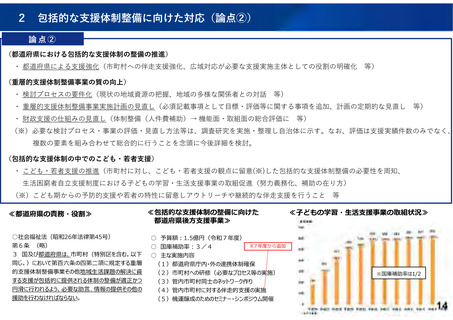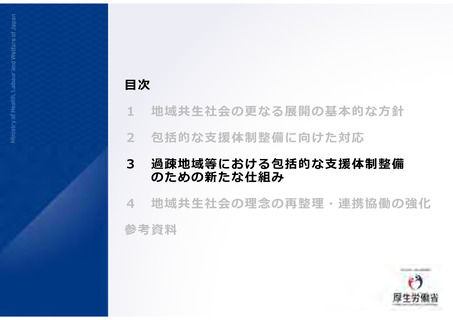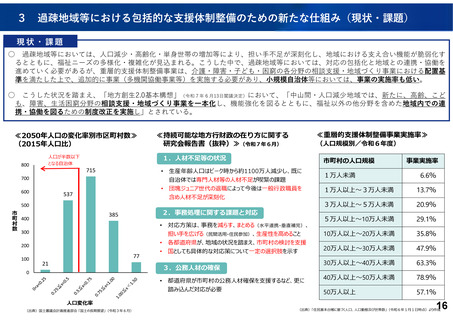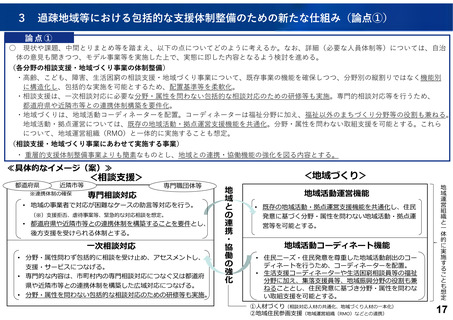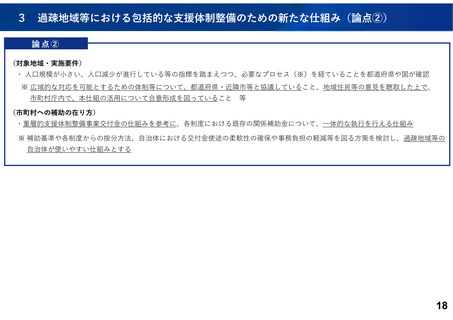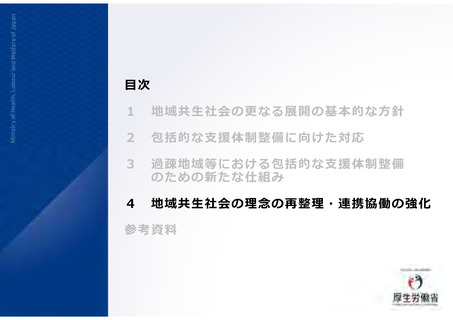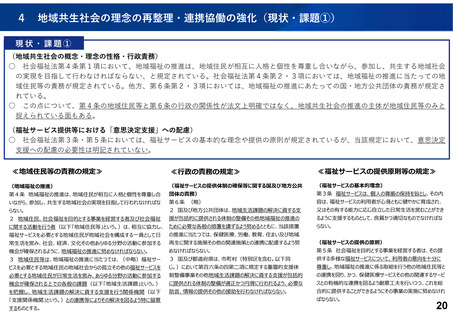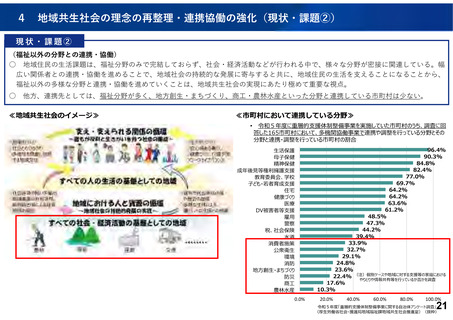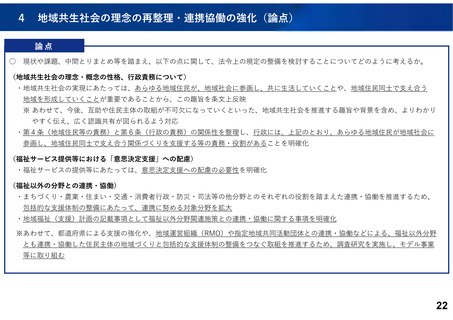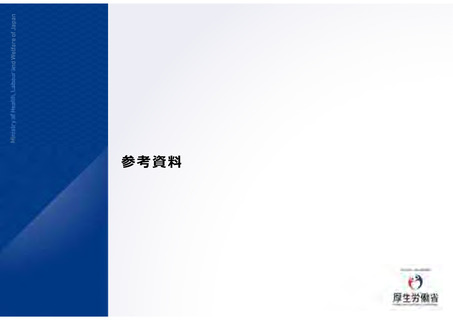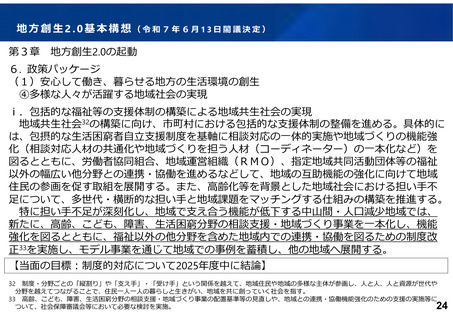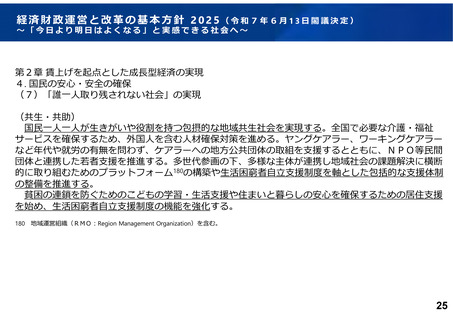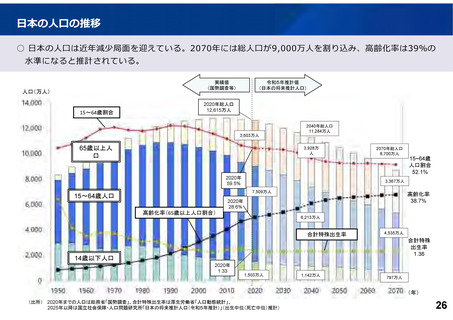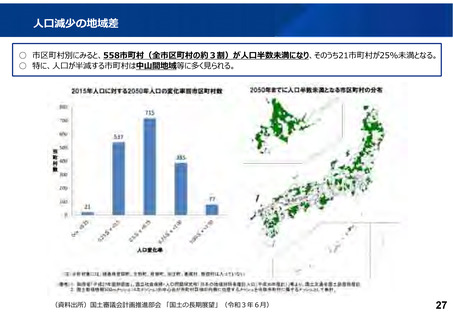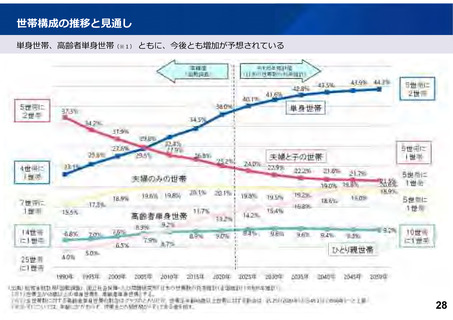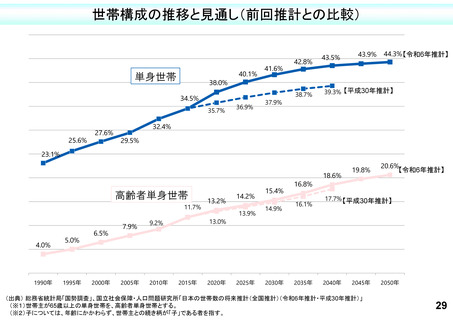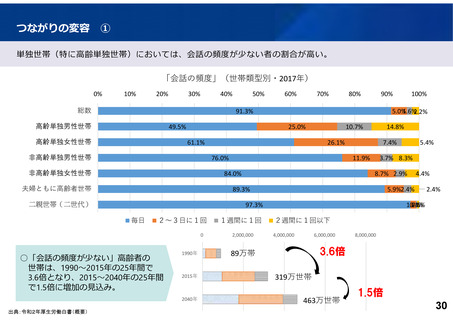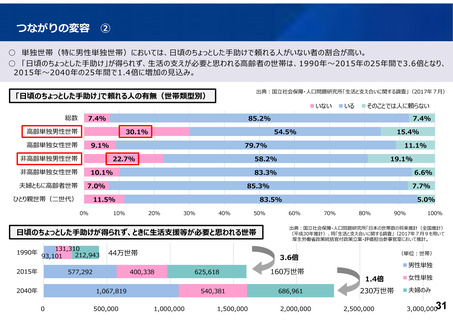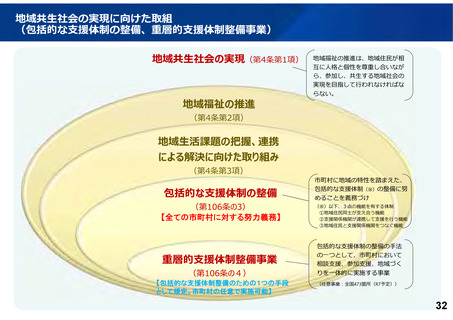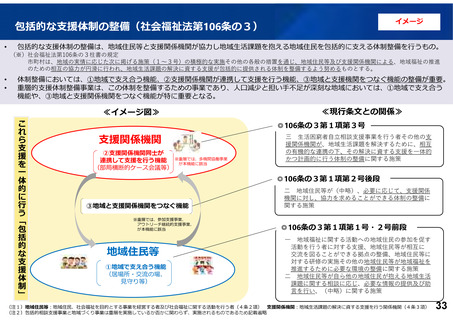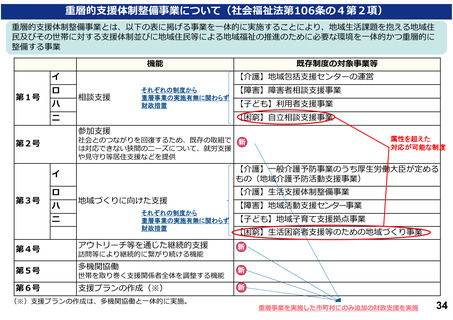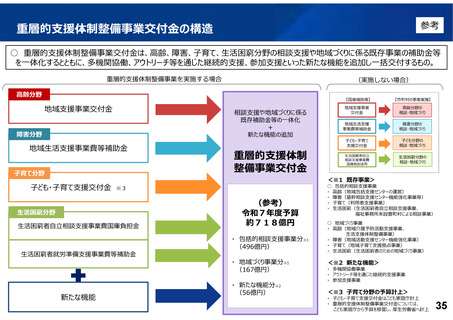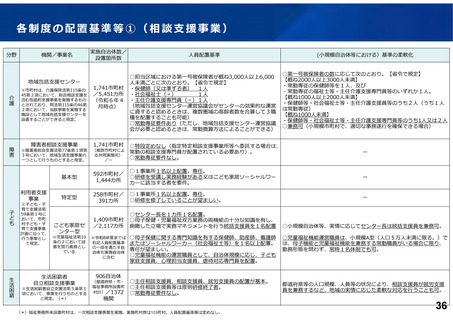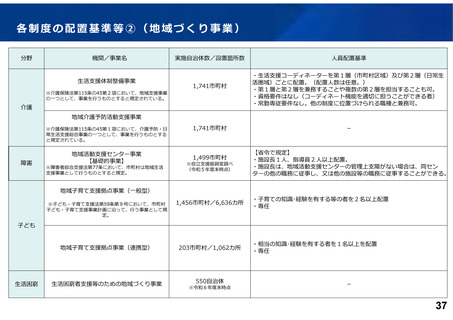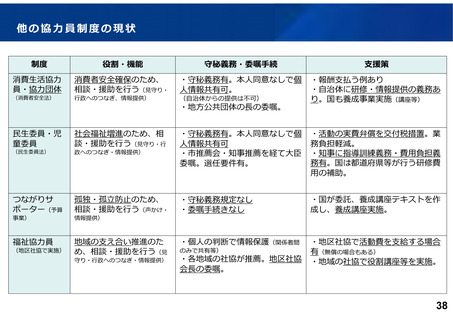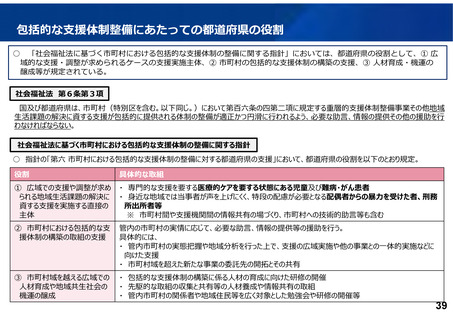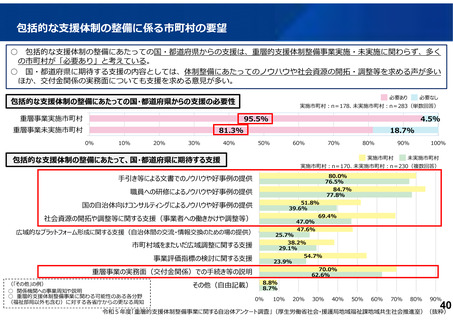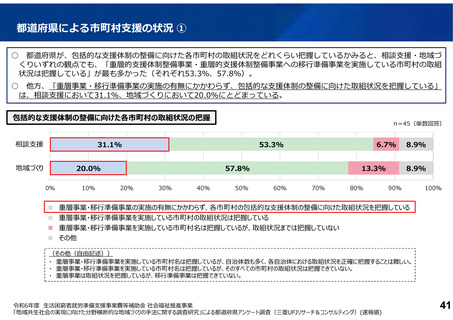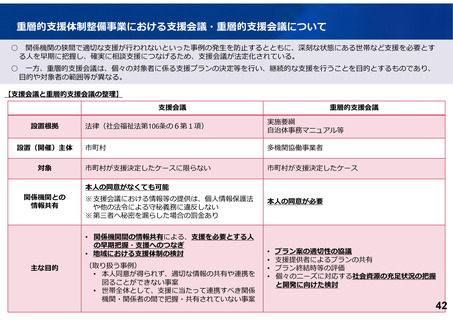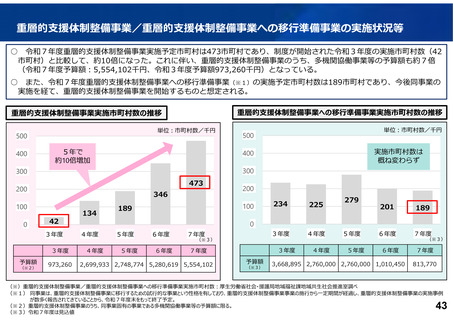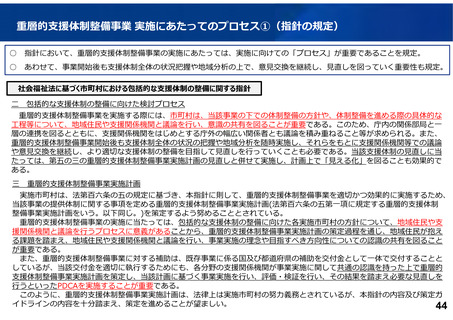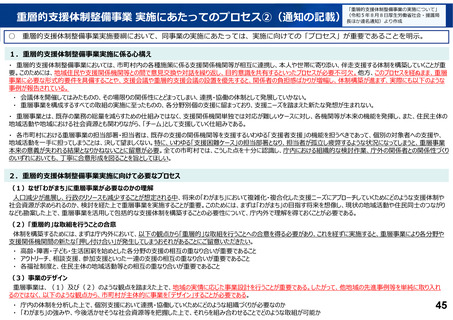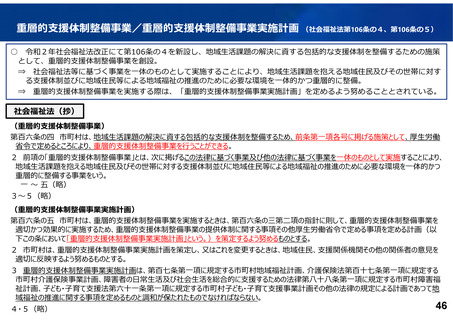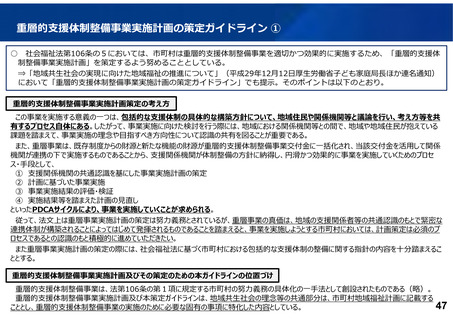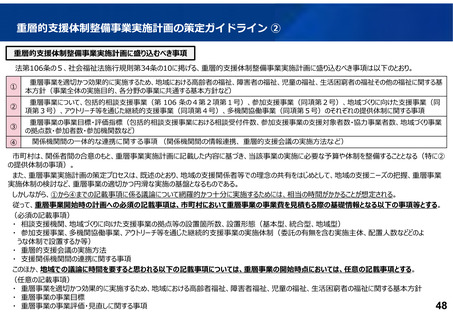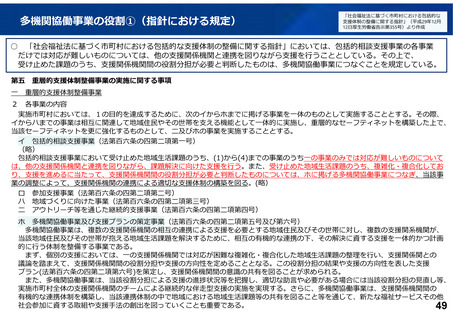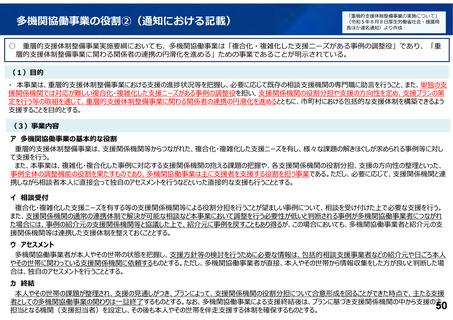よむ、つかう、まなぶ。
資料1 地域共生社会の更なる展開について (36 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63072.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 福祉部会(第29回 9/8)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
各制度の配置基準等①(相談支援事業)
分野
機関/事業名
地域包括支援センター
介護
※市町村は、介護保険法第115条の
45第2項において、総合相談支援を
含む包括的支援事業を実施するもの
とされており、同法第115条の46第
2項において、当該事業を実施する
施設として地域包括支援センターを
設置することができると規定。
障害
障害者相談支援事業
※障害差総合支援法第77条第1項第
3号において、地域生活支援事業の
一つとして行うものとすると規定。
利用者支援
事業
実施自治体数/
設置箇所数
1,741市町村
/5,451カ所
(令和6年4
月時点)
1,741市町村
(複数市町村によ
る共同実施可)
/ー
人員配置基準
○担当区域における第一号被保険者が概ね3,000人以上6,000
人未満ごとに次のとおり。【省令で規定】
・保健師(又は準ずる者) 1人
・社会福祉士(〃)
1人
・主任介護支援専門員(〃)1人
(地域包括支援センター運営協議会がセンターの効果的な運営
に資すると認めるときは、複数圏域の高齢者数を合算して3職
種を配置することも可能)
○常勤専従要件あり(ただし、地域包括支援センター運営協議
会が必要と認めるときは、常勤換算方法によることができる)
(小規模自治体等における)基準の柔軟化
○第一号被保険者の数に応じて次のとおり。【省令で規定】
【概ね2000人以上3000人未満】
・常勤専従の保健師等を1人、及び
・常勤専従の福祉士等・主任介護支援専門員等のいずれか1人。
【概ね1000人以上2000人未満】
・保健師等・社会福祉士等・主任介護支援員等のうち2人(うち1人
は常勤専従)
【概ね1000人未満】
・保健師等・社会福祉士等・主任介護支援専門員等のうち1人又は2人
○兼務可(小規模市町村で、適切な事務遂行を確保できる場合)
○特段定めなし(指定特定相談支援事業所等へ委託する場合は、
常勤の相談支援専門員が配置されている必要あり)。
○常勤専従要件なし。
ー
子ども
基本型
592市町村/
1,444カ所
○1事業所1名以上配置。専任。
○研修を受講し実務経験がある又はこども家庭ソーシャルワー
カーに該当する者を要件。
ー
特定型
258市町村/
391カ所
○1事業所1名以上配置。専任。
○研修を修了していることが望ましい。
ー
1,409市町村
/2,117カ所
○センター長を1カ所1名配置。
○母子保健・児童福祉双方業務の両機能の十分な知識を有し、
俯瞰した立場で実務マネジメントを行う統括支援員を1名配置
※子ども・子
育て支援法第
59条第1号に
おいて、市町
村子ども・子
こども家庭セ
育て支援事業
ンター型
計画に沿って、
※児童福祉法第10
行う事業とし
条の2において設
て規定。
置を努力義務とし
ている
生活困窮
生活困窮者
自立相談支援事業
※生活困窮者自立支援法第5条第1
項において、事業を行うものとする
と規定。(*)
※令和8年度までは
右記人員配置基準
の一部を満たす自
治体も実施自治体
に含む
906自治体
(都道府県・市・
福祉事務所設置町
村計)/1372
機関
○母子保健に関する専門知識を有する保健師、助産師、看護師
またはソーシャルワーカー(社会福祉士等)を1名以上配置。
専任が望ましい。
○児童福祉機能の運営職員として、自治体規模に応じ、子ども
家庭支援員、心理担当支援員、虐待対応専門員を配置。
○主任相談支援員、相談支援員、就労支援員の配置が基本。
○主任相談支援員等は原則研修終了者。
○常勤専従要件なし。
(*)福祉事務所未設置町村は、一次相談支援事業を実施。実施町村数は103町村。人員配置基準等は定めなし。
○小規模自治体等、実情に応じてセンター長は統括支援員を兼務可。
○児童福祉機能運営職員は、小規模A型(人口5万人未満に限る。)で
は、母子機能と児童福祉機能を兼務する常勤職員がいる場合に限り、
勤務形態を問わず、常時1名体制でも可。
都道府県等の人口規模、人員等の状況により、相談支援員が就労支援
員を兼務するなど、地域の実情に応じた柔軟な対応を行うことも可。
36
分野
機関/事業名
地域包括支援センター
介護
※市町村は、介護保険法第115条の
45第2項において、総合相談支援を
含む包括的支援事業を実施するもの
とされており、同法第115条の46第
2項において、当該事業を実施する
施設として地域包括支援センターを
設置することができると規定。
障害
障害者相談支援事業
※障害差総合支援法第77条第1項第
3号において、地域生活支援事業の
一つとして行うものとすると規定。
利用者支援
事業
実施自治体数/
設置箇所数
1,741市町村
/5,451カ所
(令和6年4
月時点)
1,741市町村
(複数市町村によ
る共同実施可)
/ー
人員配置基準
○担当区域における第一号被保険者が概ね3,000人以上6,000
人未満ごとに次のとおり。【省令で規定】
・保健師(又は準ずる者) 1人
・社会福祉士(〃)
1人
・主任介護支援専門員(〃)1人
(地域包括支援センター運営協議会がセンターの効果的な運営
に資すると認めるときは、複数圏域の高齢者数を合算して3職
種を配置することも可能)
○常勤専従要件あり(ただし、地域包括支援センター運営協議
会が必要と認めるときは、常勤換算方法によることができる)
(小規模自治体等における)基準の柔軟化
○第一号被保険者の数に応じて次のとおり。【省令で規定】
【概ね2000人以上3000人未満】
・常勤専従の保健師等を1人、及び
・常勤専従の福祉士等・主任介護支援専門員等のいずれか1人。
【概ね1000人以上2000人未満】
・保健師等・社会福祉士等・主任介護支援員等のうち2人(うち1人
は常勤専従)
【概ね1000人未満】
・保健師等・社会福祉士等・主任介護支援専門員等のうち1人又は2人
○兼務可(小規模市町村で、適切な事務遂行を確保できる場合)
○特段定めなし(指定特定相談支援事業所等へ委託する場合は、
常勤の相談支援専門員が配置されている必要あり)。
○常勤専従要件なし。
ー
子ども
基本型
592市町村/
1,444カ所
○1事業所1名以上配置。専任。
○研修を受講し実務経験がある又はこども家庭ソーシャルワー
カーに該当する者を要件。
ー
特定型
258市町村/
391カ所
○1事業所1名以上配置。専任。
○研修を修了していることが望ましい。
ー
1,409市町村
/2,117カ所
○センター長を1カ所1名配置。
○母子保健・児童福祉双方業務の両機能の十分な知識を有し、
俯瞰した立場で実務マネジメントを行う統括支援員を1名配置
※子ども・子
育て支援法第
59条第1号に
おいて、市町
村子ども・子
こども家庭セ
育て支援事業
ンター型
計画に沿って、
※児童福祉法第10
行う事業とし
条の2において設
て規定。
置を努力義務とし
ている
生活困窮
生活困窮者
自立相談支援事業
※生活困窮者自立支援法第5条第1
項において、事業を行うものとする
と規定。(*)
※令和8年度までは
右記人員配置基準
の一部を満たす自
治体も実施自治体
に含む
906自治体
(都道府県・市・
福祉事務所設置町
村計)/1372
機関
○母子保健に関する専門知識を有する保健師、助産師、看護師
またはソーシャルワーカー(社会福祉士等)を1名以上配置。
専任が望ましい。
○児童福祉機能の運営職員として、自治体規模に応じ、子ども
家庭支援員、心理担当支援員、虐待対応専門員を配置。
○主任相談支援員、相談支援員、就労支援員の配置が基本。
○主任相談支援員等は原則研修終了者。
○常勤専従要件なし。
(*)福祉事務所未設置町村は、一次相談支援事業を実施。実施町村数は103町村。人員配置基準等は定めなし。
○小規模自治体等、実情に応じてセンター長は統括支援員を兼務可。
○児童福祉機能運営職員は、小規模A型(人口5万人未満に限る。)で
は、母子機能と児童福祉機能を兼務する常勤職員がいる場合に限り、
勤務形態を問わず、常時1名体制でも可。
都道府県等の人口規模、人員等の状況により、相談支援員が就労支援
員を兼務するなど、地域の実情に応じた柔軟な対応を行うことも可。
36