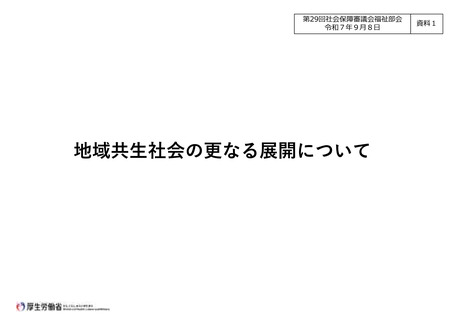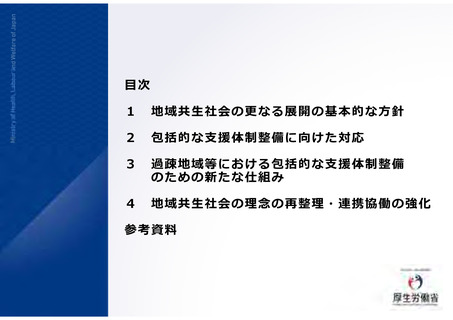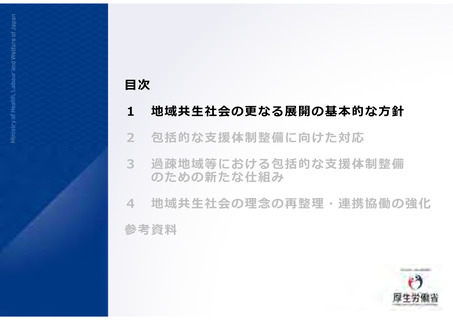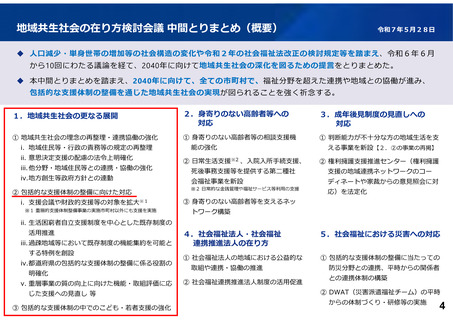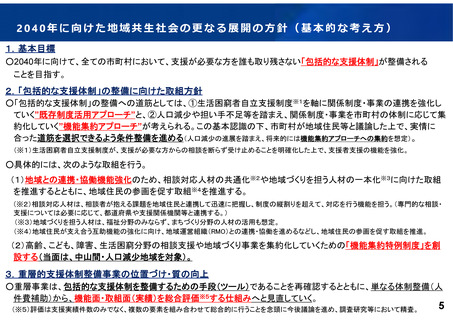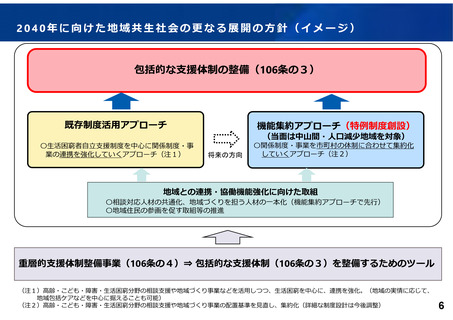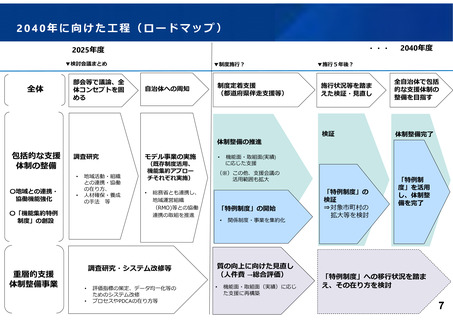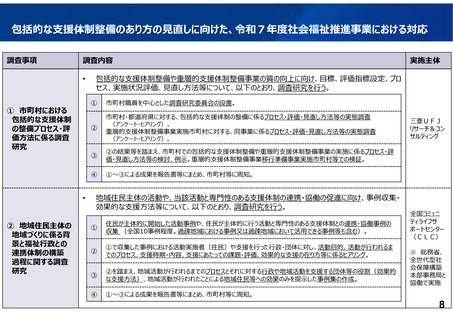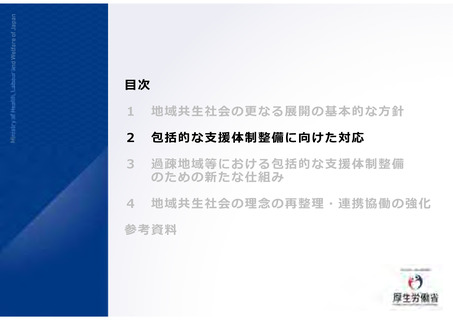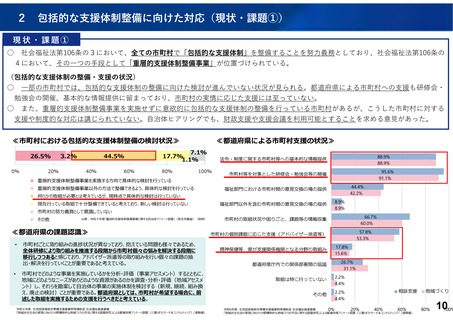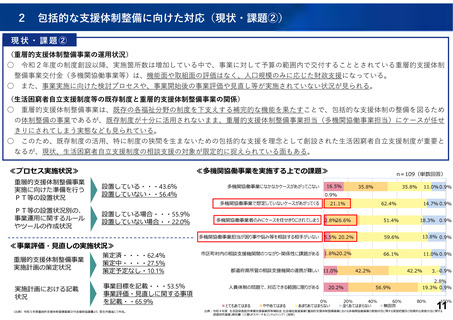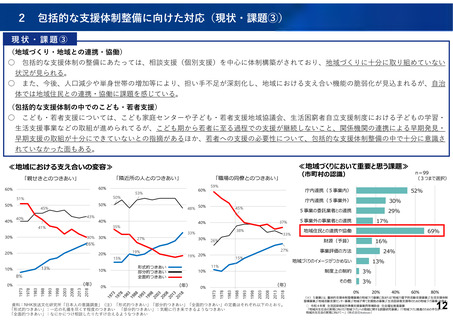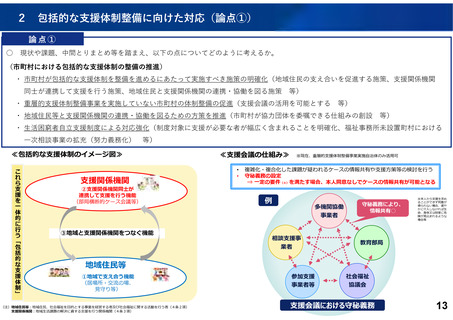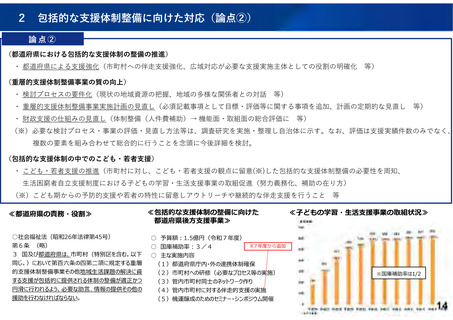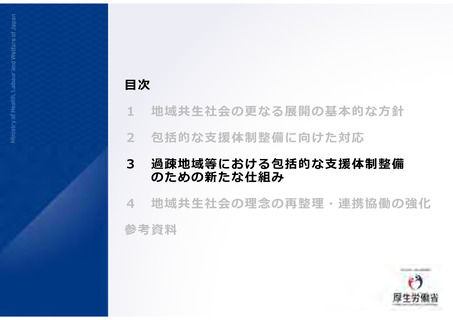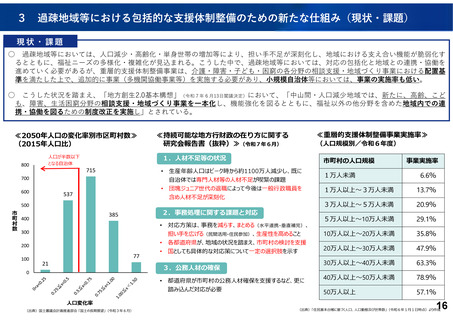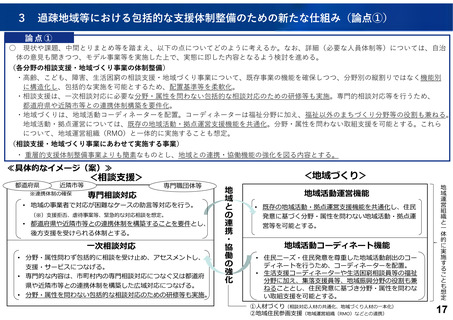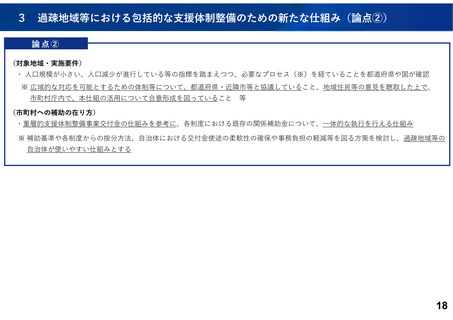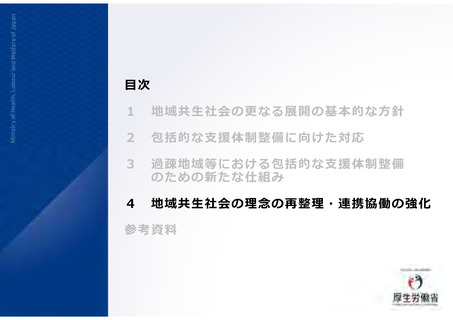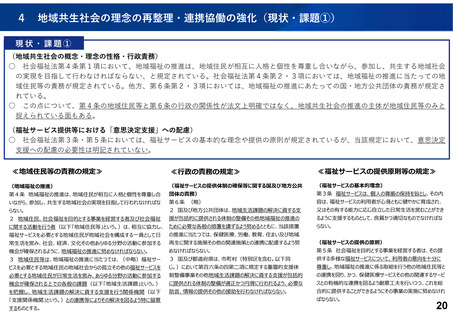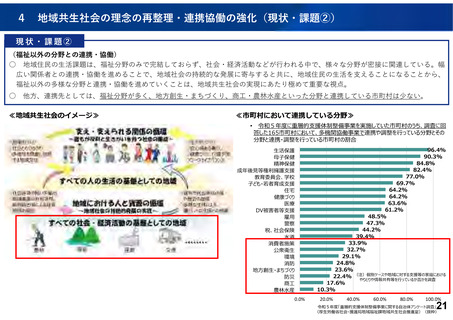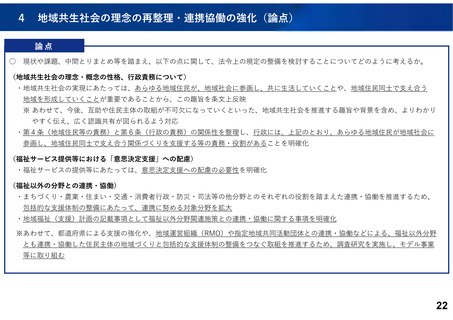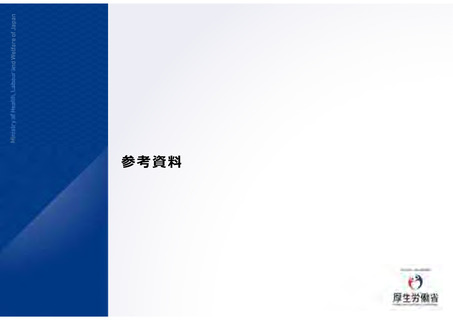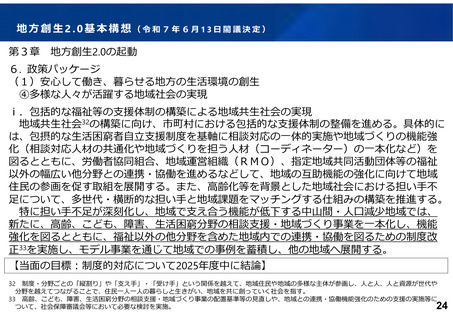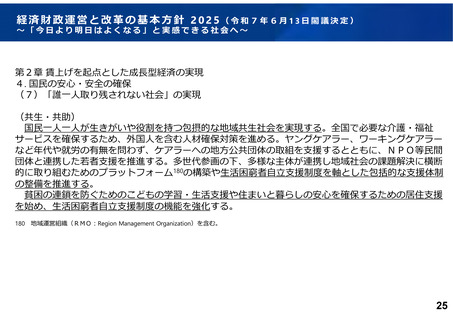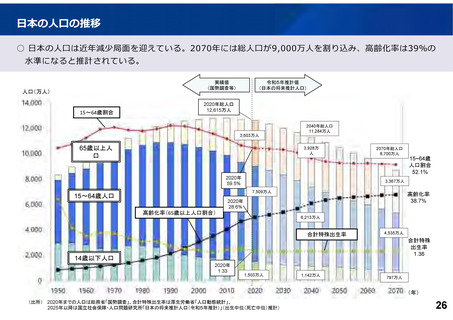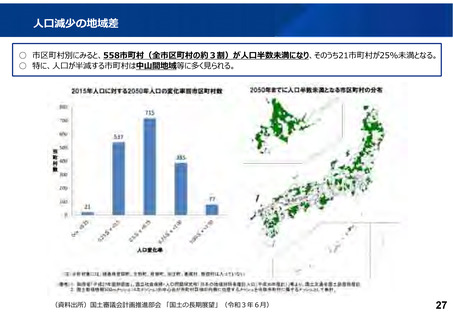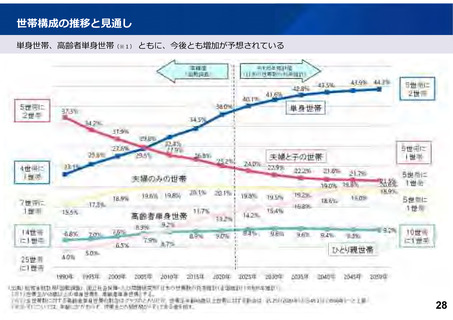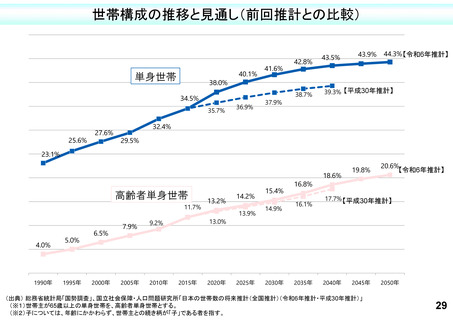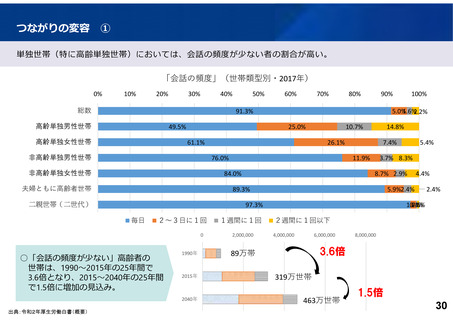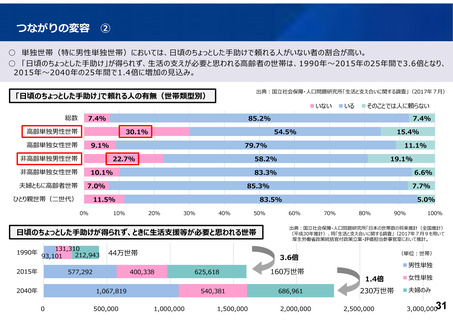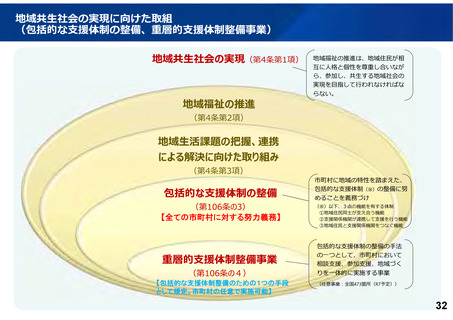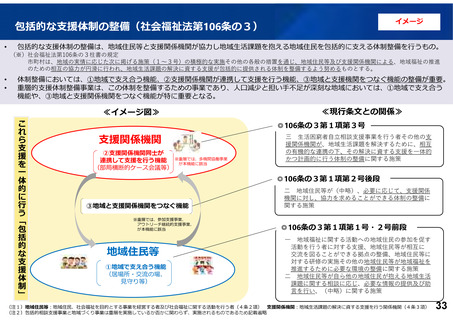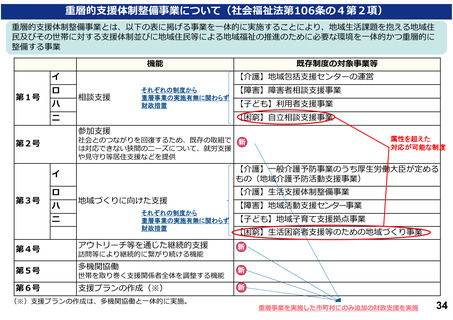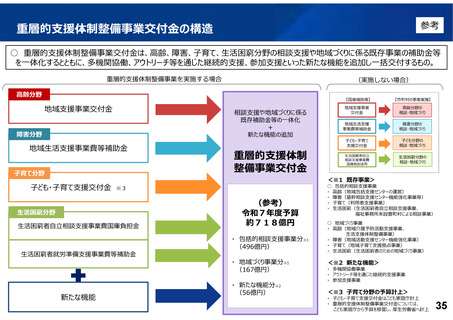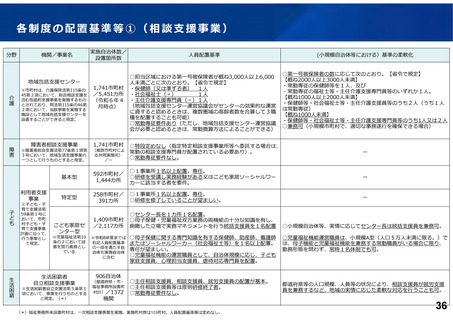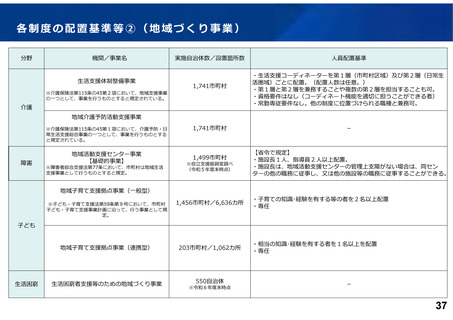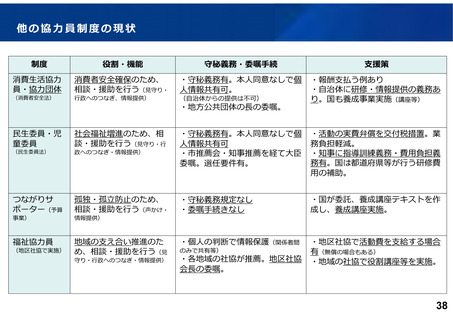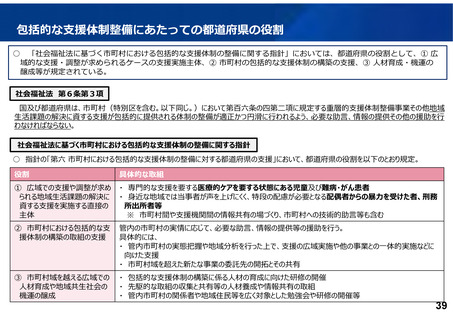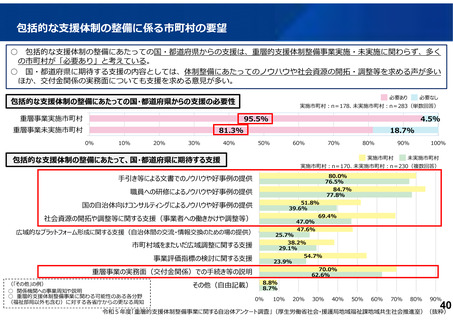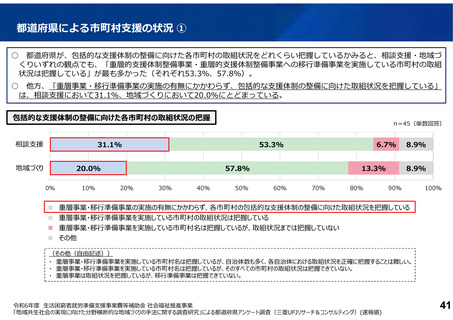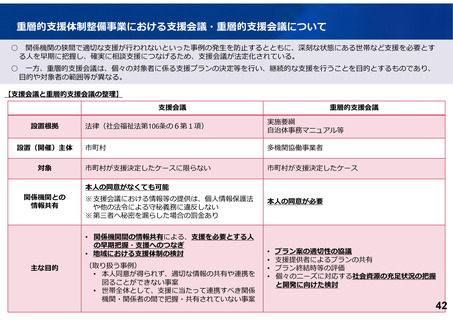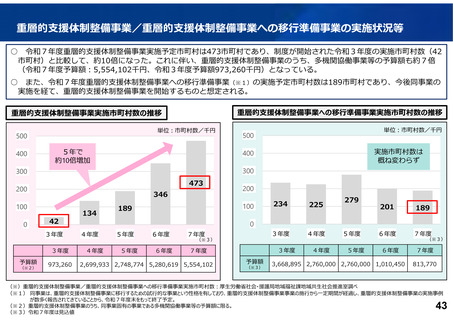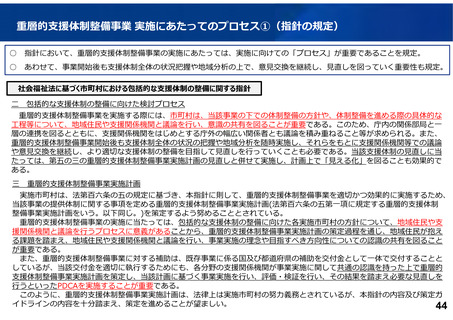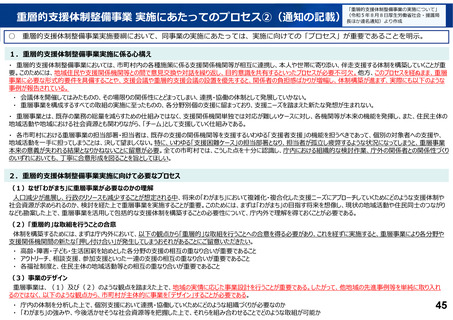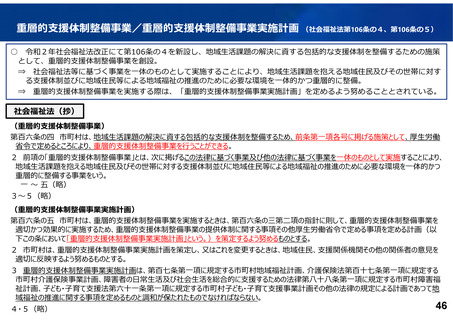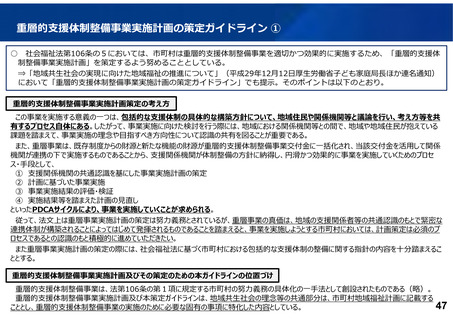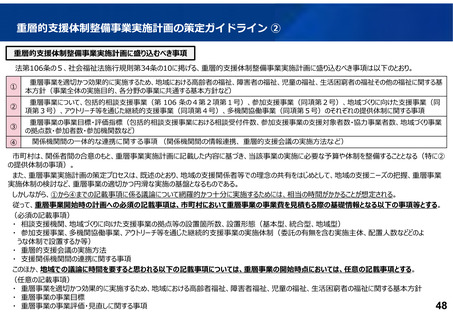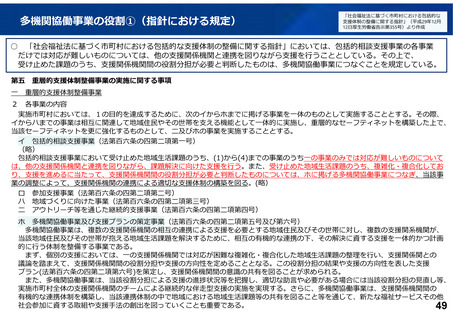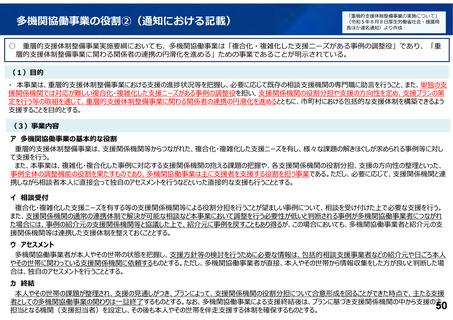よむ、つかう、まなぶ。
資料1 地域共生社会の更なる展開について (20 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63072.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 福祉部会(第29回 9/8)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
4
地域共生社会の理念の再整理・連携協働の強化(現状・課題①)
現状・課題①
(地域共生社会の概念・理念の性格・行政責務)
○ 社会福祉法第4条第1項において、地域福祉の推進は、地域住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、参加し、共生する地域社会
の実現を目指して行わなければならない、と規定されている。社会福祉法第4条第2・3項においては、地域福祉の推進に当たっての地
域住民等の責務が規定されている。他方、第6条第2・3項においては、地域福祉の推進にあたっての国・地方公共団体の責務が規定さ
れている。
○ この点について、第4条の地域住民等と第6条の行政の関係性が法文上明確ではなく、地域共生社会の推進の主体が地域住民等のみと
捉えられている面もある。
(福祉サービス提供等における「意思決定支援」への配慮)
○ 社会福祉法第3条・第5条においては、福祉サービスの基本的な理念や提供の原則が規定されているが、当該規定において、意思決定
支援への配慮の必要性は明記されていない。
≪地域住民等の責務の規定≫
≪行政の責務の規定≫
≪福祉サービスの提供原則等の規定≫
(地域福祉の推進)
(福祉サービスの提供体制の確保等に関する国及び地方公共
(福祉サービスの基本的理念)
第4条 地域福祉の推進は、地域住民が相互に人格と個性を尊重し合
団体の責務)
第3条 福祉サービスは、個人の尊厳の保持を旨とし、その内
いながら、参加し、共生する地域社会の実現を目指して行われなければな
第6条 (略)
容は、福祉サービスの利用者が心身ともに健やかに育成され、
らない。
2 国及び地方公共団体は、地域生活課題の解決に資する支
又はその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができ
2 地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉
援が包括的に提供される体制の整備その他地域福祉の推進の
るように支援するものとして、良質かつ適切なものでなければな
に関する活動を行う者(以下「地域住民等」という。)は、相互に協力し、 ために必要な各般の措置を講ずるよう努めるとともに、当該措置
の推進に当たつては、保健医療、労働、教育、住まい及び地域
福祉サービスを必要とする地域住民が地域社会を構成する一員として日
らない。
常生活を営み、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する
再生に関する施策その他の関連施策との連携に配慮するよう努
(福祉サービスの提供の原則)
機会が確保されるように、地域福祉の推進に努めなければならない。
めなければならない。
第5条 社会福祉を目的とする事業を経営する者は、その提
3 地域住民等は、地域福祉の推進に当たつては、(中略)福祉サー
3 国及び都道府県は、市町村(特別区を含む。以下同
供する多様な福祉サービスについて、利用者の意向を十分に
ビスを必要とする地域住民の地域社会からの孤立その他の福祉サービスを
じ。)において第百六条の四第二項に規定する重層的支援体
尊重し、地域福祉の推進に係る取組を行う他の地域住民等と
必要とする地域住民が日常生活を営み、あらゆる分野の活動に参加する
制整備事業その他地域生活課題の解決に資する支援が包括的
の連携を図り、かつ、保健医療サービスその他の関連するサービ
機会が確保される上での各般の課題(以下「地域生活課題」という。)
に提供される体制の整備が適正かつ円滑に行われるよう、必要な
スとの有機的な連携を図るよう創意工夫を行いつつ、これを総
を把握し、地域生活課題の解決に資する支援を行う関係機関(以下
助言、情報の提供その他の援助を行わなければならない。
合的に提供することができるようにその事業の実施に努めなけれ
「支援関係機関」という。)との連携等によりその解決を図るよう特に留意
するものとする。
ばならない。
20
地域共生社会の理念の再整理・連携協働の強化(現状・課題①)
現状・課題①
(地域共生社会の概念・理念の性格・行政責務)
○ 社会福祉法第4条第1項において、地域福祉の推進は、地域住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、参加し、共生する地域社会
の実現を目指して行わなければならない、と規定されている。社会福祉法第4条第2・3項においては、地域福祉の推進に当たっての地
域住民等の責務が規定されている。他方、第6条第2・3項においては、地域福祉の推進にあたっての国・地方公共団体の責務が規定さ
れている。
○ この点について、第4条の地域住民等と第6条の行政の関係性が法文上明確ではなく、地域共生社会の推進の主体が地域住民等のみと
捉えられている面もある。
(福祉サービス提供等における「意思決定支援」への配慮)
○ 社会福祉法第3条・第5条においては、福祉サービスの基本的な理念や提供の原則が規定されているが、当該規定において、意思決定
支援への配慮の必要性は明記されていない。
≪地域住民等の責務の規定≫
≪行政の責務の規定≫
≪福祉サービスの提供原則等の規定≫
(地域福祉の推進)
(福祉サービスの提供体制の確保等に関する国及び地方公共
(福祉サービスの基本的理念)
第4条 地域福祉の推進は、地域住民が相互に人格と個性を尊重し合
団体の責務)
第3条 福祉サービスは、個人の尊厳の保持を旨とし、その内
いながら、参加し、共生する地域社会の実現を目指して行われなければな
第6条 (略)
容は、福祉サービスの利用者が心身ともに健やかに育成され、
らない。
2 国及び地方公共団体は、地域生活課題の解決に資する支
又はその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができ
2 地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉
援が包括的に提供される体制の整備その他地域福祉の推進の
るように支援するものとして、良質かつ適切なものでなければな
に関する活動を行う者(以下「地域住民等」という。)は、相互に協力し、 ために必要な各般の措置を講ずるよう努めるとともに、当該措置
の推進に当たつては、保健医療、労働、教育、住まい及び地域
福祉サービスを必要とする地域住民が地域社会を構成する一員として日
らない。
常生活を営み、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する
再生に関する施策その他の関連施策との連携に配慮するよう努
(福祉サービスの提供の原則)
機会が確保されるように、地域福祉の推進に努めなければならない。
めなければならない。
第5条 社会福祉を目的とする事業を経営する者は、その提
3 地域住民等は、地域福祉の推進に当たつては、(中略)福祉サー
3 国及び都道府県は、市町村(特別区を含む。以下同
供する多様な福祉サービスについて、利用者の意向を十分に
ビスを必要とする地域住民の地域社会からの孤立その他の福祉サービスを
じ。)において第百六条の四第二項に規定する重層的支援体
尊重し、地域福祉の推進に係る取組を行う他の地域住民等と
必要とする地域住民が日常生活を営み、あらゆる分野の活動に参加する
制整備事業その他地域生活課題の解決に資する支援が包括的
の連携を図り、かつ、保健医療サービスその他の関連するサービ
機会が確保される上での各般の課題(以下「地域生活課題」という。)
に提供される体制の整備が適正かつ円滑に行われるよう、必要な
スとの有機的な連携を図るよう創意工夫を行いつつ、これを総
を把握し、地域生活課題の解決に資する支援を行う関係機関(以下
助言、情報の提供その他の援助を行わなければならない。
合的に提供することができるようにその事業の実施に努めなけれ
「支援関係機関」という。)との連携等によりその解決を図るよう特に留意
するものとする。
ばならない。
20