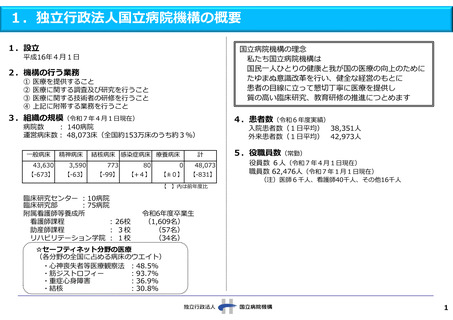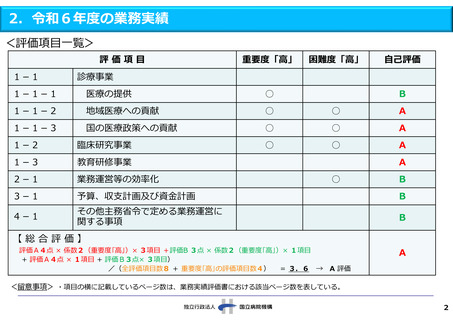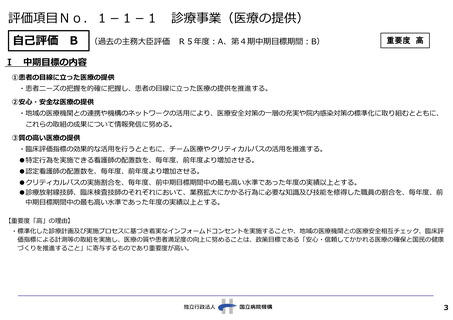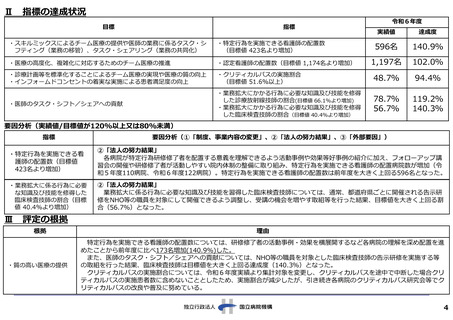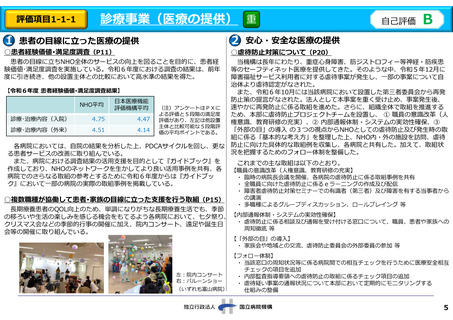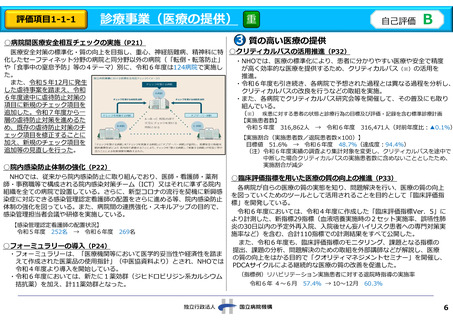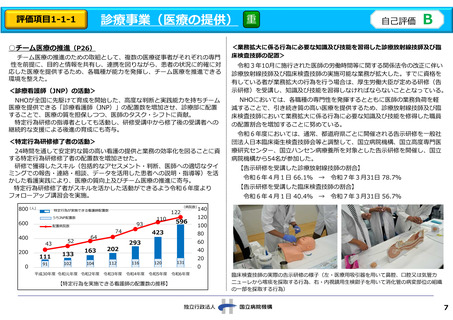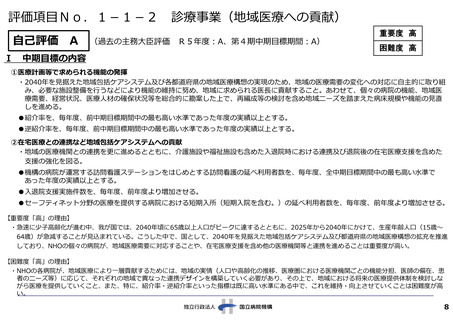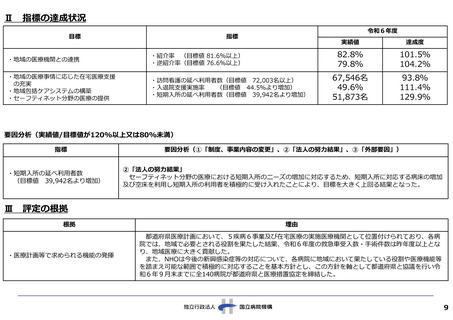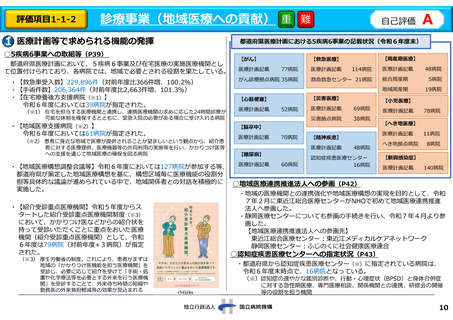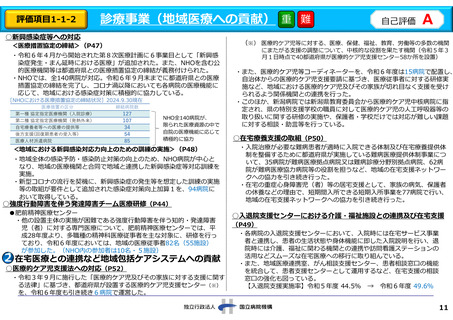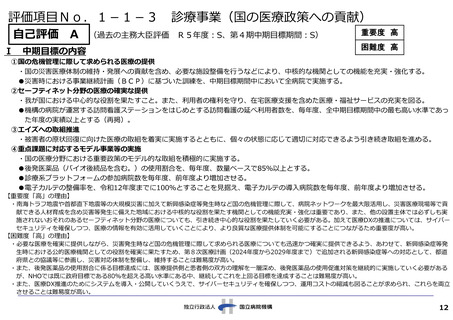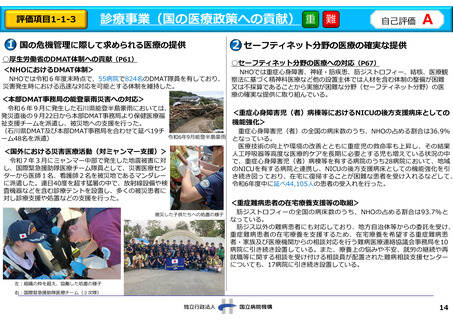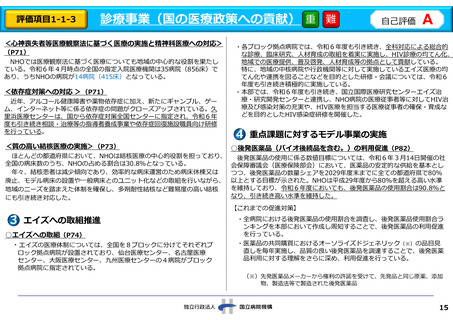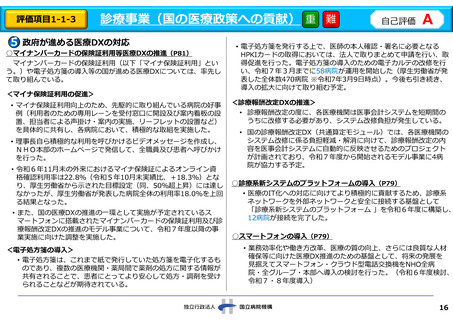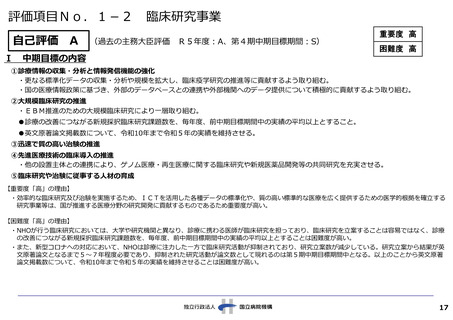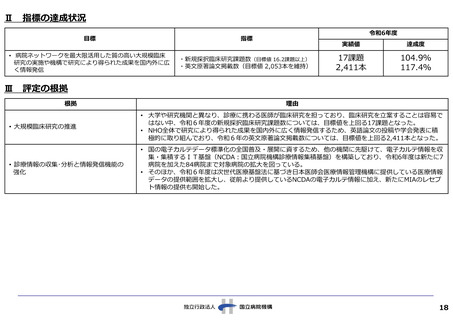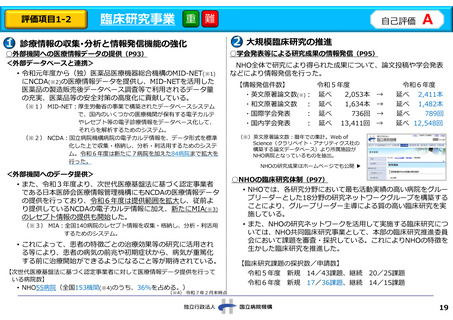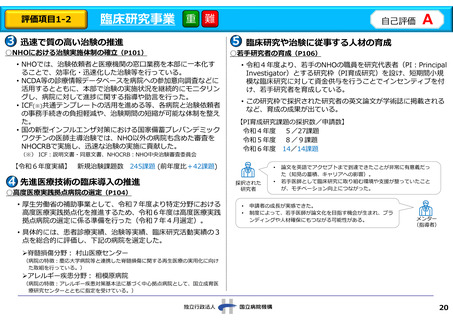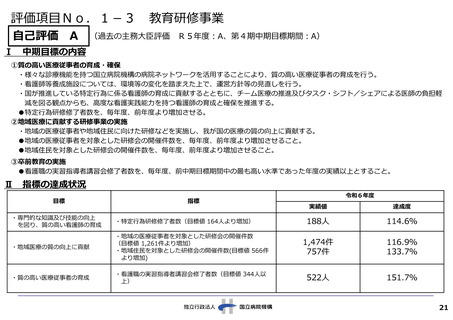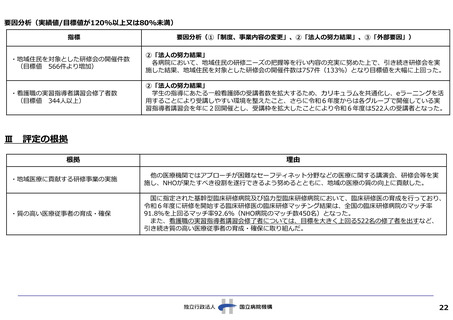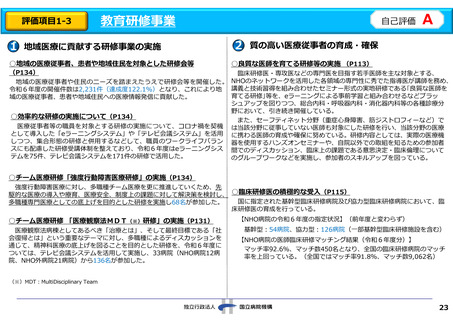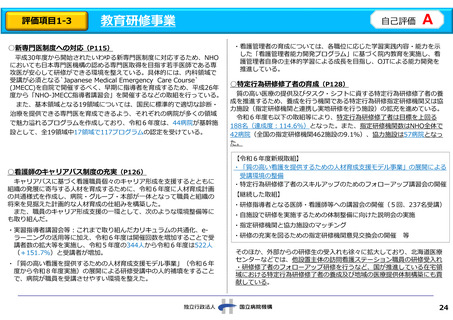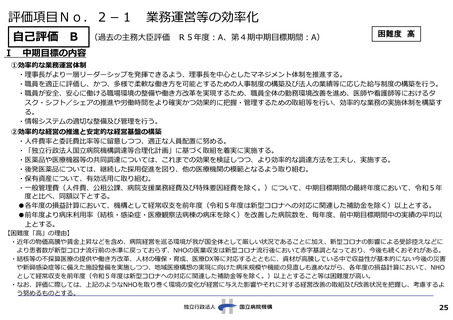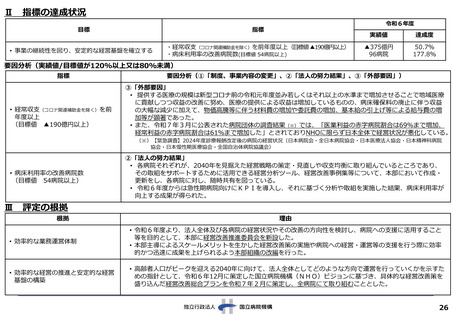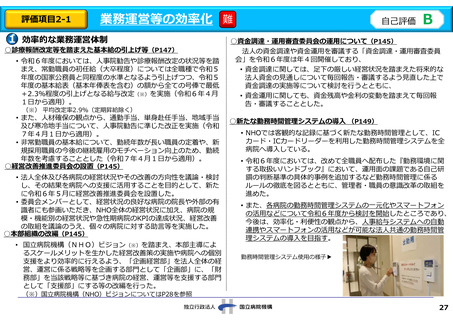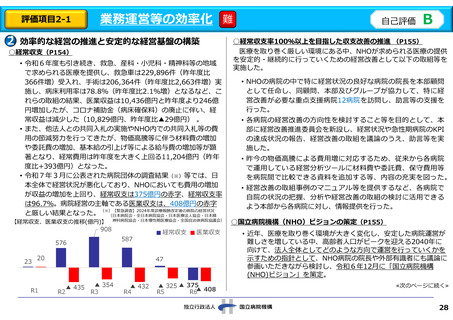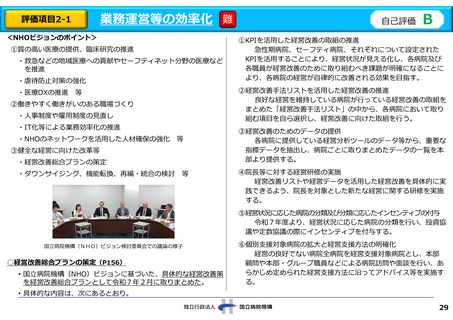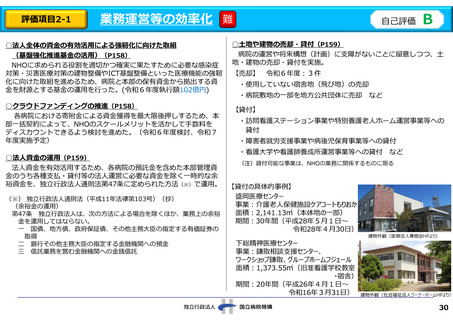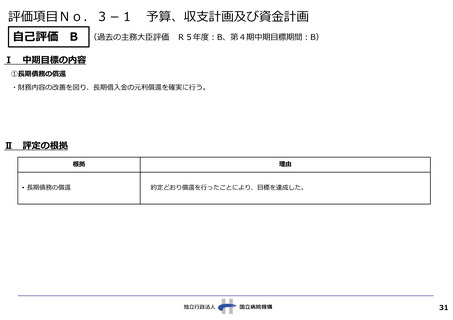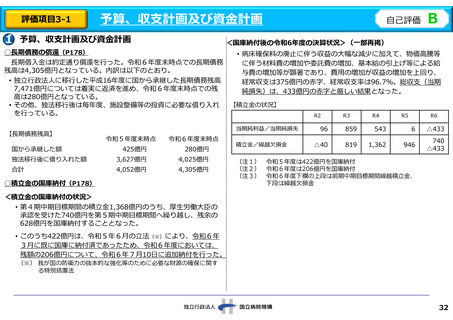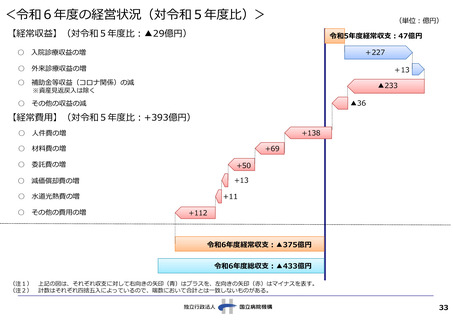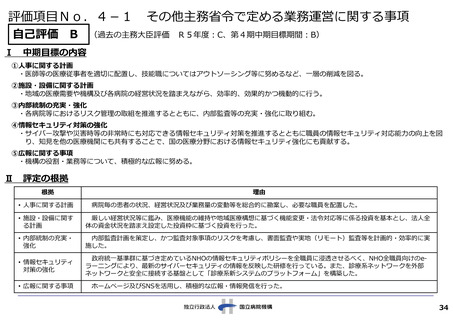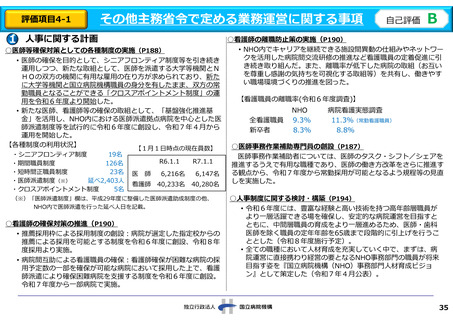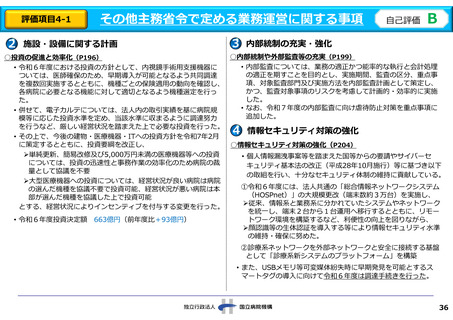よむ、つかう、まなぶ。
資料2-1 令和6年度業務実績評価説明資料 (21 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60083.html |
| 出典情報 | 独立行政法人評価に関する有識者会議 国立病院WG(第13回 7/31)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
評価項目1-2
臨床研究事業 重 難
1 診療情報の収集・分析と情報発信機能の強化
○外部機関への医療情報データの提供(P93)
<外部データベースと連携>
• 令和元年度から(独)医薬品医療機器総合機構のMID-NET(※1)
にNCDA(※2)の医療情報データを提供し、MID-NETを活用した
医薬品の製造販売後データベース調査等で利用されるデータ量
の充実、医薬品等の安全対策の高度化に貢献している。
(※1) MID-NET:厚生労働省の事業で構築されたデータベースシステム
で、国内のいくつかの医療機関が保有する電子カルテ
やレセプト等の電子診療情報をデータベース化して、
それらを解析するためのシステム。
(※2) NCDA:国立病院機構病院の電子カルテ情報を、データ形式を標準
化した上で収集・格納し、分析・利活用するためのシステ
ム。令和6年度は新たに7病院を加えた84病院まで拡大を
行った。
<外部機関へのデータ提供>
• また、令和3年度より、次世代医療基盤法に基づく認定事業者
である日本医師会医療情報管理機構にもNCDAの医療情報データ
の提供を行っており、令和6年度は提供範囲を拡大し、従前よ
り提供しているNCDAの電子カルテ情報に加え、新たにMIA(※3)
のレセプト情報の提供も開始した。
(※3) MIA:全国140病院のレセプト情報を収集・格納し、分析・利活用
するためのシステム。
• これによって、患者の特徴ごとの治療効果等の研究に活用され
る等により、患者の病気の前兆や初期症状から、病気が重篤化
する前に治療開始ができるようになること等が期待されている。
【次世代医療基盤法に基づく認定事業者に対して医療情報データ提供を行って
いる病院数】
• NHO55病院(全国153機関(※4)のうち、36%を占める。)
自己評価
A
2 大規模臨床研究の推進
○学会発表等による研究成果の情報発信(P95)
NHO全体で研究により得られた成果について、論文投稿や学会発表
などにより情報発信を行った。
【情報発信件数】
・英文原著論文数(※):
・和文原著論文数 :
・国際学会発表
:
・国内学会発表
:
令和5年度
延べ
2,053本
延べ
1,634本
延べ
736回
延べ 13,411回
→
→
→
→
令和6年度
延べ 2,411本
延べ 1,482本
延べ
789回
延べ 12,548回
(※)英文原著論文数:暦年での集計。Web of
Science(クラリベイト・アナリティクス社の
構築する論文データベース)より所属施設が
NHO病院となっているものを抽出。
NHOの研究成果はホームページでも公開
○NHOの臨床研究体制(P97)
• NHOでは、各研究分野において最も活動実績の高い病院をグルー
プリーダーとした18分野の研究ネットワークグループを構築する
ことにより、グループリーダー主導による質の高い臨床研究を実
施している。
• また、NHOの研究ネットワークを活用して実施する臨床研究につ
いては、NHO共同臨床研究事業として、本部の臨床研究推進委員
会において課題を審査・採択している。これによりNHOの特徴を
生かした臨床研究を推進した。
【臨床研究課題の採択数/申請数】
令和5年度 新規 14/43課題、継続 20/25課題
令和6年度 新規 17/36課題、継続 14/15課題
(※4) 令和7年2月末時点
19
臨床研究事業 重 難
1 診療情報の収集・分析と情報発信機能の強化
○外部機関への医療情報データの提供(P93)
<外部データベースと連携>
• 令和元年度から(独)医薬品医療機器総合機構のMID-NET(※1)
にNCDA(※2)の医療情報データを提供し、MID-NETを活用した
医薬品の製造販売後データベース調査等で利用されるデータ量
の充実、医薬品等の安全対策の高度化に貢献している。
(※1) MID-NET:厚生労働省の事業で構築されたデータベースシステム
で、国内のいくつかの医療機関が保有する電子カルテ
やレセプト等の電子診療情報をデータベース化して、
それらを解析するためのシステム。
(※2) NCDA:国立病院機構病院の電子カルテ情報を、データ形式を標準
化した上で収集・格納し、分析・利活用するためのシステ
ム。令和6年度は新たに7病院を加えた84病院まで拡大を
行った。
<外部機関へのデータ提供>
• また、令和3年度より、次世代医療基盤法に基づく認定事業者
である日本医師会医療情報管理機構にもNCDAの医療情報データ
の提供を行っており、令和6年度は提供範囲を拡大し、従前よ
り提供しているNCDAの電子カルテ情報に加え、新たにMIA(※3)
のレセプト情報の提供も開始した。
(※3) MIA:全国140病院のレセプト情報を収集・格納し、分析・利活用
するためのシステム。
• これによって、患者の特徴ごとの治療効果等の研究に活用され
る等により、患者の病気の前兆や初期症状から、病気が重篤化
する前に治療開始ができるようになること等が期待されている。
【次世代医療基盤法に基づく認定事業者に対して医療情報データ提供を行って
いる病院数】
• NHO55病院(全国153機関(※4)のうち、36%を占める。)
自己評価
A
2 大規模臨床研究の推進
○学会発表等による研究成果の情報発信(P95)
NHO全体で研究により得られた成果について、論文投稿や学会発表
などにより情報発信を行った。
【情報発信件数】
・英文原著論文数(※):
・和文原著論文数 :
・国際学会発表
:
・国内学会発表
:
令和5年度
延べ
2,053本
延べ
1,634本
延べ
736回
延べ 13,411回
→
→
→
→
令和6年度
延べ 2,411本
延べ 1,482本
延べ
789回
延べ 12,548回
(※)英文原著論文数:暦年での集計。Web of
Science(クラリベイト・アナリティクス社の
構築する論文データベース)より所属施設が
NHO病院となっているものを抽出。
NHOの研究成果はホームページでも公開
○NHOの臨床研究体制(P97)
• NHOでは、各研究分野において最も活動実績の高い病院をグルー
プリーダーとした18分野の研究ネットワークグループを構築する
ことにより、グループリーダー主導による質の高い臨床研究を実
施している。
• また、NHOの研究ネットワークを活用して実施する臨床研究につ
いては、NHO共同臨床研究事業として、本部の臨床研究推進委員
会において課題を審査・採択している。これによりNHOの特徴を
生かした臨床研究を推進した。
【臨床研究課題の採択数/申請数】
令和5年度 新規 14/43課題、継続 20/25課題
令和6年度 新規 17/36課題、継続 14/15課題
(※4) 令和7年2月末時点
19