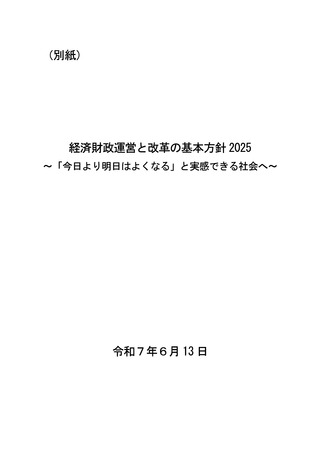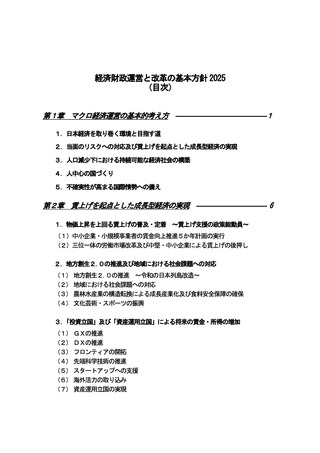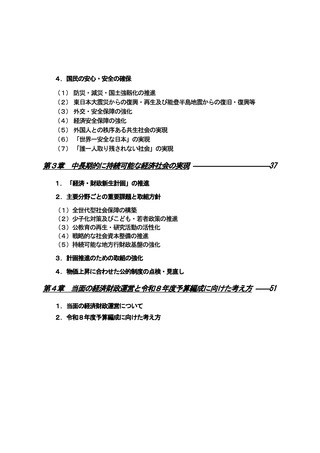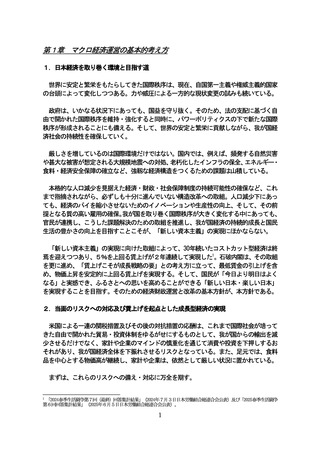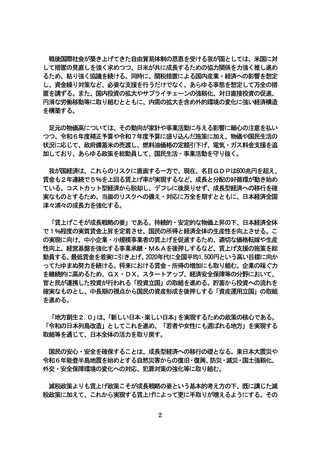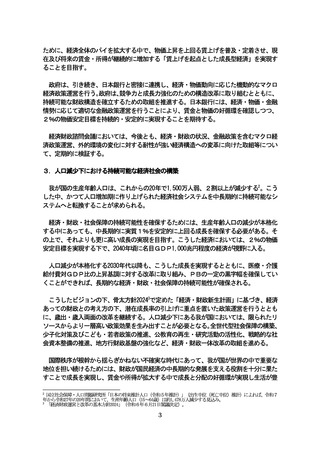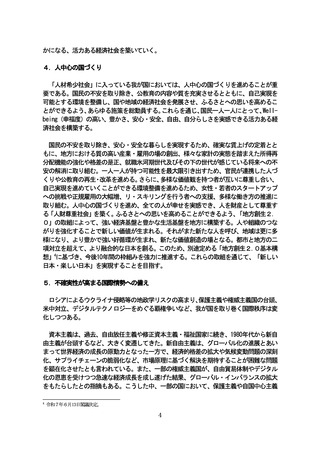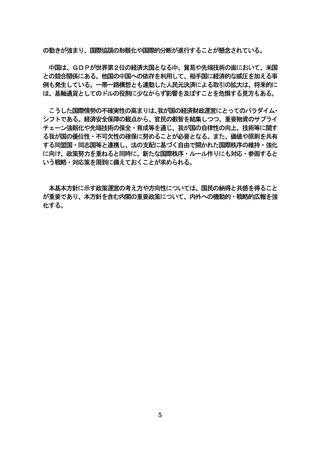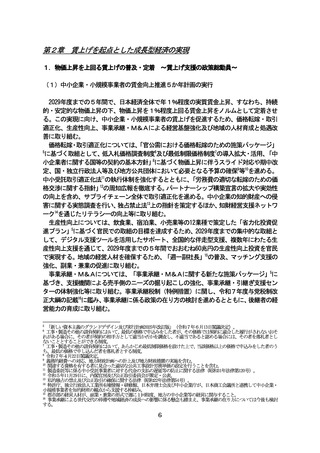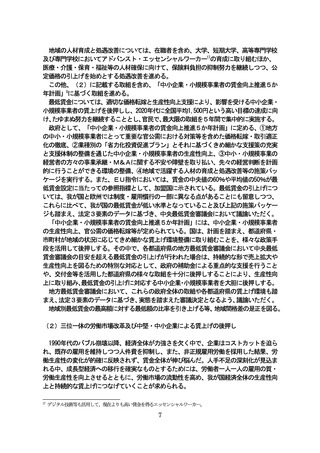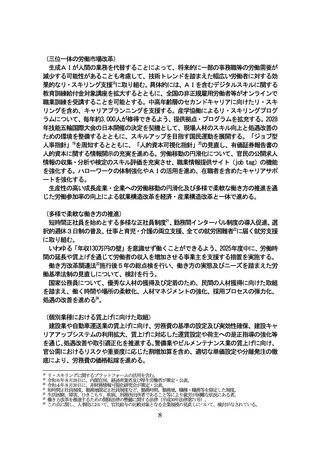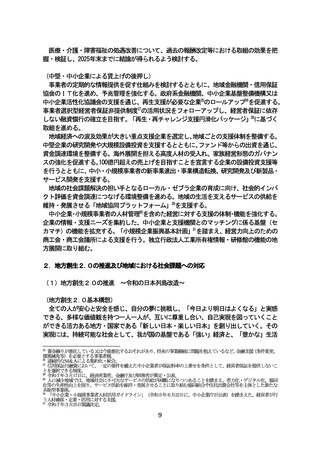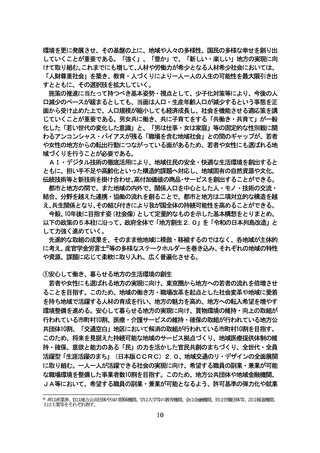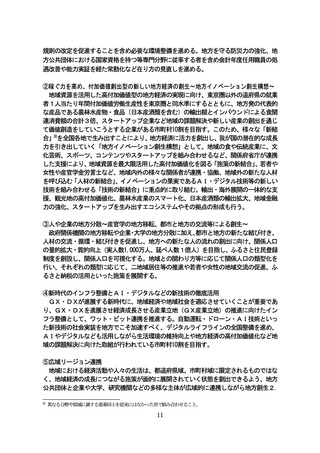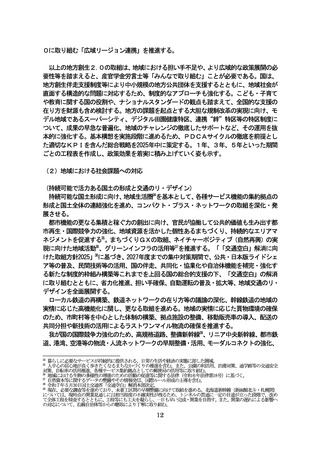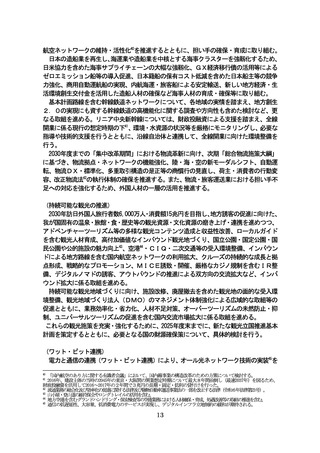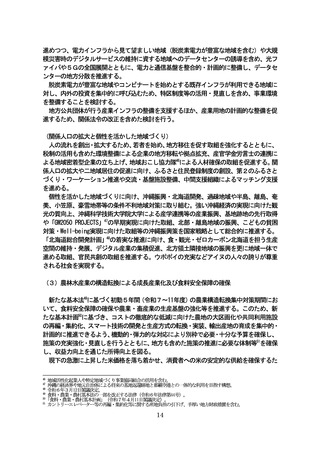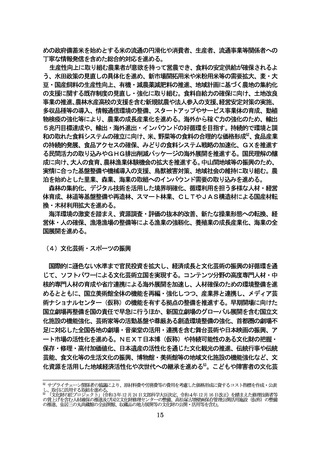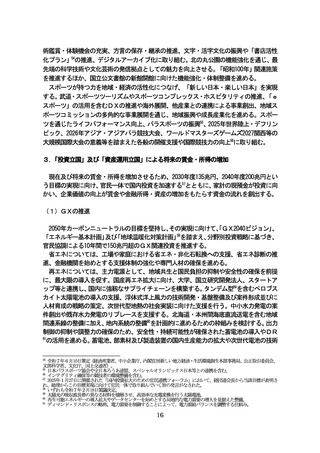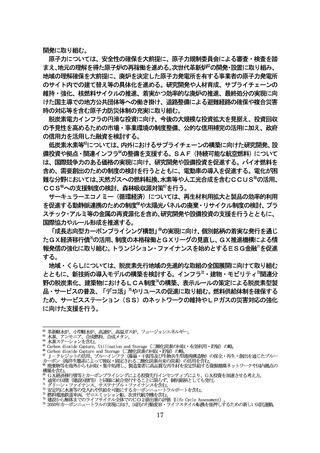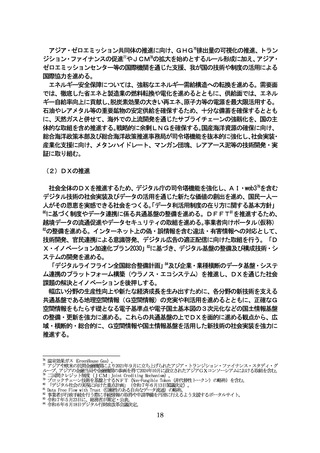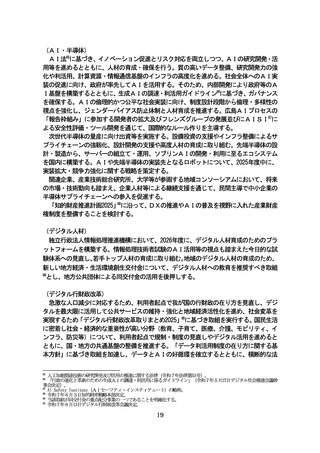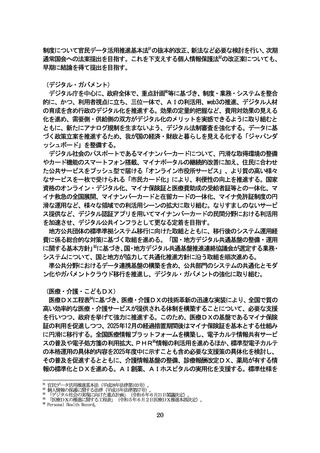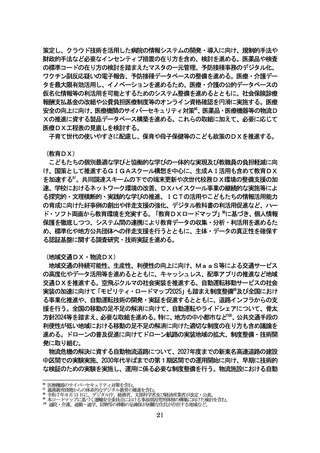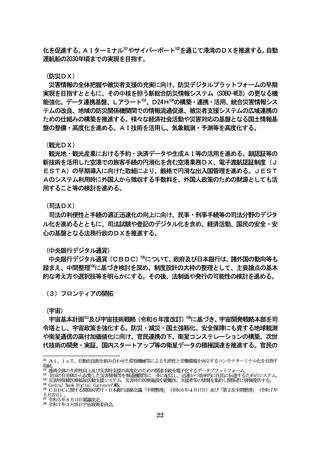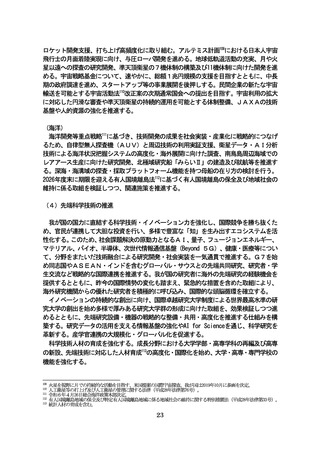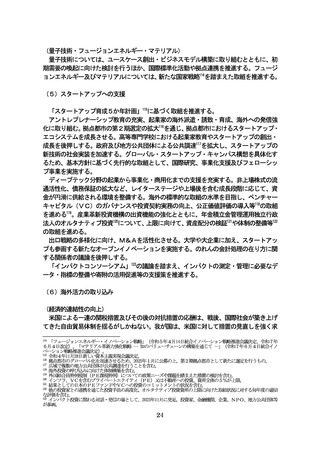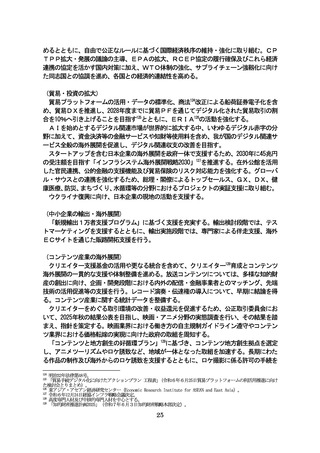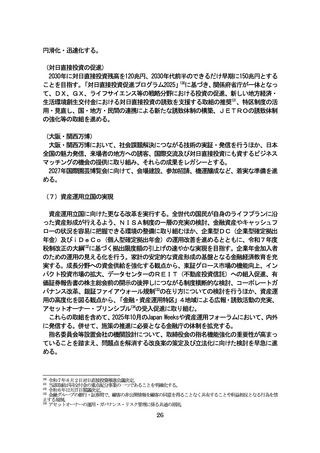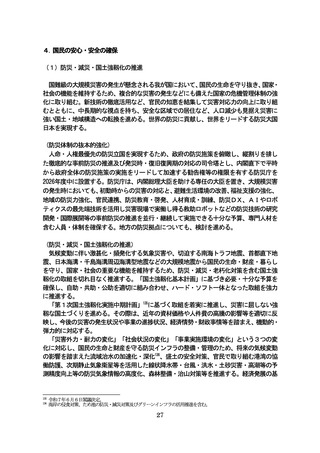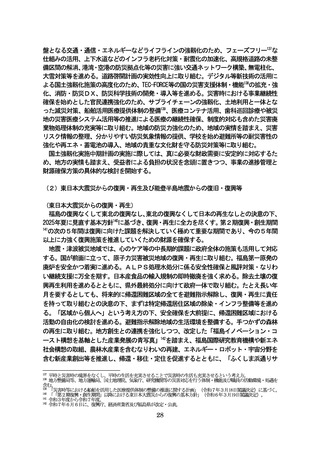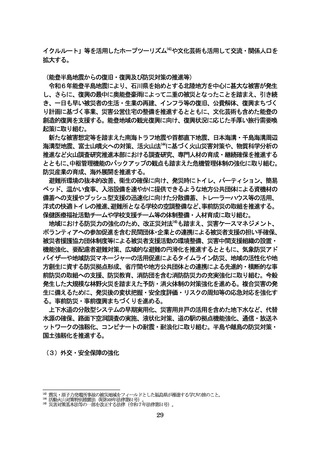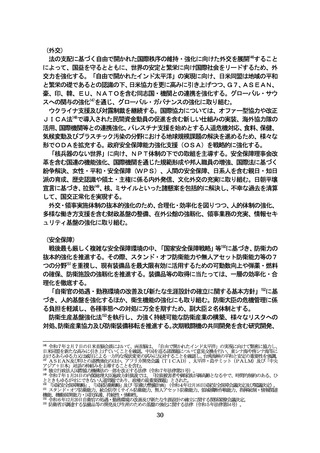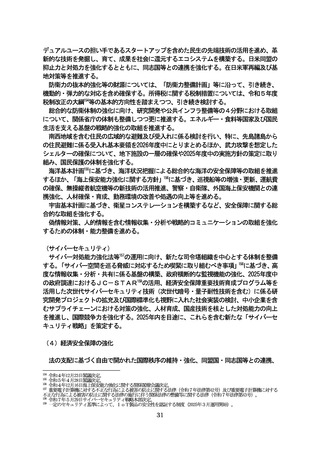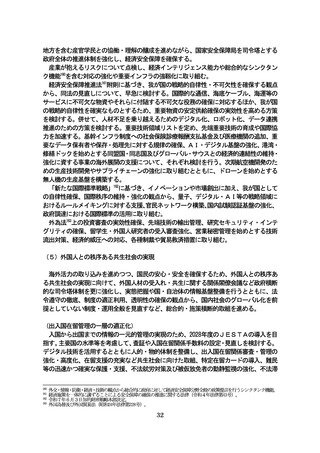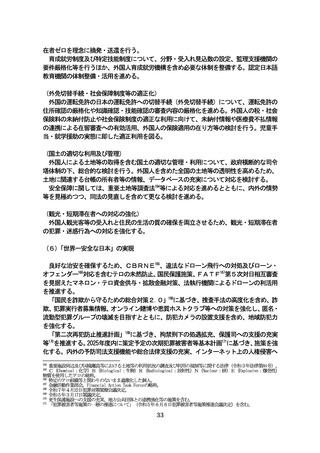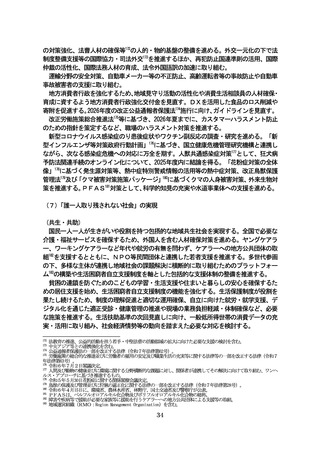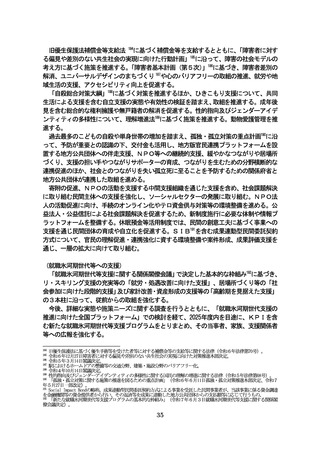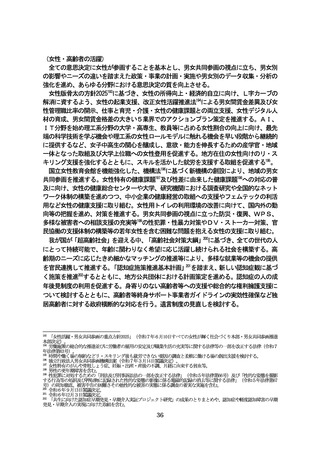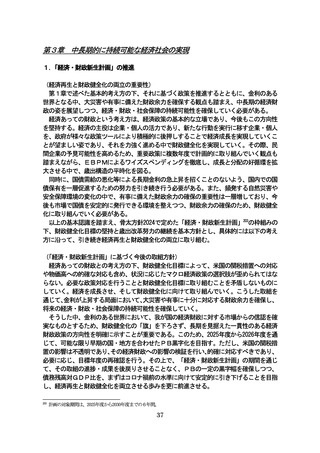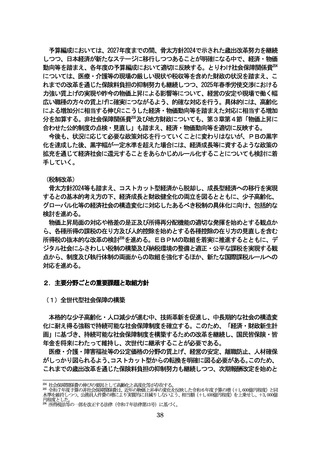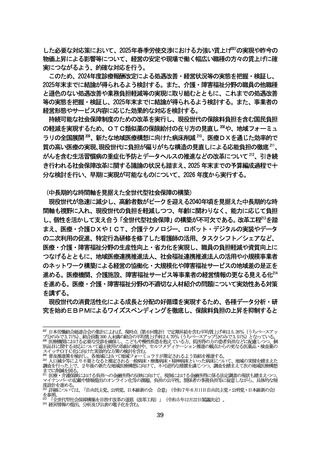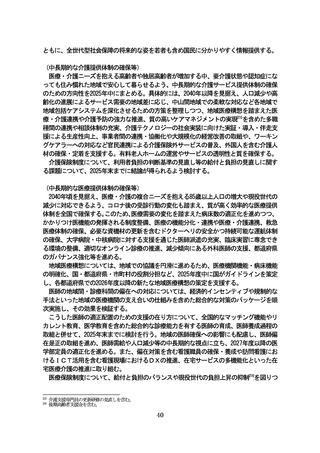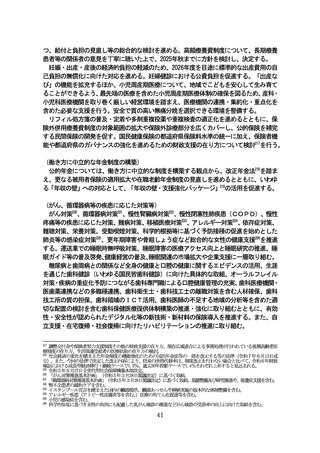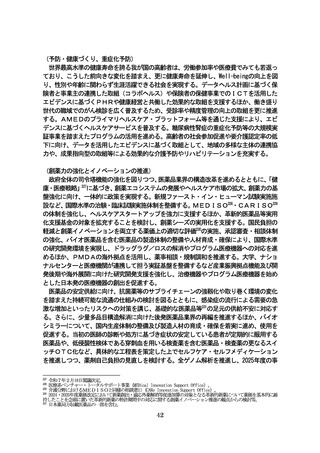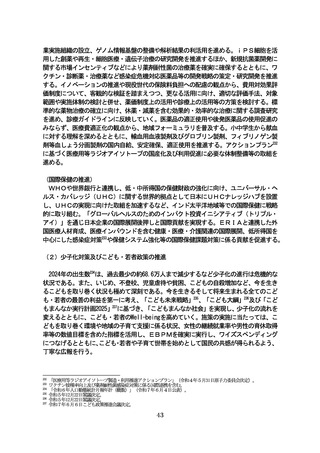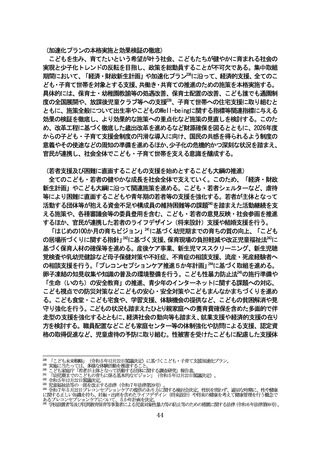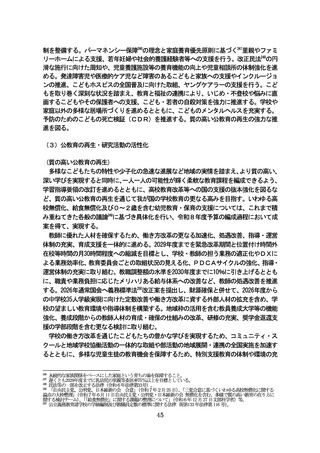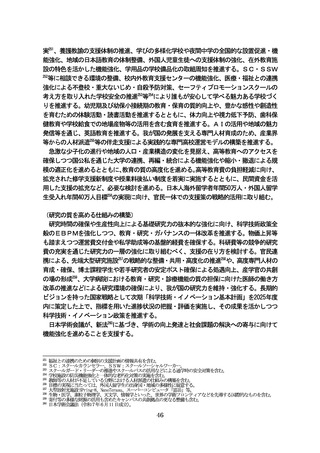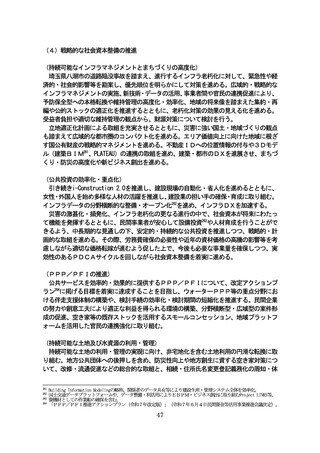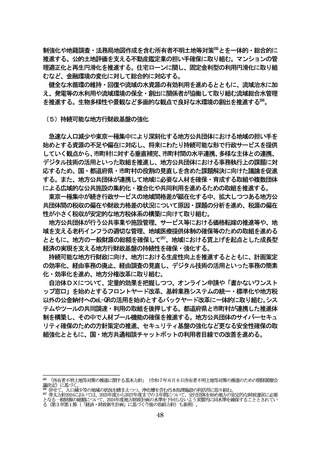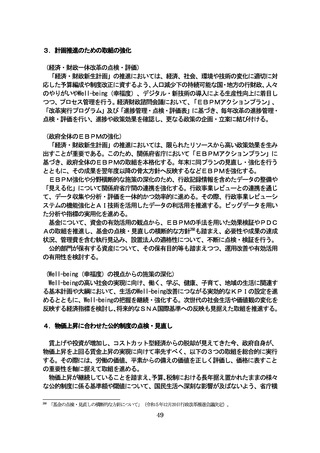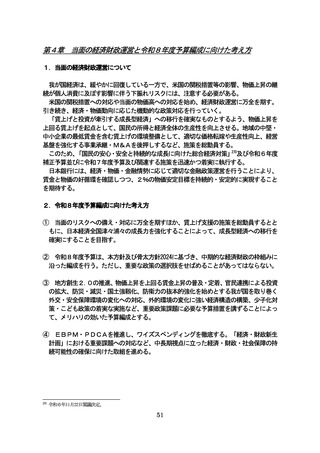よむ、つかう、まなぶ。
経済財政運営と改革の基本方針2025 ~「今日より明日はよくなる」と実感できる社会へ~(令和7年6月13日閣議決定) (40 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/cabinet/honebuto/2025/decision0613.html |
| 出典情報 | 経済財政運営と改革の基本方針2025(6/13)《内閣府》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(女性・高齢者の活躍)
全ての意思決定に女性が参画することを基本とし、男女共同参画の視点に立ち、男女別
の影響やニーズの違いを踏まえた政策・事業の計画・実施や男女別のデータ収集・分析の
強化を進め、あらゆる分野における意思決定の質を向上させる。
女性版骨太の方針2025193に基づき、女性の所得向上・経済的自立に向け、L字カーブの
解消に資するよう、女性の起業支援、改正女性活躍推進法194による男女間賃金差異及び女
性管理職比率の開示、仕事と育児・介護・女性の健康課題との両立支援、女性デジタル人
材の育成、男女間賃金格差の大きい5業界でのアクションプラン策定を推進する。AI、
IT分野を始め理工系分野の大学・高専生、教員等に占める女性割合の向上に向け、最先
端の科学技術を学ぶ機会や理工系の女性ロールモデルに触れる機会を早い段階から継続的
に提供するなど、女子中高生の関心を醸成し、意欲・能力を伸長するための産学官・地域
一体となった取組及び大学上位職への女性登用を促進する。地方在住の女性向けのリ・ス
キリング支援を強化するとともに、スキルを活かした就労を支援する取組を促進する195。
国立女性教育会館を機能強化した、機構法196に基づく新機構の創設により、地域の男女
共同参画を推進する。女性特有の健康課題197及び性差に由来した健康課題198への対応の普
及に向け、女性の健康総合センターや大学、研究機関における調査研究や全国的なネット
ワーク体制の構築を進めつつ、中小企業の健康経営の取組への支援やフェムテックの利活
用など女性の健康支援に取り組む。女性用トイレの利用環境の改善に向けて、国内外の動
向等の把握を進め、対策を推進する。男女共同参画の視点に立った防災・復興、WPS、
多様な被害者への相談支援の充実等199の性犯罪・性暴力対策やDV・ストーカー対策、官
民協働の支援体制の構築等の若年女性を含む困難な問題を抱える女性の支援に取り組む。
我が国が「超高齢社会」を迎える中、「高齢社会対策大綱」200に基づき、全ての世代の人
にとって持続可能で、年齢に関わりなく希望に応じ活躍し続けられる社会を構築する。高
齢期のニーズに応じたきめ細かなマッチングの推進等により、多様な就業等の機会の提供
を官民連携して推進する。「認知症施策推進基本計画」201を踏まえ、新しい認知症観に基づ
く施策を推進202するとともに、地方公共団体における計画策定を進める。認知症の人の成
年後見制度の利用を促進する。身寄りのない高齢者等への支援や総合的な権利擁護支援に
ついて検討するとともに、高齢者等終身サポート事業者ガイドラインの実効性確保など独
居高齢者に対する政府横断的な対応を行う。遺言制度の見直しを検討する。
193
「女性活躍・男女共同参画の重点方針2025」(令和7年6月10日すべての女性が輝く社会づくり本部・男女共同参画推進
本部決定)。
194
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7
年法律第63号)。
195
時間や働く場の制約などリ・スキリング後も就労できない要因の調査と柔軟に働ける場の創出支援を検討する。
196
独立行政法人男女共同参画機構法案(令和7年3月14日閣議決定)。
197
女性特有のがんや骨粗しょう症、妊娠・出産・産後の不調、月経に由来する貧血等。
198
男性の更年期障害を含む。
199
性犯罪に対処するための「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」(令和5年法律第66号)及び「性的な姿態を撮影
する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(令和5年法律第67
号)の周知徹底、被害申告の困難さその他性的な被害の実態に係る調査の着実な実施を含む。
200
令和6年9月13日閣議決定。
201
令和6年12月3日閣議決定。
202
「共生に向けた認知症早期発見・早期介入実証プロジェクト研究」の成果のとりまとめや、認知症や軽度認知障害の早期
発見・早期介入の実現に向けた取組を含む。
36
全ての意思決定に女性が参画することを基本とし、男女共同参画の視点に立ち、男女別
の影響やニーズの違いを踏まえた政策・事業の計画・実施や男女別のデータ収集・分析の
強化を進め、あらゆる分野における意思決定の質を向上させる。
女性版骨太の方針2025193に基づき、女性の所得向上・経済的自立に向け、L字カーブの
解消に資するよう、女性の起業支援、改正女性活躍推進法194による男女間賃金差異及び女
性管理職比率の開示、仕事と育児・介護・女性の健康課題との両立支援、女性デジタル人
材の育成、男女間賃金格差の大きい5業界でのアクションプラン策定を推進する。AI、
IT分野を始め理工系分野の大学・高専生、教員等に占める女性割合の向上に向け、最先
端の科学技術を学ぶ機会や理工系の女性ロールモデルに触れる機会を早い段階から継続的
に提供するなど、女子中高生の関心を醸成し、意欲・能力を伸長するための産学官・地域
一体となった取組及び大学上位職への女性登用を促進する。地方在住の女性向けのリ・ス
キリング支援を強化するとともに、スキルを活かした就労を支援する取組を促進する195。
国立女性教育会館を機能強化した、機構法196に基づく新機構の創設により、地域の男女
共同参画を推進する。女性特有の健康課題197及び性差に由来した健康課題198への対応の普
及に向け、女性の健康総合センターや大学、研究機関における調査研究や全国的なネット
ワーク体制の構築を進めつつ、中小企業の健康経営の取組への支援やフェムテックの利活
用など女性の健康支援に取り組む。女性用トイレの利用環境の改善に向けて、国内外の動
向等の把握を進め、対策を推進する。男女共同参画の視点に立った防災・復興、WPS、
多様な被害者への相談支援の充実等199の性犯罪・性暴力対策やDV・ストーカー対策、官
民協働の支援体制の構築等の若年女性を含む困難な問題を抱える女性の支援に取り組む。
我が国が「超高齢社会」を迎える中、「高齢社会対策大綱」200に基づき、全ての世代の人
にとって持続可能で、年齢に関わりなく希望に応じ活躍し続けられる社会を構築する。高
齢期のニーズに応じたきめ細かなマッチングの推進等により、多様な就業等の機会の提供
を官民連携して推進する。「認知症施策推進基本計画」201を踏まえ、新しい認知症観に基づ
く施策を推進202するとともに、地方公共団体における計画策定を進める。認知症の人の成
年後見制度の利用を促進する。身寄りのない高齢者等への支援や総合的な権利擁護支援に
ついて検討するとともに、高齢者等終身サポート事業者ガイドラインの実効性確保など独
居高齢者に対する政府横断的な対応を行う。遺言制度の見直しを検討する。
193
「女性活躍・男女共同参画の重点方針2025」(令和7年6月10日すべての女性が輝く社会づくり本部・男女共同参画推進
本部決定)。
194
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7
年法律第63号)。
195
時間や働く場の制約などリ・スキリング後も就労できない要因の調査と柔軟に働ける場の創出支援を検討する。
196
独立行政法人男女共同参画機構法案(令和7年3月14日閣議決定)。
197
女性特有のがんや骨粗しょう症、妊娠・出産・産後の不調、月経に由来する貧血等。
198
男性の更年期障害を含む。
199
性犯罪に対処するための「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」(令和5年法律第66号)及び「性的な姿態を撮影
する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(令和5年法律第67
号)の周知徹底、被害申告の困難さその他性的な被害の実態に係る調査の着実な実施を含む。
200
令和6年9月13日閣議決定。
201
令和6年12月3日閣議決定。
202
「共生に向けた認知症早期発見・早期介入実証プロジェクト研究」の成果のとりまとめや、認知症や軽度認知障害の早期
発見・早期介入の実現に向けた取組を含む。
36