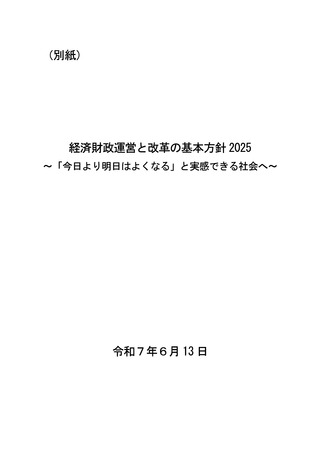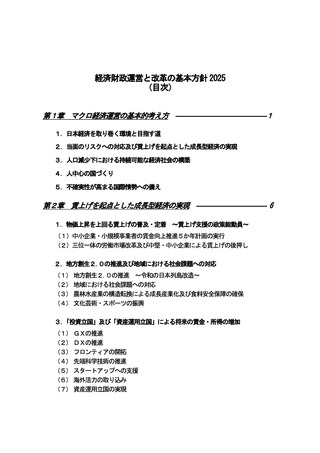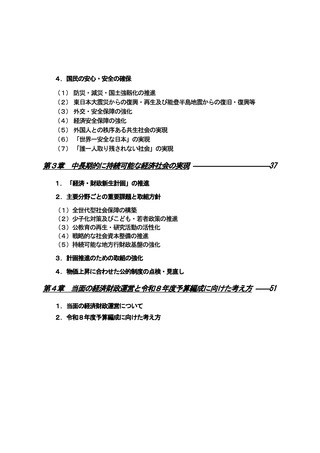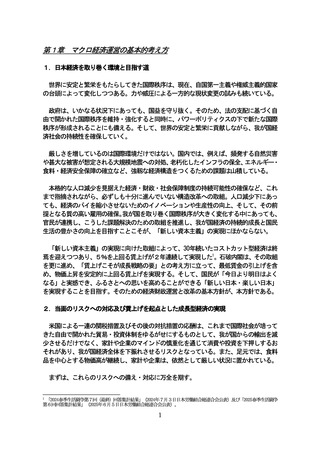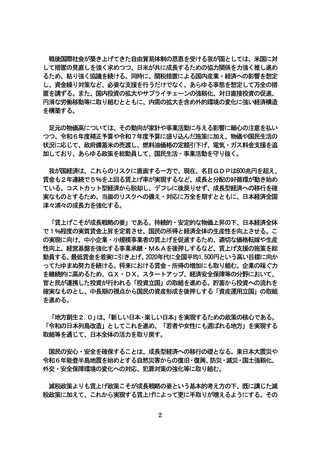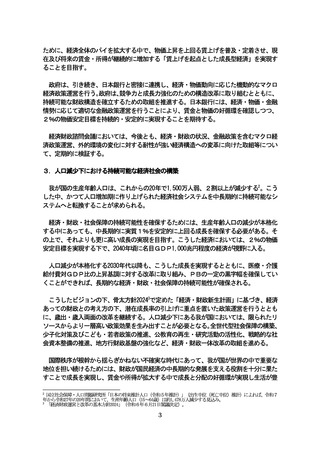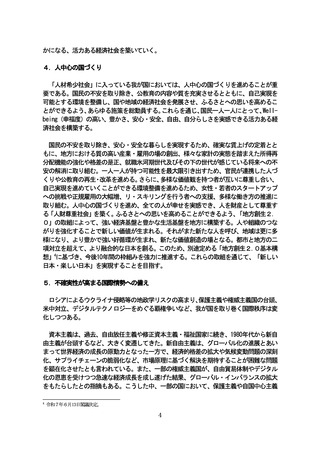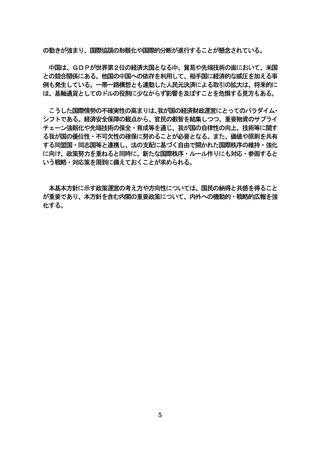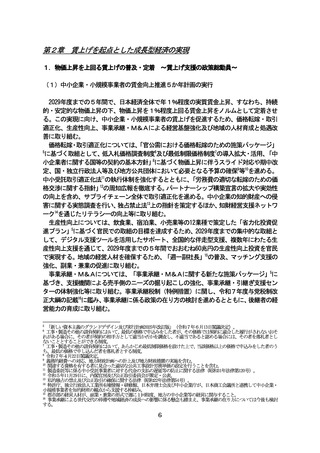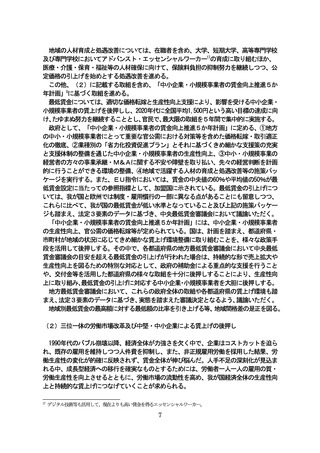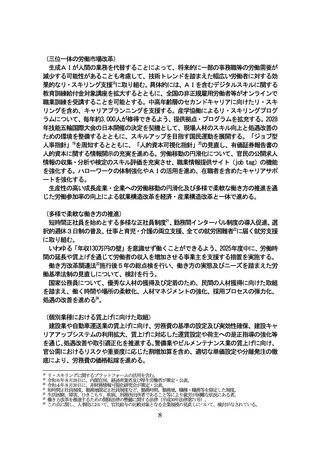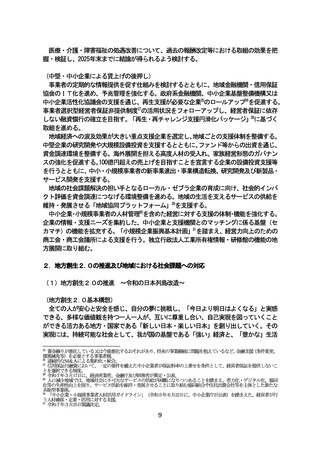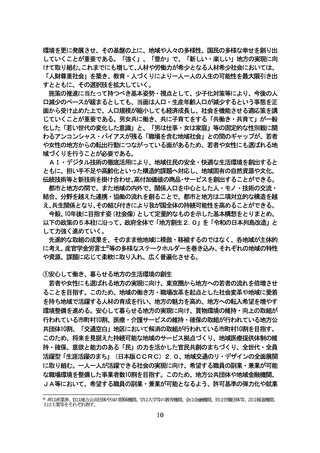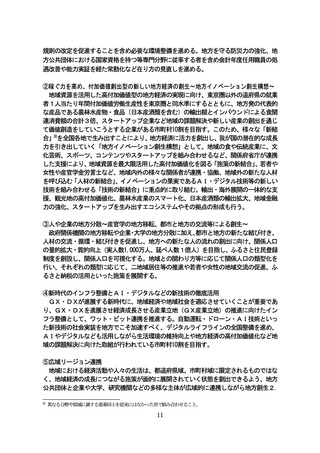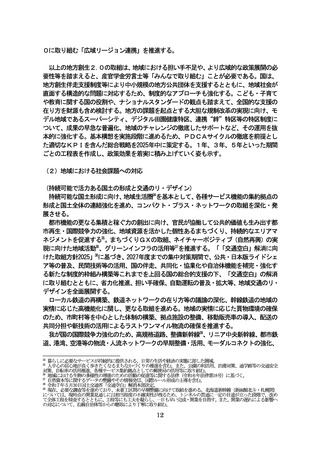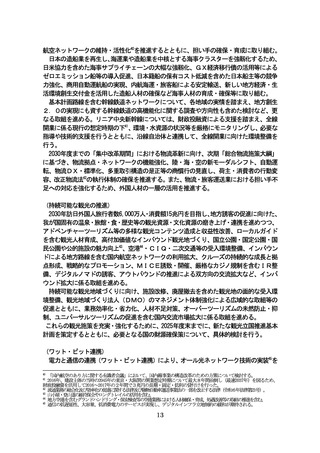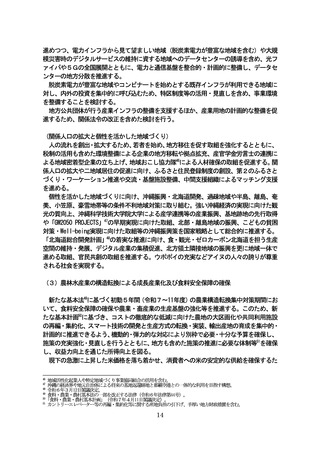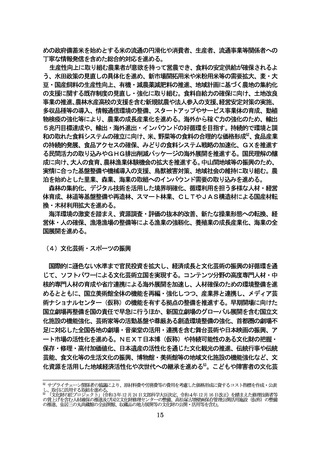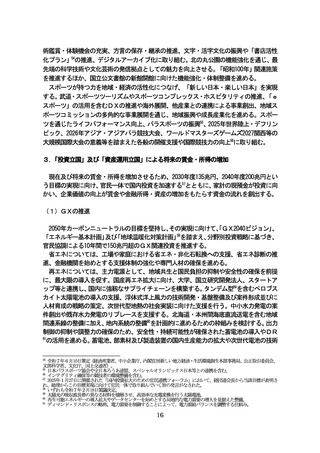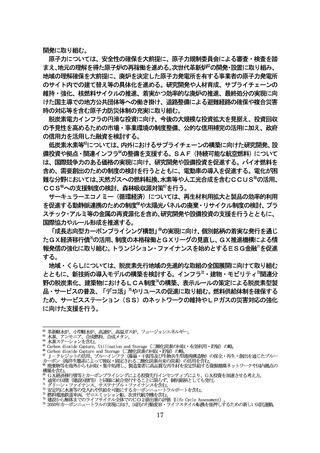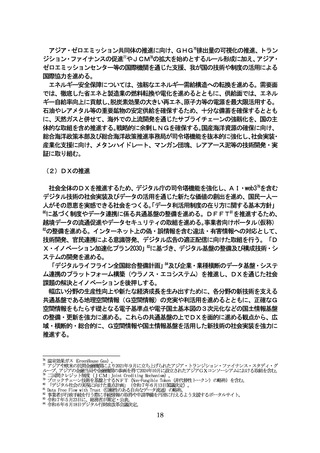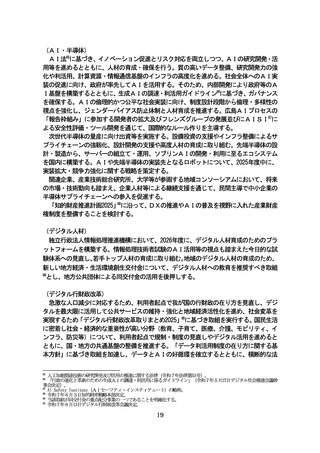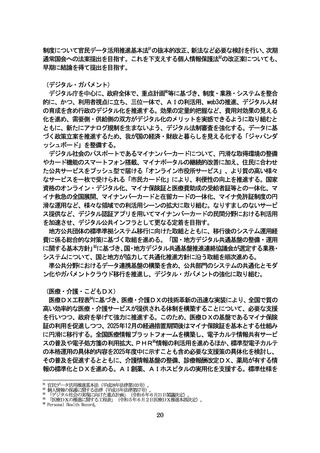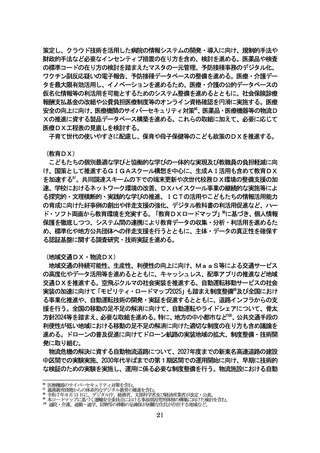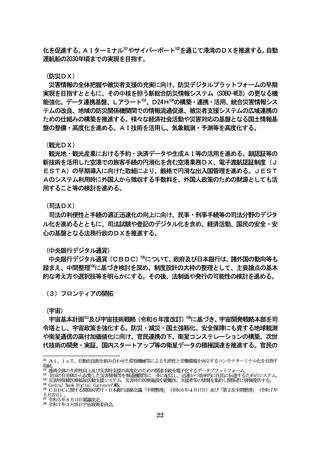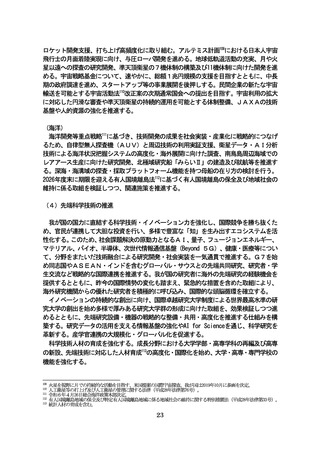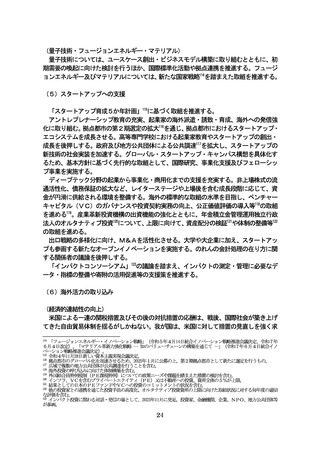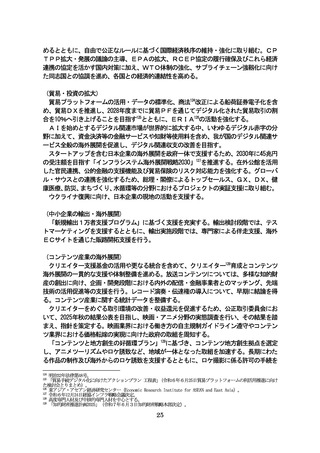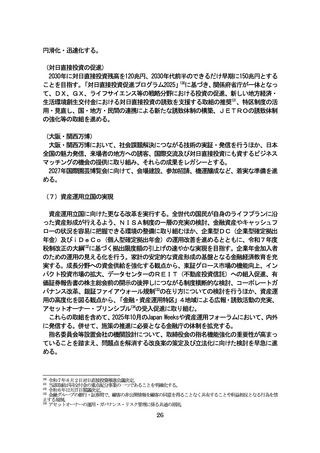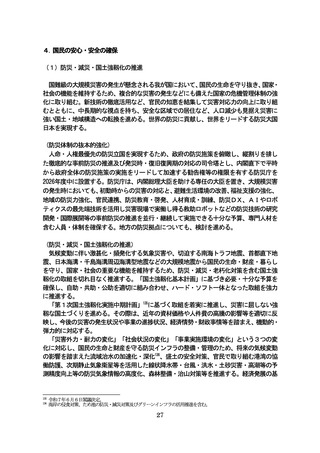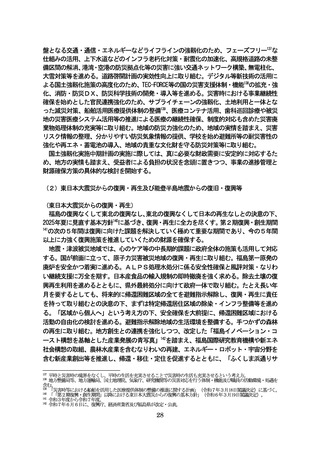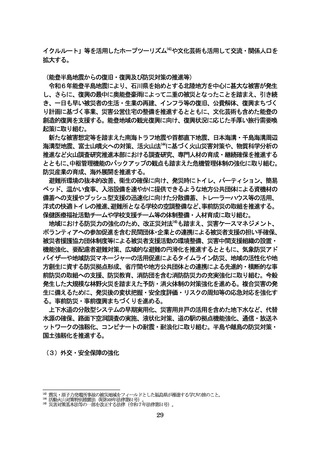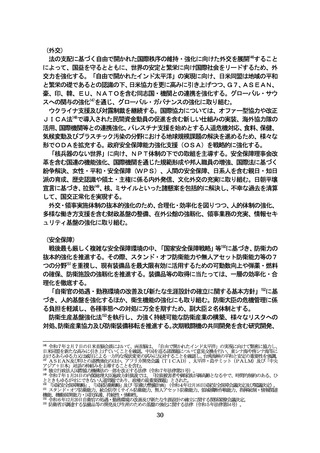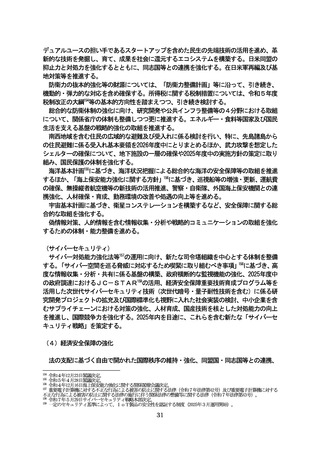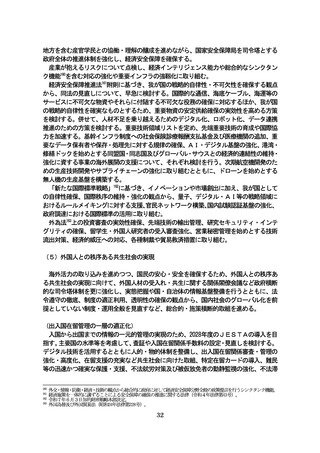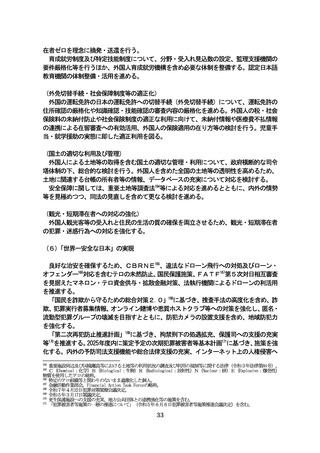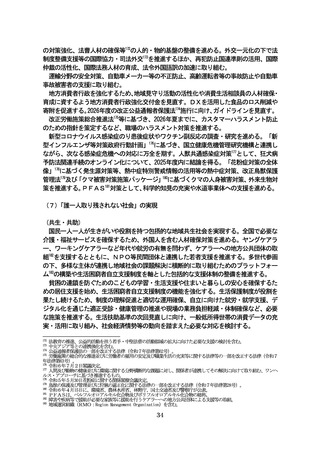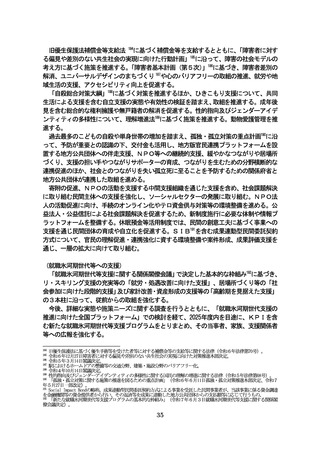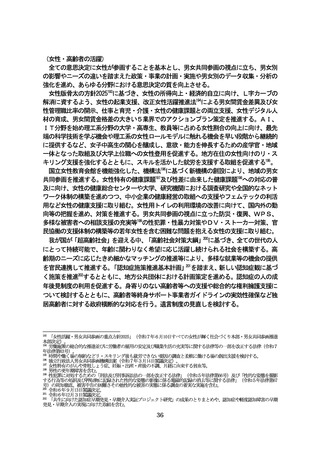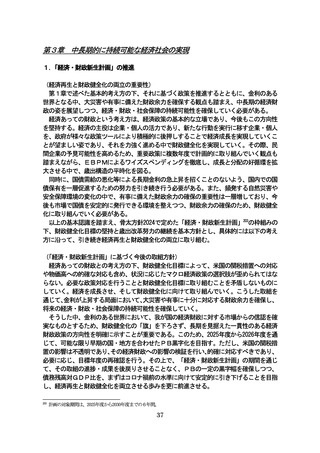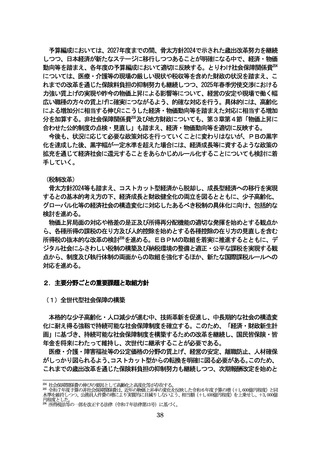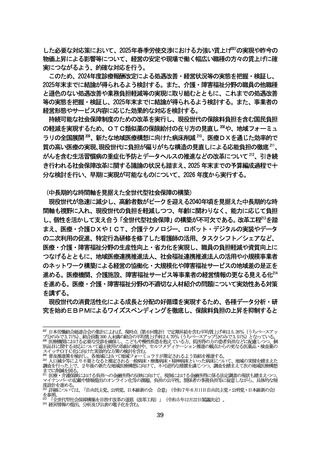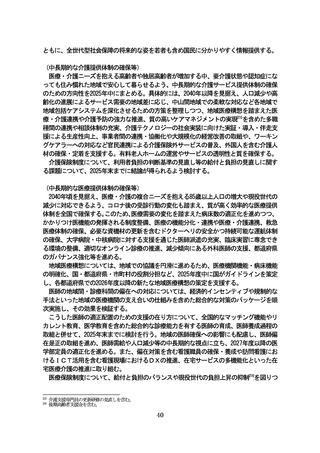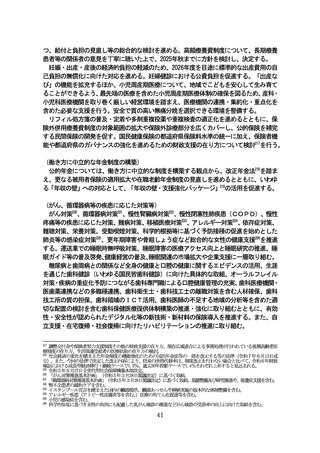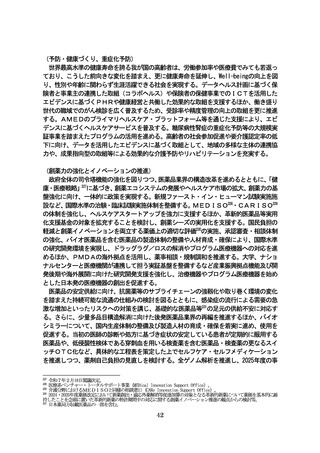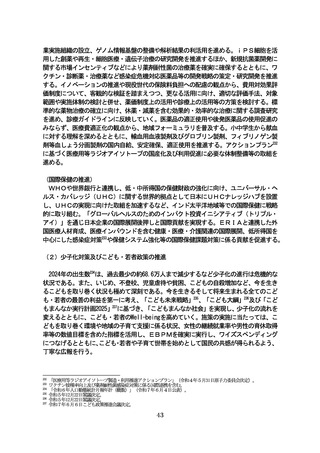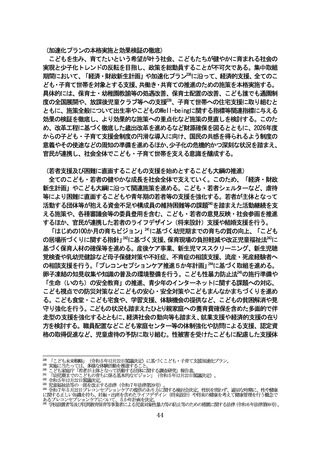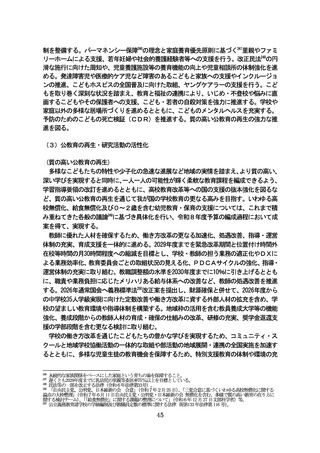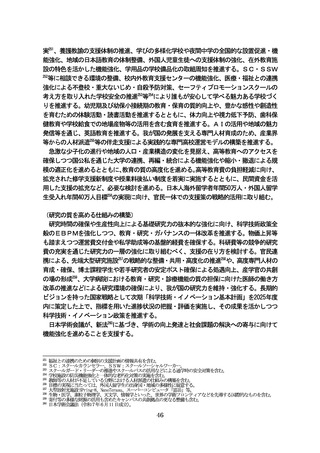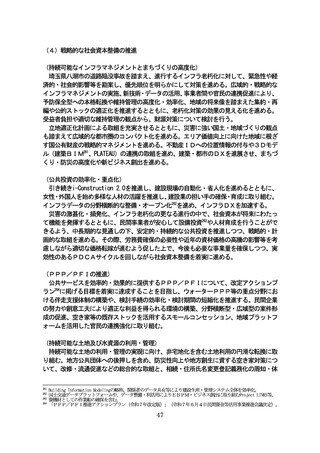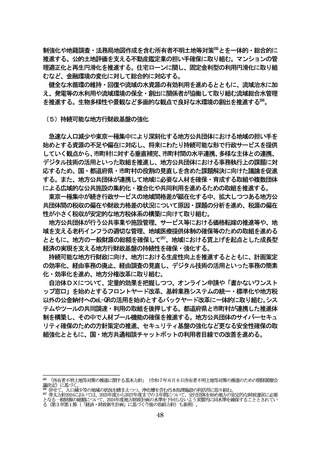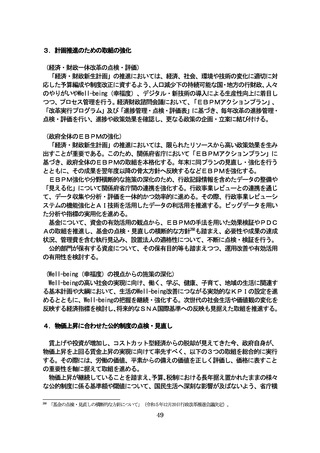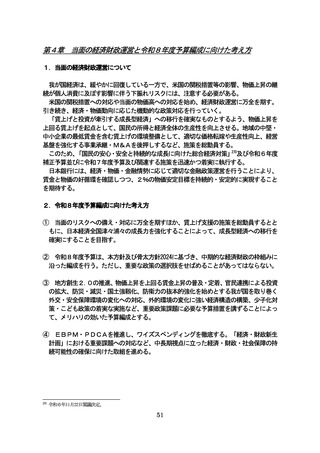よむ、つかう、まなぶ。
経済財政運営と改革の基本方針2025 ~「今日より明日はよくなる」と実感できる社会へ~(令和7年6月13日閣議決定) (14 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/cabinet/honebuto/2025/decision0613.html |
| 出典情報 | 経済財政運営と改革の基本方針2025(6/13)《内閣府》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
環境を更に発展させ、その基盤の上に、地域や人々の多様性、国民の多様な幸せを創り出
していくことが重要である。「強く」、「豊か」で、「新しい・楽しい」地方の実現に向
けて取り組む。
これまでにも増して、
人材や労働力が希少となる人材希少社会においては、
「人財尊重社会」を築き、教育・人づくりにより一人一人の人生の可能性を最大限引き出
すとともに、その選択肢を拡大していく。
施策の推進に当たって持つべき基本姿勢・視点として、少子化対策等により、今後の人
口減少のペースが緩まるとしても、当面は人口・生産年齢人口が減少するという事態を正
面から受け止めた上で、人口規模が縮小しても経済成長し、社会を機能させる適応策を講
じていくことが重要である。男女共に働き、共に子育てをする「共働き・共育て」が一般
化した「若い世代の変化した意識」と、「男は仕事・女は家庭」等の固定的な性別観に関
わるアンコンシャス・バイアスが残る「職場を含む地域社会」との間のギャップが、若者
や女性の地方からの転出行動につながっている面があるため、若者や女性にも選ばれる地
域づくりを行うことが必要である。
AI・デジタル技術の徹底活用により、地域住民の安全・快適な生活環境を創出すると
ともに、担い手不足や高齢化といった構造的課題へ対応し、地域固有の自然資源や文化、
伝統技術等と新技術を掛け合わせ、
高付加価値の商品・サービスを創出することができる。
都市と地方の間で、また地域の内外で、関係人口を中心とした人・モノ・技術の交流・
結合、分野を越えた連携・協働の流れを創ることで、都市と地方は二項対立的な構造を越
え、
共生関係となり、
その結び付きにより我が国全体の持続可能性を高めることができる。
今般、10年後に目指す姿(社会像)として定量的なものを示した基本構想をとりまとめ、
以下の政策の5本柱に沿って、政府全体で「地方創生2.0」を「令和の日本列島改造」と
して力強く進めていく。
先進的な取組の成果を、そのまま他地域に模倣・移植するのではなく、各地域が主体的
に考え、産官学金労言士32等の多様なステークホルダーを巻き込み、それぞれの地域の特性
や資源、課題に応じて柔軟に取り入れ、広く普遍化させる。
①安心して働き、暮らせる地方の生活環境の創生
若者や女性にも選ばれる地方の実現に向け、東京圏から地方への若者の流れを倍増させ
ることを目指す。このため、地域の働き方・職場改革を起点とした社会変革や地域に愛着
を持ち地域で活躍する人材の育成を行い、地方の魅力を高め、地方への転入希望を増やす
環境整備を進める。安心して暮らせる地方の実現に向け、買物環境の維持・向上の取組が
行われている市町村10割、医療・介護サービスの維持・確保の取組が行われている地方公
共団体10割、「交通空白」地区において解消の取組が行われている市町村10割を目指す。
このため、将来を見据えた持続可能な地域のサービス拠点づくり、地域医療提供体制の維
持・確保、意欲と能力のある「民」の力を活かした官民共創のまちづくり、全世代・全員
活躍型「生涯活躍のまち」(日本版CCRC)2.0、地域交通のリ・デザインの全面展開
に取り組む。一人一人が活躍できる社会の実現に向け、希望する職員の副業・兼業が可能
な職場環境を整備した事業者数10割を目指す。このため、地方公共団体や地域金融機関、
JA等において、希望する職員の副業・兼業が可能となるよう、許可基準の弾力化や就業
32
産は産業界、官は地方公共団体や国の関係機関、学は大学等の教育機関、金は金融機関、労は労働団体等、言は報道機関、
士は士業等をそれぞれ指す。
10
していくことが重要である。「強く」、「豊か」で、「新しい・楽しい」地方の実現に向
けて取り組む。
これまでにも増して、
人材や労働力が希少となる人材希少社会においては、
「人財尊重社会」を築き、教育・人づくりにより一人一人の人生の可能性を最大限引き出
すとともに、その選択肢を拡大していく。
施策の推進に当たって持つべき基本姿勢・視点として、少子化対策等により、今後の人
口減少のペースが緩まるとしても、当面は人口・生産年齢人口が減少するという事態を正
面から受け止めた上で、人口規模が縮小しても経済成長し、社会を機能させる適応策を講
じていくことが重要である。男女共に働き、共に子育てをする「共働き・共育て」が一般
化した「若い世代の変化した意識」と、「男は仕事・女は家庭」等の固定的な性別観に関
わるアンコンシャス・バイアスが残る「職場を含む地域社会」との間のギャップが、若者
や女性の地方からの転出行動につながっている面があるため、若者や女性にも選ばれる地
域づくりを行うことが必要である。
AI・デジタル技術の徹底活用により、地域住民の安全・快適な生活環境を創出すると
ともに、担い手不足や高齢化といった構造的課題へ対応し、地域固有の自然資源や文化、
伝統技術等と新技術を掛け合わせ、
高付加価値の商品・サービスを創出することができる。
都市と地方の間で、また地域の内外で、関係人口を中心とした人・モノ・技術の交流・
結合、分野を越えた連携・協働の流れを創ることで、都市と地方は二項対立的な構造を越
え、
共生関係となり、
その結び付きにより我が国全体の持続可能性を高めることができる。
今般、10年後に目指す姿(社会像)として定量的なものを示した基本構想をとりまとめ、
以下の政策の5本柱に沿って、政府全体で「地方創生2.0」を「令和の日本列島改造」と
して力強く進めていく。
先進的な取組の成果を、そのまま他地域に模倣・移植するのではなく、各地域が主体的
に考え、産官学金労言士32等の多様なステークホルダーを巻き込み、それぞれの地域の特性
や資源、課題に応じて柔軟に取り入れ、広く普遍化させる。
①安心して働き、暮らせる地方の生活環境の創生
若者や女性にも選ばれる地方の実現に向け、東京圏から地方への若者の流れを倍増させ
ることを目指す。このため、地域の働き方・職場改革を起点とした社会変革や地域に愛着
を持ち地域で活躍する人材の育成を行い、地方の魅力を高め、地方への転入希望を増やす
環境整備を進める。安心して暮らせる地方の実現に向け、買物環境の維持・向上の取組が
行われている市町村10割、医療・介護サービスの維持・確保の取組が行われている地方公
共団体10割、「交通空白」地区において解消の取組が行われている市町村10割を目指す。
このため、将来を見据えた持続可能な地域のサービス拠点づくり、地域医療提供体制の維
持・確保、意欲と能力のある「民」の力を活かした官民共創のまちづくり、全世代・全員
活躍型「生涯活躍のまち」(日本版CCRC)2.0、地域交通のリ・デザインの全面展開
に取り組む。一人一人が活躍できる社会の実現に向け、希望する職員の副業・兼業が可能
な職場環境を整備した事業者数10割を目指す。このため、地方公共団体や地域金融機関、
JA等において、希望する職員の副業・兼業が可能となるよう、許可基準の弾力化や就業
32
産は産業界、官は地方公共団体や国の関係機関、学は大学等の教育機関、金は金融機関、労は労働団体等、言は報道機関、
士は士業等をそれぞれ指す。
10