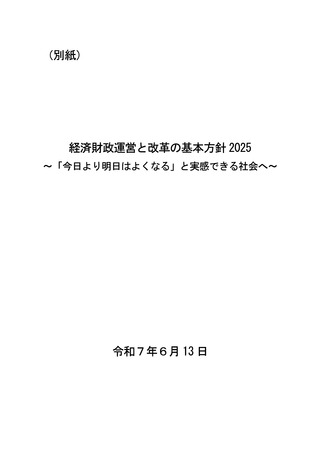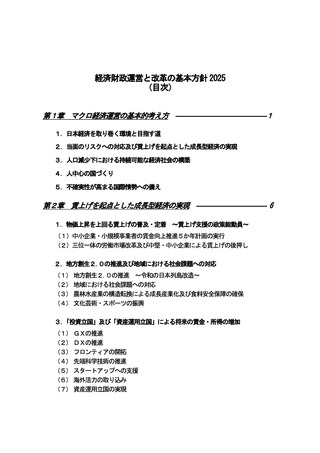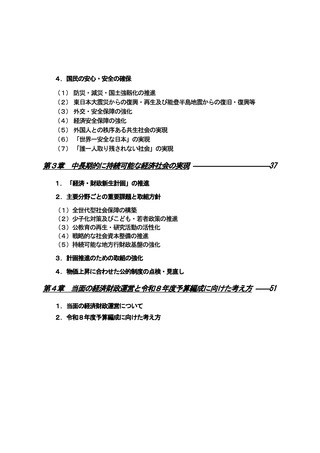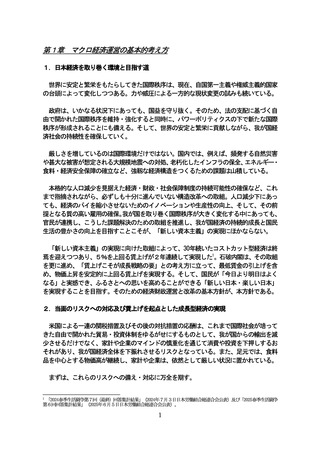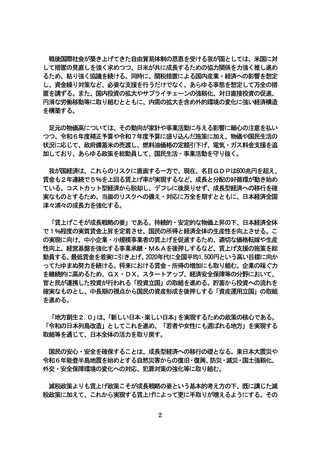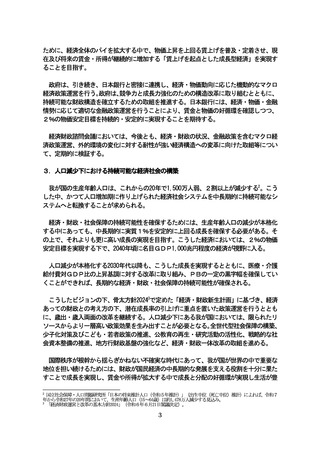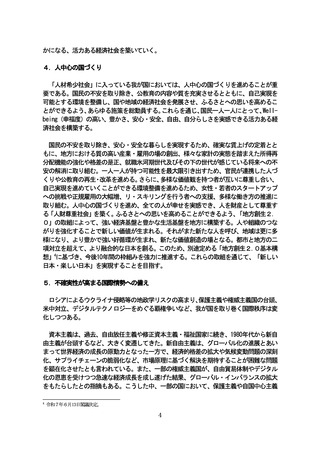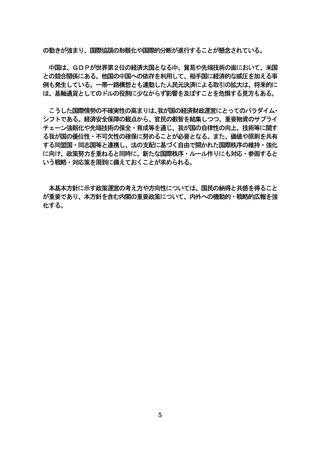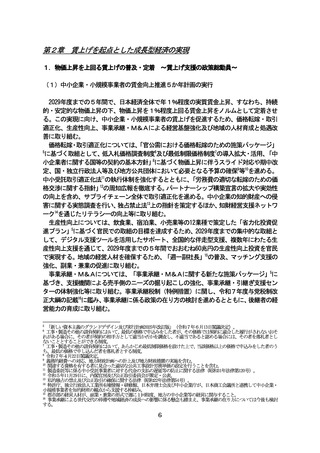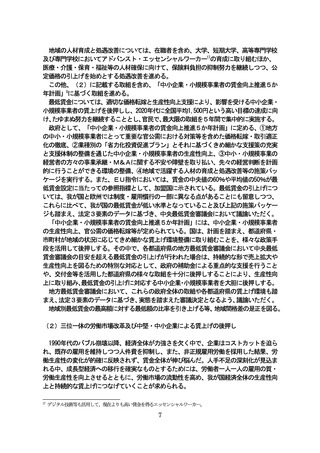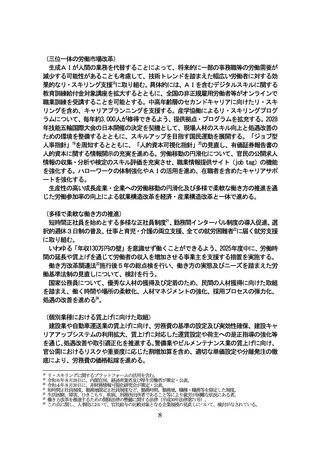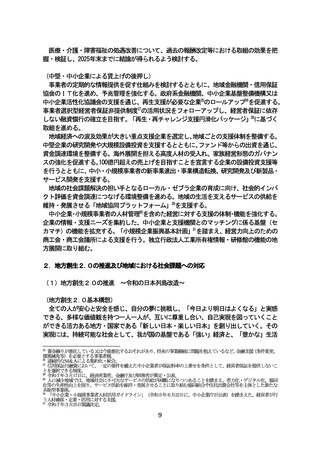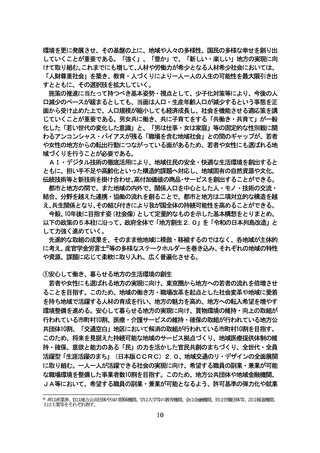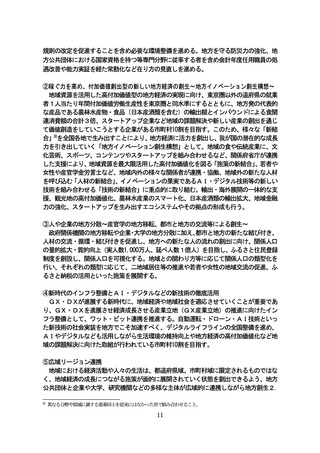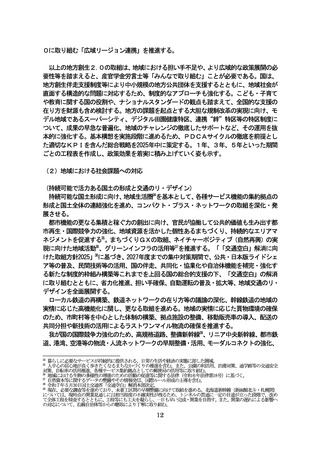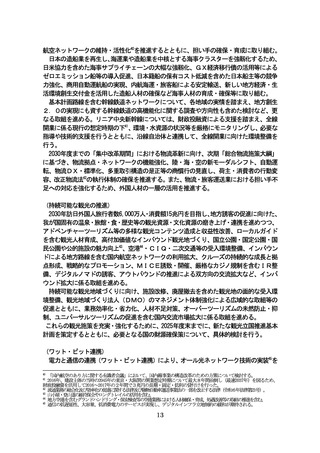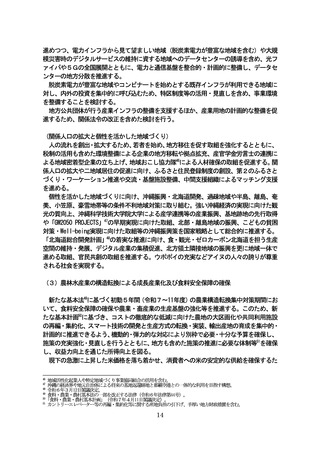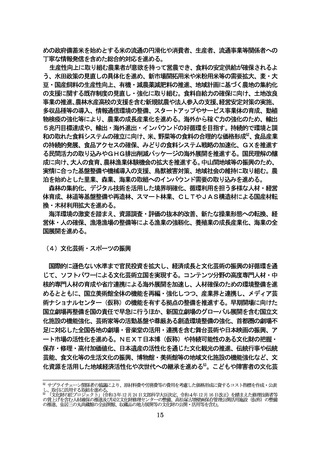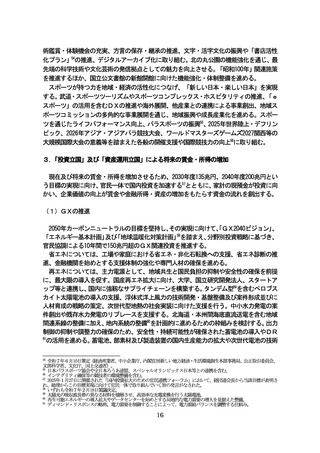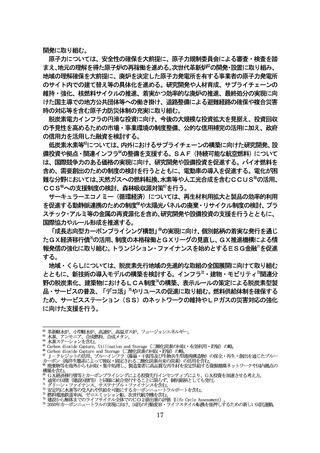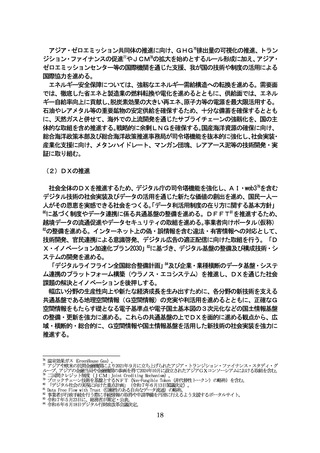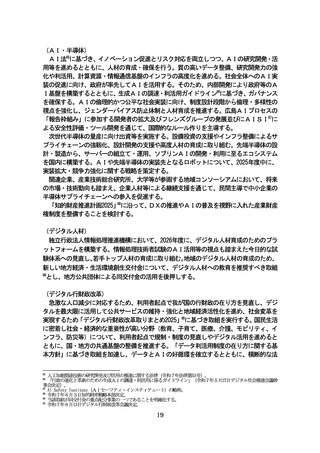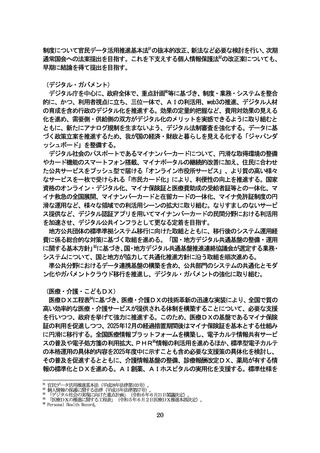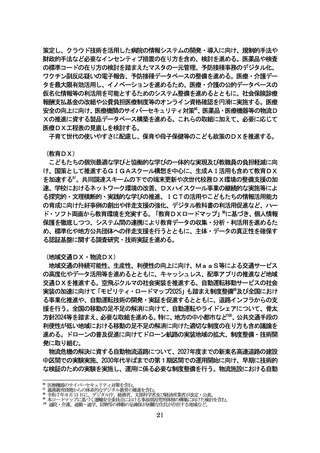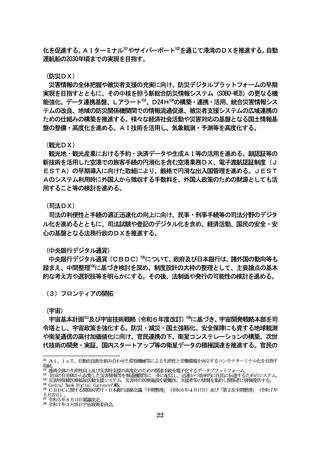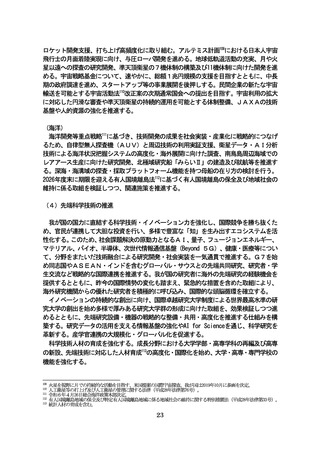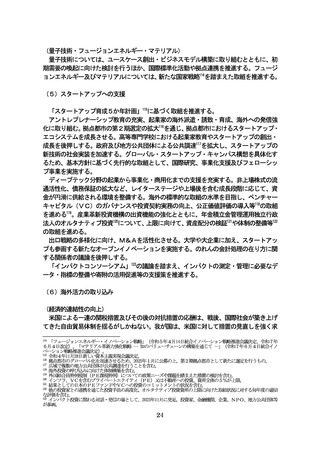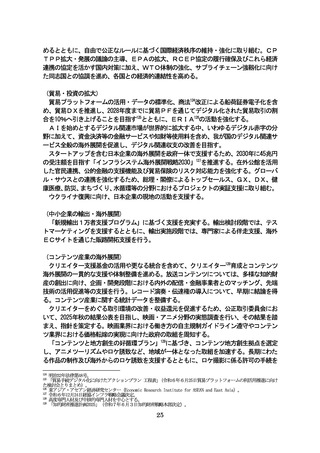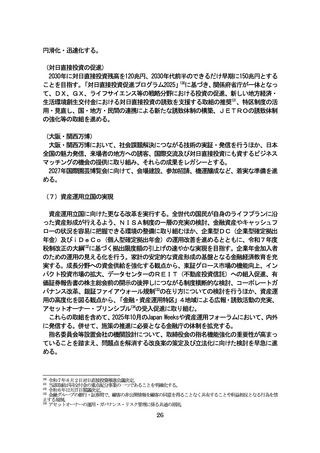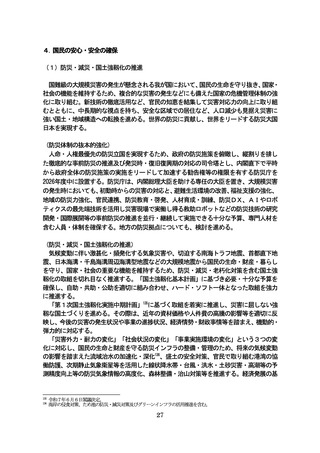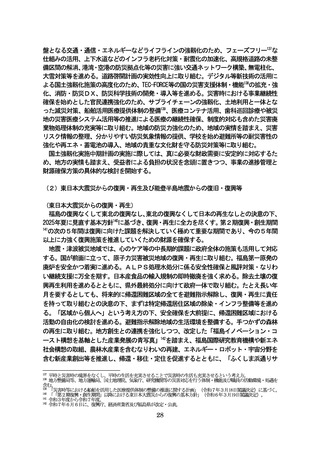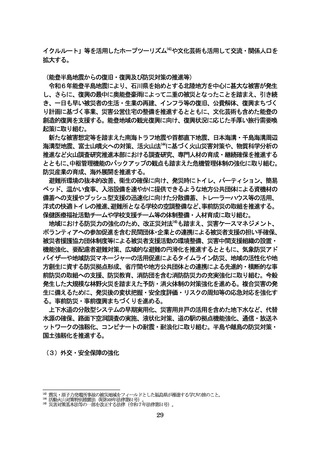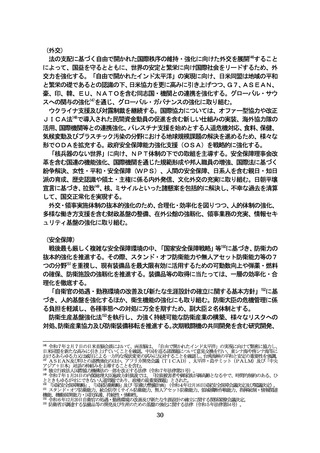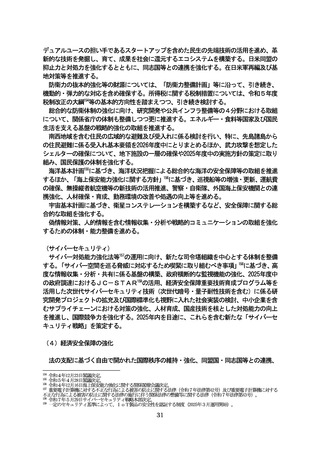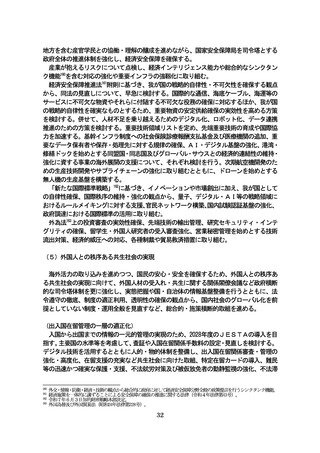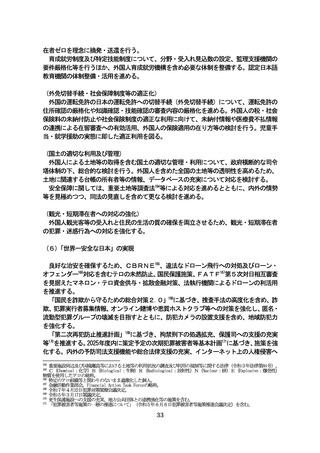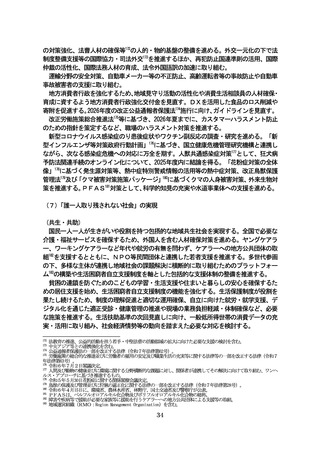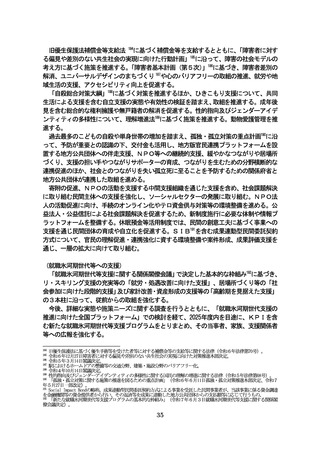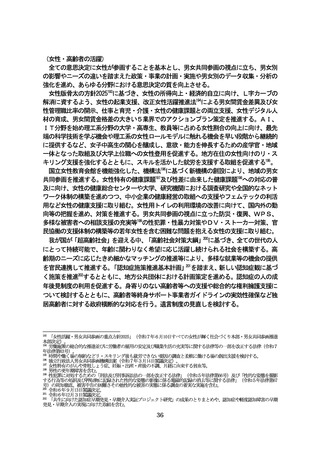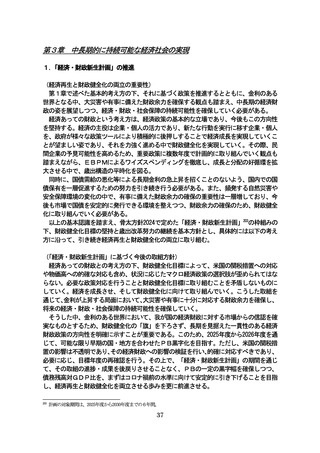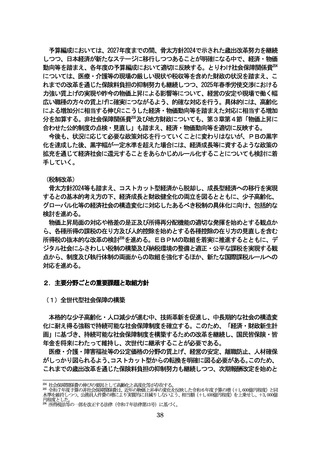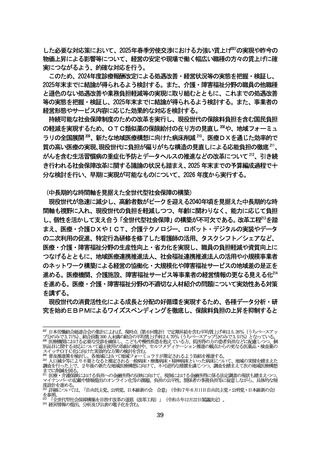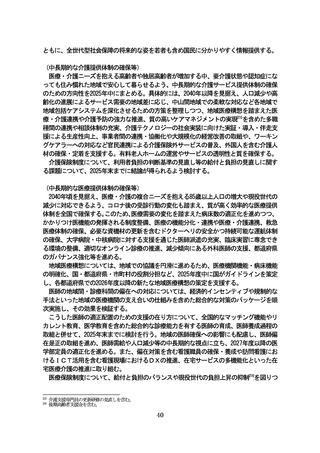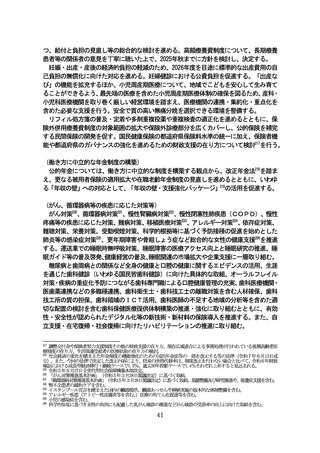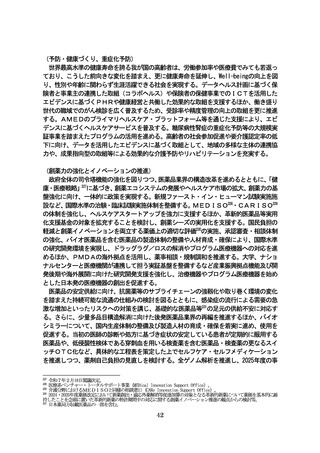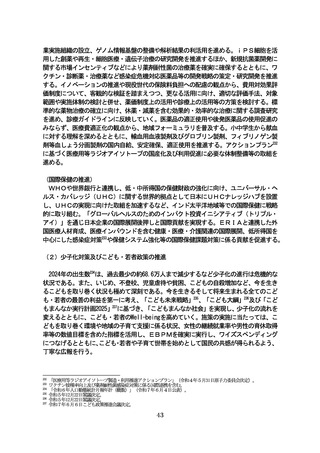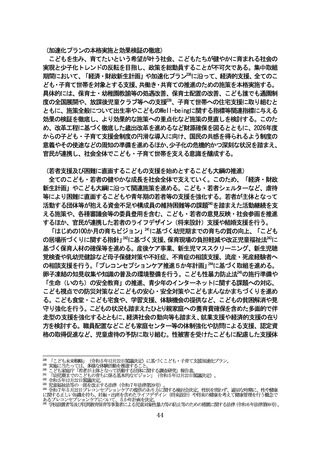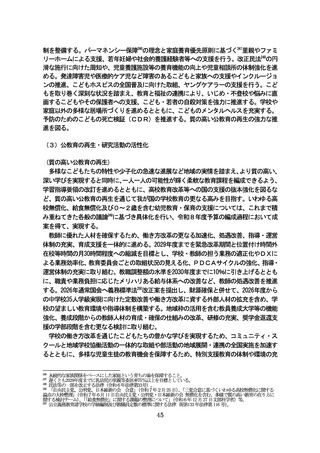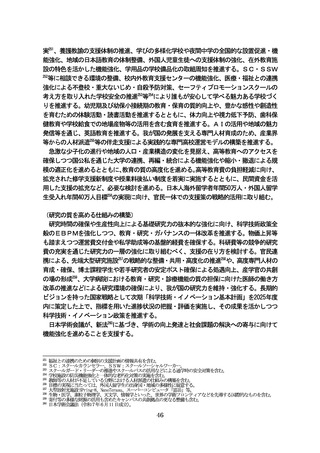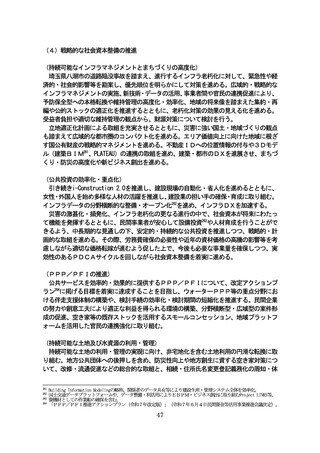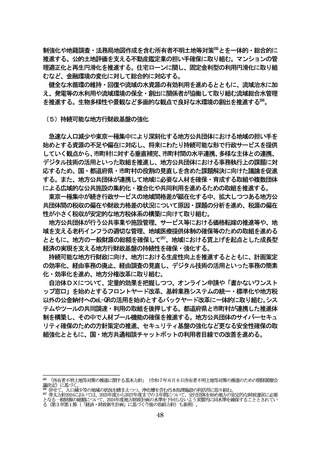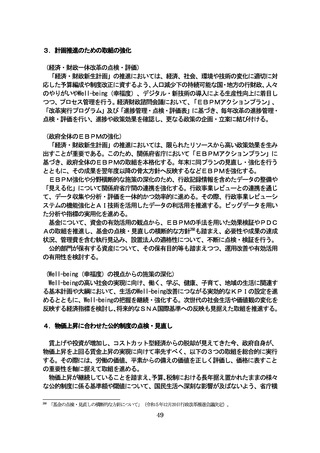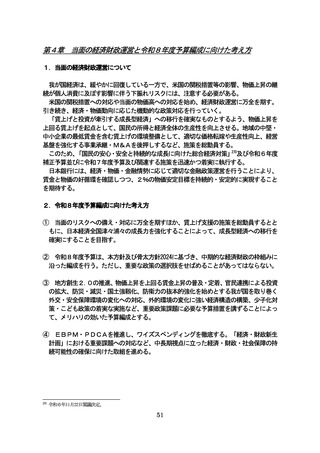よむ、つかう、まなぶ。
経済財政運営と改革の基本方針2025 ~「今日より明日はよくなる」と実感できる社会へ~(令和7年6月13日閣議決定) (32 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/cabinet/honebuto/2025/decision0613.html |
| 出典情報 | 経済財政運営と改革の基本方針2025(6/13)《内閣府》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
盤となる交通・通信・エネルギーなどライフラインの強靱化のため、フェーズフリー137な
仕組みの活用、上下水道などのインフラ老朽化対策・耐震化の加速化、高規格道路の未整
備区間の解消、港湾・空港の防災拠点化等の災害に強い交通ネットワーク構築、無電柱化、
大雪対策等を進める。道路啓開計画の実効性向上に取り組む。デジタル等新技術の活用に
よる国土強靱化施策の高度化のため、TEC-FORCE等の国の災害支援体制・機能138の拡充・強
化、消防・防災DX、防災科学技術の開発・導入等を進める。災害時における事業継続性
確保を始めとした官民連携強化のため、サプライチェーンの強靱化、土地利用と一体とな
った減災対策、船舶活用医療提供体制の整備139、医療コンテナ活用、歯科巡回診療や被災
地の災害医療システム活用等の推進による医療の継続性確保、制度的対応も含めた災害廃
棄物処理体制の充実等に取り組む。地域の防災力強化のため、地域の実情を踏まえ、災害
リスク情報の整理、分かりやすい防災気象情報の提供、学校を始め避難所等の耐災害性の
強化や再エネ・蓄電池の導入、地域の貴重な文化財を守る防災対策等に取り組む。
国土強靱化実施中期計画の実施に際しては、真に必要な財政需要に安定的に対応するた
め、地方の実情も踏まえ、受益者による負担の状況を念頭に置きつつ、事業の進捗管理と
財源確保方策の具体的な検討を開始する。
(2)東日本大震災からの復興・再生及び能登半島地震からの復旧・復興等
(東日本大震災からの復興・再生)
福島の復興なくして東北の復興なし、東北の復興なくして日本の再生なしとの決意の下、
2025年夏に見直す基本方針140に基づき、復興・再生に全力を尽くす。第2期復興・創生期間
141
の次の5年間は復興に向けた課題を解決していく極めて重要な期間であり、今の5年間
以上に力強く復興施策を推進していくための財源を確保する。
地震・津波被災地域では、心のケア等の中長期的課題に政府全体の施策も活用して対応
する。国が前面に立って、原子力災害被災地域の復興・再生に取り組む。福島第一原発の
廃炉を安全かつ着実に進める。ALPS処理水処分に係る安全性確保と風評対策・なりわ
い継続支援に万全を期す。日本産食品の輸入規制の即時撤廃を強く求める。除去土壌の復
興再生利用を進めるとともに、県外最終処分に向けて政府一体で取り組む。たとえ長い年
月を要するとしても、将来的に帰還困難区域の全てを避難指示解除し、復興・再生に責任
を持って取り組むとの決意の下、まずは特定帰還居住区域の除染・インフラ整備等を進め
る。「区域から個人へ」という考え方の下、安全確保を大前提に、帰還困難区域における
活動の自由化の検討を進める。避難指示解除地域の生活環境を整備する。手つかずの森林
の再生に取り組む。地方創生との連携を強化しつつ、改定した「福島イノベーション・コ
ースト構想を基軸とした産業発展の青写真」142を踏まえ、福島国際研究教育機構や新エネ
社会構想の取組、農林水産業を含むなりわいの再建、エネルギー・ロボット・宇宙分野を
含む新産業創出等を推進し、帰還・移住・定住を促進するとともに、「ふくしま浜通りサ
137
平時と災害時の境界をなくし、平時の生活を充実させることで災害時の生活も充実させるという考え方。
地方整備局等、地方運輸局、国土地理院、気象庁、研究機関等の災害対応を行う体制・機能及び職員の活動環境・処遇を
含む。
139
「災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する計画」(令和7年3月18日閣議決定)に基づく。
140
「「第2期復興・創生期間」以降における東日本大震災からの復興の基本方針」(令和6年3月19日閣議決定)。
141
令和3年度から令和7年度。
142
令和7年6月6日に、復興庁、経済産業省及び福島県が改定・公表。
138
28
仕組みの活用、上下水道などのインフラ老朽化対策・耐震化の加速化、高規格道路の未整
備区間の解消、港湾・空港の防災拠点化等の災害に強い交通ネットワーク構築、無電柱化、
大雪対策等を進める。道路啓開計画の実効性向上に取り組む。デジタル等新技術の活用に
よる国土強靱化施策の高度化のため、TEC-FORCE等の国の災害支援体制・機能138の拡充・強
化、消防・防災DX、防災科学技術の開発・導入等を進める。災害時における事業継続性
確保を始めとした官民連携強化のため、サプライチェーンの強靱化、土地利用と一体とな
った減災対策、船舶活用医療提供体制の整備139、医療コンテナ活用、歯科巡回診療や被災
地の災害医療システム活用等の推進による医療の継続性確保、制度的対応も含めた災害廃
棄物処理体制の充実等に取り組む。地域の防災力強化のため、地域の実情を踏まえ、災害
リスク情報の整理、分かりやすい防災気象情報の提供、学校を始め避難所等の耐災害性の
強化や再エネ・蓄電池の導入、地域の貴重な文化財を守る防災対策等に取り組む。
国土強靱化実施中期計画の実施に際しては、真に必要な財政需要に安定的に対応するた
め、地方の実情も踏まえ、受益者による負担の状況を念頭に置きつつ、事業の進捗管理と
財源確保方策の具体的な検討を開始する。
(2)東日本大震災からの復興・再生及び能登半島地震からの復旧・復興等
(東日本大震災からの復興・再生)
福島の復興なくして東北の復興なし、東北の復興なくして日本の再生なしとの決意の下、
2025年夏に見直す基本方針140に基づき、復興・再生に全力を尽くす。第2期復興・創生期間
141
の次の5年間は復興に向けた課題を解決していく極めて重要な期間であり、今の5年間
以上に力強く復興施策を推進していくための財源を確保する。
地震・津波被災地域では、心のケア等の中長期的課題に政府全体の施策も活用して対応
する。国が前面に立って、原子力災害被災地域の復興・再生に取り組む。福島第一原発の
廃炉を安全かつ着実に進める。ALPS処理水処分に係る安全性確保と風評対策・なりわ
い継続支援に万全を期す。日本産食品の輸入規制の即時撤廃を強く求める。除去土壌の復
興再生利用を進めるとともに、県外最終処分に向けて政府一体で取り組む。たとえ長い年
月を要するとしても、将来的に帰還困難区域の全てを避難指示解除し、復興・再生に責任
を持って取り組むとの決意の下、まずは特定帰還居住区域の除染・インフラ整備等を進め
る。「区域から個人へ」という考え方の下、安全確保を大前提に、帰還困難区域における
活動の自由化の検討を進める。避難指示解除地域の生活環境を整備する。手つかずの森林
の再生に取り組む。地方創生との連携を強化しつつ、改定した「福島イノベーション・コ
ースト構想を基軸とした産業発展の青写真」142を踏まえ、福島国際研究教育機構や新エネ
社会構想の取組、農林水産業を含むなりわいの再建、エネルギー・ロボット・宇宙分野を
含む新産業創出等を推進し、帰還・移住・定住を促進するとともに、「ふくしま浜通りサ
137
平時と災害時の境界をなくし、平時の生活を充実させることで災害時の生活も充実させるという考え方。
地方整備局等、地方運輸局、国土地理院、気象庁、研究機関等の災害対応を行う体制・機能及び職員の活動環境・処遇を
含む。
139
「災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する計画」(令和7年3月18日閣議決定)に基づく。
140
「「第2期復興・創生期間」以降における東日本大震災からの復興の基本方針」(令和6年3月19日閣議決定)。
141
令和3年度から令和7年度。
142
令和7年6月6日に、復興庁、経済産業省及び福島県が改定・公表。
138
28