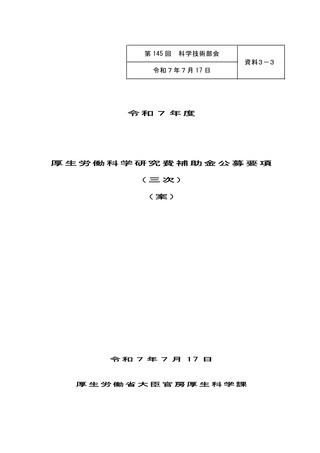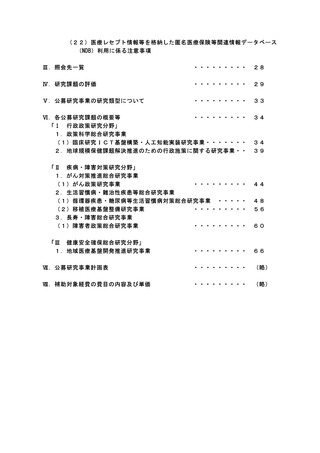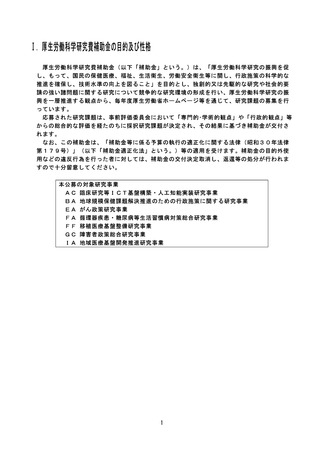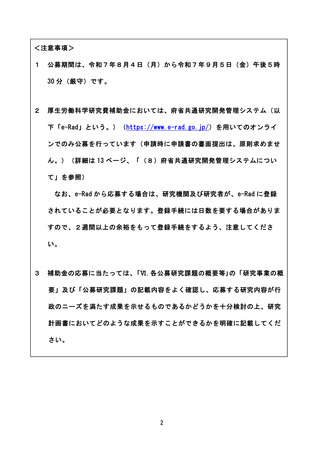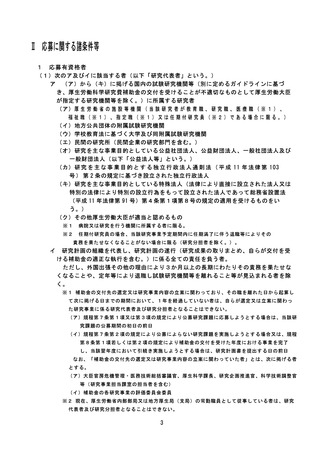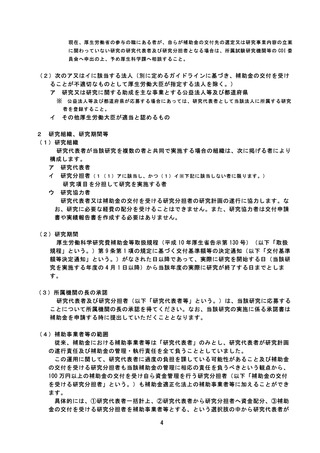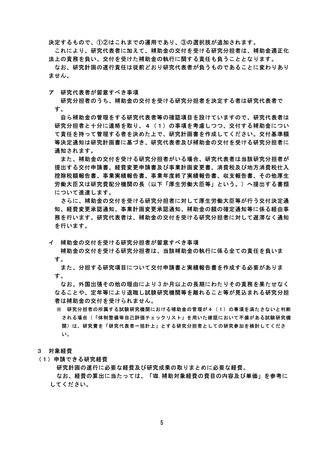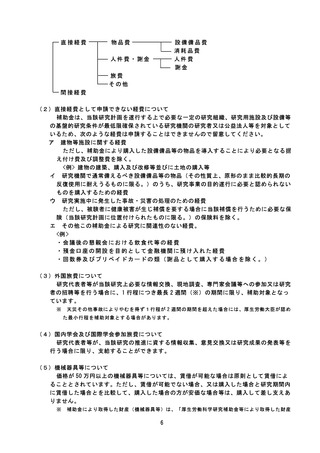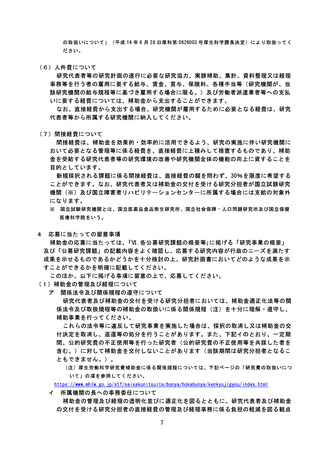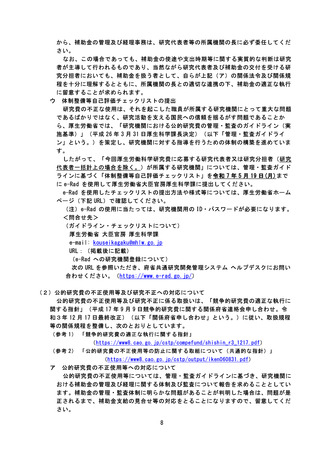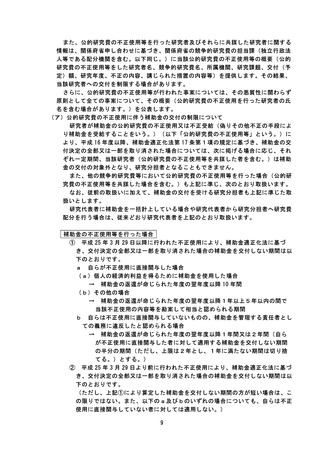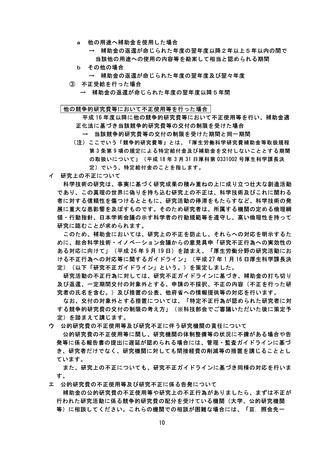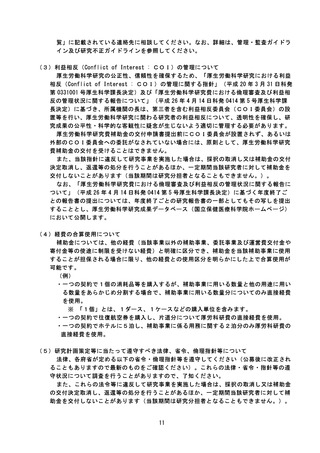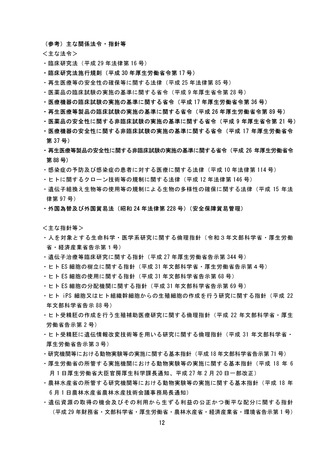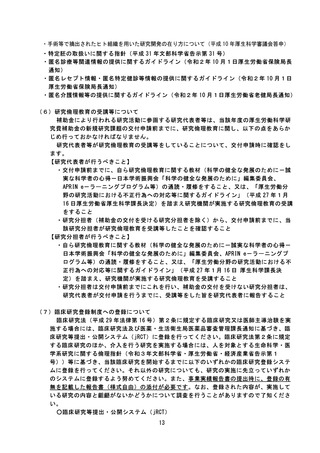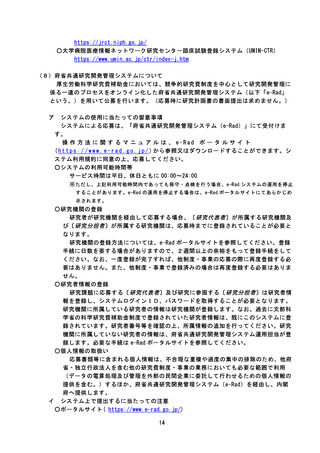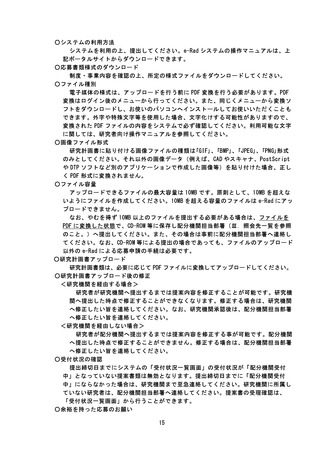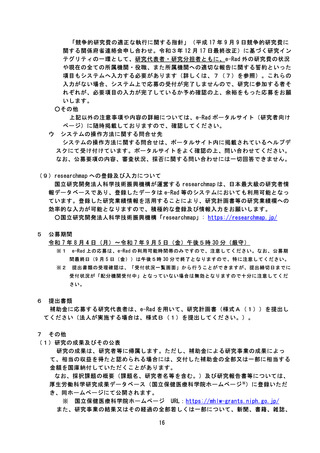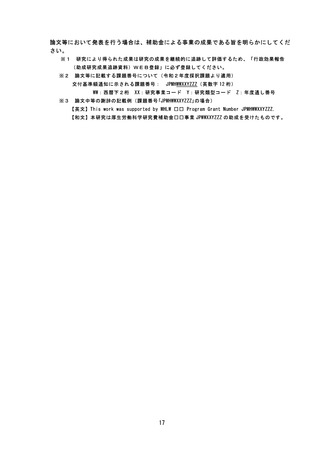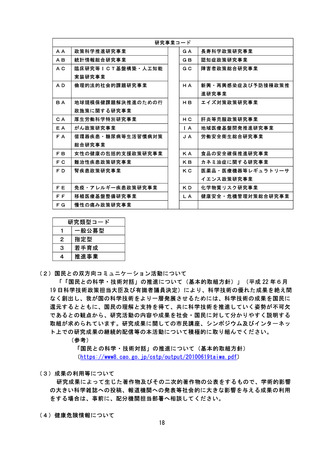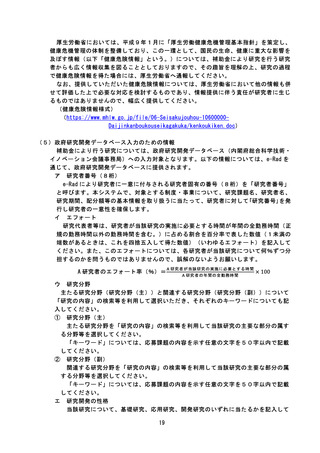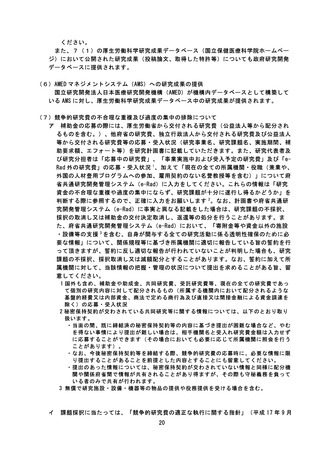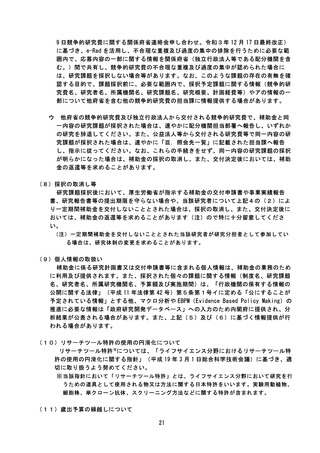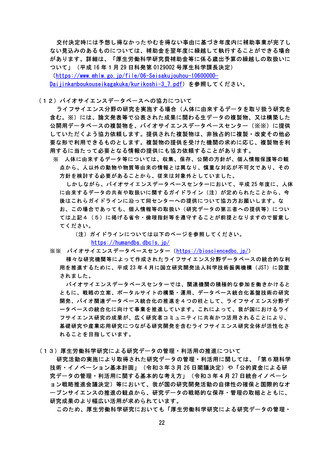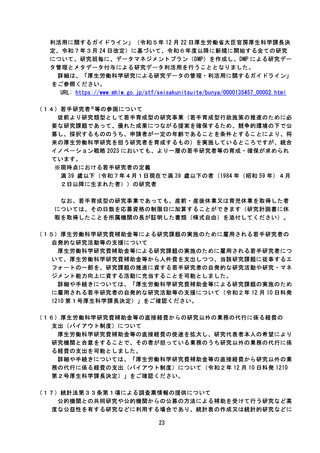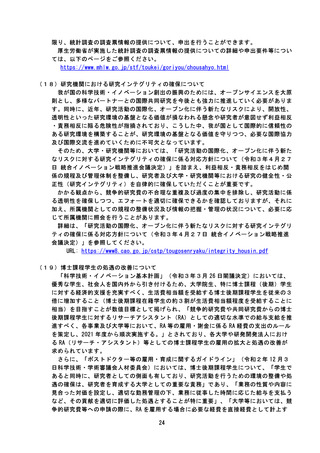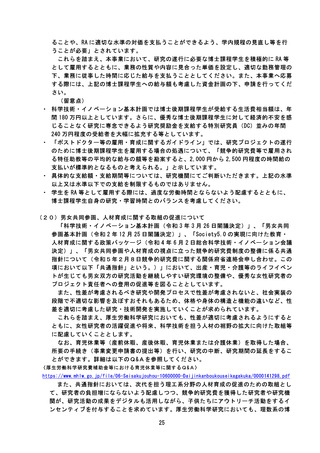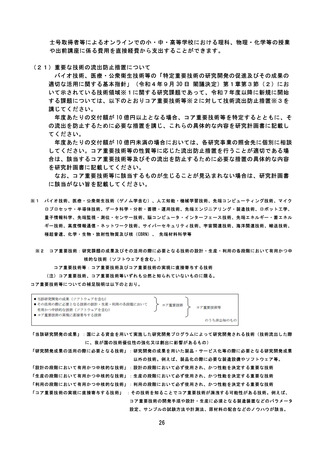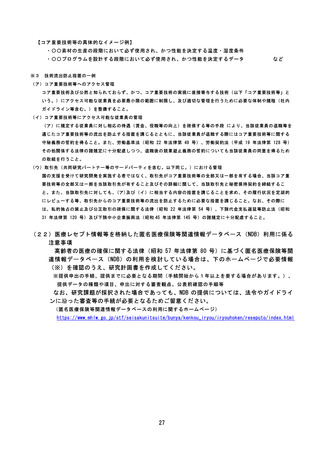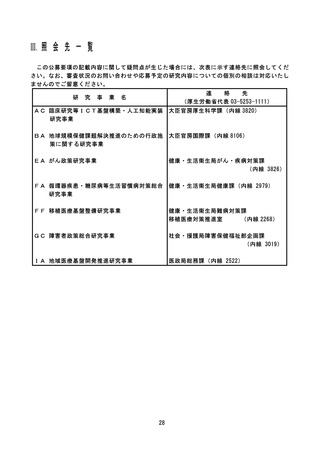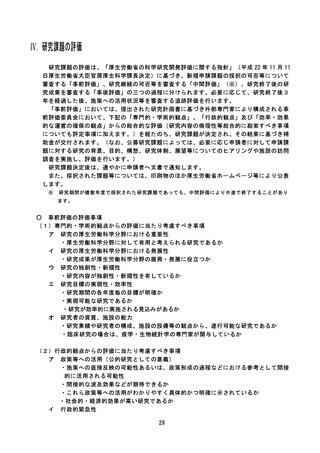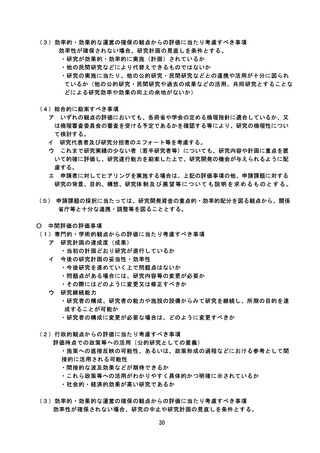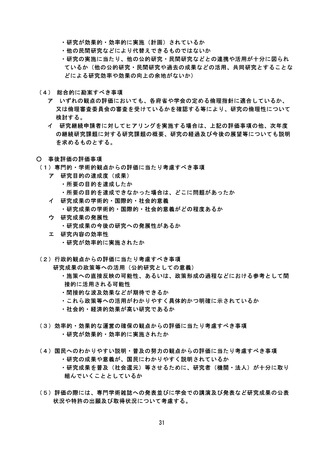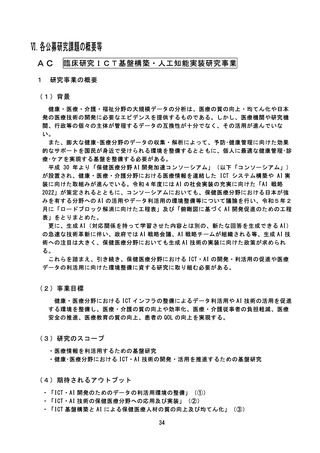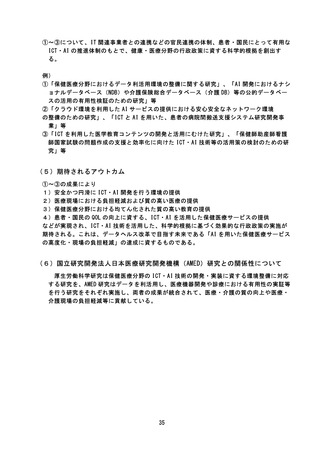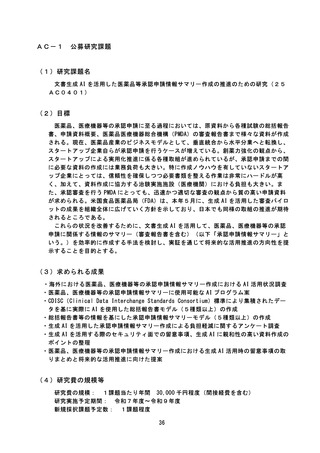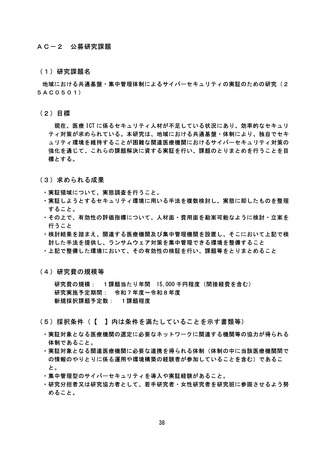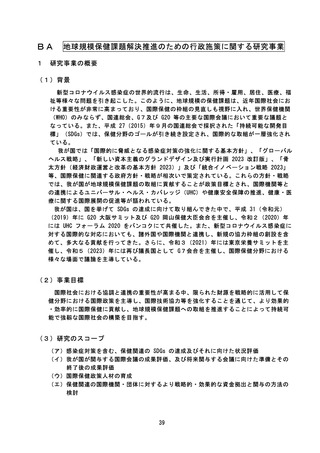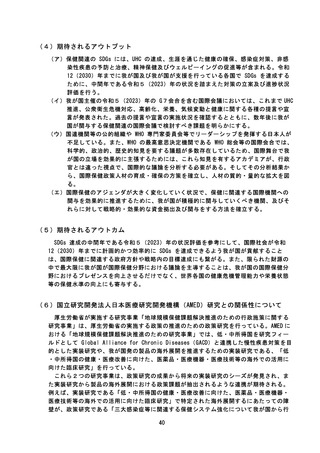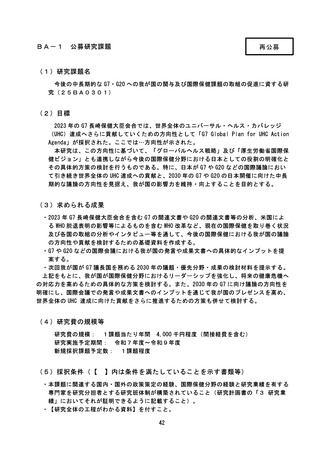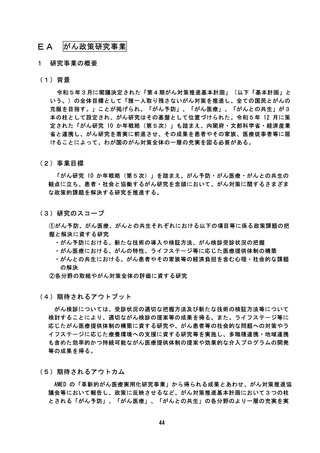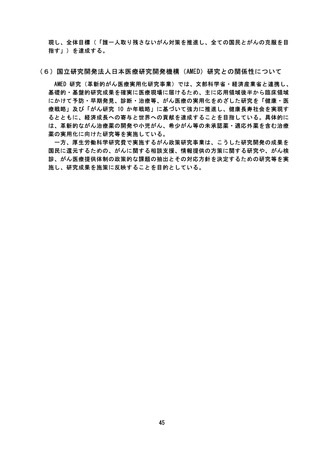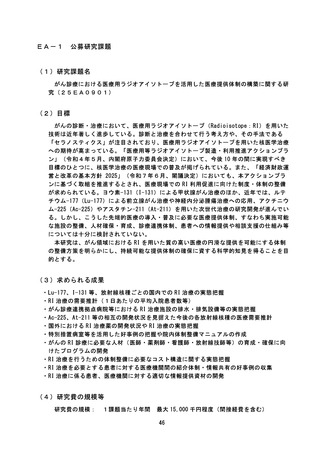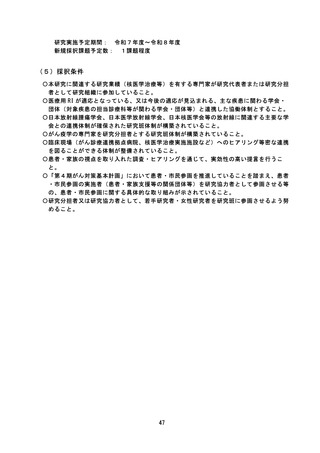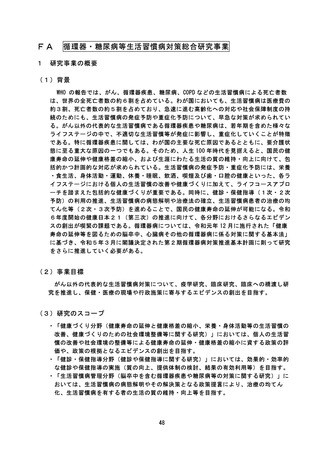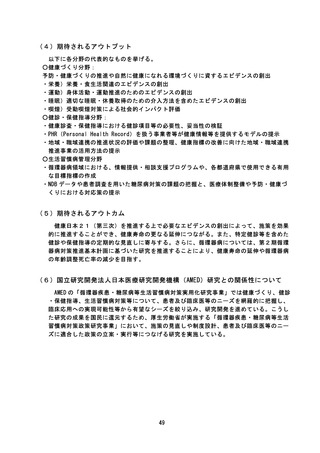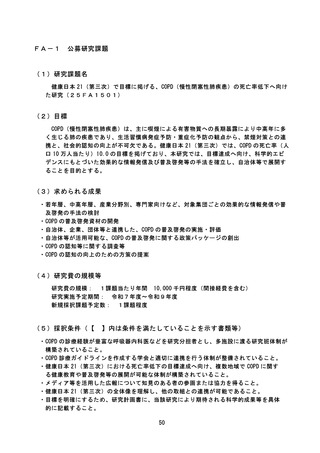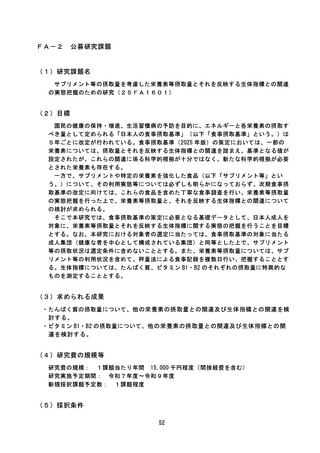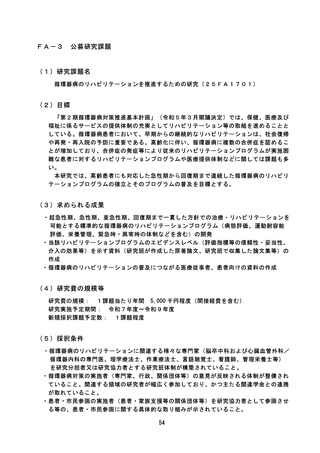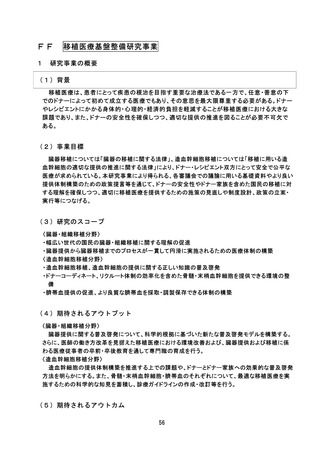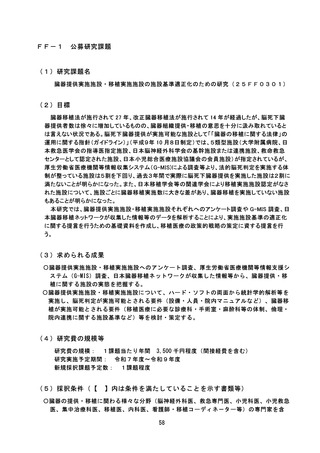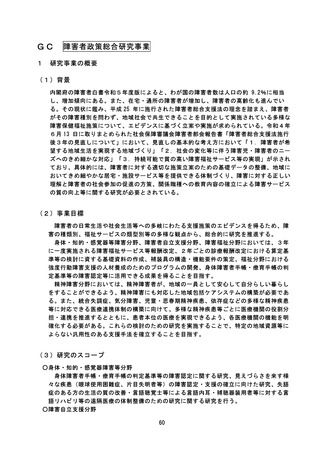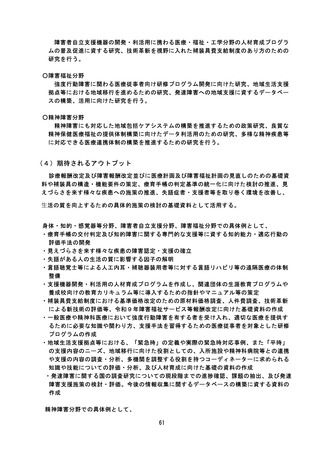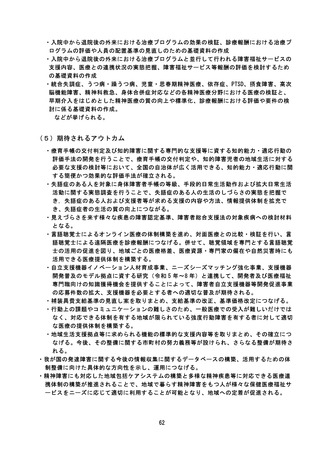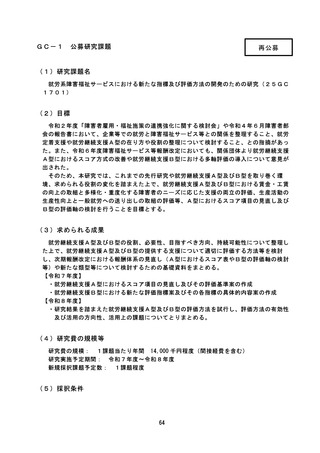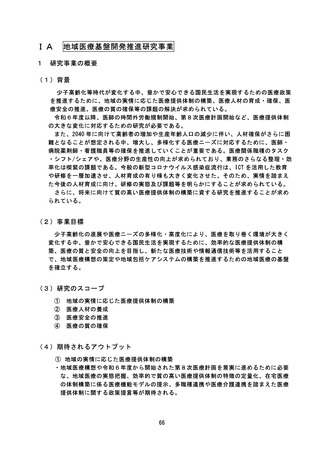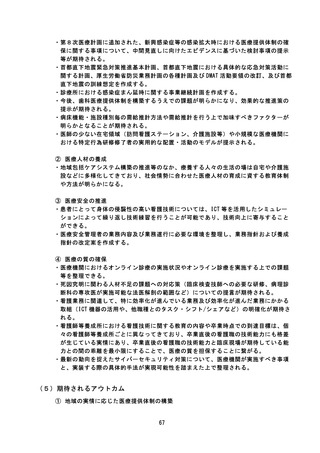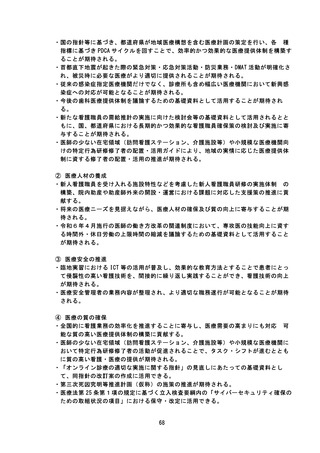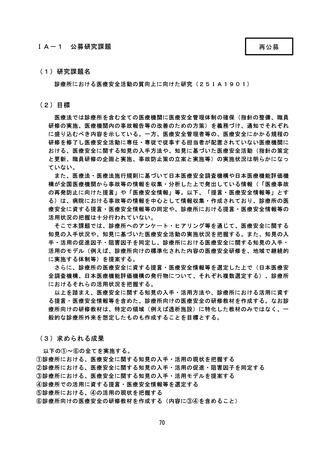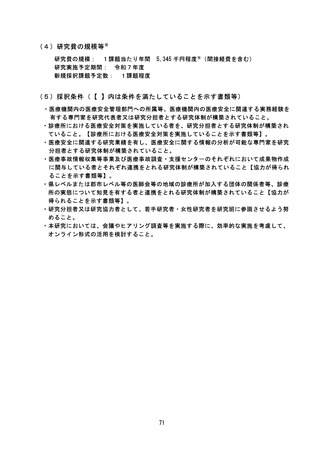よむ、つかう、まなぶ。
【資料3-3】令和7年度 厚生労働科学研究費補助金公募要項(三次)(案) (65 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59644.html |
| 出典情報 | 厚生科学審議会 科学技術部会(第145回 7/16)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
・入院中から退院後の外来における治療プログラムの効果の検証、診療報酬における治療プ
ログラムの評価や人員の配置基準の見直しのための基礎資料の作成
・入院中から退院後の外来における治療プログラムと並行して行われる障害福祉サービスの
支援内容、医療との連携状況の実態把握、障害福祉サービス等報酬の評価を検討するため
の基礎資料の作成
・統合失調症、うつ病・躁うつ病、児童・思春期精神医療、依存症、PTSD、摂食障害、高次
脳機能障害、精神科救急、身体合併症対応などの各精神医療分野における医療の検証と、
早期介入をはじめとした精神医療の質の向上や標準化、診療報酬における評価や要件の検
討に係る基礎資料の作成。
などが挙げられる。
(5)期待されるアウトカム
・療育手帳の交付判定及び知的障害に関する専門的な支援等に資する知的能力・適応行動の
評価手法の開発を行うことで、療育手帳の交付判定や、知的障害児者の地域生活に対する
必要な支援の検討等において、全国の自治体が広く活用できる、知的能力・適応行動に関
する簡便かつ効果的な評価手法が確立される。
・失語症のある人を対象に身体障害者手帳の等級、手段的日常生活動作および拡大日常生活
活動に関する実態調査を行うことで、失語症のある人の生活のしづらさの実態を把握で
き,失語症のある人および支援者等が求める支援の内容や方法、情報提供体制を拡充で
き、失語症者の生活の質の向上につながる。
・見えづらさを来す様々な疾患の障害認定基準、障害者総合支援法の対象疾病への検討材料
となる。
・言語聴覚士によるオンライン医療の体制構築を進め、対面医療との比較・検証を行い、言
語聴覚士による遠隔医療を診療報酬につなげる。併せて、聴覚領域を専門とする言語聴覚
士の活用の促進を図り、地域ごとの医療格差、医療資源・専門家の偏在や自然災害時にも
活用できる医療提供体制を構築する。
・自立支援機器イノベーション人材育成事業、ニーズシーズマッチング強化事業、支援機器
開発普及のモデル拠点に資する研究(令和 5 年~8 年)と連携して、開発者及び医療福祉
専門職向けの知識獲得機会を提供することによって、障害者自立支援機器等開発促進事業
の応募件数の拡大、支援機器を必要とする者への適切な普及が期待される。
・補装具費支給基準の見直し案を取りまとめ、支給基準の改正、基準価格改定につなげる。
・行動上の課題やコミュニケーションの難しさのため、一般医療での受入が難しいだけでは
なく、対応できる体制を有する地域が限られている強度行動障害を有する者に対して適切
な医療の提供体制を構築する。
・地域生活支援拠点等に求められる機能の標準的な支援内容等を取りまとめ、その確立につ
なげる。今後、その整備に関する市町村の努力義務等が設けられ、さらなる整備が期待さ
れる。
・我が国の発達障害に関する今後の情報収集に関するデータベースの構築、活用するための体
制整備に向けた具体的な方向性を示し、運用につなげる。
・精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築と多様な精神疾患等に対応できる医療連
携体制の構築が推進されることで、地域で暮らす精神障害をもつ人が様々な保健医療福祉サ
ービスをニーズに応じて適切に利用することが可能となり、地域への定着が促進される。
62
ログラムの評価や人員の配置基準の見直しのための基礎資料の作成
・入院中から退院後の外来における治療プログラムと並行して行われる障害福祉サービスの
支援内容、医療との連携状況の実態把握、障害福祉サービス等報酬の評価を検討するため
の基礎資料の作成
・統合失調症、うつ病・躁うつ病、児童・思春期精神医療、依存症、PTSD、摂食障害、高次
脳機能障害、精神科救急、身体合併症対応などの各精神医療分野における医療の検証と、
早期介入をはじめとした精神医療の質の向上や標準化、診療報酬における評価や要件の検
討に係る基礎資料の作成。
などが挙げられる。
(5)期待されるアウトカム
・療育手帳の交付判定及び知的障害に関する専門的な支援等に資する知的能力・適応行動の
評価手法の開発を行うことで、療育手帳の交付判定や、知的障害児者の地域生活に対する
必要な支援の検討等において、全国の自治体が広く活用できる、知的能力・適応行動に関
する簡便かつ効果的な評価手法が確立される。
・失語症のある人を対象に身体障害者手帳の等級、手段的日常生活動作および拡大日常生活
活動に関する実態調査を行うことで、失語症のある人の生活のしづらさの実態を把握で
き,失語症のある人および支援者等が求める支援の内容や方法、情報提供体制を拡充で
き、失語症者の生活の質の向上につながる。
・見えづらさを来す様々な疾患の障害認定基準、障害者総合支援法の対象疾病への検討材料
となる。
・言語聴覚士によるオンライン医療の体制構築を進め、対面医療との比較・検証を行い、言
語聴覚士による遠隔医療を診療報酬につなげる。併せて、聴覚領域を専門とする言語聴覚
士の活用の促進を図り、地域ごとの医療格差、医療資源・専門家の偏在や自然災害時にも
活用できる医療提供体制を構築する。
・自立支援機器イノベーション人材育成事業、ニーズシーズマッチング強化事業、支援機器
開発普及のモデル拠点に資する研究(令和 5 年~8 年)と連携して、開発者及び医療福祉
専門職向けの知識獲得機会を提供することによって、障害者自立支援機器等開発促進事業
の応募件数の拡大、支援機器を必要とする者への適切な普及が期待される。
・補装具費支給基準の見直し案を取りまとめ、支給基準の改正、基準価格改定につなげる。
・行動上の課題やコミュニケーションの難しさのため、一般医療での受入が難しいだけでは
なく、対応できる体制を有する地域が限られている強度行動障害を有する者に対して適切
な医療の提供体制を構築する。
・地域生活支援拠点等に求められる機能の標準的な支援内容等を取りまとめ、その確立につ
なげる。今後、その整備に関する市町村の努力義務等が設けられ、さらなる整備が期待さ
れる。
・我が国の発達障害に関する今後の情報収集に関するデータベースの構築、活用するための体
制整備に向けた具体的な方向性を示し、運用につなげる。
・精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築と多様な精神疾患等に対応できる医療連
携体制の構築が推進されることで、地域で暮らす精神障害をもつ人が様々な保健医療福祉サ
ービスをニーズに応じて適切に利用することが可能となり、地域への定着が促進される。
62