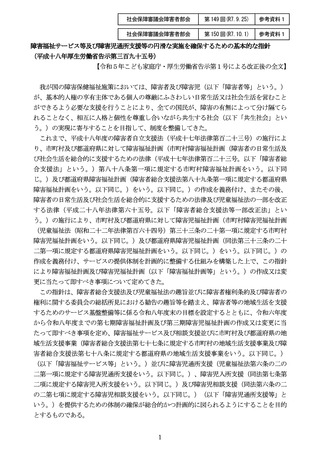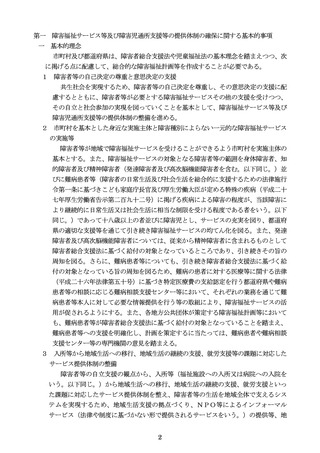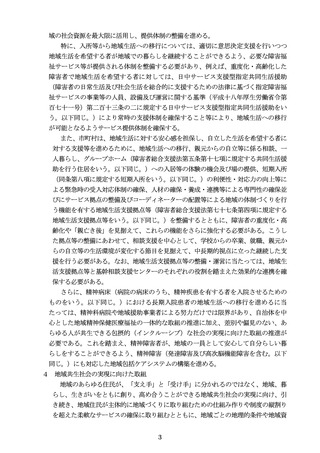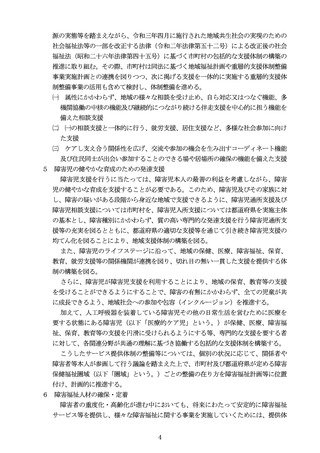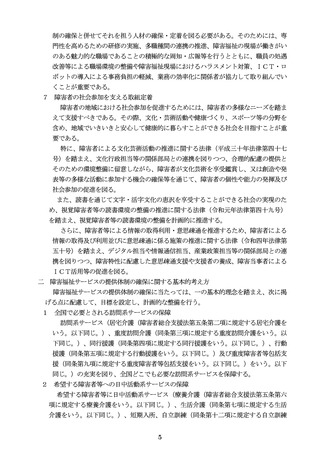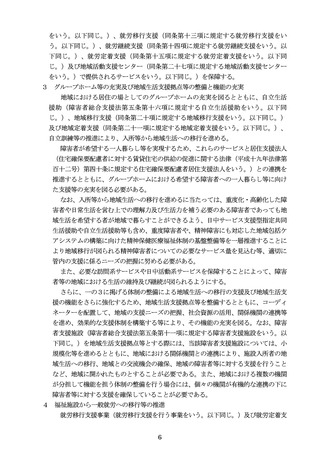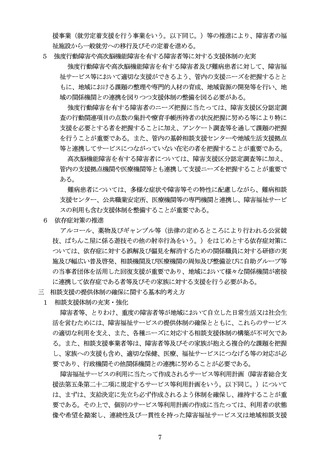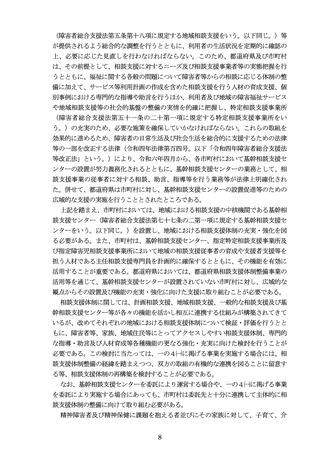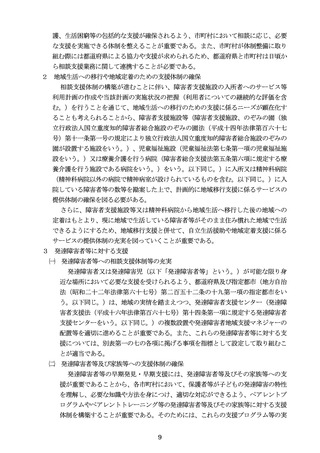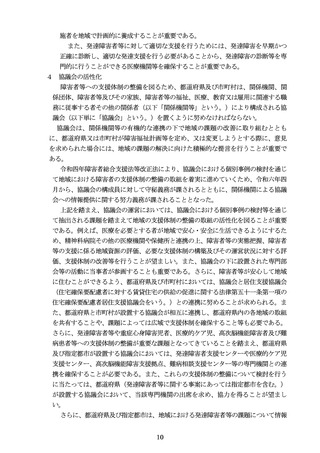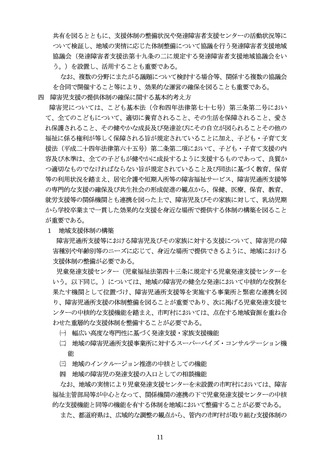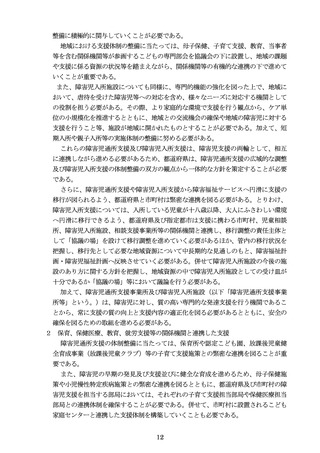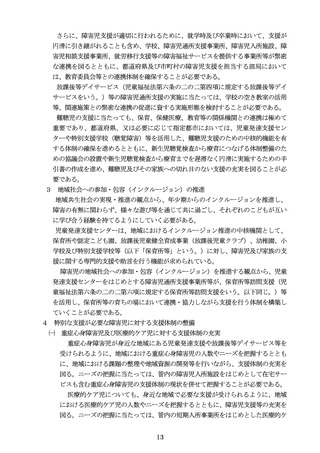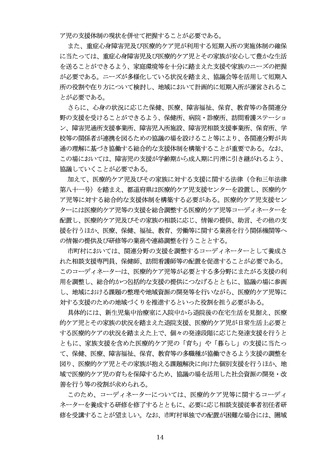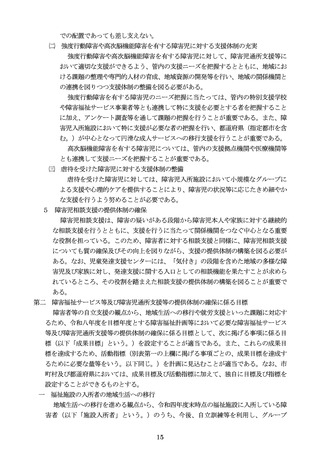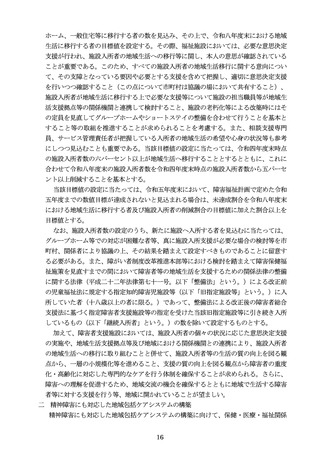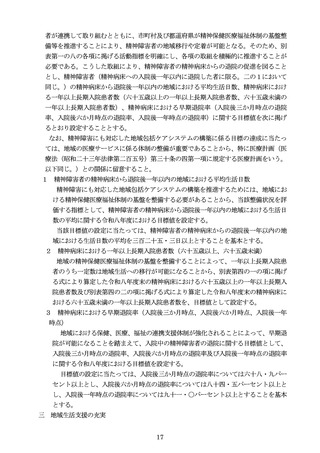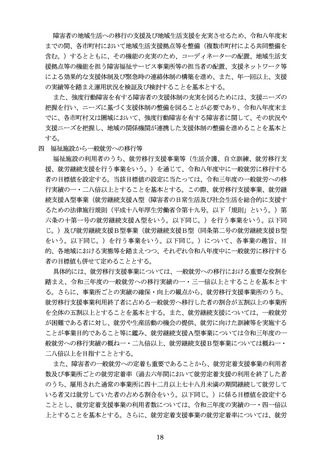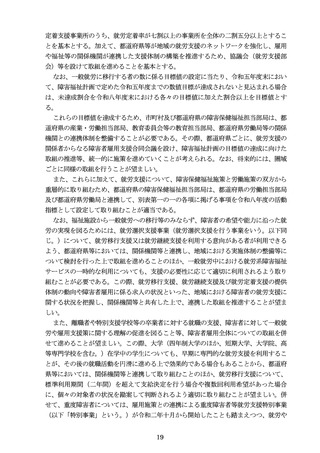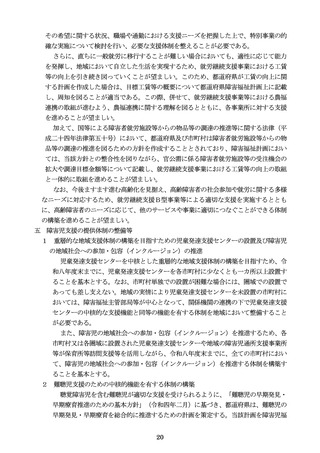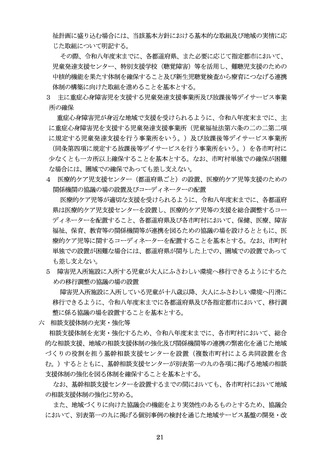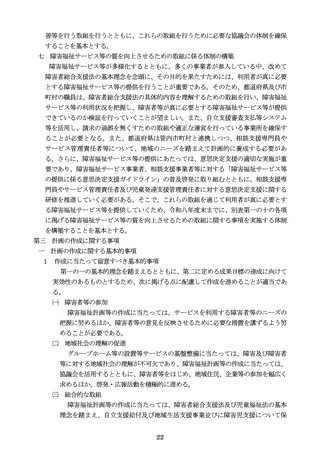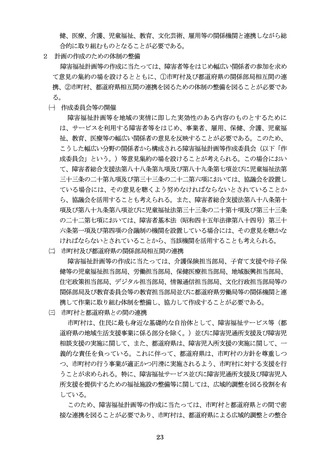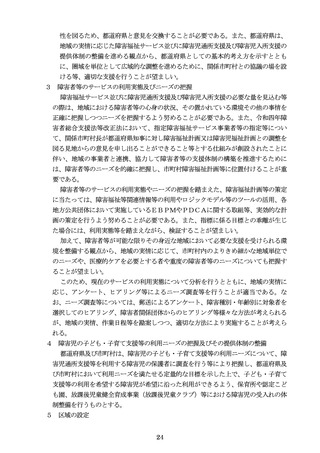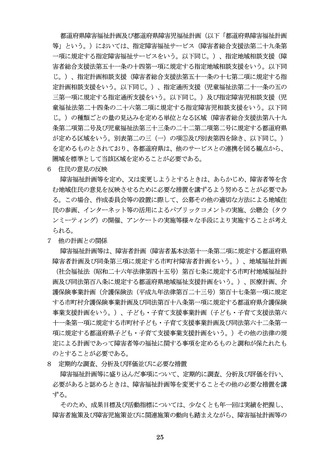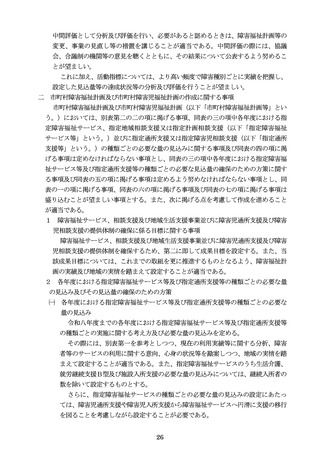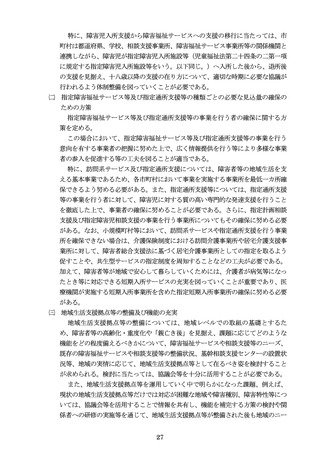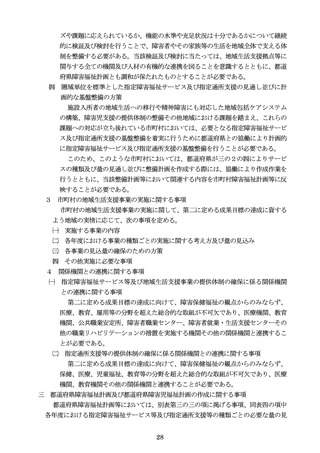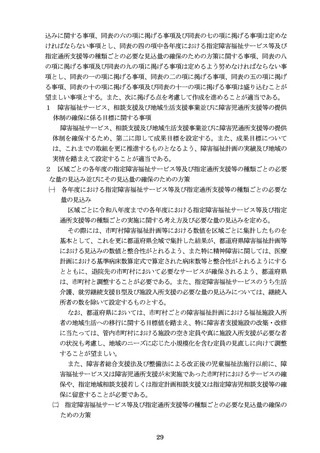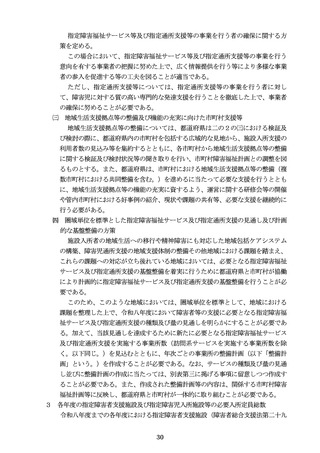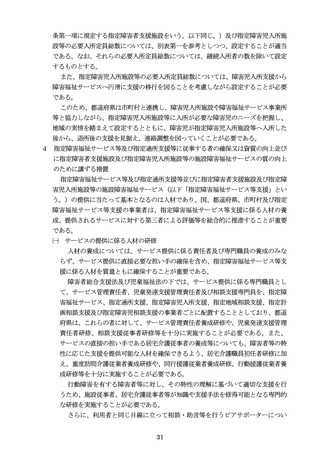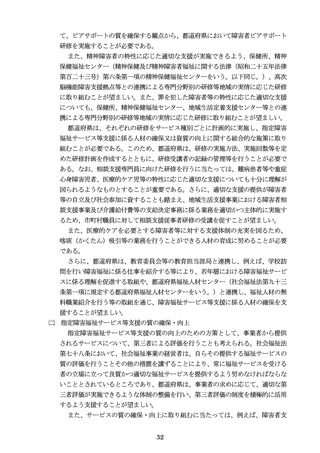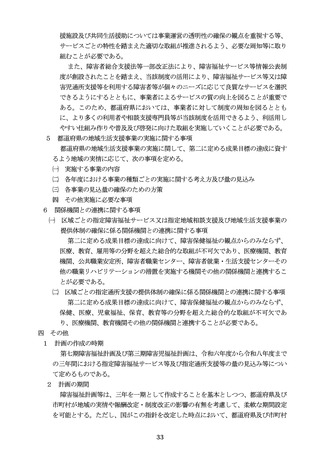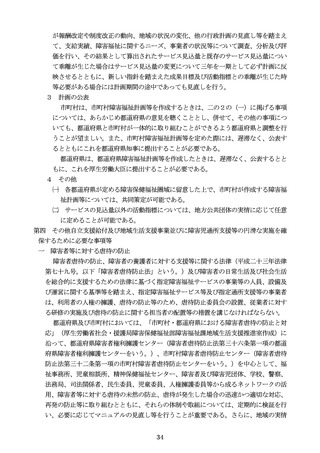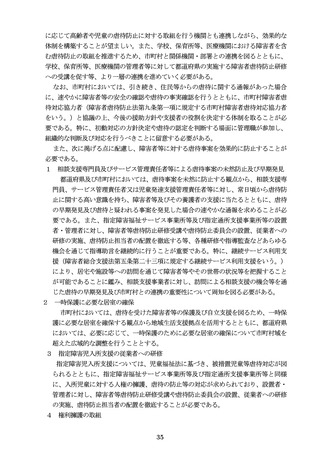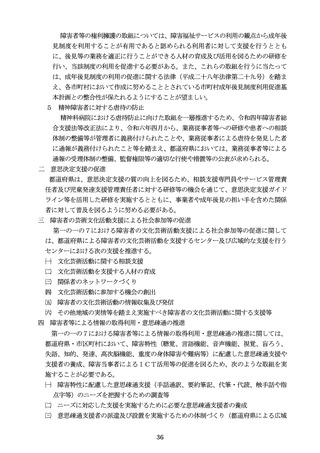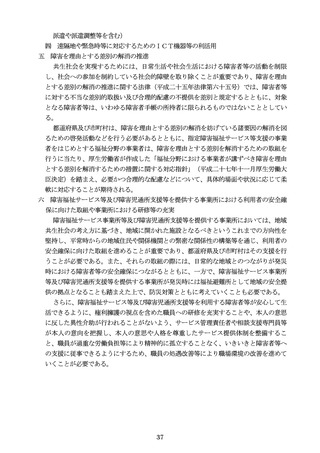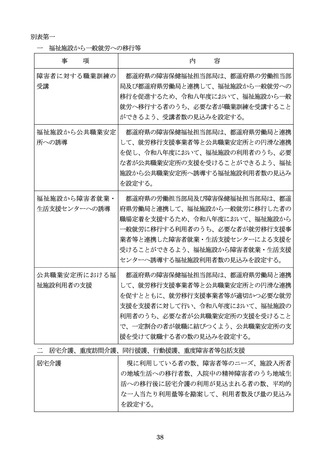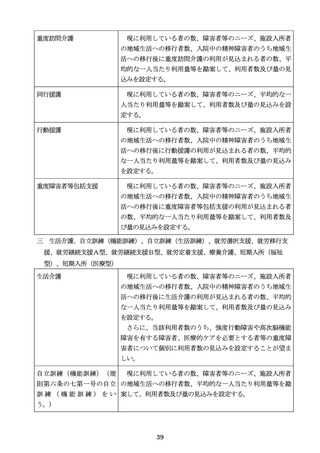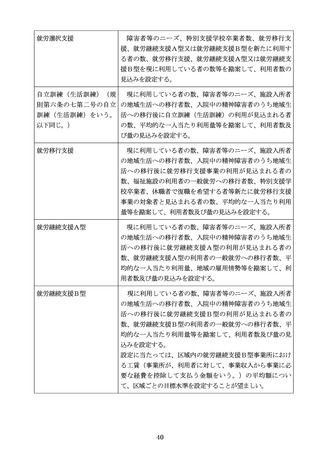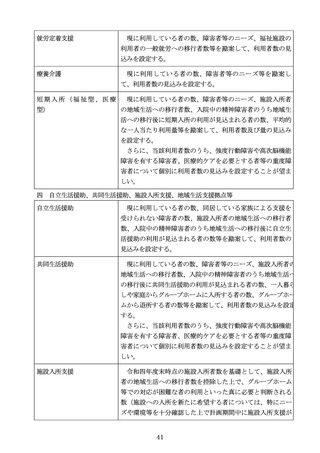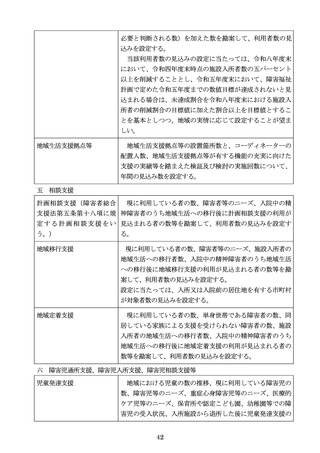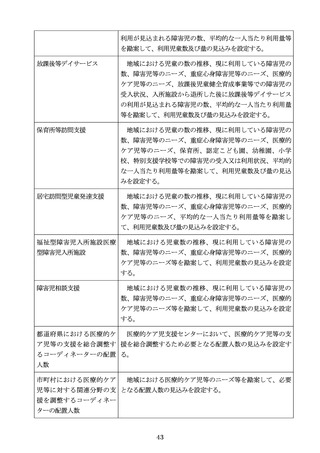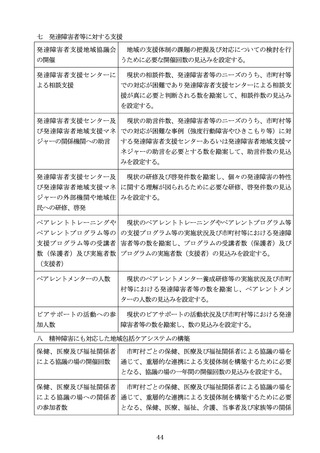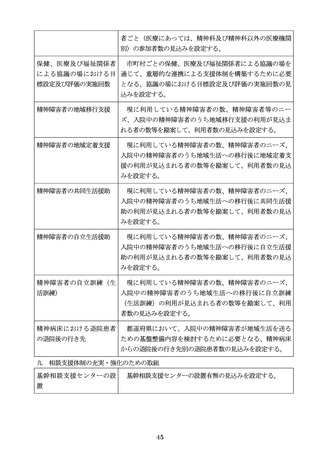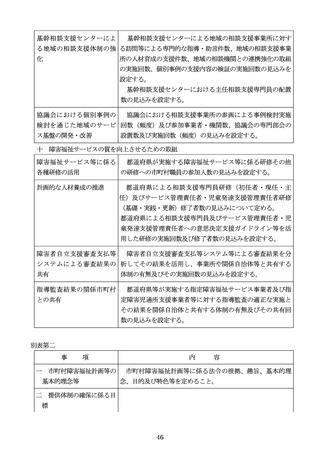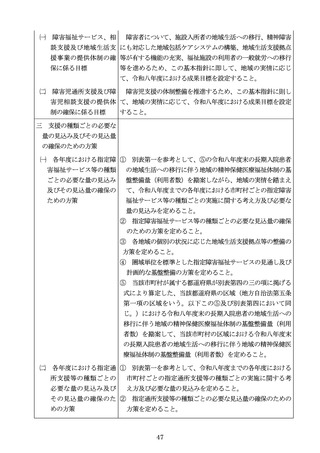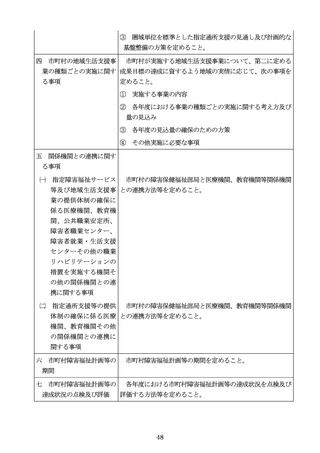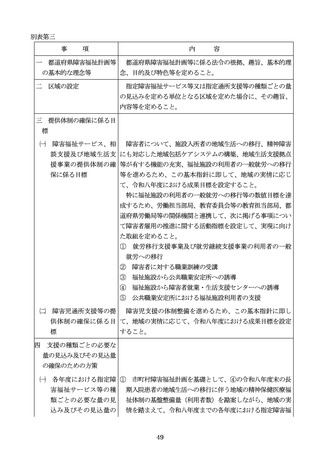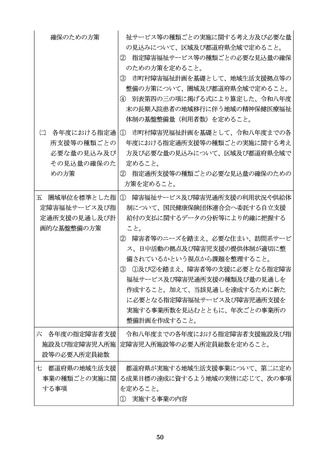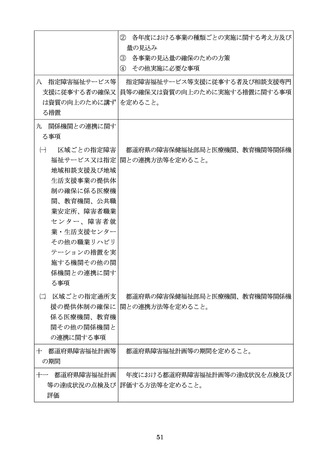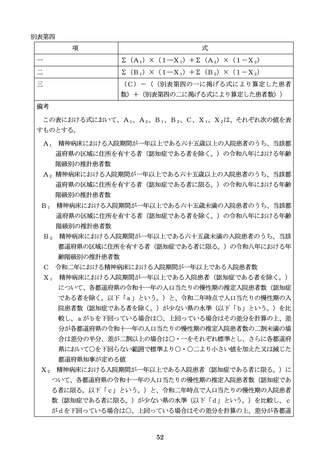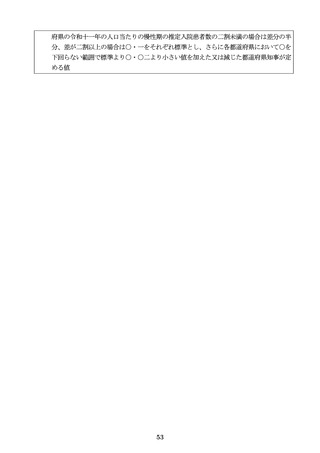よむ、つかう、まなぶ。
参考資料1 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(現行) (7 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64028.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第150回 10/1)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
援事業(就労定着支援を行う事業をいう。以下同じ。)等の推進により、障害者の福
祉施設から一般就労への移行及びその定着を進める。
5 強度行動障害や高次脳機能障害を有する障害者等に対する支援体制の充実
強度行動障害や高次脳機能障害を有する障害者及び難病患者に対して、障害福
祉サービス等において適切な支援ができるよう、管内の支援ニーズを把握するとと
もに、地域における課題の整理や専門的人材の育成、地域資源の開発等を行い、地
域の関係機関との連携を図りつつ支援体制の整備を図る必要がある。
強度行動障害を有する障害者のニーズ把握に当たっては、障害支援区分認定調
査の行動関連項目の点数の集計や療育手帳所持者の状況把握に努める等により特に
支援を必要とする者を把握することに加え、アンケート調査等を通して課題の把握
を行うことが重要である。また、管内の基幹相談支援センターや地域生活支援拠点
等と連携してサービスにつながっていない在宅の者を把握することが重要である。
高次脳機能障害を有する障害者については、障害支援区分認定調査等に加え、
管内の支援拠点機関や医療機関等とも連携して支援ニーズを把握することが重要で
ある。
難病患者については、多様な症状や障害等その特性に配慮しながら、難病相談
支援センター、公共職業安定所、医療機関等の専門機関と連携し、障害福祉サービ
スの利用も含む支援体制を整備することが重要である。
6 依存症対策の推進
アルコール、薬物及びギャンブル等(法律の定めるところにより行われる公営競
技、ぱちんこ屋に係る遊技その他の射幸行為をいう。)をはじめとする依存症対策に
ついては、依存症に対する誤解及び偏見を解消するための関係職員に対する研修の実
施及び幅広い普及啓発、相談機関及び医療機関の周知及び整備並びに自助グループ等
の当事者団体を活用した回復支援が重要であり、地域において様々な関係機関が密接
に連携して依存症である者等及びその家族に対する支援を行う必要がある。
三 相談支援の提供体制の確保に関する基本的考え方
1 相談支援体制の充実・強化
障害者等、とりわけ、重度の障害者等が地域において自立した日常生活又は社会生
活を営むためには、障害福祉サービスの提供体制の確保とともに、これらのサービス
の適切な利用を支え、また、各種ニーズに対応する相談支援体制の構築が不可欠であ
る。また、相談支援事業者等は、障害者等及びその家族が抱える複合的な課題を把握
し、家族への支援も含め、適切な保健、医療、福祉サービスにつなげる等の対応が必
要であり、行政機関その他関係機関との連携に努めることが必要である。
障害福祉サービスの利用に当たって作成されるサービス等利用計画(障害者総合支
援法第五条第二十二項に規定するサービス等利用計画をいう。以下同じ。)について
は、まずは、支給決定に先立ち必ず作成されるよう体制を確保し、維持することが重
要である。その上で、個別のサービス等利用計画の作成に当たっては、利用者の状態
像や希望を勘案し、連続性及び一貫性を持った障害福祉サービス又は地域相談支援
7
祉施設から一般就労への移行及びその定着を進める。
5 強度行動障害や高次脳機能障害を有する障害者等に対する支援体制の充実
強度行動障害や高次脳機能障害を有する障害者及び難病患者に対して、障害福
祉サービス等において適切な支援ができるよう、管内の支援ニーズを把握するとと
もに、地域における課題の整理や専門的人材の育成、地域資源の開発等を行い、地
域の関係機関との連携を図りつつ支援体制の整備を図る必要がある。
強度行動障害を有する障害者のニーズ把握に当たっては、障害支援区分認定調
査の行動関連項目の点数の集計や療育手帳所持者の状況把握に努める等により特に
支援を必要とする者を把握することに加え、アンケート調査等を通して課題の把握
を行うことが重要である。また、管内の基幹相談支援センターや地域生活支援拠点
等と連携してサービスにつながっていない在宅の者を把握することが重要である。
高次脳機能障害を有する障害者については、障害支援区分認定調査等に加え、
管内の支援拠点機関や医療機関等とも連携して支援ニーズを把握することが重要で
ある。
難病患者については、多様な症状や障害等その特性に配慮しながら、難病相談
支援センター、公共職業安定所、医療機関等の専門機関と連携し、障害福祉サービ
スの利用も含む支援体制を整備することが重要である。
6 依存症対策の推進
アルコール、薬物及びギャンブル等(法律の定めるところにより行われる公営競
技、ぱちんこ屋に係る遊技その他の射幸行為をいう。)をはじめとする依存症対策に
ついては、依存症に対する誤解及び偏見を解消するための関係職員に対する研修の実
施及び幅広い普及啓発、相談機関及び医療機関の周知及び整備並びに自助グループ等
の当事者団体を活用した回復支援が重要であり、地域において様々な関係機関が密接
に連携して依存症である者等及びその家族に対する支援を行う必要がある。
三 相談支援の提供体制の確保に関する基本的考え方
1 相談支援体制の充実・強化
障害者等、とりわけ、重度の障害者等が地域において自立した日常生活又は社会生
活を営むためには、障害福祉サービスの提供体制の確保とともに、これらのサービス
の適切な利用を支え、また、各種ニーズに対応する相談支援体制の構築が不可欠であ
る。また、相談支援事業者等は、障害者等及びその家族が抱える複合的な課題を把握
し、家族への支援も含め、適切な保健、医療、福祉サービスにつなげる等の対応が必
要であり、行政機関その他関係機関との連携に努めることが必要である。
障害福祉サービスの利用に当たって作成されるサービス等利用計画(障害者総合支
援法第五条第二十二項に規定するサービス等利用計画をいう。以下同じ。)について
は、まずは、支給決定に先立ち必ず作成されるよう体制を確保し、維持することが重
要である。その上で、個別のサービス等利用計画の作成に当たっては、利用者の状態
像や希望を勘案し、連続性及び一貫性を持った障害福祉サービス又は地域相談支援
7