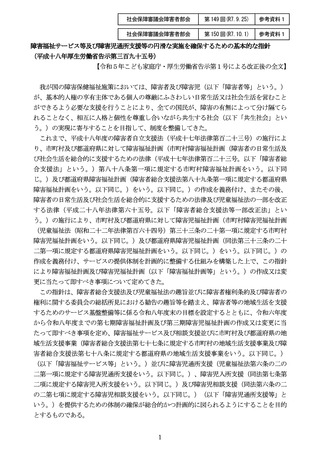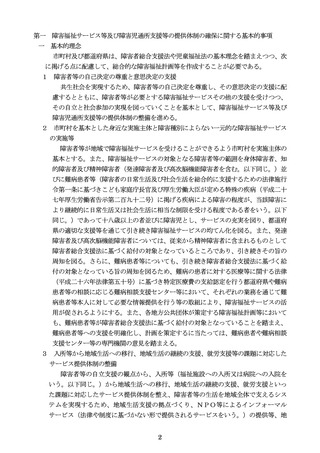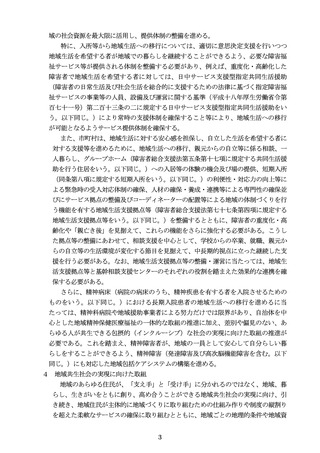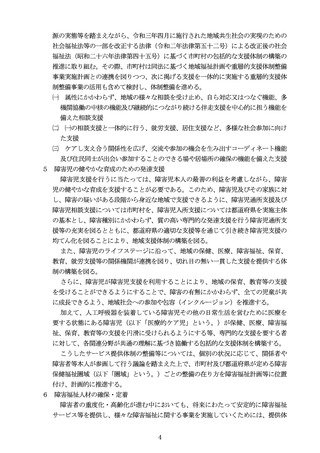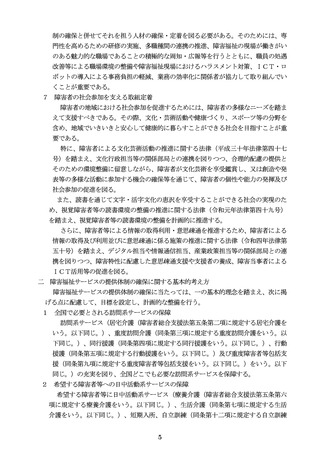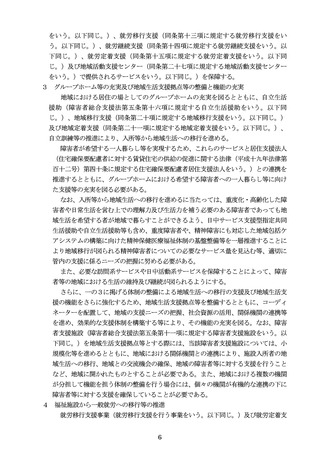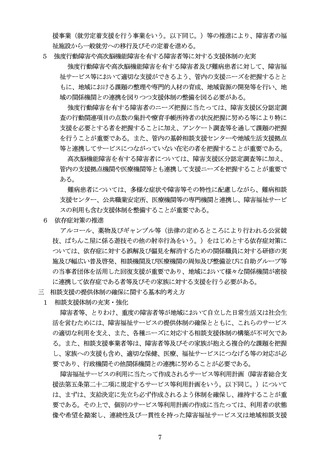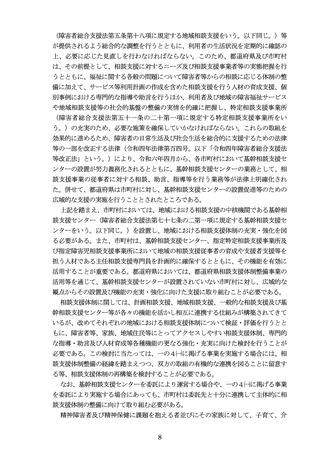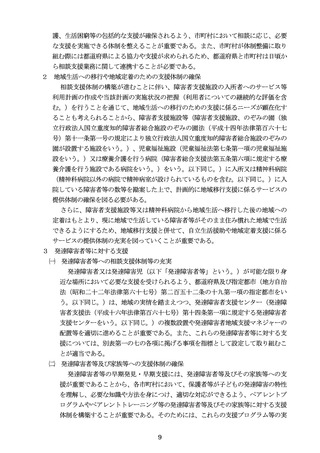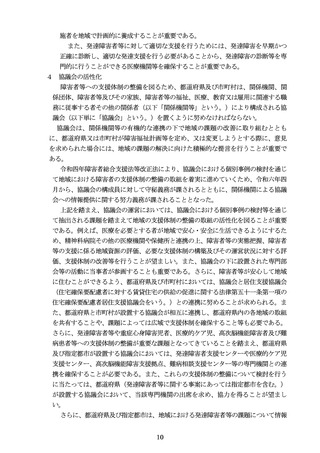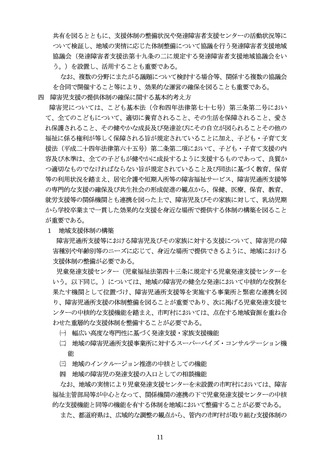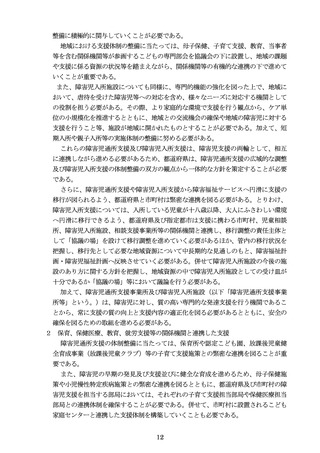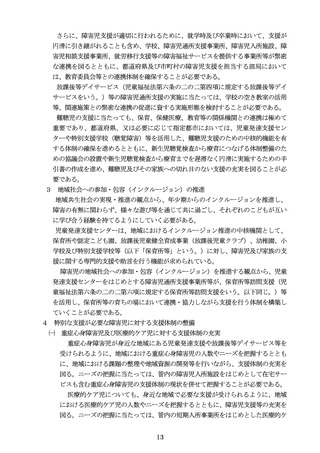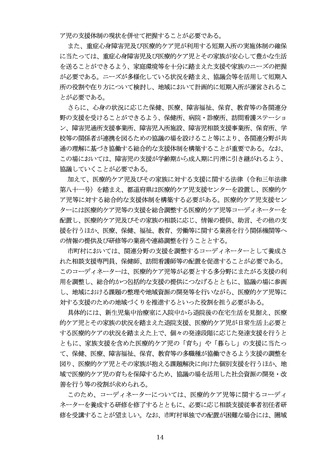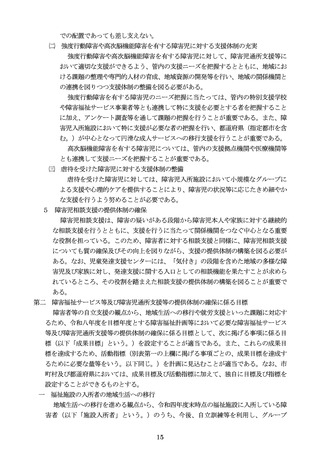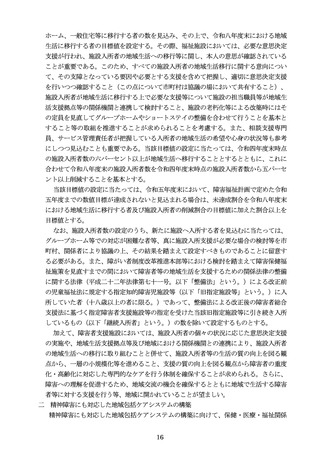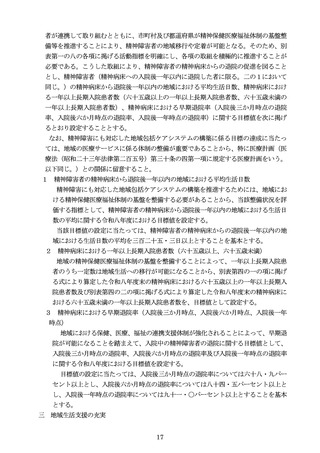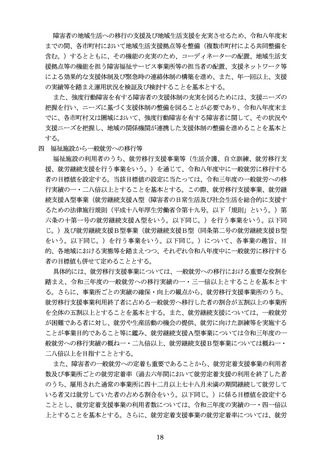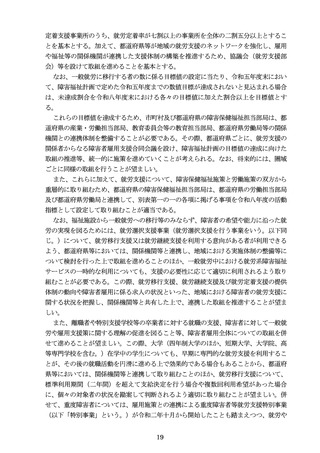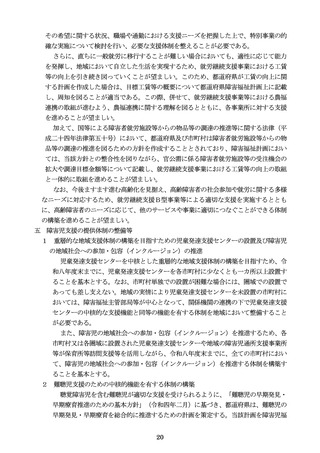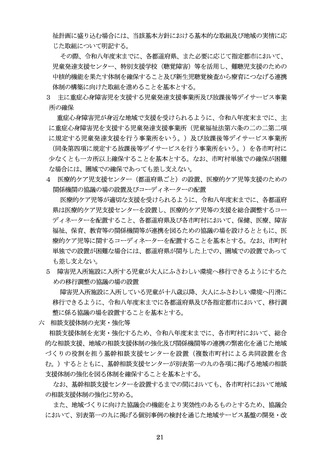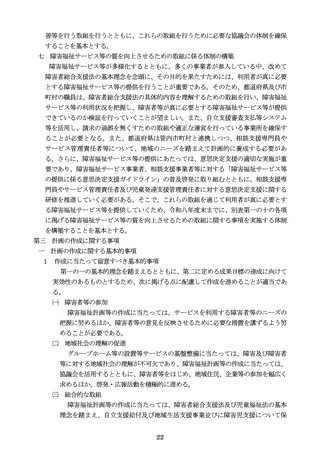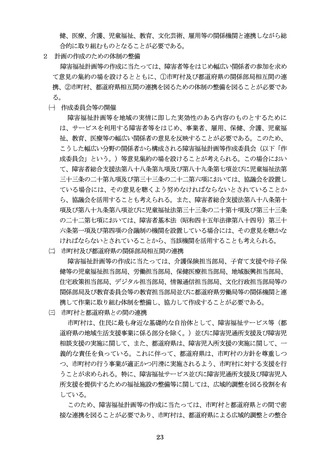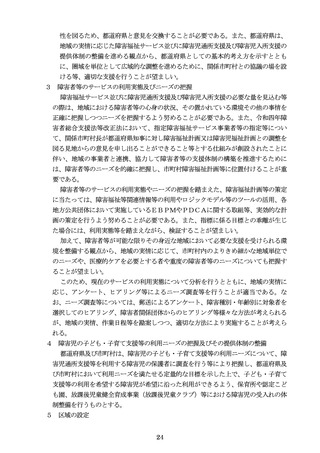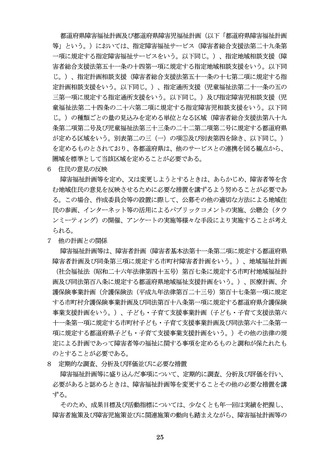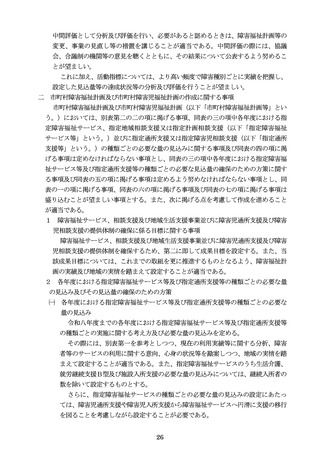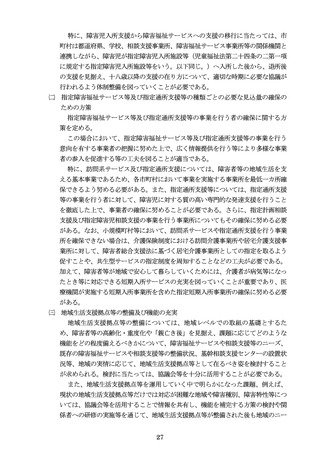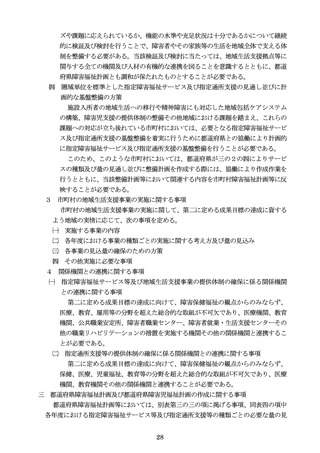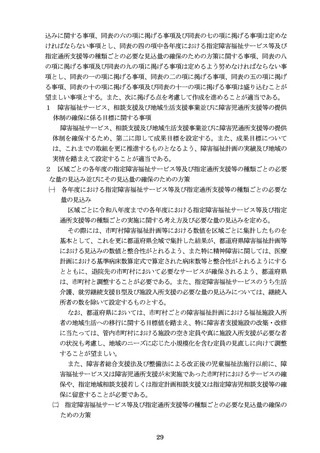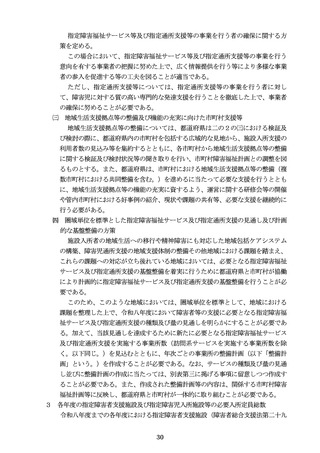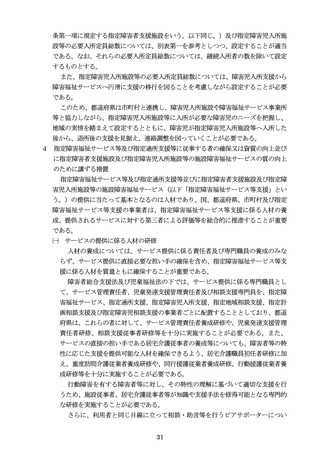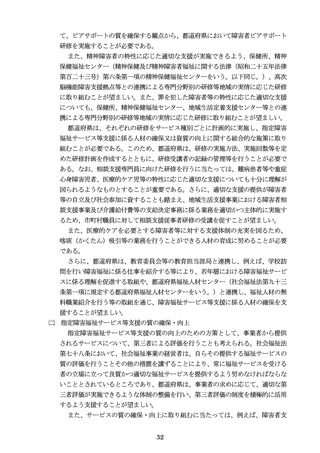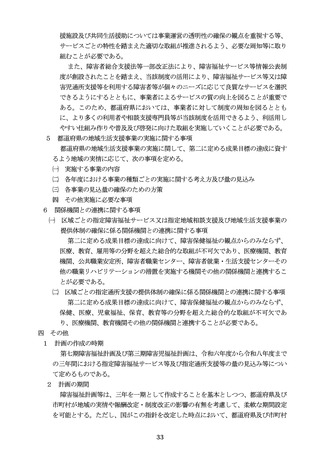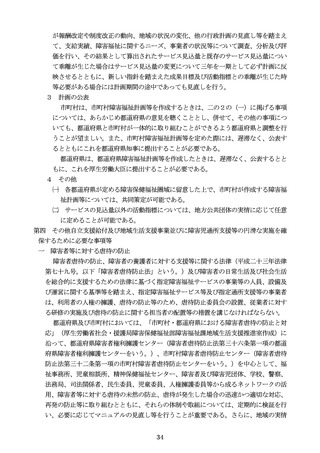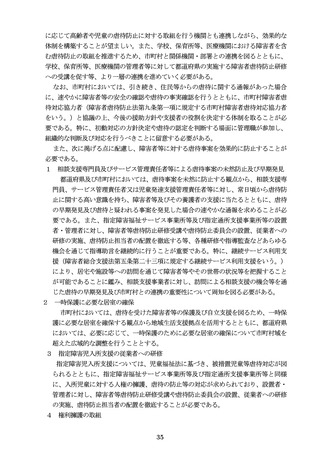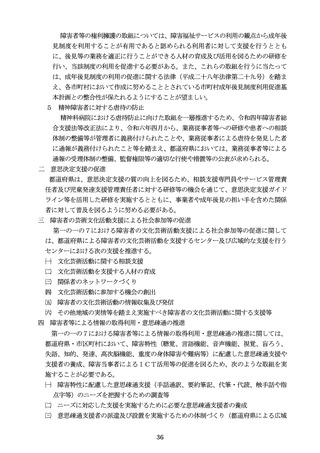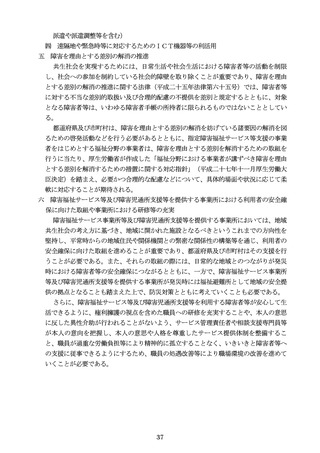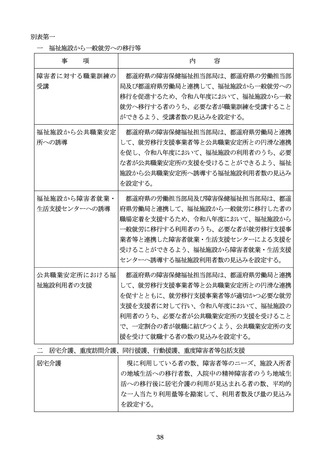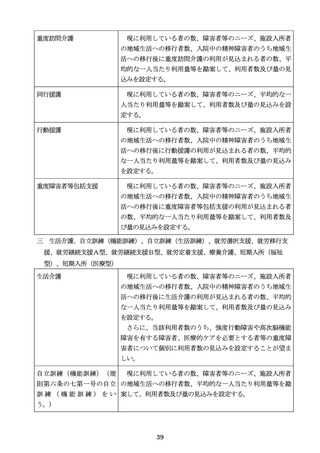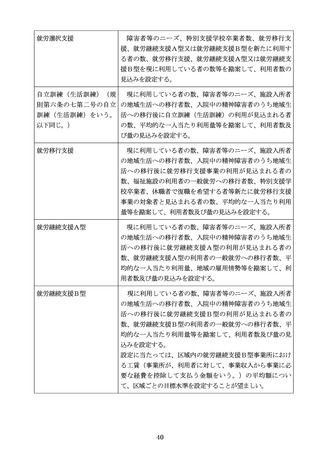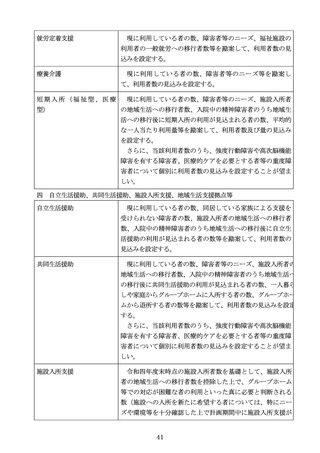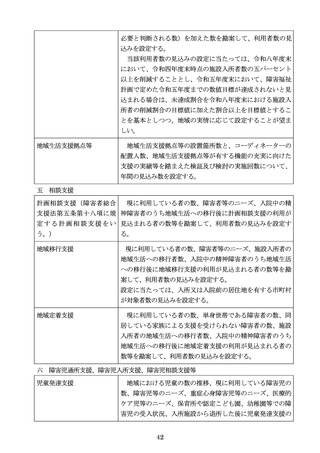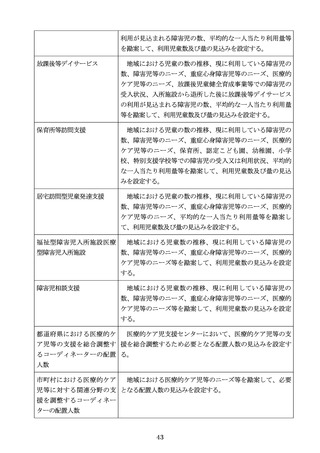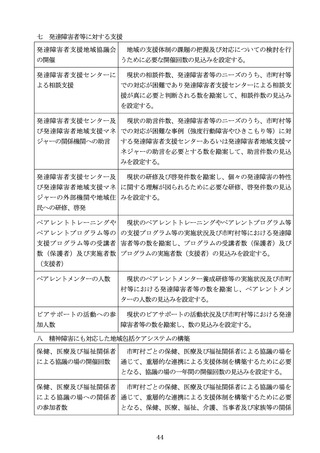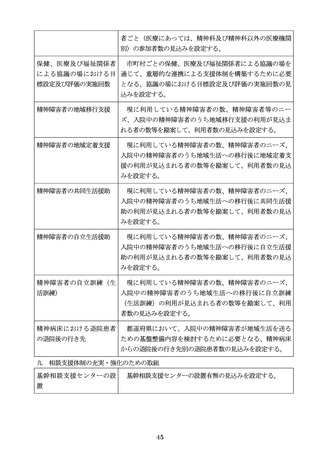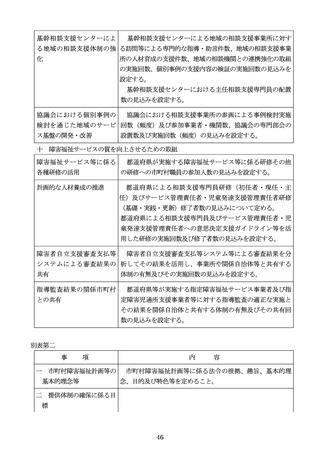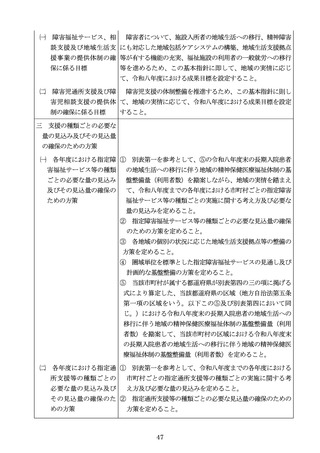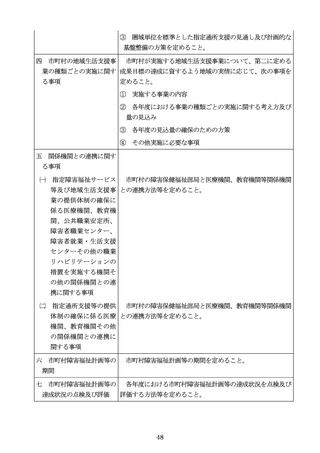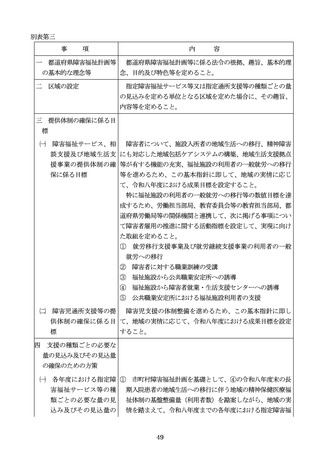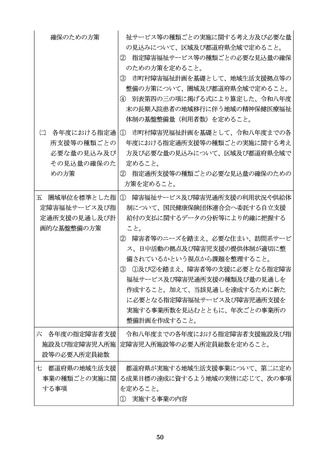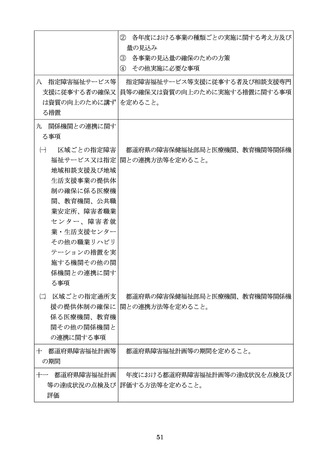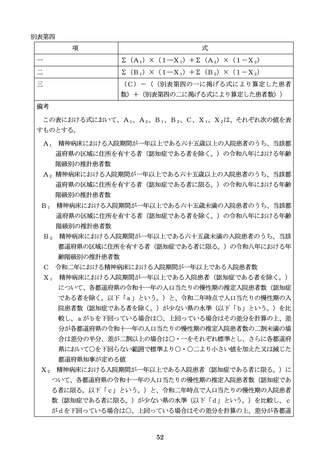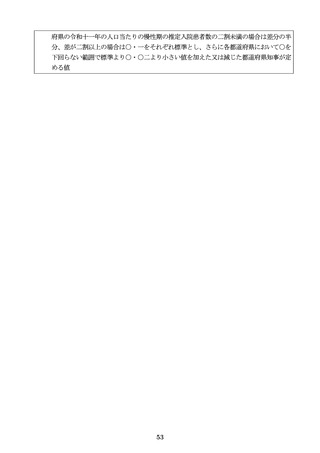よむ、つかう、まなぶ。
参考資料1 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(現行) (13 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64028.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第150回 10/1)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
さらに、障害児支援が適切に行われるために、就学時及び卒業時において、支援が
円滑に引き継がれることも含め、学校、障害児通所支援事業所、障害児入所施設、障
害児相談支援事業所、就労移行支援等の障害福祉サービスを提供する事業所等が緊密
な連携を図るとともに、都道府県及び市町村の障害児支援を担当する部局において
は、教育委員会等との連携体制を確保することが必要である。
放課後等デイサービス(児童福祉法第六条の二の二第四項に規定する放課後等デイ
サービスをいう。)等の障害児通所支援の実施に当たっては、学校の空き教室の活用
等、関連施策との緊密な連携の促進に資する実施形態を検討することが必要である。
難聴児の支援に当たっても、保育、保健医療、教育等の関係機関との連携は極めて
重要であり、都道府県、又は必要に応じて指定都市においては、児童発達支援セン
ターや特別支援学校(聴覚障害)等を活用した、難聴児支援のための中核的機能を有
する体制の確保を進めるとともに、新生児聴覚検査から療育につなげる体制整備のた
めの協議会の設置や新生児聴覚検査から療育までを遅滞なく円滑に実施するための手
引書の作成を進め、難聴児及びその家族への切れ目のない支援の充実を図ることが必
要である。
3 地域社会への参加・包容(インクルージョン)の推進
地域共生社会の実現・推進の観点から、年少期からのインクルージョンを推進し、
障害の有無に関わらず、様々な遊び等を通じて共に過ごし、それぞれのこどもが互い
に学び合う経験を持てるようにしていく必要がある。
児童発達支援センターは、地域におけるインクルージョン推進の中核機関として、
保育所や認定こども園、放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)、幼稚園、小
学校及び特別支援学校等(以下「保育所等」という。)に対し、障害児及び家族の支
援に関する専門的支援や助言を行う機能が求められている。
障害児の地域社会への参加・包容(インクルージョン)を推進する観点から、児童
発達支援センターをはじめとする障害児通所支援事業所等が、保育所等訪問支援(児
童福祉法第六条の二の二第六項に規定する保育所等訪問支援をいう。以下同じ。)等
を活用し、保育所等の育ちの場において連携・協力しながら支援を行う体制を構築し
ていくことが必要である。
4 特別な支援が必要な障害児に対する支援体制の整備
㈠ 重症心身障害児及び医療的ケア児に対する支援体制の充実
重症心身障害児が身近な地域にある児童発達支援や放課後等デイサービス等を
受けられるように、地域における重症心身障害児の人数やニーズを把握するととも
に、地域における課題の整理や地域資源の開発等を行いながら、支援体制の充実を
図る。ニーズの把握に当たっては、管内の障害児入所施設をはじめとして在宅サー
ビスも含む重症心身障害児の支援体制の現状を併せて把握することが必要である。
医療的ケア児についても、身近な地域で必要な支援が受けられるように、地域
における医療的ケア児の人数やニーズを把握するとともに、障害児支援等の充実を
図る。ニーズの把握に当たっては、管内の短期入所事業所をはじめとした医療的ケ
13
円滑に引き継がれることも含め、学校、障害児通所支援事業所、障害児入所施設、障
害児相談支援事業所、就労移行支援等の障害福祉サービスを提供する事業所等が緊密
な連携を図るとともに、都道府県及び市町村の障害児支援を担当する部局において
は、教育委員会等との連携体制を確保することが必要である。
放課後等デイサービス(児童福祉法第六条の二の二第四項に規定する放課後等デイ
サービスをいう。)等の障害児通所支援の実施に当たっては、学校の空き教室の活用
等、関連施策との緊密な連携の促進に資する実施形態を検討することが必要である。
難聴児の支援に当たっても、保育、保健医療、教育等の関係機関との連携は極めて
重要であり、都道府県、又は必要に応じて指定都市においては、児童発達支援セン
ターや特別支援学校(聴覚障害)等を活用した、難聴児支援のための中核的機能を有
する体制の確保を進めるとともに、新生児聴覚検査から療育につなげる体制整備のた
めの協議会の設置や新生児聴覚検査から療育までを遅滞なく円滑に実施するための手
引書の作成を進め、難聴児及びその家族への切れ目のない支援の充実を図ることが必
要である。
3 地域社会への参加・包容(インクルージョン)の推進
地域共生社会の実現・推進の観点から、年少期からのインクルージョンを推進し、
障害の有無に関わらず、様々な遊び等を通じて共に過ごし、それぞれのこどもが互い
に学び合う経験を持てるようにしていく必要がある。
児童発達支援センターは、地域におけるインクルージョン推進の中核機関として、
保育所や認定こども園、放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)、幼稚園、小
学校及び特別支援学校等(以下「保育所等」という。)に対し、障害児及び家族の支
援に関する専門的支援や助言を行う機能が求められている。
障害児の地域社会への参加・包容(インクルージョン)を推進する観点から、児童
発達支援センターをはじめとする障害児通所支援事業所等が、保育所等訪問支援(児
童福祉法第六条の二の二第六項に規定する保育所等訪問支援をいう。以下同じ。)等
を活用し、保育所等の育ちの場において連携・協力しながら支援を行う体制を構築し
ていくことが必要である。
4 特別な支援が必要な障害児に対する支援体制の整備
㈠ 重症心身障害児及び医療的ケア児に対する支援体制の充実
重症心身障害児が身近な地域にある児童発達支援や放課後等デイサービス等を
受けられるように、地域における重症心身障害児の人数やニーズを把握するととも
に、地域における課題の整理や地域資源の開発等を行いながら、支援体制の充実を
図る。ニーズの把握に当たっては、管内の障害児入所施設をはじめとして在宅サー
ビスも含む重症心身障害児の支援体制の現状を併せて把握することが必要である。
医療的ケア児についても、身近な地域で必要な支援が受けられるように、地域
における医療的ケア児の人数やニーズを把握するとともに、障害児支援等の充実を
図る。ニーズの把握に当たっては、管内の短期入所事業所をはじめとした医療的ケ
13