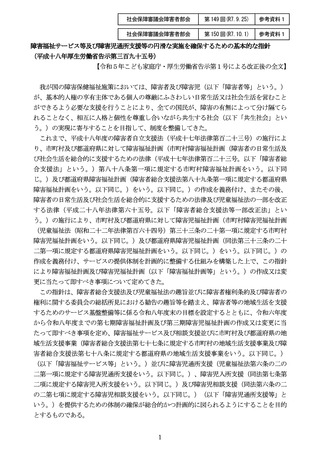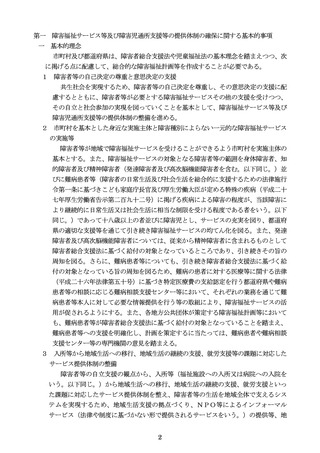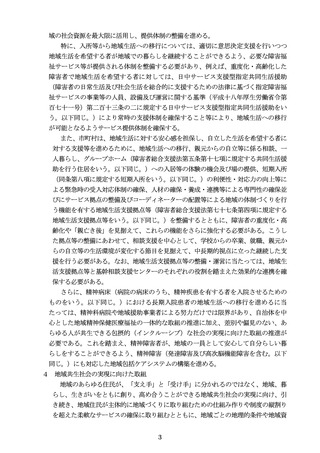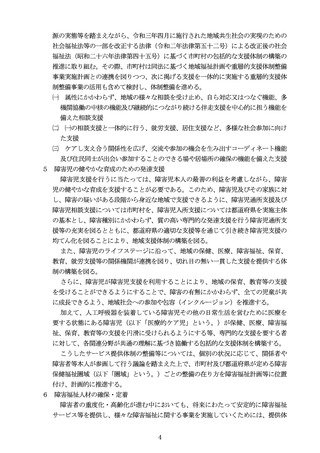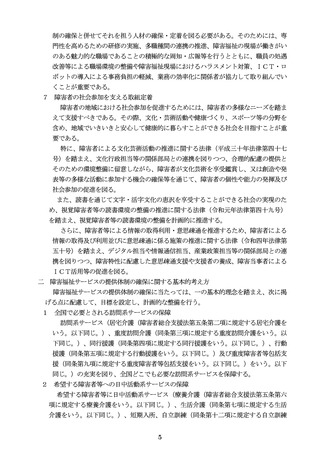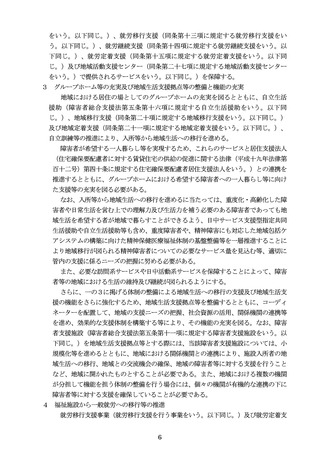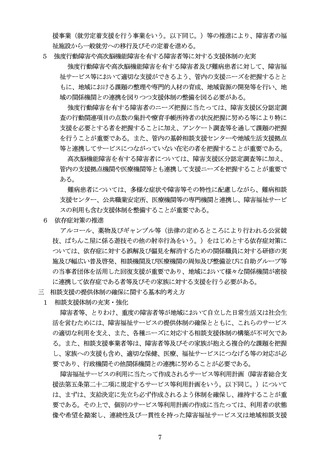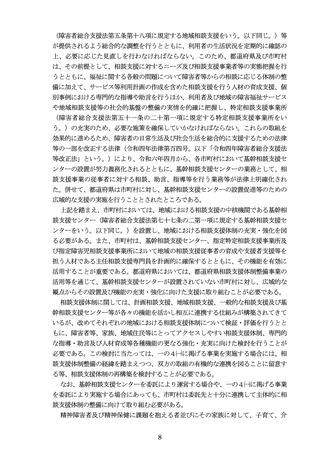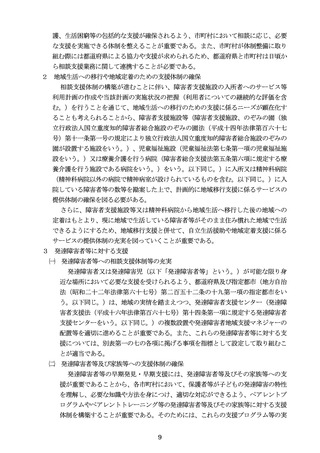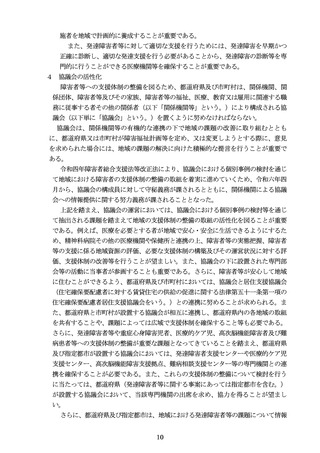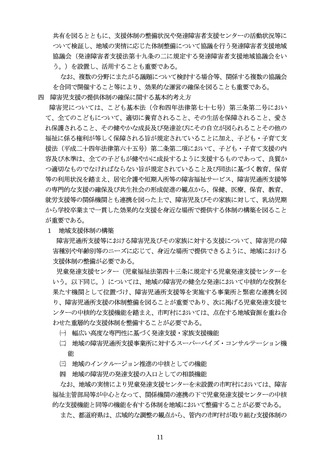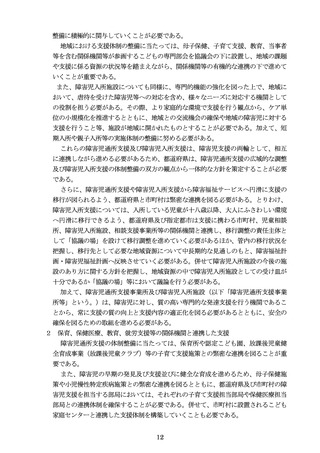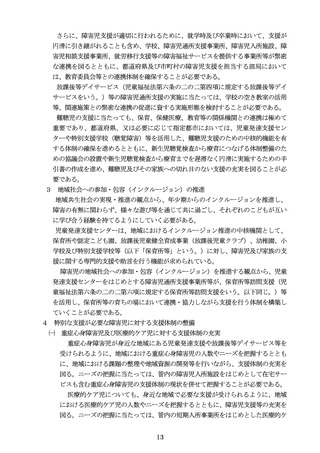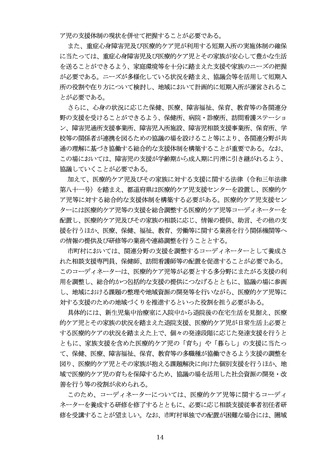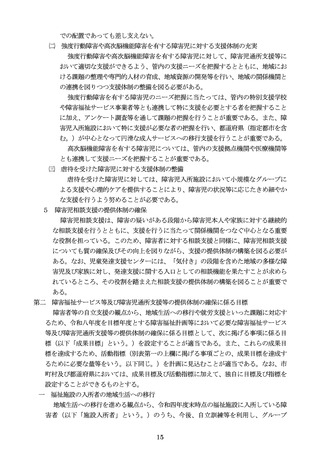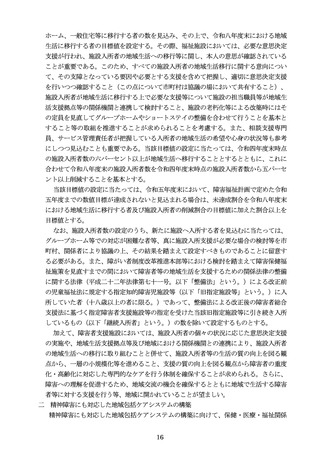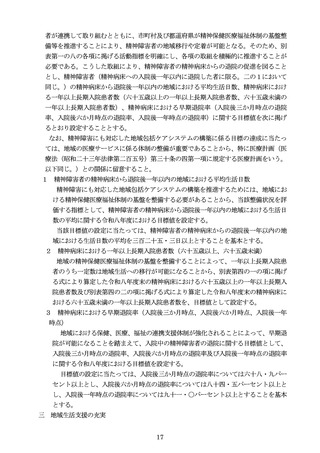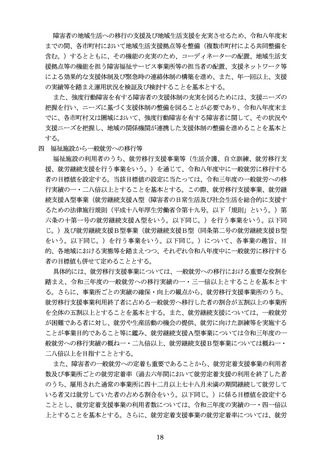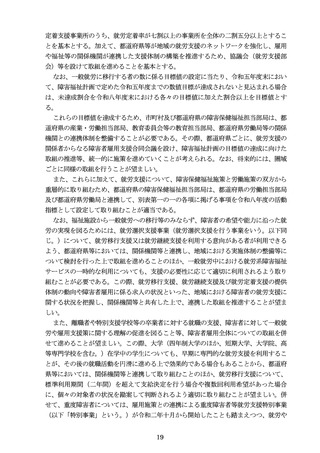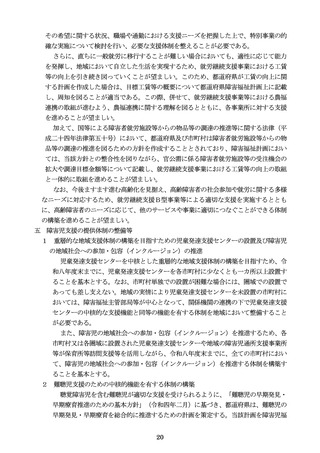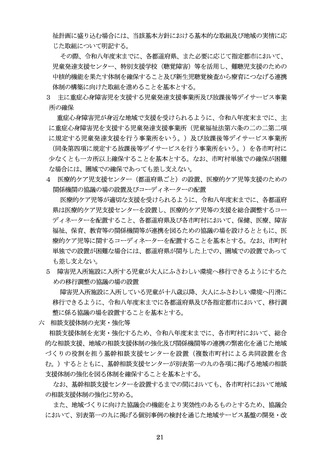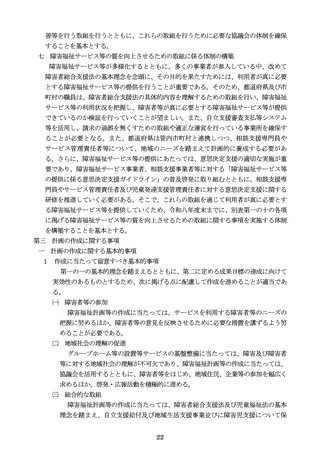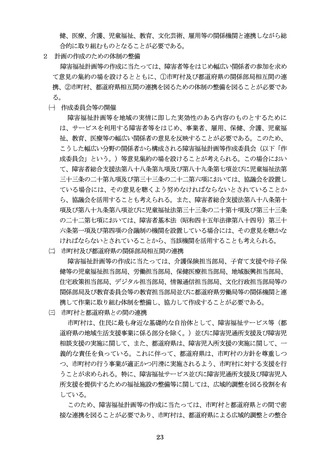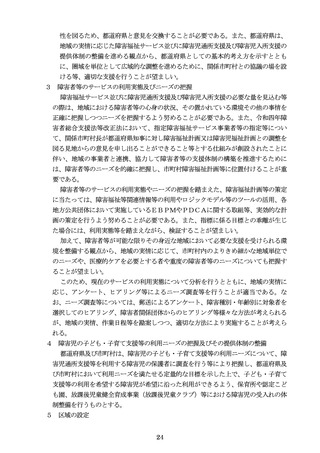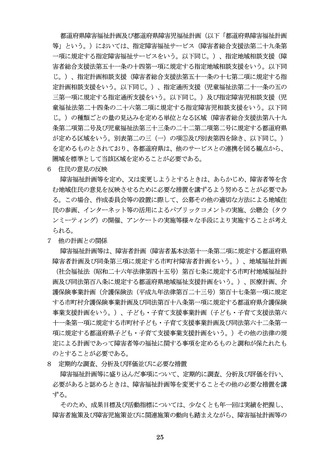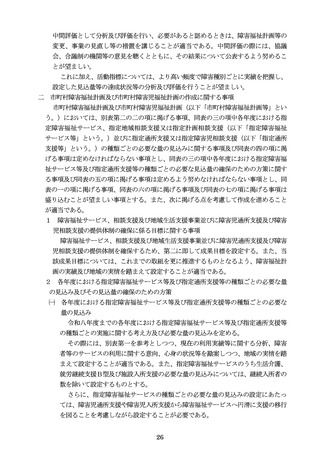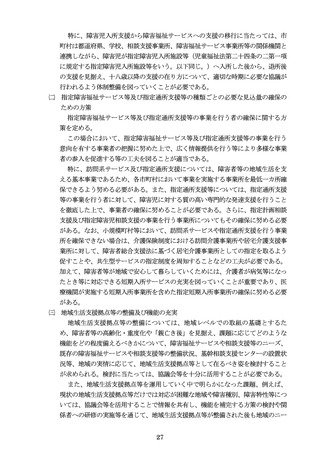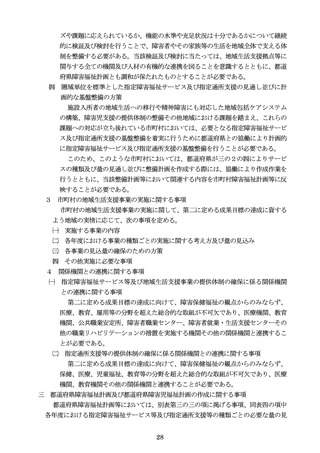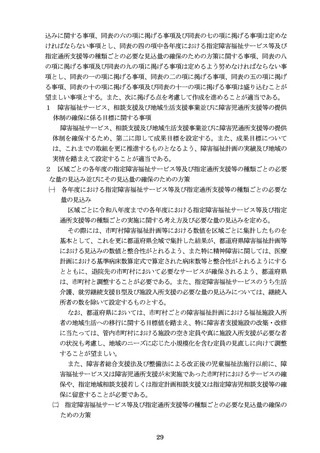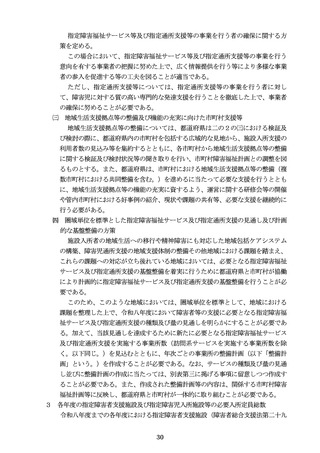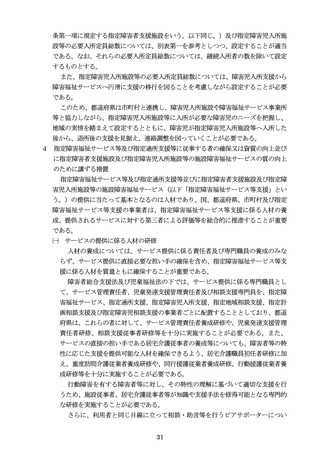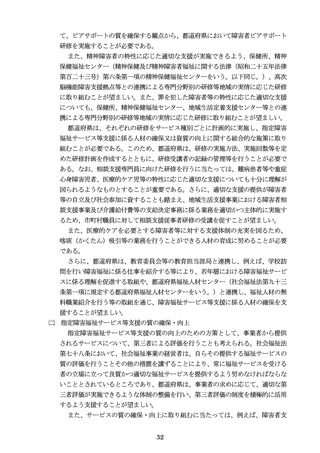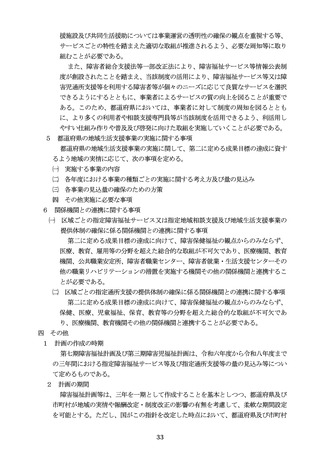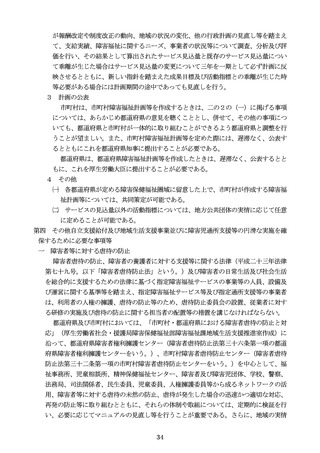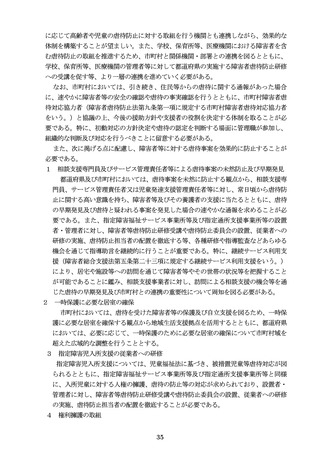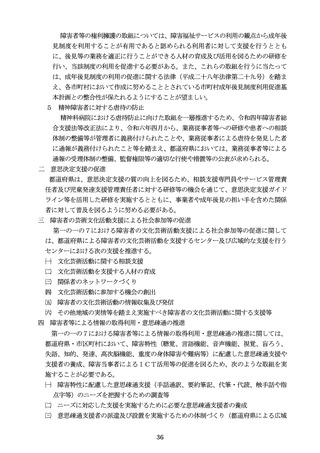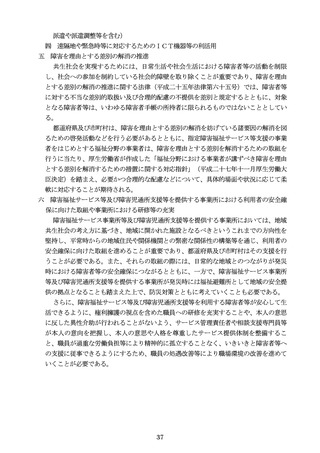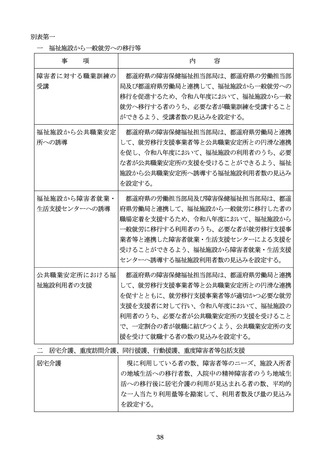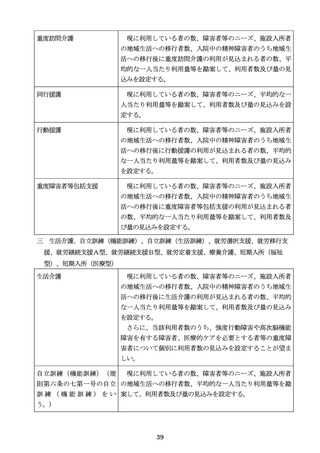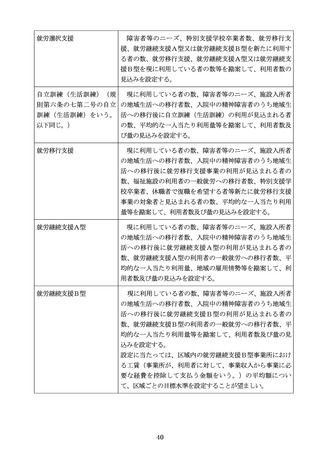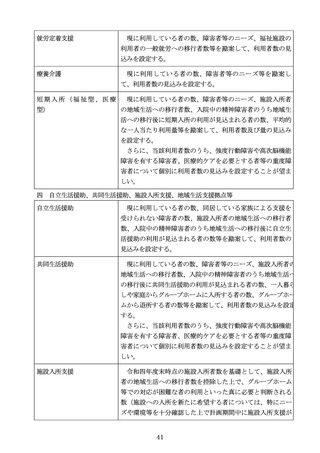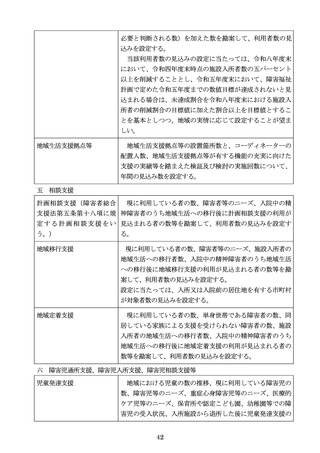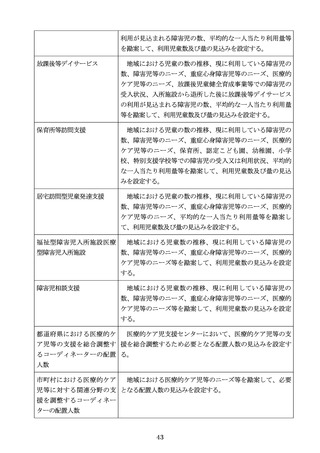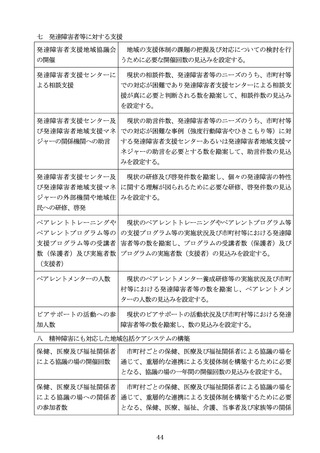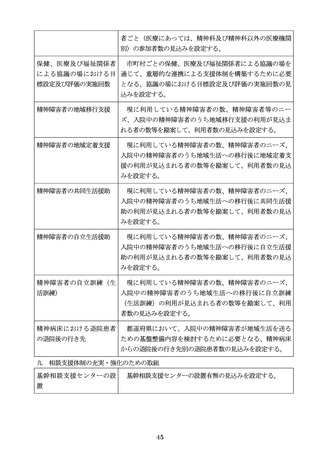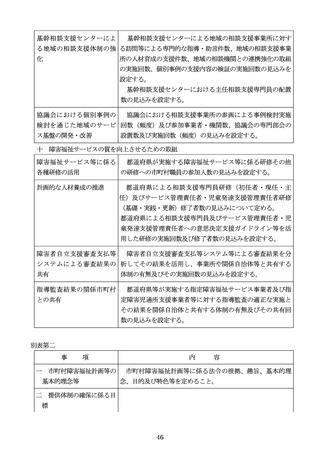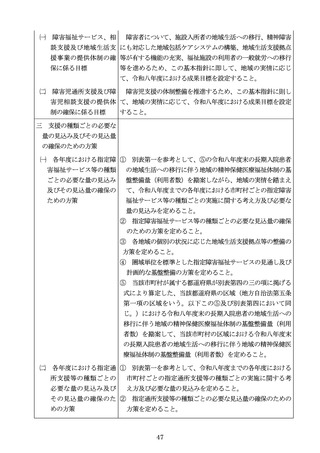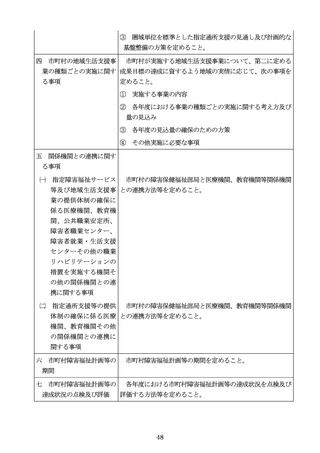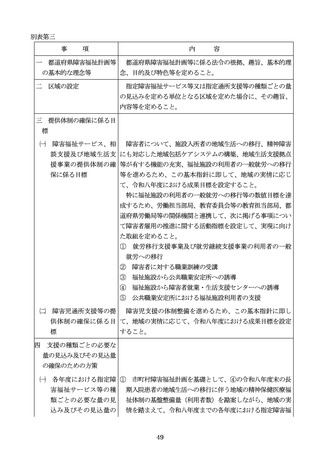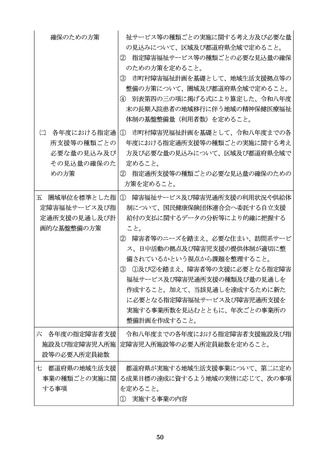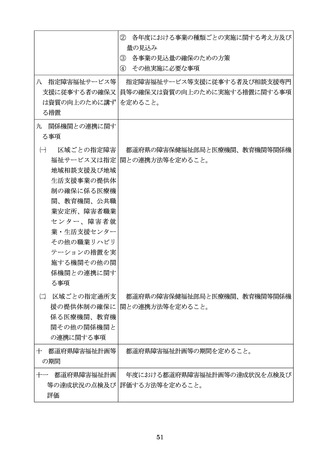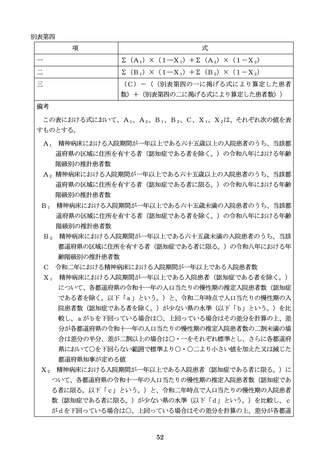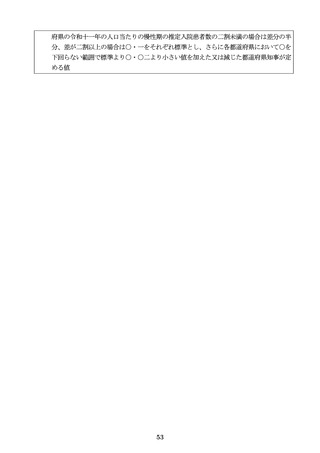よむ、つかう、まなぶ。
参考資料1 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(現行) (32 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64028.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第150回 10/1)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
て、ピアサポートの質を確保する観点から、都道府県において障害者ピアサポート
研修を実施することが必要である。
また、精神障害者の特性に応じた適切な支援が実施できるよう、保健所、精神
保健福祉センター(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律
第百二十三号)第六条第一項の精神保健福祉センターをいう。以下同じ。)、高次
脳機能障害支援拠点等との連携による専門分野別の研修等地域の実情に応じた研修
に取り組むことが望ましい。また、罪を犯した障害者等の特性に応じた適切な支援
についても、保健所、精神保健福祉センター、地域生活定着支援センター等との連
携による専門分野別の研修等地域の実情に応じた研修に取り組むことが望ましい。
都道府県は、それぞれの研修をサービス種別ごとに計画的に実施し、指定障害
福祉サービス等支援に係る人材の確保又は資質の向上に関する総合的な施策に取り
組むことが必要である。このため、都道府県は、研修の実施方法、実施回数等を定
めた研修計画を作成するとともに、研修受講者の記録の管理等を行うことが必要で
ある。なお、相談支援専門員に向けた研修を行うに当たっては、難病患者等や重症
心身障害児者、医療的ケア児等の特性に応じた適切な支援についても十分に理解が
図られるようなものとすることが重要である。さらに、適切な支援の提供が障害者
等の自立及び社会参加に資することも踏まえ、地域生活支援事業における障害者相
談支援事業及び介護給付費等の支給決定事務に係る業務を適切かつ主体的に実施す
るため、市町村職員に対して相談支援従事者研修の受講を促すことが望ましい。
また、医療的ケアを必要とする障害者等に対する支援体制の充実を図るため、
喀痰(かくたん)吸引等の業務を行うことができる人材の育成に努めることが必要
である。
さらに、都道府県は、教育委員会等の教育担当部局と連携し、例えば、学校訪
問を行い障害福祉に係る仕事を紹介する等により、若年層における障害福祉サービ
スに係る理解を促進する取組や、都道府県福祉人材センター(社会福祉法第九十三
条第一項に規定する都道府県福祉人材センターをいう。)と連携し、福祉人材の無
料職業紹介を行う等の取組を通じ、障害福祉サービス等支援に係る人材の確保を支
援することが望ましい。
㈡ 指定障害福祉サービス等支援の質の確保・向上
指定障害福祉サービス等支援の質の向上のための方策として、事業者から提供
されるサービスについて、第三者による評価を行うことも考えられる。社会福祉法
第七十八条において、社会福祉事業の経営者は、自らその提供する福祉サービスの
質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、常に福祉サービスを受ける
者の立場に立って良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めなければならな
いこととされているところであり、都道府県は、事業者の求めに応じて、適切な第
三者評価が実施できるような体制の整備を行い、第三者評価の制度を積極的に活用
するよう支援することが望ましい。
また、サービスの質の確保・向上に取り組むに当たっては、例えば、障害者支
32
研修を実施することが必要である。
また、精神障害者の特性に応じた適切な支援が実施できるよう、保健所、精神
保健福祉センター(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律
第百二十三号)第六条第一項の精神保健福祉センターをいう。以下同じ。)、高次
脳機能障害支援拠点等との連携による専門分野別の研修等地域の実情に応じた研修
に取り組むことが望ましい。また、罪を犯した障害者等の特性に応じた適切な支援
についても、保健所、精神保健福祉センター、地域生活定着支援センター等との連
携による専門分野別の研修等地域の実情に応じた研修に取り組むことが望ましい。
都道府県は、それぞれの研修をサービス種別ごとに計画的に実施し、指定障害
福祉サービス等支援に係る人材の確保又は資質の向上に関する総合的な施策に取り
組むことが必要である。このため、都道府県は、研修の実施方法、実施回数等を定
めた研修計画を作成するとともに、研修受講者の記録の管理等を行うことが必要で
ある。なお、相談支援専門員に向けた研修を行うに当たっては、難病患者等や重症
心身障害児者、医療的ケア児等の特性に応じた適切な支援についても十分に理解が
図られるようなものとすることが重要である。さらに、適切な支援の提供が障害者
等の自立及び社会参加に資することも踏まえ、地域生活支援事業における障害者相
談支援事業及び介護給付費等の支給決定事務に係る業務を適切かつ主体的に実施す
るため、市町村職員に対して相談支援従事者研修の受講を促すことが望ましい。
また、医療的ケアを必要とする障害者等に対する支援体制の充実を図るため、
喀痰(かくたん)吸引等の業務を行うことができる人材の育成に努めることが必要
である。
さらに、都道府県は、教育委員会等の教育担当部局と連携し、例えば、学校訪
問を行い障害福祉に係る仕事を紹介する等により、若年層における障害福祉サービ
スに係る理解を促進する取組や、都道府県福祉人材センター(社会福祉法第九十三
条第一項に規定する都道府県福祉人材センターをいう。)と連携し、福祉人材の無
料職業紹介を行う等の取組を通じ、障害福祉サービス等支援に係る人材の確保を支
援することが望ましい。
㈡ 指定障害福祉サービス等支援の質の確保・向上
指定障害福祉サービス等支援の質の向上のための方策として、事業者から提供
されるサービスについて、第三者による評価を行うことも考えられる。社会福祉法
第七十八条において、社会福祉事業の経営者は、自らその提供する福祉サービスの
質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、常に福祉サービスを受ける
者の立場に立って良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めなければならな
いこととされているところであり、都道府県は、事業者の求めに応じて、適切な第
三者評価が実施できるような体制の整備を行い、第三者評価の制度を積極的に活用
するよう支援することが望ましい。
また、サービスの質の確保・向上に取り組むに当たっては、例えば、障害者支
32