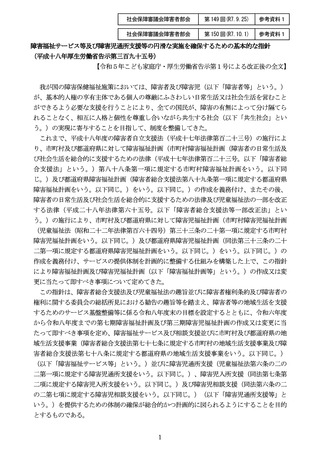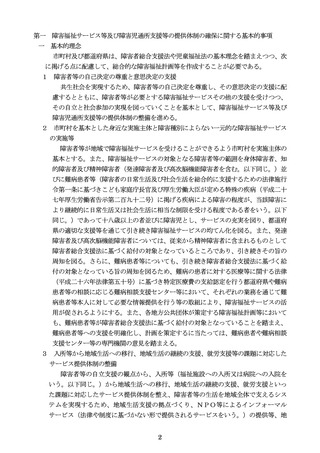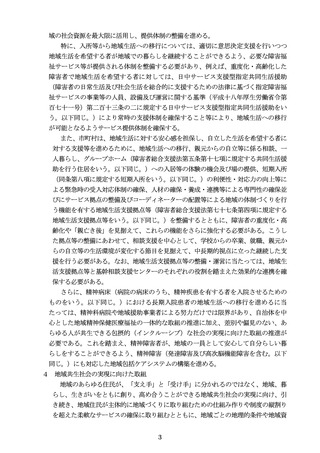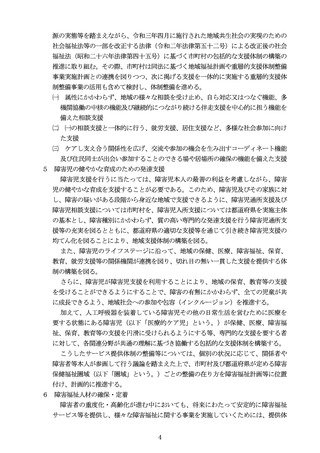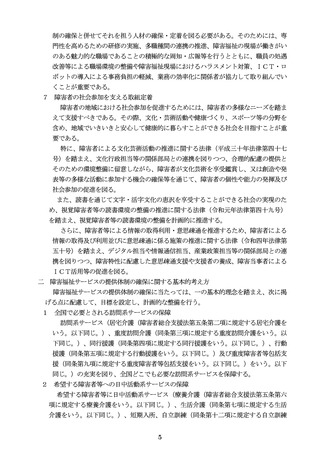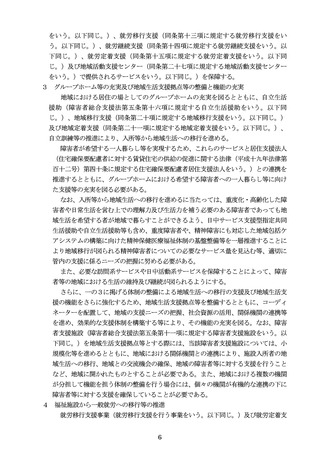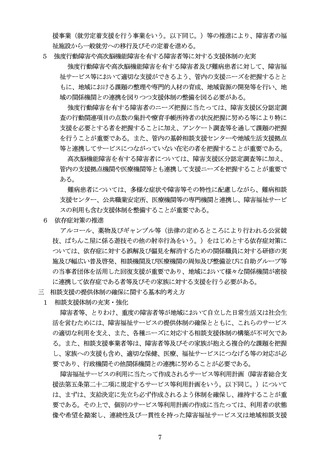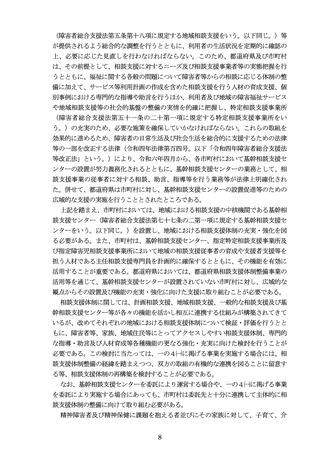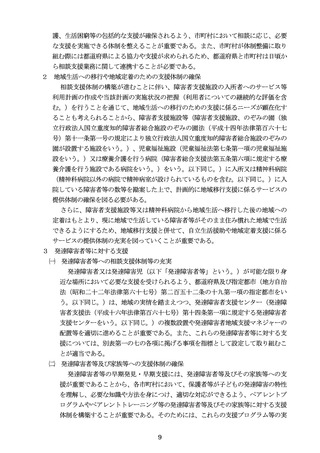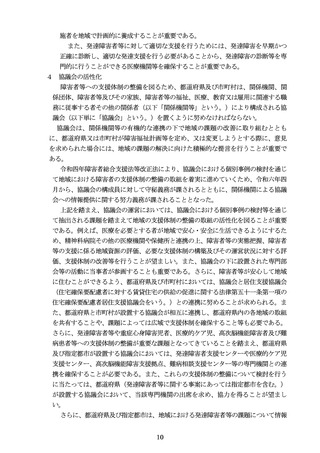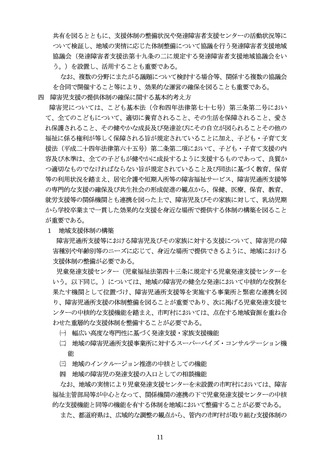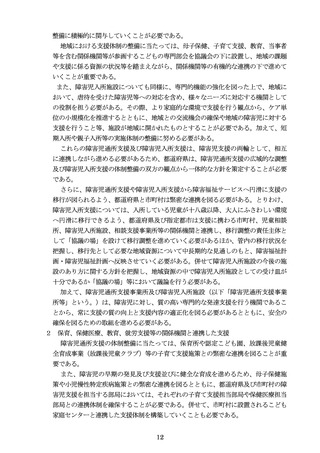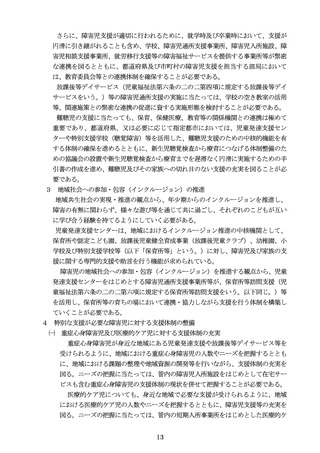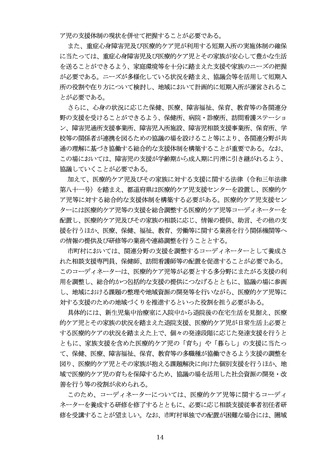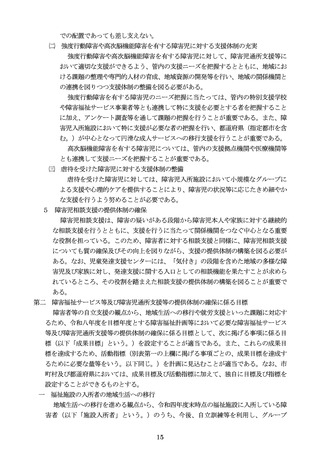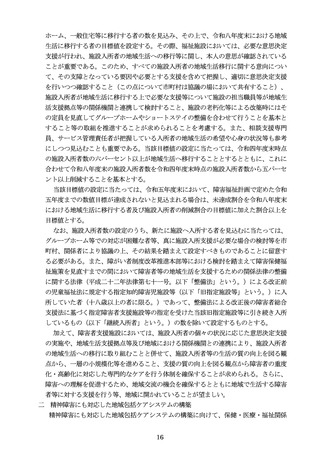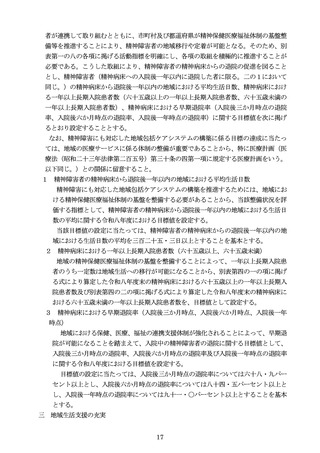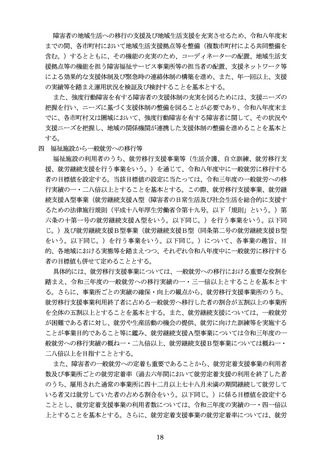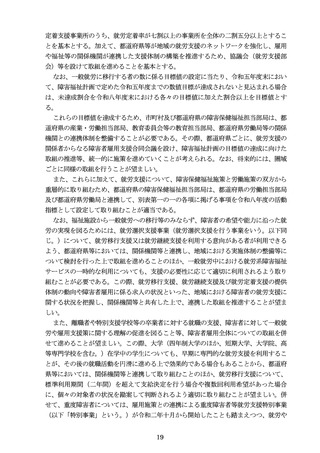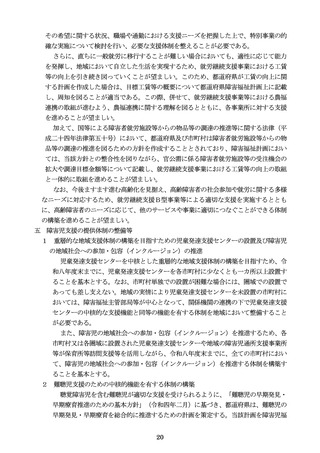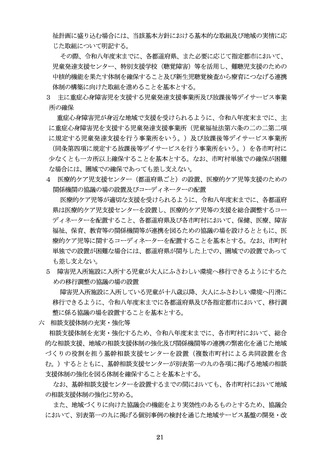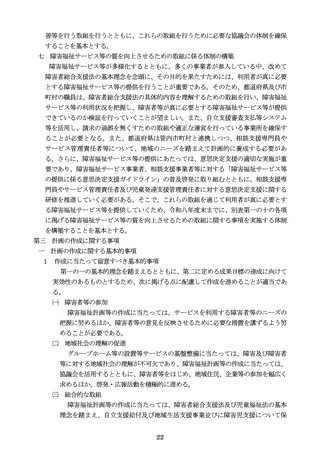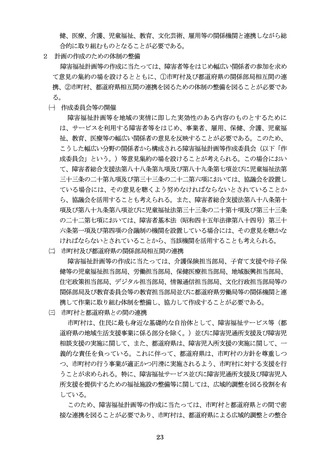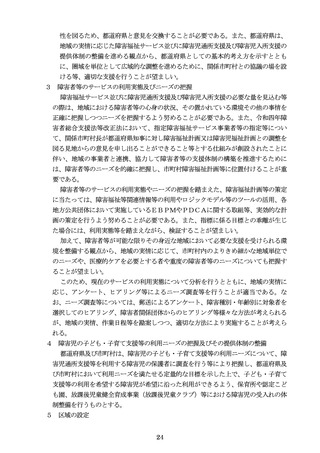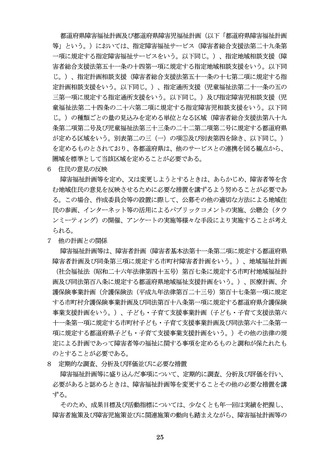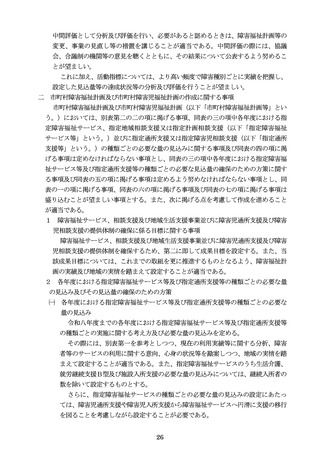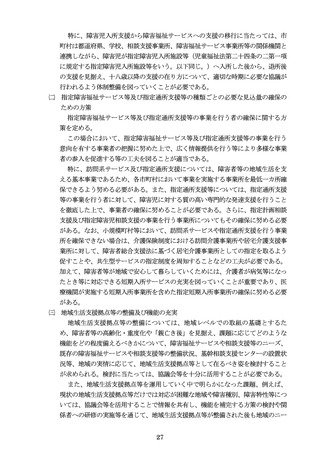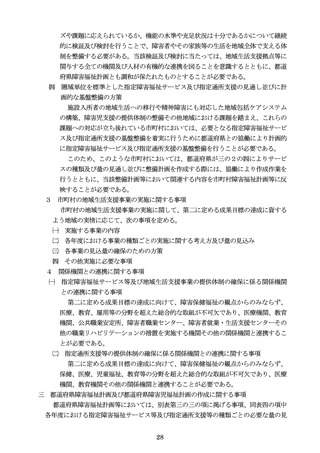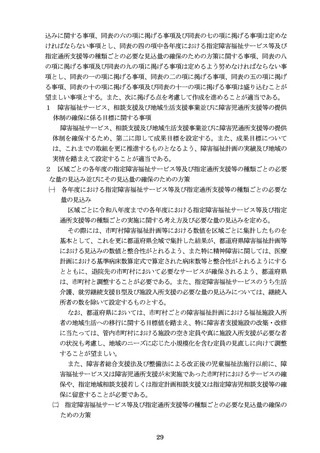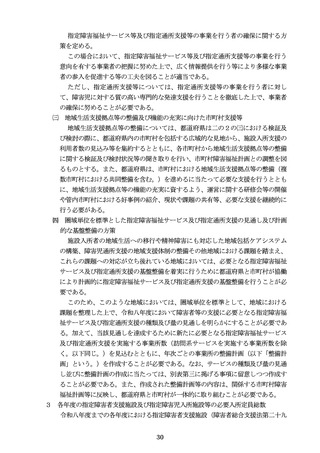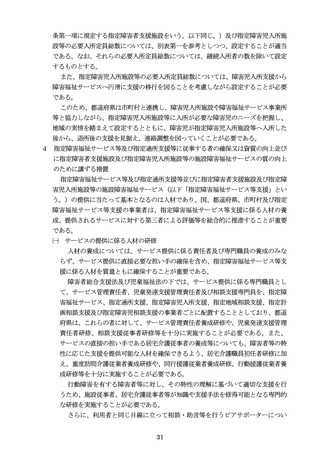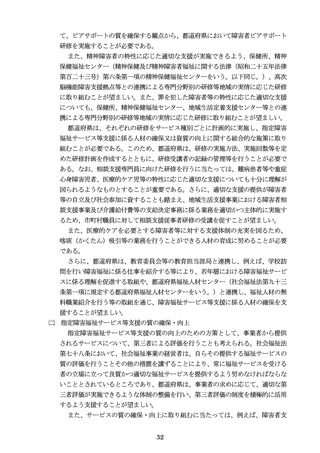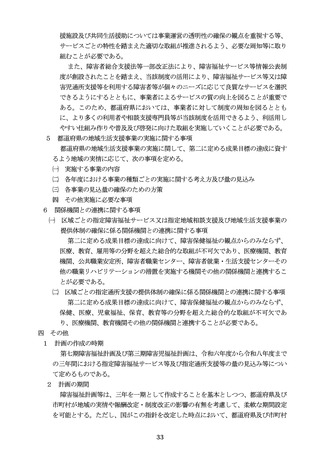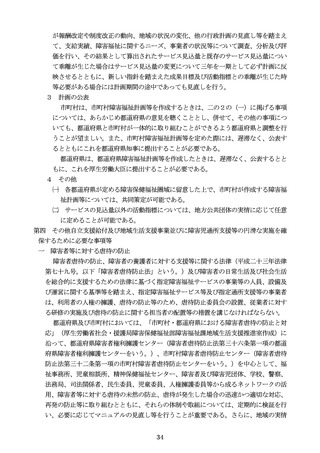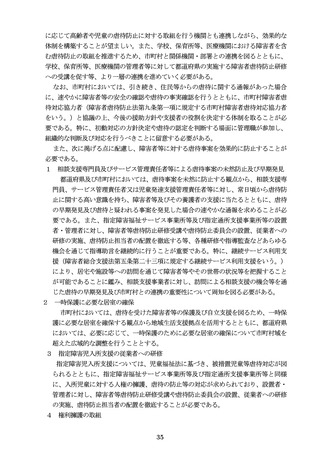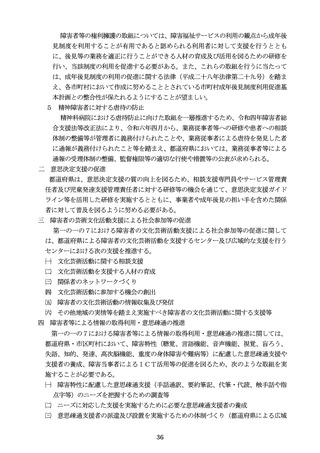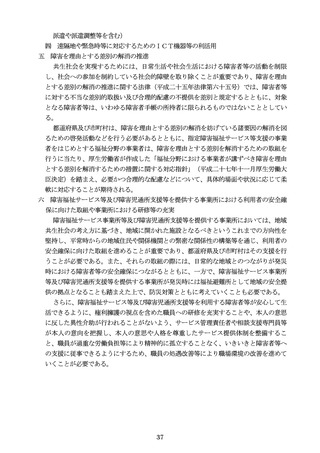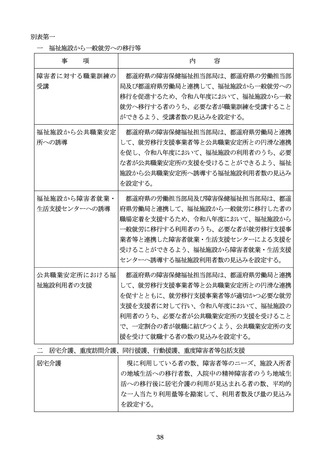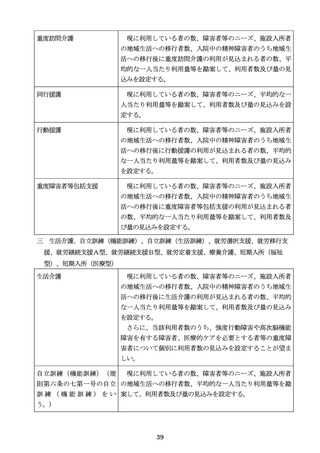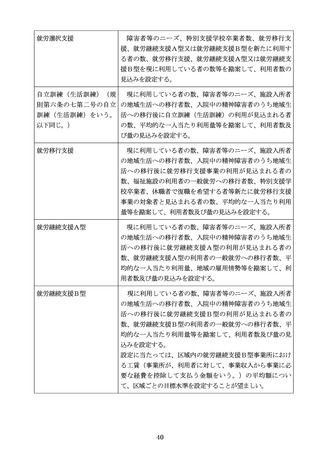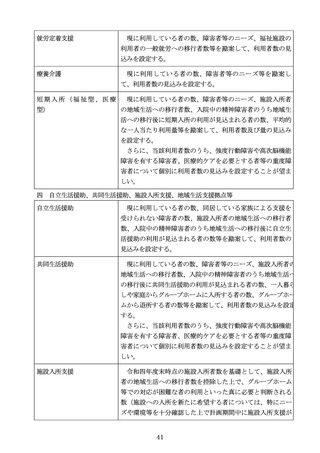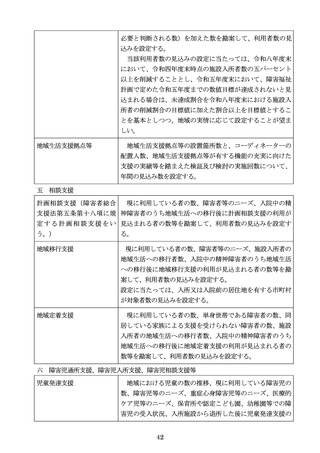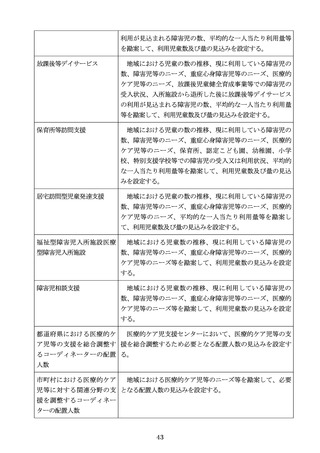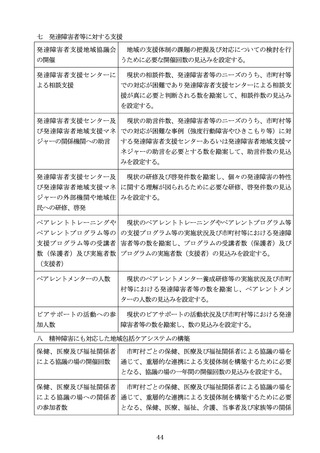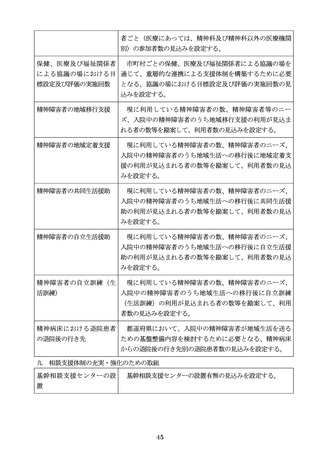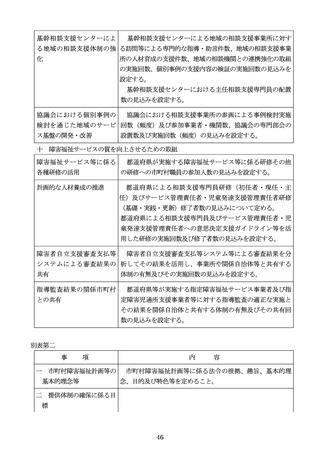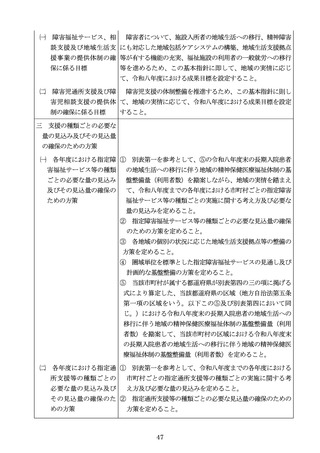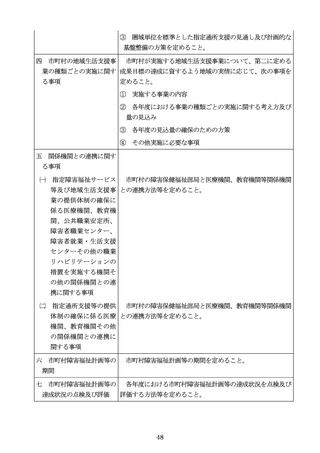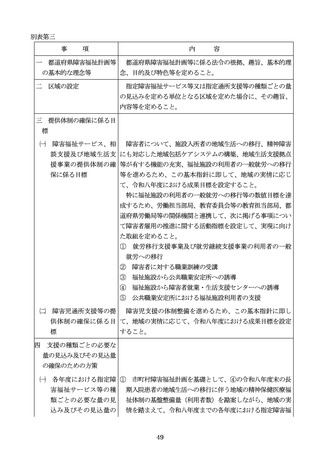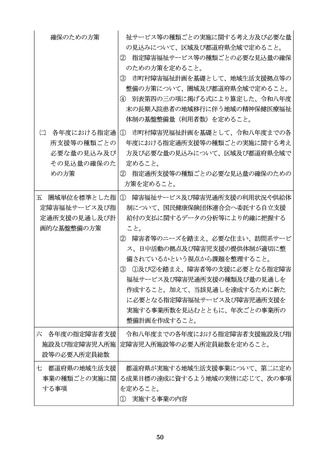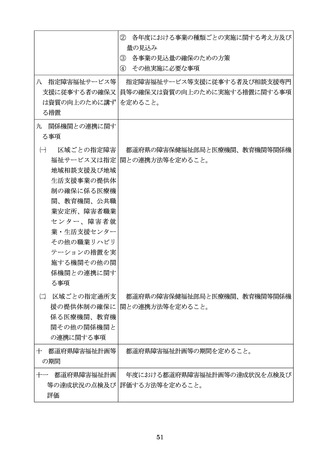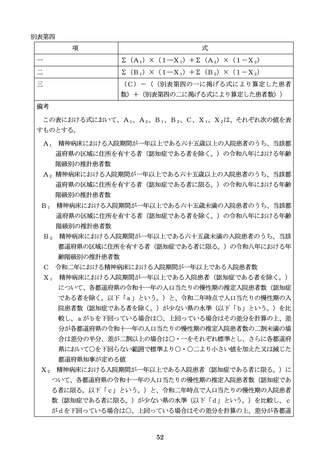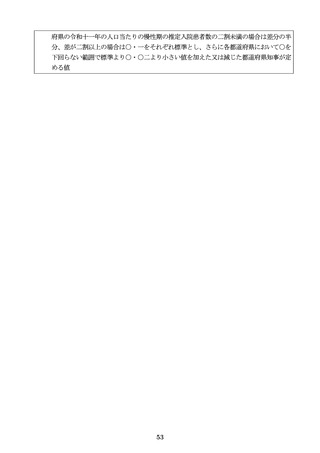よむ、つかう、まなぶ。
参考資料1 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(現行) (3 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64028.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第150回 10/1)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
域の社会資源を最大限に活用し、提供体制の整備を進める。
特に、入所等から地域生活への移行については、適切に意思決定支援を行いつつ
地域生活を希望する者が地域での暮らしを継続することができるよう、必要な障害福
祉サービス等が提供される体制を整備する必要があり、例えば、重度化・高齢化した
障害者で地域生活を希望する者に対しては、日中サービス支援型指定共同生活援助
(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福
祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第
百七十一号)第二百十三条の二に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助をい
う。以下同じ。)により常時の支援体制を確保すること等により、地域生活への移行
が可能となるようサービス提供体制を確保する。
また、市町村は、地域生活に対する安心感を担保し、自立した生活を希望する者に
対する支援等を進めるために、地域生活への移行、親元からの自立等に係る相談、一
人暮らし、グループホーム(障害者総合支援法第五条第十七項に規定する共同生活援
助を行う住居をいう。以下同じ。)への入居等の体験の機会及び場の提供、短期入所
(同条第八項に規定する短期入所をいう。以下同じ。)の利便性・対応力の向上等に
よる緊急時の受入対応体制の確保、人材の確保・養成・連携等による専門性の確保並
びにサービス拠点の整備及びコーディネーターの配置等による地域の体制づくりを行
う機能を有する地域生活支援拠点等(障害者総合支援法第七十七条第四項に規定する
地域生活支援拠点等をいう。以下同じ。)を整備するとともに、障害者の重度化・高
齢化や「親亡き後」を見据えて、これらの機能をさらに強化する必要がある。こうし
た拠点等の整備にあわせて、相談支援を中心として、学校からの卒業、就職、親元か
らの自立等の生活環境が変化する節目を見据えて、中長期的視点に立った継続した支
援を行う必要がある。なお、地域生活支援拠点等の整備・運営に当たっては、地域生
活支援拠点等と基幹相談支援センターのそれぞれの役割を踏まえた効果的な連携を確
保する必要がある。
さらに、精神病床(病院の病床のうち、精神疾患を有する者を入院させるための
ものをいう。以下同じ。)における長期入院患者の地域生活への移行を進めるに当
たっては、精神科病院や地域援助事業者による努力だけでは限界があり、自治体を中
心とした地域精神保健医療福祉の一体的な取組の推進に加え、差別や偏見のない、あ
らゆる人が共生できる包摂的(インクルーシブ)な社会の実現に向けた取組の推進が
必要である。これを踏まえ、精神障害者が、地域の一員として安心して自分らしい暮
らしをすることができるよう、精神障害(発達障害及び高次脳機能障害を含む。以下
同じ。)にも対応した地域包括ケアシステムの構築を進める。
4 地域共生社会の実現に向けた取組
地域のあらゆる住民が、「支え手」と「受け手」に分かれるのではなく、地域、暮
らし、生きがいをともに創り、高め合うことができる地域共生社会の実現に向け、引
き続き、地域住民が主体的に地域づくりに取り組むための仕組み作りや制度の縦割り
を超えた柔軟なサービスの確保に取り組むとともに、地域ごとの地理的条件や地域資
3
特に、入所等から地域生活への移行については、適切に意思決定支援を行いつつ
地域生活を希望する者が地域での暮らしを継続することができるよう、必要な障害福
祉サービス等が提供される体制を整備する必要があり、例えば、重度化・高齢化した
障害者で地域生活を希望する者に対しては、日中サービス支援型指定共同生活援助
(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福
祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第
百七十一号)第二百十三条の二に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助をい
う。以下同じ。)により常時の支援体制を確保すること等により、地域生活への移行
が可能となるようサービス提供体制を確保する。
また、市町村は、地域生活に対する安心感を担保し、自立した生活を希望する者に
対する支援等を進めるために、地域生活への移行、親元からの自立等に係る相談、一
人暮らし、グループホーム(障害者総合支援法第五条第十七項に規定する共同生活援
助を行う住居をいう。以下同じ。)への入居等の体験の機会及び場の提供、短期入所
(同条第八項に規定する短期入所をいう。以下同じ。)の利便性・対応力の向上等に
よる緊急時の受入対応体制の確保、人材の確保・養成・連携等による専門性の確保並
びにサービス拠点の整備及びコーディネーターの配置等による地域の体制づくりを行
う機能を有する地域生活支援拠点等(障害者総合支援法第七十七条第四項に規定する
地域生活支援拠点等をいう。以下同じ。)を整備するとともに、障害者の重度化・高
齢化や「親亡き後」を見据えて、これらの機能をさらに強化する必要がある。こうし
た拠点等の整備にあわせて、相談支援を中心として、学校からの卒業、就職、親元か
らの自立等の生活環境が変化する節目を見据えて、中長期的視点に立った継続した支
援を行う必要がある。なお、地域生活支援拠点等の整備・運営に当たっては、地域生
活支援拠点等と基幹相談支援センターのそれぞれの役割を踏まえた効果的な連携を確
保する必要がある。
さらに、精神病床(病院の病床のうち、精神疾患を有する者を入院させるための
ものをいう。以下同じ。)における長期入院患者の地域生活への移行を進めるに当
たっては、精神科病院や地域援助事業者による努力だけでは限界があり、自治体を中
心とした地域精神保健医療福祉の一体的な取組の推進に加え、差別や偏見のない、あ
らゆる人が共生できる包摂的(インクルーシブ)な社会の実現に向けた取組の推進が
必要である。これを踏まえ、精神障害者が、地域の一員として安心して自分らしい暮
らしをすることができるよう、精神障害(発達障害及び高次脳機能障害を含む。以下
同じ。)にも対応した地域包括ケアシステムの構築を進める。
4 地域共生社会の実現に向けた取組
地域のあらゆる住民が、「支え手」と「受け手」に分かれるのではなく、地域、暮
らし、生きがいをともに創り、高め合うことができる地域共生社会の実現に向け、引
き続き、地域住民が主体的に地域づくりに取り組むための仕組み作りや制度の縦割り
を超えた柔軟なサービスの確保に取り組むとともに、地域ごとの地理的条件や地域資
3