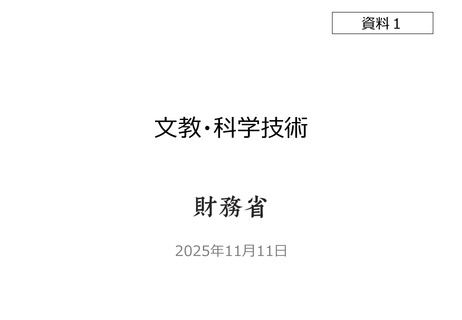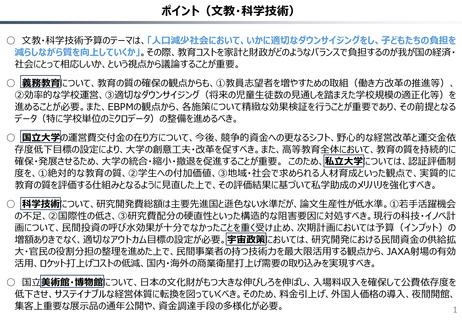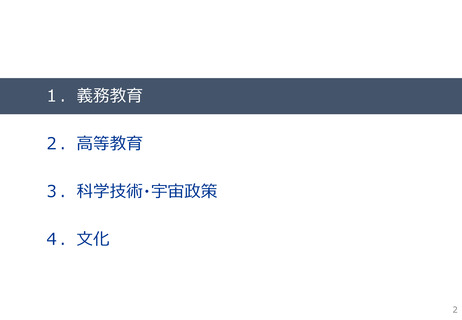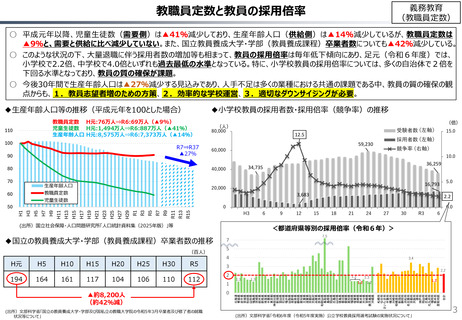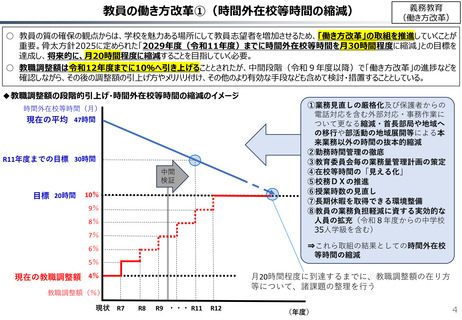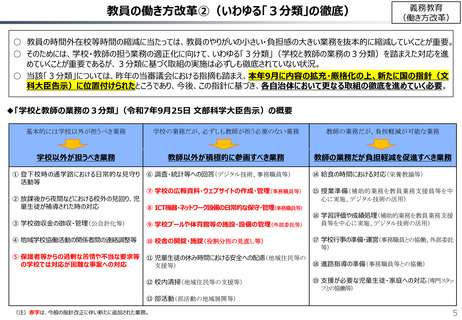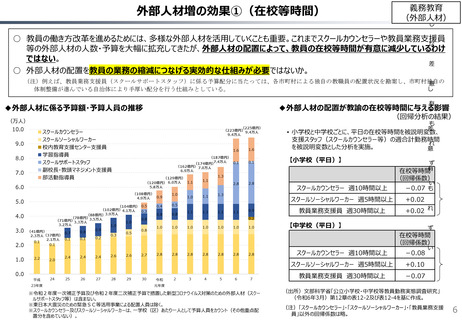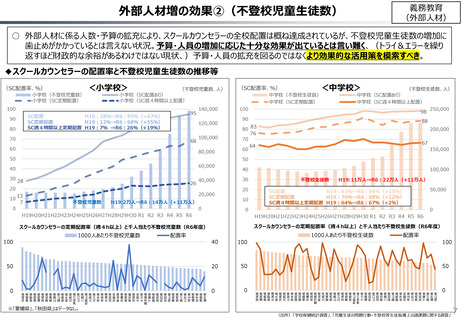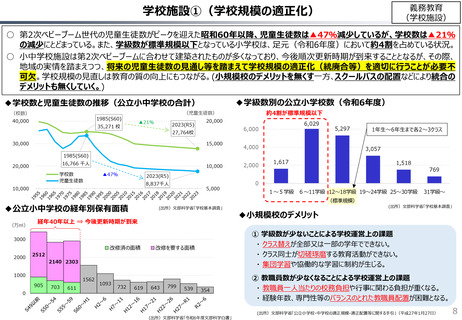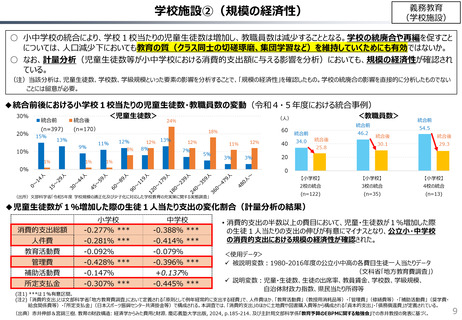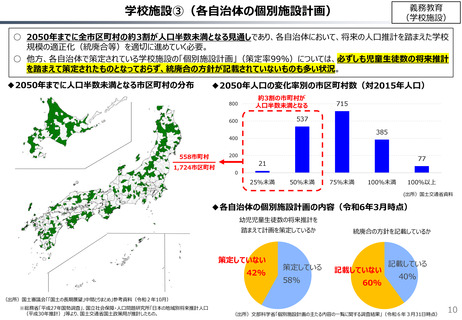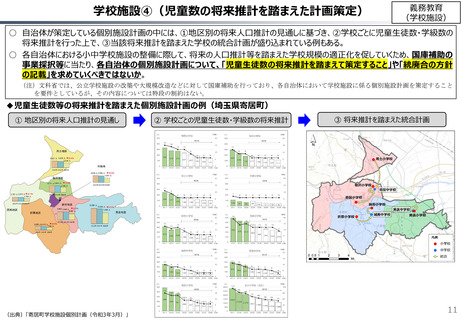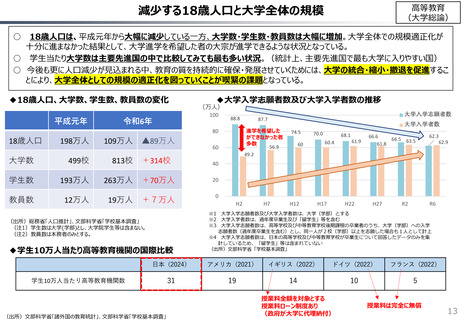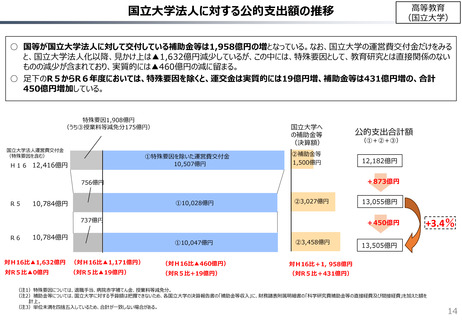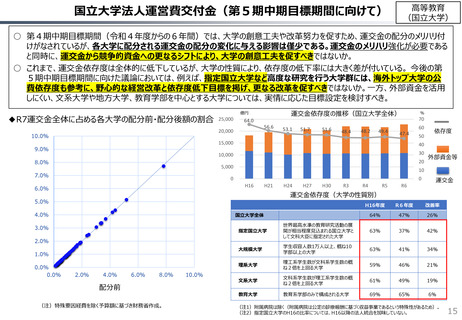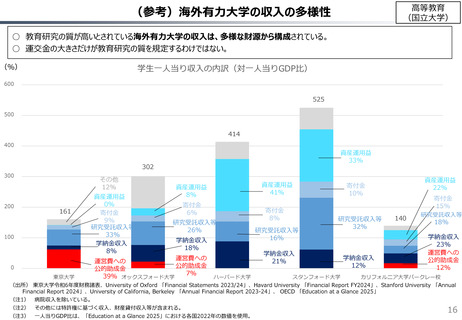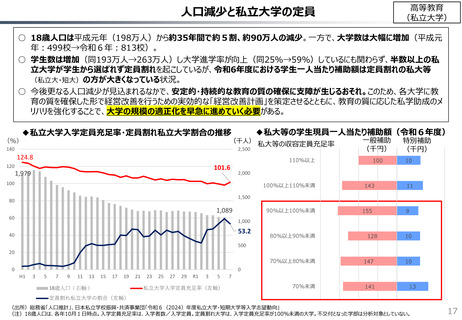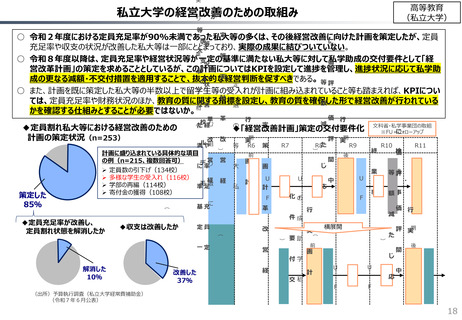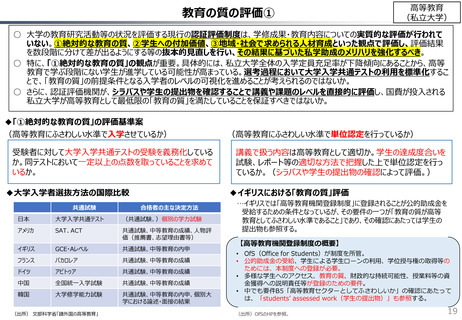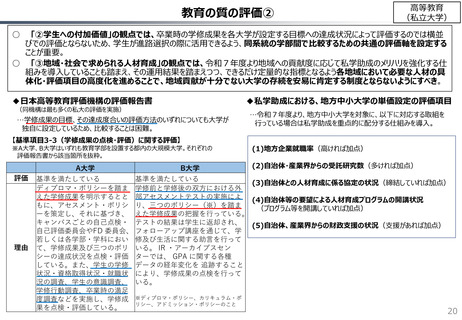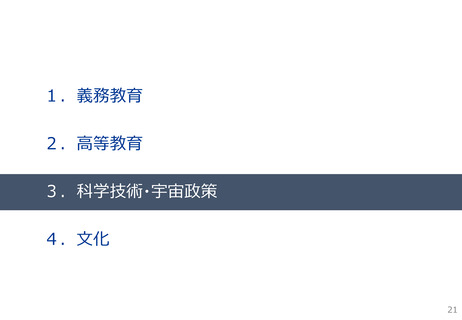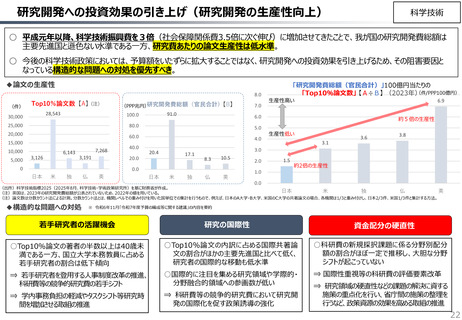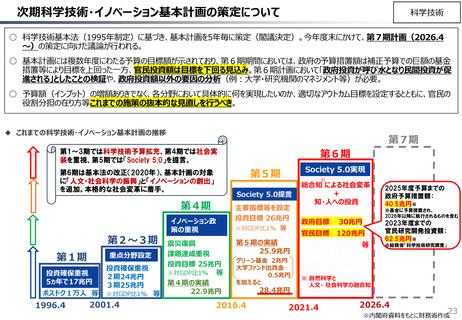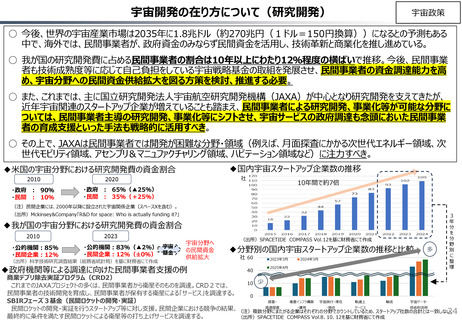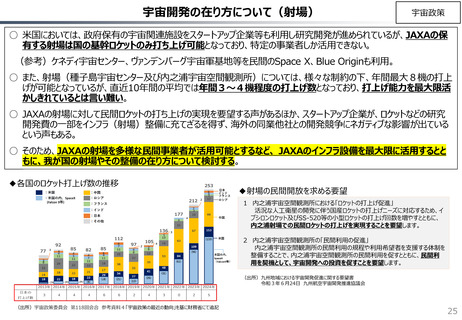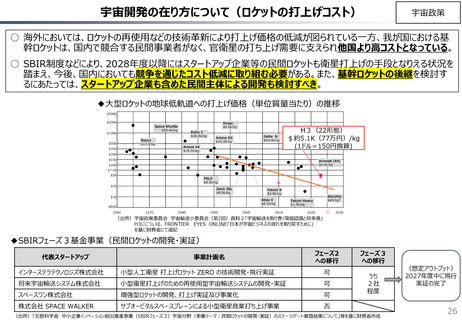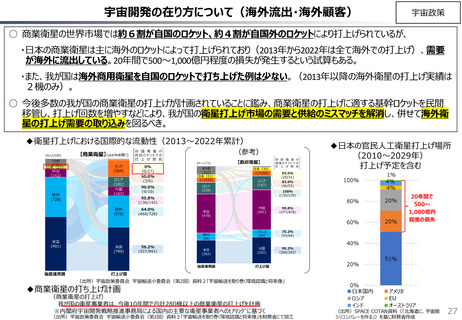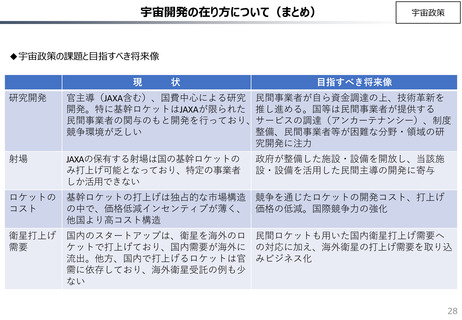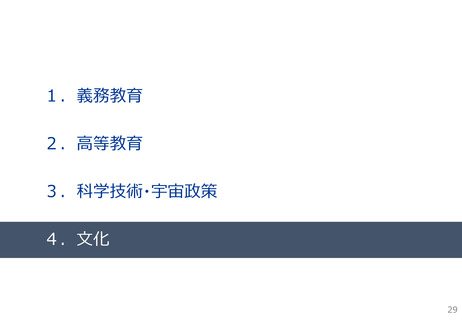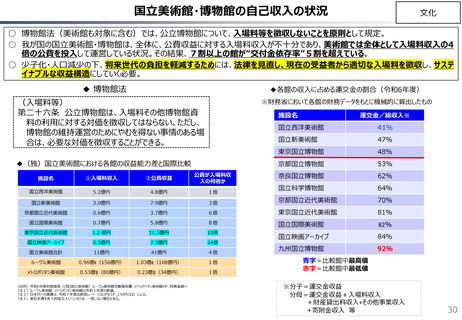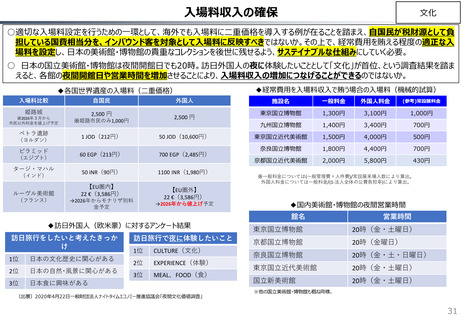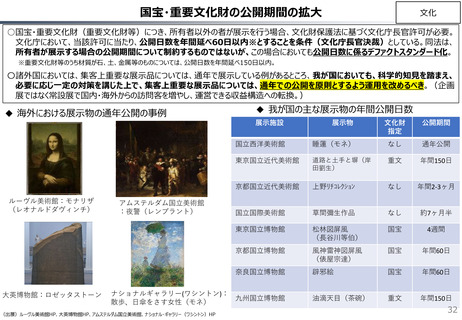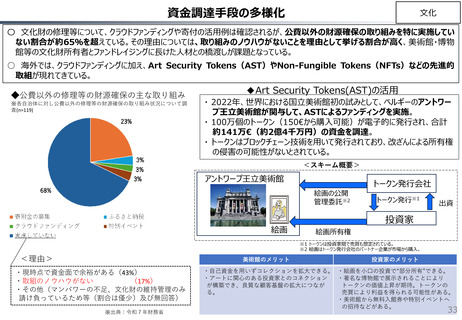よむ、つかう、まなぶ。
文教・科学技術 (23 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/20251111zaiseia.html |
| 出典情報 | 財政制度等審議会 財政制度分科会(11/11)《財務省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
研究開発への投資効果の引き上げ(研究開発の生産性向上)
科学技術
○ 平成元年以降、科学技術振興費を3倍(社会保障関係費3.5倍に次ぐ伸び)に増加させてきたことで、我が国の研究開発費総額は
主要先進国と遜色ない水準である一方、研究費あたりの論文生産性は低水準。
○ 今後の科学技術政策においては、予算額をいたずらに拡大することではなく、研究開発への投資効果を引き上げるため、その阻害要因と
なっている構造的な問題への対処を優先すべき。
◆論文の生産性
(件)
(注)
Top10%論文数【A】
28,543
30,000
8.0
(PPP兆円)研究開発費総額(官民合計)【B】
91.0
100.0
7.0
80.0
20,000
5.0
60.0
4.0
10,000
5,000
0
6,143
3,126
日本
米
3,191
独
仏
7,268
40.0
20.4
20.0
英
0.0
日本
17.1
米
生産性高い
6.9
6.0
25,000
15,000
「研究開発費総額(官民合計)」100億円当たりの
(件/PPP100億円)
「Top10%論文数」 【A÷B】 (2023年)
独
約5倍の生産性
生産性低い
3.1
3.0
8.3
仏
10.5
英
2.0
1.0
1.5
3.6
3.8
約2倍の生産性
0.0
(出所)科学技術指標2025(2025年8月、科学技術・学術政策研究所)を基に財務省が作成。
日本
米
独
仏
英
(注)英国は、2023年の研究開発費総額が公表されていないため、2022年の値を用いている。
(注)論文数は分数カウント法による計測。分数カウント法とは、機関レベルでの重み付けを用いた国単位での集計を行うもので、例えば、日本のA大学・B大学、米国のC大学の共著論文の場合、各機関は1/3と重み付けし、日本2/3件、米国1/3件と集計する方法。
◆構造的な問題への対処
※ 令和6年11月「令和7年度予算の編成等に関する建議」の内容を要約
若手研究者の活躍機会
研究の国際性
資金配分の硬直性
○Top10%論文の著者の半数以上は40歳未
満である一方、国立大学本務教員に占める
若手研究者の割合は低下傾向
○Top10%論文の内訳に占める国際共著論
文の割合がほかの主要先進国と比べて低く、
研究者の国際的な移動も低水準
○科研費の新規採択課題に係る分野別配分
額の割合がほぼ一定で推移し、大胆な分野
シフトが起こっていない
⇒ 若手研究者を登用する人事制度改革の推進、
科研費等の競争的研究費の若手シフト
○国際的に注目を集める研究領域や学際的・
分野融合的領域への参画数が低い
⇒ 国際性重視等の科研費の評価要素改革
⇒ 学内事務負担の軽減やタスクシフト等研究時
間を増加させる取組の推進
⇒ 科研費等の競争的研究費において研究開
発の国際化を促す政策誘導の強化
⇒ 研究領域の硬直性などの課題の解決に資する
施策の重点化を行い、省庁間の施策の整理を
行うなど、政策資源の効果を高める取組の推進
22
科学技術
○ 平成元年以降、科学技術振興費を3倍(社会保障関係費3.5倍に次ぐ伸び)に増加させてきたことで、我が国の研究開発費総額は
主要先進国と遜色ない水準である一方、研究費あたりの論文生産性は低水準。
○ 今後の科学技術政策においては、予算額をいたずらに拡大することではなく、研究開発への投資効果を引き上げるため、その阻害要因と
なっている構造的な問題への対処を優先すべき。
◆論文の生産性
(件)
(注)
Top10%論文数【A】
28,543
30,000
8.0
(PPP兆円)研究開発費総額(官民合計)【B】
91.0
100.0
7.0
80.0
20,000
5.0
60.0
4.0
10,000
5,000
0
6,143
3,126
日本
米
3,191
独
仏
7,268
40.0
20.4
20.0
英
0.0
日本
17.1
米
生産性高い
6.9
6.0
25,000
15,000
「研究開発費総額(官民合計)」100億円当たりの
(件/PPP100億円)
「Top10%論文数」 【A÷B】 (2023年)
独
約5倍の生産性
生産性低い
3.1
3.0
8.3
仏
10.5
英
2.0
1.0
1.5
3.6
3.8
約2倍の生産性
0.0
(出所)科学技術指標2025(2025年8月、科学技術・学術政策研究所)を基に財務省が作成。
日本
米
独
仏
英
(注)英国は、2023年の研究開発費総額が公表されていないため、2022年の値を用いている。
(注)論文数は分数カウント法による計測。分数カウント法とは、機関レベルでの重み付けを用いた国単位での集計を行うもので、例えば、日本のA大学・B大学、米国のC大学の共著論文の場合、各機関は1/3と重み付けし、日本2/3件、米国1/3件と集計する方法。
◆構造的な問題への対処
※ 令和6年11月「令和7年度予算の編成等に関する建議」の内容を要約
若手研究者の活躍機会
研究の国際性
資金配分の硬直性
○Top10%論文の著者の半数以上は40歳未
満である一方、国立大学本務教員に占める
若手研究者の割合は低下傾向
○Top10%論文の内訳に占める国際共著論
文の割合がほかの主要先進国と比べて低く、
研究者の国際的な移動も低水準
○科研費の新規採択課題に係る分野別配分
額の割合がほぼ一定で推移し、大胆な分野
シフトが起こっていない
⇒ 若手研究者を登用する人事制度改革の推進、
科研費等の競争的研究費の若手シフト
○国際的に注目を集める研究領域や学際的・
分野融合的領域への参画数が低い
⇒ 国際性重視等の科研費の評価要素改革
⇒ 学内事務負担の軽減やタスクシフト等研究時
間を増加させる取組の推進
⇒ 科研費等の競争的研究費において研究開
発の国際化を促す政策誘導の強化
⇒ 研究領域の硬直性などの課題の解決に資する
施策の重点化を行い、省庁間の施策の整理を
行うなど、政策資源の効果を高める取組の推進
22