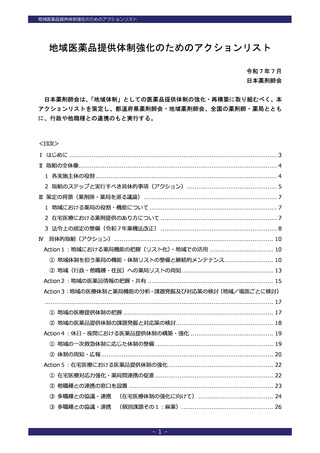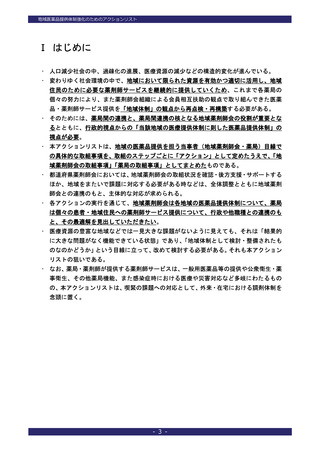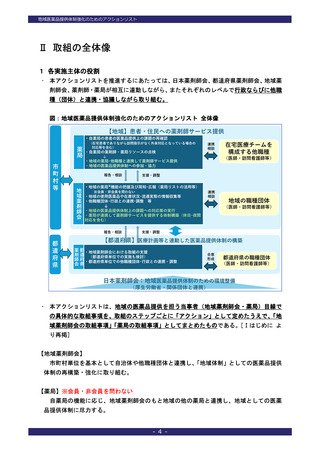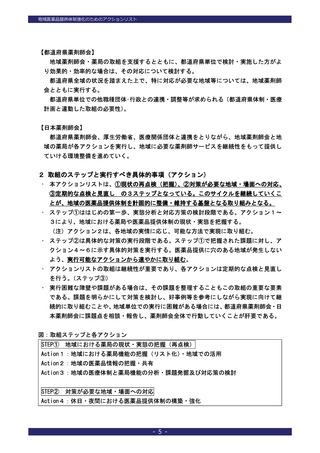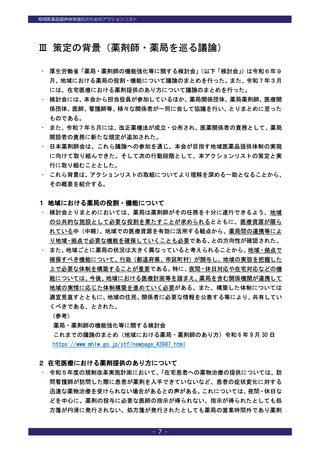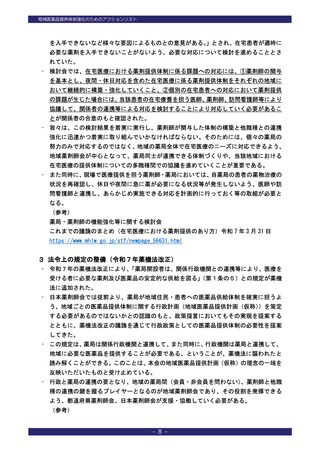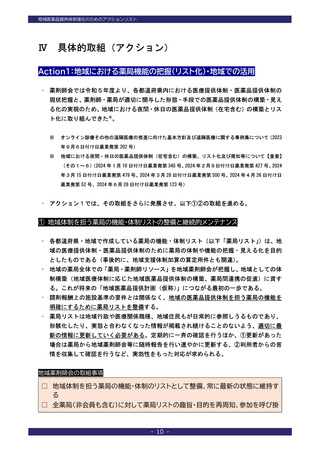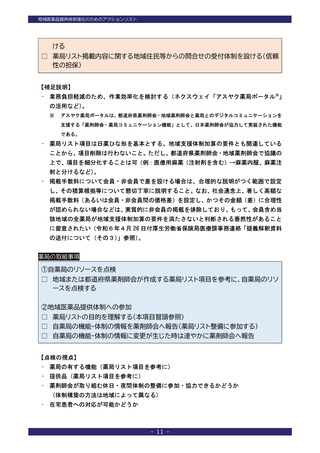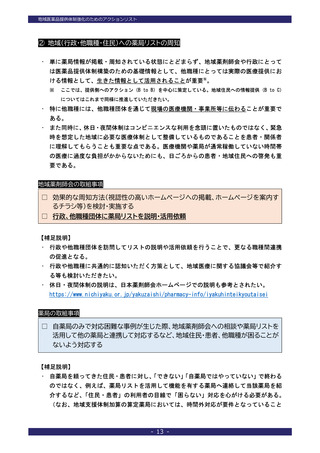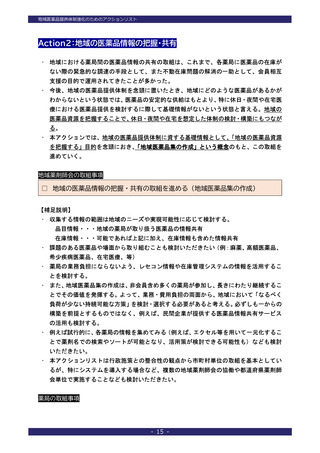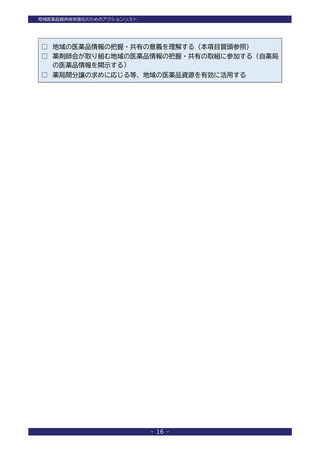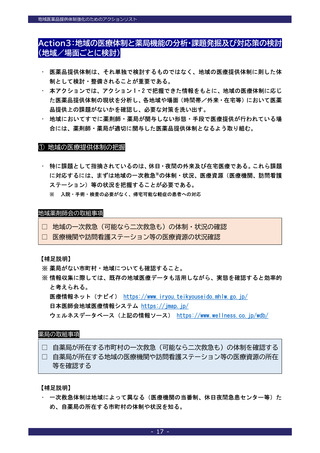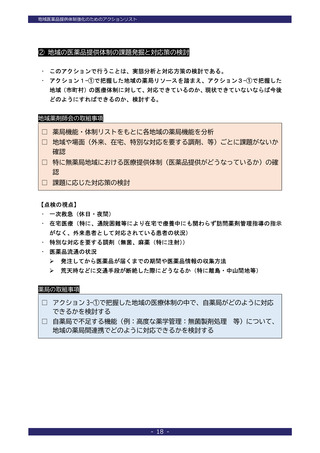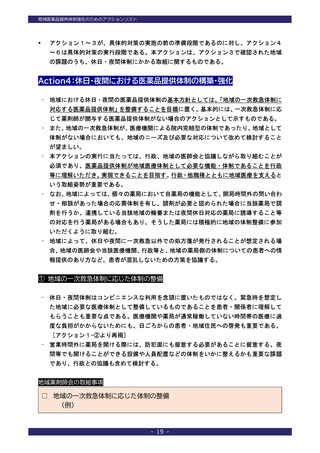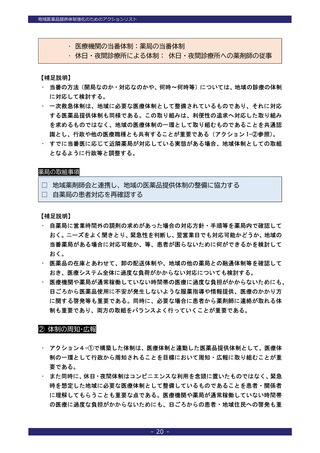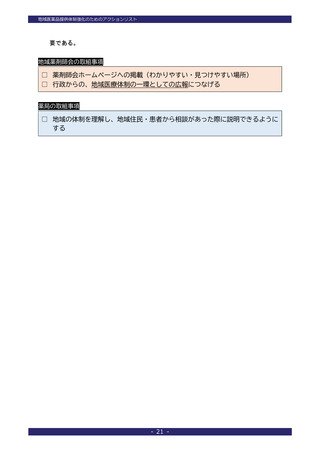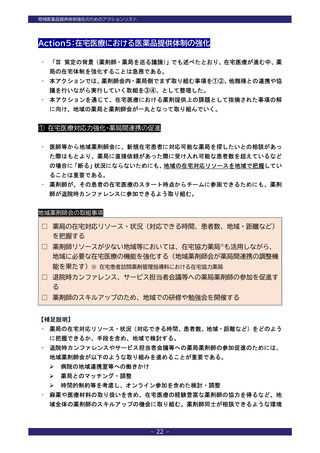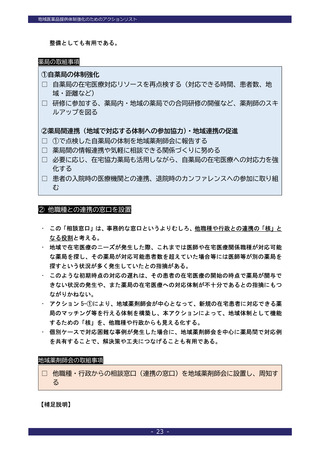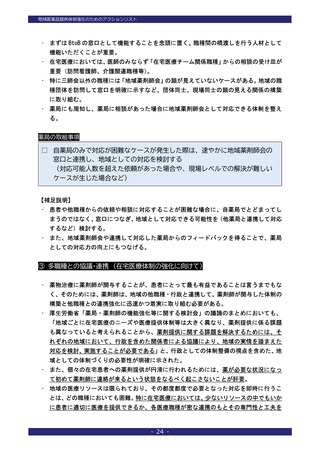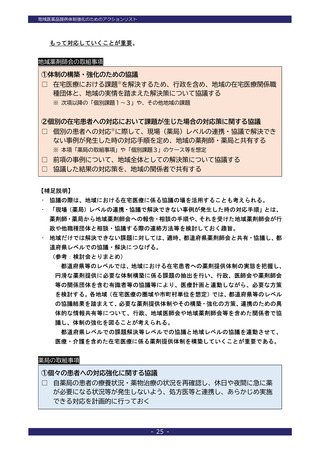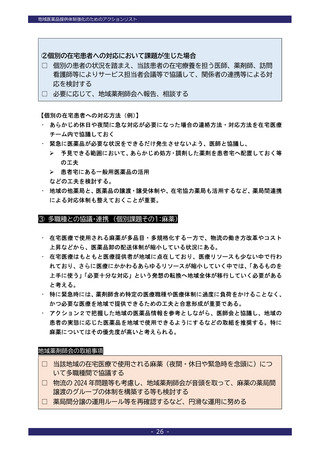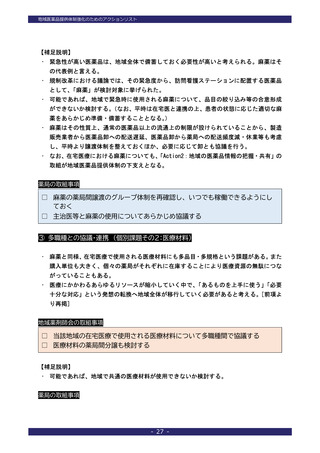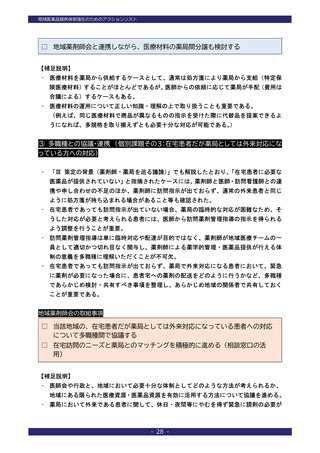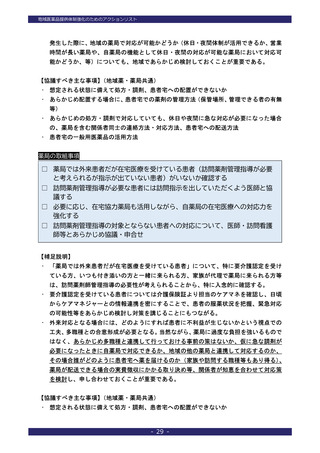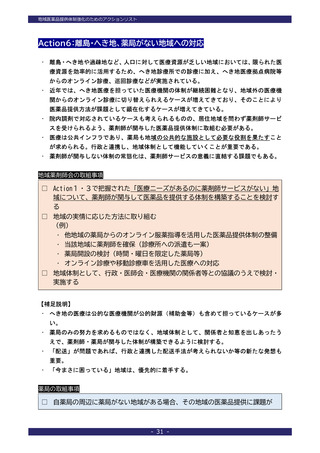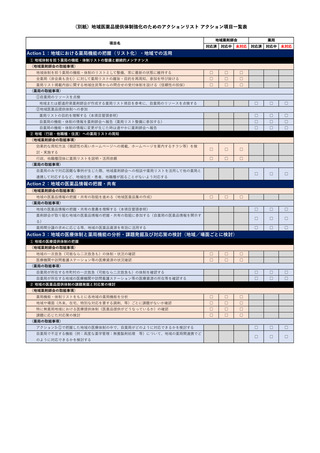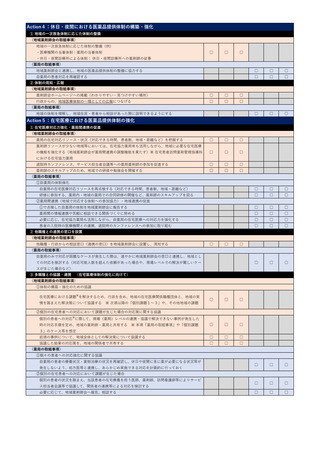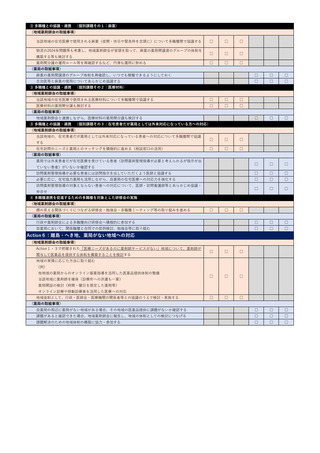よむ、つかう、まなぶ。
地域医薬品提供体制強化のためのアクションリスト(令和7年7月) (23 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.nichiyaku.or.jp/yakuzaishi/activities/division/actionlist |
| 出典情報 | 地域医薬品提供体制強化のためのアクションリストについて(7/17)《日本薬剤師会》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
地域医薬品提供体制強化のためのアクションリスト
整備としても有用である。
薬局の取組事項
①自薬局の体制強化
□ 自薬局の在宅医療対応リソースを再点検する(対応できる時間、患者数、地
域・距離など)
□ 研修に参加する、薬局内・地域の薬局での合同研修の開催など、薬剤師のスキ
ルアップを図る
②薬局間連携(地域で対応する体制への参加協力)・地域連携の促進
□ ①で点検した自薬局の体制を地域薬剤師会に報告する
□ 薬局間の情報連携や気軽に相談できる関係づくりに努める
□ 必要に応じ、在宅協力薬局も活用しながら、自薬局の在宅医療への対応力を強
化する
□ 患者の入院時の医療機関との連携、退院時のカンファレンスへの参加に取り組
む
② 他職種との連携の窓口を設置
この「相談窓口」は、事務的な窓口というよりむしろ、他職種や行政との連携の「核」と
なる役割と考える。
地域で在宅医療のニーズが発生した際、これまでは医師や在宅医療関係職種が対応可能
な薬局を探し、その薬局が対応可能患者数を超えていた場合等には医師等が別の薬局を
探すという状況が多く発生していたとの指摘がある。
このような初期時点の対応の遅れは、その患者の在宅医療の開始の時点で薬局が関与で
きない状況の発生や、また薬局の在宅医療への対応体制が不十分であるとの指摘にもつ
ながりかねない。
アクション 5-①により、地域薬剤師会が中心となって、新規の在宅患者に対応できる薬
局のマッチング等を行える体制を構築し、本アクションによって、地域体制として機能
するための「核」を、他職種や行政からも見える化する。
個別ケースで対応困難な事例が発生した場合に、地域薬剤師会を中心に薬局間で対応例
を共有することで、解決策や工夫につなげることも有用である。
地域薬剤師会の取組事項
□ 他職種・行政からの相談窓口(連携の窓口)を地域薬剤師会に設置し、周知す
る
【補足説明】
- 23 -
整備としても有用である。
薬局の取組事項
①自薬局の体制強化
□ 自薬局の在宅医療対応リソースを再点検する(対応できる時間、患者数、地
域・距離など)
□ 研修に参加する、薬局内・地域の薬局での合同研修の開催など、薬剤師のスキ
ルアップを図る
②薬局間連携(地域で対応する体制への参加協力)・地域連携の促進
□ ①で点検した自薬局の体制を地域薬剤師会に報告する
□ 薬局間の情報連携や気軽に相談できる関係づくりに努める
□ 必要に応じ、在宅協力薬局も活用しながら、自薬局の在宅医療への対応力を強
化する
□ 患者の入院時の医療機関との連携、退院時のカンファレンスへの参加に取り組
む
② 他職種との連携の窓口を設置
この「相談窓口」は、事務的な窓口というよりむしろ、他職種や行政との連携の「核」と
なる役割と考える。
地域で在宅医療のニーズが発生した際、これまでは医師や在宅医療関係職種が対応可能
な薬局を探し、その薬局が対応可能患者数を超えていた場合等には医師等が別の薬局を
探すという状況が多く発生していたとの指摘がある。
このような初期時点の対応の遅れは、その患者の在宅医療の開始の時点で薬局が関与で
きない状況の発生や、また薬局の在宅医療への対応体制が不十分であるとの指摘にもつ
ながりかねない。
アクション 5-①により、地域薬剤師会が中心となって、新規の在宅患者に対応できる薬
局のマッチング等を行える体制を構築し、本アクションによって、地域体制として機能
するための「核」を、他職種や行政からも見える化する。
個別ケースで対応困難な事例が発生した場合に、地域薬剤師会を中心に薬局間で対応例
を共有することで、解決策や工夫につなげることも有用である。
地域薬剤師会の取組事項
□ 他職種・行政からの相談窓口(連携の窓口)を地域薬剤師会に設置し、周知す
る
【補足説明】
- 23 -