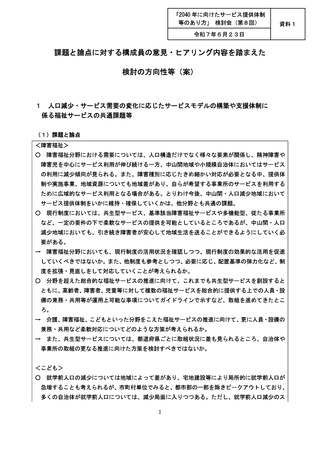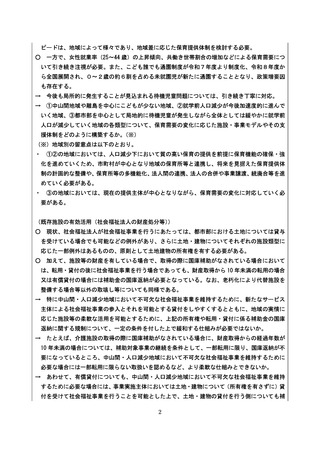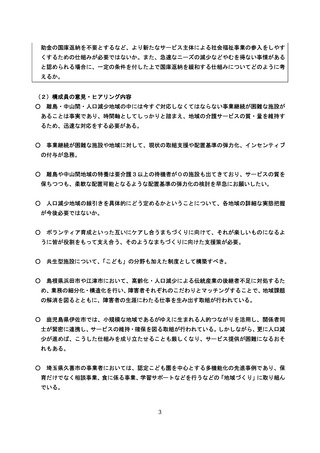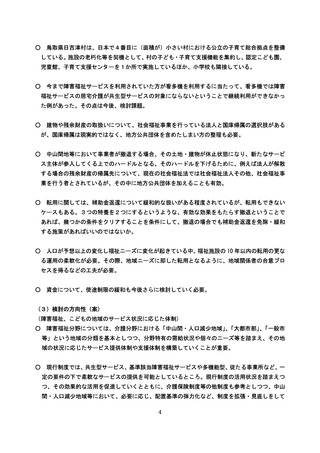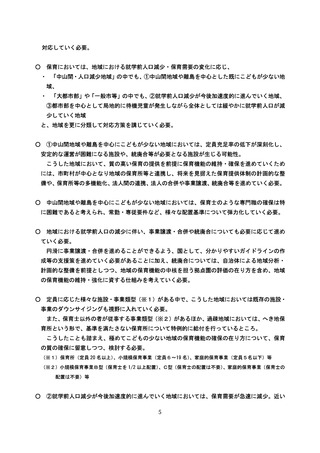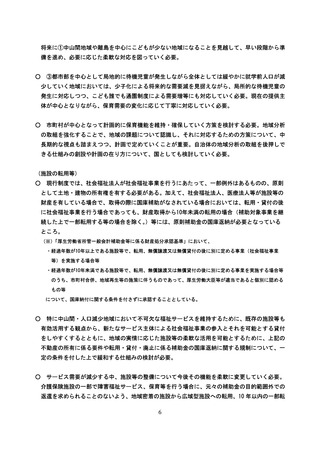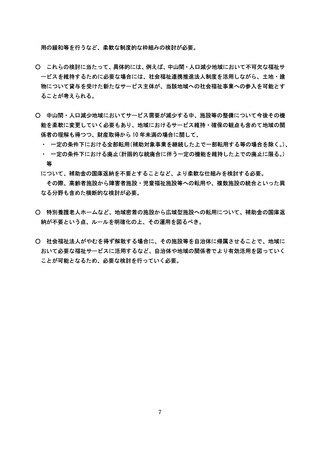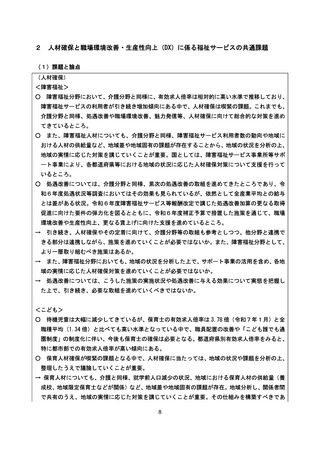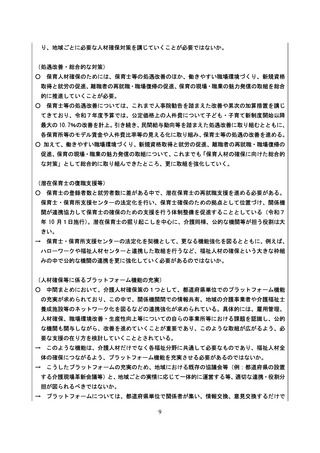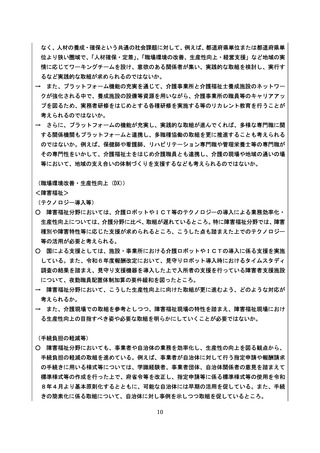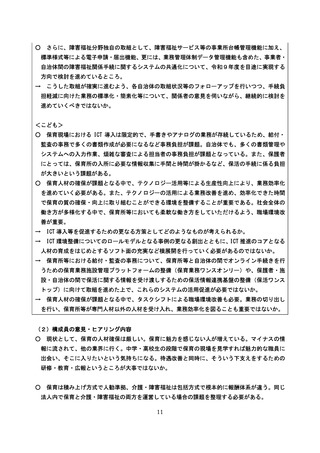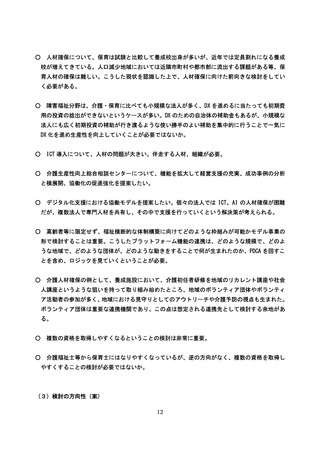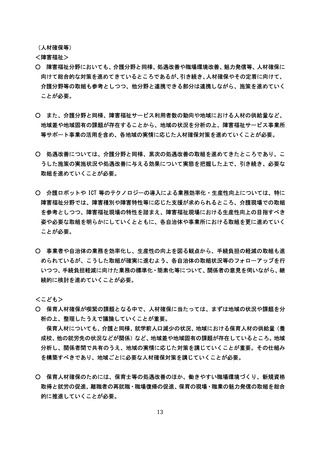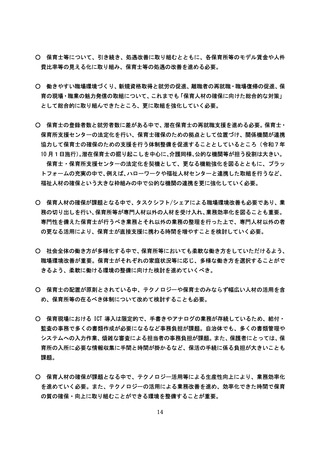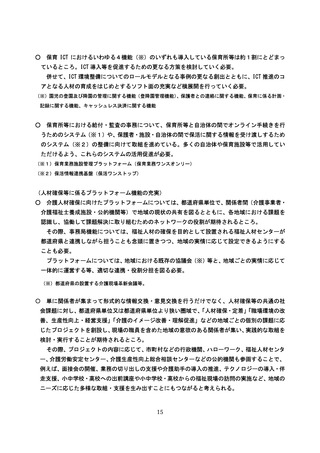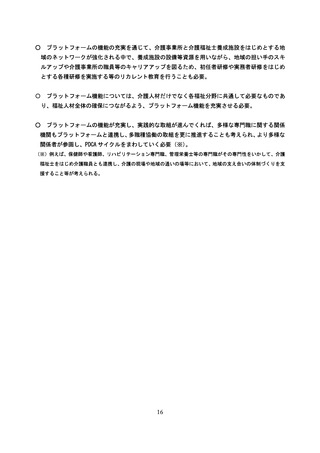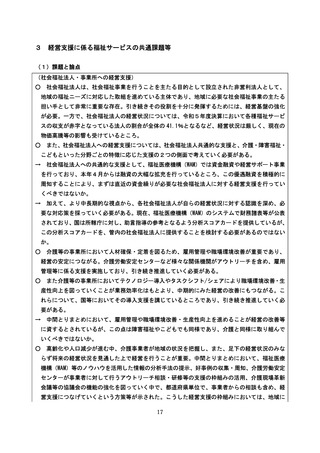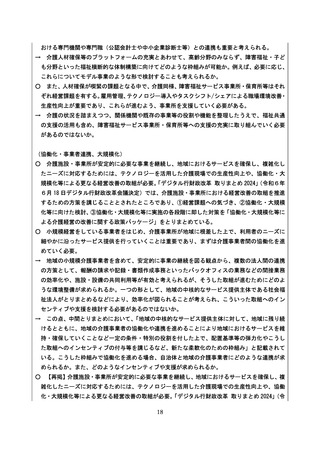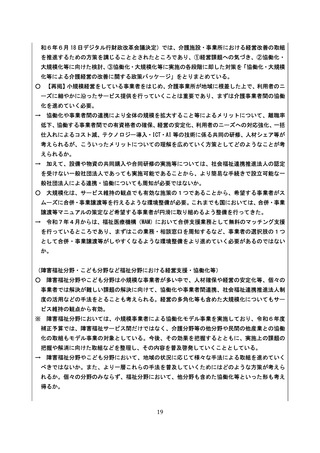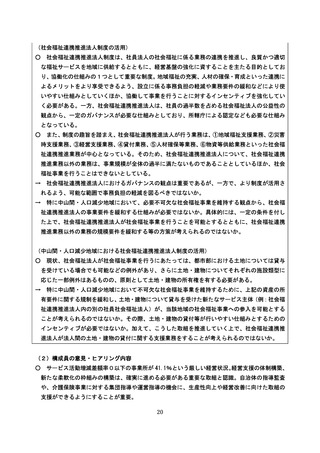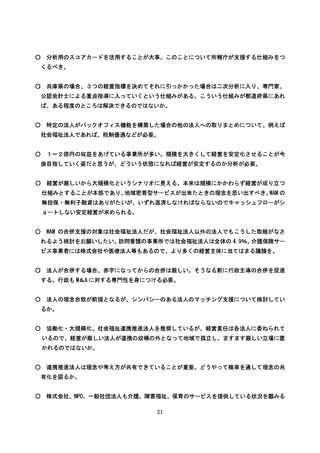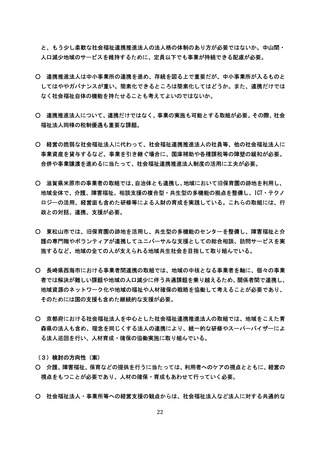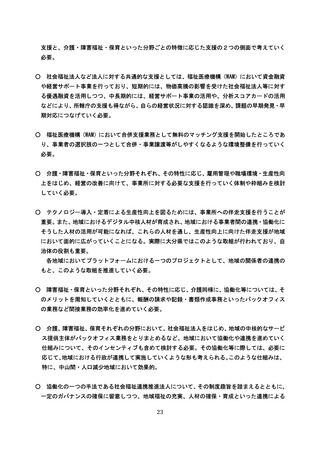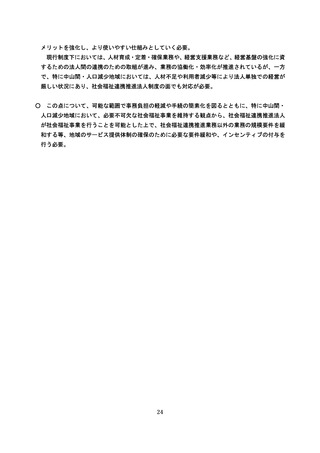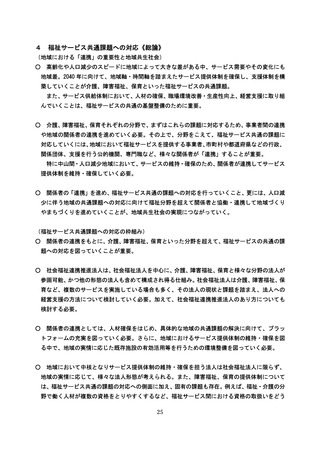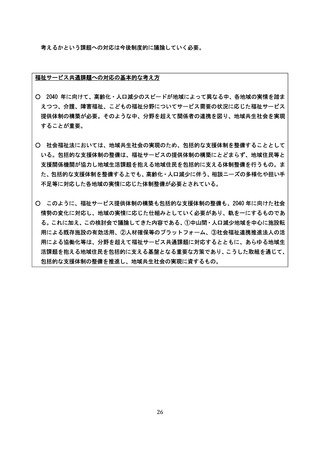よむ、つかう、まなぶ。
資料1 課題と論点に対する構成員の意見・ヒアリング内容を踏 まえた検討の方向性等(案) (2 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59051.html |
| 出典情報 | 「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会(第8回 6/23)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
ピードは、地域によって様々であり、地域差に応じた保育提供体制を検討する必要。
○ 一方で、女性就業率(25~44 歳)の上昇傾向、共働き世帯割合の増加などによる保育需要につ
いて引き続き注視が必要。また、こども誰でも通園制度が令和7年度より制度化、令和8年度か
ら全国展開され、0~2歳の約6割を占める未就園児が新たに通園することとなり、政策増要因
も存在する。
→ 今後も局所的に発生することが見込まれる待機児童問題については、引き続き丁寧に対応。
→ ①中山間地域や離島を中心にこどもが少ない地域、②就学前人口減少が今後加速度的に進んで
いく地域、③都市部を中心として局地的に待機児童が発生しながら全体としては緩やかに就学前
人口が減少していく地域の各類型について、保育需要の変化に応じた施設・事業モデルやその支
援体制をどのように構築するか。(※)
(※)地域別の留意点は以下のとおり。
・
①②の地域においては、人口減少下において質の高い保育の提供を前提に保育機能の確保・強
化を進めていくため、市町村が中心となり地域の保育所等と連携し、将来を見据えた保育提供体
制の計画的な整備や、保育所等の多機能化、法人間の連携、法人の合併や事業譲渡、統廃合等を進
めていく必要がある。
・ ③の地域においては、現在の提供主体が中心となりながら、保育需要の変化に対応していく必
要がある。
(既存施設の有効活用(社会福祉法人の財産処分等)
)
○ 現状、社会福祉法人が社会福祉事業を行うにあたっては、都市部における土地については貸与
を受けている場合でも可能などの例外があり、さらに土地・建物についてそれぞれの施設類型に
応じた一部例外はあるものの、原則として土地建物の所有権を有する必要がある。
○ 加えて、施設等の財産を有している場合で、取得の際に国庫補助がなされている場合において
は、転用・貸付の後に社会福祉事業を行う場合であっても、財産取得から 10 年未満の転用の場合
又は有償貸付の場合には補助金の国庫返納が必要となっている。なお、老朽化により代替施設を
整備する場合等以外の取壊し等についても同様である。
→ 特に中山間・人口減少地域において不可欠な社会福祉事業を維持するために、新たなサービス
主体による社会福祉事業の参入とそれを可能とする貸付をしやすくするとともに、地域の実情に
応じた施設等の柔軟な活用を可能とするために、上記の所有権や転用・貸付に係る補助金の国庫
返納に関する規制について、一定の条件を付した上で緩和する仕組みが必要ではないか。
→ たとえば、介護施設の取得の際に国庫補助がなされている場合に、財産取得からの経過年数が
10 年未満の場合については、補助対象事業の継続を条件として、一部転用に限り、国庫返納が不
要になっているところ、中山間・人口減少地域において不可欠な社会福祉事業を維持するために
必要な場合には一部転用に限らない取扱いを認めるなど、より柔軟な仕組みとできないか。
→ あわせて、有償貸付についても、中山間・人口減少地域において不可欠な社会福祉事業を維持
するために必要な場合には、事業実施主体においては土地・建物について(所有権を有さずに)貸
付を受けて社会福祉事業を行うことを可能とした上で、土地・建物の貸付を行う側についても補
2
○ 一方で、女性就業率(25~44 歳)の上昇傾向、共働き世帯割合の増加などによる保育需要につ
いて引き続き注視が必要。また、こども誰でも通園制度が令和7年度より制度化、令和8年度か
ら全国展開され、0~2歳の約6割を占める未就園児が新たに通園することとなり、政策増要因
も存在する。
→ 今後も局所的に発生することが見込まれる待機児童問題については、引き続き丁寧に対応。
→ ①中山間地域や離島を中心にこどもが少ない地域、②就学前人口減少が今後加速度的に進んで
いく地域、③都市部を中心として局地的に待機児童が発生しながら全体としては緩やかに就学前
人口が減少していく地域の各類型について、保育需要の変化に応じた施設・事業モデルやその支
援体制をどのように構築するか。(※)
(※)地域別の留意点は以下のとおり。
・
①②の地域においては、人口減少下において質の高い保育の提供を前提に保育機能の確保・強
化を進めていくため、市町村が中心となり地域の保育所等と連携し、将来を見据えた保育提供体
制の計画的な整備や、保育所等の多機能化、法人間の連携、法人の合併や事業譲渡、統廃合等を進
めていく必要がある。
・ ③の地域においては、現在の提供主体が中心となりながら、保育需要の変化に対応していく必
要がある。
(既存施設の有効活用(社会福祉法人の財産処分等)
)
○ 現状、社会福祉法人が社会福祉事業を行うにあたっては、都市部における土地については貸与
を受けている場合でも可能などの例外があり、さらに土地・建物についてそれぞれの施設類型に
応じた一部例外はあるものの、原則として土地建物の所有権を有する必要がある。
○ 加えて、施設等の財産を有している場合で、取得の際に国庫補助がなされている場合において
は、転用・貸付の後に社会福祉事業を行う場合であっても、財産取得から 10 年未満の転用の場合
又は有償貸付の場合には補助金の国庫返納が必要となっている。なお、老朽化により代替施設を
整備する場合等以外の取壊し等についても同様である。
→ 特に中山間・人口減少地域において不可欠な社会福祉事業を維持するために、新たなサービス
主体による社会福祉事業の参入とそれを可能とする貸付をしやすくするとともに、地域の実情に
応じた施設等の柔軟な活用を可能とするために、上記の所有権や転用・貸付に係る補助金の国庫
返納に関する規制について、一定の条件を付した上で緩和する仕組みが必要ではないか。
→ たとえば、介護施設の取得の際に国庫補助がなされている場合に、財産取得からの経過年数が
10 年未満の場合については、補助対象事業の継続を条件として、一部転用に限り、国庫返納が不
要になっているところ、中山間・人口減少地域において不可欠な社会福祉事業を維持するために
必要な場合には一部転用に限らない取扱いを認めるなど、より柔軟な仕組みとできないか。
→ あわせて、有償貸付についても、中山間・人口減少地域において不可欠な社会福祉事業を維持
するために必要な場合には、事業実施主体においては土地・建物について(所有権を有さずに)貸
付を受けて社会福祉事業を行うことを可能とした上で、土地・建物の貸付を行う側についても補
2