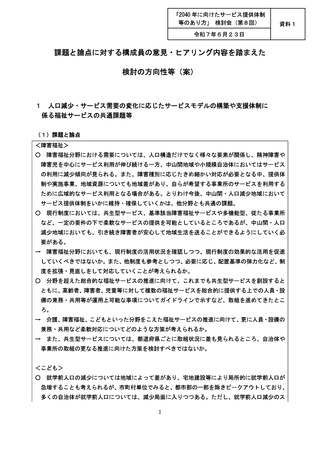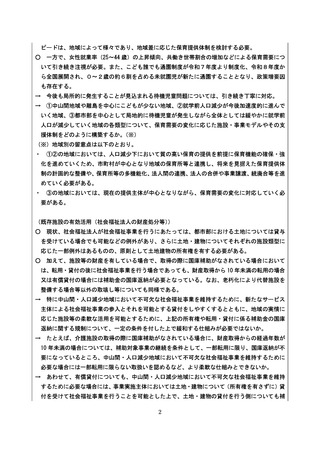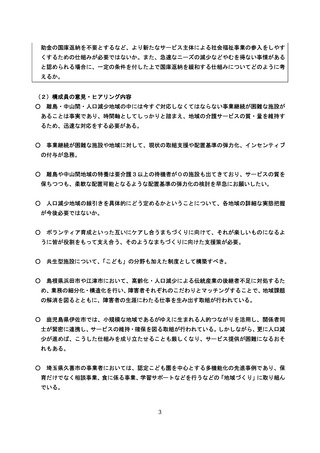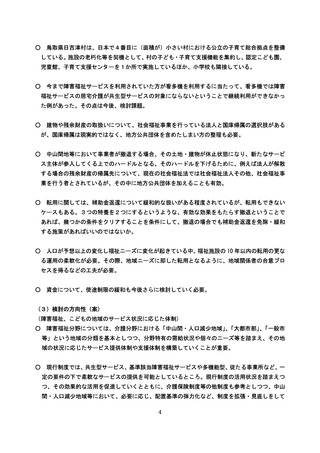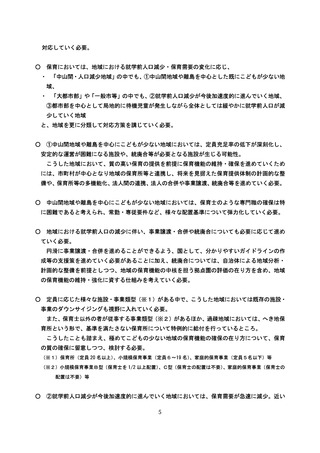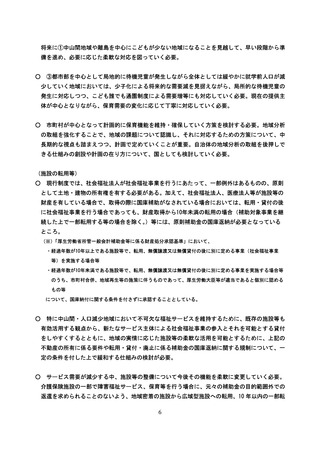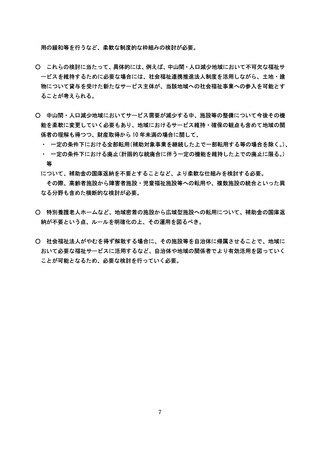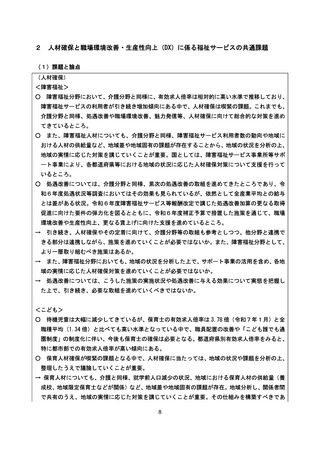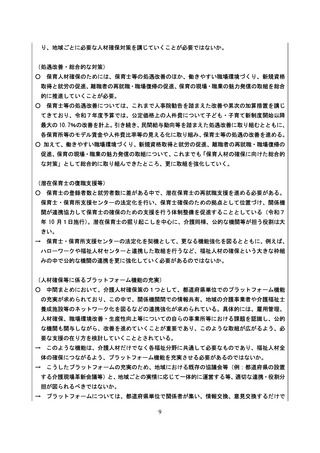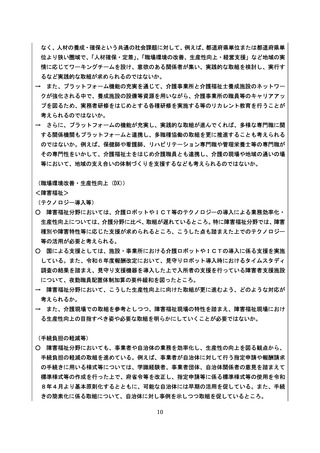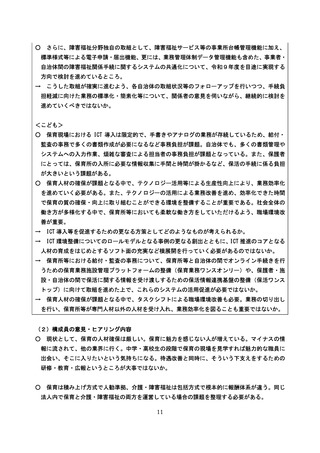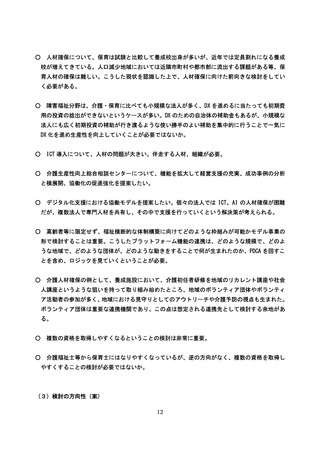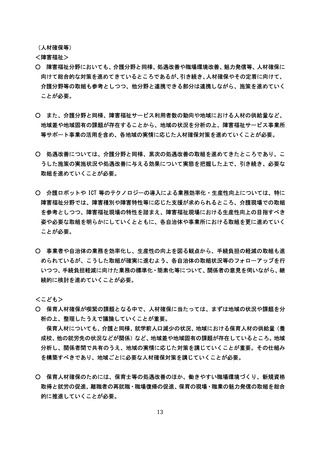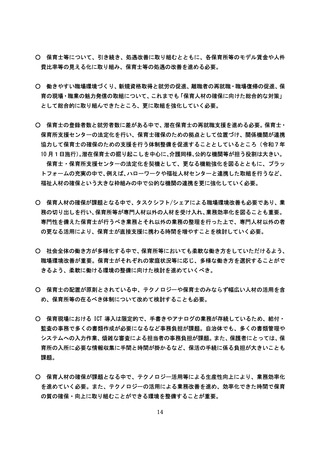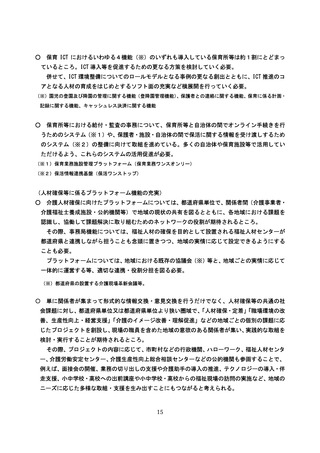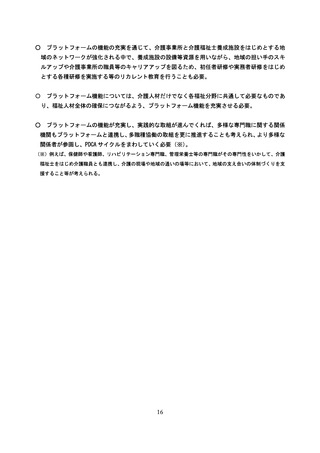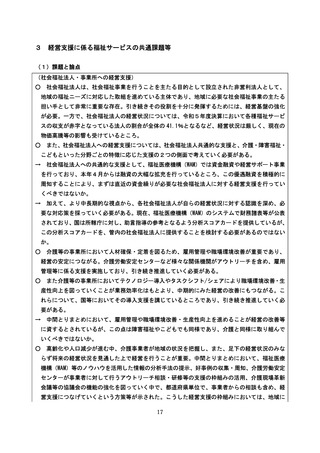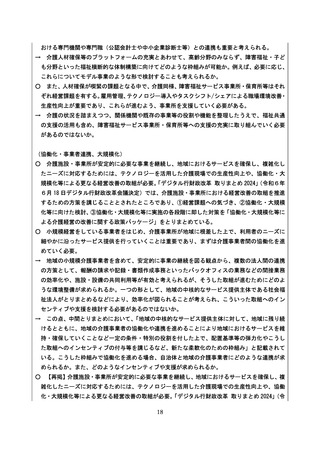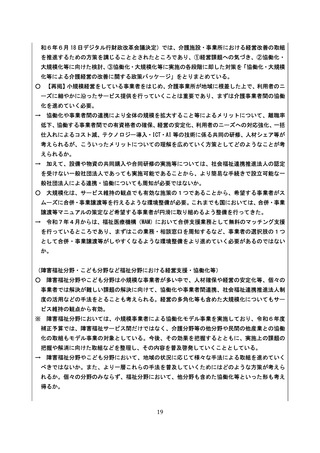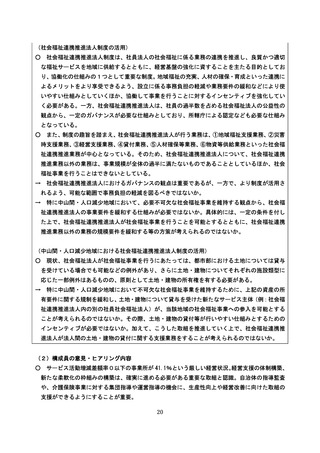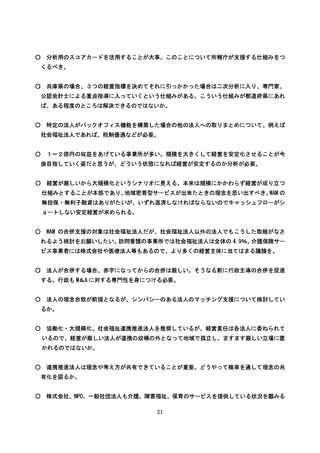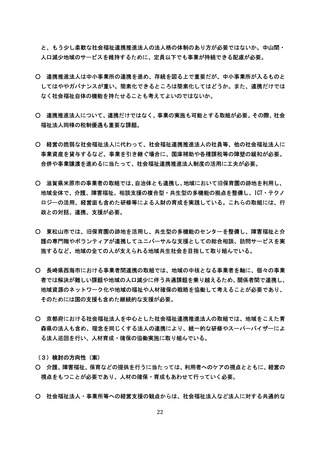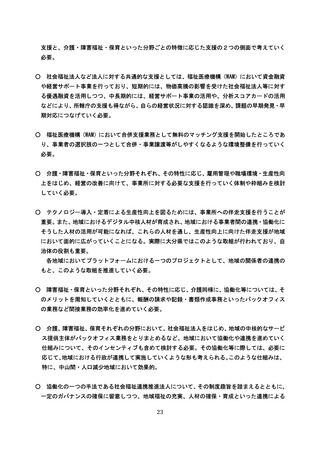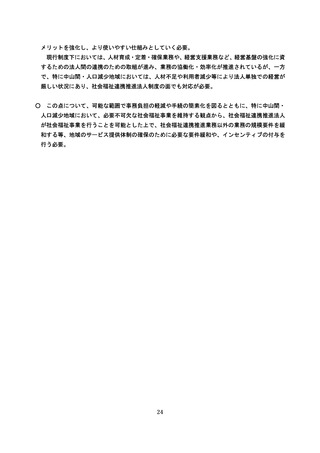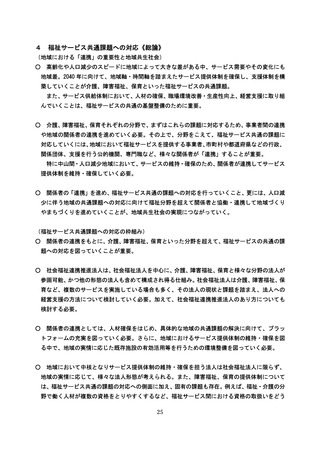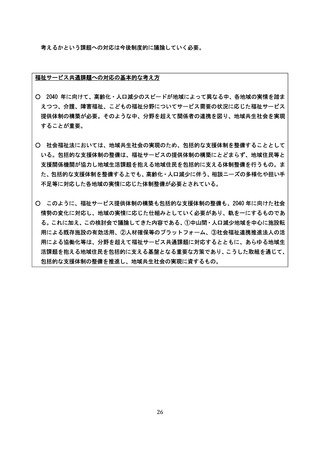よむ、つかう、まなぶ。
資料1 課題と論点に対する構成員の意見・ヒアリング内容を踏 まえた検討の方向性等(案) (14 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59051.html |
| 出典情報 | 「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会(第8回 6/23)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
○ 保育士等について、引き続き、処遇改善に取り組むとともに、各保育所等のモデル賃金や人件
費比率等の見える化に取り組み、保育士等の処遇の改善を進める必要。
○ 働きやすい職場環境づくり、新規資格取得と就労の促進、離職者の再就職・職場復帰の促進、保
育の現場・職業の魅力発信の取組について、これまでも「保育人材の確保に向けた総合的な対策」
として総合的に取り組んできたところ、更に取組を強化していく必要。
○ 保育士の登録者数と就労者数に差がある中で、潜在保育士の再就職支援を進める必要。保育士・
保育所支援センターの法定化を行い、保育士確保のための拠点として位置づけ、関係機関が連携
協力して保育士の確保のための支援を行う体制整備を促進することとしているところ(令和7年
10 月1日施行)
。潜在保育士の掘り起こしを中心に、
介護同様、
公的な機関等が担う役割は大きい。
保育士・保育所支援センターの法定化を契機として、更なる機能強化を図るとともに、プラッ
トフォームの充実の中で、例えば、ハローワークや福祉人材センターと連携した取組を行うなど、
福祉人材の確保という大きな枠組みの中で公的な機関の連携を更に強化していく必要。
○ 保育人材の確保が課題となる中で、タスクシフト/シェアによる職場環境改善も必要であり、業
務の切り出しを行い、保育所等が専門人材以外の人材を受け入れ、業務効率化を図ることも重要。
専門性を備えた保育士が行うべき業務とそれ以外の業務の整理を行った上で、専門人材以外の者
の更なる活用により、保育士が直接支援に携わる時間を増やすことを検討していく必要。
○ 社会全体の働き方が多様化する中で、保育所等においても柔軟な働き方をしていただけるよう、
職場環境改善が重要。保育士がそれぞれの家庭状況等に応じ、多様な働き方を選択することがで
きるよう、柔軟に働ける環境の整備に向けた検討を進めていくべき。
○ 保育士の配置が原則とされている中、テクノロジーや保育士のみならず幅広い人材の活用を含
め、保育所等の在るべき体制について改めて検討することも必要。
○ 保育現場における ICT 導入は限定的で、手書きやアナログの業務が存続しているため、給付・
監査の事務で多くの書類作成が必要になるなど事務負担が課題。自治体でも、多くの書類管理や
システムへの入力作業、煩雑な審査による担当者の事務負担が課題。また、保護者にとっては、保
育所の入所に必要な情報収集に手間と時間が掛かるなど、保活の手続に係る負担が大きいことも
課題。
○ 保育人材の確保が課題となる中で、テクノロジー活用等による生産性向上により、業務効率化
を進めていく必要。また、テクノロジーの活用による業務改善を進め、効率化できた時間で保育
の質の確保・向上に取り組むことができる環境を整備することが重要。
14
費比率等の見える化に取り組み、保育士等の処遇の改善を進める必要。
○ 働きやすい職場環境づくり、新規資格取得と就労の促進、離職者の再就職・職場復帰の促進、保
育の現場・職業の魅力発信の取組について、これまでも「保育人材の確保に向けた総合的な対策」
として総合的に取り組んできたところ、更に取組を強化していく必要。
○ 保育士の登録者数と就労者数に差がある中で、潜在保育士の再就職支援を進める必要。保育士・
保育所支援センターの法定化を行い、保育士確保のための拠点として位置づけ、関係機関が連携
協力して保育士の確保のための支援を行う体制整備を促進することとしているところ(令和7年
10 月1日施行)
。潜在保育士の掘り起こしを中心に、
介護同様、
公的な機関等が担う役割は大きい。
保育士・保育所支援センターの法定化を契機として、更なる機能強化を図るとともに、プラッ
トフォームの充実の中で、例えば、ハローワークや福祉人材センターと連携した取組を行うなど、
福祉人材の確保という大きな枠組みの中で公的な機関の連携を更に強化していく必要。
○ 保育人材の確保が課題となる中で、タスクシフト/シェアによる職場環境改善も必要であり、業
務の切り出しを行い、保育所等が専門人材以外の人材を受け入れ、業務効率化を図ることも重要。
専門性を備えた保育士が行うべき業務とそれ以外の業務の整理を行った上で、専門人材以外の者
の更なる活用により、保育士が直接支援に携わる時間を増やすことを検討していく必要。
○ 社会全体の働き方が多様化する中で、保育所等においても柔軟な働き方をしていただけるよう、
職場環境改善が重要。保育士がそれぞれの家庭状況等に応じ、多様な働き方を選択することがで
きるよう、柔軟に働ける環境の整備に向けた検討を進めていくべき。
○ 保育士の配置が原則とされている中、テクノロジーや保育士のみならず幅広い人材の活用を含
め、保育所等の在るべき体制について改めて検討することも必要。
○ 保育現場における ICT 導入は限定的で、手書きやアナログの業務が存続しているため、給付・
監査の事務で多くの書類作成が必要になるなど事務負担が課題。自治体でも、多くの書類管理や
システムへの入力作業、煩雑な審査による担当者の事務負担が課題。また、保護者にとっては、保
育所の入所に必要な情報収集に手間と時間が掛かるなど、保活の手続に係る負担が大きいことも
課題。
○ 保育人材の確保が課題となる中で、テクノロジー活用等による生産性向上により、業務効率化
を進めていく必要。また、テクノロジーの活用による業務改善を進め、効率化できた時間で保育
の質の確保・向上に取り組むことができる環境を整備することが重要。
14