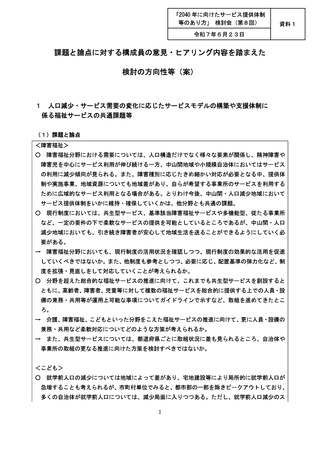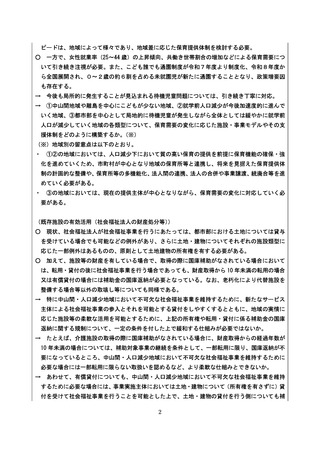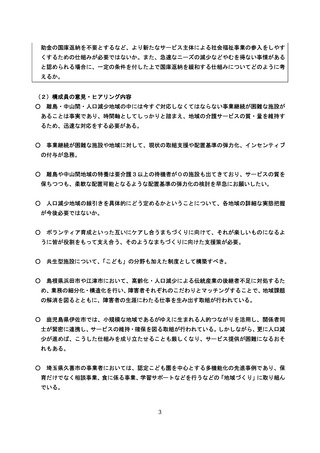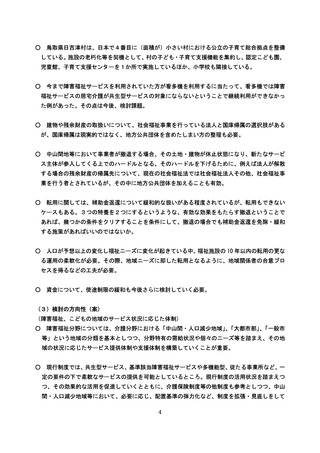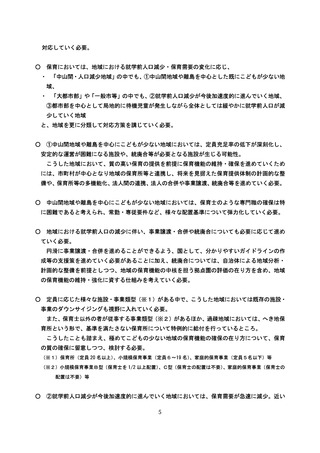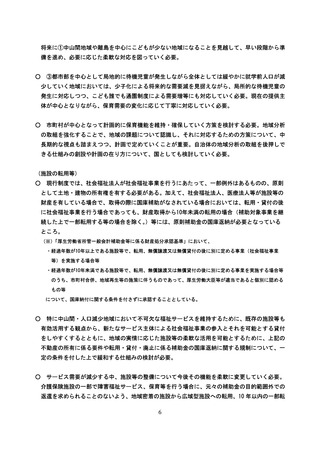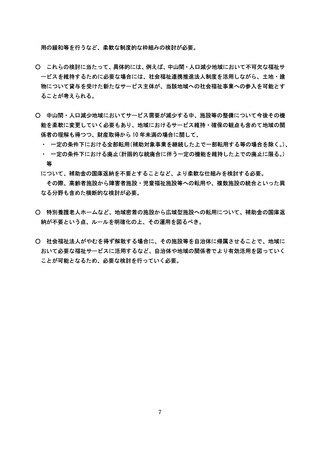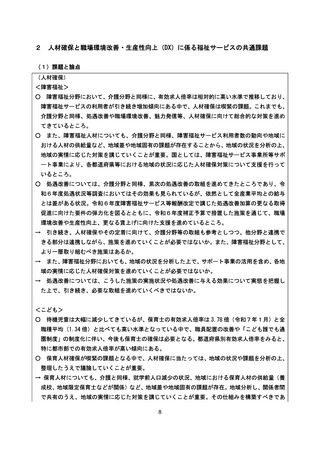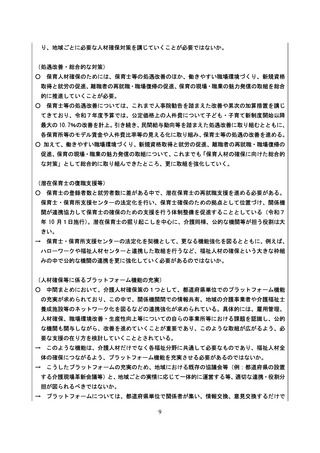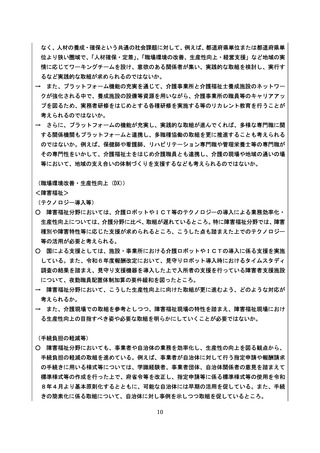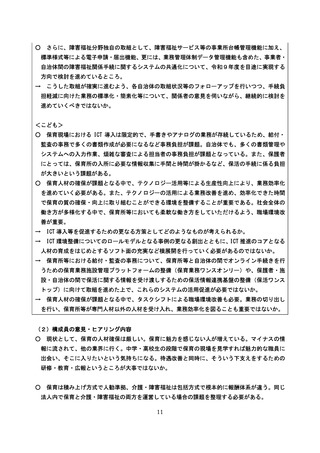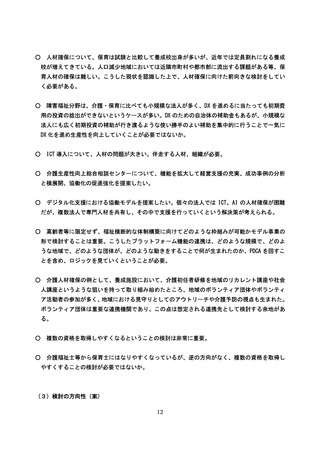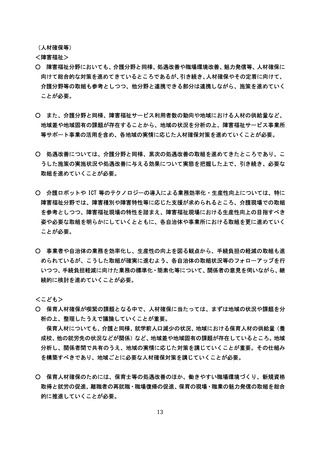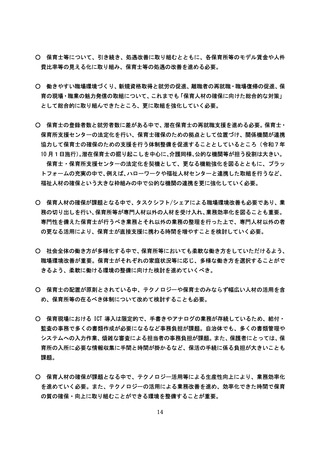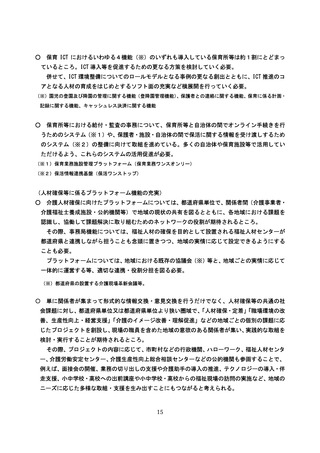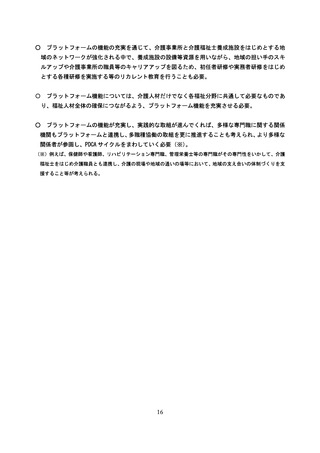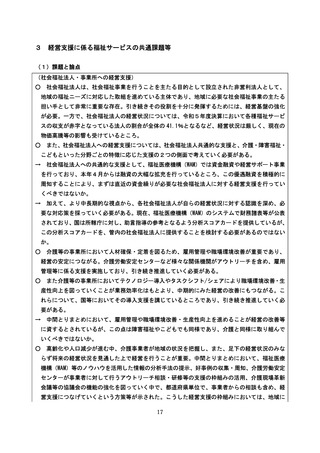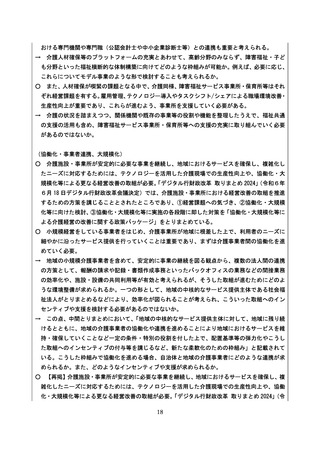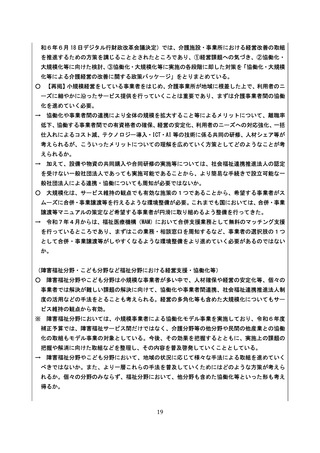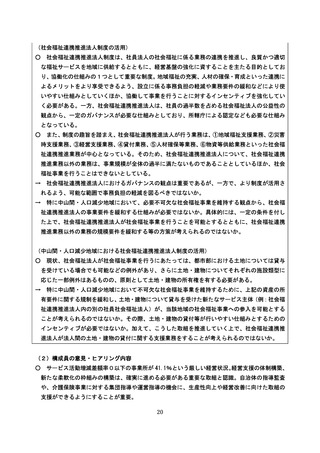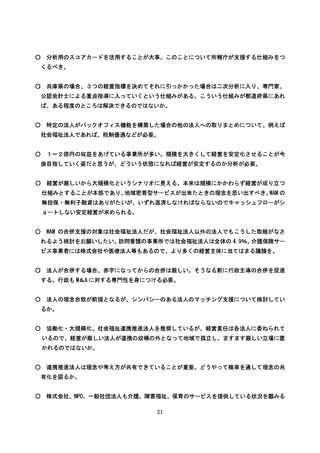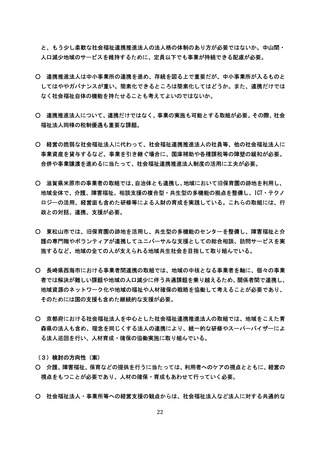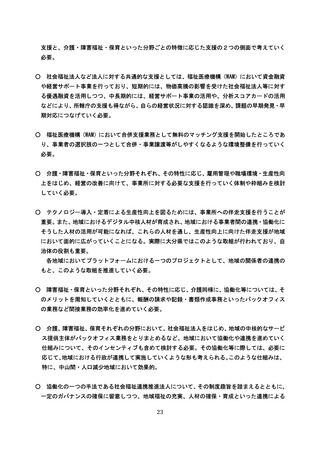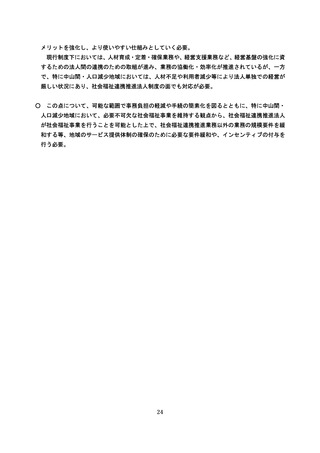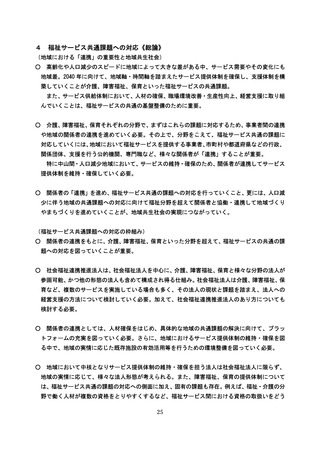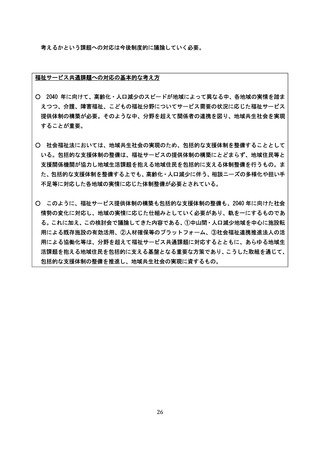よむ、つかう、まなぶ。
資料1 課題と論点に対する構成員の意見・ヒアリング内容を踏 まえた検討の方向性等(案) (19 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59051.html |
| 出典情報 | 「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会(第8回 6/23)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
和6年6月 18 日デジタル行財政改革会議決定)では、介護施設・事業所における経営改善の取組
を推進するための方策を講じることとされたところであり、①経営課題への気づき、②協働化・
大規模化等に向けた検討、③協働化・大規模化等に実施の各段階に即した対策を「協働化・大規模
化等による介護経営の改善に関する政策パッケージ」をとりまとめている。
○ 【再掲】小規模経営をしている事業者をはじめ、介護事業所が地域に根差した上で、利用者のニ
ーズに細やかに沿ったサービス提供を行っていくことは重要であり、まずは介護事業者間の協働
化を進めていく必要。
→ 協働化や事業者間の連携により全体の規模を拡大すること等によるメリットについて、離職率
低下、協働する事業者間での有資格者の確保、経営の安定化、利用者のニーズへの対応強化、一括
仕入れによるコスト減、テクノロジー導入・ICT・AI 等の技術に係る共同の研修、人材シェア等が
考えられるが、こういったメリットについての理解を広めていく方策としてどのようなことが考
えられるか。
→ 加えて、設備や物資の共同購入や合同研修の実施等については、社会福祉連携推進法人の認定
を受けない一般社団法人であっても実施可能であることから、より簡易な手続きで設立可能な一
般社団法人による連携・協働についても周知が必要ではないか。
○ 大規模化は、サービス維持の観点でも有効な施策の1つであることから、希望する事業者がス
ムーズに合併・事業譲渡等を行えるような環境整備が必要。これまでも国においては、合併・事業
譲渡等マニュアルの策定など希望する事業者が円滑に取り組めるよう整備を行ってきた。
→ 令和7年4月からは、福祉医療機構(WAM)において合併支援業務として無料のマッチング支援
を行っているところであり、まずはこの業務・相談窓口を周知するなど、事業者の選択肢の1つ
として合併・事業譲渡等がしやすくなるような環境整備をより進めていく必要があるのではない
か。
(障害福祉分野・こども分野など福祉分野における経営支援・協働化等)
○ 障害福祉分野やこども分野は小規模な事業者が多い中で、人材確保や経営の安定化等、個々の
事業者では解決が難しい課題の解決に向けて、協働化や事業者間連携、社会福祉連携推進法人制
度の活用などの手法をとることも考えられる。経営の多角化等も含めた大規模化についてもサー
ビス維持の観点から有効。
※ 障害福祉分野においては、小規模事業者による協働化モデル事業を実施しており、令和6年度
補正予算では、障害福祉サービス間だけではなく、介護分野等の他分野や民間の他産業との協働
化の取組もモデル事業の対象としている。今後、その効果を把握するとともに、実施上の課題の
把握や解消に向けた取組などを整理し、その内容を普及啓発していくこととしている。
→ 障害福祉分野やこども分野において、地域の状況に応じて様々な手法による取組を進めていく
べきではないか。また、より一層これらの手法を普及していくためにはどのような方策が考えら
れるか。個々の分野のみならず、福祉分野において、他分野も含めた協働化等といった形も考え
得るか。
19
を推進するための方策を講じることとされたところであり、①経営課題への気づき、②協働化・
大規模化等に向けた検討、③協働化・大規模化等に実施の各段階に即した対策を「協働化・大規模
化等による介護経営の改善に関する政策パッケージ」をとりまとめている。
○ 【再掲】小規模経営をしている事業者をはじめ、介護事業所が地域に根差した上で、利用者のニ
ーズに細やかに沿ったサービス提供を行っていくことは重要であり、まずは介護事業者間の協働
化を進めていく必要。
→ 協働化や事業者間の連携により全体の規模を拡大すること等によるメリットについて、離職率
低下、協働する事業者間での有資格者の確保、経営の安定化、利用者のニーズへの対応強化、一括
仕入れによるコスト減、テクノロジー導入・ICT・AI 等の技術に係る共同の研修、人材シェア等が
考えられるが、こういったメリットについての理解を広めていく方策としてどのようなことが考
えられるか。
→ 加えて、設備や物資の共同購入や合同研修の実施等については、社会福祉連携推進法人の認定
を受けない一般社団法人であっても実施可能であることから、より簡易な手続きで設立可能な一
般社団法人による連携・協働についても周知が必要ではないか。
○ 大規模化は、サービス維持の観点でも有効な施策の1つであることから、希望する事業者がス
ムーズに合併・事業譲渡等を行えるような環境整備が必要。これまでも国においては、合併・事業
譲渡等マニュアルの策定など希望する事業者が円滑に取り組めるよう整備を行ってきた。
→ 令和7年4月からは、福祉医療機構(WAM)において合併支援業務として無料のマッチング支援
を行っているところであり、まずはこの業務・相談窓口を周知するなど、事業者の選択肢の1つ
として合併・事業譲渡等がしやすくなるような環境整備をより進めていく必要があるのではない
か。
(障害福祉分野・こども分野など福祉分野における経営支援・協働化等)
○ 障害福祉分野やこども分野は小規模な事業者が多い中で、人材確保や経営の安定化等、個々の
事業者では解決が難しい課題の解決に向けて、協働化や事業者間連携、社会福祉連携推進法人制
度の活用などの手法をとることも考えられる。経営の多角化等も含めた大規模化についてもサー
ビス維持の観点から有効。
※ 障害福祉分野においては、小規模事業者による協働化モデル事業を実施しており、令和6年度
補正予算では、障害福祉サービス間だけではなく、介護分野等の他分野や民間の他産業との協働
化の取組もモデル事業の対象としている。今後、その効果を把握するとともに、実施上の課題の
把握や解消に向けた取組などを整理し、その内容を普及啓発していくこととしている。
→ 障害福祉分野やこども分野において、地域の状況に応じて様々な手法による取組を進めていく
べきではないか。また、より一層これらの手法を普及していくためにはどのような方策が考えら
れるか。個々の分野のみならず、福祉分野において、他分野も含めた協働化等といった形も考え
得るか。
19