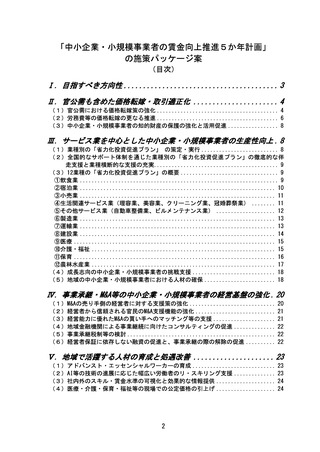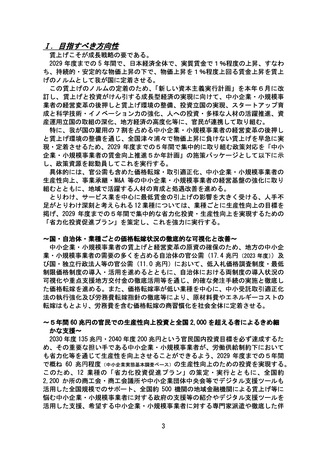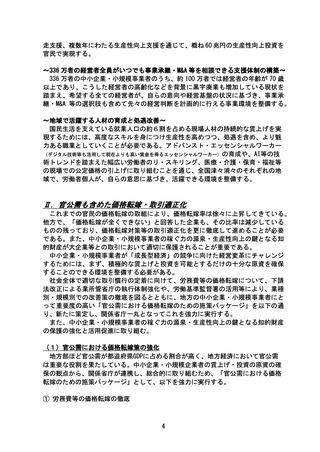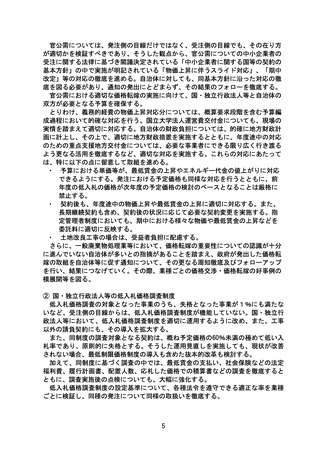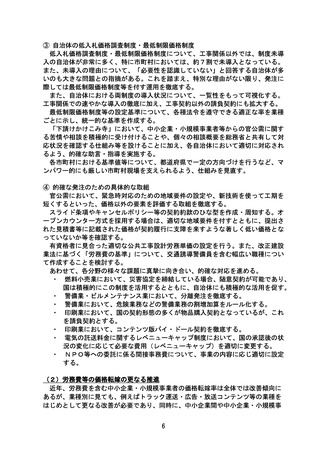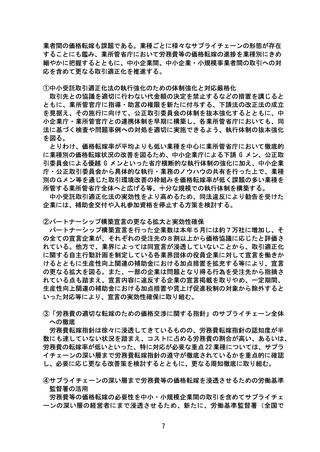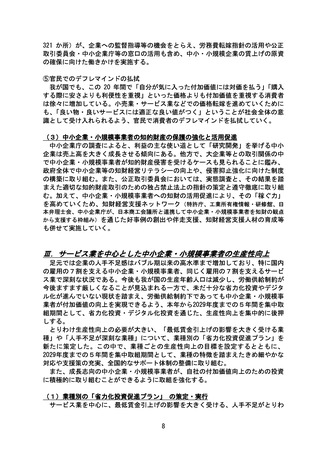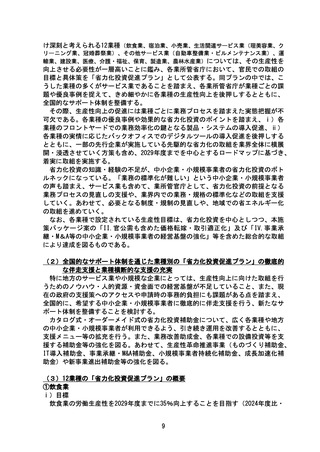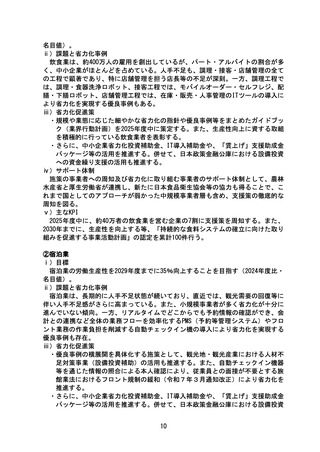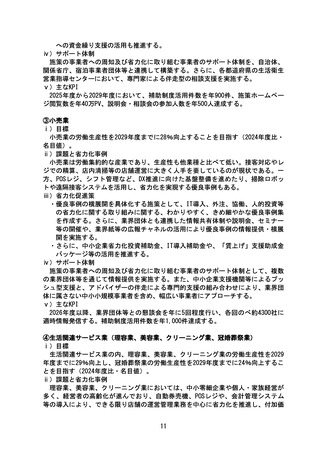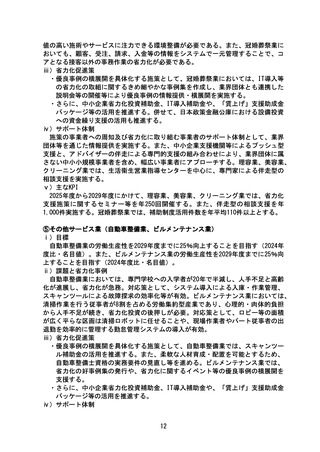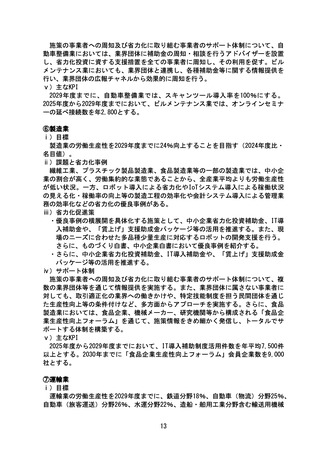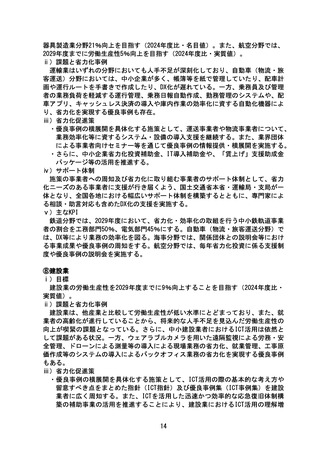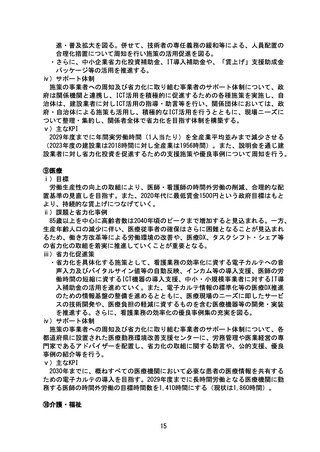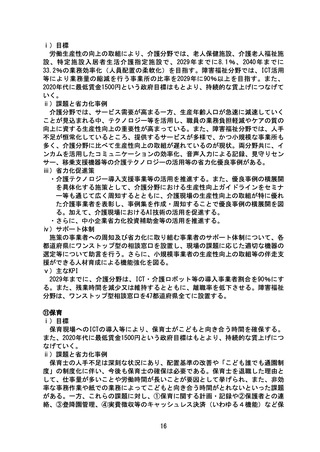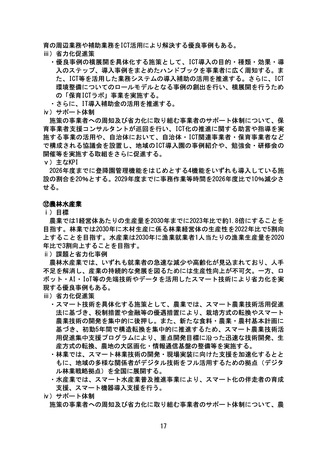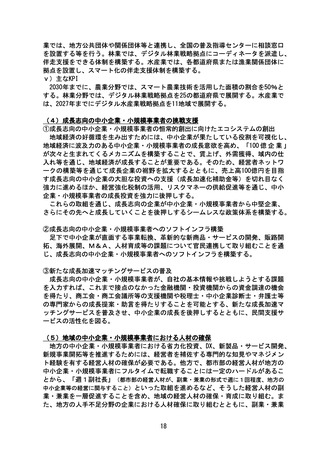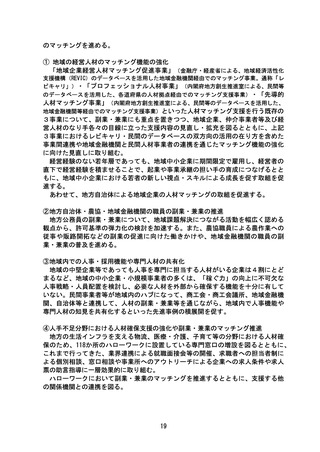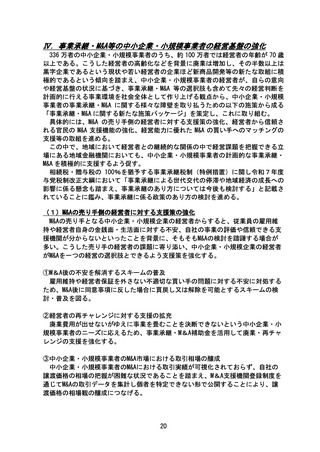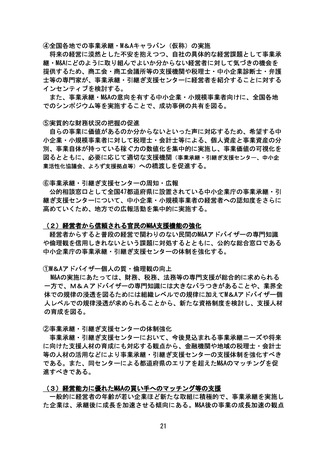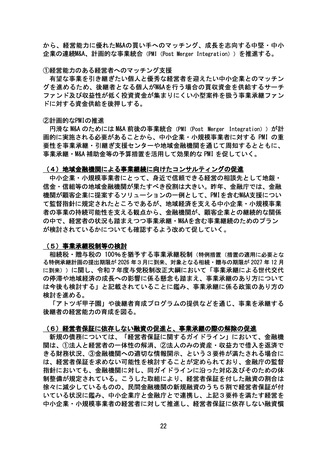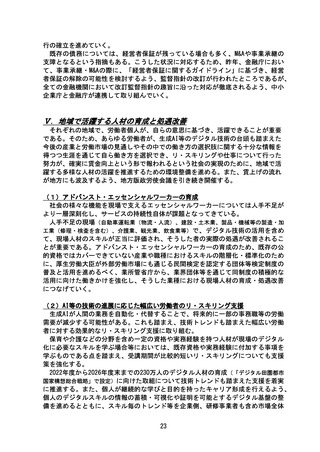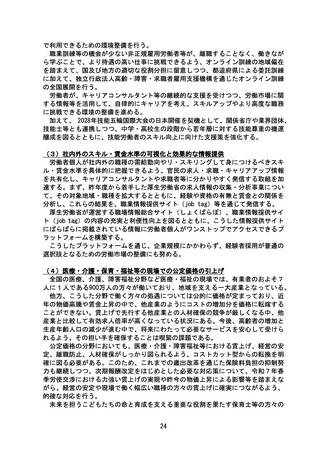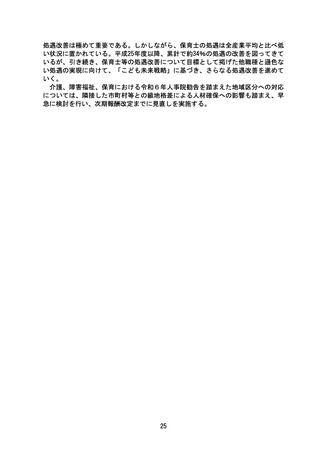よむ、つかう、まなぶ。
資料1「中小企業・小規模事業者の賃金向上推進5か年計画」の施策パッケージ案 (23 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/kaigi/dai34/gijisidai.html |
| 出典情報 | 新しい資本主義実現会議(第34回 5/14)《内閣官房》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
行の確立を進めていく。
既存の債務については、経営者保証が残っている場合も多く、M&Aや事業承継の
支障となるという指摘もある。こうした状況に対応するため、昨年、金融庁におい
て、事業承継・M&Aの際に、「経営者保証に関するガイドライン」に基づき、経営
者保証の解除の可能性を検討するよう、監督指針の改訂が行われたところであるが、
全ての金融機関において改訂監督指針の趣旨に沿った対応が徹底されるよう、中小
企業庁と金融庁が連携して取り組んでいく。
Ⅴ.地域で活躍する人材の育成と処遇改善
それぞれの地域で、労働者個人が、自らの意思に基づき、活躍できることが重要
である。そのため、あらゆる労働者が、生成AI等のデジタル技術の台頭も踏まえた
今後の産業と労働市場の見通しやその中での働き方の選択肢に関する十分な情報を
得つつ生涯を通じて自ら働き方を選択でき、リ・スキリングや仕事について行った
努力が、確実に賃金向上という形で報われるという社会の実現のために、地域で活
躍する多様な人材の活躍を推進するための環境整備を進める。また、賃上げの流れ
が地方にも波及するよう、地方版政労使会議を引き続き開催する。
(1)アドバンスト・エッセンシャルワーカーの育成
社会の様々な機能を現場で支えるエッセンシャルワーカーについては人手不足が
より一層深刻化し、サービスの持続性自体が課題となってきている。
人手不足の現場(自動車運転業(物流・人流)、建設・土木業、製品・機械等の製造・加
工業(修理・検査を含む)、介護業、観光業、飲食業等) で、デジタル技術の活用を含め
て、現場人材のスキルが正当に評価され、そうした者の実際の処遇が改善されるこ
とが重要である。アドバンスト・エッセンシャルワーカーの育成のため、既存の公
的資格ではカバーできていない産業や職種におけるスキルの階層化・標準化のため
に、厚生労働大臣が外部労働市場にも通じる民間検定を認定する団体等検定制度の
普及と活用を進めるべく、業所管省庁から、業界団体等を通じて同制度の積極的な
活用に向けた働きかけを強化し、そうした業種における現場人材の育成・処遇改善
につなげていく。
(2)AI等の技術の進展に応じた幅広い労働者のリ・スキリング支援
生成AIが人間の業務を自動化・代替することで、将来的に一部の事務職等の労働
需要が減少する可能性がある。これも踏まえ、技術トレンドも踏まえた幅広い労働
者に対する効果的なリ・スキリング支援に取り組む。
保育や介護などの分野を含め一定の資格や実務経験を持つ人材が現場のデジタル
化に必要なスキルを学ぶ場合等においては、既存資格や実務経験に付加する事項を
学ぶものである点を踏まえ、受講期間が比較的短いリ・スキリングについても支援
策を強化する。
2022年度から2026年度末までの230万人のデジタル人材の育成(「デジタル田園都市
国家構想総合戦略」で設定)に向けた取組について技術トレンドも踏まえた支援を着実
に推進する。また、個人が継続的な学びと目的を持ったキャリア形成を行えるよう、
個人のデジタルスキルの情報の蓄積・可視化や証明を可能とするデジタル基盤の整
備を進めるとともに、スキル毎のトレンド等を企業側、研修事業者も含め市場全体
23
既存の債務については、経営者保証が残っている場合も多く、M&Aや事業承継の
支障となるという指摘もある。こうした状況に対応するため、昨年、金融庁におい
て、事業承継・M&Aの際に、「経営者保証に関するガイドライン」に基づき、経営
者保証の解除の可能性を検討するよう、監督指針の改訂が行われたところであるが、
全ての金融機関において改訂監督指針の趣旨に沿った対応が徹底されるよう、中小
企業庁と金融庁が連携して取り組んでいく。
Ⅴ.地域で活躍する人材の育成と処遇改善
それぞれの地域で、労働者個人が、自らの意思に基づき、活躍できることが重要
である。そのため、あらゆる労働者が、生成AI等のデジタル技術の台頭も踏まえた
今後の産業と労働市場の見通しやその中での働き方の選択肢に関する十分な情報を
得つつ生涯を通じて自ら働き方を選択でき、リ・スキリングや仕事について行った
努力が、確実に賃金向上という形で報われるという社会の実現のために、地域で活
躍する多様な人材の活躍を推進するための環境整備を進める。また、賃上げの流れ
が地方にも波及するよう、地方版政労使会議を引き続き開催する。
(1)アドバンスト・エッセンシャルワーカーの育成
社会の様々な機能を現場で支えるエッセンシャルワーカーについては人手不足が
より一層深刻化し、サービスの持続性自体が課題となってきている。
人手不足の現場(自動車運転業(物流・人流)、建設・土木業、製品・機械等の製造・加
工業(修理・検査を含む)、介護業、観光業、飲食業等) で、デジタル技術の活用を含め
て、現場人材のスキルが正当に評価され、そうした者の実際の処遇が改善されるこ
とが重要である。アドバンスト・エッセンシャルワーカーの育成のため、既存の公
的資格ではカバーできていない産業や職種におけるスキルの階層化・標準化のため
に、厚生労働大臣が外部労働市場にも通じる民間検定を認定する団体等検定制度の
普及と活用を進めるべく、業所管省庁から、業界団体等を通じて同制度の積極的な
活用に向けた働きかけを強化し、そうした業種における現場人材の育成・処遇改善
につなげていく。
(2)AI等の技術の進展に応じた幅広い労働者のリ・スキリング支援
生成AIが人間の業務を自動化・代替することで、将来的に一部の事務職等の労働
需要が減少する可能性がある。これも踏まえ、技術トレンドも踏まえた幅広い労働
者に対する効果的なリ・スキリング支援に取り組む。
保育や介護などの分野を含め一定の資格や実務経験を持つ人材が現場のデジタル
化に必要なスキルを学ぶ場合等においては、既存資格や実務経験に付加する事項を
学ぶものである点を踏まえ、受講期間が比較的短いリ・スキリングについても支援
策を強化する。
2022年度から2026年度末までの230万人のデジタル人材の育成(「デジタル田園都市
国家構想総合戦略」で設定)に向けた取組について技術トレンドも踏まえた支援を着実
に推進する。また、個人が継続的な学びと目的を持ったキャリア形成を行えるよう、
個人のデジタルスキルの情報の蓄積・可視化や証明を可能とするデジタル基盤の整
備を進めるとともに、スキル毎のトレンド等を企業側、研修事業者も含め市場全体
23