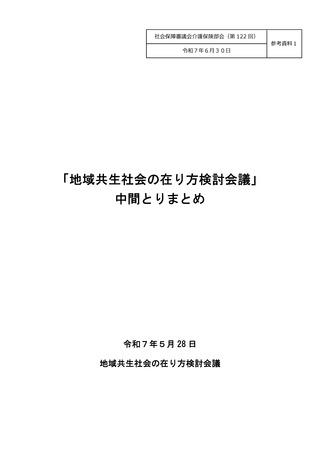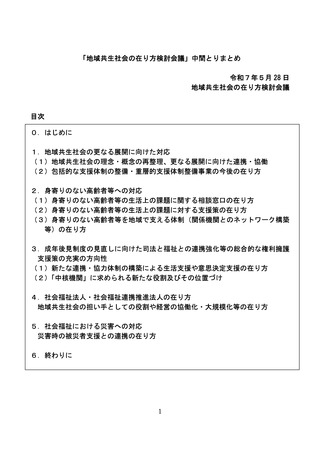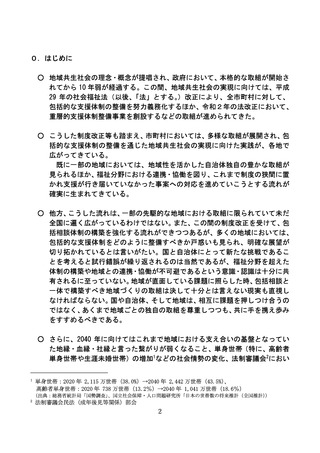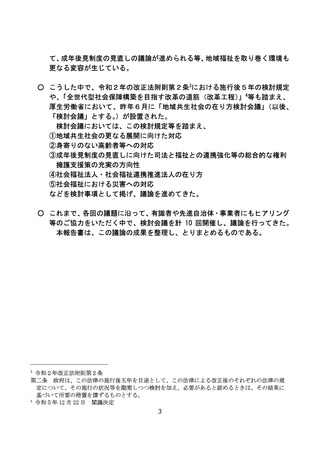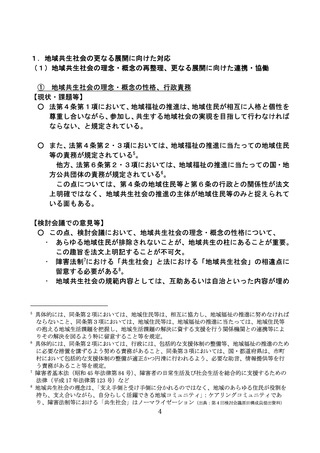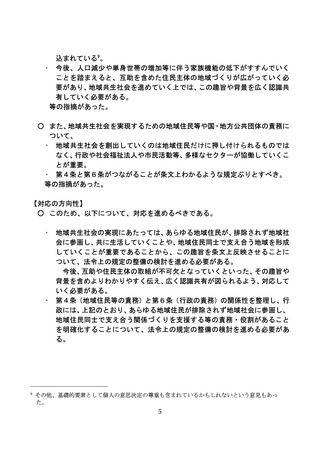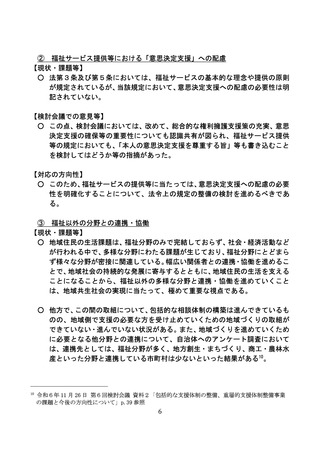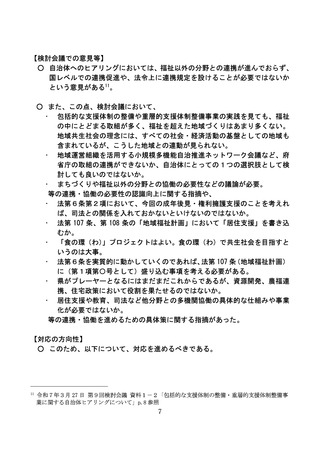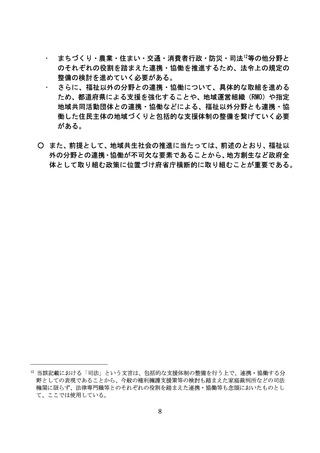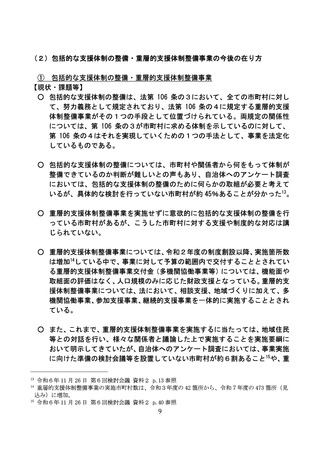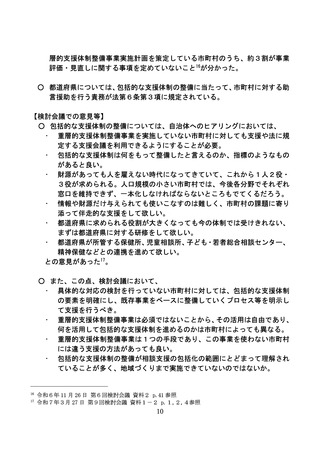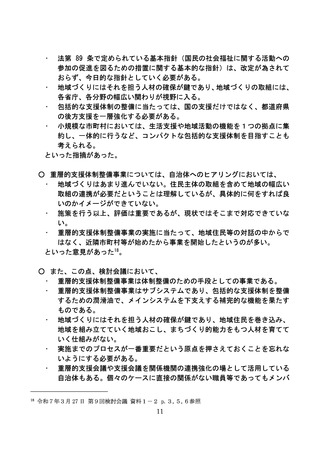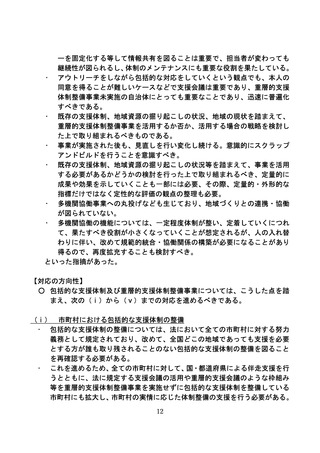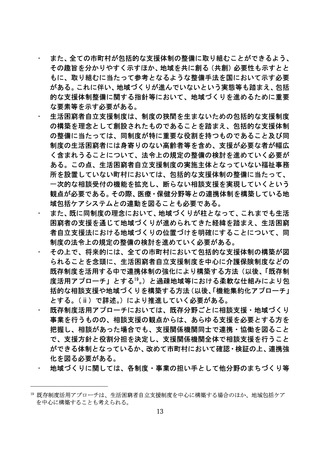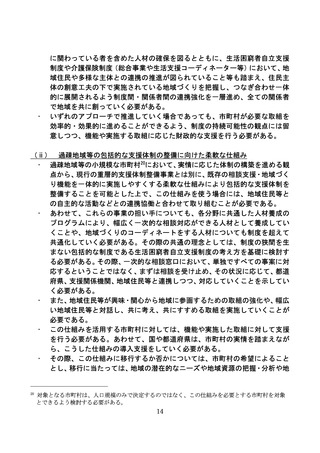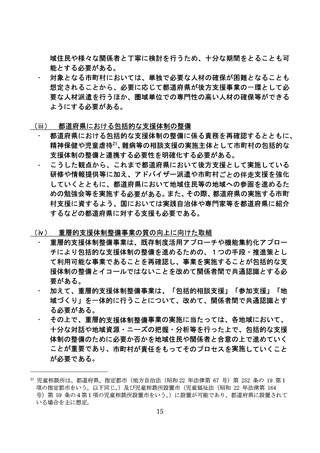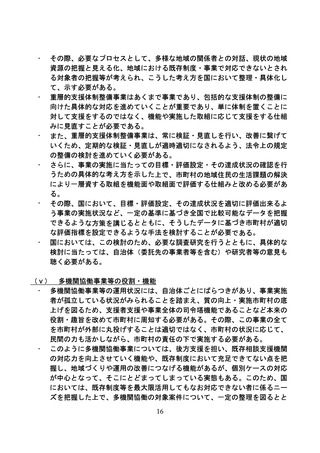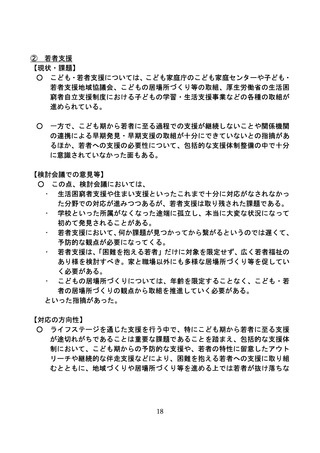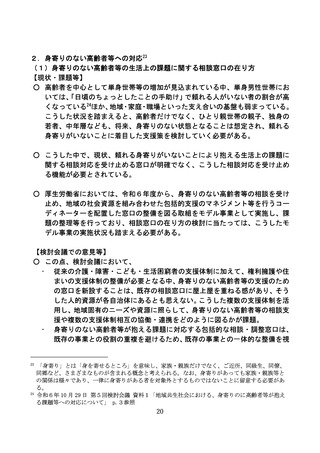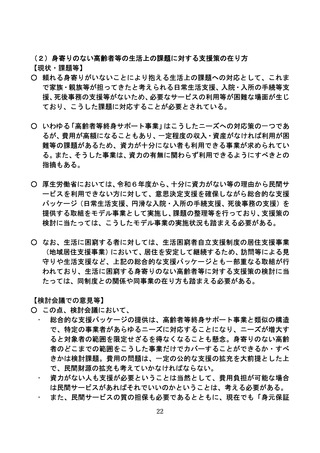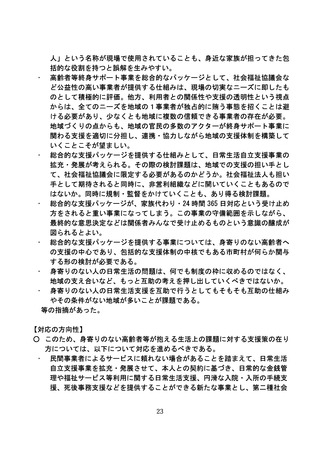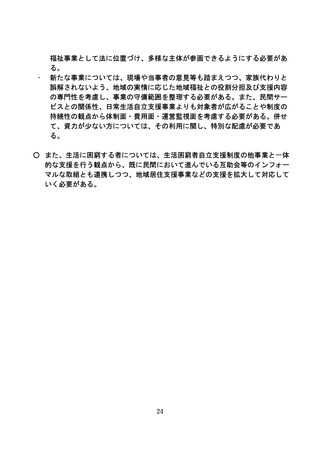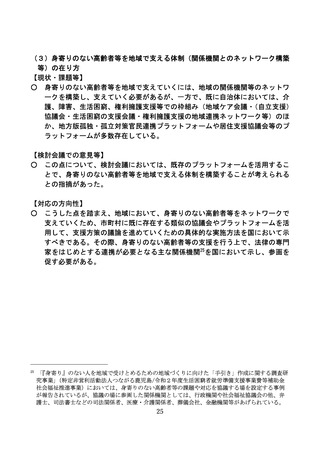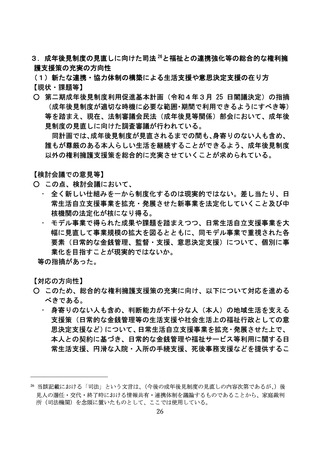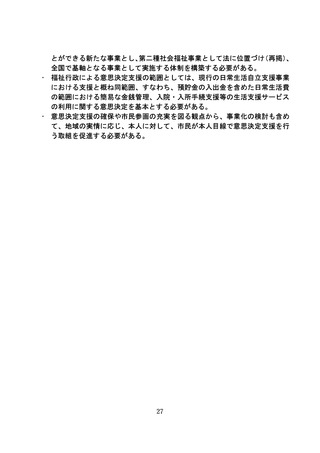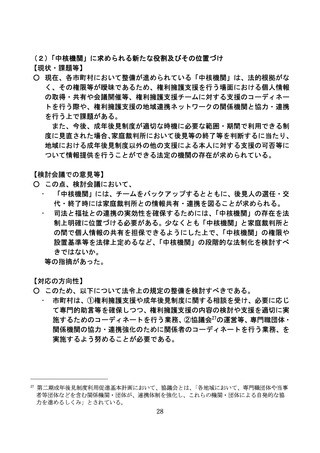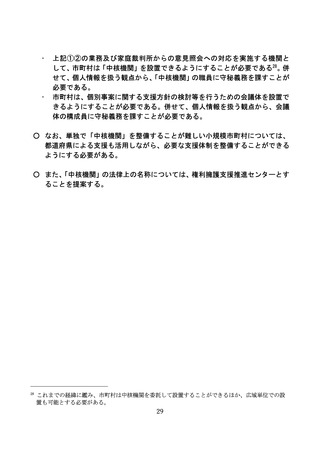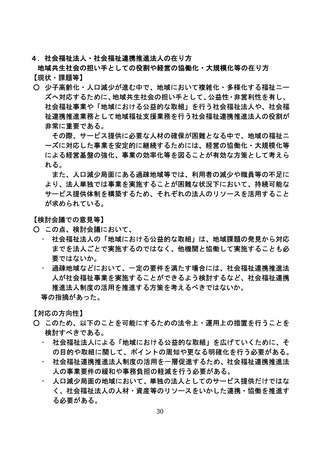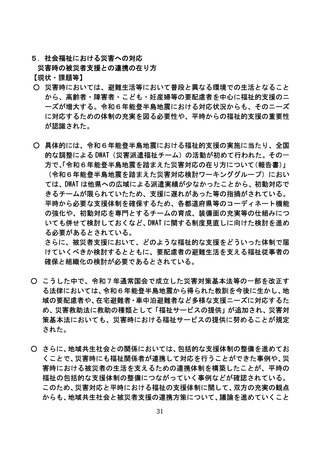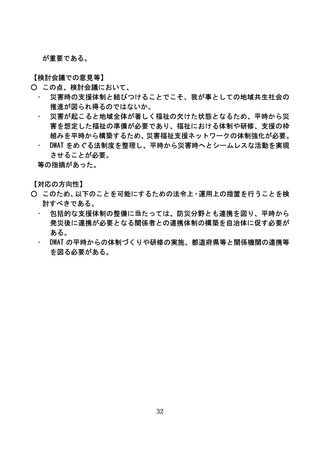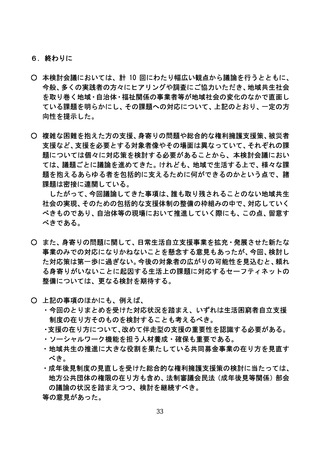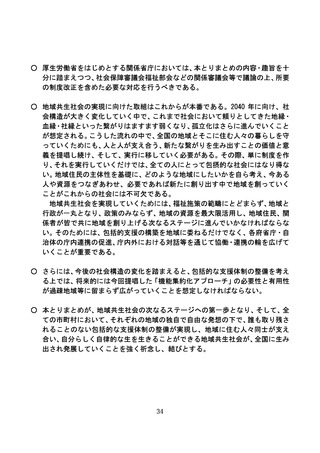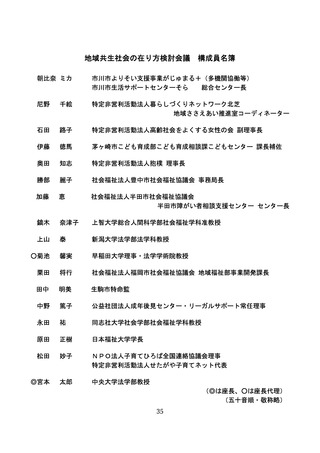よむ、つかう、まなぶ。
参考資料1 「地域共生社会の在り方検討会議」 中間とりまとめ (3 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59213.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第122回 6/30)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
0.はじめに
○ 地域共生社会の理念・概念が提唱され、政府において、本格的な取組が開始さ
れてから 10 年弱が経過する。この間、地域共生社会の実現に向けては、平成
29 年の社会福祉法(以後、「法」とする。)改正により、全市町村に対して、
包括的な支援体制の整備を努力義務化するほか、令和2年の法改正において、
重層的支援体制整備事業を創設するなどの取組が進められてきた。
○ こうした制度改正等も踏まえ、市町村においては、多様な取組が展開され、包
括的な支援体制の整備を通じた地域共生社会の実現に向けた実践が、各地で
広がってきている。
既に一部の地域においては、地域性を活かした自治体独自の豊かな取組が
見られるほか、福祉分野における連携・協働を図り、これまで制度の狭間に置
かれ支援が行き届いていなかった事案への対応を進めていこうとする流れが
確実に生まれてきている。
○ 他方、こうした流れは、一部の先駆的な地域における取組に限られていて未だ
全国に遍く広がっているわけではない。また、この間の制度改正を受けて、包
括相談体制の構築を強化する流れができつつあるが、多くの地域においては、
包括的な支援体制をどのように整備すべきか戸惑いも見られ、明確な展望が
切り拓かれているとは言いがたい。国と自治体にとって新たな挑戦であるこ
とを考えると試行錯誤が繰り返されるのは当然であるが、福祉分野を超えた
体制の構築や地域との連携・協働が不可避であるという意識・認識は十分に共
有されるに至っていない。地域が直面している課題に照らした時、包括相談と
一体で構築すべき地域づくりの取組は決して十分とは言えない現実も直視し
なければならない。国や自治体、そして地域は、相互に課題を押しつけ合うの
ではなく、あくまで地域ごとの独自の取組を尊重しつつも、共に手を携え歩み
をすすめるべきである。
○ さらに、2040 年に向けてはこれまで地域における支え合いの基盤となってい
た地縁・血縁・社縁と言った繋がりが弱くなること、単身世帯(特に、高齢者
単身世帯や生涯未婚世帯)の増加1などの社会情勢の変化、法制審議会2におい
1
単身世帯:2020 年 2,115 万世帯(38.0%)→2040 年 2,442 万世帯(43.5%)
、
高齢者単身世帯:2020 年 738 万世帯(13.2%)→2040 年 1,041 万世帯(18.6%)
(出典:総務省統計局「国勢調査」
、国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計(全国推計)
)
2
法制審議会民法(成年後見等関係)部会
2
○ 地域共生社会の理念・概念が提唱され、政府において、本格的な取組が開始さ
れてから 10 年弱が経過する。この間、地域共生社会の実現に向けては、平成
29 年の社会福祉法(以後、「法」とする。)改正により、全市町村に対して、
包括的な支援体制の整備を努力義務化するほか、令和2年の法改正において、
重層的支援体制整備事業を創設するなどの取組が進められてきた。
○ こうした制度改正等も踏まえ、市町村においては、多様な取組が展開され、包
括的な支援体制の整備を通じた地域共生社会の実現に向けた実践が、各地で
広がってきている。
既に一部の地域においては、地域性を活かした自治体独自の豊かな取組が
見られるほか、福祉分野における連携・協働を図り、これまで制度の狭間に置
かれ支援が行き届いていなかった事案への対応を進めていこうとする流れが
確実に生まれてきている。
○ 他方、こうした流れは、一部の先駆的な地域における取組に限られていて未だ
全国に遍く広がっているわけではない。また、この間の制度改正を受けて、包
括相談体制の構築を強化する流れができつつあるが、多くの地域においては、
包括的な支援体制をどのように整備すべきか戸惑いも見られ、明確な展望が
切り拓かれているとは言いがたい。国と自治体にとって新たな挑戦であるこ
とを考えると試行錯誤が繰り返されるのは当然であるが、福祉分野を超えた
体制の構築や地域との連携・協働が不可避であるという意識・認識は十分に共
有されるに至っていない。地域が直面している課題に照らした時、包括相談と
一体で構築すべき地域づくりの取組は決して十分とは言えない現実も直視し
なければならない。国や自治体、そして地域は、相互に課題を押しつけ合うの
ではなく、あくまで地域ごとの独自の取組を尊重しつつも、共に手を携え歩み
をすすめるべきである。
○ さらに、2040 年に向けてはこれまで地域における支え合いの基盤となってい
た地縁・血縁・社縁と言った繋がりが弱くなること、単身世帯(特に、高齢者
単身世帯や生涯未婚世帯)の増加1などの社会情勢の変化、法制審議会2におい
1
単身世帯:2020 年 2,115 万世帯(38.0%)→2040 年 2,442 万世帯(43.5%)
、
高齢者単身世帯:2020 年 738 万世帯(13.2%)→2040 年 1,041 万世帯(18.6%)
(出典:総務省統計局「国勢調査」
、国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計(全国推計)
)
2
法制審議会民法(成年後見等関係)部会
2