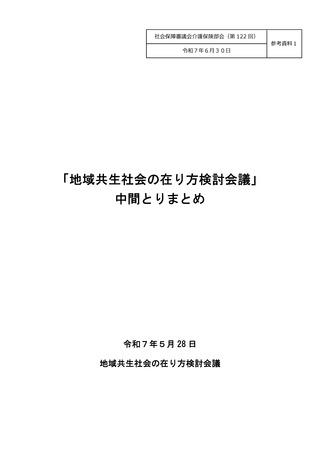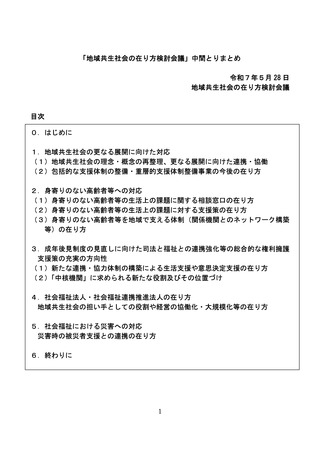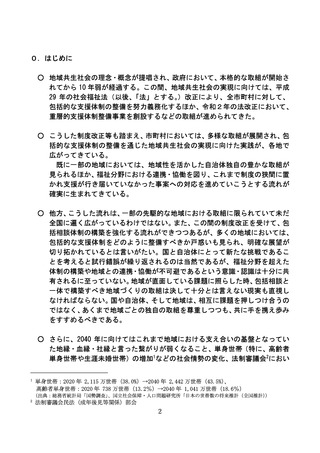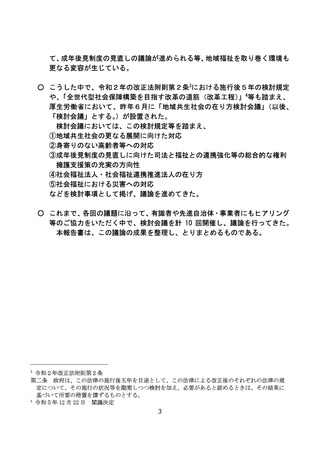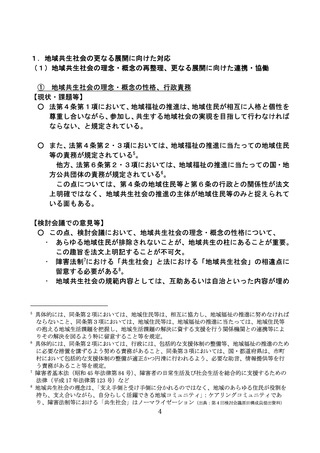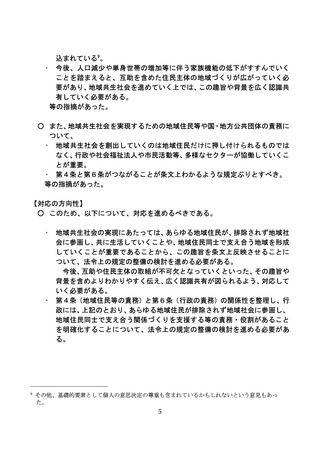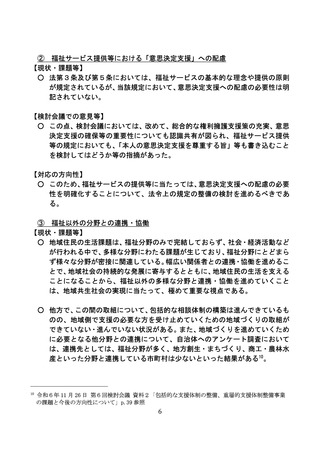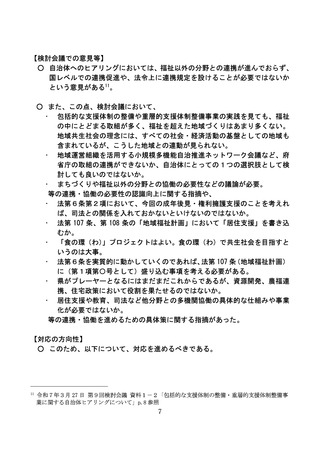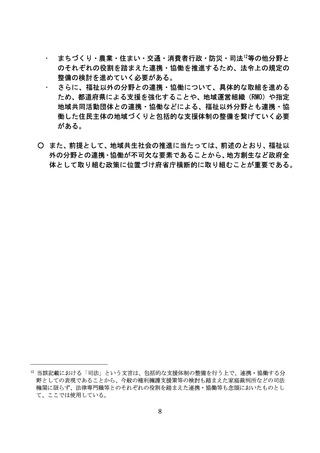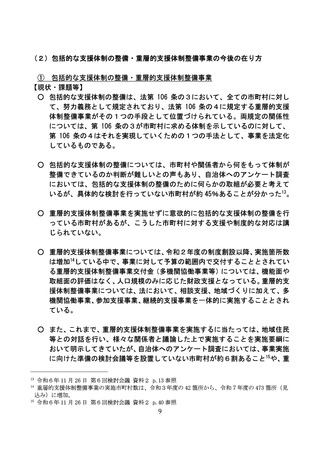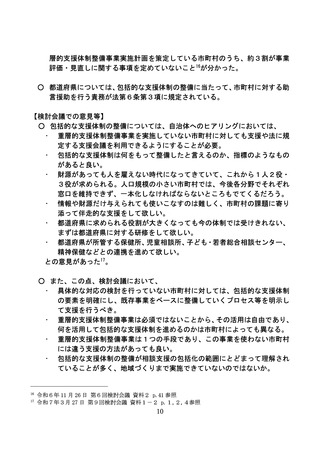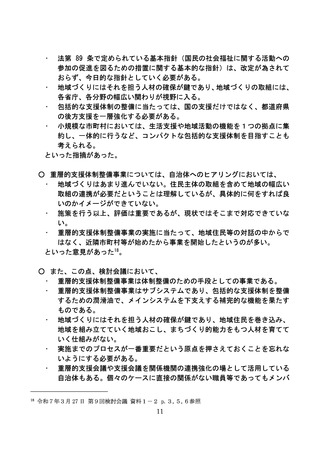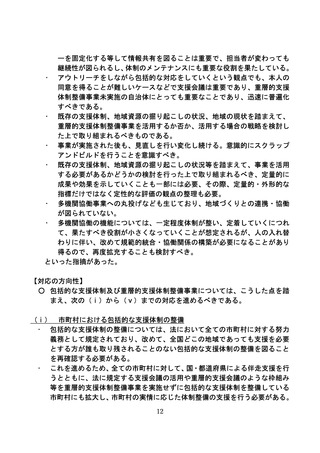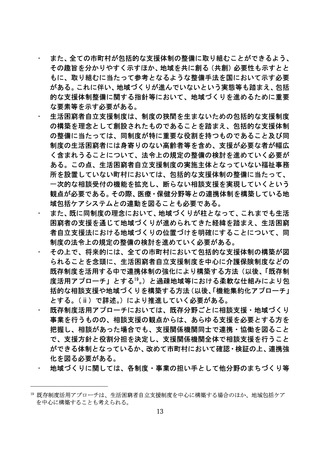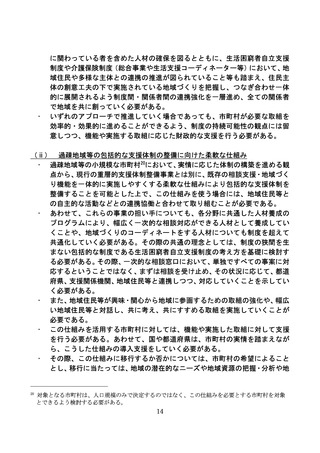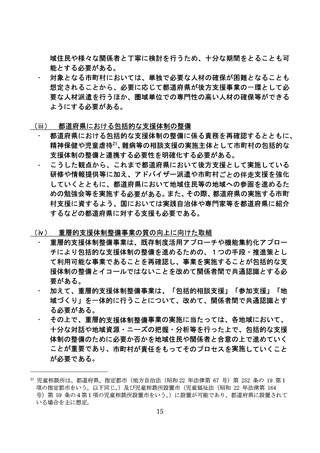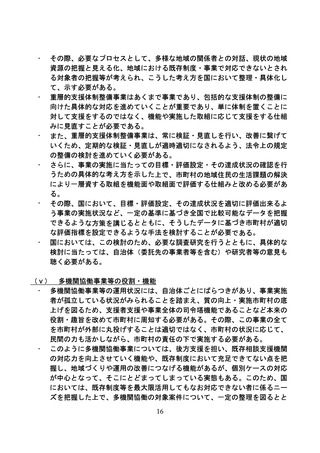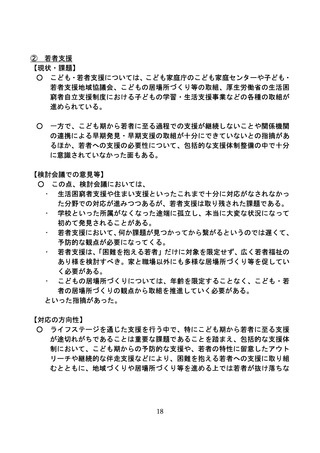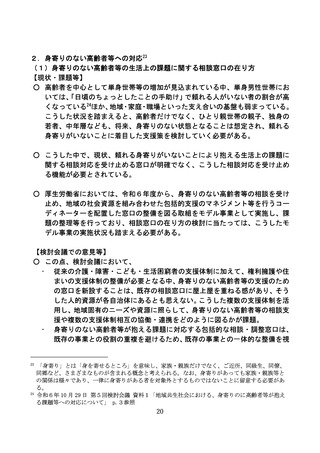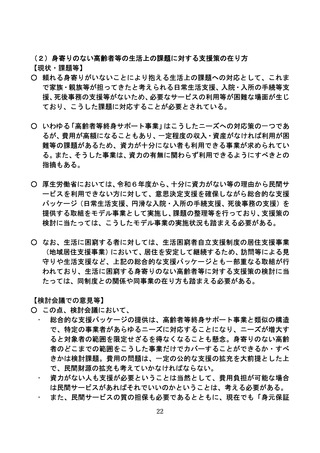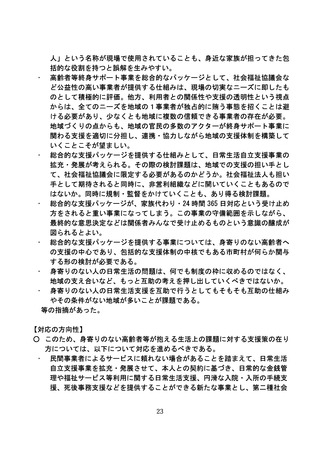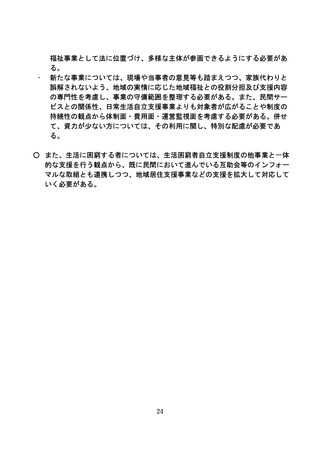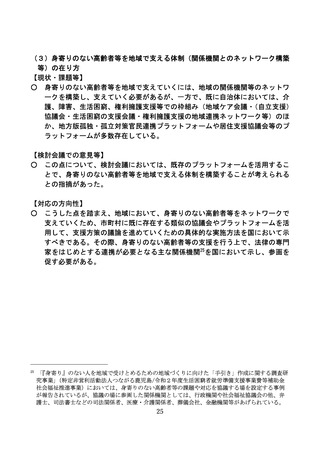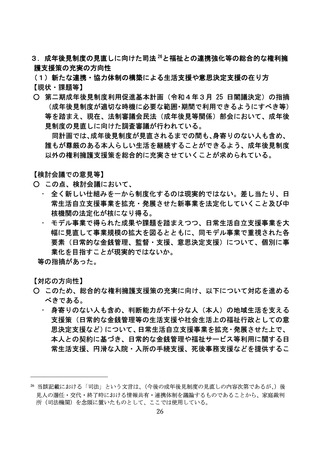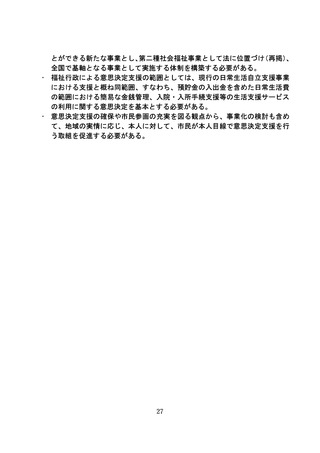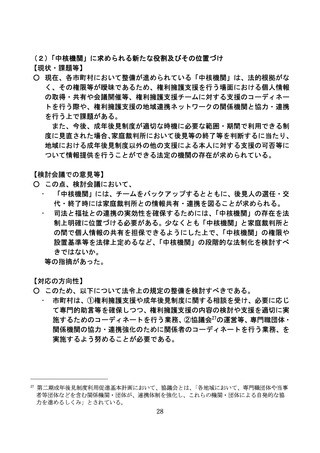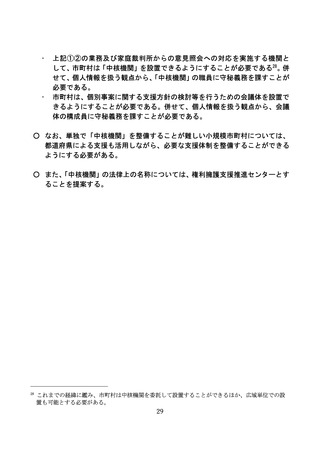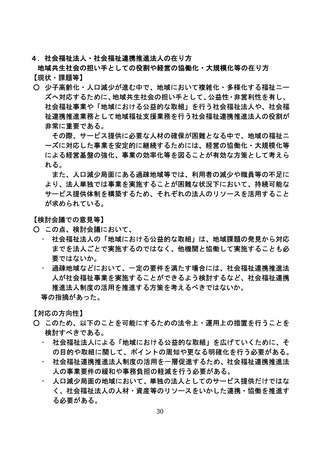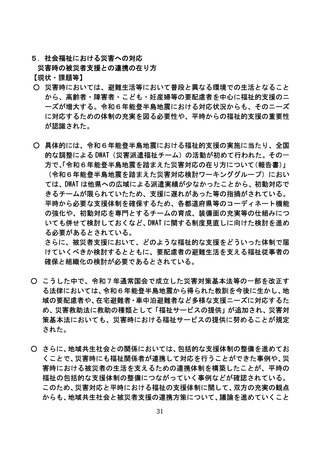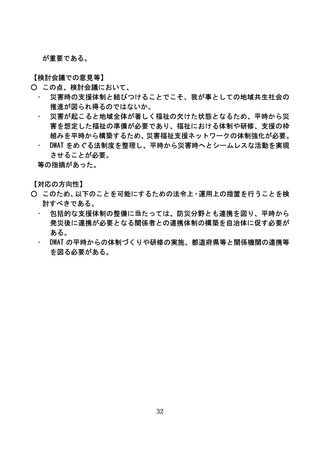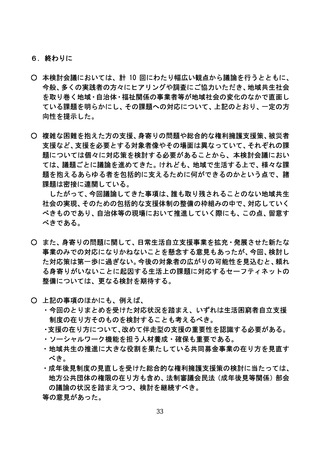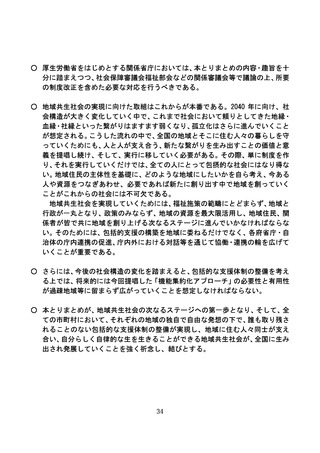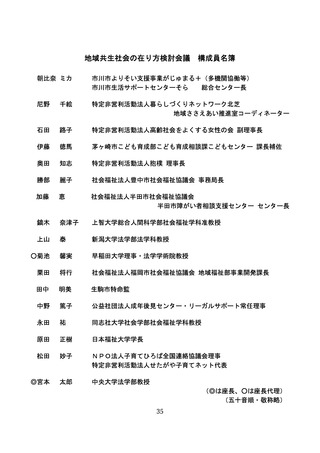よむ、つかう、まなぶ。
参考資料1 「地域共生社会の在り方検討会議」 中間とりまとめ (12 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59213.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第122回 6/30)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
法第 89 条で定められている基本指針(国民の社会福祉に関する活動への
参加の促進を図るための措置に関する基本的な指針)は、改定が為されて
おらず、今日的な指針としていく必要がある。
地域づくりにはそれを担う人材の確保が鍵であり、地域づくりの取組には、
各省庁、各分野の幅広い関わりが視野に入る。
包括的な支援体制の整備に当たっては、国の支援だけではなく、都道府県
の後方支援を一層強化する必要がある。
小規模な市町村においては、生活支援や地域活動の機能を1つの拠点に集
約し、一体的に行うなど、コンパクトな包括的な支援体制を目指すことも
考えられる。
といった指摘があった。
○ 重層的支援体制整備事業については、自治体へのヒアリングにおいては、
地域づくりはあまり進んでいない。住民主体の取組を含めて地域の幅広い
取組の連携が必要だということは理解しているが、具体的に何をすれば良
いのかイメージができていない。
施策を行う以上、評価は重要であるが、現状ではそこまで対応できていな
い。
重層的支援体制整備事業の実施に当たって、地域住民等の対話の中からで
はなく、近隣市町村等が始めたから事業を開始したというのが多い。
といった意見があった18。
○ また、この点、検討会議において、
重層的支援体制整備事業は体制整備のための手段としての事業である。
重層的支援体制整備事業はサブシステムであり、包括的な支援体制を整備
するための潤滑油で、メインシステムを下支えする補完的な機能を果たす
ものである。
地域づくりにはそれを担う人材の確保が鍵であり、地域住民を巻き込み、
地域を組み立てていく地域おこし、まちづくり的能力をもつ人材を育てて
いく仕組みがない。
実施までのプロセスが一番重要だという原点を押さえておくことを忘れな
いようにする必要がある。
重層的支援会議や支援会議を関係機関の連携強化の場として活用している
自治体もある。個々のケースに直接の関係がない職員等であってもメンバ
18
令和7年3月 27 日 第9回検討会議 資料1-2 p.3,5,6参照
11
法第 89 条で定められている基本指針(国民の社会福祉に関する活動への
参加の促進を図るための措置に関する基本的な指針)は、改定が為されて
おらず、今日的な指針としていく必要がある。
地域づくりにはそれを担う人材の確保が鍵であり、地域づくりの取組には、
各省庁、各分野の幅広い関わりが視野に入る。
包括的な支援体制の整備に当たっては、国の支援だけではなく、都道府県
の後方支援を一層強化する必要がある。
小規模な市町村においては、生活支援や地域活動の機能を1つの拠点に集
約し、一体的に行うなど、コンパクトな包括的な支援体制を目指すことも
考えられる。
といった指摘があった。
○ 重層的支援体制整備事業については、自治体へのヒアリングにおいては、
地域づくりはあまり進んでいない。住民主体の取組を含めて地域の幅広い
取組の連携が必要だということは理解しているが、具体的に何をすれば良
いのかイメージができていない。
施策を行う以上、評価は重要であるが、現状ではそこまで対応できていな
い。
重層的支援体制整備事業の実施に当たって、地域住民等の対話の中からで
はなく、近隣市町村等が始めたから事業を開始したというのが多い。
といった意見があった18。
○ また、この点、検討会議において、
重層的支援体制整備事業は体制整備のための手段としての事業である。
重層的支援体制整備事業はサブシステムであり、包括的な支援体制を整備
するための潤滑油で、メインシステムを下支えする補完的な機能を果たす
ものである。
地域づくりにはそれを担う人材の確保が鍵であり、地域住民を巻き込み、
地域を組み立てていく地域おこし、まちづくり的能力をもつ人材を育てて
いく仕組みがない。
実施までのプロセスが一番重要だという原点を押さえておくことを忘れな
いようにする必要がある。
重層的支援会議や支援会議を関係機関の連携強化の場として活用している
自治体もある。個々のケースに直接の関係がない職員等であってもメンバ
18
令和7年3月 27 日 第9回検討会議 資料1-2 p.3,5,6参照
11