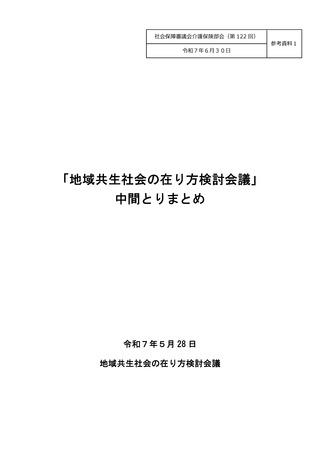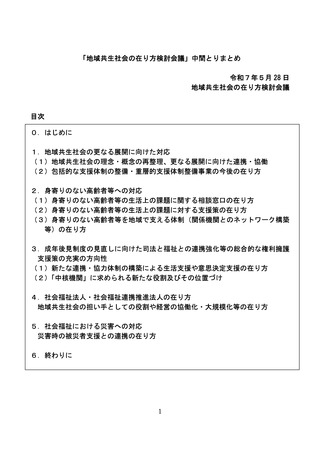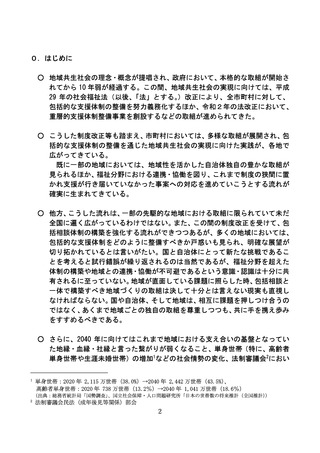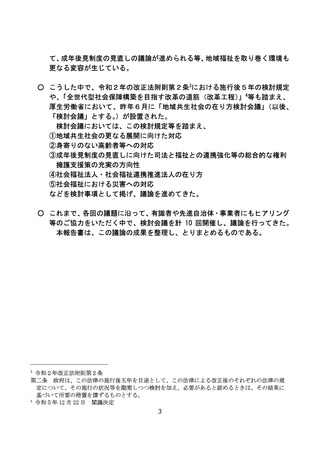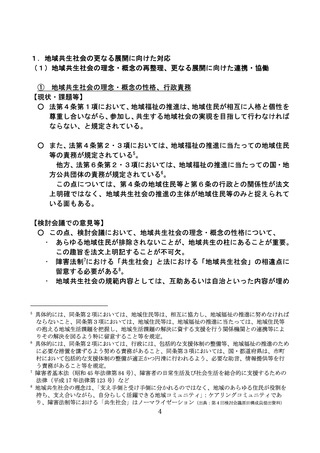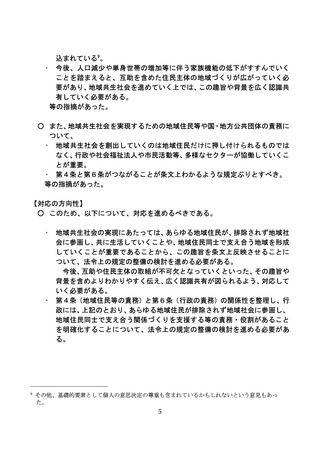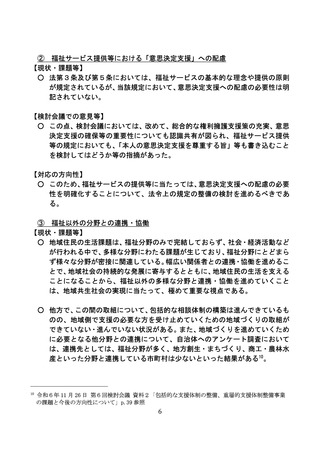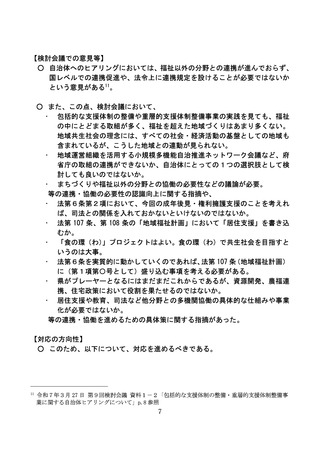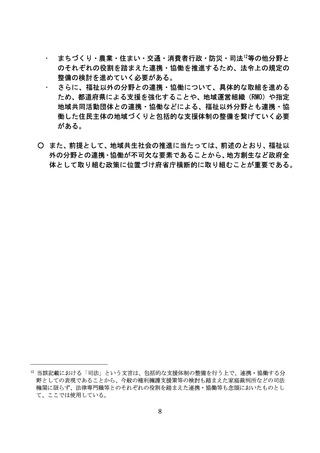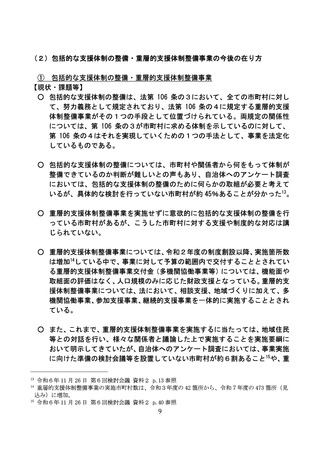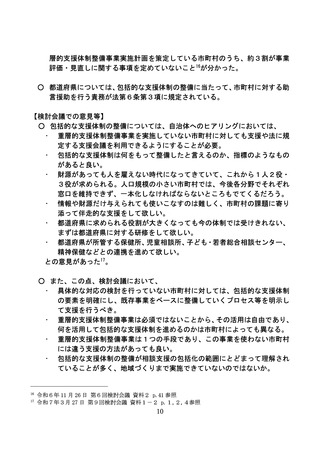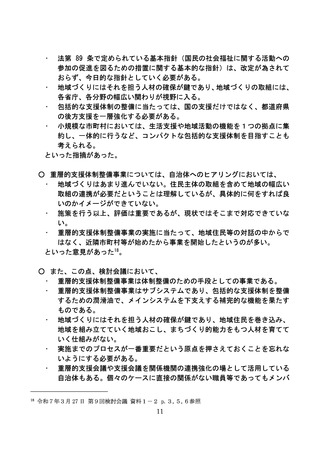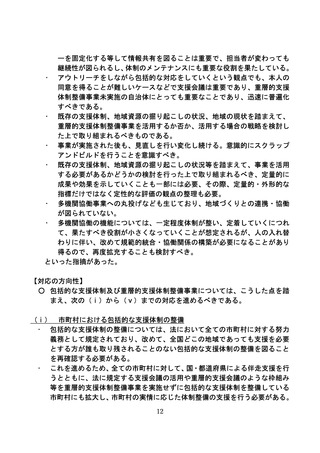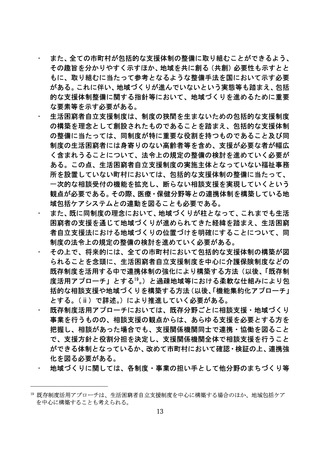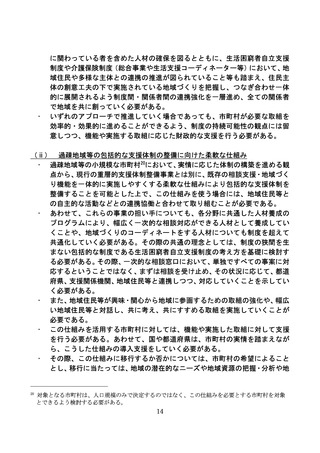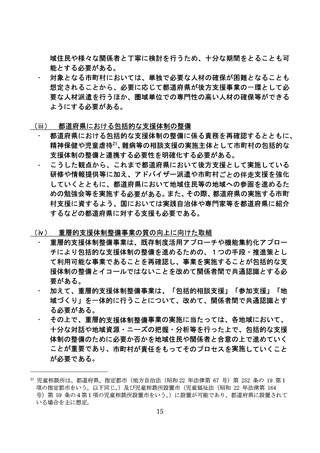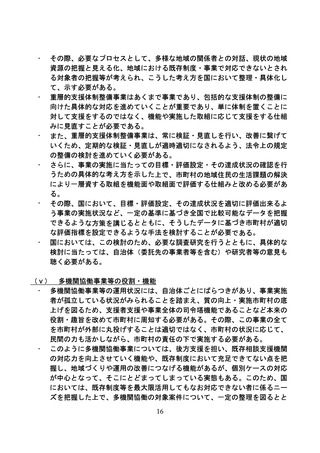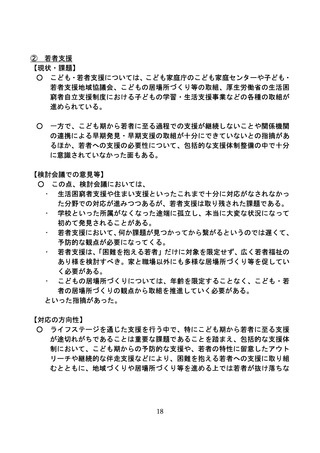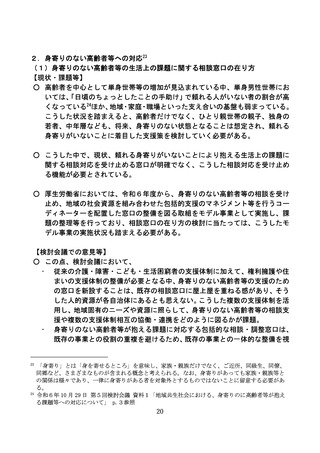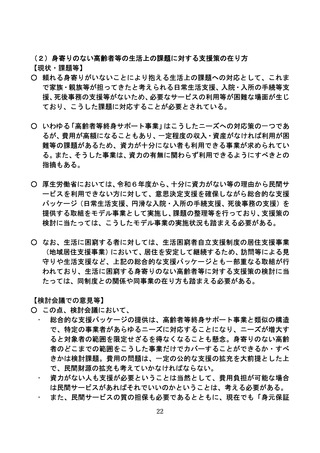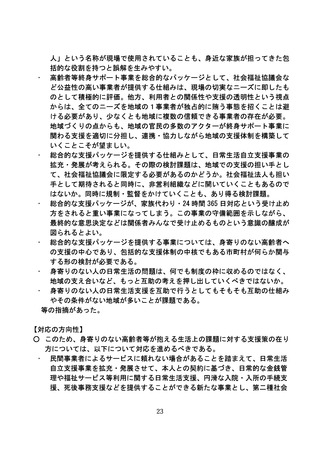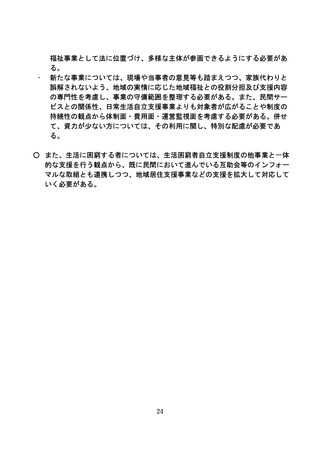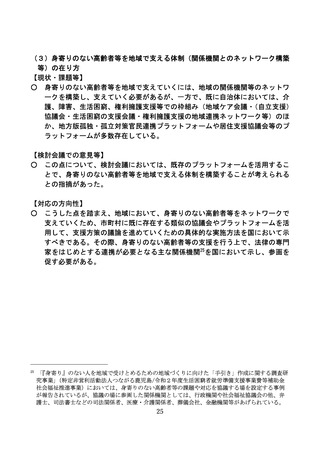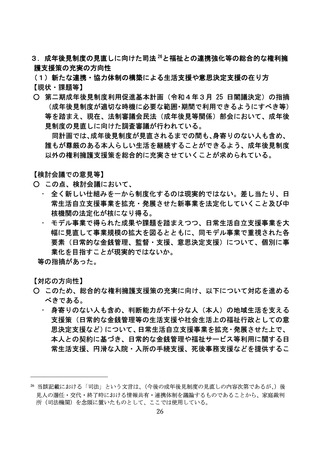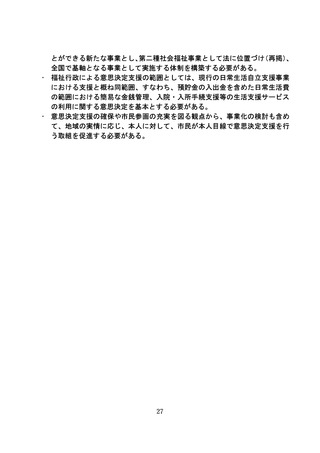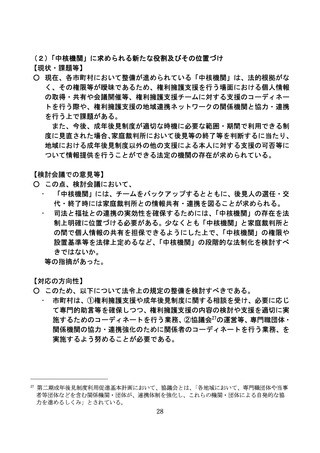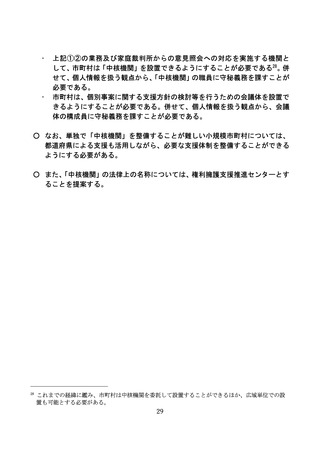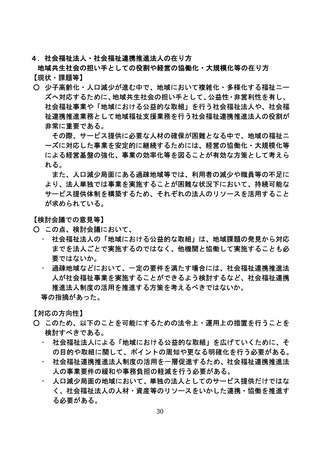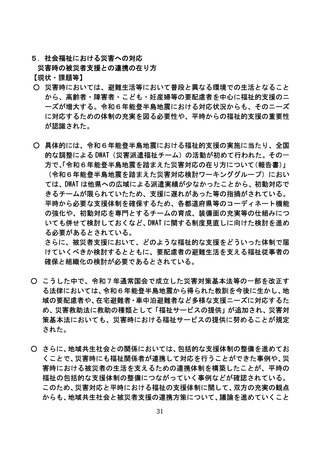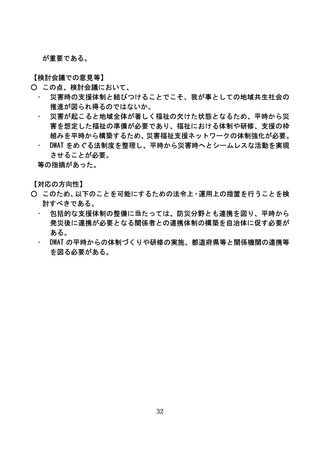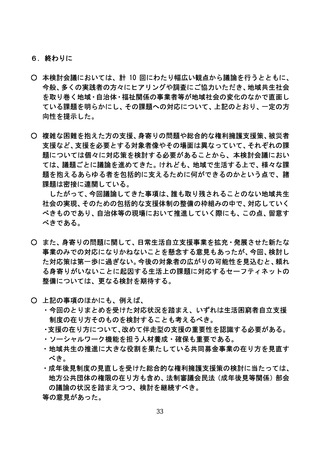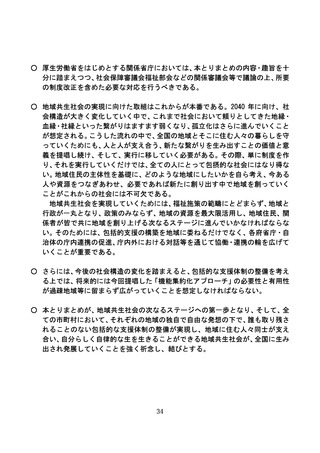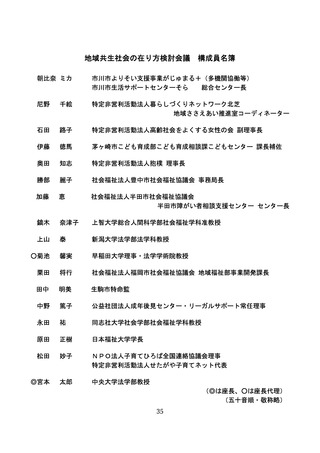よむ、つかう、まなぶ。
参考資料1 「地域共生社会の在り方検討会議」 中間とりまとめ (24 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59213.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第122回 6/30)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
人」という名称が現場で使用されていることも、身近な家族が担ってきた包
括的な役割を持つと誤解を生みやすい。
高齢者等終身サポート事業を総合的なパッケージとして、社会福祉協議会な
ど公益性の高い事業者が提供する仕組みは、現場の切実なニーズに即したも
のとして積極的に評価。他方、利用者との関係性や支援の透明性という視点
からは、全てのニーズを地域の1事業者が独占的に賄う事態を招くことは避
ける必要があり、少なくとも地域に複数の信頼できる事業者の存在が必要。
地域づくりの点からも、地域の官民の多数のアクターが終身サポート事業に
関わる支援を適切に分担し、連携・協力しながら地域の支援体制を構築して
いくことこそが望ましい。
総合的な支援パッケージを提供する仕組みとして、日常生活自立支援事業の
拡充・発展が考えられる。その際の検討課題は、地域での支援の担い手とし
て、社会福祉協議会に限定する必要があるのかどうか。社会福祉法人も担い
手として期待されると同時に、非営利組織などに開いていくこともあるので
はないか。同時に規制・監督をかけていくことも、あり得る検討課題。
総合的な支援パッケージが、家族代わり・24 時間 365 日対応という受け止め
方をされると重い事業になってしまう。この事業の守備範囲を示しながら、
最終的な意思決定などは関係者みんなで受け止めるものという意識の醸成が
図られるとよい。
総合的な支援パッケージを提供する事業については、身寄りのない高齢者へ
の支援の中心であり、包括的な支援体制の中核でもある市町村が何らか関与
する形の検討が必要である。
身寄りのない人の日常生活の問題は、何でも制度の枠に収めるのではなく、
地域の支え合いなど、もっと互助の考えを押し出していくべきではないか。
身寄りのない人の日常生活支援を互助で行うとしてもそもそも互助の仕組み
やその条件がない地域が多いことが課題である。
等の指摘があった。
【対応の方向性】
○ このため、身寄りのない高齢者等が抱える生活上の課題に対する支援策の在り
方については、以下について対応を進めるべきである。
民間事業者によるサービスに頼れない場合があることを踏まえて、日常生活
自立支援事業を拡充・発展させて、本人との契約に基づき、日常的な金銭管
理や福祉サービス等利用に関する日常生活支援、円滑な入院・入所の手続支
援、死後事務支援などを提供することができる新たな事業とし、第二種社会
23
括的な役割を持つと誤解を生みやすい。
高齢者等終身サポート事業を総合的なパッケージとして、社会福祉協議会な
ど公益性の高い事業者が提供する仕組みは、現場の切実なニーズに即したも
のとして積極的に評価。他方、利用者との関係性や支援の透明性という視点
からは、全てのニーズを地域の1事業者が独占的に賄う事態を招くことは避
ける必要があり、少なくとも地域に複数の信頼できる事業者の存在が必要。
地域づくりの点からも、地域の官民の多数のアクターが終身サポート事業に
関わる支援を適切に分担し、連携・協力しながら地域の支援体制を構築して
いくことこそが望ましい。
総合的な支援パッケージを提供する仕組みとして、日常生活自立支援事業の
拡充・発展が考えられる。その際の検討課題は、地域での支援の担い手とし
て、社会福祉協議会に限定する必要があるのかどうか。社会福祉法人も担い
手として期待されると同時に、非営利組織などに開いていくこともあるので
はないか。同時に規制・監督をかけていくことも、あり得る検討課題。
総合的な支援パッケージが、家族代わり・24 時間 365 日対応という受け止め
方をされると重い事業になってしまう。この事業の守備範囲を示しながら、
最終的な意思決定などは関係者みんなで受け止めるものという意識の醸成が
図られるとよい。
総合的な支援パッケージを提供する事業については、身寄りのない高齢者へ
の支援の中心であり、包括的な支援体制の中核でもある市町村が何らか関与
する形の検討が必要である。
身寄りのない人の日常生活の問題は、何でも制度の枠に収めるのではなく、
地域の支え合いなど、もっと互助の考えを押し出していくべきではないか。
身寄りのない人の日常生活支援を互助で行うとしてもそもそも互助の仕組み
やその条件がない地域が多いことが課題である。
等の指摘があった。
【対応の方向性】
○ このため、身寄りのない高齢者等が抱える生活上の課題に対する支援策の在り
方については、以下について対応を進めるべきである。
民間事業者によるサービスに頼れない場合があることを踏まえて、日常生活
自立支援事業を拡充・発展させて、本人との契約に基づき、日常的な金銭管
理や福祉サービス等利用に関する日常生活支援、円滑な入院・入所の手続支
援、死後事務支援などを提供することができる新たな事業とし、第二種社会
23