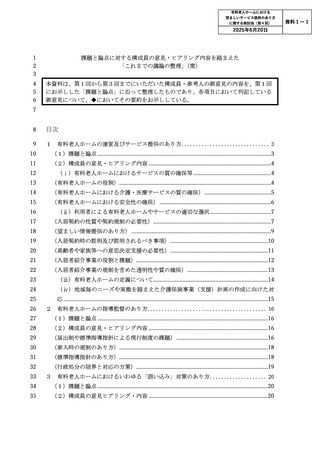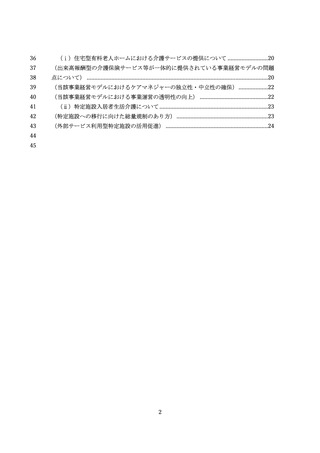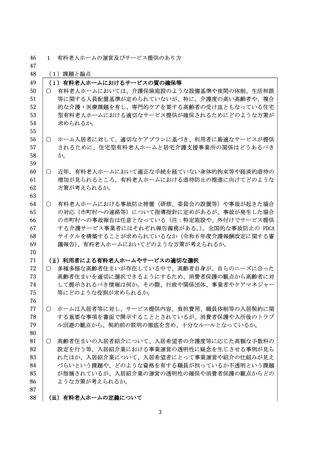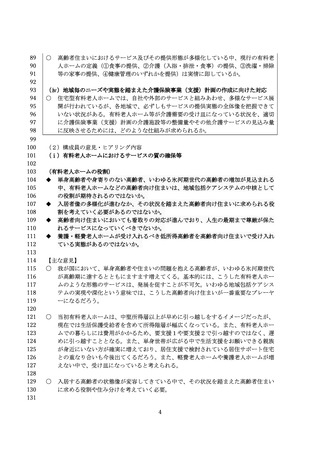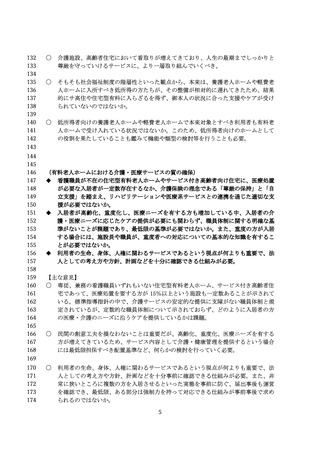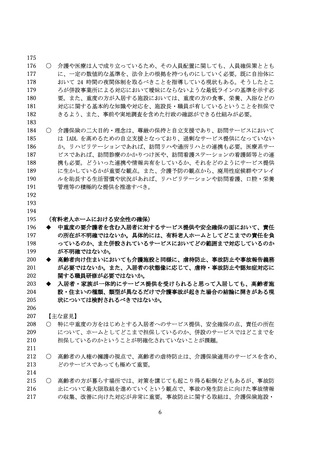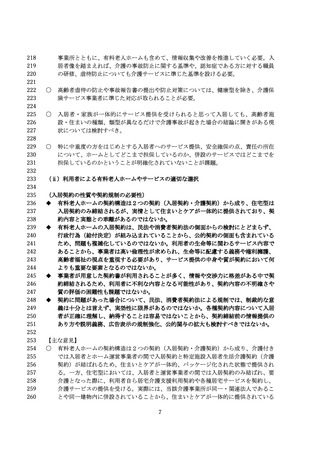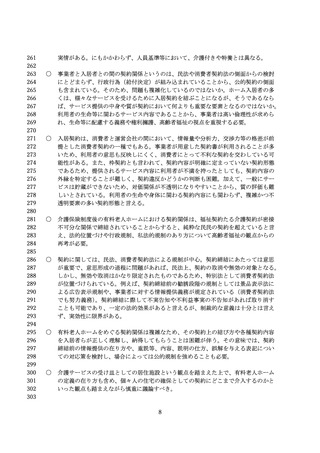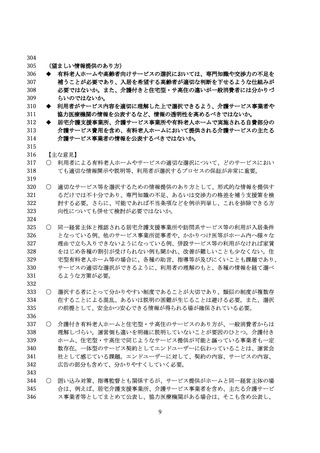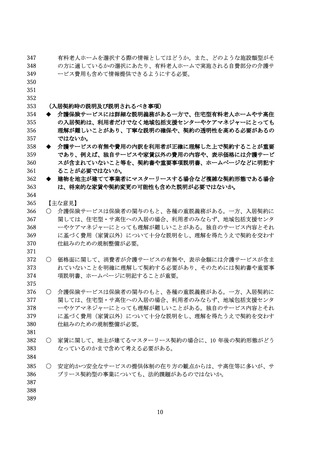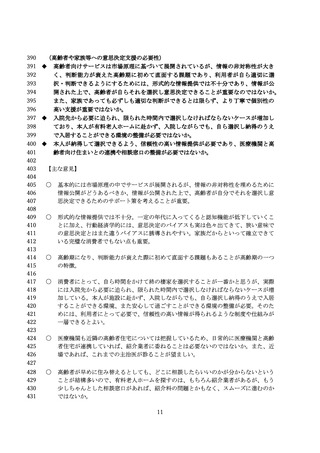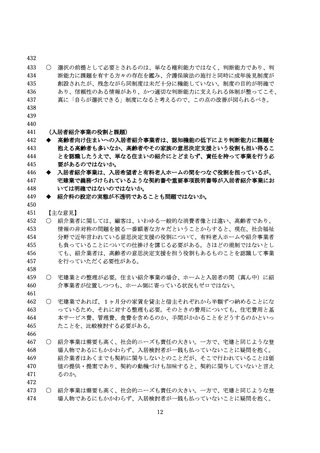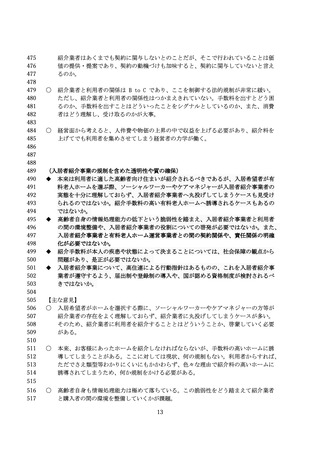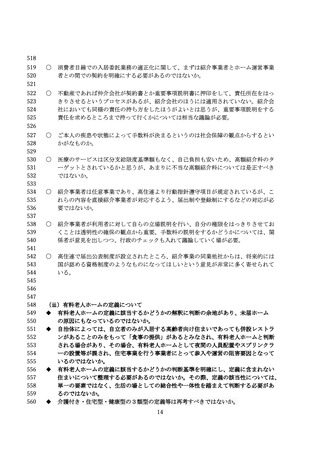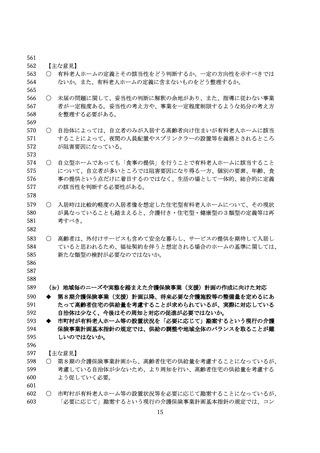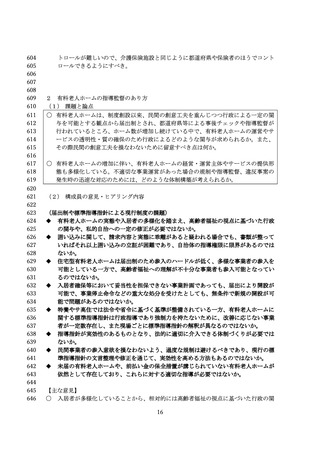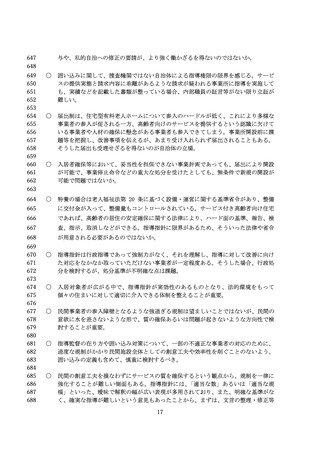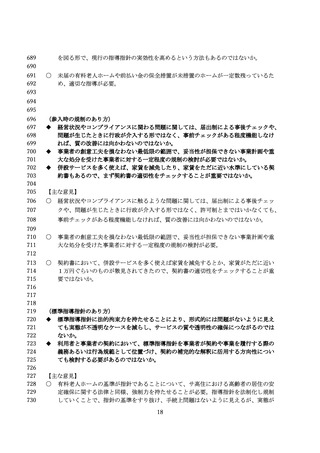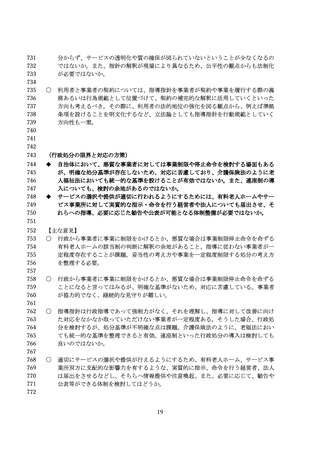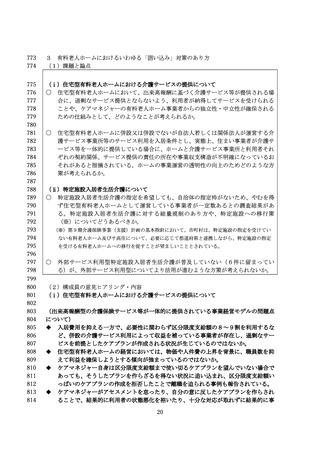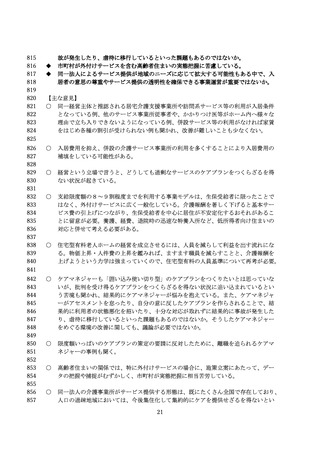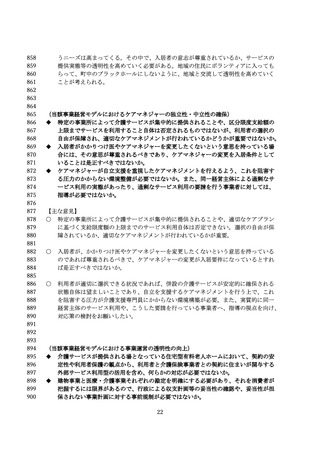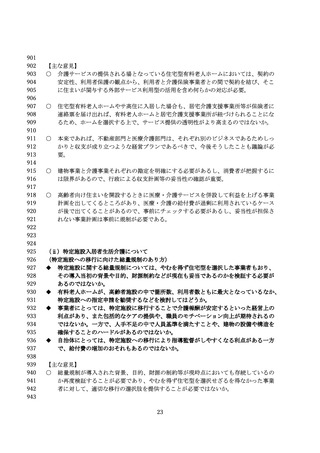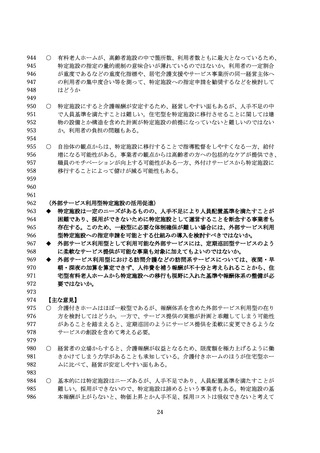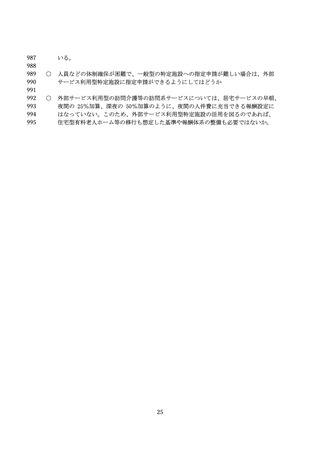よむ、つかう、まなぶ。
資料1-1 課題と論点に対する構成員の意見・ヒアリング内容を踏まえた これまでの議論の整理(案) (9 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59007.html |
| 出典情報 | 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第4回 6/20)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
(望ましい情報提供のあり方)
◆ 有料老人ホームや高齢者向けサービスの選択においては、専門知識や交渉力の不足を
補うことが必要であり、入居を希望する高齢者が適切な判断を下せるような仕組みが
必要ではないか。また、介護付きと住宅型・サ高住の違いが一般消費者には分かりづ
らいのではないか。
◆ 利用者がサービス内容を適切に理解した上で選択できるよう、介護サービス事業者や
協力医療機関の情報を公表するなど、情報の透明性を高めるべきではないか。
◆ 居宅介護支援事業所、介護サービス事業所や有料老人ホームで実施される自費部分の
介護サービス費用を含め、有料老人ホームにおいて提供される介護サービスの主たる
介護サービス事業者の情報を公表するべきではないか。
【主な意見】
○ 利用者による有料老人ホームやサービスの適切な選択について、どのサービスにおい
ても適切な情報開示や説明等、利用者が選択するプロセスの保証が非常に重要。
○
適切なサービス等を選択するための情報提供のあり方として、形式的な情報を提供す
るだけでは不十分であり、専門知識の不足、あるいは交渉力の格差を補う支援策を検
討する必要。さらに、可能であれば不当条項などを例示列挙し、これを排除できる方
向性についても併せて検討が必要ではないか。
○
同一経営主体と推認される居宅介護支援事業所や訪問系サービス等の利用が入居条件
となっている例、他のサービス事業所従事者や、かかりつけ医等がホーム内へ様々な
理由で立ち入りできないようになっている例、併設サービス等の利用がなければ家賃
をはじめ各種の割引が受けられない例も聞かれ、改善が難しいことも少なくない。住
宅型有料老人ホーム等の場合に、各種の助言、指導等が及びにくいことも課題であり、
サービスの適切な選択ができるように、利用者の理解のもと、各種の情報を経て選べ
るような方策が必要。
○
選択する者にとって分かりやすい制度であることが大切であり、類似の制度が複数存
在することによる混乱、あるいは説明の困難が生じることは避ける必要。また、選択
の前提として、安全かつ安心できる情報が得られる場が確保されている必要。
○
介護付き有料老人ホームと住宅型・サ高住のサービスのあり方が、一般消費者からは
理解しづらい。運営側も違いを明確に説明していないことが要因のひとつ。介護付き
ホーム、住宅型・サ高住で同じようなサービス提供が可能と謳っている事業者も一定
数存在。一体型のサービス契約としてエンドユーザーに伝わっていることは、運営会
社として感じている課題。エンドユーザーに対して、契約の内容、サービスの内容、
広告の部分も含めて、分かりやすくしていく必要。
○
囲い込み対策、指導監督とも関係するが、サービス提供がホームと同一経営主体の場
合は、例えば、居宅介護支援事業所、介護サービス事業者を含め、主たる介護サービ
ス事業者等としてまとめて公表し、協力医療機関がある場合は、そこも含め公表し、
9
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
(望ましい情報提供のあり方)
◆ 有料老人ホームや高齢者向けサービスの選択においては、専門知識や交渉力の不足を
補うことが必要であり、入居を希望する高齢者が適切な判断を下せるような仕組みが
必要ではないか。また、介護付きと住宅型・サ高住の違いが一般消費者には分かりづ
らいのではないか。
◆ 利用者がサービス内容を適切に理解した上で選択できるよう、介護サービス事業者や
協力医療機関の情報を公表するなど、情報の透明性を高めるべきではないか。
◆ 居宅介護支援事業所、介護サービス事業所や有料老人ホームで実施される自費部分の
介護サービス費用を含め、有料老人ホームにおいて提供される介護サービスの主たる
介護サービス事業者の情報を公表するべきではないか。
【主な意見】
○ 利用者による有料老人ホームやサービスの適切な選択について、どのサービスにおい
ても適切な情報開示や説明等、利用者が選択するプロセスの保証が非常に重要。
○
適切なサービス等を選択するための情報提供のあり方として、形式的な情報を提供す
るだけでは不十分であり、専門知識の不足、あるいは交渉力の格差を補う支援策を検
討する必要。さらに、可能であれば不当条項などを例示列挙し、これを排除できる方
向性についても併せて検討が必要ではないか。
○
同一経営主体と推認される居宅介護支援事業所や訪問系サービス等の利用が入居条件
となっている例、他のサービス事業所従事者や、かかりつけ医等がホーム内へ様々な
理由で立ち入りできないようになっている例、併設サービス等の利用がなければ家賃
をはじめ各種の割引が受けられない例も聞かれ、改善が難しいことも少なくない。住
宅型有料老人ホーム等の場合に、各種の助言、指導等が及びにくいことも課題であり、
サービスの適切な選択ができるように、利用者の理解のもと、各種の情報を経て選べ
るような方策が必要。
○
選択する者にとって分かりやすい制度であることが大切であり、類似の制度が複数存
在することによる混乱、あるいは説明の困難が生じることは避ける必要。また、選択
の前提として、安全かつ安心できる情報が得られる場が確保されている必要。
○
介護付き有料老人ホームと住宅型・サ高住のサービスのあり方が、一般消費者からは
理解しづらい。運営側も違いを明確に説明していないことが要因のひとつ。介護付き
ホーム、住宅型・サ高住で同じようなサービス提供が可能と謳っている事業者も一定
数存在。一体型のサービス契約としてエンドユーザーに伝わっていることは、運営会
社として感じている課題。エンドユーザーに対して、契約の内容、サービスの内容、
広告の部分も含めて、分かりやすくしていく必要。
○
囲い込み対策、指導監督とも関係するが、サービス提供がホームと同一経営主体の場
合は、例えば、居宅介護支援事業所、介護サービス事業者を含め、主たる介護サービ
ス事業者等としてまとめて公表し、協力医療機関がある場合は、そこも含め公表し、
9