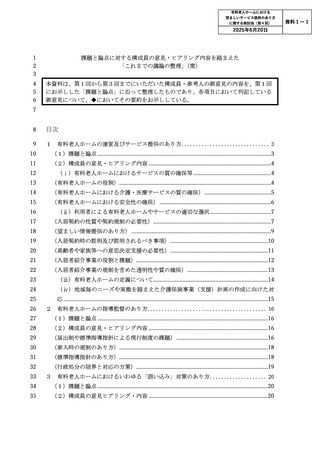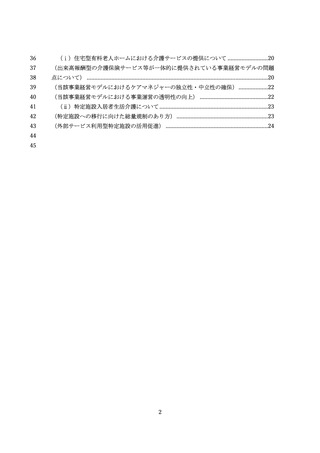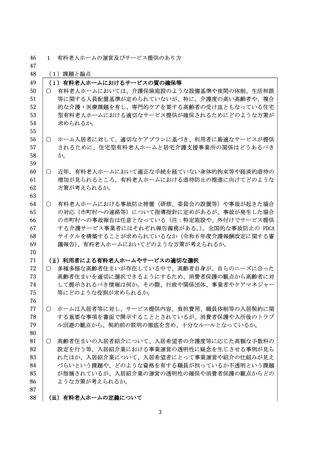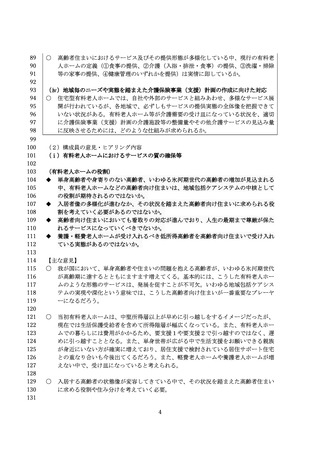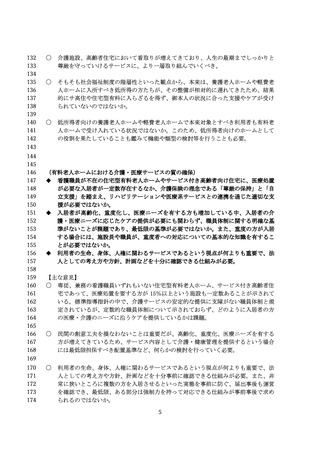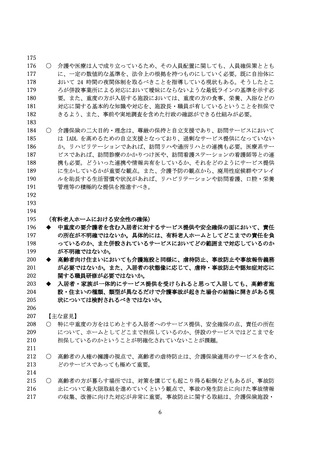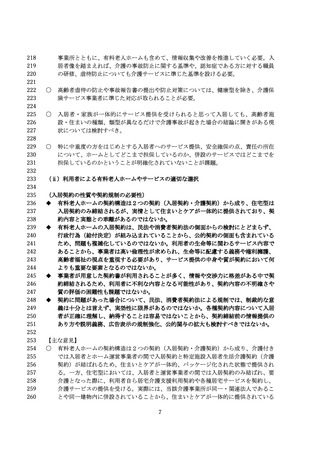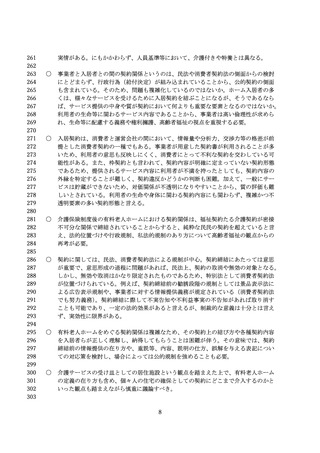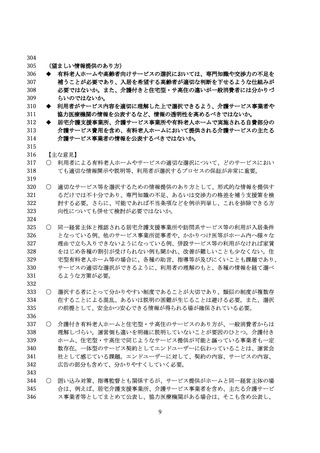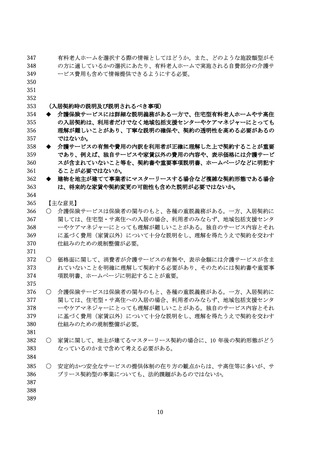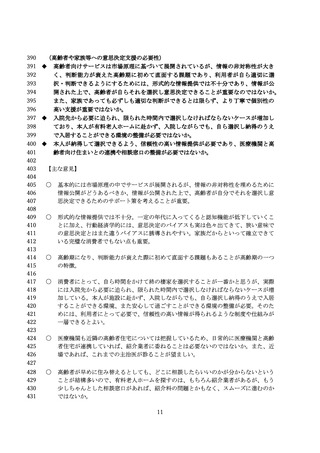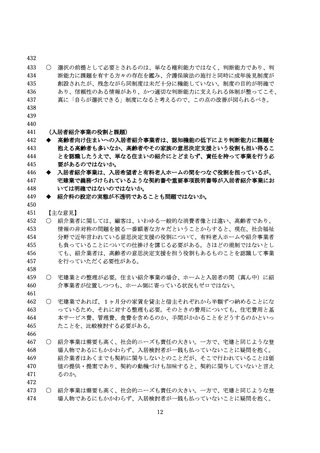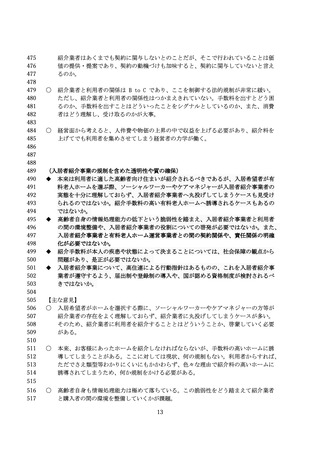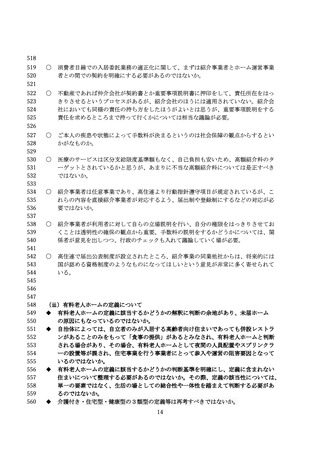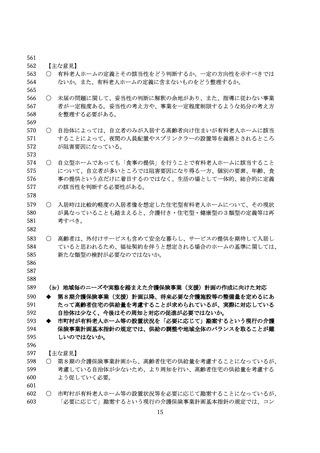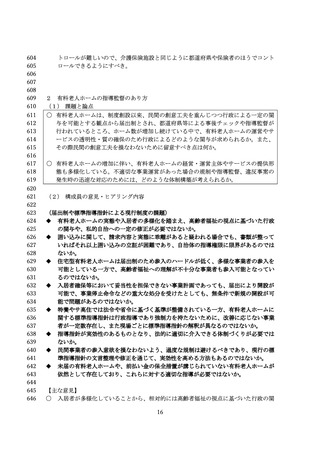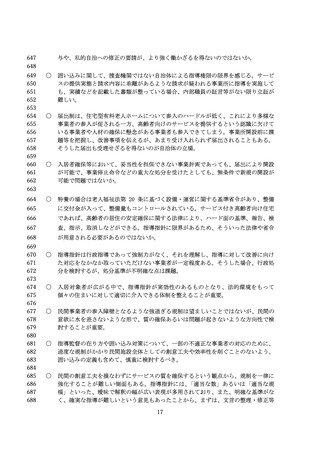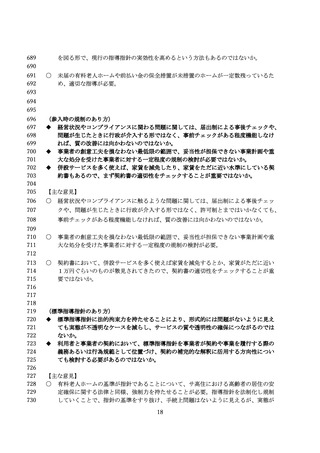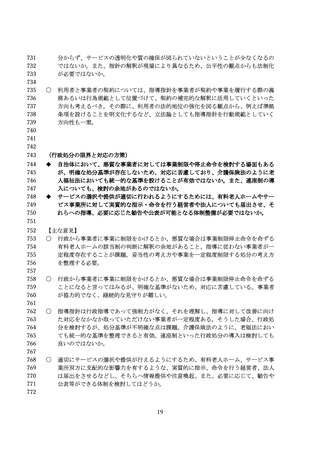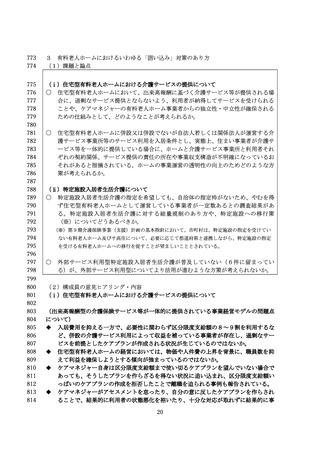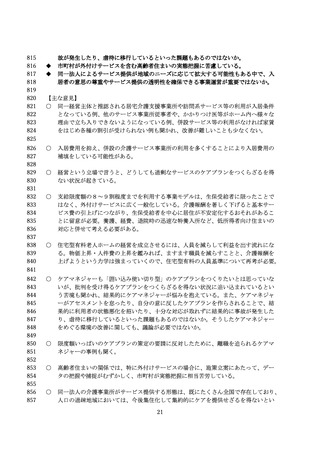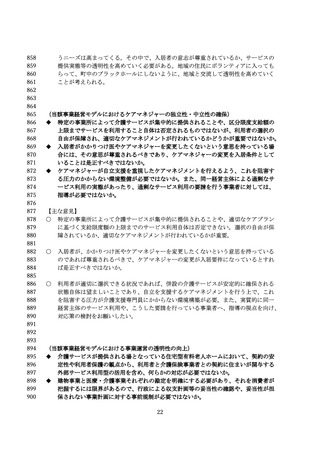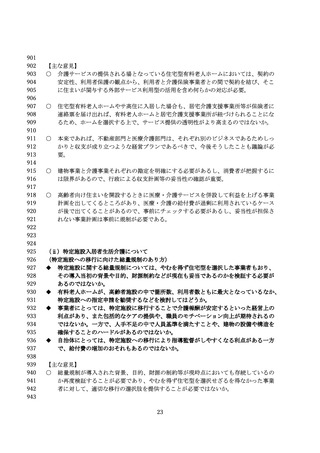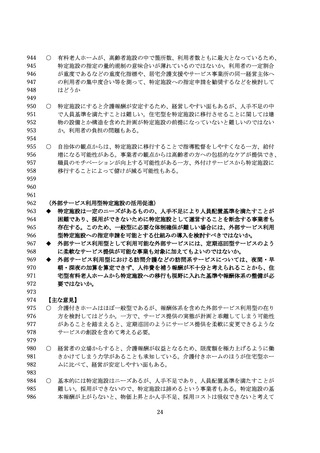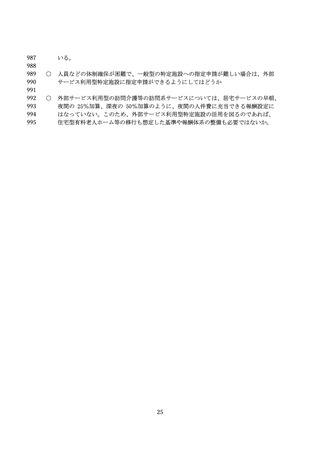よむ、つかう、まなぶ。
資料1-1 課題と論点に対する構成員の意見・ヒアリング内容を踏まえた これまでの議論の整理(案) (13 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59007.html |
| 出典情報 | 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第4回 6/20)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
紹介業者はあくまでも契約に関与しないとのことだが、そこで行われていることは価
値の提供・提案であり、契約の動機づけも加味すると、契約に関与していないと言え
るのか。
○
紹介業者と利用者の関係は B to C であり、ここを制御する法的規制が非常に緩い。
ただし、紹介業者と利用者の関係性はつかまえきれていない。手数料を出すとどう困
るのか、手数料を出すことはどういったことをシグナルとしているのか、また、消費
者はどう理解し、受け取るのかが大事。
○
経営面から考えると、人件費や物価の上昇の中で収益を上げる必要があり、紹介料を
上げてでも利用者を集めさせてしまう経営者の力学が働く。
(入居者紹介事業の規制を含めた透明性や質の確保)
◆ 本来は利用者に適した高齢者向け住まいが紹介されるべきであるが、入居希望者が有
料老人ホームを選ぶ際、ソーシャルワーカーやケアマネジャーが入居者紹介事業者の
実態を十分に理解しておらず、入居者紹介事業者へ丸投げしてしまうケースも見受け
られるのではないか。紹介手数料の高い有料老人ホームへ誘導されるケースもあるの
ではないか。
◆ 高齢者自身の情報処理能力の低下という脆弱性を踏まえ、入居者紹介事業者と利用者
の間の環境整備や、入居者紹介事業者の役割についての啓発が必要ではないか。また、
入居者紹介事業者と有料老人ホーム運営事業者との間の契約関係や、責任関係の明確
化が必要ではないか。
◆ 紹介手数料が本人の疾患や状態によって決まることについては、社会保障の観点から
問題があり、是正が必要ではないか。
◆ 入居者紹介事業について、高住連による行動指針はあるものの、これを入居者紹介事
業者が遵守するよう、届出制や登録制の導入や、国が認める資格制度が検討されるべ
きではないか。
【主な意見】
○ 入居希望者がホームを選択する際に、ソーシャルワーカーやケアマネジャーの方等が
紹介業者の存在をよく理解しておらず、紹介業者に丸投げしてしまうケースが多い。
そのため、紹介業者に利用者を紹介することとはどういうことか、啓蒙していく必要
がある。
○
本来、お客様にあったホームを紹介しなければならないが、手数料の高いホームに誘
導してしまうことがある。ここに対しては現状、何の規制もない。利用者からすれば、
ただでさえ類型等わかりにくいにもかかわらず、色々な理由で紹介料の高いホームに
誘導されてしまうため、何か規制をかける必要がある。
○
高齢者自身も情報処理能力は極めて落ちている。この脆弱性をどう踏まえて紹介業者
と購入者の間の環境を整備していくかが課題。
13
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
紹介業者はあくまでも契約に関与しないとのことだが、そこで行われていることは価
値の提供・提案であり、契約の動機づけも加味すると、契約に関与していないと言え
るのか。
○
紹介業者と利用者の関係は B to C であり、ここを制御する法的規制が非常に緩い。
ただし、紹介業者と利用者の関係性はつかまえきれていない。手数料を出すとどう困
るのか、手数料を出すことはどういったことをシグナルとしているのか、また、消費
者はどう理解し、受け取るのかが大事。
○
経営面から考えると、人件費や物価の上昇の中で収益を上げる必要があり、紹介料を
上げてでも利用者を集めさせてしまう経営者の力学が働く。
(入居者紹介事業の規制を含めた透明性や質の確保)
◆ 本来は利用者に適した高齢者向け住まいが紹介されるべきであるが、入居希望者が有
料老人ホームを選ぶ際、ソーシャルワーカーやケアマネジャーが入居者紹介事業者の
実態を十分に理解しておらず、入居者紹介事業者へ丸投げしてしまうケースも見受け
られるのではないか。紹介手数料の高い有料老人ホームへ誘導されるケースもあるの
ではないか。
◆ 高齢者自身の情報処理能力の低下という脆弱性を踏まえ、入居者紹介事業者と利用者
の間の環境整備や、入居者紹介事業者の役割についての啓発が必要ではないか。また、
入居者紹介事業者と有料老人ホーム運営事業者との間の契約関係や、責任関係の明確
化が必要ではないか。
◆ 紹介手数料が本人の疾患や状態によって決まることについては、社会保障の観点から
問題があり、是正が必要ではないか。
◆ 入居者紹介事業について、高住連による行動指針はあるものの、これを入居者紹介事
業者が遵守するよう、届出制や登録制の導入や、国が認める資格制度が検討されるべ
きではないか。
【主な意見】
○ 入居希望者がホームを選択する際に、ソーシャルワーカーやケアマネジャーの方等が
紹介業者の存在をよく理解しておらず、紹介業者に丸投げしてしまうケースが多い。
そのため、紹介業者に利用者を紹介することとはどういうことか、啓蒙していく必要
がある。
○
本来、お客様にあったホームを紹介しなければならないが、手数料の高いホームに誘
導してしまうことがある。ここに対しては現状、何の規制もない。利用者からすれば、
ただでさえ類型等わかりにくいにもかかわらず、色々な理由で紹介料の高いホームに
誘導されてしまうため、何か規制をかける必要がある。
○
高齢者自身も情報処理能力は極めて落ちている。この脆弱性をどう踏まえて紹介業者
と購入者の間の環境を整備していくかが課題。
13