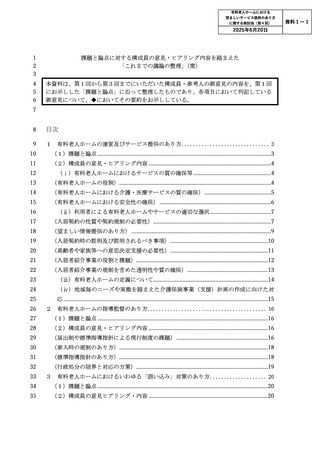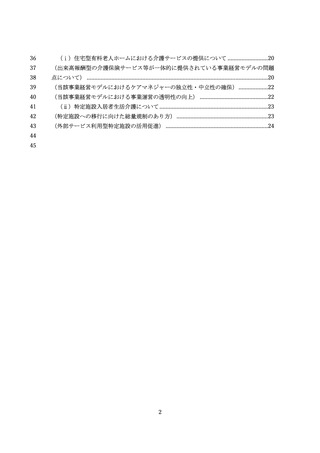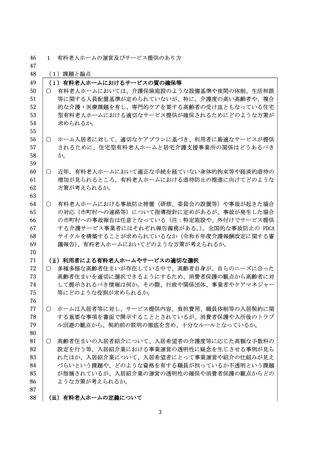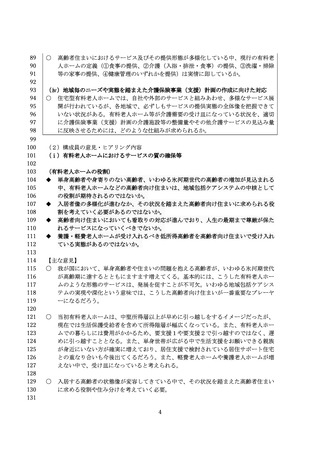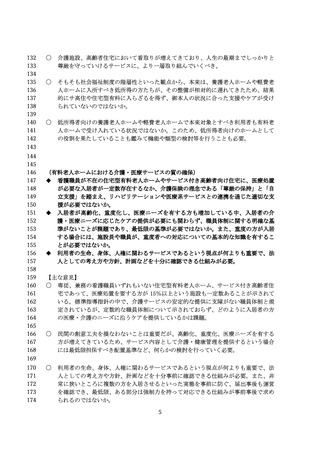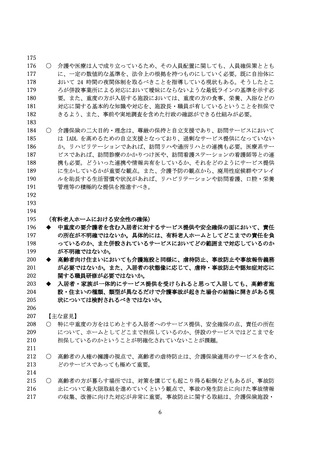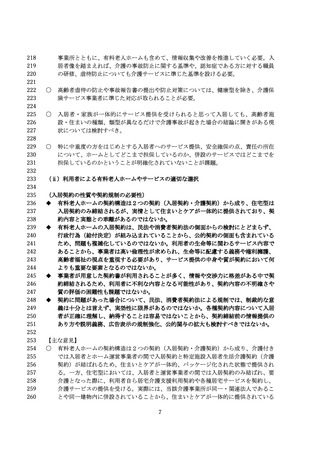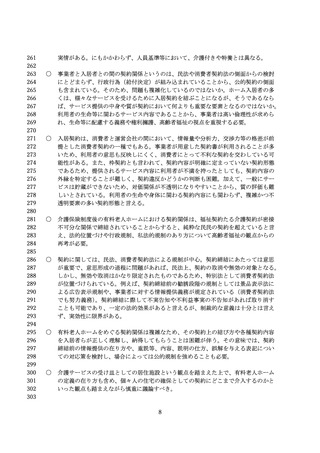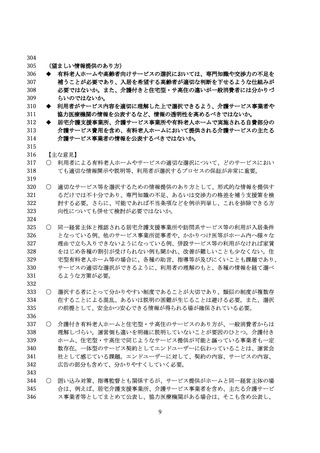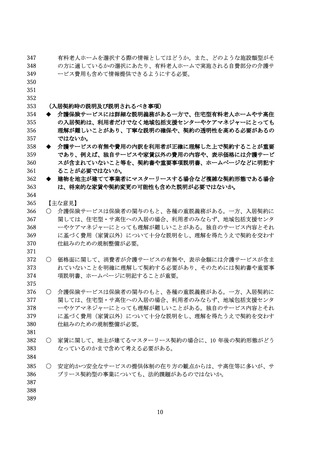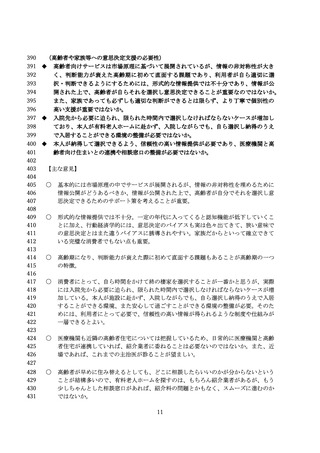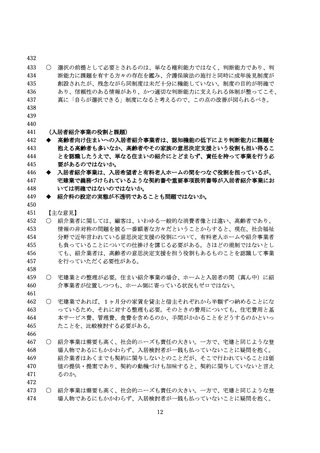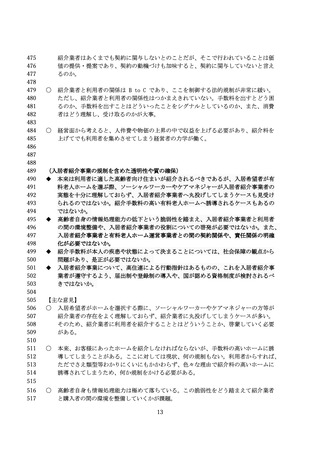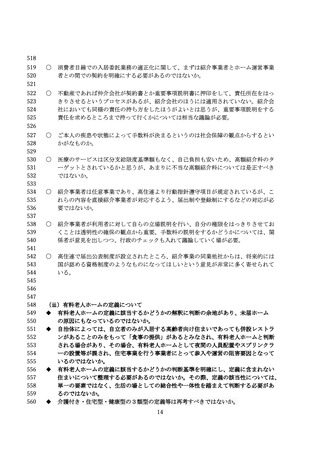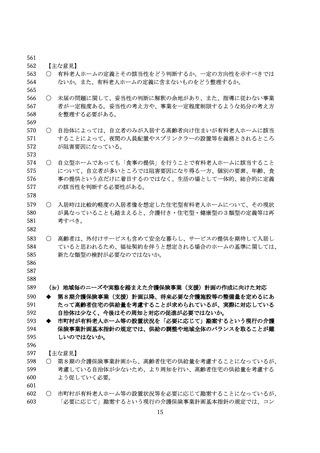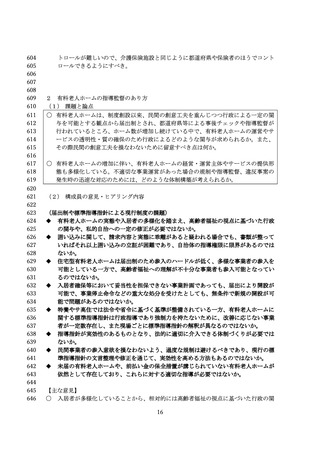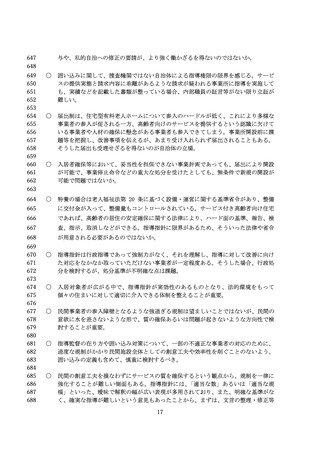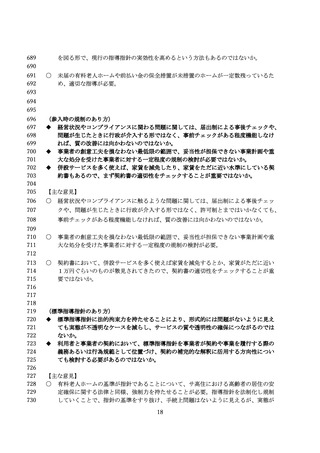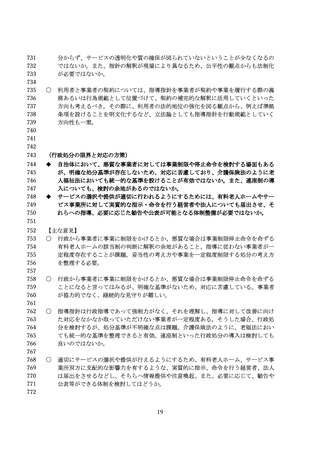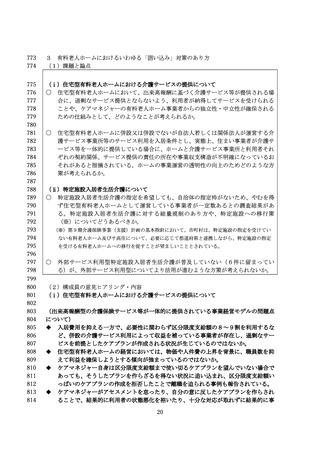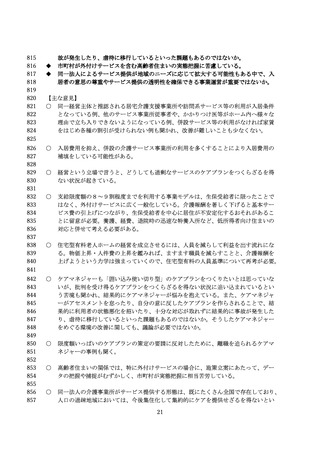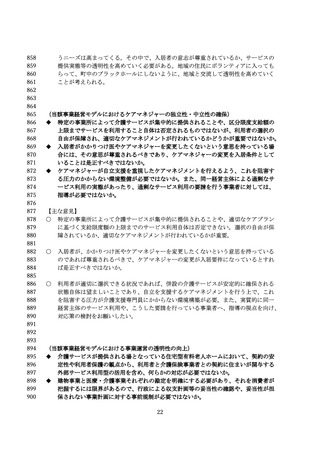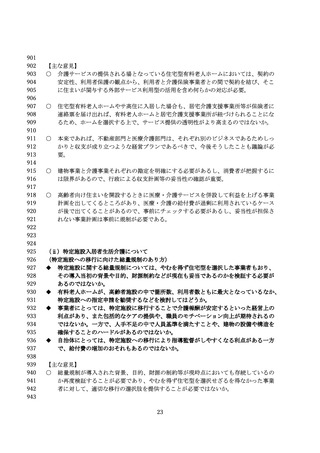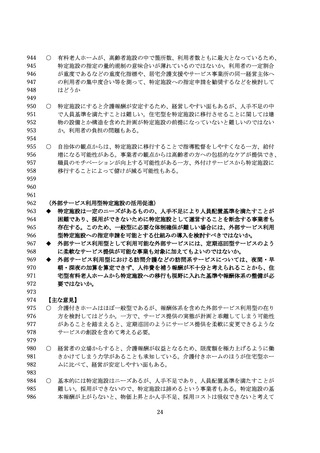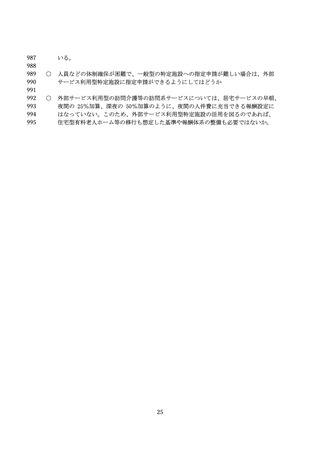よむ、つかう、まなぶ。
資料1-1 課題と論点に対する構成員の意見・ヒアリング内容を踏まえた これまでの議論の整理(案) (17 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59007.html |
| 出典情報 | 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第4回 6/20)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
与や、私的自治への修正の要請が、より強く働かざるを得ないのではないか。
○
囲い込みに関して、捜査機関ではない自治体による指導権限の限界を感じる。サービ
スの提供実態と請求内容に乖離があるような請求が疑われる事業所に指導を実施して
も、実績などを記載した書類が整っている場合、内部職員の証言等がない限り立証が
難しい。
○
届出制は、住宅型有料老人ホームについて参入のハードルが低く、これにより多様な
事業者の参入が促される一方、高齢者向けのサービスを提供するという認識に欠けて
いる事業者や人材の確保に懸念がある事業者も参入できてしまう。事業所開設前に課
題等を把握し、改善事項を伝えるが、あまり受け入れられず届出されることもある。
そうした届出も受理せざるを得ないのが自治体の立場。
○
入居者確保等において、妥当性を担保できない事業計画であっても、届出により開設
が可能で、事業停止命令などの重大な処分を受けたとしても、無条件で新規の開設が
可能で問題ではないか。
○
特養の場合は老人福祉法第 20 条に基づく設備・運営に関する基準省令があり、整備
663
664
665
に交付金が入って、整備量もコントロールされている。サービス付き高齢者向け住宅
666
であれば、高齢者の居住の安定確保に関する法律により、ハード面の基準、報告、検
667
査、指示、取消しなどができる。指導指針に限界があるため、そういった法律や省令
668
が用意される必要があるのではないか。
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
○
指導指針は行政指導であって強制力がなく、それを理解し、指導に対して改善に向け
た対応をなかなか取っていただけない事業者が一定程度ある。そうした場合、行政処
分を検討するが、処分基準が不明確な点は課題。
○
入居対象者が広がる中で、指導指針が実効性のあるものとなり、法的環境をもって
個々の住まいに対して適切に介入できる体制を整えることが重要。
○
民間事業者の参入障壁となるような強過ぎる規制は望ましいことではないが、民間の
意欲に水を差さないような形で、質の確保あるいは問題が起きないような方向性で検
討することが重要。
○
指導監督の在り方や囲い込み対策について、一部の不適正な事業者の対応のために、
過度な規制がかかり民間施設全体としての創意工夫や効率性を削ぐことのないよう、
囲い込みの定義も含めて、慎重に検討するべき。
○
民間の創意工夫を損なわずにサービスの質を確保するという観点から、規制を一律に
強化することが難しい側面もある。指導指針には、「適当な数」あるいは「適当な規
模」といった、曖昧で解釈の幅が広い表現が多用されており、また、明確な基準がな
く、確実な指導が難しいという意見もあったことから、まずは、文言の整理・修正等
17
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
与や、私的自治への修正の要請が、より強く働かざるを得ないのではないか。
○
囲い込みに関して、捜査機関ではない自治体による指導権限の限界を感じる。サービ
スの提供実態と請求内容に乖離があるような請求が疑われる事業所に指導を実施して
も、実績などを記載した書類が整っている場合、内部職員の証言等がない限り立証が
難しい。
○
届出制は、住宅型有料老人ホームについて参入のハードルが低く、これにより多様な
事業者の参入が促される一方、高齢者向けのサービスを提供するという認識に欠けて
いる事業者や人材の確保に懸念がある事業者も参入できてしまう。事業所開設前に課
題等を把握し、改善事項を伝えるが、あまり受け入れられず届出されることもある。
そうした届出も受理せざるを得ないのが自治体の立場。
○
入居者確保等において、妥当性を担保できない事業計画であっても、届出により開設
が可能で、事業停止命令などの重大な処分を受けたとしても、無条件で新規の開設が
可能で問題ではないか。
○
特養の場合は老人福祉法第 20 条に基づく設備・運営に関する基準省令があり、整備
663
664
665
に交付金が入って、整備量もコントロールされている。サービス付き高齢者向け住宅
666
であれば、高齢者の居住の安定確保に関する法律により、ハード面の基準、報告、検
667
査、指示、取消しなどができる。指導指針に限界があるため、そういった法律や省令
668
が用意される必要があるのではないか。
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
○
指導指針は行政指導であって強制力がなく、それを理解し、指導に対して改善に向け
た対応をなかなか取っていただけない事業者が一定程度ある。そうした場合、行政処
分を検討するが、処分基準が不明確な点は課題。
○
入居対象者が広がる中で、指導指針が実効性のあるものとなり、法的環境をもって
個々の住まいに対して適切に介入できる体制を整えることが重要。
○
民間事業者の参入障壁となるような強過ぎる規制は望ましいことではないが、民間の
意欲に水を差さないような形で、質の確保あるいは問題が起きないような方向性で検
討することが重要。
○
指導監督の在り方や囲い込み対策について、一部の不適正な事業者の対応のために、
過度な規制がかかり民間施設全体としての創意工夫や効率性を削ぐことのないよう、
囲い込みの定義も含めて、慎重に検討するべき。
○
民間の創意工夫を損なわずにサービスの質を確保するという観点から、規制を一律に
強化することが難しい側面もある。指導指針には、「適当な数」あるいは「適当な規
模」といった、曖昧で解釈の幅が広い表現が多用されており、また、明確な基準がな
く、確実な指導が難しいという意見もあったことから、まずは、文言の整理・修正等
17