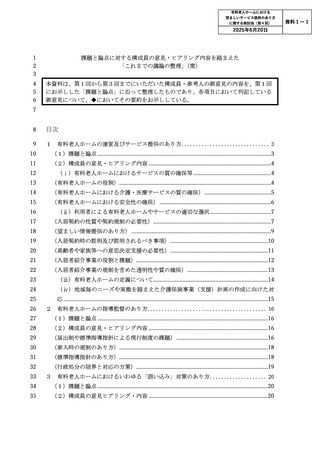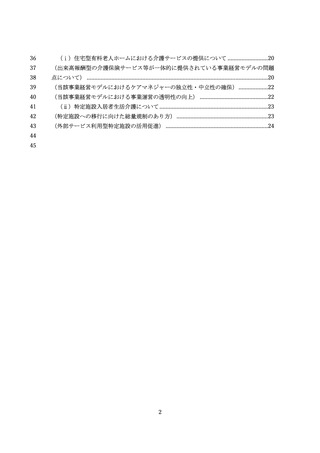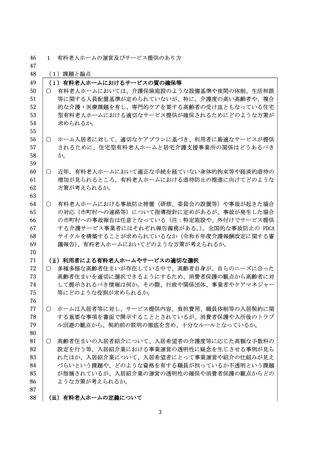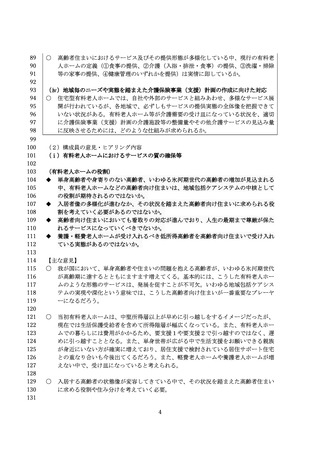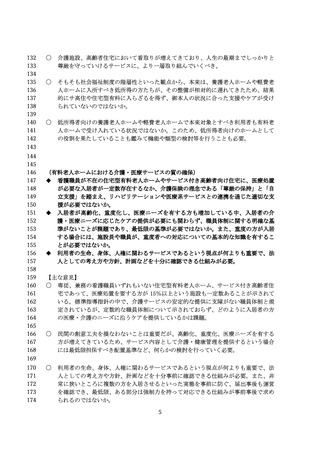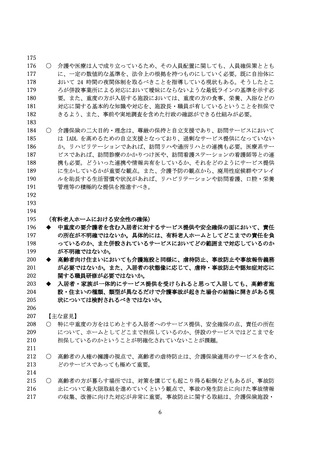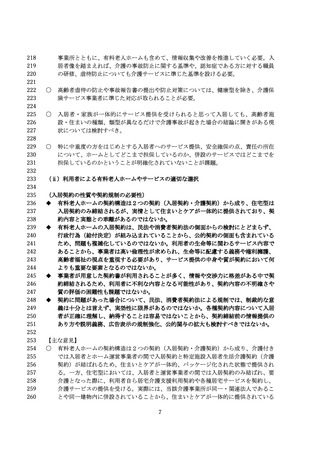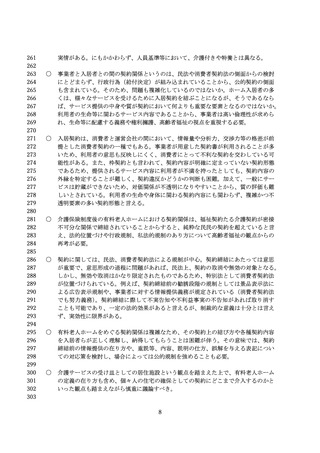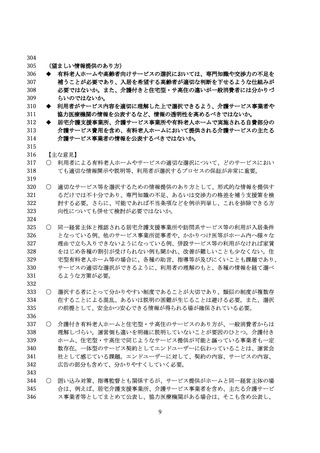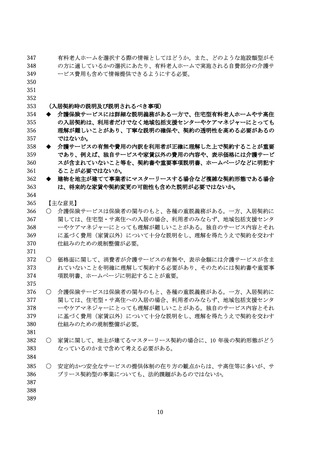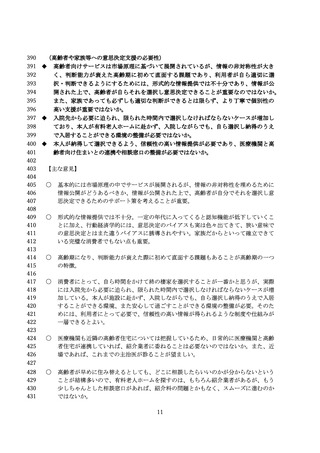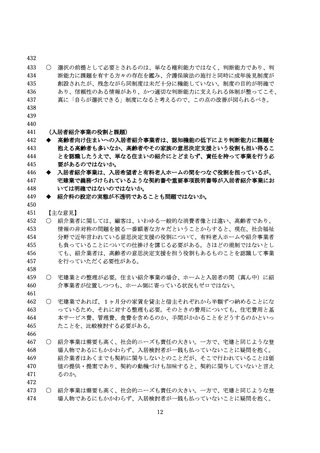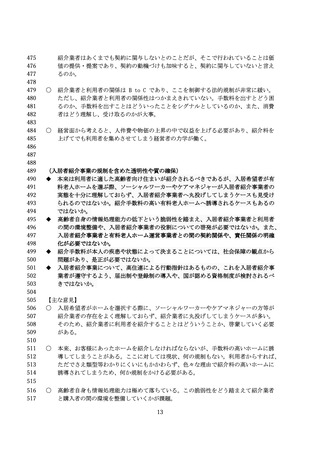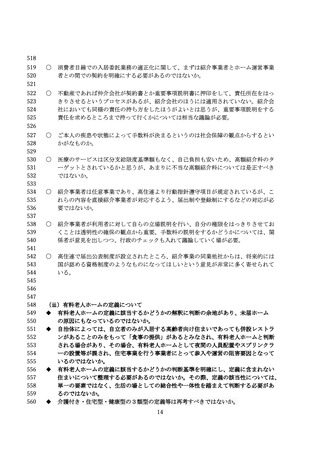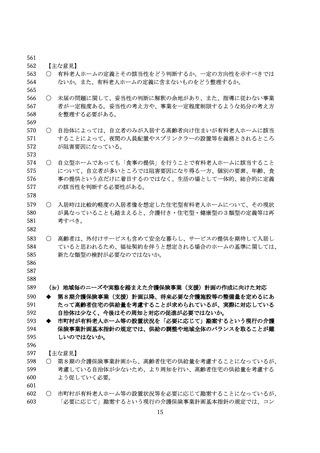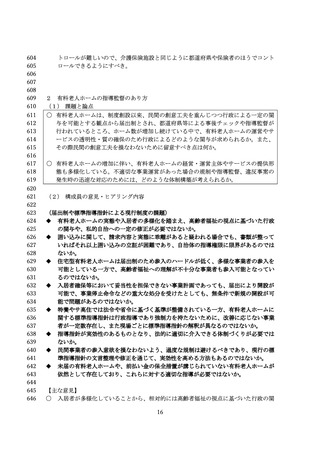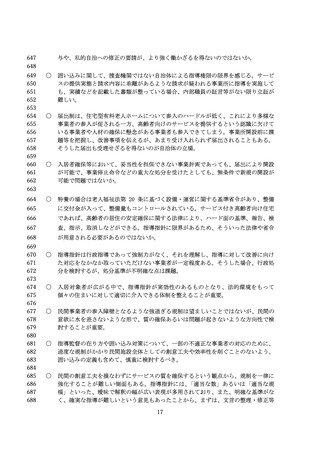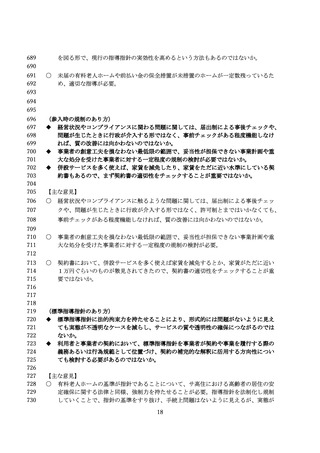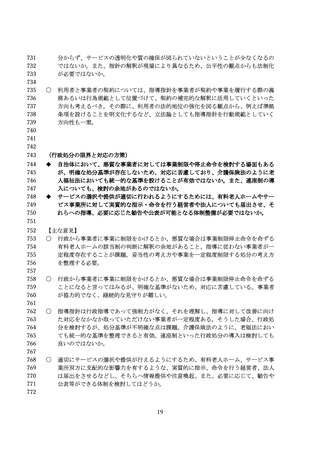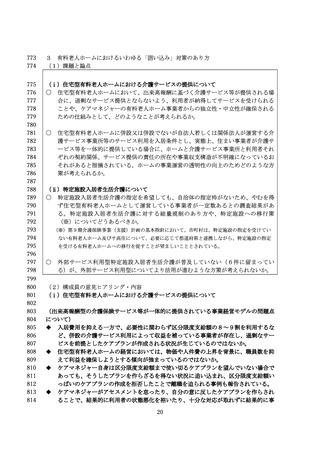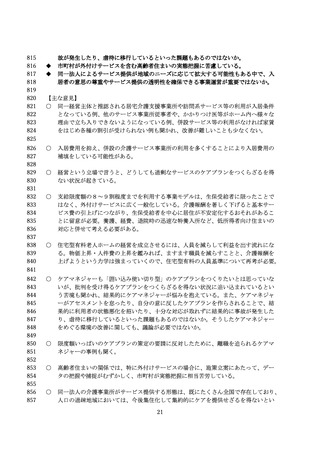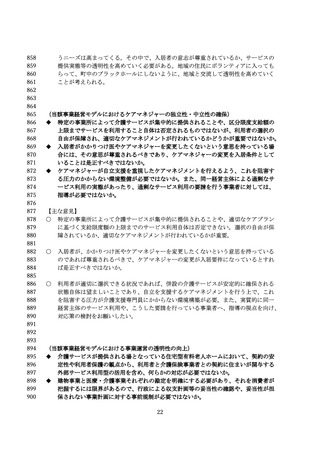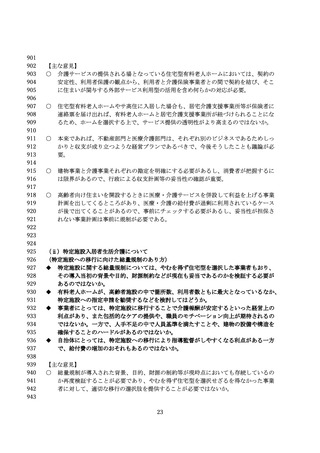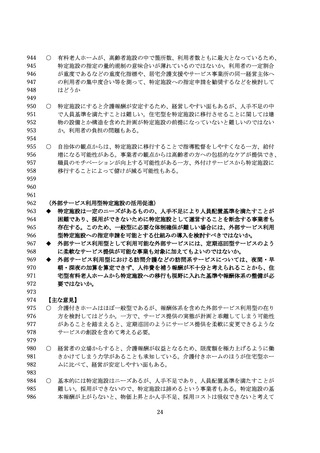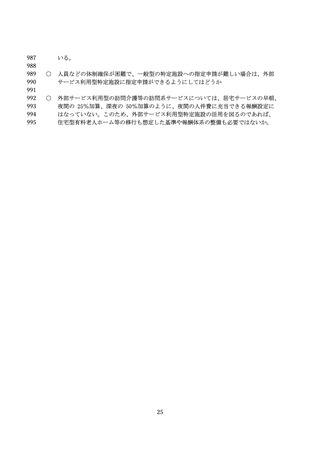よむ、つかう、まなぶ。
資料1-1 課題と論点に対する構成員の意見・ヒアリング内容を踏まえた これまでの議論の整理(案) (8 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59007.html |
| 出典情報 | 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第4回 6/20)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
実情がある。にもかかわらず、人員基準等において、介護付きや特養とは異なる。
○
事業者と入居者との間の契約関係というのは、民法や消費者契約法の側面からの検討
にとどまらず、行政行為(給付決定)が組み込まれていることから、公的契約の側面
も含まれている。そのため、問題も複雑化しているのではないか。ホーム入居者の多
くは、様々なサービスを受けるために入居契約を結ぶことになるが、そうであるなら
ば、サービス提供の中身や質が契約において何よりも重要な要素となるのではないか。
利用者の生命等に関わるサービス内容であることから、事業者は高い倫理性が求めら
れ、生命等に配慮する義務や権利擁護、高齢者福祉の視点を重視する必要。
○
入居契約は、消費者と運営会社の間において、情報量や分析力、交渉力等の格差が前
提とした消費者契約の一種でもある。事業者が用意した契約書が利用されることが多
いため、利用者の意思も反映しにくく、消費者にとって不利な契約を交わしている可
能性がある。また、枠契約とも言われて、契約内容が明確に定まっていない契約形態
であるため、提供されるサービス内容に利用者が不満を持ったとしても、契約内容の
外縁を特定することが難しく、契約違反かどうかの判断も困難。加えて、一般にサー
ビスは貯蔵ができないため、対価関係が不透明になりやすいことから、質の評価も難
しいとされている。利用者の生命や身体に関わる契約内容にも関わらず、複雑かつ不
透明要素の多い契約形態と言える。
○
介護保険制度後の有料老人ホームにおける契約関係は、福祉契約たる介護契約が密接
不可分な関係で締結されていることからすると、純粋な民民の契約を超えていると言
え、法的位置づけや行政規制、私法的規制のあり方について高齢者福祉の観点からの
再考が必要。
○
契約に関しては、民法、消費者契約法による規制が中心。契約締結にあたっては意思
が重要で、意思形成の過程に問題があれば、民法上、契約の取消や無効の対象となる。
しかし、無効や取消はかなり限定されたものであるため、特別法として消費者契約法
が位置づけられている。例えば、契約締結前の勧誘段階の規制としては景品表示法に
よる広告表示規制や、事業者に対する情報提供義務が規定されている(消費者契約法
でも努力義務)。契約締結に際して不実告知や不利益事実の不告知があれば取り消す
ことも可能であり、一定の法的効果があると言えるが、制裁的な意義は十分とは言え
ず、実効性に限界がある。
○
有料老人ホームをめぐる契約関係は複雑なため、その契約上の結び方や各種契約内容
を入居者らが正しく理解し、納得してもらうことは困難が伴う。その意味では、契約
締結前の情報提供の在り方や、重説等、内容、説明の仕方、誤解を与える表記につい
ての対応策を検討し、場合によっては公的規制を強めることも必要。
○
介護サービスの受け皿としての居住施設という観点を踏まえた上で、有料老人ホーム
の定義の在り方も含め、個々人の住宅の確保としての契約にどこまで介入するのかと
いった観点も踏まえながら慎重に議論すべき。
8
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
実情がある。にもかかわらず、人員基準等において、介護付きや特養とは異なる。
○
事業者と入居者との間の契約関係というのは、民法や消費者契約法の側面からの検討
にとどまらず、行政行為(給付決定)が組み込まれていることから、公的契約の側面
も含まれている。そのため、問題も複雑化しているのではないか。ホーム入居者の多
くは、様々なサービスを受けるために入居契約を結ぶことになるが、そうであるなら
ば、サービス提供の中身や質が契約において何よりも重要な要素となるのではないか。
利用者の生命等に関わるサービス内容であることから、事業者は高い倫理性が求めら
れ、生命等に配慮する義務や権利擁護、高齢者福祉の視点を重視する必要。
○
入居契約は、消費者と運営会社の間において、情報量や分析力、交渉力等の格差が前
提とした消費者契約の一種でもある。事業者が用意した契約書が利用されることが多
いため、利用者の意思も反映しにくく、消費者にとって不利な契約を交わしている可
能性がある。また、枠契約とも言われて、契約内容が明確に定まっていない契約形態
であるため、提供されるサービス内容に利用者が不満を持ったとしても、契約内容の
外縁を特定することが難しく、契約違反かどうかの判断も困難。加えて、一般にサー
ビスは貯蔵ができないため、対価関係が不透明になりやすいことから、質の評価も難
しいとされている。利用者の生命や身体に関わる契約内容にも関わらず、複雑かつ不
透明要素の多い契約形態と言える。
○
介護保険制度後の有料老人ホームにおける契約関係は、福祉契約たる介護契約が密接
不可分な関係で締結されていることからすると、純粋な民民の契約を超えていると言
え、法的位置づけや行政規制、私法的規制のあり方について高齢者福祉の観点からの
再考が必要。
○
契約に関しては、民法、消費者契約法による規制が中心。契約締結にあたっては意思
が重要で、意思形成の過程に問題があれば、民法上、契約の取消や無効の対象となる。
しかし、無効や取消はかなり限定されたものであるため、特別法として消費者契約法
が位置づけられている。例えば、契約締結前の勧誘段階の規制としては景品表示法に
よる広告表示規制や、事業者に対する情報提供義務が規定されている(消費者契約法
でも努力義務)。契約締結に際して不実告知や不利益事実の不告知があれば取り消す
ことも可能であり、一定の法的効果があると言えるが、制裁的な意義は十分とは言え
ず、実効性に限界がある。
○
有料老人ホームをめぐる契約関係は複雑なため、その契約上の結び方や各種契約内容
を入居者らが正しく理解し、納得してもらうことは困難が伴う。その意味では、契約
締結前の情報提供の在り方や、重説等、内容、説明の仕方、誤解を与える表記につい
ての対応策を検討し、場合によっては公的規制を強めることも必要。
○
介護サービスの受け皿としての居住施設という観点を踏まえた上で、有料老人ホーム
の定義の在り方も含め、個々人の住宅の確保としての契約にどこまで介入するのかと
いった観点も踏まえながら慎重に議論すべき。
8