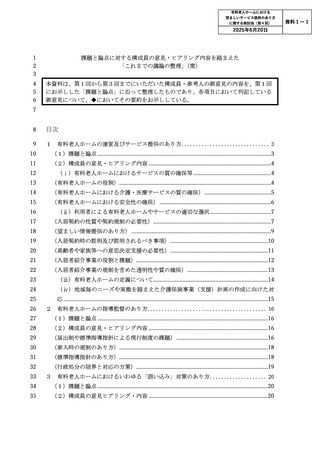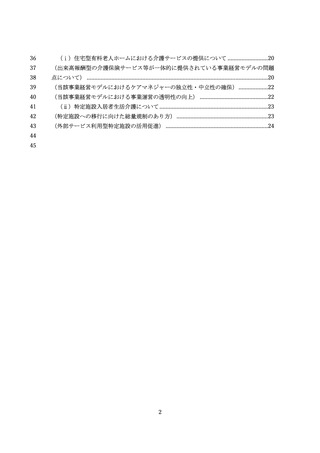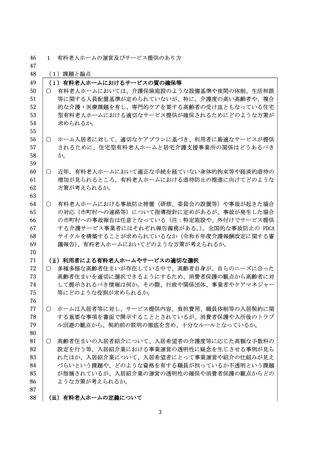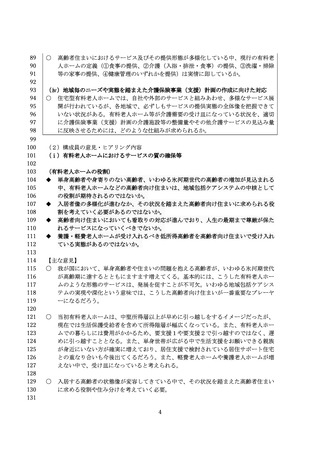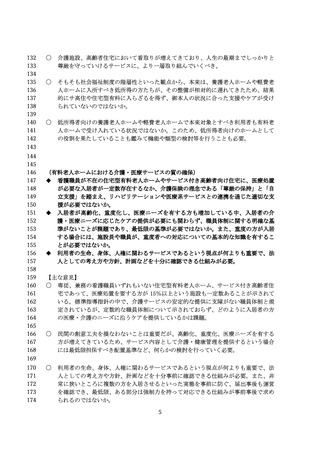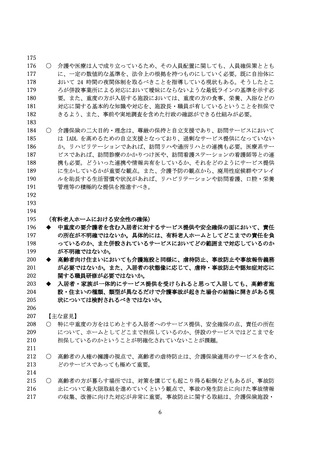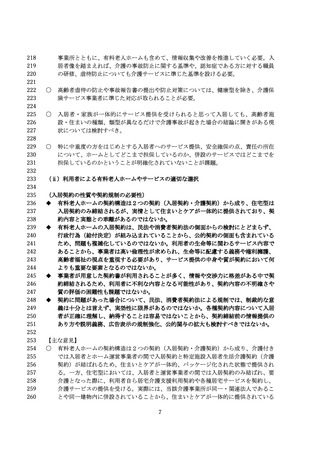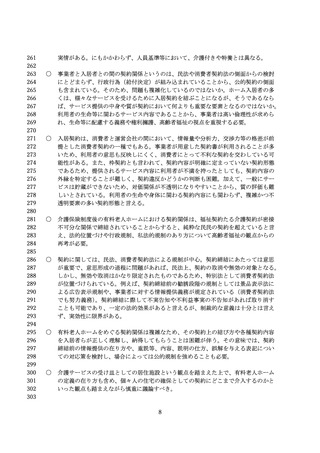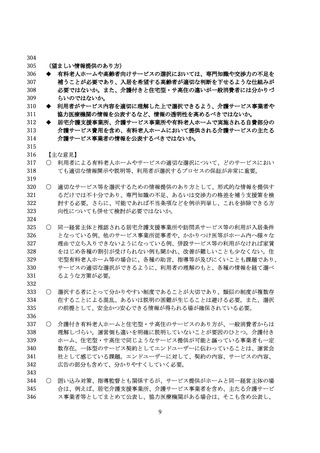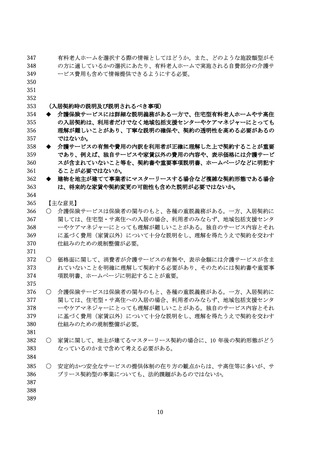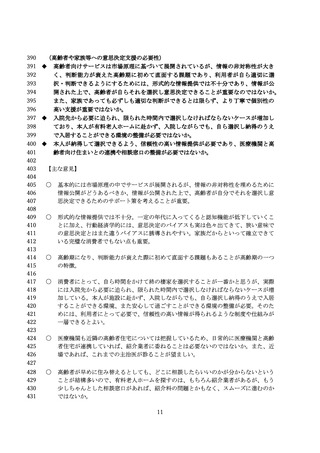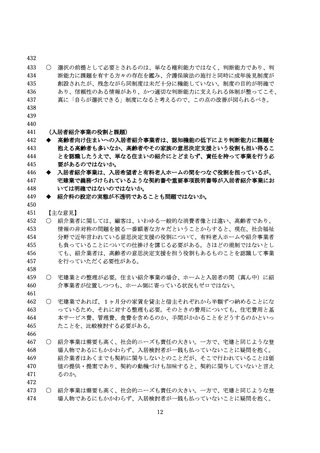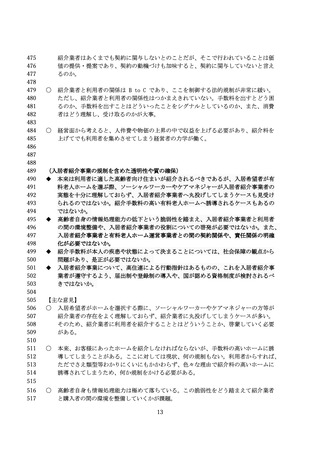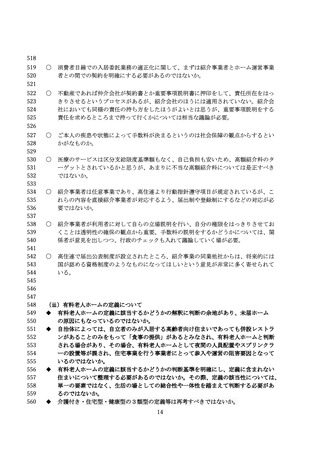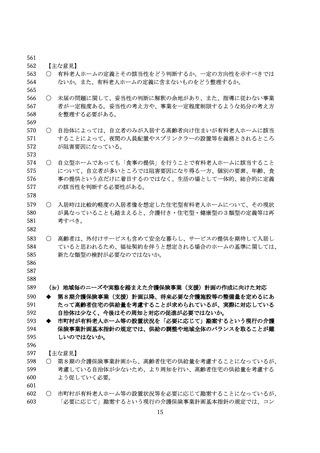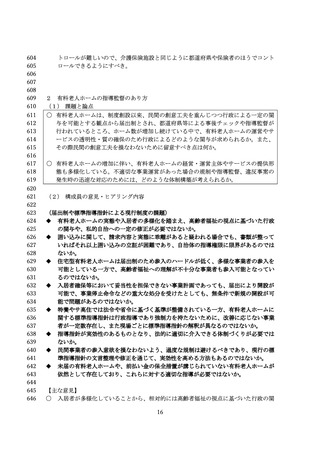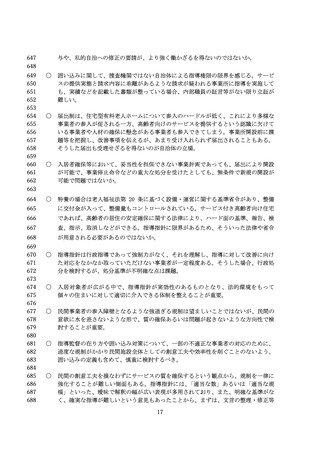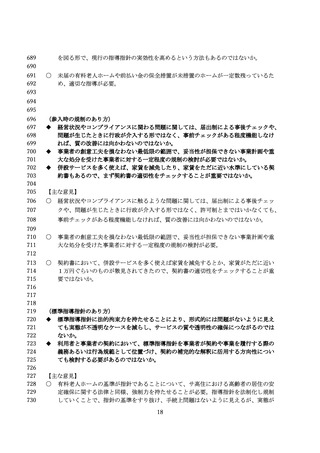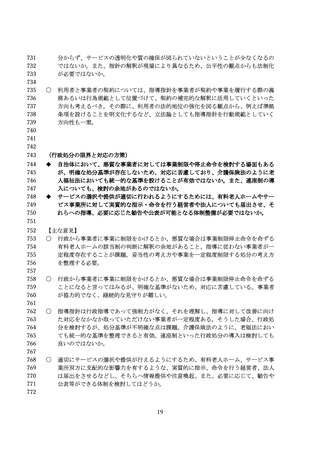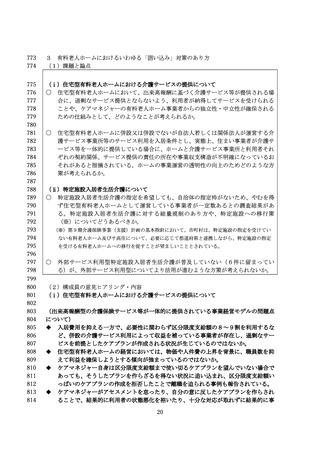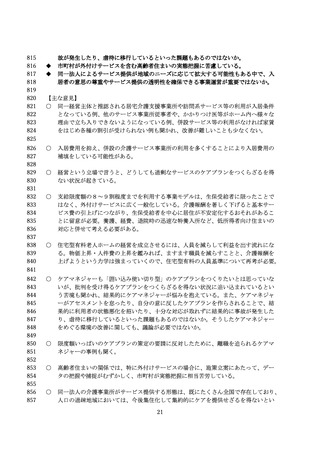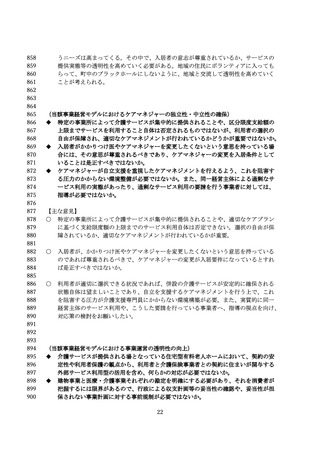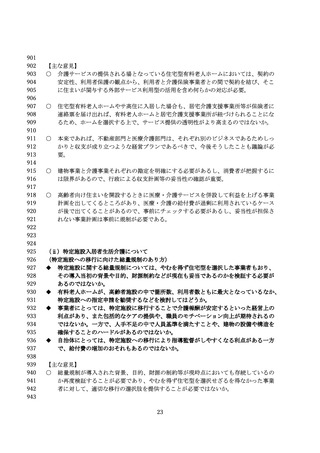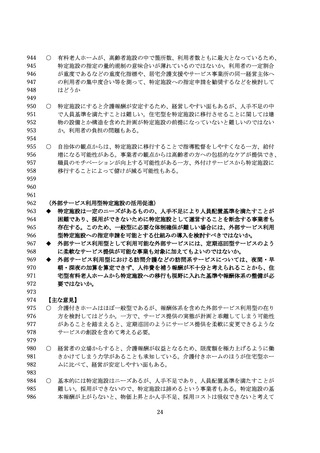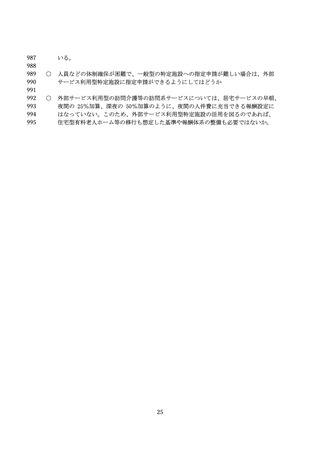よむ、つかう、まなぶ。
資料1-1 課題と論点に対する構成員の意見・ヒアリング内容を踏まえた これまでの議論の整理(案) (15 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59007.html |
| 出典情報 | 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第4回 6/20)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
【主な意見】
○ 有料老人ホームの定義とその該当性をどう判断するか、一定の方向性を示すべきでは
ないか。また、有料老人ホームの定義に含まないものをどう整理するか。
○
未届の問題に関して、妥当性の判断に解釈の余地があり、また、指導に従わない事業
者が一定程度ある。妥当性の考え方や、事業を一定程度制限するような処分の考え方
を整理する必要がある。
○
自治体によっては、自立者のみが入居する高齢者向け住まいが有料老人ホームに該当
することによって、夜間の人員配置やスプリンクラーの設置等を義務とされるところ
が阻害要因になっている。
○
自立型ホームであっても「食事の提供」を行うことで有料老人ホームに該当すること
について、自立者が多いところでは阻害要因になり得る一方、個別の要素、年齢、食
事の提供という点だけに着目するのではなく、生活の場として一体的、総合的に定義
の該当性を判断する必要性がある。
○
入居時は比較的軽度の入居者像を想定した住宅型有料老人ホームについて、その現状
が異なっていることも踏まえると、介護付き・住宅型・健康型の3類型の定義等は再
考すべき。
583
584
585
586
587
588
589
○
高齢者は、外付けサービスも含めて安全な暮らし、サービスの提供を期待して入居し
ていると思われるため、福祉契約を伴うと想定される場合のホームの基準に関しては、
新たな類型の検討が必要なのではないか。
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
◆
579
580
581
582
(ⅳ)地域毎のニーズや実態を踏まえた介護保険事業(支援)計画の作成に向けた対応
◆
第8期介護保険事業(支援)計画以降、将来必要な介護施設等の整備量を定めるにあ
たって高齢者住宅の供給量を考慮することが求められているが、実際に対応している
自治体は少なく、今後はその周知と対応の促進が必要ではないか。
市町村が有料老人ホーム等の設置状況を「必要に応じて」勘案するという現行の介護
保険事業計画基本指針の規定では、供給の調整や地域全体のバランスを取ることが難
しいのではないか。
【主な意見】
○ 第8期の介護保険事業計画から、高齢者住宅の供給量を考慮することになっているが、
考慮している自治体が少ないため、より周知を行い、高齢者住宅の供給量を考慮する
よう促していく必要。
○
市町村が有料老人ホーム等の設置状況等を必要に応じて勘案することになっているが、
「必要に応じて」勘案するという現行の介護保険事業計画基本指針の規定では、コン
15
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
【主な意見】
○ 有料老人ホームの定義とその該当性をどう判断するか、一定の方向性を示すべきでは
ないか。また、有料老人ホームの定義に含まないものをどう整理するか。
○
未届の問題に関して、妥当性の判断に解釈の余地があり、また、指導に従わない事業
者が一定程度ある。妥当性の考え方や、事業を一定程度制限するような処分の考え方
を整理する必要がある。
○
自治体によっては、自立者のみが入居する高齢者向け住まいが有料老人ホームに該当
することによって、夜間の人員配置やスプリンクラーの設置等を義務とされるところ
が阻害要因になっている。
○
自立型ホームであっても「食事の提供」を行うことで有料老人ホームに該当すること
について、自立者が多いところでは阻害要因になり得る一方、個別の要素、年齢、食
事の提供という点だけに着目するのではなく、生活の場として一体的、総合的に定義
の該当性を判断する必要性がある。
○
入居時は比較的軽度の入居者像を想定した住宅型有料老人ホームについて、その現状
が異なっていることも踏まえると、介護付き・住宅型・健康型の3類型の定義等は再
考すべき。
583
584
585
586
587
588
589
○
高齢者は、外付けサービスも含めて安全な暮らし、サービスの提供を期待して入居し
ていると思われるため、福祉契約を伴うと想定される場合のホームの基準に関しては、
新たな類型の検討が必要なのではないか。
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
◆
579
580
581
582
(ⅳ)地域毎のニーズや実態を踏まえた介護保険事業(支援)計画の作成に向けた対応
◆
第8期介護保険事業(支援)計画以降、将来必要な介護施設等の整備量を定めるにあ
たって高齢者住宅の供給量を考慮することが求められているが、実際に対応している
自治体は少なく、今後はその周知と対応の促進が必要ではないか。
市町村が有料老人ホーム等の設置状況を「必要に応じて」勘案するという現行の介護
保険事業計画基本指針の規定では、供給の調整や地域全体のバランスを取ることが難
しいのではないか。
【主な意見】
○ 第8期の介護保険事業計画から、高齢者住宅の供給量を考慮することになっているが、
考慮している自治体が少ないため、より周知を行い、高齢者住宅の供給量を考慮する
よう促していく必要。
○
市町村が有料老人ホーム等の設置状況等を必要に応じて勘案することになっているが、
「必要に応じて」勘案するという現行の介護保険事業計画基本指針の規定では、コン
15