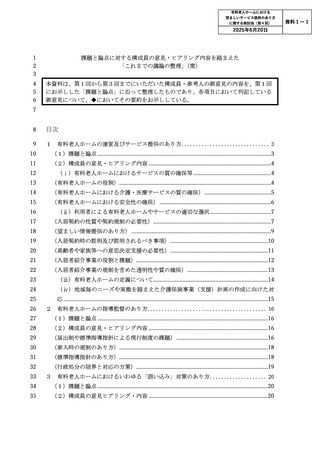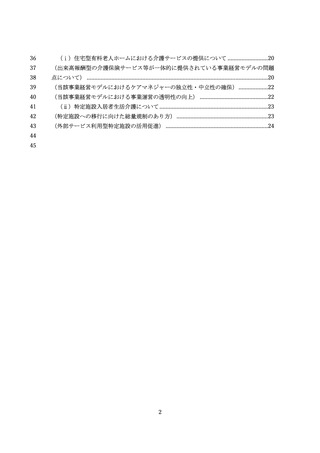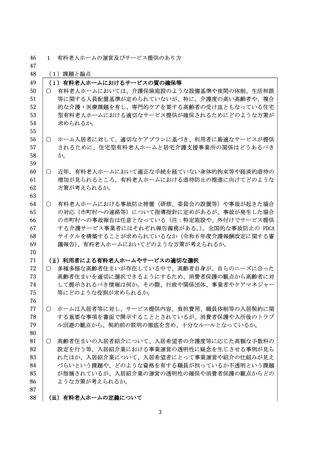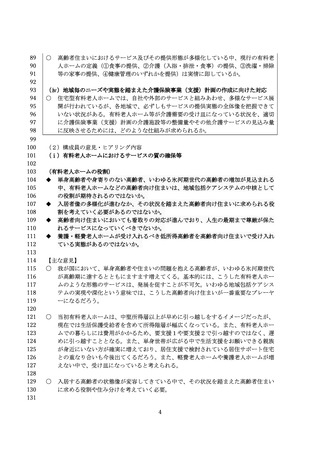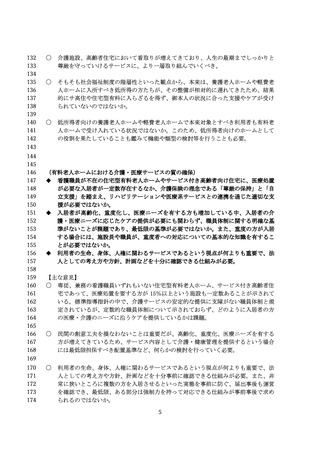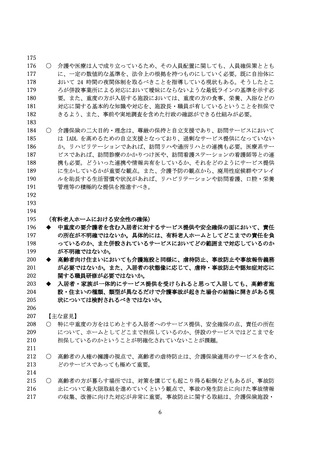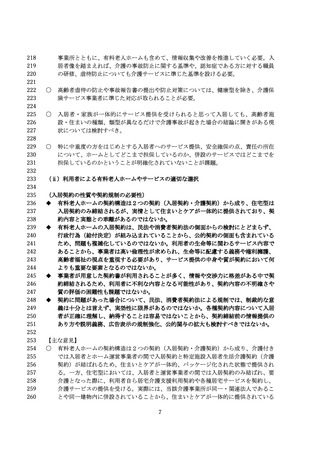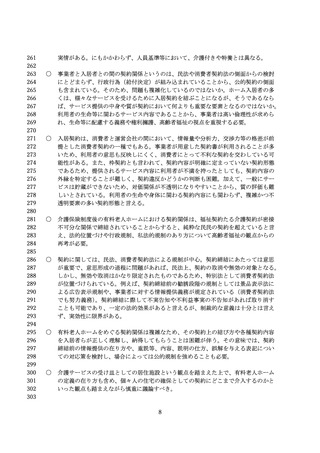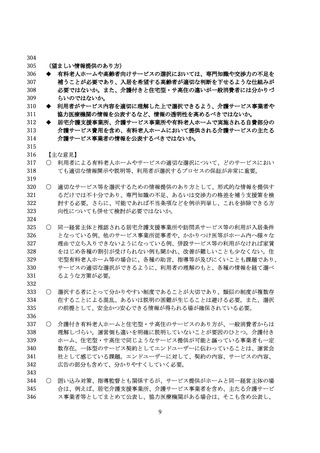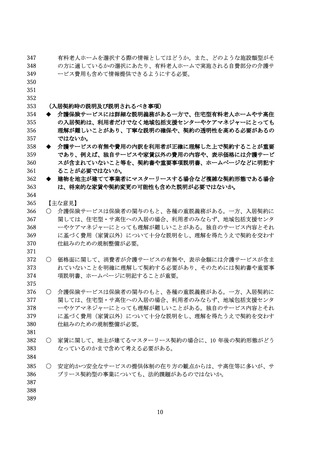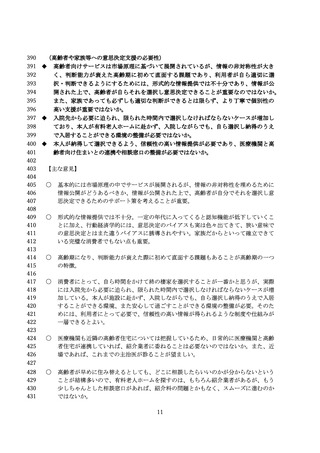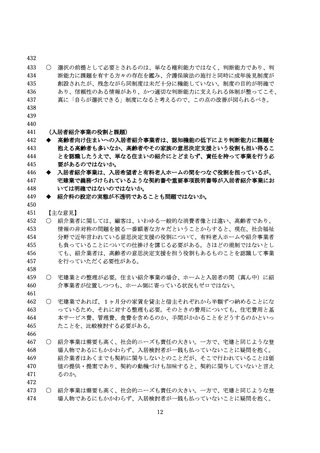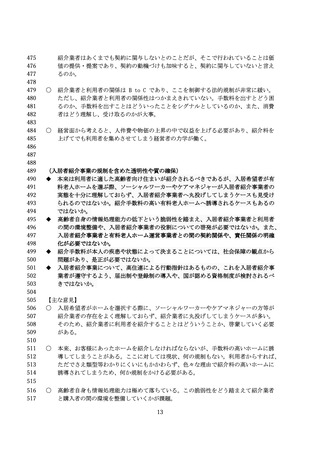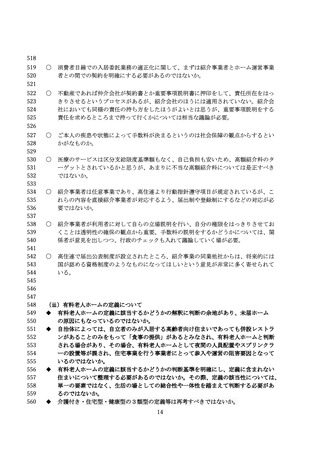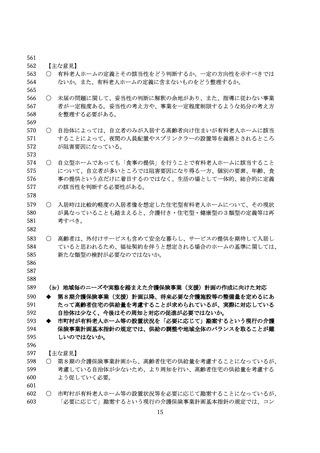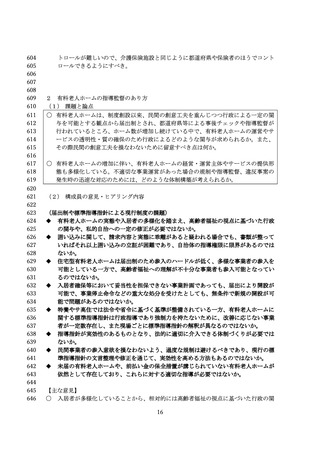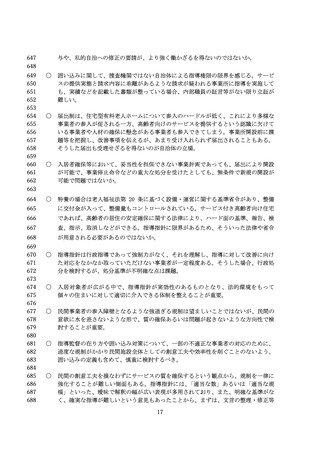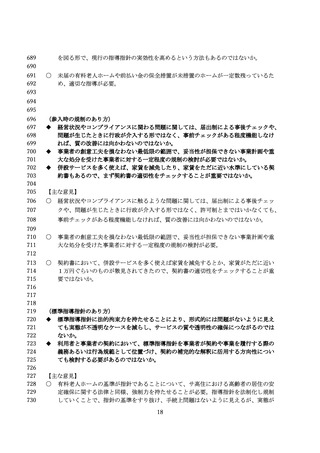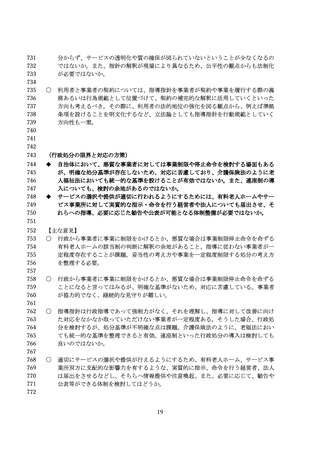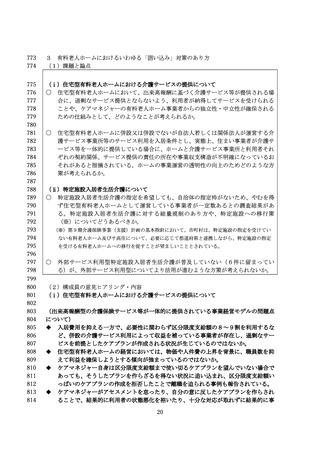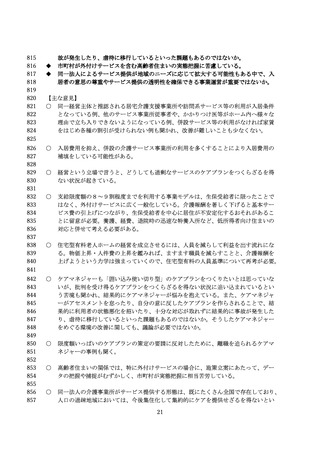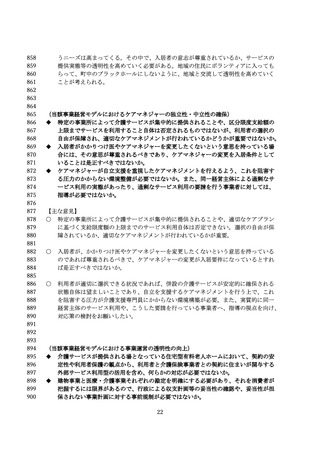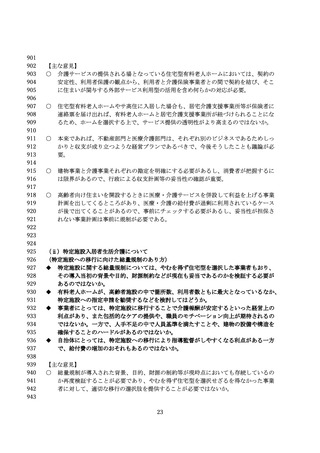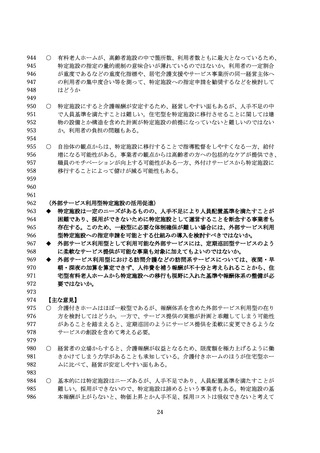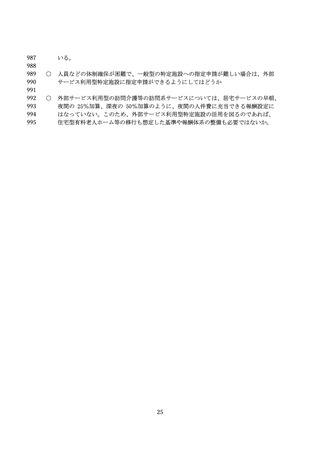よむ、つかう、まなぶ。
資料1-1 課題と論点に対する構成員の意見・ヒアリング内容を踏まえた これまでの議論の整理(案) (23 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59007.html |
| 出典情報 | 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第4回 6/20)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
【主な意見】
○ 介護サービスの提供される場となっている住宅型有料老人ホームにおいては、契約の
安定性、利用者保護の観点から、利用者と介護保険事業者との間で契約を結び、そこ
に住まいが関与する外部サービス利用型の活用を含め何らかの対応が必要。
○
住宅型有料老人ホームやサ高住に入居した場合も、居宅介護支援事業所等が保険者に
連絡票を届け出れば、有料老人ホームと居宅介護支援事業所が紐づけられることにな
るため、ホームを選択する上で、サービス提供の透明性がより高まるのではないか。
○
本来であれば、不動産部門と医療介護部門は、それぞれ別のビジネスであるためしっ
かりと収支が成り立つような経営プランであるべきで、今後そうしたことも議論が必
要。
○
建物事業と介護事業それぞれの勘定を明確にする必要があるし、消費者が把握するに
は限界があるので、行政による収支計画等の妥当性の確認が重要。
○
高齢者向け住まいを開設するときに医療・介護サービスを併設して利益を上げる事業
計画を出してくるところがあり、医療・介護の給付費が過剰に利用されているケース
が後で出てくることがあるので、事前にチェックする必要があるし、妥当性が担保さ
れない事業計画は事前に規制が必要である。
(ⅱ)特定施設入居者生活介護について
(特定施設への移行に向けた総量規制のあり方)
◆ 特定施設に関する総量規制については、やむを得ず住宅型を選択した事業者もおり、
その導入当初の背景や目的、財源制約などが現在も妥当であるのかを検証する必要が
あるのではないか。
◆ 有料老人ホームが、高齢者施設の中で箇所数、利用者数ともに最大となっているなか、
特定施設への指定申請を勧奨するなどを検討してはどうか。
◆ 事業者にとっては、特定施設に移行することで介護報酬が安定するといった経営上の
利点があり、また包括的なケアの提供や、職員のモチベーション向上が期待されるの
ではないか。一方で、人手不足の中で人員基準を満たすことや、建物の設備や構造を
確保することのハードルがあるのではないか。
◆ 自治体にとっては、特定施設への移行により指導監督がしやすくなる利点がある一方
で、給付費の増加のおそれもあるのではないか。
【主な意見】
○ 総量規制が導入された背景、目的、財源の制約等が現時点においても存続しているの
か再度検証することが必要であり、やむを得ず住宅型を選択せざるを得なかった事業
者に対して、適切な移行の選択肢を提供することが必要ではないか。
23
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
【主な意見】
○ 介護サービスの提供される場となっている住宅型有料老人ホームにおいては、契約の
安定性、利用者保護の観点から、利用者と介護保険事業者との間で契約を結び、そこ
に住まいが関与する外部サービス利用型の活用を含め何らかの対応が必要。
○
住宅型有料老人ホームやサ高住に入居した場合も、居宅介護支援事業所等が保険者に
連絡票を届け出れば、有料老人ホームと居宅介護支援事業所が紐づけられることにな
るため、ホームを選択する上で、サービス提供の透明性がより高まるのではないか。
○
本来であれば、不動産部門と医療介護部門は、それぞれ別のビジネスであるためしっ
かりと収支が成り立つような経営プランであるべきで、今後そうしたことも議論が必
要。
○
建物事業と介護事業それぞれの勘定を明確にする必要があるし、消費者が把握するに
は限界があるので、行政による収支計画等の妥当性の確認が重要。
○
高齢者向け住まいを開設するときに医療・介護サービスを併設して利益を上げる事業
計画を出してくるところがあり、医療・介護の給付費が過剰に利用されているケース
が後で出てくることがあるので、事前にチェックする必要があるし、妥当性が担保さ
れない事業計画は事前に規制が必要である。
(ⅱ)特定施設入居者生活介護について
(特定施設への移行に向けた総量規制のあり方)
◆ 特定施設に関する総量規制については、やむを得ず住宅型を選択した事業者もおり、
その導入当初の背景や目的、財源制約などが現在も妥当であるのかを検証する必要が
あるのではないか。
◆ 有料老人ホームが、高齢者施設の中で箇所数、利用者数ともに最大となっているなか、
特定施設への指定申請を勧奨するなどを検討してはどうか。
◆ 事業者にとっては、特定施設に移行することで介護報酬が安定するといった経営上の
利点があり、また包括的なケアの提供や、職員のモチベーション向上が期待されるの
ではないか。一方で、人手不足の中で人員基準を満たすことや、建物の設備や構造を
確保することのハードルがあるのではないか。
◆ 自治体にとっては、特定施設への移行により指導監督がしやすくなる利点がある一方
で、給付費の増加のおそれもあるのではないか。
【主な意見】
○ 総量規制が導入された背景、目的、財源の制約等が現時点においても存続しているの
か再度検証することが必要であり、やむを得ず住宅型を選択せざるを得なかった事業
者に対して、適切な移行の選択肢を提供することが必要ではないか。
23