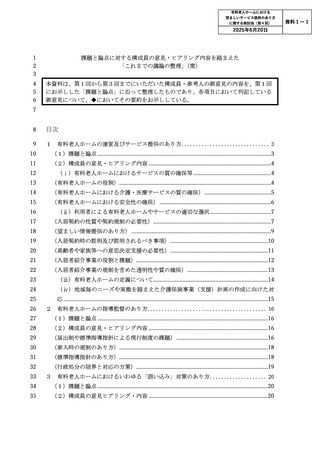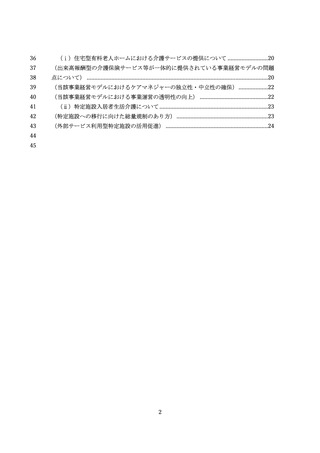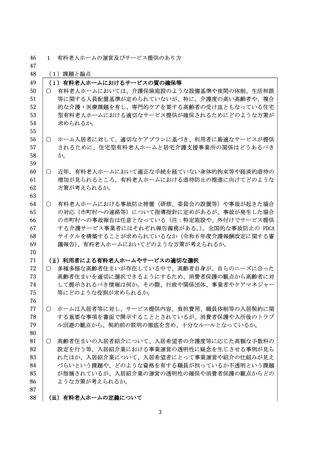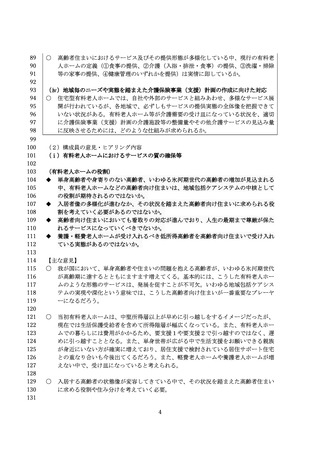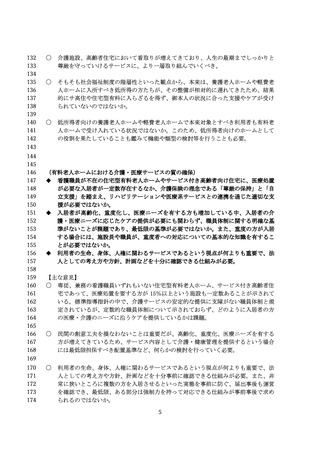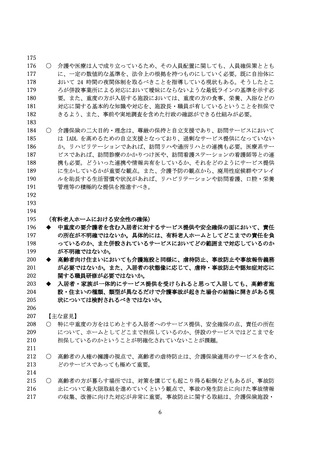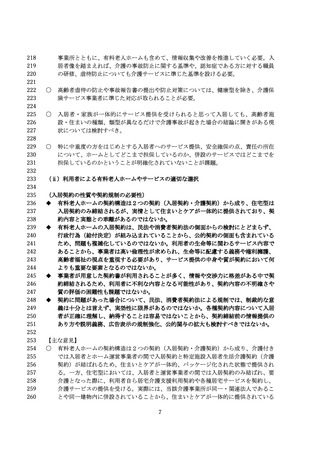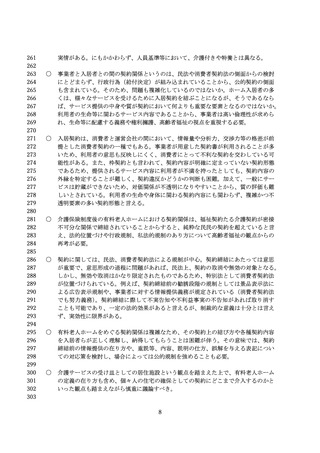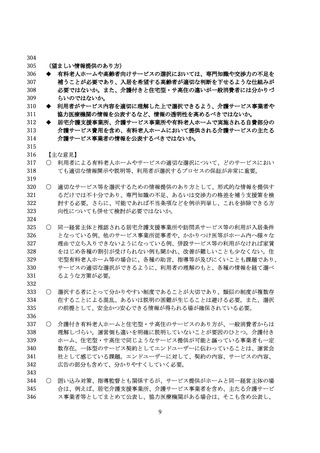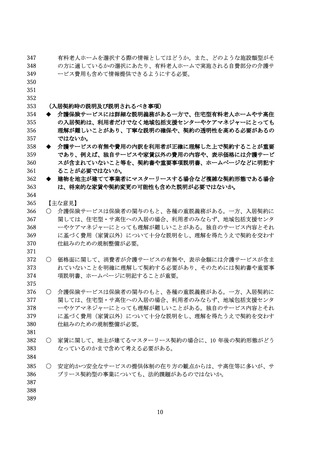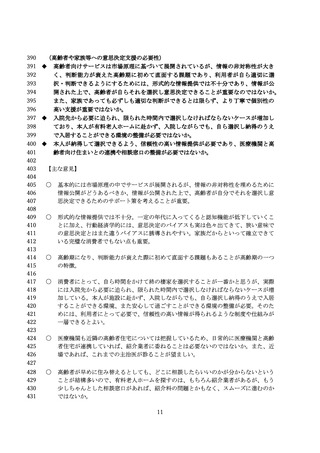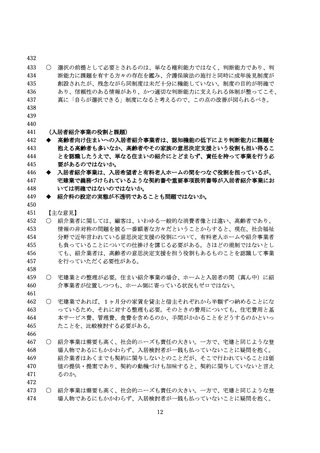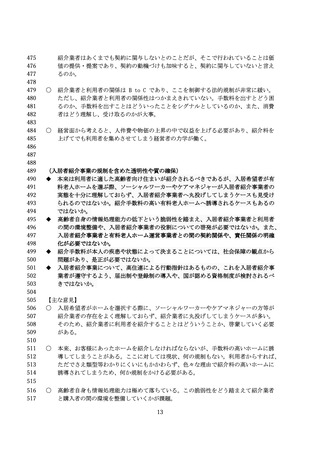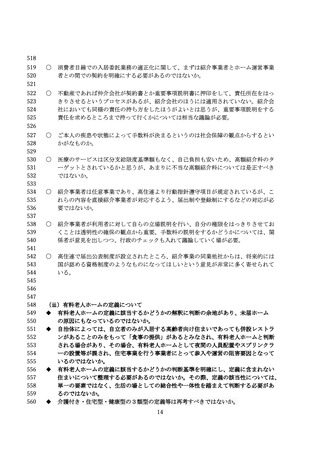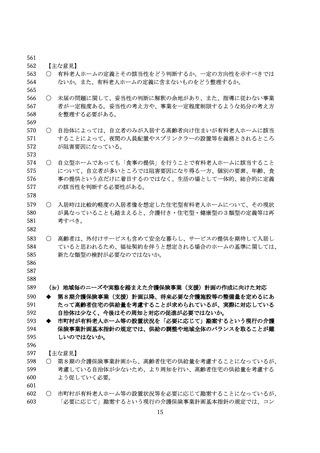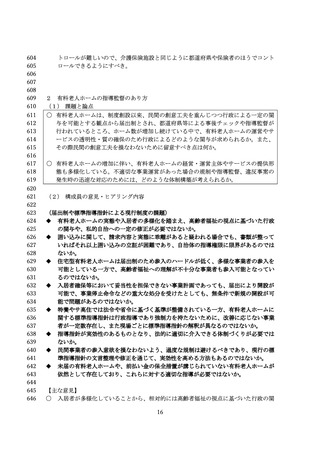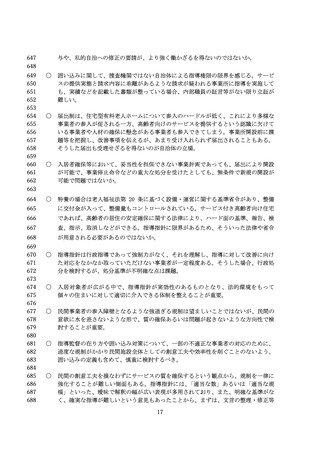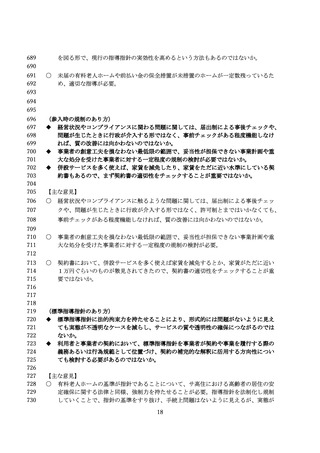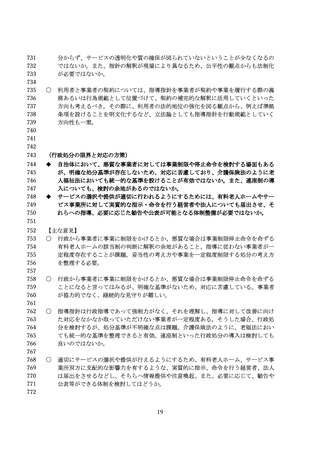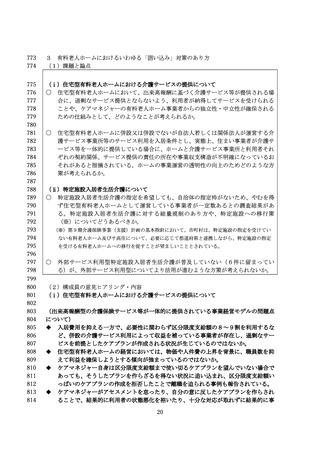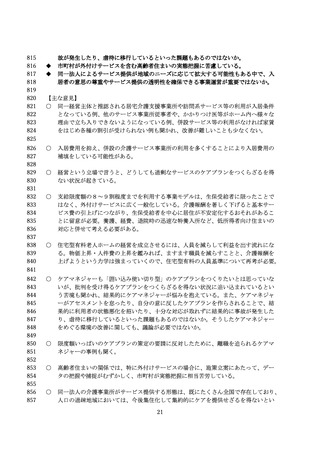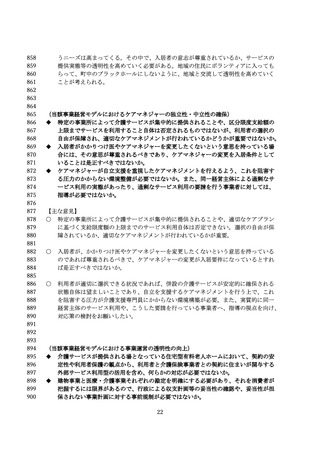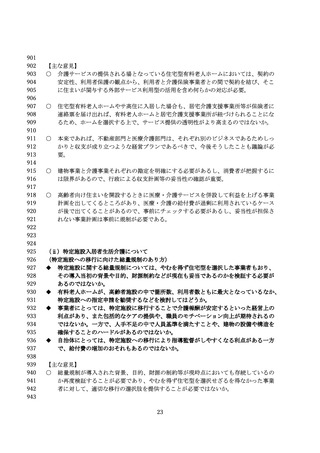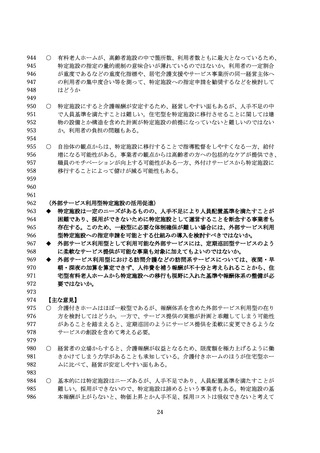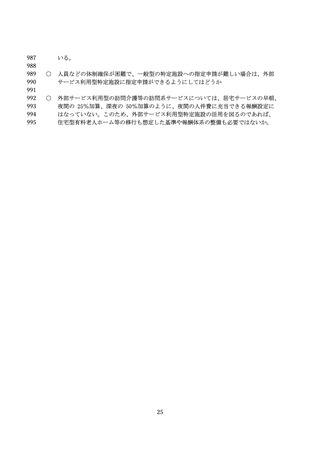よむ、つかう、まなぶ。
資料1-1 課題と論点に対する構成員の意見・ヒアリング内容を踏まえた これまでの議論の整理(案) (21 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59007.html |
| 出典情報 | 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第4回 6/20)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
◆
◆
故が発生したり、虐待に移行しているといった課題もあるのではないか。
市町村が外付けサービスを含む高齢者住まいの実態把握に苦慮している。
同一法人によるサービス提供が地域のニーズに応じて拡大する可能性もある中で、入
居者の意思の尊重やサービス提供の透明性を確保できる事業運営が重要ではないか。
【主な意見】
○ 同一経営主体と推認される居宅介護支援事業所や訪問系サービス等の利用が入居条件
となっている例、他のサービス事業所従事者や、かかりつけ医等がホーム内へ様々な
理由で立ち入りできないようになっている例、併設サービス等の利用がなければ家賃
をはじめ各種の割引が受けられない例も聞かれ、改善が難しいことも少なくない。
○
入居費用を抑え、併設の介護サービス事業所の利用を多くすることにより入居費用の
補填をしている可能性がある。
○
経営という立場で言うと、どうしても過剰なサービスのケアプランをつくらざるを得
ない状況が起きている。
○
支給限度額の8~9割程度までを利用する事業モデルは、生保受給者に限ったことで
はなく、外付けサービスに広く一般化している。介護報酬を著しく下げると基本サー
ビス費の引上げにつながり、生保受給者を中心に居住が不安定化するおそれがあるこ
とに留意が必要。養護、経費、退院時の迅速な特養入所など、低所得者向け住まいの
対応と併せて考える必要がある。
○
住宅型有料老人ホームの経営を成立させるには、人員を減らして利益を出す流れにな
る。物価上昇・人件費の上昇を鑑みれば、ますます職員を減らすことと、介護報酬を
上げようという力学は強まっていくので、住宅型有料の人員基準について再考が必要。
○
ケアマネジャーも「囲い込み使い切り型」のケアプランをつくりたいとは思っていな
いが、批判を受け得るケアプランをつくらざるを得ない状況に追い込まれているとい
う苦境も聞かれ、結果的にケアマネジャーが悩みを抱えている。また、ケアマネジャ
ーがアセスメントを怠ったり、自分の意に反したケアプランを作らされることで、結
果的に利用者の状態悪化を招いたり、十分な対応が取れずに結果的に事故が発生した
り、虐待に移行しているといった課題もあるのではないか。そうしたケアマネジャー
をめぐる環境の改善に関しても、議論が必要ではないか。
○
限度額いっぱいのケアプランの策定の要請に反対したために、離職を迫られるケアマ
ネジャーの事例も聞く。
○
高齢者住まいの関係では、特に外付けサービスの場合に、施策立案にあたって、デー
タの把握や捕捉がむずかしく、市町村が実態把握に相当苦労している。
○
同一法人の介護事業所がサービス提供する形態は、既にたくさん全国で存在しており、
人口の過疎地域においては、今後集住化して集約的にケアを提供せざるを得ないとい
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
21
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
◆
◆
故が発生したり、虐待に移行しているといった課題もあるのではないか。
市町村が外付けサービスを含む高齢者住まいの実態把握に苦慮している。
同一法人によるサービス提供が地域のニーズに応じて拡大する可能性もある中で、入
居者の意思の尊重やサービス提供の透明性を確保できる事業運営が重要ではないか。
【主な意見】
○ 同一経営主体と推認される居宅介護支援事業所や訪問系サービス等の利用が入居条件
となっている例、他のサービス事業所従事者や、かかりつけ医等がホーム内へ様々な
理由で立ち入りできないようになっている例、併設サービス等の利用がなければ家賃
をはじめ各種の割引が受けられない例も聞かれ、改善が難しいことも少なくない。
○
入居費用を抑え、併設の介護サービス事業所の利用を多くすることにより入居費用の
補填をしている可能性がある。
○
経営という立場で言うと、どうしても過剰なサービスのケアプランをつくらざるを得
ない状況が起きている。
○
支給限度額の8~9割程度までを利用する事業モデルは、生保受給者に限ったことで
はなく、外付けサービスに広く一般化している。介護報酬を著しく下げると基本サー
ビス費の引上げにつながり、生保受給者を中心に居住が不安定化するおそれがあるこ
とに留意が必要。養護、経費、退院時の迅速な特養入所など、低所得者向け住まいの
対応と併せて考える必要がある。
○
住宅型有料老人ホームの経営を成立させるには、人員を減らして利益を出す流れにな
る。物価上昇・人件費の上昇を鑑みれば、ますます職員を減らすことと、介護報酬を
上げようという力学は強まっていくので、住宅型有料の人員基準について再考が必要。
○
ケアマネジャーも「囲い込み使い切り型」のケアプランをつくりたいとは思っていな
いが、批判を受け得るケアプランをつくらざるを得ない状況に追い込まれているとい
う苦境も聞かれ、結果的にケアマネジャーが悩みを抱えている。また、ケアマネジャ
ーがアセスメントを怠ったり、自分の意に反したケアプランを作らされることで、結
果的に利用者の状態悪化を招いたり、十分な対応が取れずに結果的に事故が発生した
り、虐待に移行しているといった課題もあるのではないか。そうしたケアマネジャー
をめぐる環境の改善に関しても、議論が必要ではないか。
○
限度額いっぱいのケアプランの策定の要請に反対したために、離職を迫られるケアマ
ネジャーの事例も聞く。
○
高齢者住まいの関係では、特に外付けサービスの場合に、施策立案にあたって、デー
タの把握や捕捉がむずかしく、市町村が実態把握に相当苦労している。
○
同一法人の介護事業所がサービス提供する形態は、既にたくさん全国で存在しており、
人口の過疎地域においては、今後集住化して集約的にケアを提供せざるを得ないとい
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
21