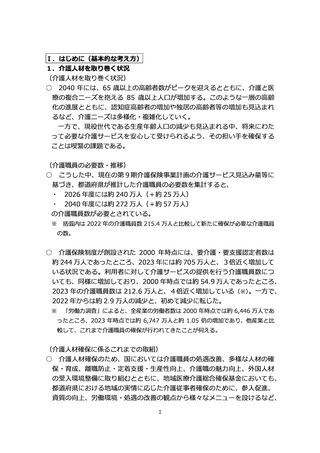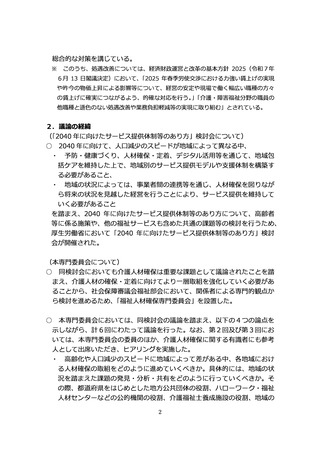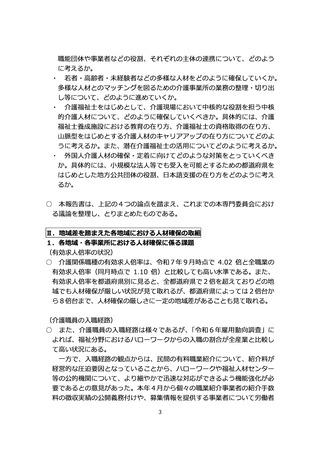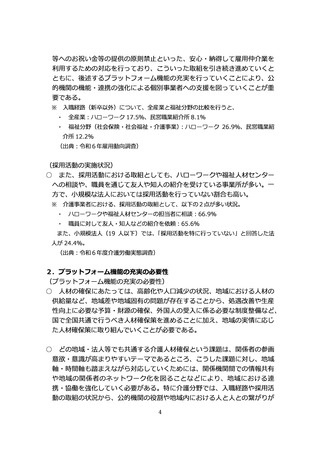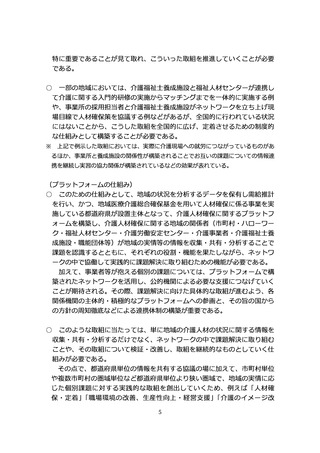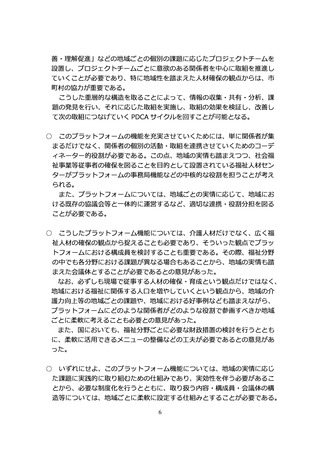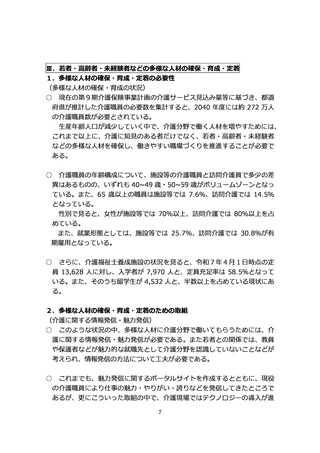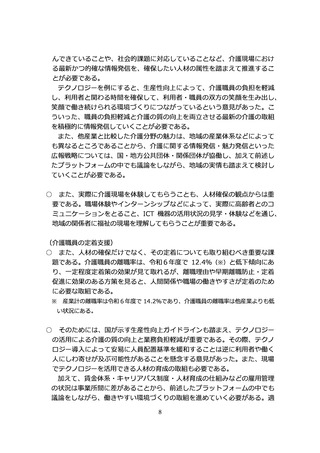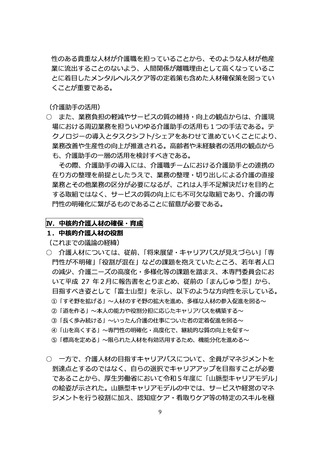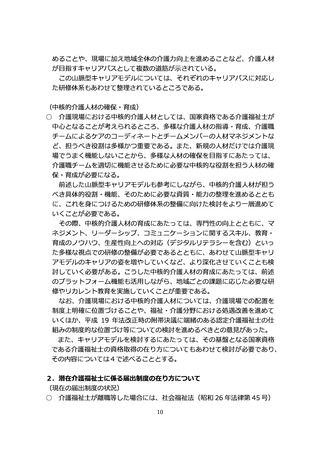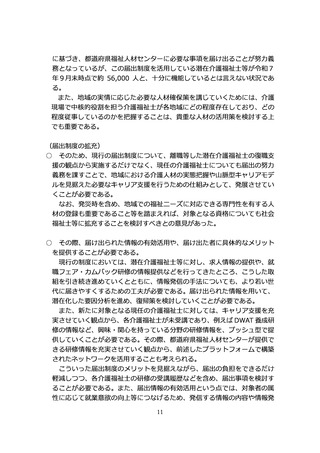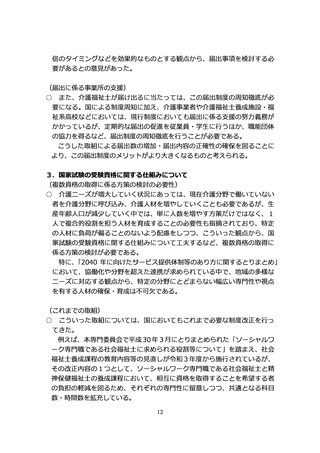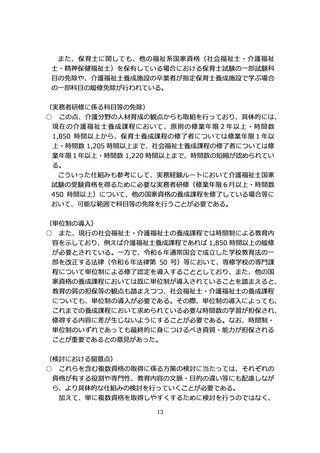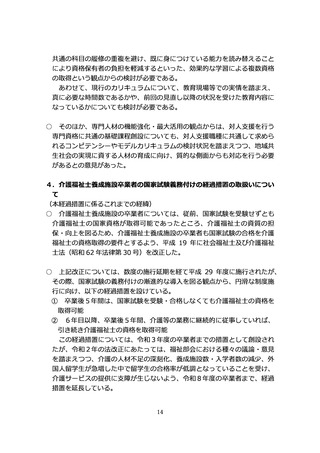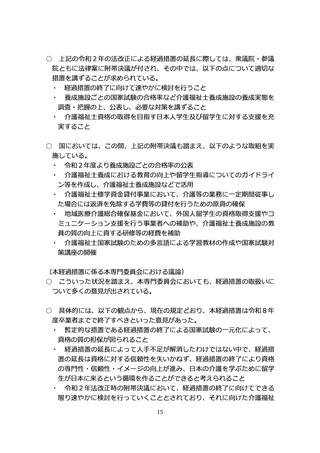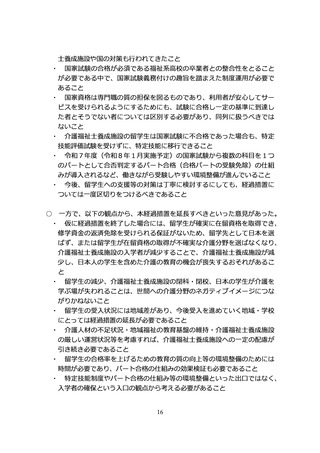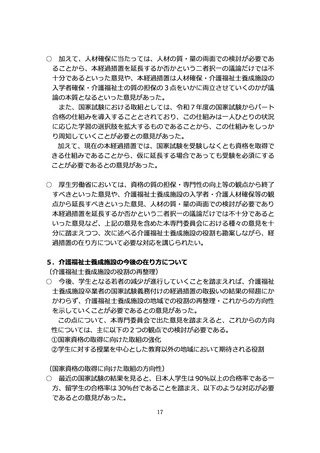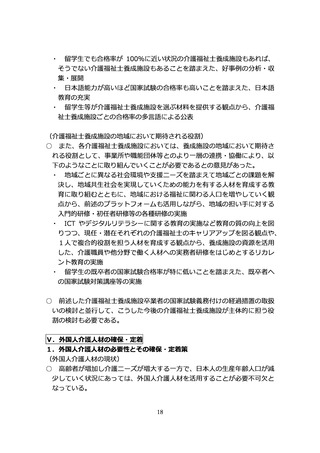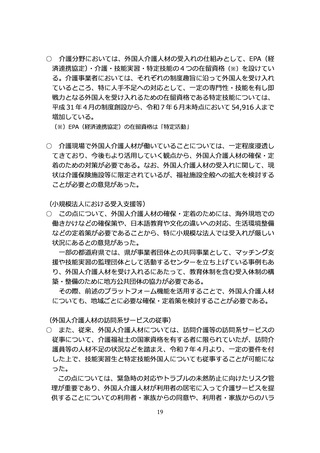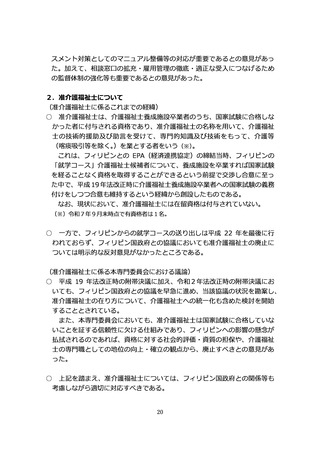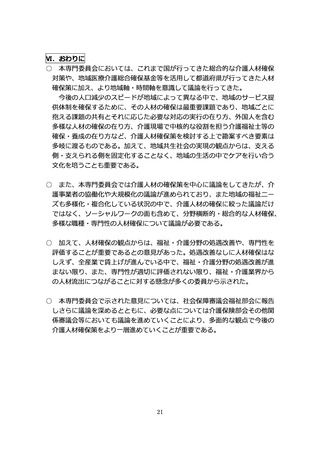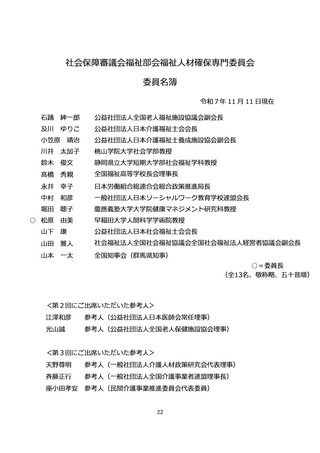よむ、つかう、まなぶ。
資料3-1 福祉人材確保専門委員会における議論の整理 (21 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65945.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 福祉部会(第31回 11/17)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
○
介護分野においては、外国人介護人材の受入れの仕組みとして、EPA(経
済連携協定)・介護・技能実習・特定技能の4つの在留資格(※)を設けてい
る。介護事業者においては、それぞれの制度趣旨に沿って外国人を受け入れ
ているところ、特に人手不足への対応として、一定の専門性・技能を有し即
戦力となる外国人を受け入れるための在留資格である特定技能については、
平成 31 年4月の制度創設から、令和7年6月末時点において 54,916 人まで
増加している。
(※)EPA(経済連携協定)の在留資格は「特定活動」
○
介護現場で外国人介護人材が働いていることについては、一定程度浸透し
てきており、今後もより活用していく観点から、外国人介護人材の確保・定
着のための対策が必要である。なお、外国人介護人材の受入れに関して、現
状は介護保険施設等に限定されているが、福祉施設全般への拡大を検討する
ことが必要との意見があった。
(小規模法人における受入支援等)
○ この点について、外国人介護人材の確保・定着のためには、海外現地での
働きかけなどの確保策や、日本語教育や文化の違いへの対応、生活環境整備
などの定着策が必要であることから、特に小規模な法人では受入れが厳しい
状況にあるとの意見があった。
一部の都道府県では、県が事業者団体との共同事業として、マッチング支
援や技能実習の監理団体として活動するセンターを立ち上げている事例もあ
り、外国人介護人材を受け入れるにあたって、教育体制を含む受入体制の構
築・整備のために地方公共団体の協力が必要である。
その際、前述のプラットフォーム機能を活用することで、外国人介護人材
についても、地域ごとに必要な確保・定着策を検討することが必要である。
(外国人介護人材の訪問系サービスの従事)
○ また、従来、外国人介護人材については、訪問介護等の訪問系サービスの
従事について、介護福祉士の国家資格を有する者に限られていたが、訪問介
護員等の人材不足の状況などを踏まえ、令和7年4月より、一定の要件を付
した上で、技能実習生と特定技能外国人についても従事することが可能にな
った。
この点については、緊急時の対応やトラブルの未然防止に向けたリスク管
理が重要であり、外国人介護人材が利用者の居宅に入って介護サービスを提
供することについての利用者・家族からの同意や、利用者・家族からのハラ
19
介護分野においては、外国人介護人材の受入れの仕組みとして、EPA(経
済連携協定)・介護・技能実習・特定技能の4つの在留資格(※)を設けてい
る。介護事業者においては、それぞれの制度趣旨に沿って外国人を受け入れ
ているところ、特に人手不足への対応として、一定の専門性・技能を有し即
戦力となる外国人を受け入れるための在留資格である特定技能については、
平成 31 年4月の制度創設から、令和7年6月末時点において 54,916 人まで
増加している。
(※)EPA(経済連携協定)の在留資格は「特定活動」
○
介護現場で外国人介護人材が働いていることについては、一定程度浸透し
てきており、今後もより活用していく観点から、外国人介護人材の確保・定
着のための対策が必要である。なお、外国人介護人材の受入れに関して、現
状は介護保険施設等に限定されているが、福祉施設全般への拡大を検討する
ことが必要との意見があった。
(小規模法人における受入支援等)
○ この点について、外国人介護人材の確保・定着のためには、海外現地での
働きかけなどの確保策や、日本語教育や文化の違いへの対応、生活環境整備
などの定着策が必要であることから、特に小規模な法人では受入れが厳しい
状況にあるとの意見があった。
一部の都道府県では、県が事業者団体との共同事業として、マッチング支
援や技能実習の監理団体として活動するセンターを立ち上げている事例もあ
り、外国人介護人材を受け入れるにあたって、教育体制を含む受入体制の構
築・整備のために地方公共団体の協力が必要である。
その際、前述のプラットフォーム機能を活用することで、外国人介護人材
についても、地域ごとに必要な確保・定着策を検討することが必要である。
(外国人介護人材の訪問系サービスの従事)
○ また、従来、外国人介護人材については、訪問介護等の訪問系サービスの
従事について、介護福祉士の国家資格を有する者に限られていたが、訪問介
護員等の人材不足の状況などを踏まえ、令和7年4月より、一定の要件を付
した上で、技能実習生と特定技能外国人についても従事することが可能にな
った。
この点については、緊急時の対応やトラブルの未然防止に向けたリスク管
理が重要であり、外国人介護人材が利用者の居宅に入って介護サービスを提
供することについての利用者・家族からの同意や、利用者・家族からのハラ
19