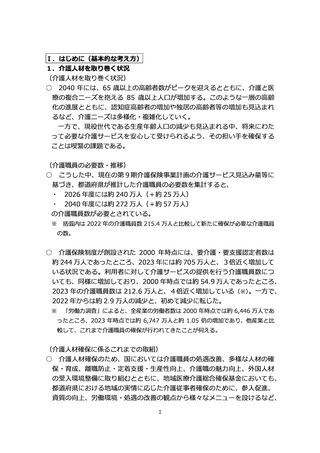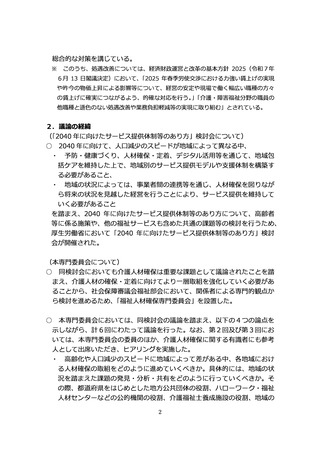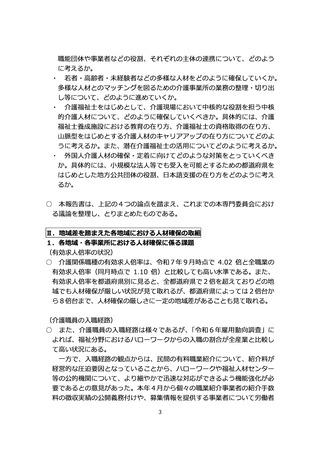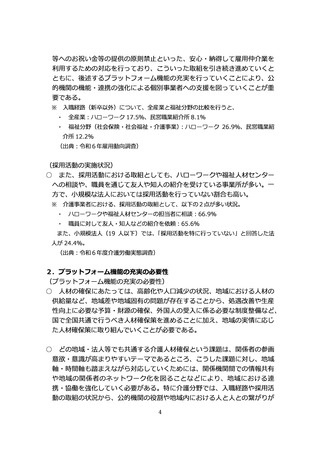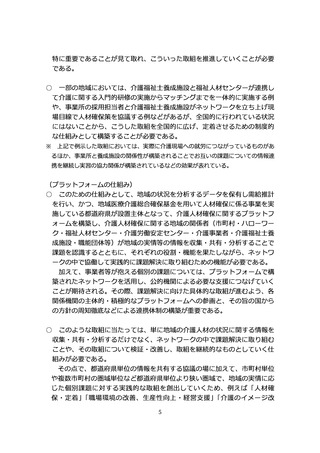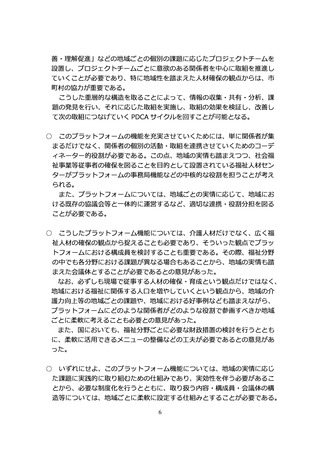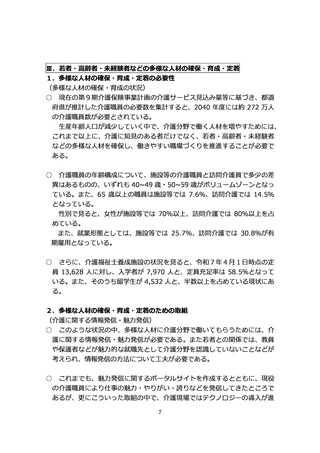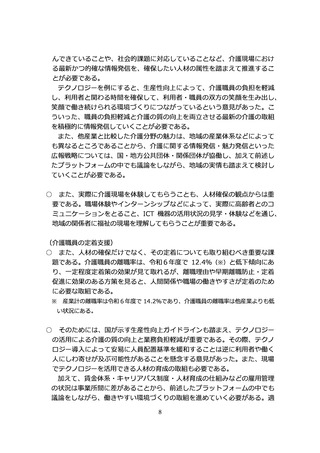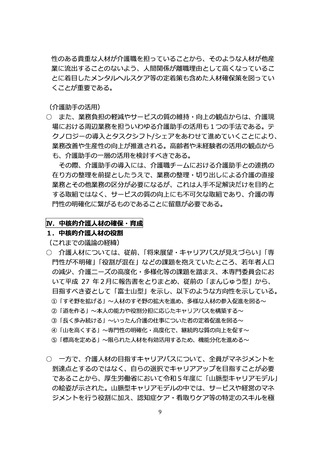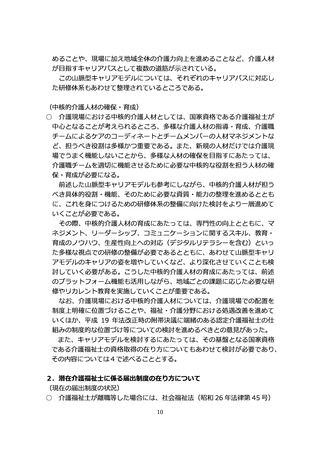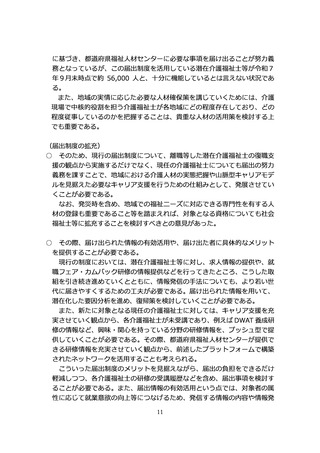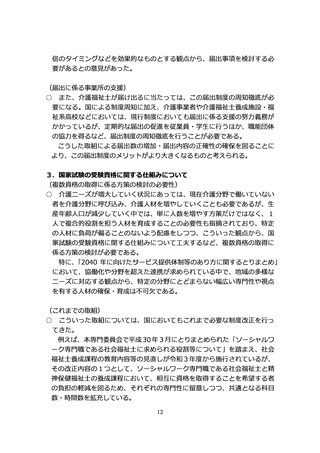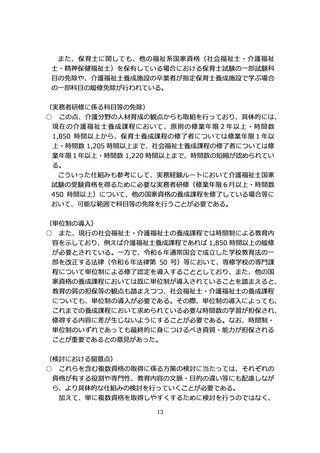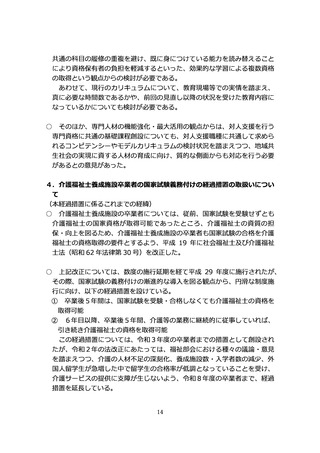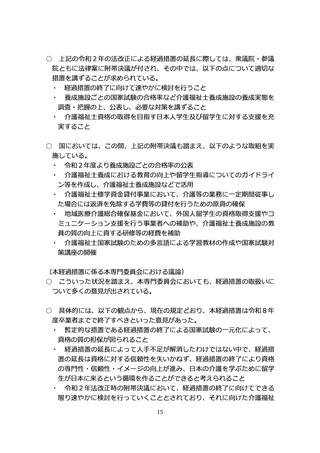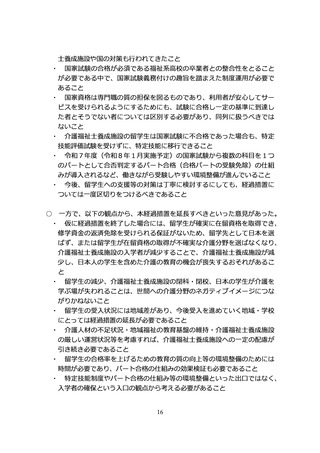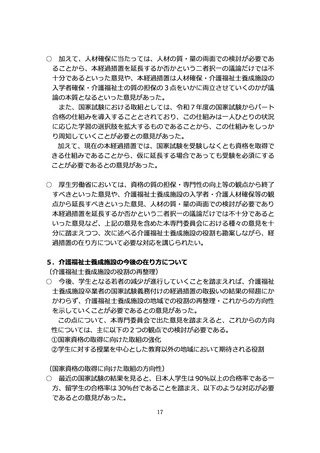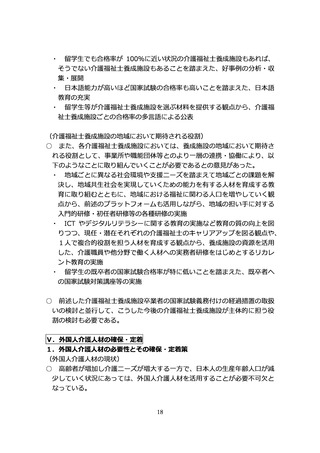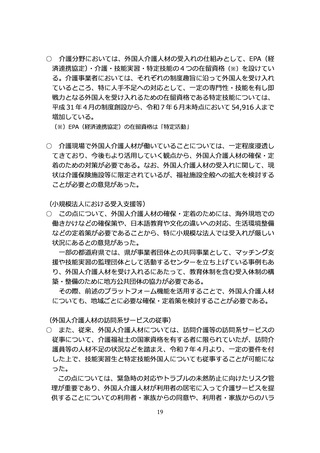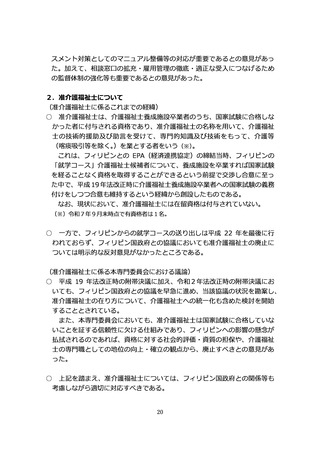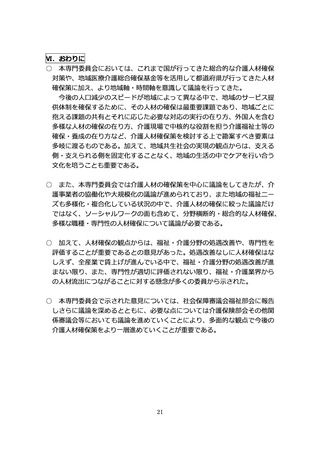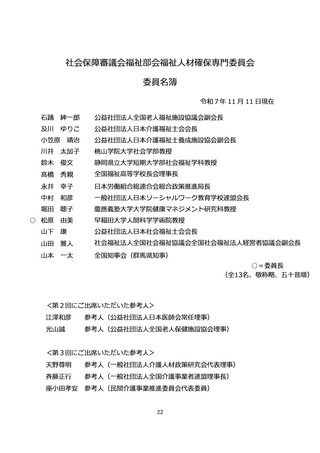よむ、つかう、まなぶ。
資料3-1 福祉人材確保専門委員会における議論の整理 (15 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65945.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 福祉部会(第31回 11/17)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
また、保育士に関しても、他の福祉系国家資格(社会福祉士・介護福祉
士・精神保健福祉士)を保有している場合における保育士試験の一部試験科
目の免除や、介護福祉士養成施設の卒業者が指定保育士養成施設で学ぶ場合
の一部科目の履修免除が行われている。
(実務者研修に係る科目等の免除)
○ この点、介護分野の人材育成の観点からも取組を行っており、具体的には、
現在の介護福祉士養成課程において、原則の修業年限2年以上・時間数
1,850 時間以上から、保育士養成課程の修了者については修業年限1年以
上・時間数 1,205 時間以上まで、社会福祉士養成課程の修了者については修
業年限1年以上・時間数 1,220 時間以上まで、時間数の短縮が認められてい
る。
こういった仕組みも参考にして、実務経験ルートにおいて介護福祉士国家
試験の受験資格を得るために必要な実務者研修(修業年限6月以上・時間数
450 時間以上)について、他の国家資格の養成課程を修了している場合等に
おいて、可能な範囲で科目等の免除を行うことが必要である。
(単位制の導入)
○ また、現行の社会福祉士・介護福祉士の養成課程では時間制による教育内
容を示しており、例えば介護福祉士養成課程であれば 1,850 時間以上の履修
が必要とされている。一方で、令和6年通常国会で成立した学校教育法の一
部を改正する法律(令和6年法律第 50 号)等において、専修学校の専門課
程について単位制による修了認定を導入することとしており、また、他の国
家資格の養成課程においては既に単位制が導入されていることを踏まえると、
教育の質の担保等の観点も踏まえつつ、社会福祉士・介護福祉士の養成課程
についても、単位制の導入が必要である。その際、単位制の導入によっても、
これまでの養成課程において求められている必要な時間数の学習が担保され、
修得する内容に差が生じないようにすることが必要である。なお、時間制・
単位制のいずれであっても最終的に身につけるべき資質・能力が担保される
ことが重要であるとの意見があった。
(検討における留意点)
○ これらを含む複数資格の取得に係る方策の検討に当たっては、それぞれの
資格が有する役割や専門性、教育内容の文脈・目的の違い等にも配慮しなが
ら、より具体的な仕組みの検討を行っていくことが必要である。
加えて、単に複数資格を取得しやすくするために検討を行うのではなく、
13
士・精神保健福祉士)を保有している場合における保育士試験の一部試験科
目の免除や、介護福祉士養成施設の卒業者が指定保育士養成施設で学ぶ場合
の一部科目の履修免除が行われている。
(実務者研修に係る科目等の免除)
○ この点、介護分野の人材育成の観点からも取組を行っており、具体的には、
現在の介護福祉士養成課程において、原則の修業年限2年以上・時間数
1,850 時間以上から、保育士養成課程の修了者については修業年限1年以
上・時間数 1,205 時間以上まで、社会福祉士養成課程の修了者については修
業年限1年以上・時間数 1,220 時間以上まで、時間数の短縮が認められてい
る。
こういった仕組みも参考にして、実務経験ルートにおいて介護福祉士国家
試験の受験資格を得るために必要な実務者研修(修業年限6月以上・時間数
450 時間以上)について、他の国家資格の養成課程を修了している場合等に
おいて、可能な範囲で科目等の免除を行うことが必要である。
(単位制の導入)
○ また、現行の社会福祉士・介護福祉士の養成課程では時間制による教育内
容を示しており、例えば介護福祉士養成課程であれば 1,850 時間以上の履修
が必要とされている。一方で、令和6年通常国会で成立した学校教育法の一
部を改正する法律(令和6年法律第 50 号)等において、専修学校の専門課
程について単位制による修了認定を導入することとしており、また、他の国
家資格の養成課程においては既に単位制が導入されていることを踏まえると、
教育の質の担保等の観点も踏まえつつ、社会福祉士・介護福祉士の養成課程
についても、単位制の導入が必要である。その際、単位制の導入によっても、
これまでの養成課程において求められている必要な時間数の学習が担保され、
修得する内容に差が生じないようにすることが必要である。なお、時間制・
単位制のいずれであっても最終的に身につけるべき資質・能力が担保される
ことが重要であるとの意見があった。
(検討における留意点)
○ これらを含む複数資格の取得に係る方策の検討に当たっては、それぞれの
資格が有する役割や専門性、教育内容の文脈・目的の違い等にも配慮しなが
ら、より具体的な仕組みの検討を行っていくことが必要である。
加えて、単に複数資格を取得しやすくするために検討を行うのではなく、
13