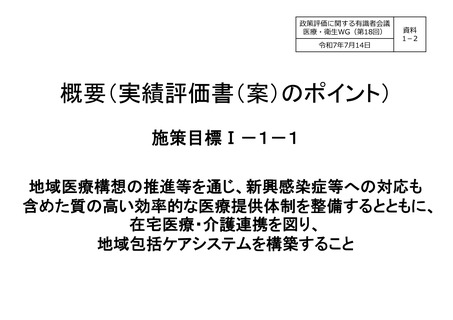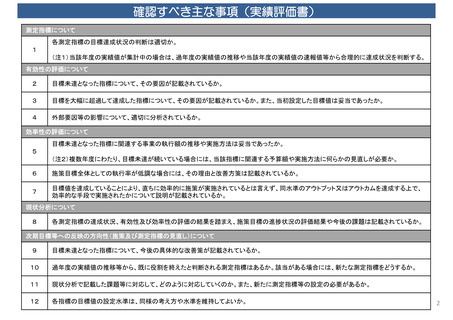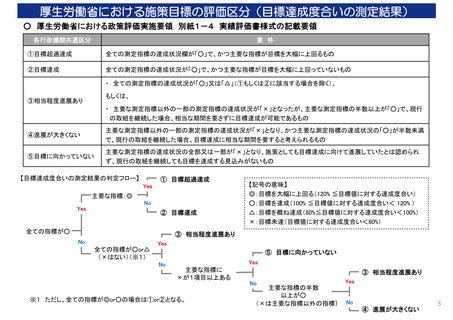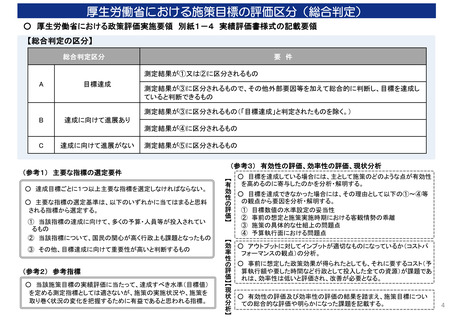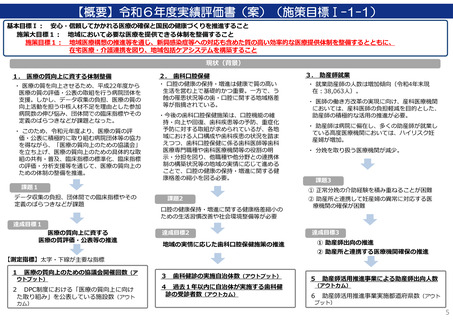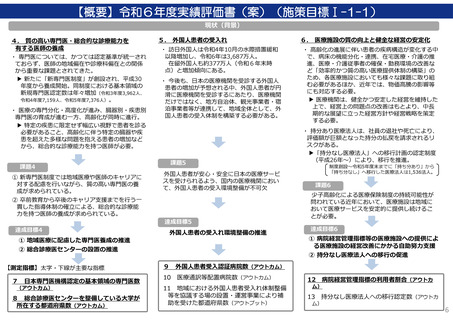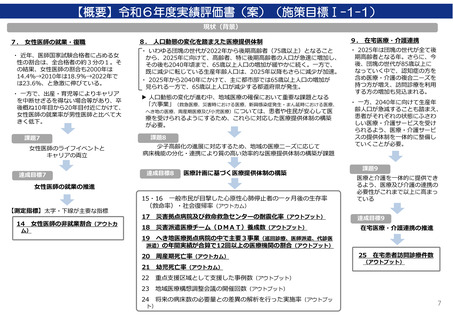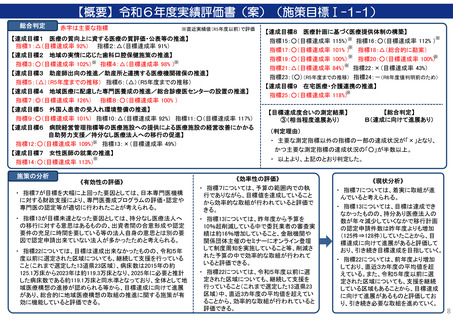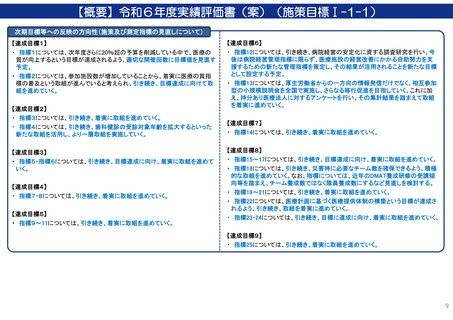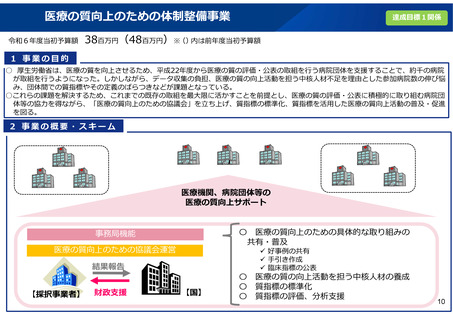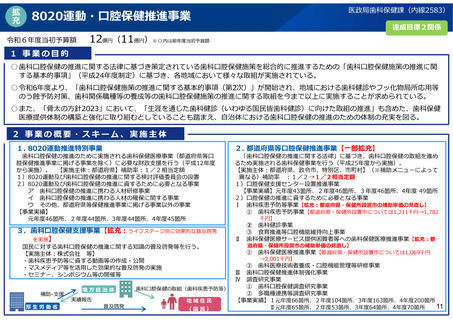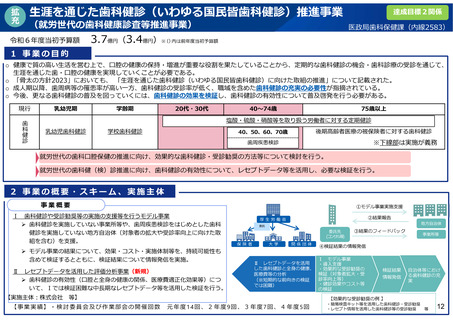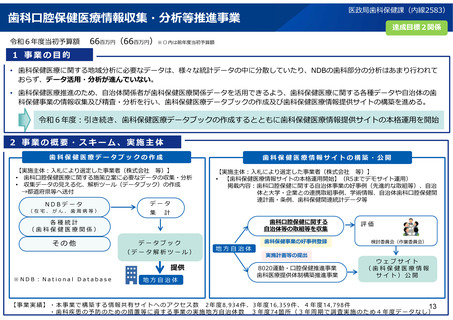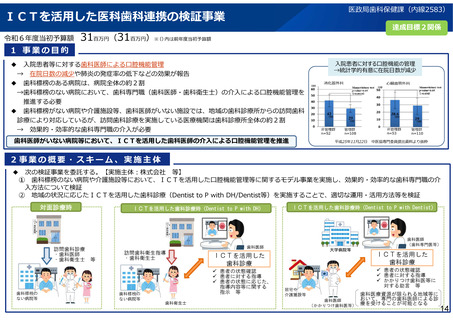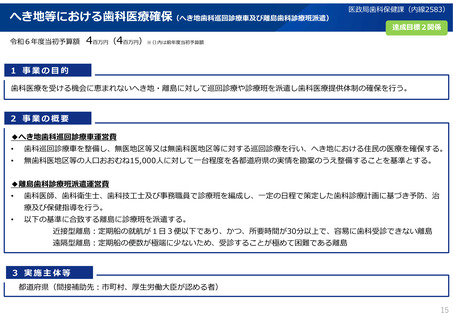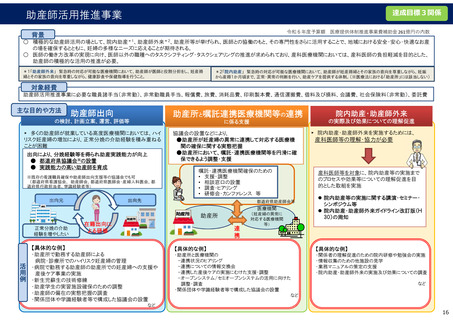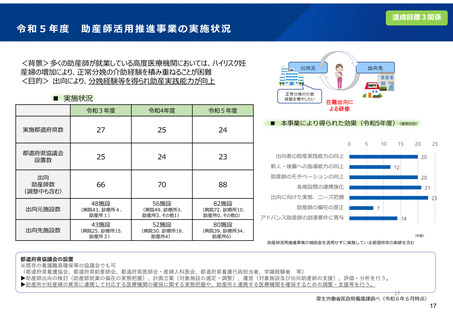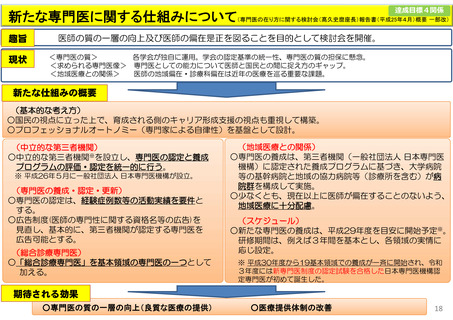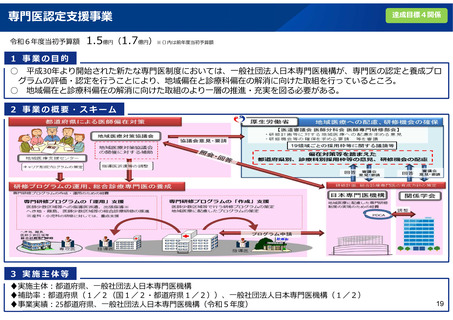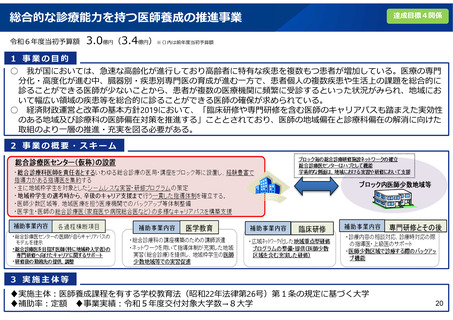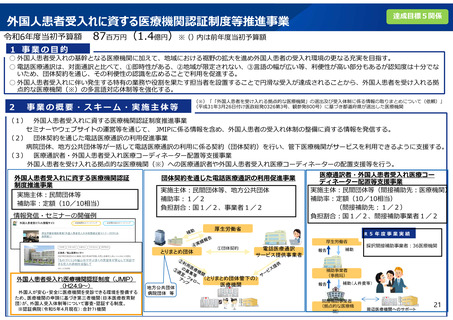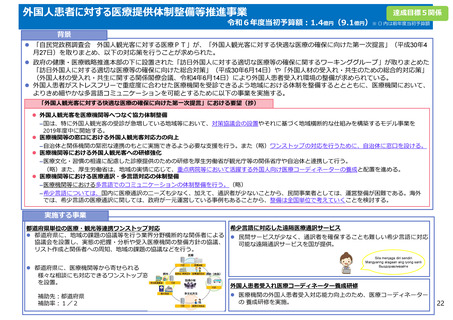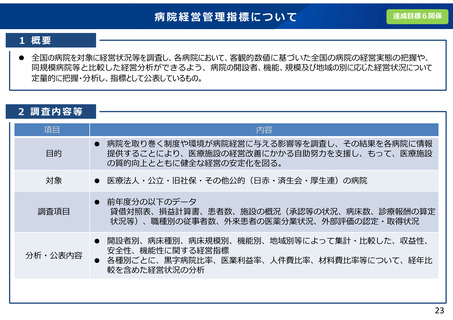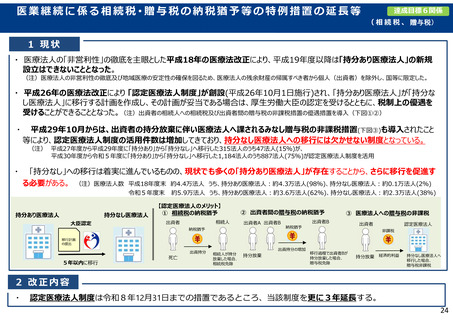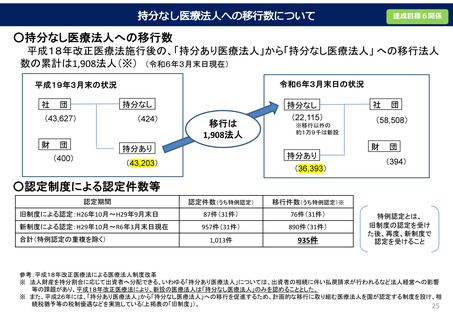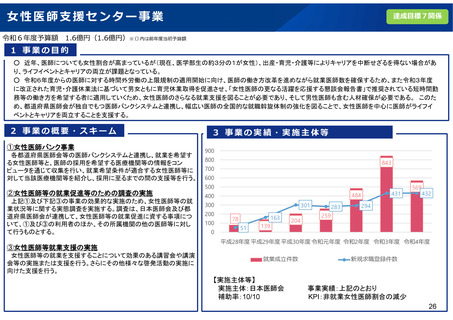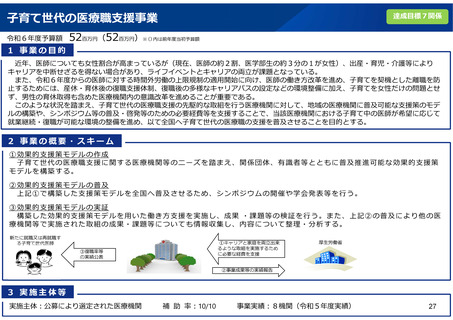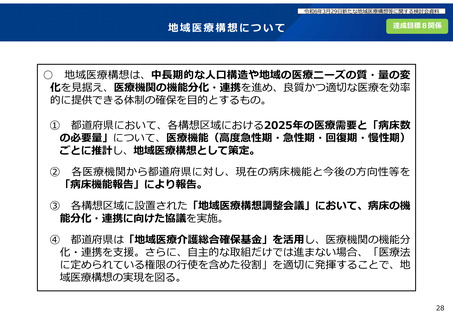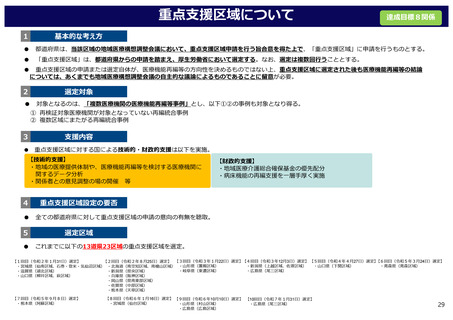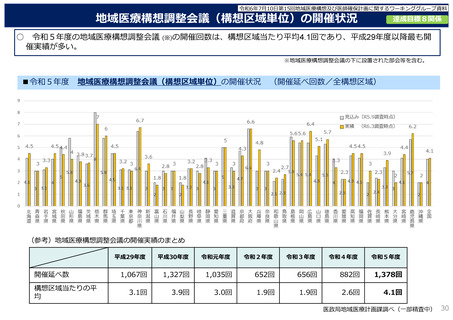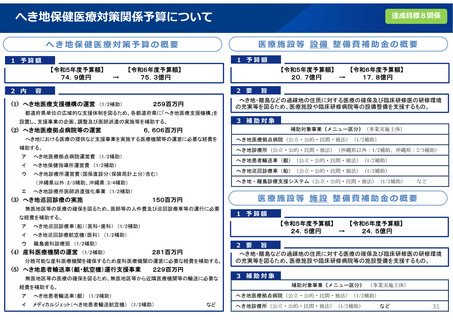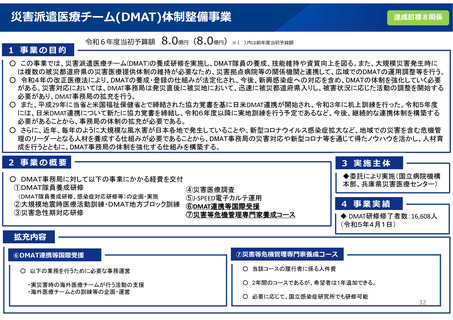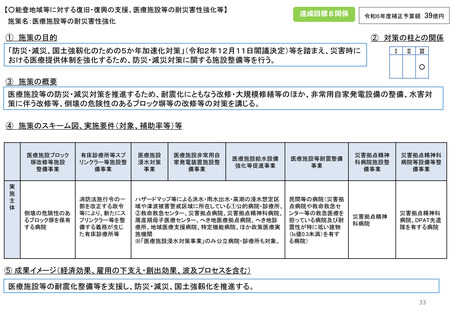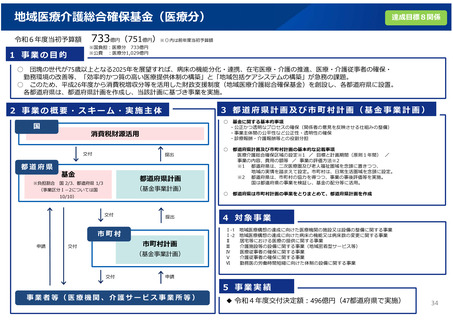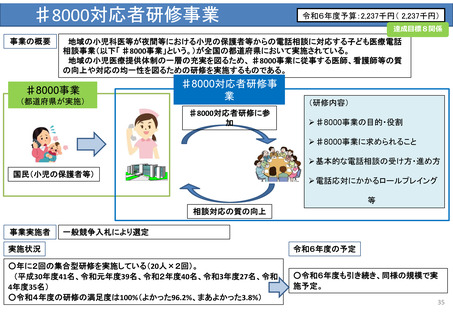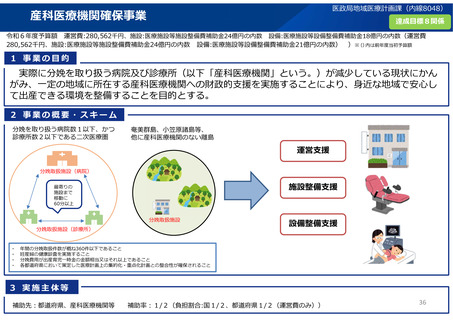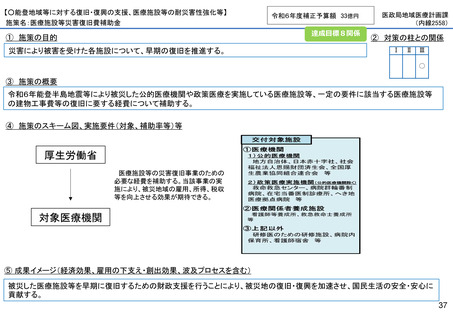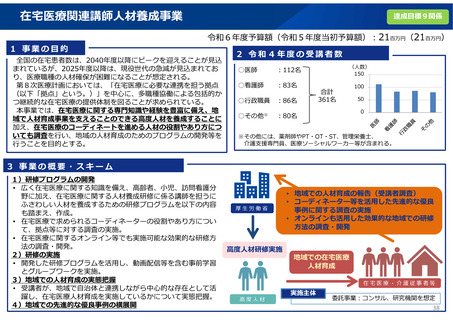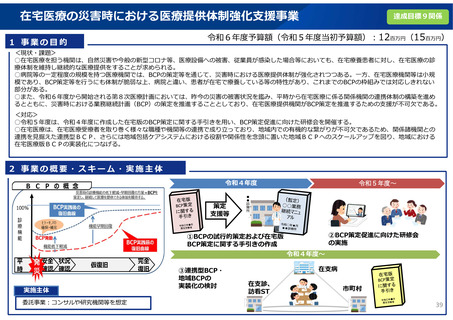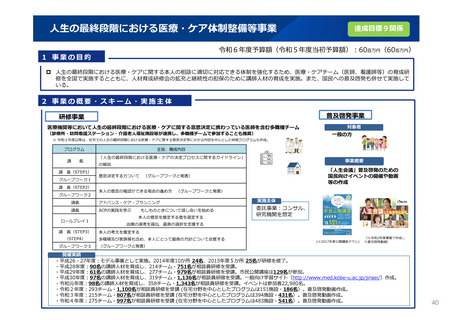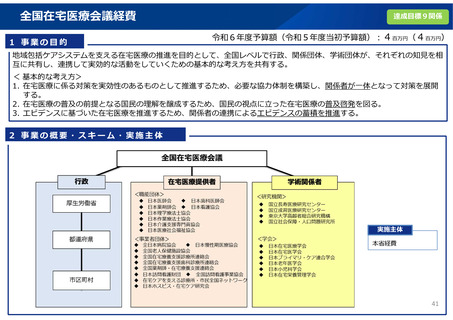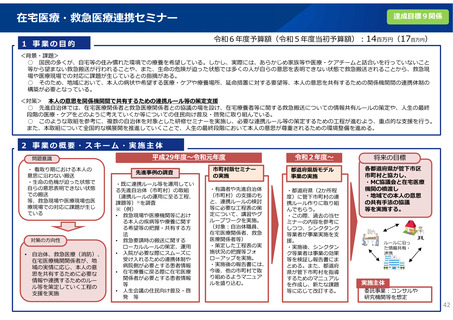よむ、つかう、まなぶ。
資料1-2_概要(施策目標Ⅰ-1-1) (6 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/newpage_00152.html |
| 出典情報 | 政策評価に関する有識者会議 医療・衛生WG(第18回 7/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
【概要】令和6年度実績評価書(案)(施策目標Ⅰ-1-1)
現状(背景)
4. 質の高い専門医・総合的な診療能力を
有する医師の養成
・ 専門医については、かつては認定基準が統一され
ておらず、医師の地域偏在や診療科偏在との関係
から重要な課題とされてきた。
新たに「新専門医制度」が創設され、平成30
年度から養成開始。同制度における基本領域の
新規専門医認定数は年々増加(令和3年度3,962人、
令和4年度7,159人、令和5年度7,376人)。
・ 医療の専門分化・高度化が進み、臓器別・疾患別
専門医の育成が進む一方、高齢化が同時に進行。
特定の疾患に限定せず幅広い視野で患者を診る
必要があること、高齢化に伴う特定の臓器や疾
患を超えた多様な問題を抱える患者の増加など
から、総合的な診療能力を持つ医師が必要。
課題4
① 新専門医制度では地域医療や医師のキャリアに
対する配慮を行いながら、質の高い専門医の養
成が求められている。
② 卒前教育から卒後のキャリア支援までを行う一
貫した指導体制の確立による、総合的な診療能
力を持つ医師の養成が求められている。
達成目標4
5.
・ 訪日外国人は令和4年10月の水際措置緩和
以降増加し、令和6年は3,687万人。
在留外国人も約377万人(令和6年末時
点)と増加傾向にある。
・ 今後も、日本の医療機関を受診する外国人
患者の増加が予想される中、外国人患者が円
滑に医療機関を受診するにあたり、医療機関
だけではなく、地方自治体、観光事業者・宿
泊事業者等が連携して、地域全体として、外
国人患者の受入体制を構築する必要がある。
課題5
外国人患者が安心・安全に日本の医療サービ
スを受けられるよう、国内の医療機関におい
て、外国人患者の受入環境整備が不可欠
達成目標5
外国人患者の受入れ環境整備の推進
① 地域医療に配慮した専門医養成の推進
② 総合診療医センターの設置の推進
【測定指標】太字・下線が主要な指標
7
日本専門医機構認定の基本領域の専門医数
(アウトカム)
8 総合診療医センターを整備している大学が
所在する都道府県数(アウトカム)
外国人患者の受入れ
9
外国人患者受入認証病院数(アウトカム)
10
医療通訳等配置病院数(アウトカム)
11 地域における外国人患者受入れ体制整備
等を協議する場の設置・運営事業により補
助を受けた都道府県数(アウトプット)
6.
医療施設の質の向上と健全な経営の安定化
・ 高齢化の進展に伴い患者の疾病構造が変化する中
で、病床の機能分化・連携、在宅医療・介護の推
進、医療・介護従事者の確保・勤務環境の改善な
ど「効率的かつ質の高い医療提供体制の構築」の
ため、各医療施設においても様々な課題に取り組
む必要があるほか、近年では、物価高騰の影響等
にも対応する必要。
医療機関は、健全かつ安定した経営を維持した
上で、経営上の問題点の改善はもとより、中長
期的な展望に立った経営方針や経営戦略を策定
する必要。
・ 持分あり医療法人は、社員の退社や死亡により、
評価額が巨額となった持分の払戻を請求されるリ
スクがある。
「持分なし医療法人」への移行計画の認定制度
(平成26年~)により、移行を推進。
制度創設~令和5年度末までに「持ち分あり」から
「持ち分なし」へ移行した医療法人は1,536法人。
課題6
少子高齢化による医療保険制度の持続可能性が
問われている近年において、医療施設は地域に
おいて医療サービスを安定的に提供し続けるこ
とが必要。
達成目標6
① 病院経営管理指標等の医療施設への提供によ
る医療施設の経営改善にかかる自助努力支援
② 持分なし医療法人への移行の促進
12
病院経営管理指標の利用者割合(アウトカ
13
持分なし医療法人への移行認定数(アウトカ
ム)
ム)
6
現状(背景)
4. 質の高い専門医・総合的な診療能力を
有する医師の養成
・ 専門医については、かつては認定基準が統一され
ておらず、医師の地域偏在や診療科偏在との関係
から重要な課題とされてきた。
新たに「新専門医制度」が創設され、平成30
年度から養成開始。同制度における基本領域の
新規専門医認定数は年々増加(令和3年度3,962人、
令和4年度7,159人、令和5年度7,376人)。
・ 医療の専門分化・高度化が進み、臓器別・疾患別
専門医の育成が進む一方、高齢化が同時に進行。
特定の疾患に限定せず幅広い視野で患者を診る
必要があること、高齢化に伴う特定の臓器や疾
患を超えた多様な問題を抱える患者の増加など
から、総合的な診療能力を持つ医師が必要。
課題4
① 新専門医制度では地域医療や医師のキャリアに
対する配慮を行いながら、質の高い専門医の養
成が求められている。
② 卒前教育から卒後のキャリア支援までを行う一
貫した指導体制の確立による、総合的な診療能
力を持つ医師の養成が求められている。
達成目標4
5.
・ 訪日外国人は令和4年10月の水際措置緩和
以降増加し、令和6年は3,687万人。
在留外国人も約377万人(令和6年末時
点)と増加傾向にある。
・ 今後も、日本の医療機関を受診する外国人
患者の増加が予想される中、外国人患者が円
滑に医療機関を受診するにあたり、医療機関
だけではなく、地方自治体、観光事業者・宿
泊事業者等が連携して、地域全体として、外
国人患者の受入体制を構築する必要がある。
課題5
外国人患者が安心・安全に日本の医療サービ
スを受けられるよう、国内の医療機関におい
て、外国人患者の受入環境整備が不可欠
達成目標5
外国人患者の受入れ環境整備の推進
① 地域医療に配慮した専門医養成の推進
② 総合診療医センターの設置の推進
【測定指標】太字・下線が主要な指標
7
日本専門医機構認定の基本領域の専門医数
(アウトカム)
8 総合診療医センターを整備している大学が
所在する都道府県数(アウトカム)
外国人患者の受入れ
9
外国人患者受入認証病院数(アウトカム)
10
医療通訳等配置病院数(アウトカム)
11 地域における外国人患者受入れ体制整備
等を協議する場の設置・運営事業により補
助を受けた都道府県数(アウトプット)
6.
医療施設の質の向上と健全な経営の安定化
・ 高齢化の進展に伴い患者の疾病構造が変化する中
で、病床の機能分化・連携、在宅医療・介護の推
進、医療・介護従事者の確保・勤務環境の改善な
ど「効率的かつ質の高い医療提供体制の構築」の
ため、各医療施設においても様々な課題に取り組
む必要があるほか、近年では、物価高騰の影響等
にも対応する必要。
医療機関は、健全かつ安定した経営を維持した
上で、経営上の問題点の改善はもとより、中長
期的な展望に立った経営方針や経営戦略を策定
する必要。
・ 持分あり医療法人は、社員の退社や死亡により、
評価額が巨額となった持分の払戻を請求されるリ
スクがある。
「持分なし医療法人」への移行計画の認定制度
(平成26年~)により、移行を推進。
制度創設~令和5年度末までに「持ち分あり」から
「持ち分なし」へ移行した医療法人は1,536法人。
課題6
少子高齢化による医療保険制度の持続可能性が
問われている近年において、医療施設は地域に
おいて医療サービスを安定的に提供し続けるこ
とが必要。
達成目標6
① 病院経営管理指標等の医療施設への提供によ
る医療施設の経営改善にかかる自助努力支援
② 持分なし医療法人への移行の促進
12
病院経営管理指標の利用者割合(アウトカ
13
持分なし医療法人への移行認定数(アウトカ
ム)
ム)
6