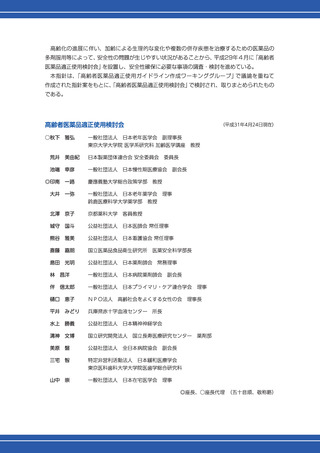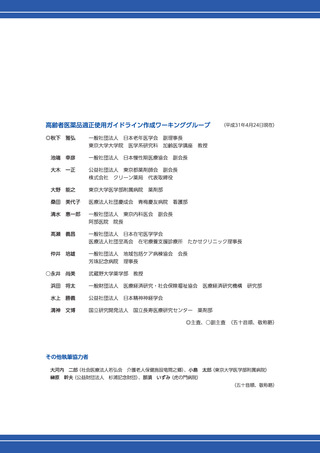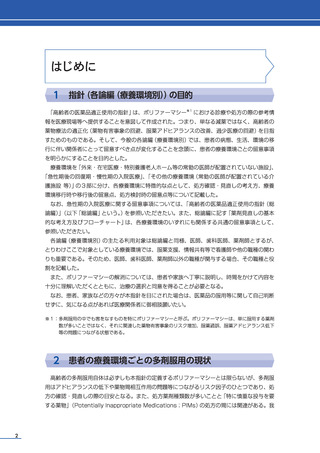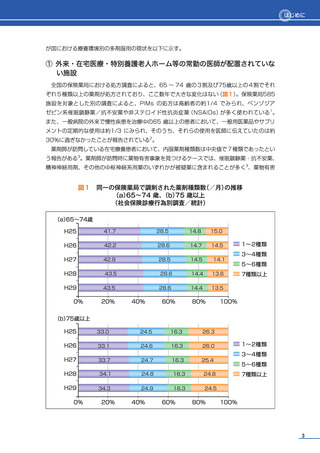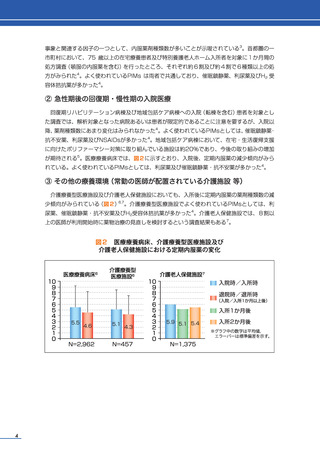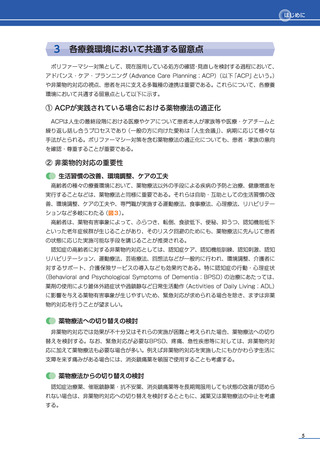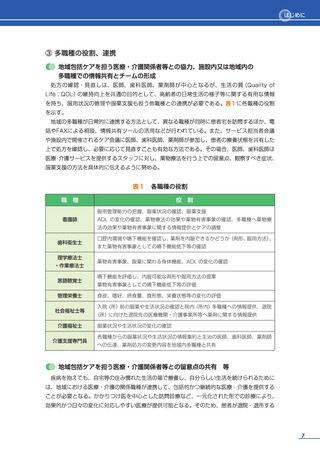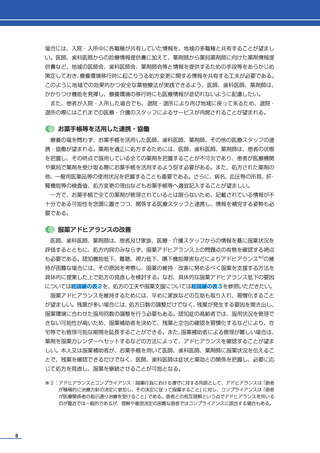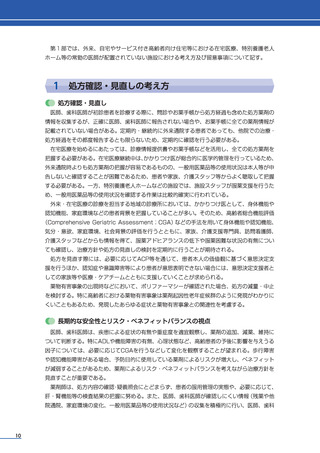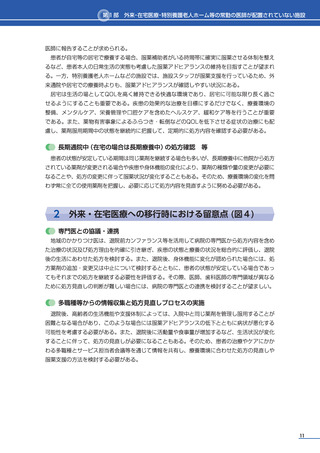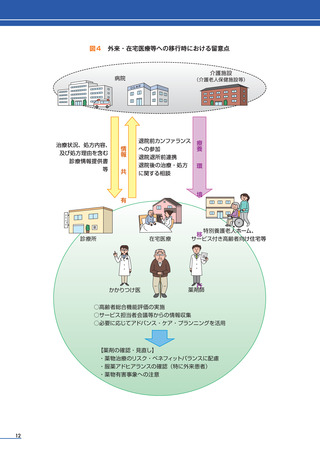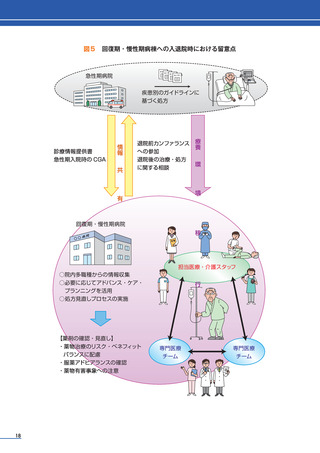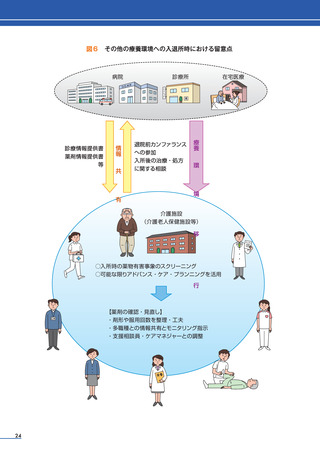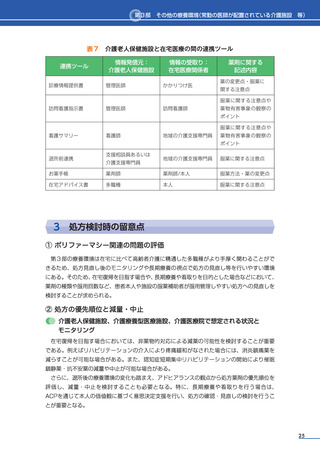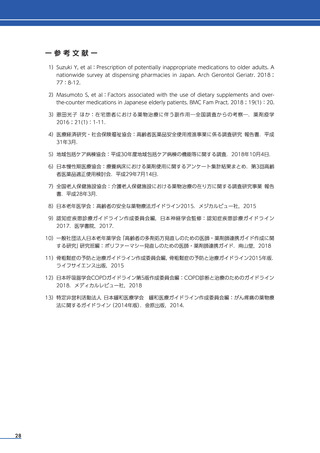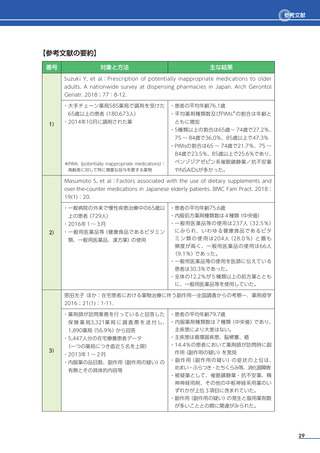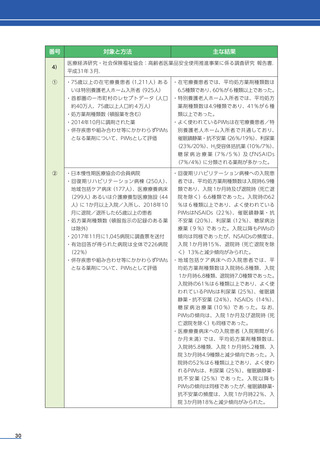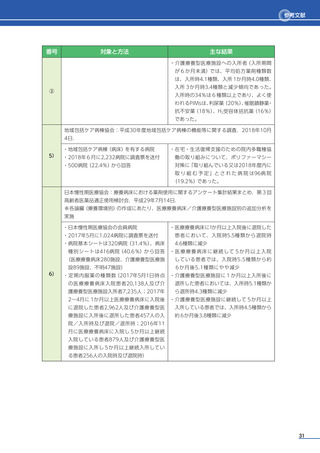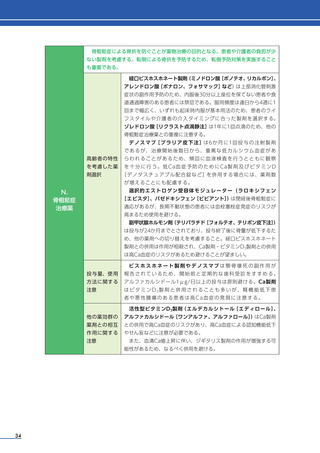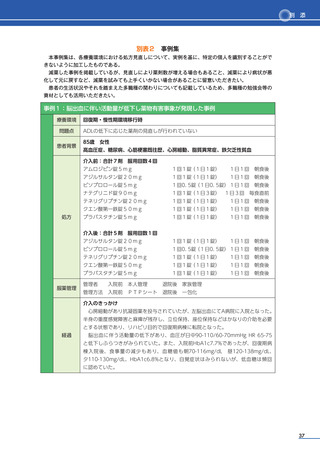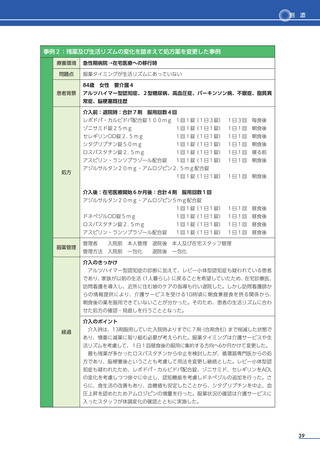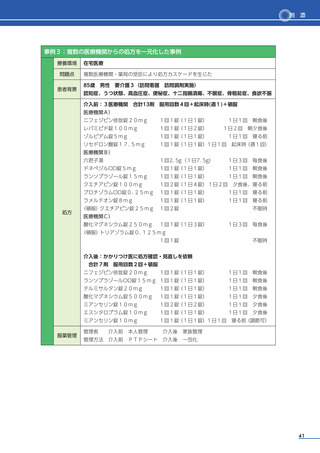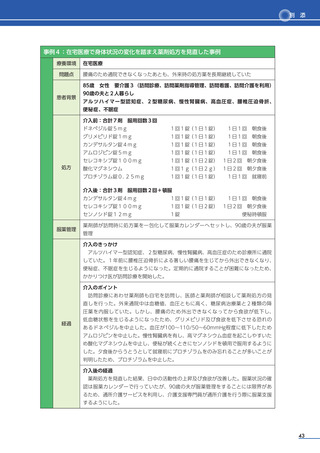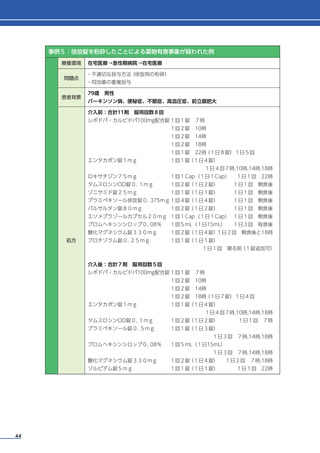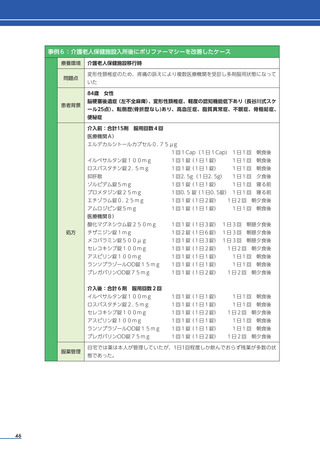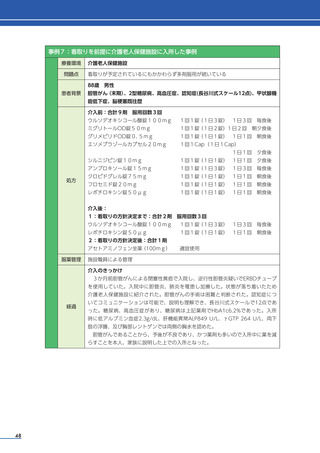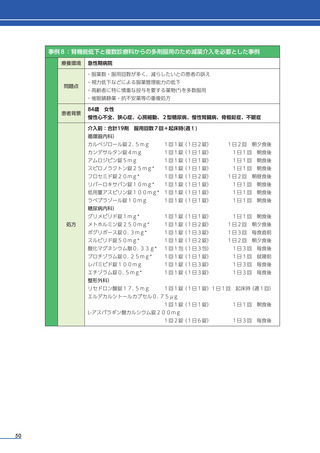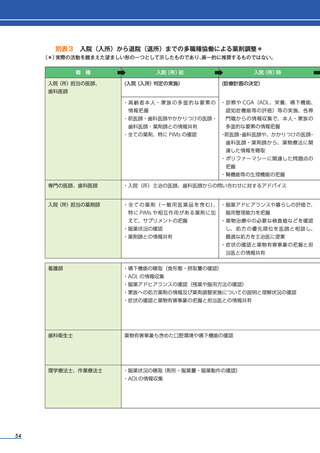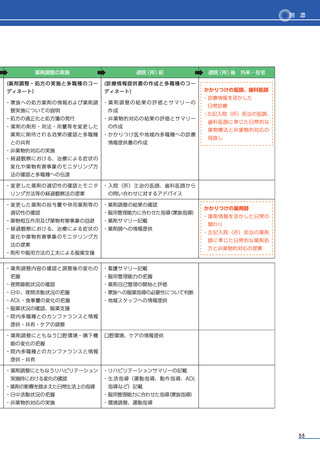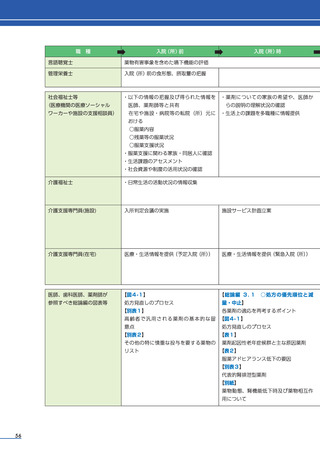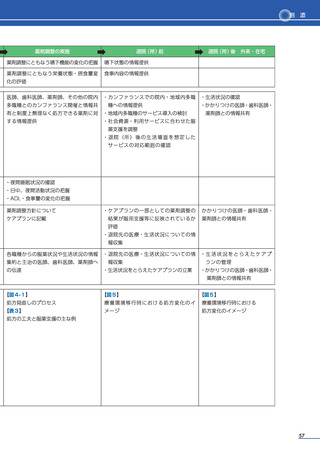よむ、つかう、まなぶ。
参考資料2 高齢者の医薬品適正使用の指針(各論編(療養環境別)) (38 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25107.html |
| 出典情報 | 高齢者医薬品適正使用検討会(第15回 4/13)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
骨粗鬆症による骨折を防ぐことが薬物治療の目的となる。患者や介護者の負担が少
ない製剤を考慮する。転倒による骨折を予防するため、転倒予防対策を実施すること
も重要である。
経口ビスホスホネート製剤(ミノドロン酸[ボノテオ、リカルボン]
、
アレンドロン酸[ボナロン、フォサマック]など)は上部消化管刺激
症状の副作用予防のため、内服後30分以上座位を保てない患者や食
道通過障害のある患者には禁忌である。服用頻度は連日から4週に1
回まで幅広く、いずれも起床時内服が基本用法のため、患者のライ
フスタイルや介護者の介入タイミングに合った製剤を選択する。
ゾレドロン酸[リクラスト点滴静注]は1年に1回点滴のため、他の
骨粗鬆症治療薬との重複に注意する。
デ ノ ス マ ブ[ プ ラ リ ア 皮 下 注 ]は6か 月 に1回 投 与 の 注 射 製 剤
で あ る が、 治 療 開 始 後 数 日 か ら、 重 篤 な 低 カ ル シ ウ ム 血 症 が あ
高齢者の特性
を考慮した薬
剤選択
ら わ れる ことが あるため、頻回 に 血液検 査 を 行うと と もに 観察
を 十 分 に 行 う。 低Ca血 症 予 防 の た め にCa製 剤 及 び ビ タ ミ ンD
[デノタスチュアブル配合錠など]を併用する場合には、薬剤数
が増えることにも配慮する。
選択 的 エ ス ト ロ ゲ ン 受 容 体 モ ジ ュ レ ー タ ー( ラ ロ キ シ フ ェ ン
N.
骨粗鬆症
治療薬
[エビスタ]
、バゼドキシフェン[ビビアント]
)は閉経後骨粗鬆症に
適応があるが、長期不動状態の患者には血栓塞栓症発症のリスクが
高まるため使用を避ける。
副甲状腺ホルモン剤(テリパラチド[フォルテオ、テリボン皮下注]
)
は投与が24か月までとされており、投与終了後に骨量が低下するた
め、他の薬剤への切り替えを考慮すること。経口ビスホスホネート
製剤との併用は作用が相殺され、Ca製剤・ビタミンD3製剤との併用
は高Ca血症のリスクがあるため避けることが望ましい。
ビスホスホネート製剤やデノスマブは顎骨壊死の副作用が
投与量、使用
報告されているため、開始前と定期的な歯科受診をすすめる。
方法に関する
アルファカルシドール1μg/日以上の投与は原則避ける。Ca製剤
注意
は ビ タ ミ ン D 3製 剤 と 併 用 さ れ る こ と も 多 い が 、 腎 機 能 低 下 患
者や悪性腫瘍のある患者は高Ca血症の発現に注意する。
活性型ビタミンD3製剤(エルデカルシトール[エディロール]、
他の薬効群の
アルファカルシドール[ワンアルファ、アルファロール]
)はCa製剤
薬剤との相互
との併用で高Ca血症のリスクがあり、高Ca血症による認知機能低下
作用に関する
やせん妄などに注意が必要である。
注意
また、血清Ca値上昇に伴い、ジギタリス製剤の作用が増強する可
能性があるため、なるべく併用を避ける。
34
ない製剤を考慮する。転倒による骨折を予防するため、転倒予防対策を実施すること
も重要である。
経口ビスホスホネート製剤(ミノドロン酸[ボノテオ、リカルボン]
、
アレンドロン酸[ボナロン、フォサマック]など)は上部消化管刺激
症状の副作用予防のため、内服後30分以上座位を保てない患者や食
道通過障害のある患者には禁忌である。服用頻度は連日から4週に1
回まで幅広く、いずれも起床時内服が基本用法のため、患者のライ
フスタイルや介護者の介入タイミングに合った製剤を選択する。
ゾレドロン酸[リクラスト点滴静注]は1年に1回点滴のため、他の
骨粗鬆症治療薬との重複に注意する。
デ ノ ス マ ブ[ プ ラ リ ア 皮 下 注 ]は6か 月 に1回 投 与 の 注 射 製 剤
で あ る が、 治 療 開 始 後 数 日 か ら、 重 篤 な 低 カ ル シ ウ ム 血 症 が あ
高齢者の特性
を考慮した薬
剤選択
ら わ れる ことが あるため、頻回 に 血液検 査 を 行うと と もに 観察
を 十 分 に 行 う。 低Ca血 症 予 防 の た め にCa製 剤 及 び ビ タ ミ ンD
[デノタスチュアブル配合錠など]を併用する場合には、薬剤数
が増えることにも配慮する。
選択 的 エ ス ト ロ ゲ ン 受 容 体 モ ジ ュ レ ー タ ー( ラ ロ キ シ フ ェ ン
N.
骨粗鬆症
治療薬
[エビスタ]
、バゼドキシフェン[ビビアント]
)は閉経後骨粗鬆症に
適応があるが、長期不動状態の患者には血栓塞栓症発症のリスクが
高まるため使用を避ける。
副甲状腺ホルモン剤(テリパラチド[フォルテオ、テリボン皮下注]
)
は投与が24か月までとされており、投与終了後に骨量が低下するた
め、他の薬剤への切り替えを考慮すること。経口ビスホスホネート
製剤との併用は作用が相殺され、Ca製剤・ビタミンD3製剤との併用
は高Ca血症のリスクがあるため避けることが望ましい。
ビスホスホネート製剤やデノスマブは顎骨壊死の副作用が
投与量、使用
報告されているため、開始前と定期的な歯科受診をすすめる。
方法に関する
アルファカルシドール1μg/日以上の投与は原則避ける。Ca製剤
注意
は ビ タ ミ ン D 3製 剤 と 併 用 さ れ る こ と も 多 い が 、 腎 機 能 低 下 患
者や悪性腫瘍のある患者は高Ca血症の発現に注意する。
活性型ビタミンD3製剤(エルデカルシトール[エディロール]、
他の薬効群の
アルファカルシドール[ワンアルファ、アルファロール]
)はCa製剤
薬剤との相互
との併用で高Ca血症のリスクがあり、高Ca血症による認知機能低下
作用に関する
やせん妄などに注意が必要である。
注意
また、血清Ca値上昇に伴い、ジギタリス製剤の作用が増強する可
能性があるため、なるべく併用を避ける。
34