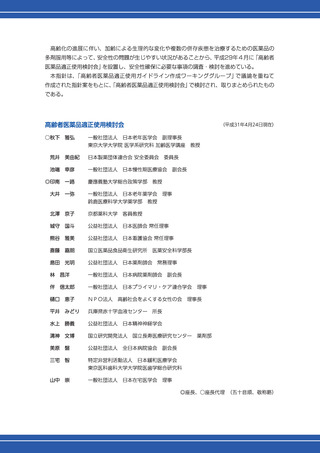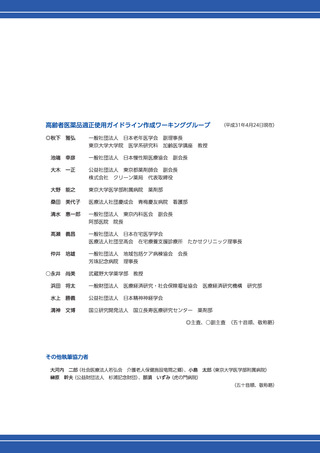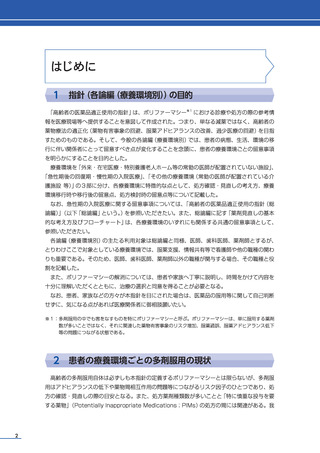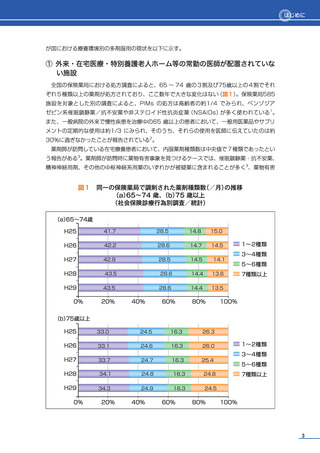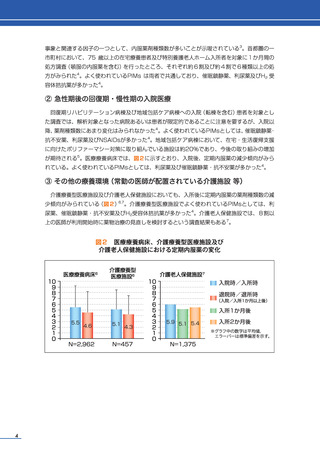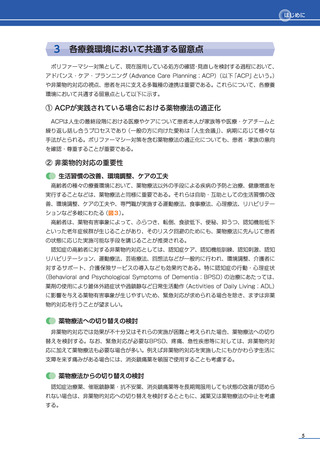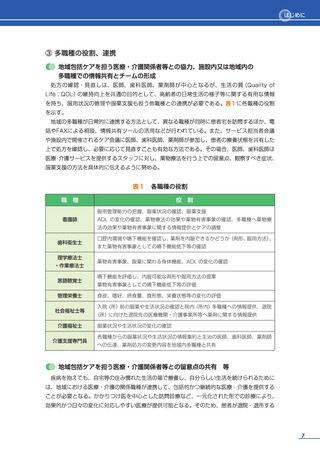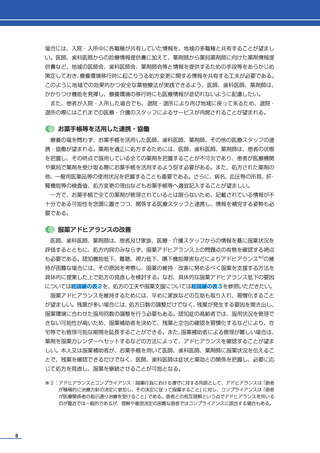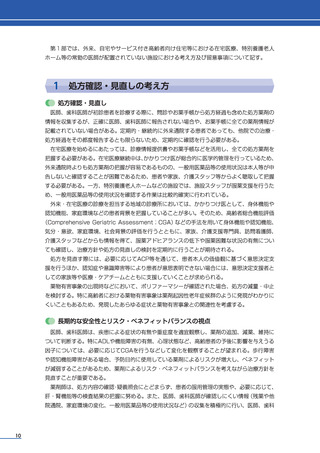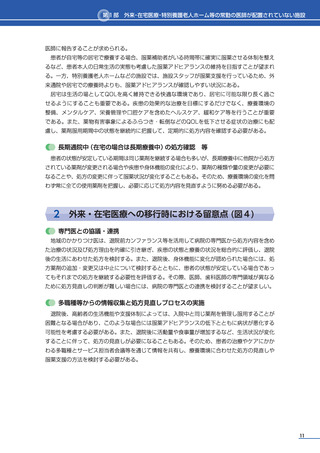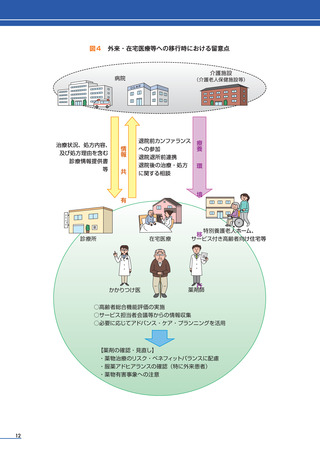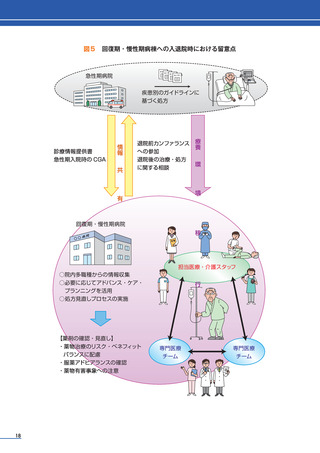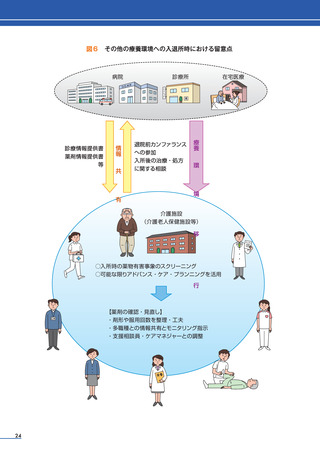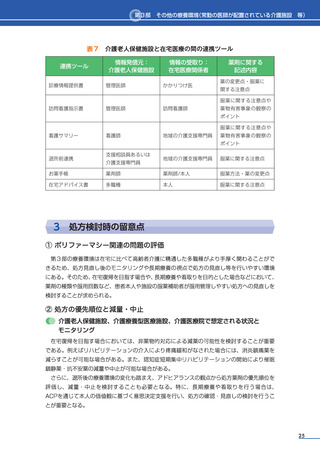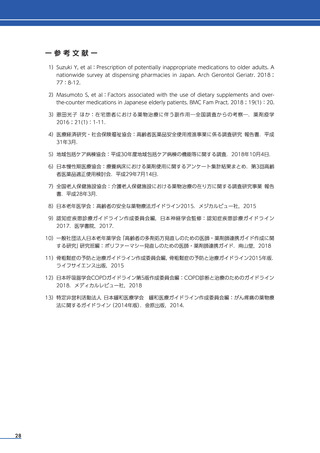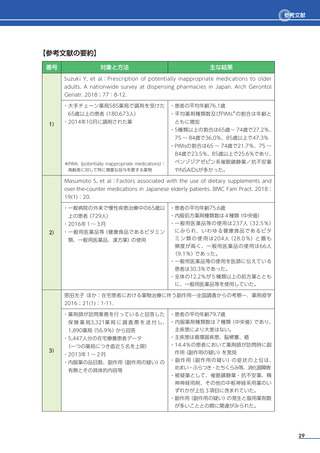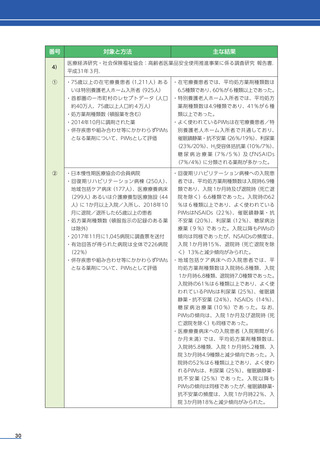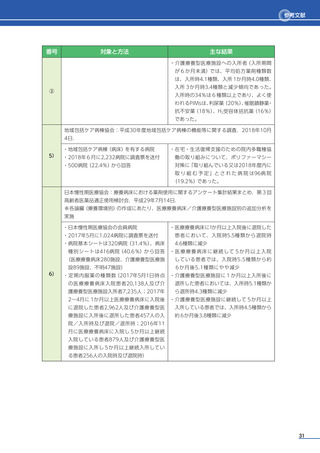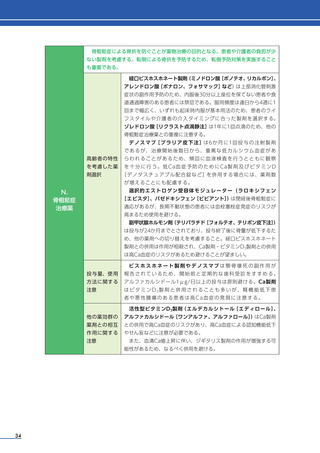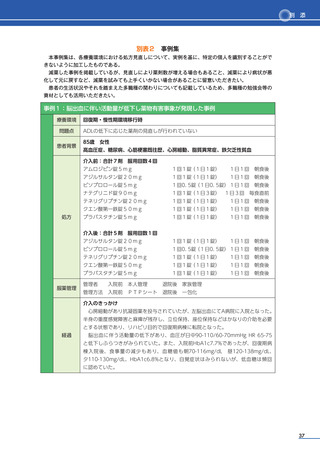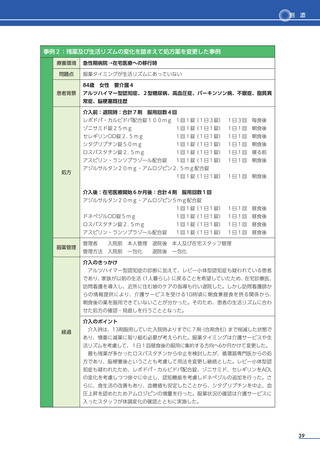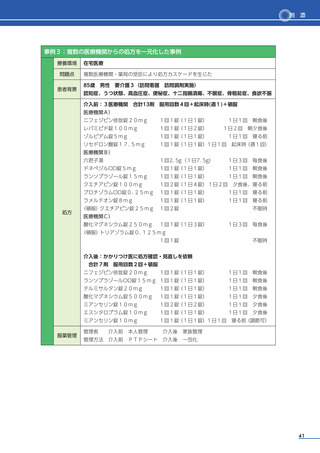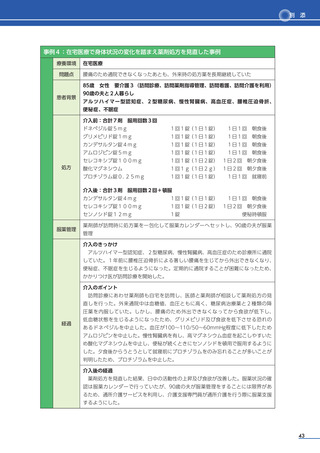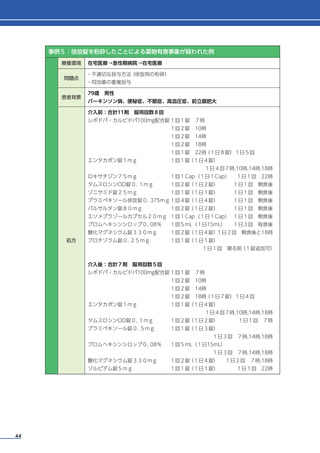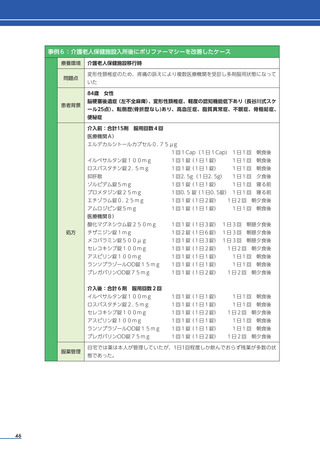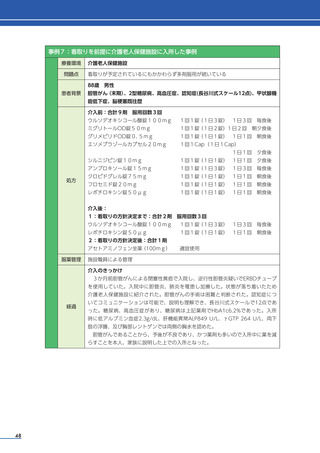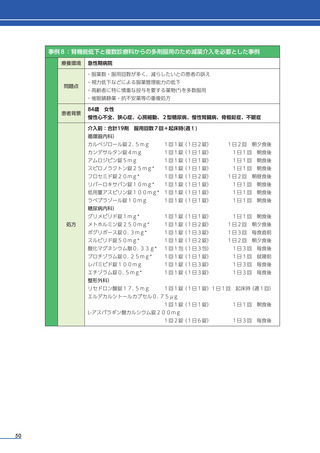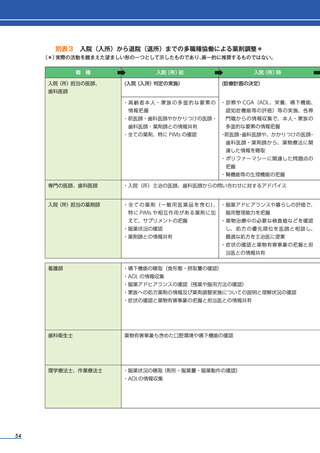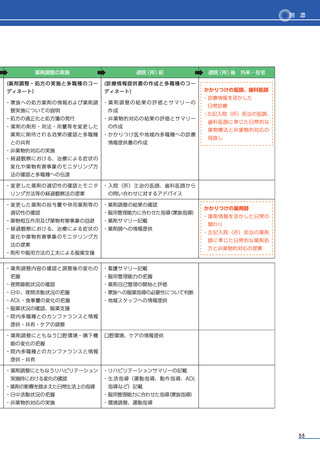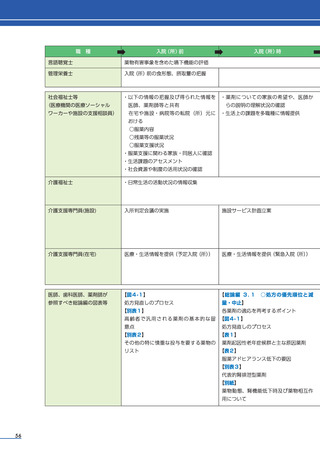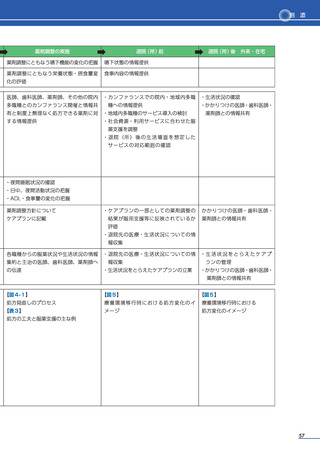よむ、つかう、まなぶ。
参考資料2 高齢者の医薬品適正使用の指針(各論編(療養環境別)) (31 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25107.html |
| 出典情報 | 高齢者医薬品適正使用検討会(第15回 4/13)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
おわりに
おわりに
●
● 患者・国民への啓発の重要性
医療関係者がポリファーマシーに取り組んでも、患者と家族を含む一般の方の理解と協力がな
ければポリファーマシーの解消にはつながらない。したがって、一般の方は本指針の利用対象で
はないものの、本指針の基本的内容を患者・国民に啓発していくことが何より重要である。
●
● 平易で丁寧な説明と注意喚起
啓発に際しては、ポリファーマシーの問題についての理解が患者・家族には難しい場合もある
ことを踏まえて、医療関係者からの丁寧な説明や情報提供が必要である。病状や療養環境にもよ
るが、薬物有害事象のリスクだけでなく、薬剤の減量や中止により病状が改善する場合があるた
め、すべての病状に対して薬物療法を必要とする場合ばかりではないといった点について、具体
的でわかりやすい言葉を用いて説明するように心がけることが重要となる。一方で、自己判断に
よる減薬や中止の危険性に関して注意喚起を行うとともに、服薬状況を医師、歯科医師、薬剤師
に正しく伝えることの重要性についても患者・家族に繰り返し理解を求める必要がある。
●
● 患者・家族の意向を尊重
最後に、薬物療法及びその適正化は患者・家族の意向を尊重して行わなければならないことを
強調しておきたい。意向を直接確認することはもとより、
CGA等で得られる生活機能や生活状況、
日常の訴えや意見などの情報から患者・家族の意向を推測することが求められる。また、患者・
家族の意思決定支援のためにもACPの考え方と手法を積極的に取り入れることも推奨される。
27
おわりに
●
● 患者・国民への啓発の重要性
医療関係者がポリファーマシーに取り組んでも、患者と家族を含む一般の方の理解と協力がな
ければポリファーマシーの解消にはつながらない。したがって、一般の方は本指針の利用対象で
はないものの、本指針の基本的内容を患者・国民に啓発していくことが何より重要である。
●
● 平易で丁寧な説明と注意喚起
啓発に際しては、ポリファーマシーの問題についての理解が患者・家族には難しい場合もある
ことを踏まえて、医療関係者からの丁寧な説明や情報提供が必要である。病状や療養環境にもよ
るが、薬物有害事象のリスクだけでなく、薬剤の減量や中止により病状が改善する場合があるた
め、すべての病状に対して薬物療法を必要とする場合ばかりではないといった点について、具体
的でわかりやすい言葉を用いて説明するように心がけることが重要となる。一方で、自己判断に
よる減薬や中止の危険性に関して注意喚起を行うとともに、服薬状況を医師、歯科医師、薬剤師
に正しく伝えることの重要性についても患者・家族に繰り返し理解を求める必要がある。
●
● 患者・家族の意向を尊重
最後に、薬物療法及びその適正化は患者・家族の意向を尊重して行わなければならないことを
強調しておきたい。意向を直接確認することはもとより、
CGA等で得られる生活機能や生活状況、
日常の訴えや意見などの情報から患者・家族の意向を推測することが求められる。また、患者・
家族の意思決定支援のためにもACPの考え方と手法を積極的に取り入れることも推奨される。
27