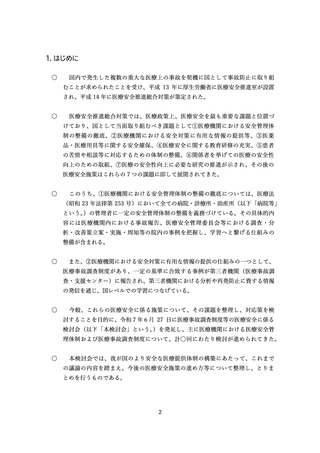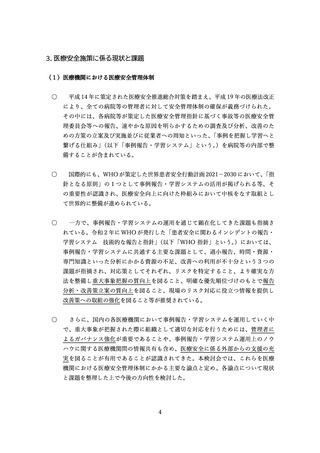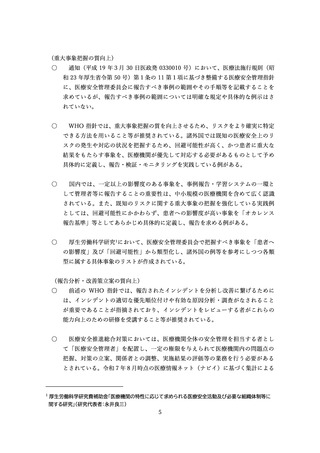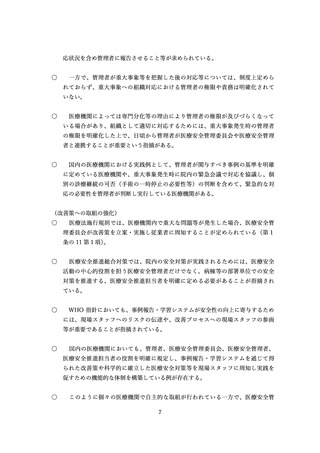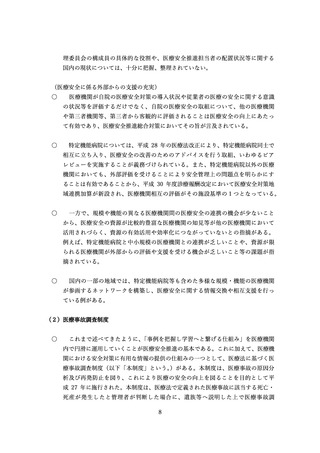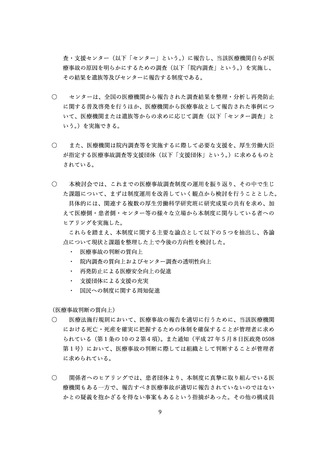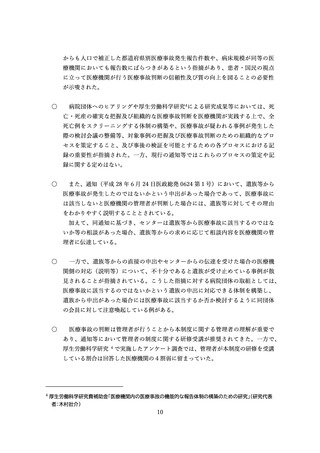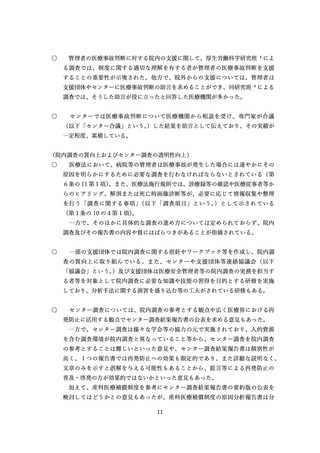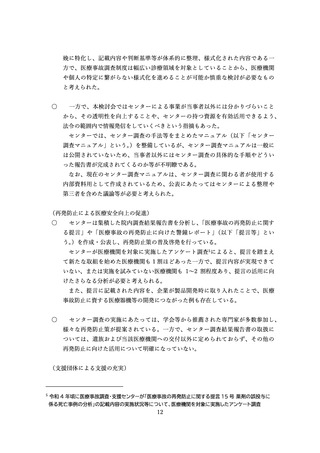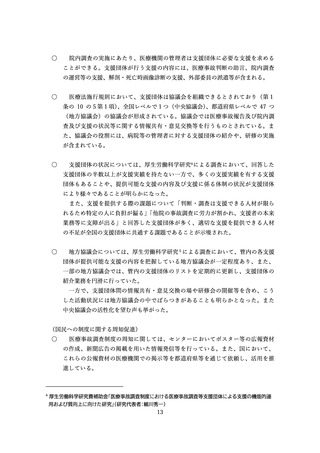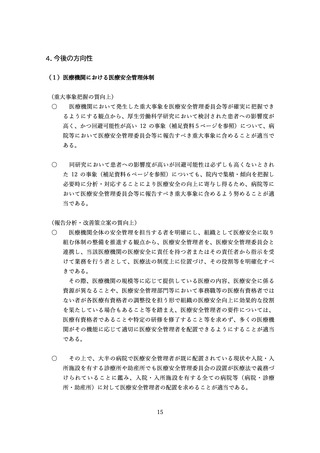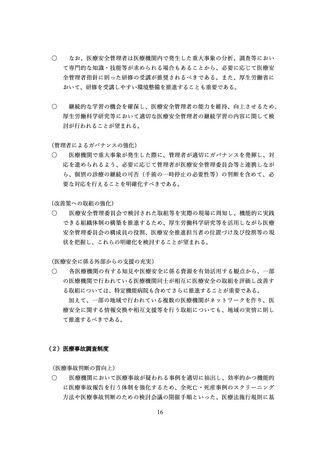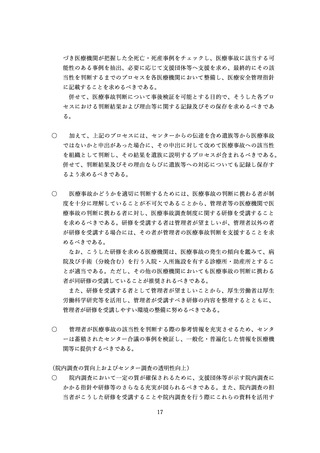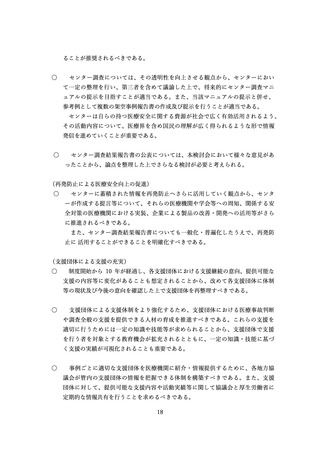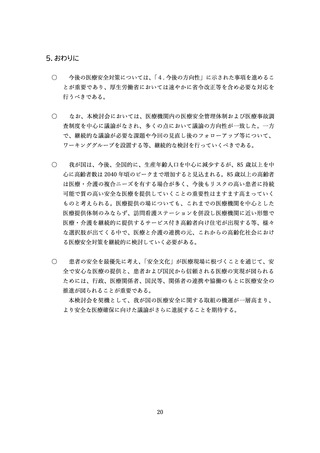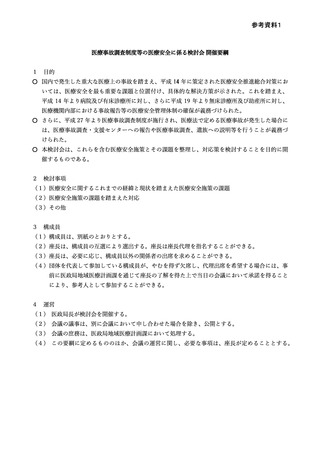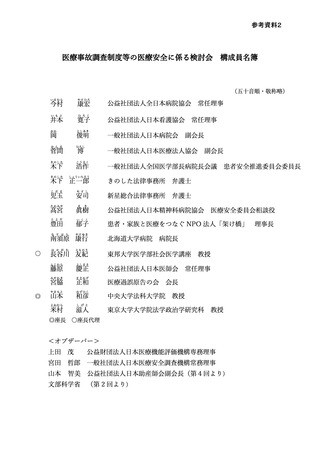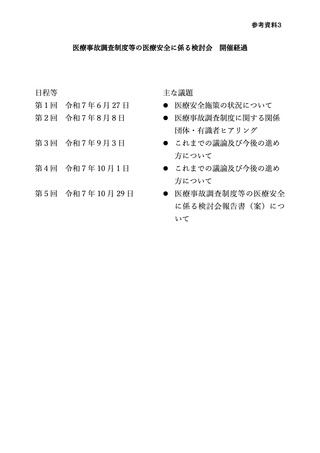よむ、つかう、まなぶ。
資料2 医療事故調査制度等の医療安全に係る検討会報告書(案) (7 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65345.html |
| 出典情報 | 医療事故調査制度等の医療安全に係る検討会(第5回 10/29)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
と、約 95%の病院において医療安全管理者が配置されている2。
○
厚生労働省は「医療安全管理者の業務指針および養成のための研修プログラム
作成指針」(以下「医療安全管理者指針」という。)を作成、周知しており、同指
針の中で、報告された事象の分析を含め、医療安全管理者が必要な能力を習得す
るために受講すべき研修の内容を具体的に示している。また、医療安全管理者の
研修受講は診療報酬における医療安全対策加算等の施設基準の1つとなっており、
令和 7 年 7 月時点において少なくとも約半数の病院が医療安全管理者指針に即した
研修を受講した医療安全管理者を配置している。
○
一方で、医療安全管理者の位置づけが医療法に基づく制度上では明確に定めら
れていないことから、場合によっては医療現場でその役割や責務を適切に設定す
ることが難しく、医療安全管理者が重大事象の分析や改善策立案等の対応で難し
さを感じる場合があることや、医療機関において医療安全管理者の育成が進まな
い要因となっている場合がある等の課題が指摘されている。
○
また、現在、医療安全管理者として業務に携わっている者は主に看護師である
ことが多い一方で、医療安全管理部門等に所属する事務職等の医療有資格者では
ない者が各医療有資格者の調整役を担う等の形で組織の医療安全向上に効果的な
役割を果たしている例も紹介された。
○
なお、医療安全管理者指針において、医療安全管理者が継続的に医療安全に資
する学習と経験を積み重ねることの必要性について言及される等、医療安全管理
者の継続的な学習機会の確保が必要であることが指摘されているが、継続研修に
ついては一部の研修実施団体の自主的な取組に留まっている。現在、厚生労働科
学研究3 において、一度研修を受講した医療安全管理者のさらなる継続学習の現状
把握及び望ましい継続学習の内容の整理が試みられている。
(管理者によるガバナンスの強化)
○
医療法に基づき、病院等の管理者は当該病院等における医療の安全を確保する
ための措置を講じなければならず(第6条の 12)、通知(平成 19 年3月 30 日医政
発 0330010 号)において医療安全管理委員会に重要な検討内容について患者への対
2
医療機能情報提供制度に基づき、全国の医療機関を検索することができる「医療情報ネット(ナビイ)」の登
3
厚生労働科学研究費補助金「医療安全管理者の活動の質向上に向けた研究」(研究代表者:長谷川友紀)
録データより集計。
6
○
厚生労働省は「医療安全管理者の業務指針および養成のための研修プログラム
作成指針」(以下「医療安全管理者指針」という。)を作成、周知しており、同指
針の中で、報告された事象の分析を含め、医療安全管理者が必要な能力を習得す
るために受講すべき研修の内容を具体的に示している。また、医療安全管理者の
研修受講は診療報酬における医療安全対策加算等の施設基準の1つとなっており、
令和 7 年 7 月時点において少なくとも約半数の病院が医療安全管理者指針に即した
研修を受講した医療安全管理者を配置している。
○
一方で、医療安全管理者の位置づけが医療法に基づく制度上では明確に定めら
れていないことから、場合によっては医療現場でその役割や責務を適切に設定す
ることが難しく、医療安全管理者が重大事象の分析や改善策立案等の対応で難し
さを感じる場合があることや、医療機関において医療安全管理者の育成が進まな
い要因となっている場合がある等の課題が指摘されている。
○
また、現在、医療安全管理者として業務に携わっている者は主に看護師である
ことが多い一方で、医療安全管理部門等に所属する事務職等の医療有資格者では
ない者が各医療有資格者の調整役を担う等の形で組織の医療安全向上に効果的な
役割を果たしている例も紹介された。
○
なお、医療安全管理者指針において、医療安全管理者が継続的に医療安全に資
する学習と経験を積み重ねることの必要性について言及される等、医療安全管理
者の継続的な学習機会の確保が必要であることが指摘されているが、継続研修に
ついては一部の研修実施団体の自主的な取組に留まっている。現在、厚生労働科
学研究3 において、一度研修を受講した医療安全管理者のさらなる継続学習の現状
把握及び望ましい継続学習の内容の整理が試みられている。
(管理者によるガバナンスの強化)
○
医療法に基づき、病院等の管理者は当該病院等における医療の安全を確保する
ための措置を講じなければならず(第6条の 12)、通知(平成 19 年3月 30 日医政
発 0330010 号)において医療安全管理委員会に重要な検討内容について患者への対
2
医療機能情報提供制度に基づき、全国の医療機関を検索することができる「医療情報ネット(ナビイ)」の登
3
厚生労働科学研究費補助金「医療安全管理者の活動の質向上に向けた研究」(研究代表者:長谷川友紀)
録データより集計。
6