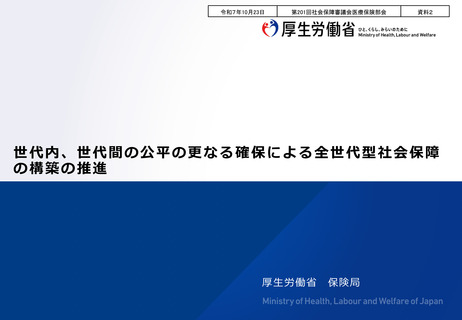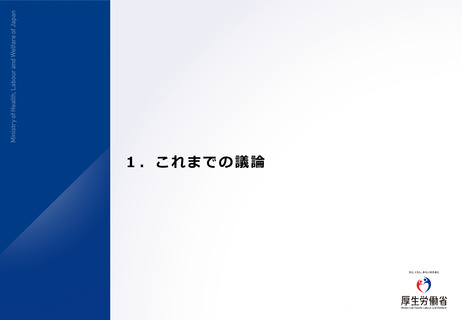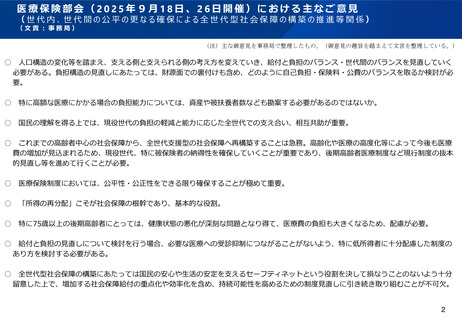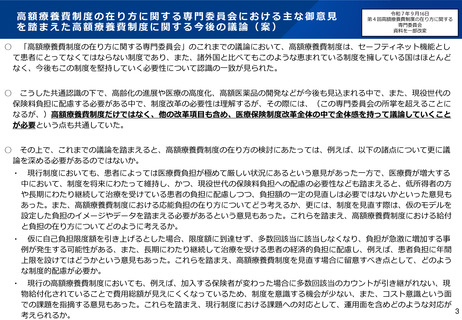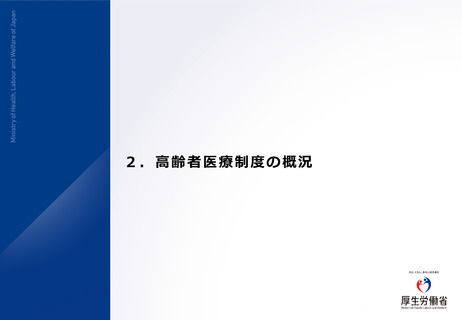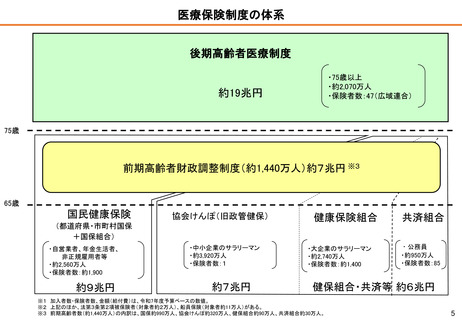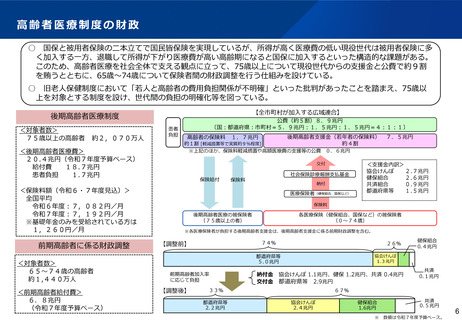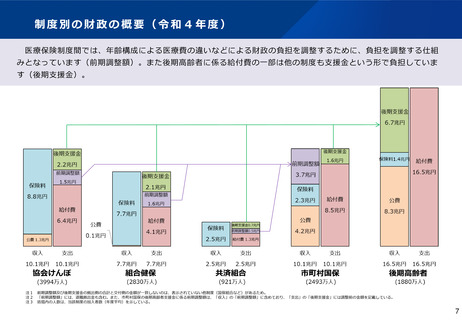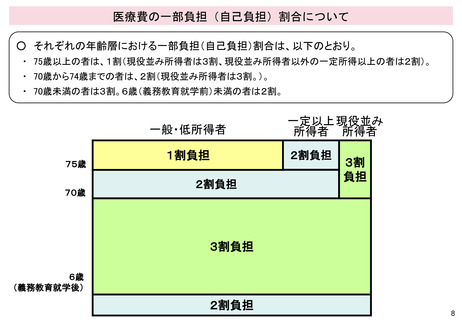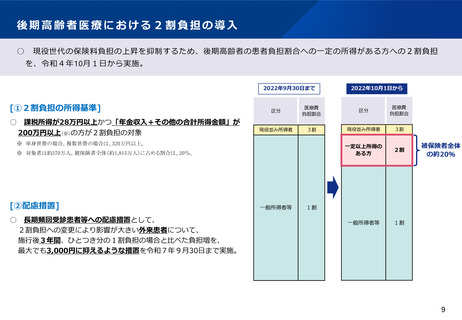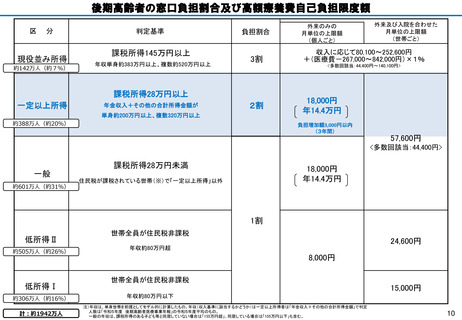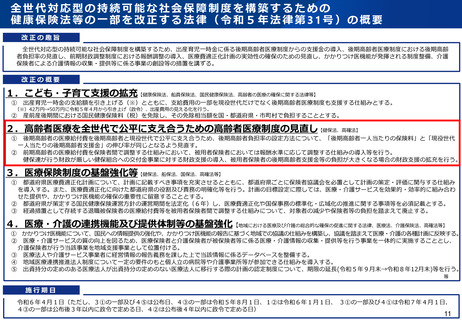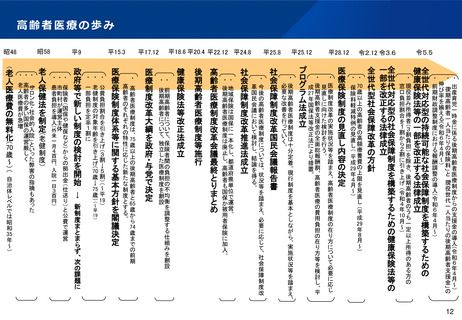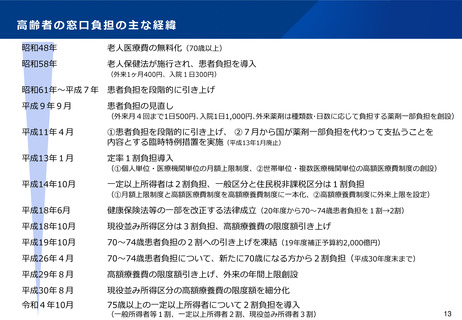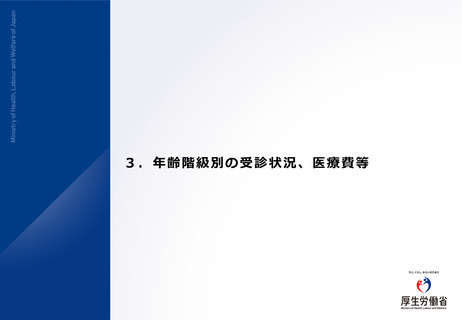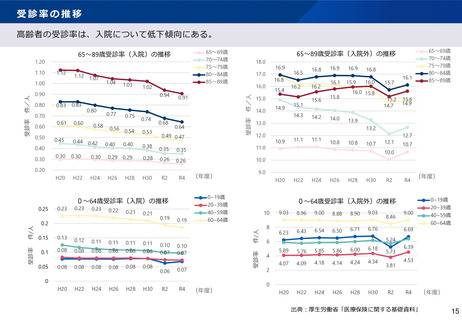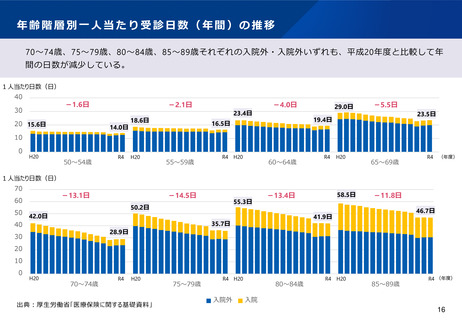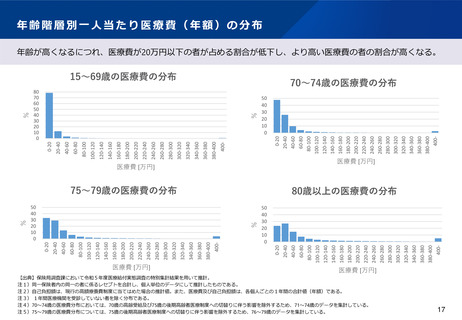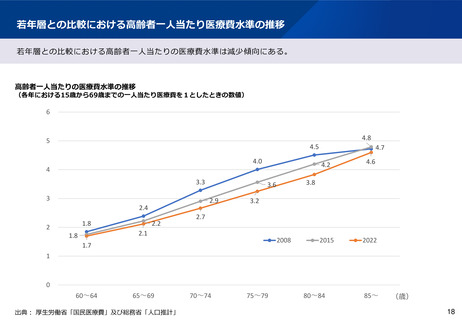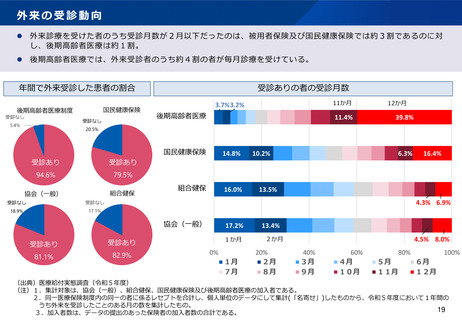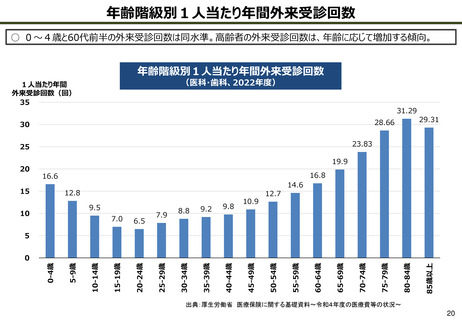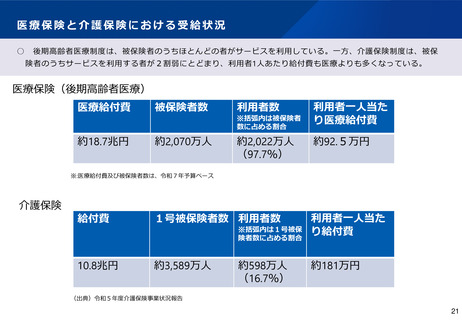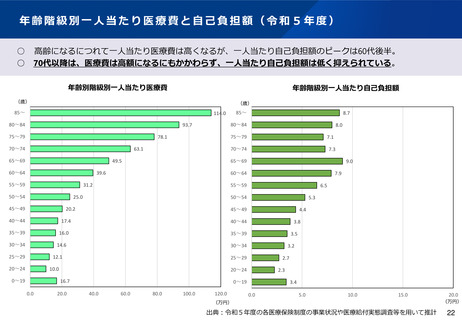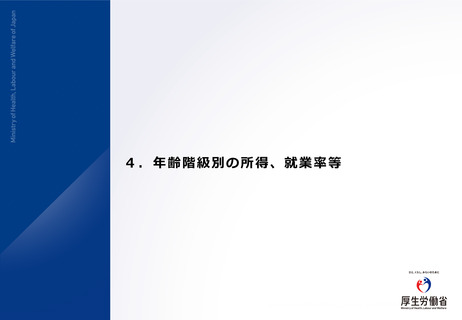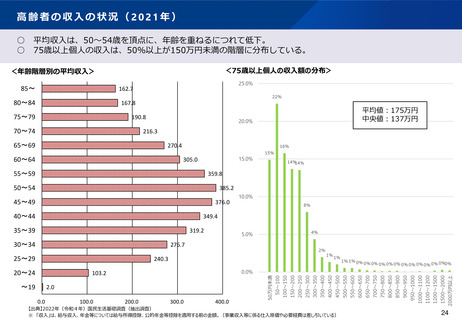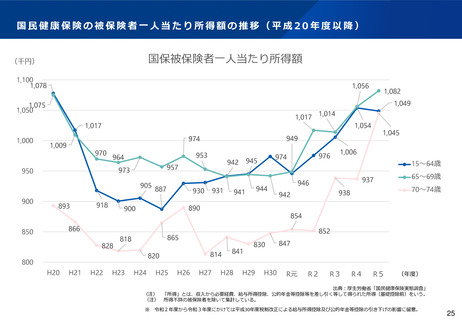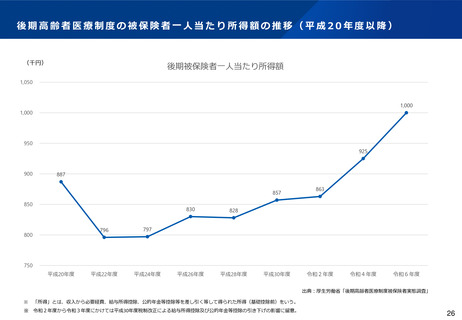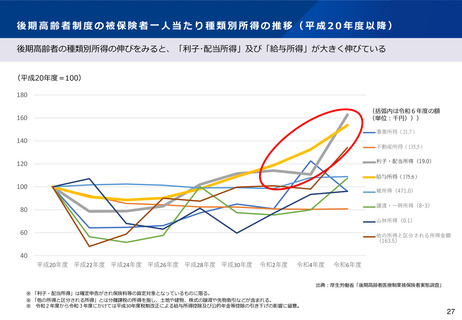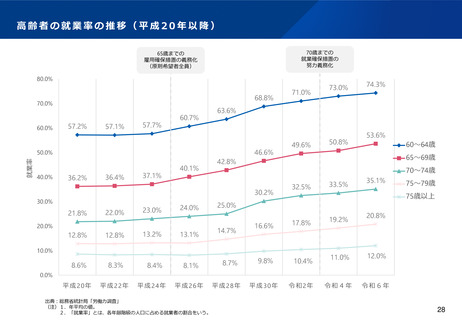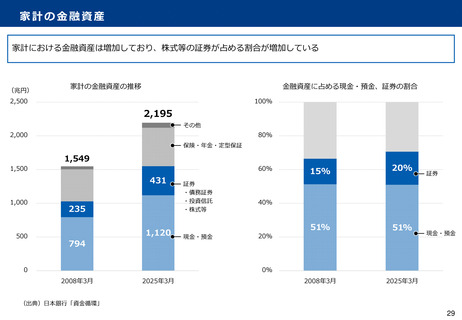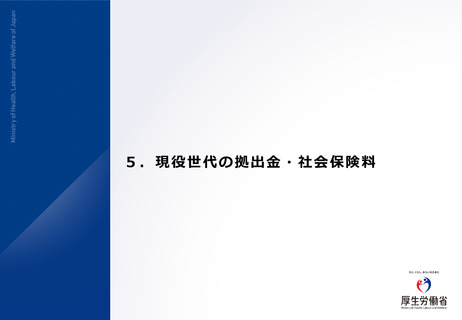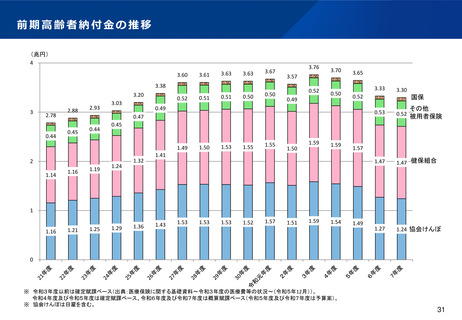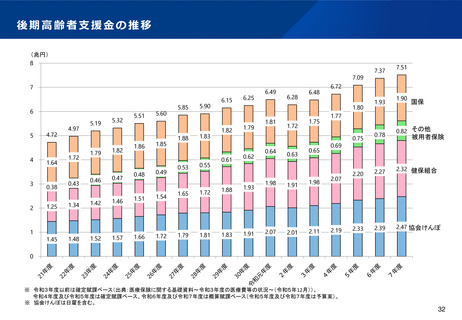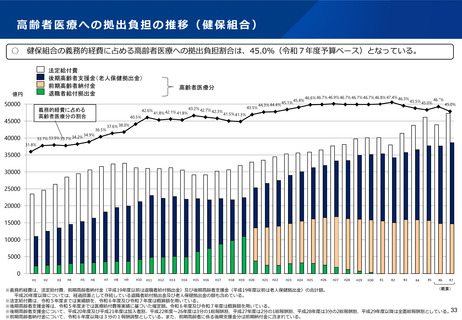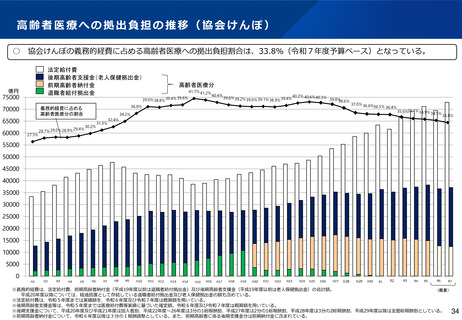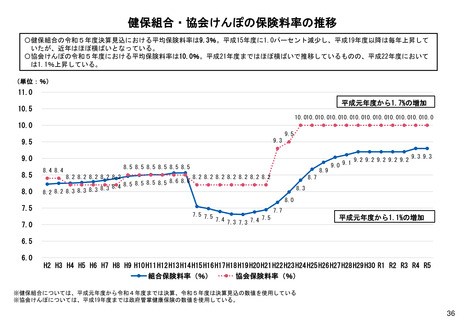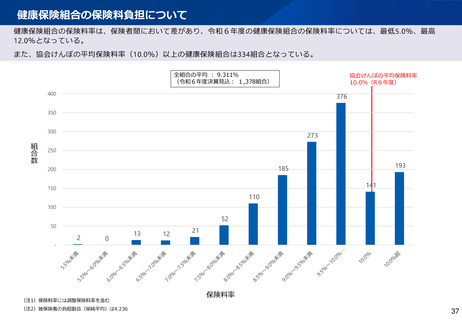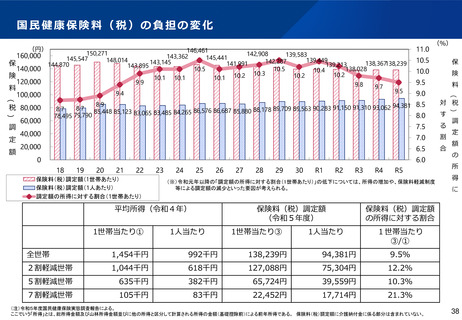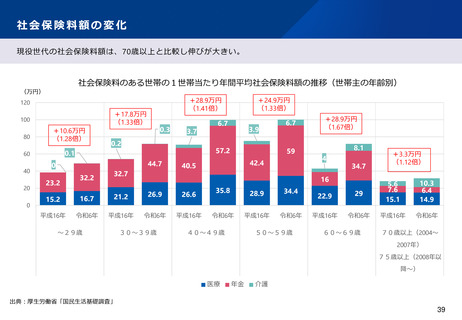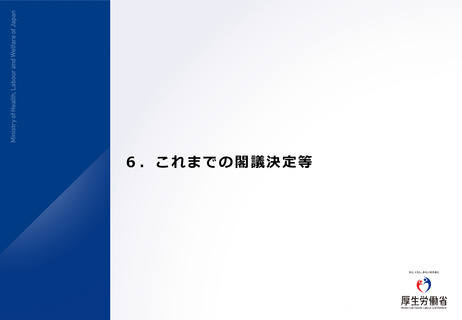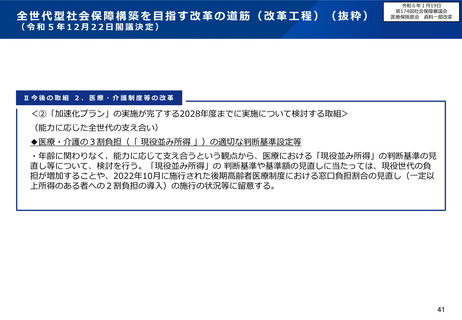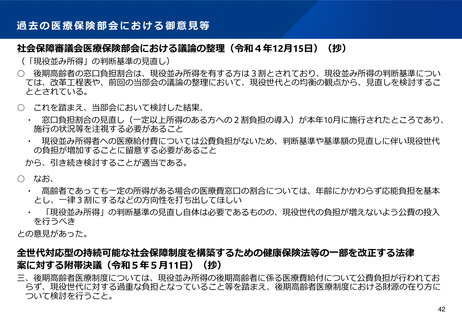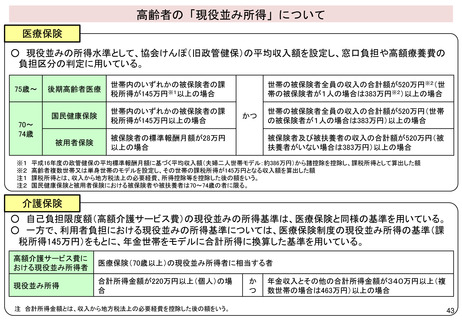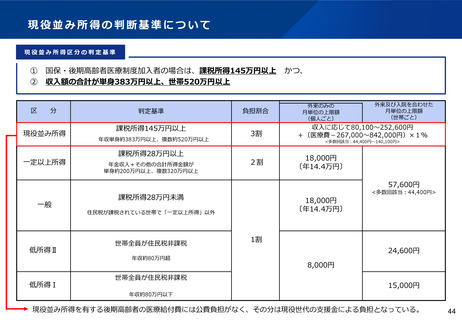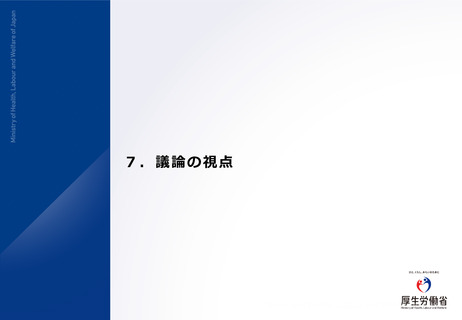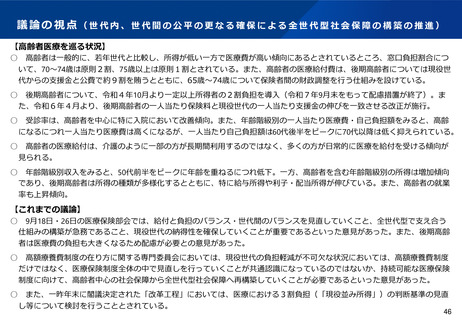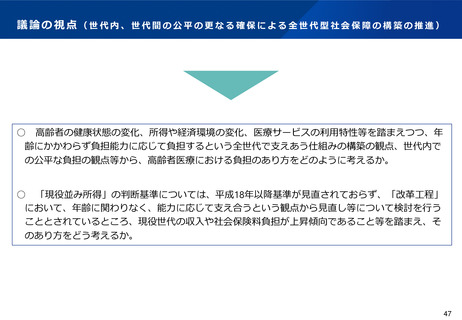よむ、つかう、まなぶ。
【資料2】世代内、世代間の公平の更なる確保による全世代型社会保障の構築の推進 (14 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65085.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第201回 10/23)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
高齢者の窓口負担の主な経緯
昭和48年
老人医療費の無料化(70歳以上)
昭和58年
老人保健法が施行され、患者負担を導入
(外来1ヶ月400円、入院1日300円)
昭和61年~平成7年
患者負担を段階的に引き上げ
平成9年9月
患者負担の見直し
(外来月4回まで1日500円、入院1日1,000円、外来薬剤は種類数・日数に応じて負担する薬剤一部負担を創設)
平成11年4月
①患者負担を段階的に引き上げ、 ②7月から国が薬剤一部負担を代わって支払うことを
内容とする臨時特例措置を実施(平成13年1月廃止)
平成13年1月
定率1割負担導入
(①個人単位・医療機関単位の月額上限制度、②世帯単位・複数医療機関単位の高額医療費制度の創設)
平成14年10月
一定以上所得者は2割負担、一般区分と住民税非課税区分は1割負担
(①月額上限制度と高額医療費制度を高額療養費制度に一本化、②高額療養費制度に外来上限を設定)
平成18年6月
健康保険法等の一部を改正する法律成立(20年度から70~74歳患者負担を1割→2割)
平成18年10月
現役並み所得区分は3割負担、高額療養費の限度額引き上げ
平成19年10月
70~74歳患者負担の2割への引き上げを凍結(19年度補正予算約2,000億円)
平成26年4月
70~74歳患者負担について、新たに70歳になる方から2割負担(平成30年度末まで)
平成29年8月
高額療養費の限度額引き上げ、外来の年間上限創設
平成30年8月
現役並み所得区分の高額療養費の限度額を細分化
令和4年10月
75歳以上の一定以上所得者について2割負担を導入
(一般所得者等1割、一定以上所得者2割、現役並み所得者3割)
13
昭和48年
老人医療費の無料化(70歳以上)
昭和58年
老人保健法が施行され、患者負担を導入
(外来1ヶ月400円、入院1日300円)
昭和61年~平成7年
患者負担を段階的に引き上げ
平成9年9月
患者負担の見直し
(外来月4回まで1日500円、入院1日1,000円、外来薬剤は種類数・日数に応じて負担する薬剤一部負担を創設)
平成11年4月
①患者負担を段階的に引き上げ、 ②7月から国が薬剤一部負担を代わって支払うことを
内容とする臨時特例措置を実施(平成13年1月廃止)
平成13年1月
定率1割負担導入
(①個人単位・医療機関単位の月額上限制度、②世帯単位・複数医療機関単位の高額医療費制度の創設)
平成14年10月
一定以上所得者は2割負担、一般区分と住民税非課税区分は1割負担
(①月額上限制度と高額医療費制度を高額療養費制度に一本化、②高額療養費制度に外来上限を設定)
平成18年6月
健康保険法等の一部を改正する法律成立(20年度から70~74歳患者負担を1割→2割)
平成18年10月
現役並み所得区分は3割負担、高額療養費の限度額引き上げ
平成19年10月
70~74歳患者負担の2割への引き上げを凍結(19年度補正予算約2,000億円)
平成26年4月
70~74歳患者負担について、新たに70歳になる方から2割負担(平成30年度末まで)
平成29年8月
高額療養費の限度額引き上げ、外来の年間上限創設
平成30年8月
現役並み所得区分の高額療養費の限度額を細分化
令和4年10月
75歳以上の一定以上所得者について2割負担を導入
(一般所得者等1割、一定以上所得者2割、現役並み所得者3割)
13