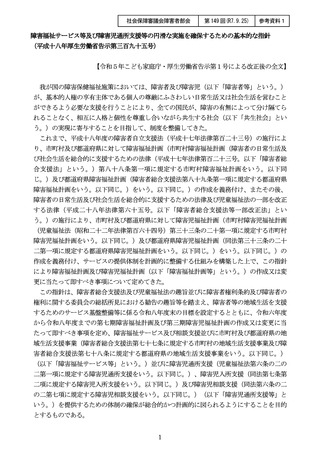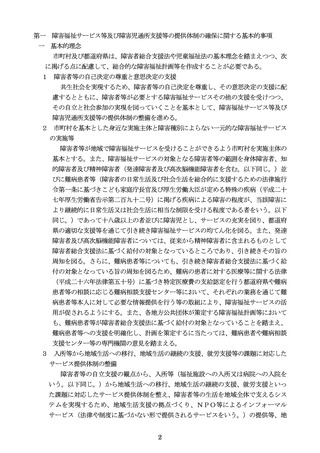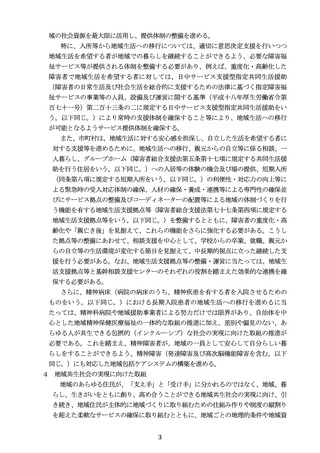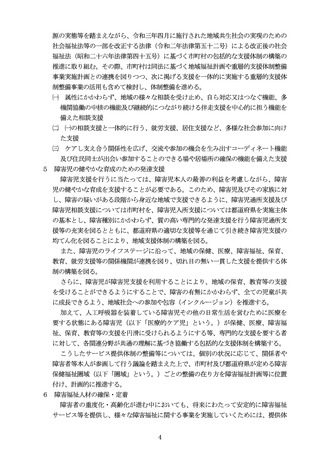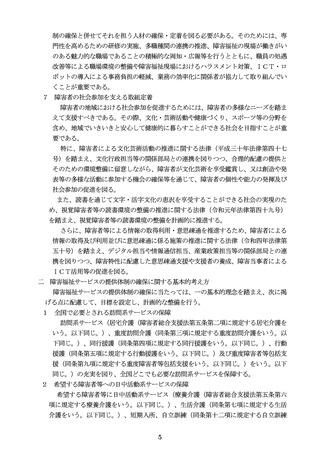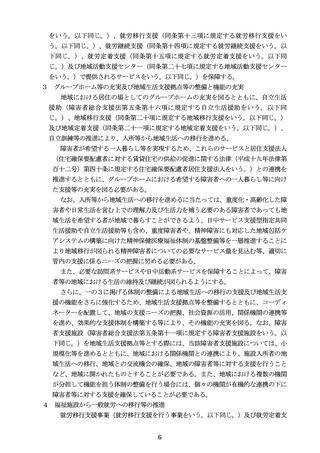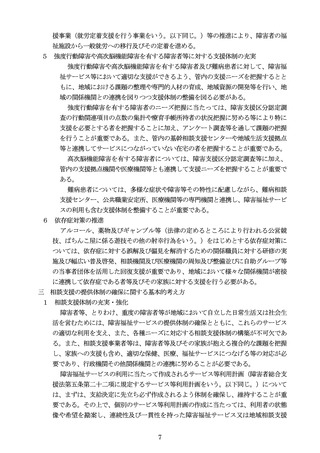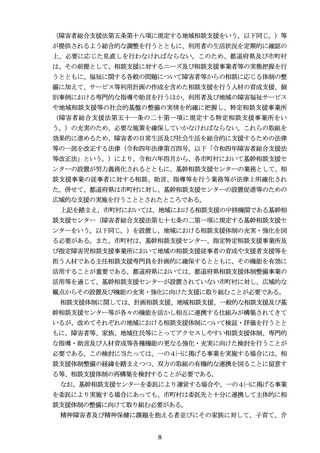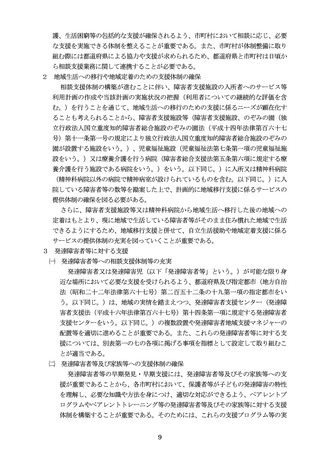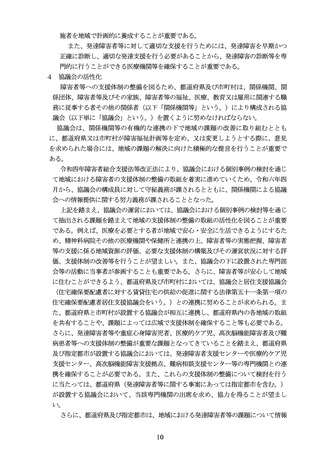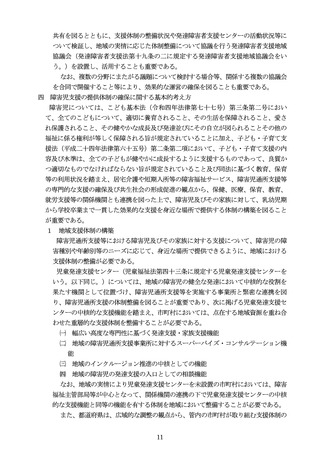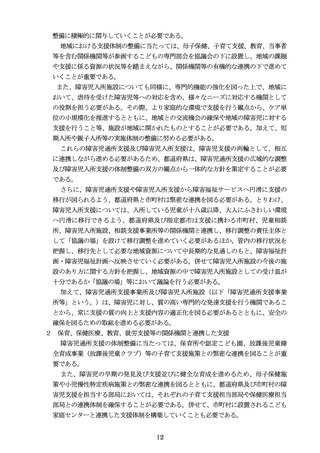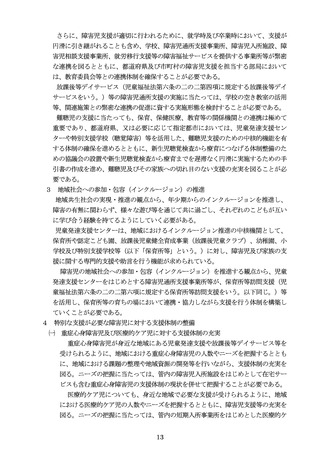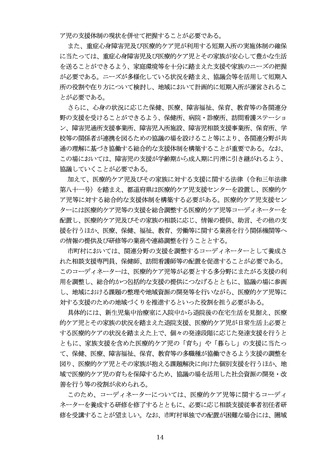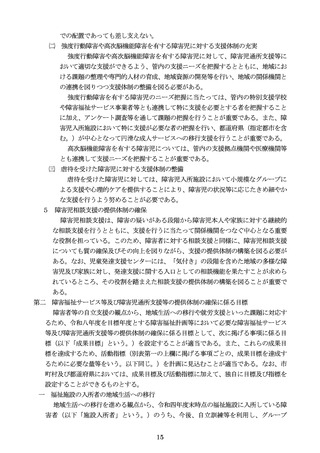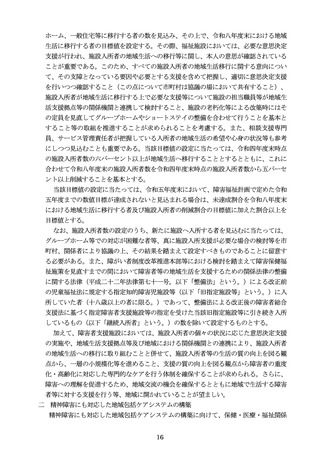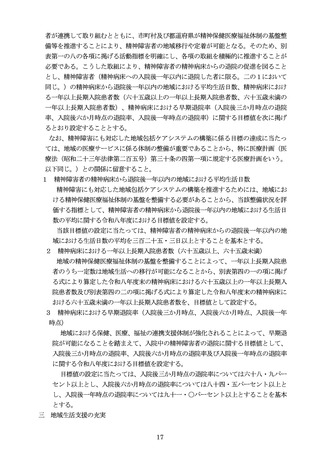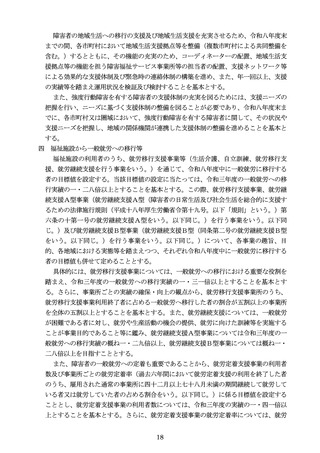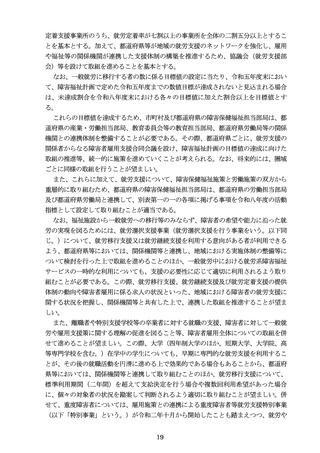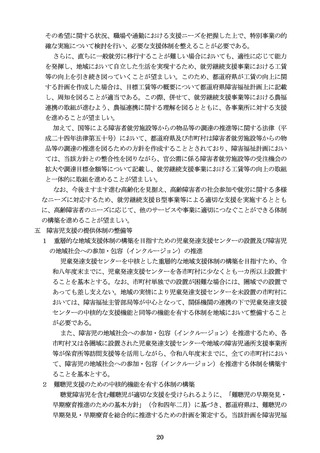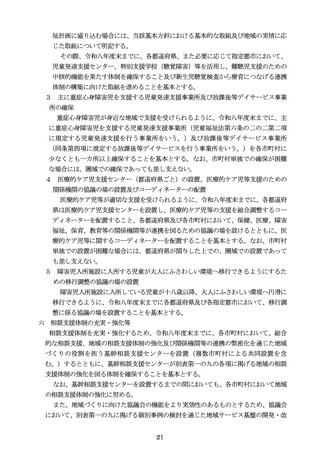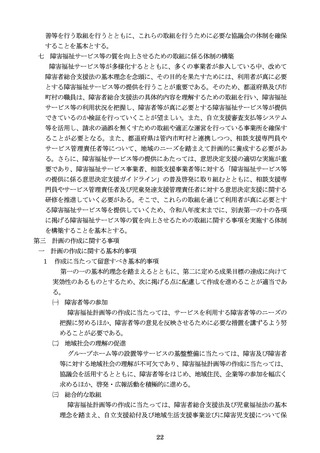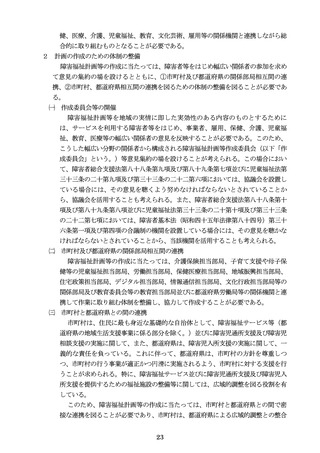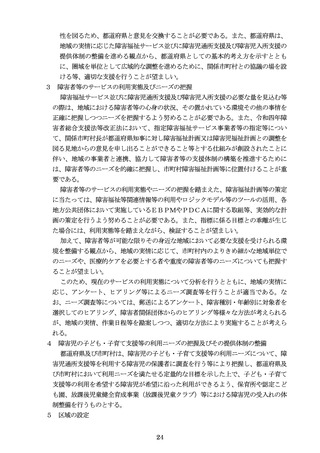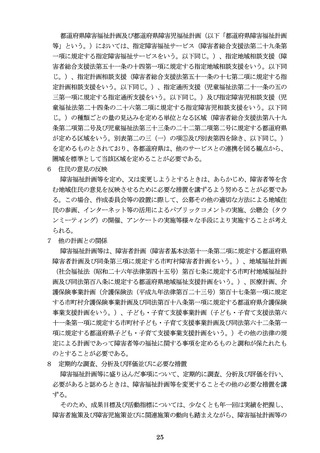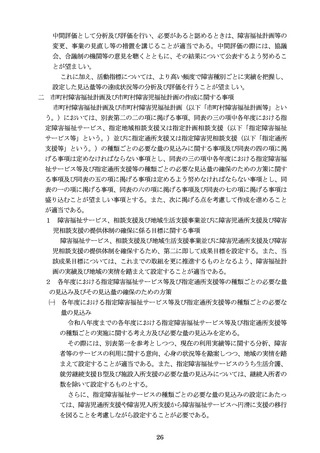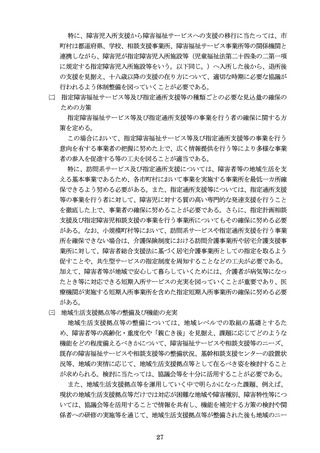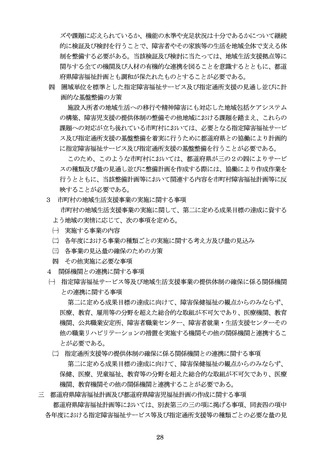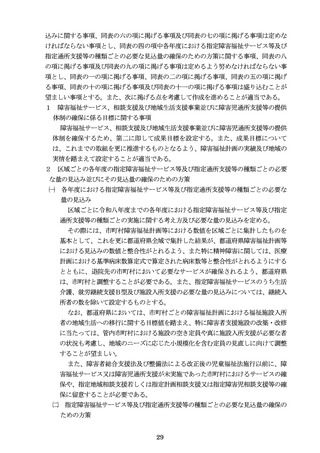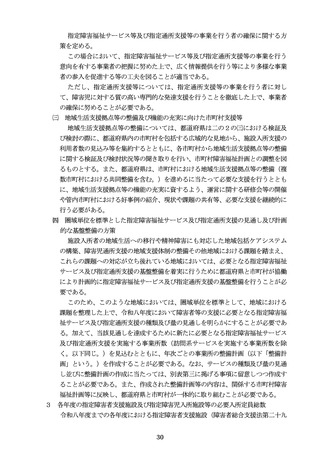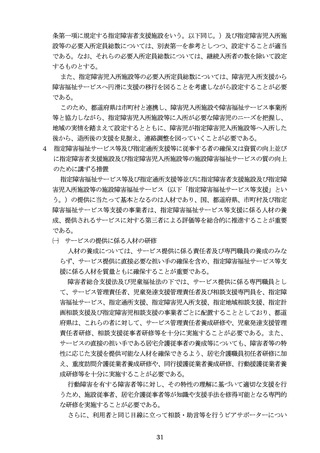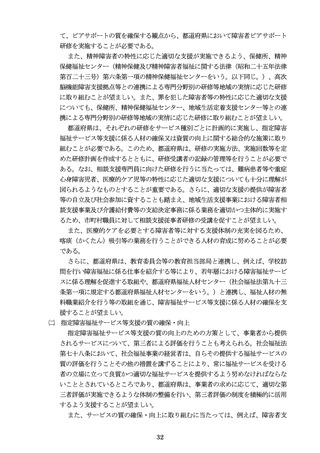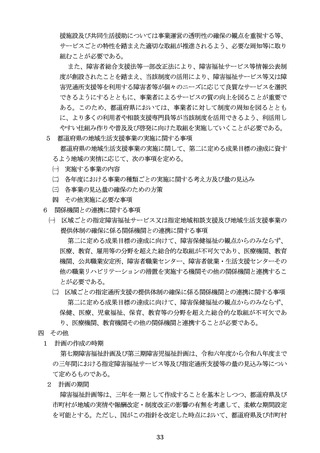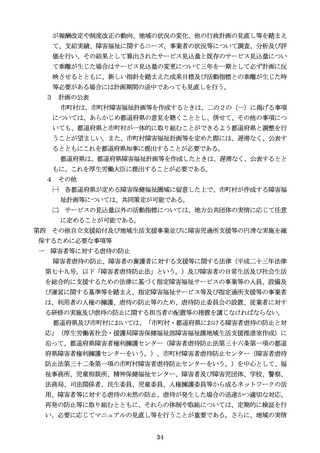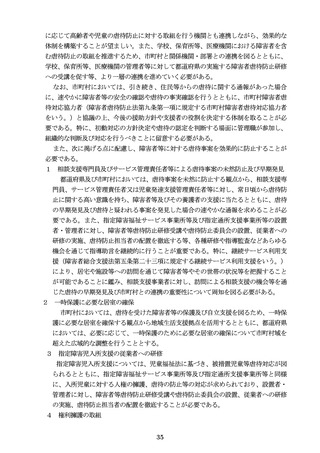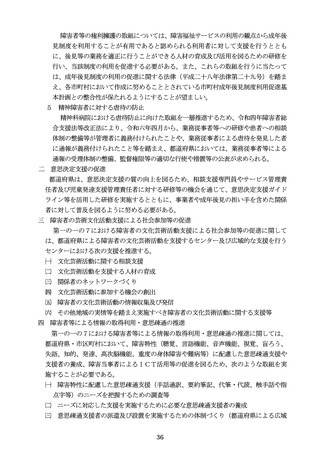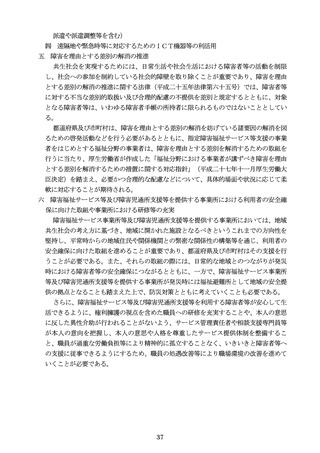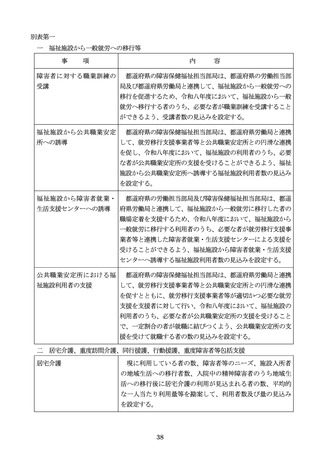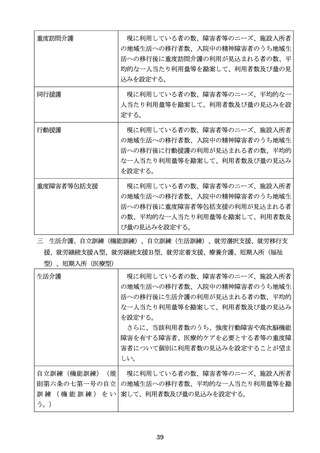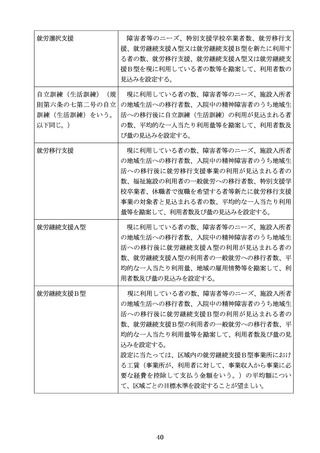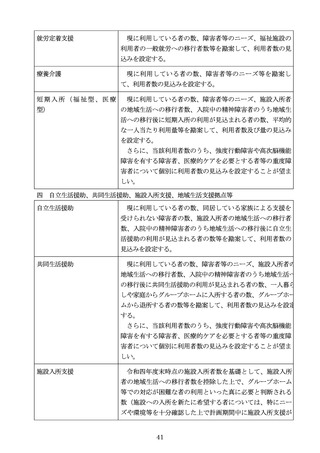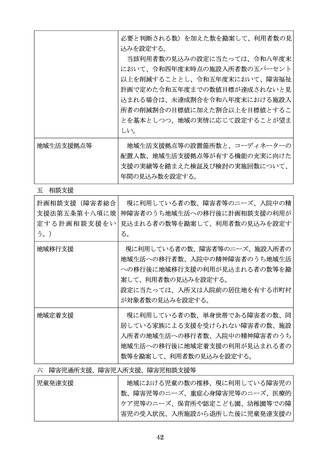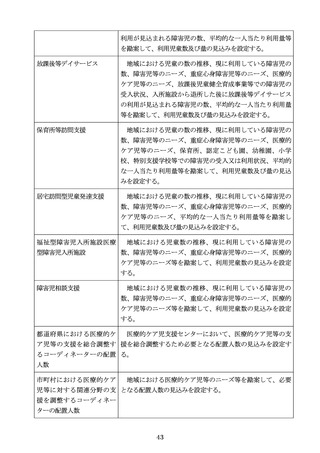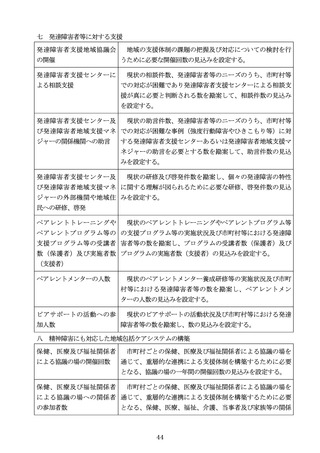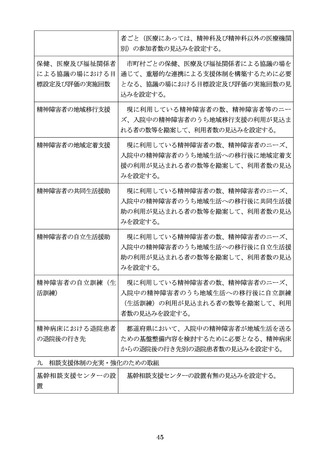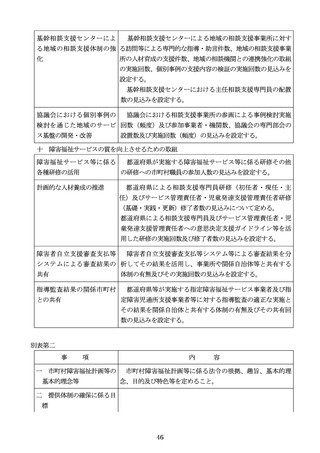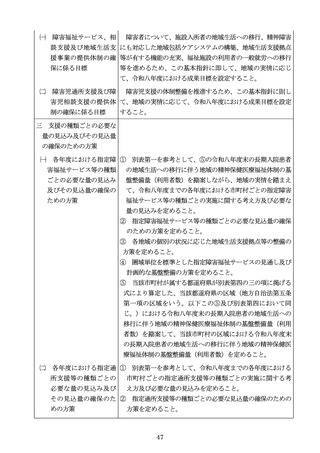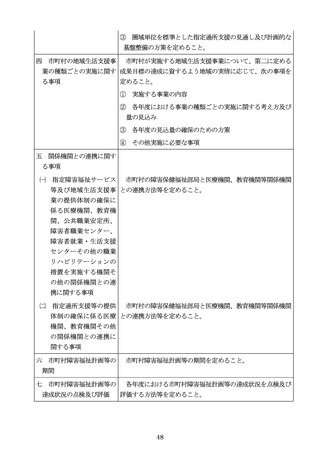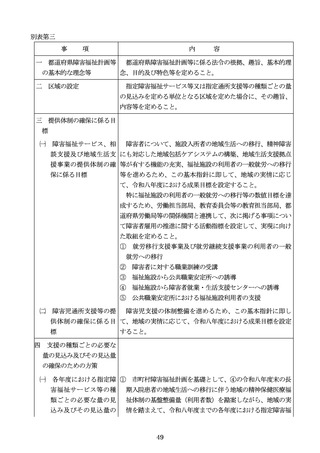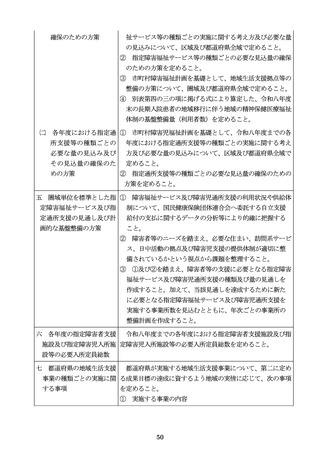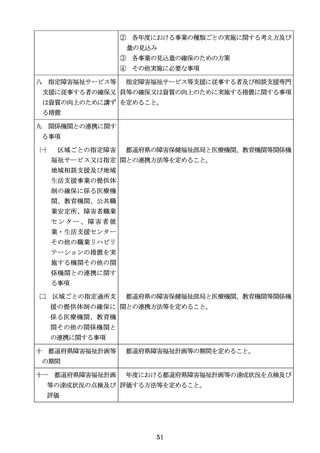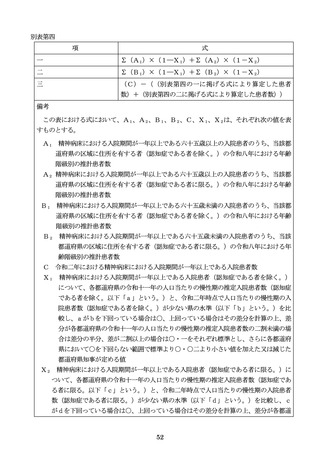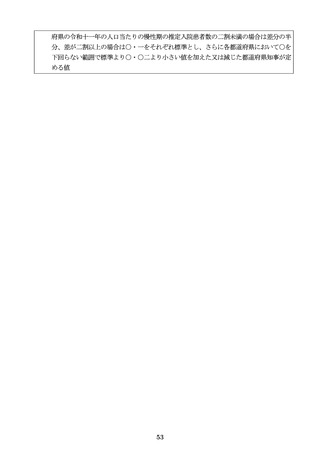よむ、つかう、まなぶ。
参考資料1 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(現行) (10 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63886.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第149回 9/25)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
施者を地域で計画的に養成することが重要である。
また、発達障害者等に対して適切な支援を行うためには、発達障害を早期かつ
正確に診断し、適切な発達支援を行う必要があることから、発達障害の診断等を専
門的に行うことができる医療機関等を確保することが重要である。
4 協議会の活性化
障害者等への支援体制の整備を図るため、都道府県及び市町村は、関係機関、関
係団体、障害者等及びその家族、障害者等の福祉、医療、教育又は雇用に関連する職
務に従事する者その他の関係者(以下「関係機関等」という。)により構成される協
議会(以下単に「協議会」という。)を置くように努めなければならない。
協議会は、関係機関等の有機的な連携の下で地域の課題の改善に取り組むととも
に、都道府県又は市町村が障害福祉計画等を定め、又は変更しようとする際に、意見
を求められた場合には、地域の課題の解決に向けた積極的な提言を行うことが重要で
ある。
令和四年障害者総合支援法等改正法により、協議会における個別事例の検討を通じ
て地域における障害者の支援体制の整備の取組を着実に進めていくため、令和六年四
月から、協議会の構成員に対して守秘義務が課されるとともに、関係機関による協議
会への情報提供に関する努力義務が課されることとなった。
上記を踏まえ、協議会の運営においては、協議会における個別事例の検討等を通じ
て抽出される課題を踏まえて地域の支援体制の整備の取組の活性化を図ることが重要
である。例えば、医療を必要とする者が地域で安心・安全に生活できるようにするた
め、精神科病院その他の医療機関や保健所と連携の上、障害者等の実態把握、障害者
等の支援に係る地域資源の評価、必要な支援体制の構築及びその運営状況に対する評
価、支援体制の改善等を行うことが望ましい。また、協議会の下に設置された専門部
会等の活動に当事者が参画することも重要である。さらに、障害者等が安心して地域
に住むことができるよう、都道府県及び市町村においては、協議会と居住支援協議会
(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第五十一条第一項の
住宅確保要配慮者居住支援協議会をいう。)との連携に努めることが求められる。ま
た、都道府県と市町村が設置する協議会が相互に連携し、都道府県内の各地域の取組
を共有することや、課題によっては広域で支援体制を確保すること等も必要である。
さらに、発達障害者等や重症心身障害児者、医療的ケア児、高次脳機能障害者及び難
病患者等への支援体制の整備が重要な課題となってきていることを踏まえ、都道府県
及び指定都市が設置する協議会においては、発達障害者支援センターや医療的ケア児
支援センター、高次脳機能障害支援拠点、難病相談支援センター等の専門機関との連
携を確保することが必要である。また、これらの支援体制の整備について検討を行う
に当たっては、都道府県(発達障害者等に関する事案にあっては指定都市を含む。)
が設置する協議会において、当該専門機関の出席を求め、協力を得ることが望まし
い。
さらに、都道府県及び指定都市は、地域における発達障害者等の課題について情報
10
また、発達障害者等に対して適切な支援を行うためには、発達障害を早期かつ
正確に診断し、適切な発達支援を行う必要があることから、発達障害の診断等を専
門的に行うことができる医療機関等を確保することが重要である。
4 協議会の活性化
障害者等への支援体制の整備を図るため、都道府県及び市町村は、関係機関、関
係団体、障害者等及びその家族、障害者等の福祉、医療、教育又は雇用に関連する職
務に従事する者その他の関係者(以下「関係機関等」という。)により構成される協
議会(以下単に「協議会」という。)を置くように努めなければならない。
協議会は、関係機関等の有機的な連携の下で地域の課題の改善に取り組むととも
に、都道府県又は市町村が障害福祉計画等を定め、又は変更しようとする際に、意見
を求められた場合には、地域の課題の解決に向けた積極的な提言を行うことが重要で
ある。
令和四年障害者総合支援法等改正法により、協議会における個別事例の検討を通じ
て地域における障害者の支援体制の整備の取組を着実に進めていくため、令和六年四
月から、協議会の構成員に対して守秘義務が課されるとともに、関係機関による協議
会への情報提供に関する努力義務が課されることとなった。
上記を踏まえ、協議会の運営においては、協議会における個別事例の検討等を通じ
て抽出される課題を踏まえて地域の支援体制の整備の取組の活性化を図ることが重要
である。例えば、医療を必要とする者が地域で安心・安全に生活できるようにするた
め、精神科病院その他の医療機関や保健所と連携の上、障害者等の実態把握、障害者
等の支援に係る地域資源の評価、必要な支援体制の構築及びその運営状況に対する評
価、支援体制の改善等を行うことが望ましい。また、協議会の下に設置された専門部
会等の活動に当事者が参画することも重要である。さらに、障害者等が安心して地域
に住むことができるよう、都道府県及び市町村においては、協議会と居住支援協議会
(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第五十一条第一項の
住宅確保要配慮者居住支援協議会をいう。)との連携に努めることが求められる。ま
た、都道府県と市町村が設置する協議会が相互に連携し、都道府県内の各地域の取組
を共有することや、課題によっては広域で支援体制を確保すること等も必要である。
さらに、発達障害者等や重症心身障害児者、医療的ケア児、高次脳機能障害者及び難
病患者等への支援体制の整備が重要な課題となってきていることを踏まえ、都道府県
及び指定都市が設置する協議会においては、発達障害者支援センターや医療的ケア児
支援センター、高次脳機能障害支援拠点、難病相談支援センター等の専門機関との連
携を確保することが必要である。また、これらの支援体制の整備について検討を行う
に当たっては、都道府県(発達障害者等に関する事案にあっては指定都市を含む。)
が設置する協議会において、当該専門機関の出席を求め、協力を得ることが望まし
い。
さらに、都道府県及び指定都市は、地域における発達障害者等の課題について情報
10