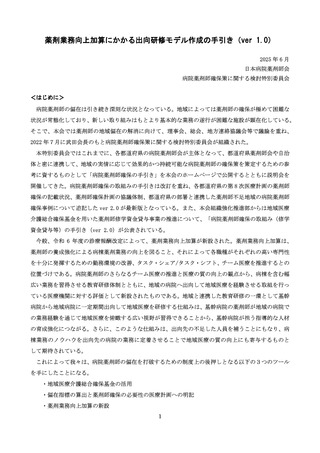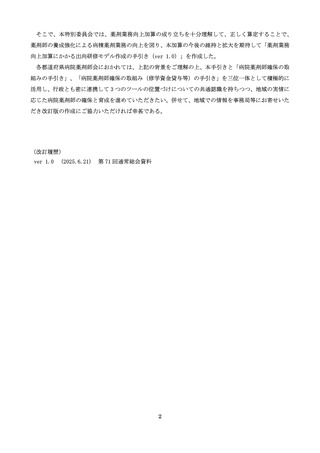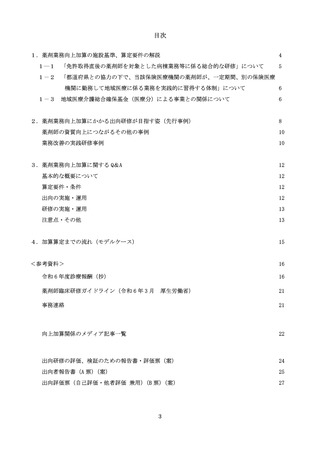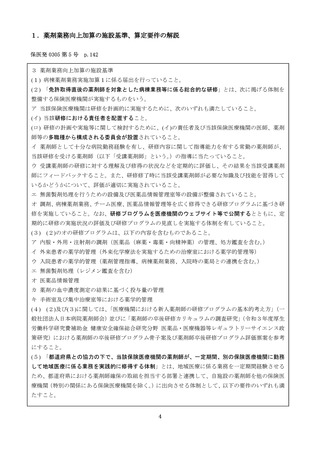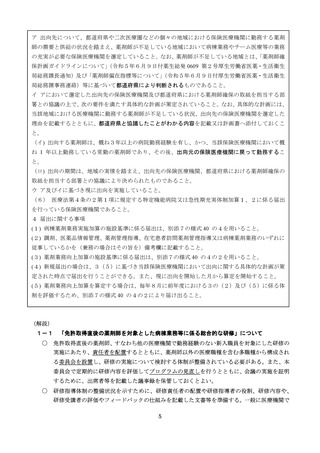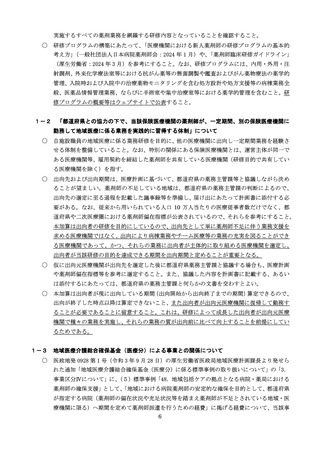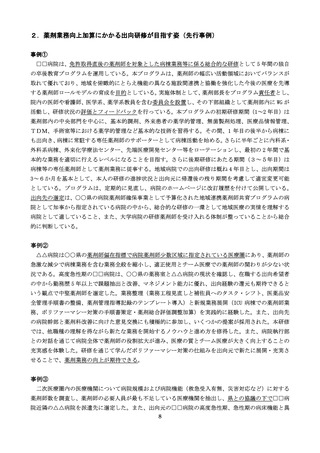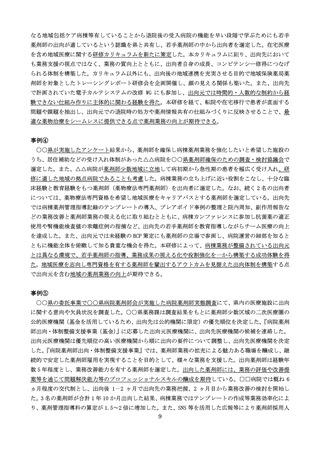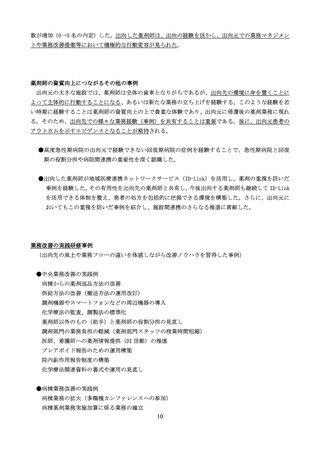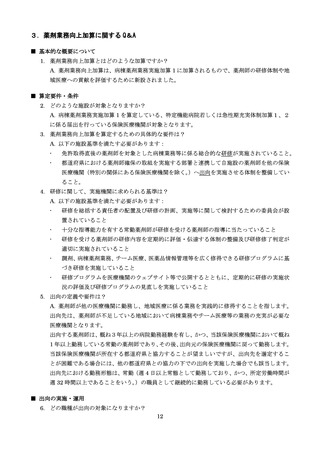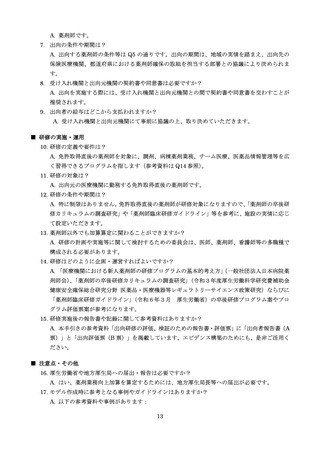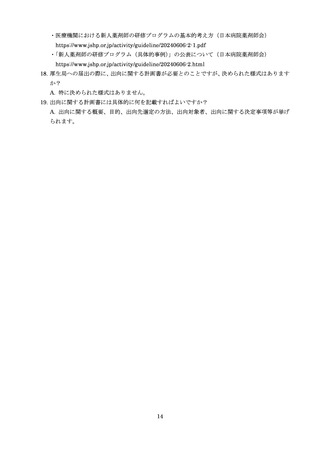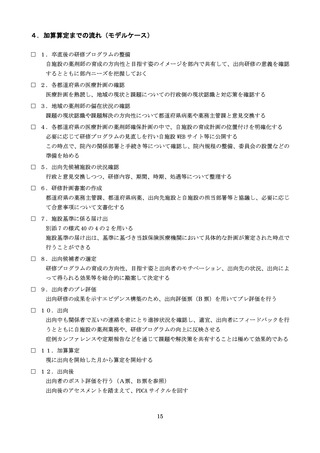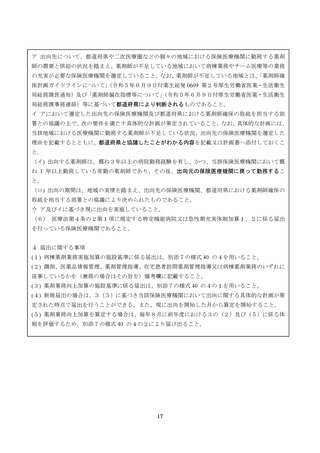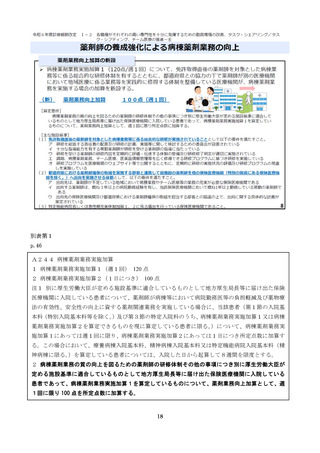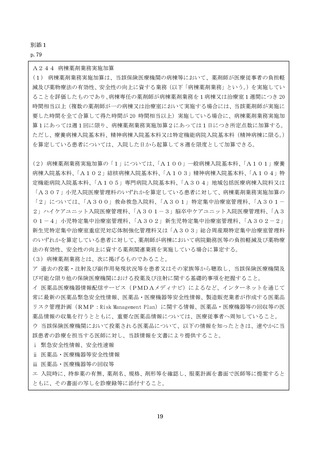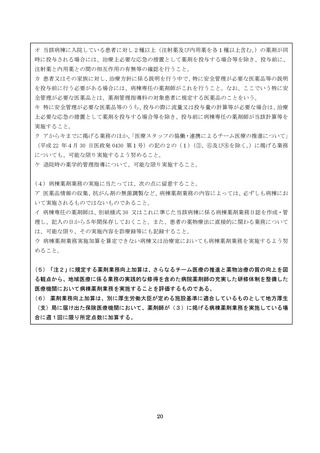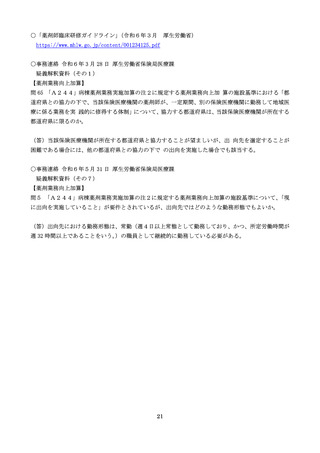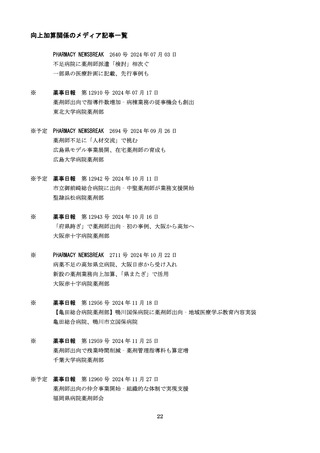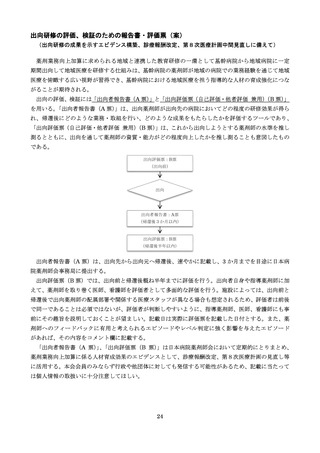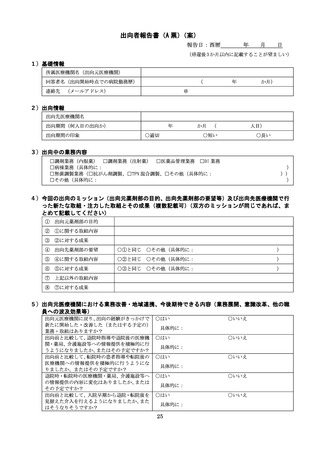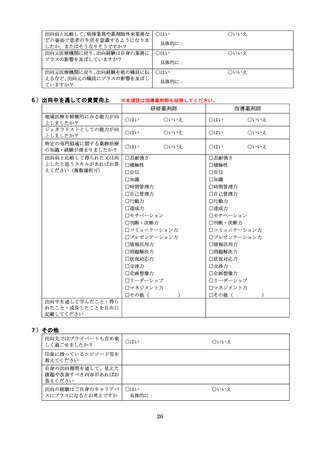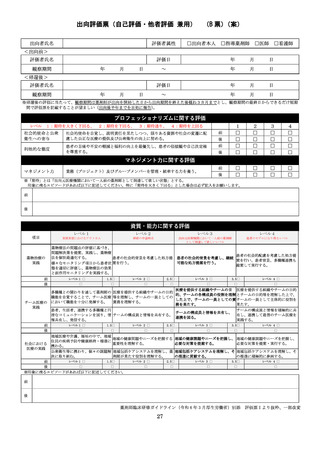よむ、つかう、まなぶ。
薬剤業務向上加算にかかる出向研修モデル作成の手引き(ver 1.0) (8 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.jshp.or.jp/content/2025/0703-1.html |
| 出典情報 | 薬剤業務向上加算にかかる出向研修モデル作成の手引き(ver 1.0)の公表について(7/3)《日本病院薬剤師会》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
2.薬剤業務向上加算にかかる出向研修が目指す姿(先行事例)
事例①
□□病院は、免許取得直後の薬剤師を対象とした病棟業務等に係る総合的な研修として 5 年間の独自
の卒後教育プログラムを運用している。本プログラムは、薬剤師の幅広い活動領域においてバランスが
取れて優れており、地域を俯瞰的にとらえ機能の異なる施設間連携と協働を強化した今後の医療を先導
する薬剤師ロールモデルの育成を目的としている。実施体制として、薬剤部長をプログラム責任者とし、
院内の医師や看護師、医学系、薬学系教員を含む委員会を設置し、その下部組織として薬剤部内に WG が
活動し、研修状況の評価とフィードバックを行っている。本プログラムの初期研修期間(1~2 年目)は
薬剤部内の中央部門を中心に、基本的調剤、外来患者の薬学的管理、無菌製剤処理、医療品情報管理、
TDM、手術室等における薬学的管理など基本的な技術を習得する。その間、1 年目の後半から病棟に
も出向き、病棟に常駐する専任薬剤師のサポーターとして病棟活動を始める。さらに半年ごとに内科系・
外科系病棟、外来化学療法センター、先端医療開発センター等をローテーションし、最初の 2 年間で基
本的な業務を適切に行えるレベルになることを目指す。さらに後期研修にあたる期間(3~5年目)は
病棟等の専任薬剤師として薬剤業務に従事する。地域病院での出向研修は概ね 4 年目とし、出向期間は
3~6か月を基本として、本人の研修の進捗状況と出向元に帰還後の残り期間を考慮して適宜変更可能
としている。プログラムは、定期的に見直し、病院のホームページに改訂履歴を付けて公開している。
出向先の選定は、〇〇県の病院薬剤師確保事業として予算化された地域連携薬剤師共育プログラムの病
院として知事から指定されている病院の中から、総合的な研修の一環として地域医療の実情を理解する
病院として適していること、また、大学病院の研修薬剤師を受け入れる体制が整っていることから総合
的に判断している。
事例②
△△病院は〇〇県の薬剤師偏在指標で病院薬剤師少数区域に指定されている医療圏にあり、薬剤師の
急激な減少で病棟業務を含む業務全般を縮小し、適正使用とチーム医療での薬剤師の関わりが少ない状
況である。高度急性期の□□病院は、〇〇県の薬務室と△△病院の現状を確認し、在職する出向希望者
の中から勤務歴 5 年以上で課題抽出と改善、マネジメント能力に優れ、出向経験の還元も期待できると
いう観点で中堅薬剤師を選定した。業務整理(業務工程見直しと補佐員へのタスク・シフト、医薬品安
全管理手順書の整備、薬剤管理指導記録のテンプレート導入)と新規業務展開(ICU 病棟での薬剤師業
務、ポリファーマシー対策の手順書策定・薬剤総合評価調整加算)を実践的に経験した。また、出向先
の病院幹部と薬剤科改善に向けた意見交換にも積極的に参加し、いくつかの提案が採用された。本研修
では、他職種の理解を得ながら新たな業務を開始するノウハウと進め方を修得した。また、病院執行部
との対話を通じて病院全体で薬剤師の役割拡大が進み、医療の質とチーム医療が大きく向上することの
充実感を体験した。研修を通じて学んだポリファーマシー対策の仕組みを出向元で新たに展開・充実さ
せることで、薬剤業務の向上が期待できる。
事例③
二次医療圏内の医療機関について病院規模および病院機能(救急受入有無、災害対応など)に対する
薬剤師数を調査し、薬剤師の必要人員が最も不足している医療機関を抽出し、県との協議の下で□□病
院近隣の△△病院を派遣先に選定した。また、出向元の□□病院の高度急性期、急性期の病床機能と異
8
事例①
□□病院は、免許取得直後の薬剤師を対象とした病棟業務等に係る総合的な研修として 5 年間の独自
の卒後教育プログラムを運用している。本プログラムは、薬剤師の幅広い活動領域においてバランスが
取れて優れており、地域を俯瞰的にとらえ機能の異なる施設間連携と協働を強化した今後の医療を先導
する薬剤師ロールモデルの育成を目的としている。実施体制として、薬剤部長をプログラム責任者とし、
院内の医師や看護師、医学系、薬学系教員を含む委員会を設置し、その下部組織として薬剤部内に WG が
活動し、研修状況の評価とフィードバックを行っている。本プログラムの初期研修期間(1~2 年目)は
薬剤部内の中央部門を中心に、基本的調剤、外来患者の薬学的管理、無菌製剤処理、医療品情報管理、
TDM、手術室等における薬学的管理など基本的な技術を習得する。その間、1 年目の後半から病棟に
も出向き、病棟に常駐する専任薬剤師のサポーターとして病棟活動を始める。さらに半年ごとに内科系・
外科系病棟、外来化学療法センター、先端医療開発センター等をローテーションし、最初の 2 年間で基
本的な業務を適切に行えるレベルになることを目指す。さらに後期研修にあたる期間(3~5年目)は
病棟等の専任薬剤師として薬剤業務に従事する。地域病院での出向研修は概ね 4 年目とし、出向期間は
3~6か月を基本として、本人の研修の進捗状況と出向元に帰還後の残り期間を考慮して適宜変更可能
としている。プログラムは、定期的に見直し、病院のホームページに改訂履歴を付けて公開している。
出向先の選定は、〇〇県の病院薬剤師確保事業として予算化された地域連携薬剤師共育プログラムの病
院として知事から指定されている病院の中から、総合的な研修の一環として地域医療の実情を理解する
病院として適していること、また、大学病院の研修薬剤師を受け入れる体制が整っていることから総合
的に判断している。
事例②
△△病院は〇〇県の薬剤師偏在指標で病院薬剤師少数区域に指定されている医療圏にあり、薬剤師の
急激な減少で病棟業務を含む業務全般を縮小し、適正使用とチーム医療での薬剤師の関わりが少ない状
況である。高度急性期の□□病院は、〇〇県の薬務室と△△病院の現状を確認し、在職する出向希望者
の中から勤務歴 5 年以上で課題抽出と改善、マネジメント能力に優れ、出向経験の還元も期待できると
いう観点で中堅薬剤師を選定した。業務整理(業務工程見直しと補佐員へのタスク・シフト、医薬品安
全管理手順書の整備、薬剤管理指導記録のテンプレート導入)と新規業務展開(ICU 病棟での薬剤師業
務、ポリファーマシー対策の手順書策定・薬剤総合評価調整加算)を実践的に経験した。また、出向先
の病院幹部と薬剤科改善に向けた意見交換にも積極的に参加し、いくつかの提案が採用された。本研修
では、他職種の理解を得ながら新たな業務を開始するノウハウと進め方を修得した。また、病院執行部
との対話を通じて病院全体で薬剤師の役割拡大が進み、医療の質とチーム医療が大きく向上することの
充実感を体験した。研修を通じて学んだポリファーマシー対策の仕組みを出向元で新たに展開・充実さ
せることで、薬剤業務の向上が期待できる。
事例③
二次医療圏内の医療機関について病院規模および病院機能(救急受入有無、災害対応など)に対する
薬剤師数を調査し、薬剤師の必要人員が最も不足している医療機関を抽出し、県との協議の下で□□病
院近隣の△△病院を派遣先に選定した。また、出向元の□□病院の高度急性期、急性期の病床機能と異
8